【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の持分は放棄できる!手続きを進めるうえでの注意点も解説
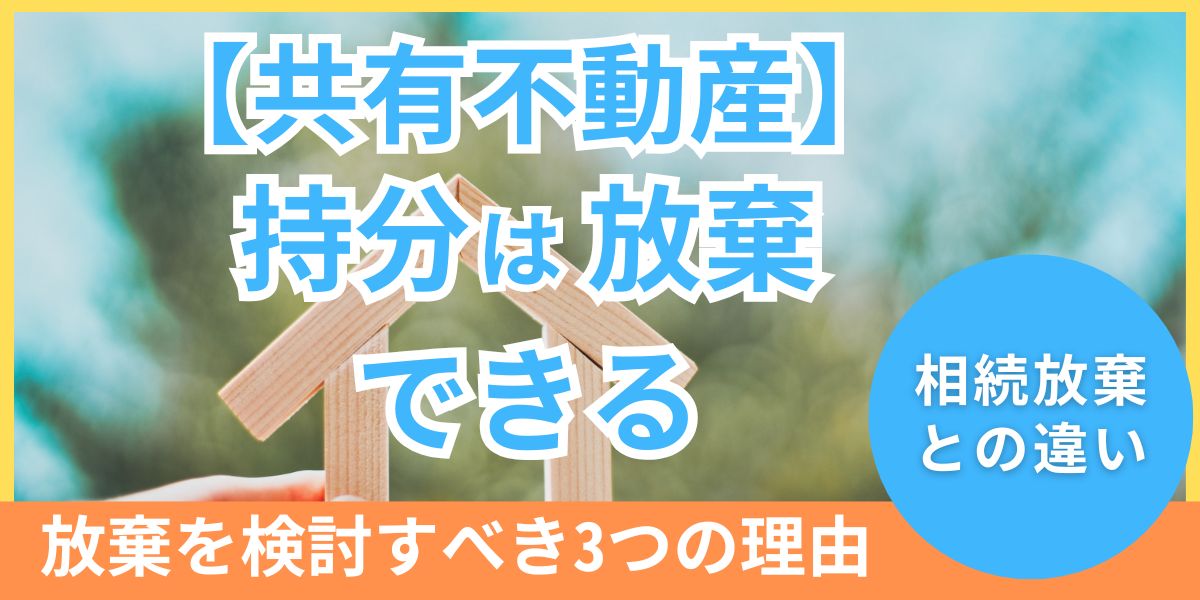
共有持分を所有していると他の共有者との間のトラブルや相続トラブルが起こる可能性があるため、トラブルを避けるために放棄を検討すべきケースもあるでしょう。
この記事では、共有不動産の持分放棄を検討している方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
共有持分の放棄をめぐるトラブルを回避するには、放棄の効果や影響などを事前に理解しておくことが重要です。
共有不動産をめぐるトラブルを回避したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の持分は放棄できる

共有不動産の所有者は、意思表示のみで共有持分を放棄できます。
共有者の1人が共有持分を放棄した場合、共有持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。
一方、不動産を単独所有している人は、不動産の所有権を意思表示のみで放棄することはできません。
たとえば、父親と長男が2分の1ずつの持分で不動産を共有していたケースで父親が持分を放棄すると、父親の持分が長男に帰属して長男の単独所有となります。
その後、不動産を単独所有することになった長男は、意思表示のみで不動産の所有権を放棄することはできません。
なお、共有持分を放棄した後で、持分放棄の登記を申請するには他の共有者との共同申請が必要です。
持分の放棄は一方的な意思表示による単独行為ですが、共有持分の放棄による所有権移転登記は登記義務者(放棄した人)と登記権利者(他の共有者)とが共同で申請しなければなりません。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有持分の放棄を検討すべき3つの理由

共有持分は、意思表示のみでいつでも放棄できますが、持分の放棄を検討すべき理由としては、次のものが挙げられます。
それぞれの理由について詳しく解説します。
共有持分を所有するリスクについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:共有持分について解説
共有不動産は他の共有者とのトラブルに巻き込まれやすい
共有不動産を所有していると、他の共有者との意見が合わずに管理や処分をめぐるトラブルに巻き込まれやすくなります。
共有不動産を処分・変更するには共有者全員の同意が必要です。
共有不動産の処分行為としては、不動産を売却する行為や物理的に破壊する行為などが挙げられます。
変更行為の具体例は、畑を宅地に造成する行為や大規模な増改築などが挙げられるでしょう。
また、共有不動産の管理行為には、過半数の共有持分を所有する者の同意が必要です。
たとえば、共有不動産について賃貸借契約を締結したり、解除したりする行為は管理行為に当たるため、過半数の持分を所有する者が同意しなければ行えません(共有不動産の賃貸は、契約内容によっては変更行為に該当するケースもあります)。
共有者間で意見が対立すると、それぞれの意見に沿った共有不動産の活用ができなくなってしまうため、共有不動産の処分や管理方法をめぐるトラブルが起こりやすいです。
こうしたトラブルに巻き込まれるのを回避することは、共有持分の放棄を検討する理由の1つとなります。
相続によるトラブルが発生しやすい
共有持分の所有者が亡くなった場合には、他の共有者ではなく相続人が共有持分を相続します。
相続人が複数いると共有者の数が増え、その分だけトラブルが起こりやすくなるでしょう。
特に、被相続人の代から他の共有者との関係が悪化していたようなケースでは、そのまま相続が発生すると、相続人にトラブルの種を押し付ける恐れがあります。
また、他の共有者との関係にかかわらず、誰が共有持分を相続するかという点で、相続人間のトラブルを引き起こす可能性もあるのです。
共有持分を所有したまま亡くなると相続によるトラブルが起こりやすくなるということは、生前に持分の放棄を検討すべき理由となります。
管理の負担が大きくなるケースがある
共有持分を所有していると、固定資産税や管理コストが見合わない状況になることがあります。
共有不動産の活用方法について共有者間で意見の対立があると、共有者の中には不動産を全く活用していないのに固定資産税だけを負担しているという人が出てくることもあります。
他の共有者が遠方に居住しているため管理を一方的に押し付けられるというケースもあるでしょう。
共有者が誰も管理できない土地を所有していると、管理の不全により他人が被った損害を賠償しなければならなくなることもあります。
こうしたケースでは、共有持分を所有し続けることのリスクが大きいため、持分の放棄を検討すべき理由となります。
共有持分を放棄する方法

ここでは、実際に共有持分を放棄する際の手続きの流れを解説します。共有持分を放棄するには、次の2つの手続きが必要です。
それぞれの手続きの内容について解説します。
関連記事:共有名義の解消方法とは?手続きについてもわかりやすく解説
他の共有者に持分放棄の意思表示をする
共有持分を放棄する際は、他の共有者に対して持分を放棄する旨の意思表示を行います。
共有持分の放棄は、意思表示のみで行えますが、意思表示をした証拠を残しておくために内容証明郵便で放棄の意思を伝えるのが良いでしょう。
共有者の1人が共有持分を放棄した場合、他の共有者は放棄の効果を争うことはできません。
共有者が2人のケースで1人が持分を放棄すると、もう1人の共有者は不動産を単独所有することになり、所有権の放棄はできなくなってしまいます。
価値のない土地を2人で共有しているケースでは、最初に持分を放棄した人がもう1人の共有者に価値のない土地の所有権を押し付けることができるため、「共有持分放棄は早い者勝ち」と言われることがあります。
共有持分の放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:「共有持分放棄は早い者勝ち」は本当なのか?手続きの流れや注意点を解説
共有持分変更の登記手続きを行う
共有持分の放棄による所有権移転登記は、持分を放棄した人と他の共有者が共同で申請しなければなりません。
共有持分の移転登記に必要な書類は、次のとおりです。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(持分放棄の内容証明など)
- 登記識別情報または権利証
- 固定資産評価証明書
- 住民票、印鑑証明 など
他の共有者が持分の放棄に納得していないときは、登記手続に協力してくれないこともあるでしょう。
その場合には、登記引取請求訴訟で判決を取得すれば、単独での登記手続が可能です。
訴訟では、持分放棄の意思表示をした証拠が必要となるので、その際に内容証明郵便が用いられます。
関連記事:共有不動産の持分放棄のやり方について解説
共有持分の放棄と相続放棄は何が違う?

共有持分を放棄するケースとしては、現に共有持分を所有している人が放棄するケースのほか、相続による共有持分の取得を放棄するケースがあります。
共有持分を放棄するのと、共有持分の相続を放棄するのとでは、次のような違いがあります。
| 共有持分の放棄 | 相続放棄 | |
| 放棄の対象 | 共有持分のみ | すべての遺産 |
| 期間制限 | いつでも | 相続から3ヵ月以内 |
| 手続きの方法 | 意思表示のみ | 家庭裁判所での申述 |
共有持分を相続する際、共有持分だけを放棄することはできません。
相続放棄する際は、すべての遺産の相続を放棄することになります。
他の遺産を相続したい場合には、共有持分を相続したうえで、改めて共有持分の放棄の意思表示が必要です。
また、相続放棄には、相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内の期間制限がありますが、共有持分の放棄はいつでも可能です。
共有不動産の持分を放棄する際の注意点

ここでは、繰り返しになる部分もありますが、共有不動産の持分を放棄する際の注意点を解説します。放棄する際の注意点は、次の3つです。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
複数人が放棄したときは先の意思表示が有効となる
複数人が持分を放棄したときは、先の意思表示が有効となり、最後の1人は放棄の意思表示ができなくなります。
たとえば、長男、次男、三男の3人が3分の1ずつの共有持分を所有している場合、長男、次男、三男の順に持分を放棄すると、共有関係は次のように変動します。
【長男による共有持分の放棄】
最初に意思表示をした長男による持分の放棄が有効となり、長男の持分は次男と三男に引き継がれます。この際、長男の持分(3分の1)が半分ずつ次男、三男に引き継がれるため、次男と三男が新たに取得する持分は全体の6分の1(1/3÷2)となり、それぞれが全体の2分の1ずつ(1/3+1/6)の持分を所有することになります。
【次男による共有持分の放棄】
次に、次男は、次男と三男が2分の1ずつの持分を所有している状況で持分を放棄することになるため、次男による共有持分の放棄によって三男が不動産を単独所有することになります。
【三男による共有持分の放棄】
三男は不動産を単独所有しているため、所有権を放棄することはできません。
他の共有者には贈与税が課税される
共有持分を放棄すると、他の共有者に所有権が移転します。そのため、共有持分の放棄は共有持分の譲渡と同視されて贈与税の課税対象となります。
放棄された共有持分の評価額が年間110万円までの基礎控除の範囲内であれば、贈与税は課税されません。
しかし、評価額が110万円を超える場合には、他の共有者に贈与税が課税されます。
共有持分の放棄は一方的な意思表示によって行えますが、事前の相談がない共有持分の放棄によって他の共有者に贈与税が課税された場合には、トラブルに発展する可能性があるため、十分に注意が必要です。
共有持分を放棄した場合でも当該年度の固定資産税は発生する
固定資産税の負担を免れるために共有持分を放棄した場合でも、当該年度の固定資産税は負担しなければなりません。
固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
年の途中で共有持分を放棄した場合でも、その年の固定資産税の負担を免れることはできません。
関連記事:共有者が固定資産税を払わないときは?立て替えた際の請求方法や解決策を解説
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有不動産の持分放棄についてよくある質問

ここでは、共有不動産の持分放棄についてよくある質問に回答します。
共有持分の放棄と相続放棄はどちらを選ぶべきですか?
共有不動産以外の財産を相続したい場合には、共有不動産を含む不動産を相続したうえで、共有持分の放棄を行うことになります。
このケースでは、不要と考える共有不動産についても相続税を負担しなければなりません。
また、他の相続人が先に共有持分の放棄をした場合には、持分の放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄するか、いったん相続したうえで持分を放棄するかは、他に相続したい遺産があるか、相続した場合のリスクなどを総合考慮して、どちらが良いかを選択すべきです。
共有持分を放棄するのではなく、売却はできないのですか?
共有持分は売却することも可能です。
共有持分を売却できれば代金を得られるため、共有持分の放棄は売却の見込みがないときや他の共有者との関係で放棄を急ぎたい場合の手段と考えるべきでしょう。
共有不動産の売却について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:共有不動産はどうしたら売却できるの?同意が必要なケースと持分の処分方法を解説
まとめ
今回は、共有不動産の持分を放棄する手続きを理解するために、次の内容について解説しました。
- 共有持分は意思表示のみで放棄できる
- 共有持分を所有していると共有者とのトラブルや相続トラブルに巻き込まれるリスクがある
- 共有持分の放棄は先に意思表示をした者が優先される
共有不動産についてトラブルに巻き込まれてしまった場合には、弁護士への相談をおすすめします。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









