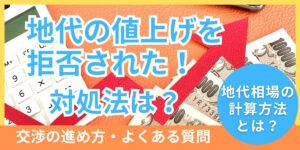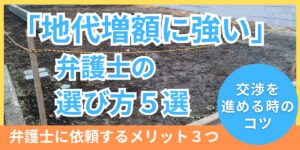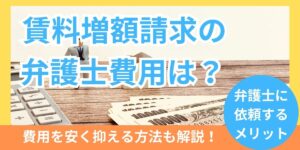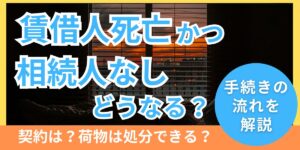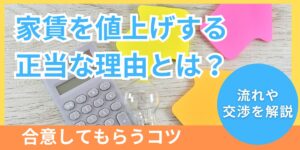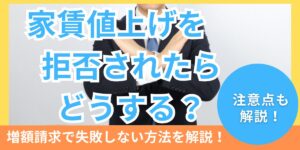【無料相談受付中】24時間365日対応
家賃値上げを拒否もしくは応じてくれないときは追い出しできる?交渉の進め方やトラブルの対処法を解説
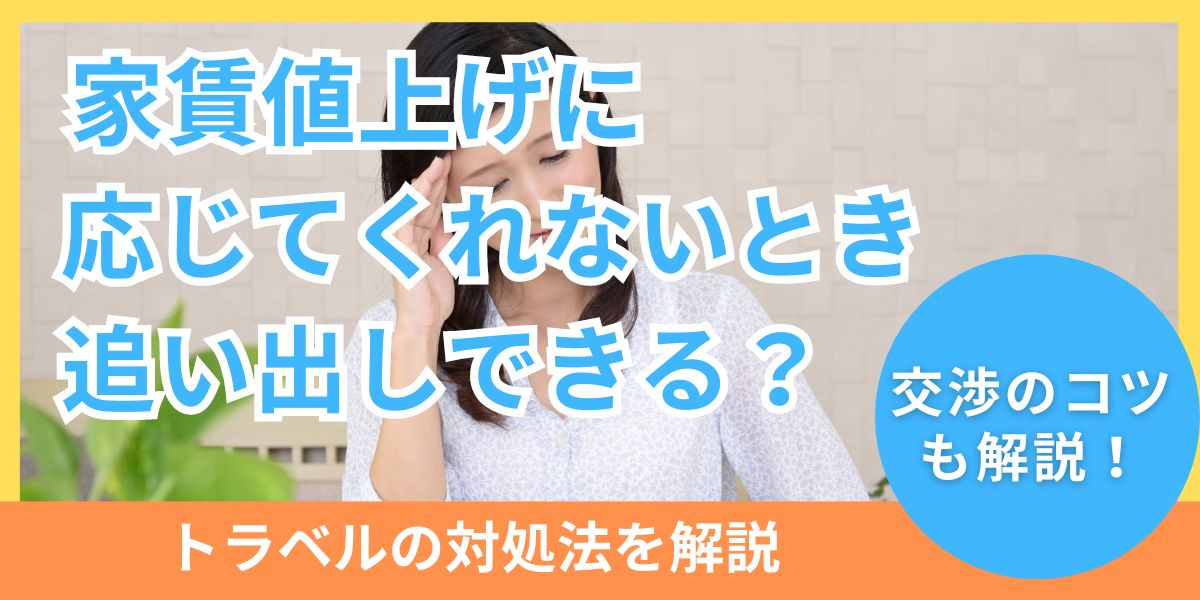
家賃値上げは入居者にとっても切実な問題です。
入居者が家賃値上げにすんなりと応じてくれるとは限りません。
家賃値上げには正当理由が必要です。

入居者から家賃値上げを拒否された場合のオーナーの対処法など、家賃値上げをスムーズに進めるための交渉のコツ・注意点を解説します。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
家賃値上げに応じてくれない場合の追い出しは「基本的に認められない」


家賃は、オーナーと入居者の合意によって決まります。
家賃値上げも、原則としてオーナーと入居者の合意が必要です。
入居者から家賃値上げを拒否された場合、調停や裁判を行わない限り、オーナーは家賃値上げできません。
家賃値上げを拒否している入居者に対して、家賃値上げ拒否を理由として契約の更新拒否や契約解除すること、まして入居者を追い出すことは、基本認められません。
家賃値上げには正当理由が必要ですが、入居者の追い出し(強制退去)にもオーナー側に正当理由が必要です。
関連記事:家賃滞納者の強制退去について解説
正当理由があるとして入居者の追い出しが認められる可能性があるのは、次のような場合に限られます。
- 入居者とオーナーとの信頼関係が破綻した(家賃滞納や悪質な迷惑行為などを続けた場合など)
- 重大な契約違反行為がある
家賃値上げ拒否だけでは明渡し請求の正当理由とは言えませんが、立退料の支払いを正当理由の補完条件として、明渡し請求が認められる場合はあります。
アクロピースでは値上げ拒否など不動産問題全般のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



“値上げを断られたから追い出す”は原則できません。まずは話し合いです。退去が認められるのは、滞納や重大な迷惑行為など特別な理由があるときに限られます。
関連記事:強制退去が可能な条件とは?退去理由や執行の流れと費用、注意点も解説
家賃を値上げするには正当理由が必要


家賃は、オーナーの都合で一方的に上げることはできません。
家賃の値上げには、借地借家法32条1項(借賃増減請求権)に定められている正当理由が必要です。
(借賃増減請求権) 借地借家法 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。引用:民法 | e-Gov 法令検索
たとえば、次のような事情がある場合は「正当理由」に該当する可能性があります。
- 賃貸物件の固定資産税などの税の増額や修繕積立金・管理費の値上げがあった
- 物価や人件費の上昇など経済状況の変化があった
- 再開発の進展などにより賃貸物件の家賃が周辺の家賃水準より低くなった
ただし、上記のような事情があっても、家賃の値上げが直ちに認められるとは限りません。
家賃値上げの正当性は、他の事情(当事者間の事情、従前家賃との乖離状況、一定期間の経過など)も総合的に考慮して判断されます。



値上げには理由の筋が大切。固定資産税や物価の上昇、相場とのズレなど、誰が見ても納得しやすい根拠を数字で示しましょう。
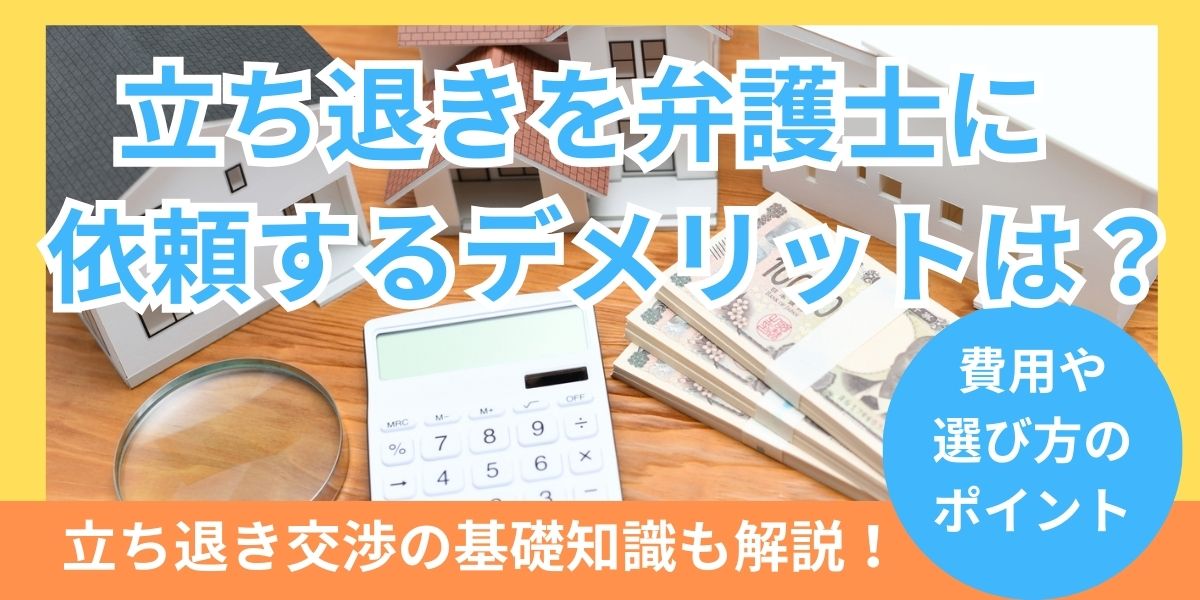
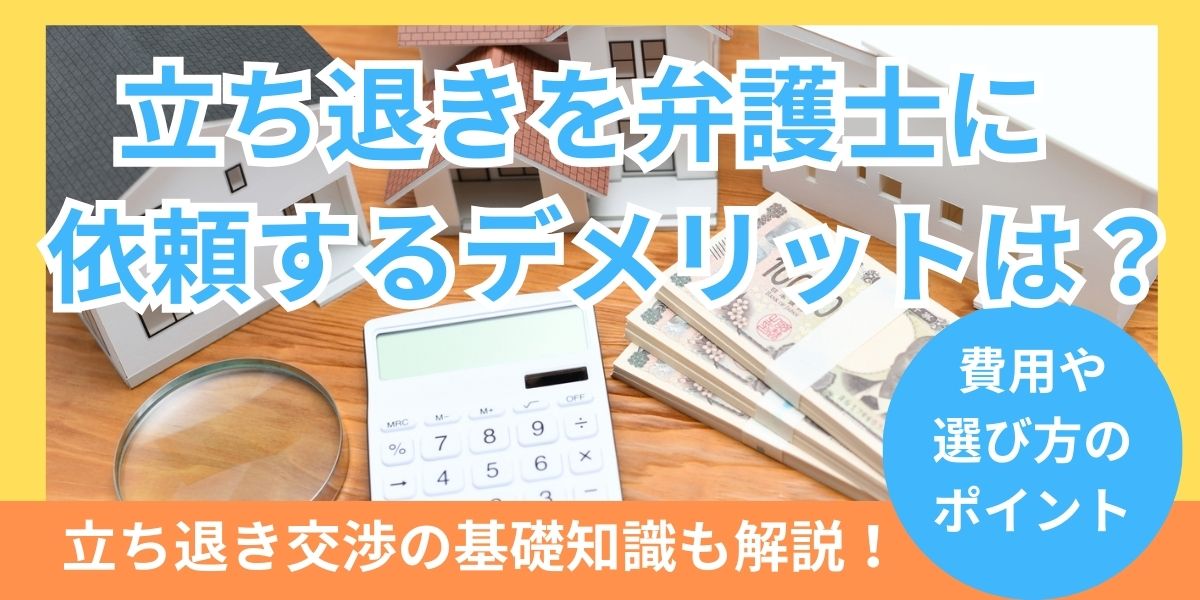
家賃値上げの正当理由と認められない例


次のような場合は、家賃値上げの正当理由と認められません。
- オーナーの都合による単なる収入増が目的の場合
- 設定しようとする家賃が周辺の家賃相場より著しく高い場合
- 契約書に家賃値上げをしない旨の明文の特約がある場合
オーナーが賃貸物件の経営とは関係のない自分の経済的事情により、単なる収入増目的で家賃値上げすることは、家賃値上げの正当理由とは言えません。
「とにかく収入を増やしたい」「別途発生した損失を補てんしたい」などの理由で家賃値上げすることは、難しいでしょう。
周辺の家賃相場よりも著しく高い家賃を設定しようとする場合も、値上げは困難です。
値上げするとしても、値上げ後の家賃は正当と認められる範囲内にする必要があります。
「家賃は増額しない」という特約がある場合は、特約は原則有効で値上げは困難です。
「周辺の家賃相場より家賃が低い」「固定資産税が上がった」など、家賃値上げの正当理由に該当し得る事情があっても、特約があれば値上げは認められない可能性が高いでしょう。



“収入を増やしたいだけ”や“相場とかけ離れた金額”は通りにくいです。値上げしない特約があるときも要注意。まず契約書と近隣相場をチェックしましょう。
家賃の値上げ交渉で起こり得る3つのトラブル


家賃値上げ交渉で起こり得るトラブルとして、次のようなことがあります。
家賃の値上げは、オーナー側に正当理由があっても、入居者との間でトラブルになることがあります。
どのようなトラブルがあり得るのかをあらかじめ認識したうえで、慎重な検討と準備が必要です。
家賃の支払いを拒否される
家賃値上げでよくあるトラブルは、家賃の支払い拒否です。
値上げ分の家賃差額の支払い拒否だけでなく、家賃全額の支払いを拒否される事態もあり得ます。
たとえば「家賃値上げはオーナーの勝手な都合」と入居者が判断した場合、家賃値上げに同意せず家賃全額の支払いを拒否することもあるでしょう。
入居者は値上げに不服でも従前の家賃を支払う義務があり、家賃全額の支払い拒否は本来認められません。
しかし、オーナーが家賃値上げ理由の説明や値上げの通知をきちんと行っていない場合は、裁判上の争いになるリスクがあります。
家賃値上げを行う場合は、前もって値上げの理由を入居者に説明し、きちんと通知することが重要です。
家賃値上げを理由に解約される
家賃値上げを理由にして解約されることもよくある事態です。
家賃は毎月必要な固定的な経費であるため、入居者にとって値上げは大きな負担になる場合があります。
そのため、家賃値上げに応じるより解約を選ぶ入居者もいるでしょう。
解約された場合、新たな入居者をすぐに確保できる保証はありません。
家賃収入を増やそうと考えて値上げを求めたのに、家賃収入の減少になってしまいかねません。
家賃値上げをするとしても、周辺の家賃相場を踏まえた値上げ幅にとどめるなど適切な配慮が必要です。
夜逃げのおそれもある
家賃値上げを告げられた入居者が夜逃げする事態もあり得ます。
金銭面などで問題がある入居者は、オーナーに連絡せずこのような行動に走る可能性がないとは言えません。
夜逃げされてしまうと、急に空室が発生するため、新たな借主が見つかるまで家賃収入が途絶えてしまいます。
オーナーに断りもなく退去された場合、家賃回収が困難になるだけでなく、居室の原状回復費用など追加的な費用もかかり、入居者の新規募集などの予定外の問題も発生します。
家賃値上げは、入居者の状況をきちんと把握しておき、慎重に進めることが大事です。



トラブルを減らすコツは早めの説明と書面化。理由を丁寧に伝え、通知は内容証明で。段階的値上げや設備改善の提案も有効です。
家賃の値上げのタイミングは「契約更新時が多い」


家賃値上げをスムーズに進めるためには、値上げのタイミングが重要です。
家賃値上げの時期に決まりはありませんが、契約期間中は据え置き契約更新時に家賃値上げするケースが多いでしょう。
入居者を新規募集する際やオーナーが変わった際に、家賃を上げる例もあります。
賃貸借契約書では、契約更新時に限らず、物価高騰などの事情があれば、契約期間中でも値上げできるという条項を入れているのが通例です。
いずれにしても、家賃値上げには正当理由が必要であり、闇雲に値上げできるわけではありません。
家賃値上げを検討する場合、タイミングによっては、入居者の退去により空室が発生するリスクがあることを認識しておきましょう。



一番まとまりやすいのは更新時。ただし、契約期間中でも値上げできるの条項があっても、時期の配慮は必要です。繁忙期・退去リスクも見て決めましょう。
家賃値上げ交渉の進め方とポイント


家賃値上げ交渉の進め方のポイントは、次の3点です。
家賃値上げは、決して容易なことではありません。
スムーズに家賃値上げを実現するため、進め方のポイントをしっかり把握しておきましょう。
家賃値上げの理由を明示して通知する
家賃値上げ交渉をスムーズに進めるためには、入居者に対する家賃値上げ理由の説明と通知が必須です。
その際、次の点に留意する必要があります。
- 家賃値上げの理由・根拠を明確にする
- できるだけ早く通知する
- 配達証明付き内容証明郵便で通知する
まず、家賃値上げの理由・根拠を入居者が納得しやすいように、きちんと明示して説明することが大事です。
それでも入居者に納得してもらえず、話し合いが手間取ることも考えられます。
家賃値上げを早期に実現したいのであれば、できるだけ早く理由を付して、入居者に値上げの通知をしましょう。
家賃の値上げの説明や通知は口頭でも可能ですが、口頭の場合、後で言った言わないと争いになることもあるため、必ず書面で通知すべきです。
書面による通知の方法は、調停や訴訟に移行する場合も考えられるため、配達日と内容を確認できる配達証明付き内容証明郵便にしましょう。
もめたときはまず調停で話し合う
家賃値上げの話がまとまらない場合は、調停の申立をしましょう。
法的には、オーナーの賃料増額請求の意思表示が相手方に到達した時点で効果が生じ、入居者の承諾がなくても将来的に家賃が増額されます。
しかし、これには強制力がないため、金額に争いがある場合は、調停や裁判を利用することになります。
賃料の増減は調停前置主義となっており、まず調停を申し立てなければなりません。
調停は、原則として物件の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
調停で合意が成立しない場合は訴訟を起こす
調停で合意が成立しない場合は、最終的に訴訟で決着することになります。
裁判では値上げの正当性が争われるため、鑑定結果などが重要な証拠となります。
争いが長期化するのは面倒だからと、簡単に契約を解除することはできません。
オーナーからの契約解除には、正当理由が必要です。
値上げ後の家賃差額未払いは契約解除の理由になり得ますが、賃貸人が建物を必要とする事情や立退料等を考慮して、正当理由があると認められなければ契約は解除できません(借地借家法28条)。



手順は通知→説明・交渉→調停→訴訟。まずは理由を1~2枚に要約して渡し、相手の事情も聞く。話が止まったら調停で第三者に入ってもらいましょう。
関連記事:立ち退き交渉・裁判の流れとは?費用や期間、交渉するポイントも解説
関連記事:家賃増額に強い弁護士が必要な理由と選び方!
家賃値上げの話し合いがまとまらないときの3つの対処法


家賃値上げの話し合いがまとまらないときの対処法を紹介します。
家賃を値上げせずに据え置く
家賃収入の安定的確保を優先するのであれば、現状のまま家賃を据え置くことも選択肢にしましょう。
入居者が家賃値上げに応じない理由は、経済的な事情、周辺の家賃相場などいろいろ考えられます。
相手の言い分もよく聞いて、家賃収入が引き続き確保されることを優先することも大切な判断です。
入居者に立退料を支払って解約・明渡しを求める
値上げに応じない入居者に居座わられるのは困るというときは、立退料を支払って、解約・明渡しを求めましょう。
オーナー側から賃貸借契約解約を申し入れる際は、正当理由が必要です。
「老朽化した物件を建替える」「賃貸人が物件を利用する」などの理由だけでは、解約・明渡しは通常認められません。
老朽化などの事情に加えて、立ち退きを求める入居者に一定の金銭的補償(立退料)をしなければ、正当理由を認めないとする裁判例が多いのが実情です。
立退料は当事者の交渉で決定しますが、明確な相場や基準はないため、よくわからないときは、弁護士と相談してみましょう。
関連記事:【大家都合で退去】立退料の相場と交渉方法は?過去の判例も紹介
家賃値上げを拒否された場合は物件の売却を検討する
家賃値上げを入居者に拒否された場合は、収益性も考慮し賃貸物件を売却することも選択肢に入れるべきです。
値上げしないと赤字がさらに拡大し経営が困難になるが、調停や訴訟は費用も手間もかかるため避けたいという場合に、有効な対策になります。



選択肢は据え置き/立退料で解約合意/売却。収支と空室リスクを並べて数字で比較すると、次の一手が決めやすくなります。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
家賃値上げによる追い出しに関するよくある質問
家賃値上げの通知は何日前までに行う必要がありますか?
家賃の値上げを行う際、法的には「○日前までに通知しなければならない」という明確な日数の規定はありません。
ただし、実務上は以下のような点に注意が必要です。
まず、値上げの通知は早めに行うのが原則です。
特に契約更新時に家賃値上げを検討している場合は、少なくとも1〜2ヶ月前までに通知しておくことが望ましいとされています。遅れると、入居者が新しい条件に対する判断・準備ができず、交渉やトラブルがこじれるリスクが高まります。
また、通知は口頭ではなく必ず書面で行うべきです。
後のトラブル防止や裁判となった場合の証拠とするため、配達証明付き内容証明郵便など証拠が残る方法で通知すると安心です。
仮に、正当な理由があり値上げの必要性が高いとしても、通知の仕方が不十分だと入居者の不信感を招きスムーズな合意に至らないことがあります。
家賃値上げの実施には、準備・タイミング・通知方法のいずれも慎重な対応が求められます。対応に不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
家賃値上げの上限はいくらまで認められますか?
家賃の値上げには、法律上の明確な上限はありません。
しかし、無制限に値上げが認められるわけではなく、「借地借家法32条」に基づく正当な理由があることが大前提です(借地借家法32条)。
具体的には、以下のような要素を総合的に考慮して増額が「社会通念上相当かどうか」が判断されます。
- 周辺の家賃相場との比較
- 現行の家賃の額と合意時期
- 建物や設備の老朽化状況
- 固定資産税・管理費・物価の上昇
- オーナー・入居者双方の経済的事情
仮に、家賃を2倍、3倍に引き上げようとした場合、それが地域相場や物件の実態から著しく乖離していれば、裁判では不当と判断される可能性が高いでしょう。
家賃値上げの目的が単なる収益増やオーナーの事情に基づく場合、正当な理由とみなされず、交渉がこじれる原因となることもあります。
したがって値上げ幅については、相場データや過去事例に照らし妥当な水準に抑える配慮が必要です。判断に迷う場合は、早期に専門家へ相談することをおすすめします。
賃貸のオーナーチェンジでよくあるトラブルとは?
オーナーチェンジとは、物件の所有者が変わっても賃貸契約自体は継続されることを指します。しかし、売却後の新しいオーナーと入居者との間で、さまざまなトラブルが生じることがあります。
代表的なものは以下の通りです。
- 急な家賃値上げや契約条件の変更
- 修繕義務や設備対応をめぐる認識のズレ
- 敷金返還や更新料に関するトラブル
- オーナー変更を知らされず、対応窓口が不明なまま放置される
特に問題となりやすいのが、新しいオーナーが契約内容を十分に把握しないまま入居者に一方的な通知を出すケースです。このような対応は、信頼関係の破綻を招きトラブルが長期化する原因になります。
また、入居者側も、「新しいオーナーには従う必要がない」と誤解することで、家賃支払いの遅延や交渉の拒否などの問題が生じることがあります。
オーナーチェンジにあたっては、契約内容や物件の状態過去の対応履歴などの引き継ぎを丁寧に行い入居者には適切な書面通知で変更内容を明示することが重要です。
不動産売買や相続でオーナーが交代する場合は、事前に弁護士に確認の上で対応を検討することで無用なトラブルを避けやすくなります。
まとめ|家賃値上げや追い出しで悩むときは弁護士に相談しよう!


家賃値上げを拒否された場合の追い出しの可否・対処法についてまとめます。
- 家賃値上げや入居者の追い出しには正当理由が必要
- 単なる収入増目的・設定家賃が相場より著しく高い・値上げしない特約があるなどの場合、家賃値上げの正当理由と認められない
- 家賃値上げに対して、家賃支払い拒否・解約・夜逃げなどのトラブルがあり得る
- 家賃値上げ交渉は、理由を明示して通知する・もめたときは調停で話し合う・最終的には訴訟になる
- 値上げ交渉がまとまらないときは、家賃据え置き・立退料を払い明渡し請求・物件売却が選択肢になる
家賃値上げや追い出しの正当理由は、根拠となる資料が必要で交渉は決して容易ではありません。
冷静な話し合いが難しい場合は、借地借家問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。



根拠を集めて、早めに伝える。書面に残して、段階的に進める。 これらを気をつければ、多くの揉め事は減らせます。迷ったら専門家に早めの相談を。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応