【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の使用貸借とは?認められる要件やリスク・トラブル対処法を弁護士が解説
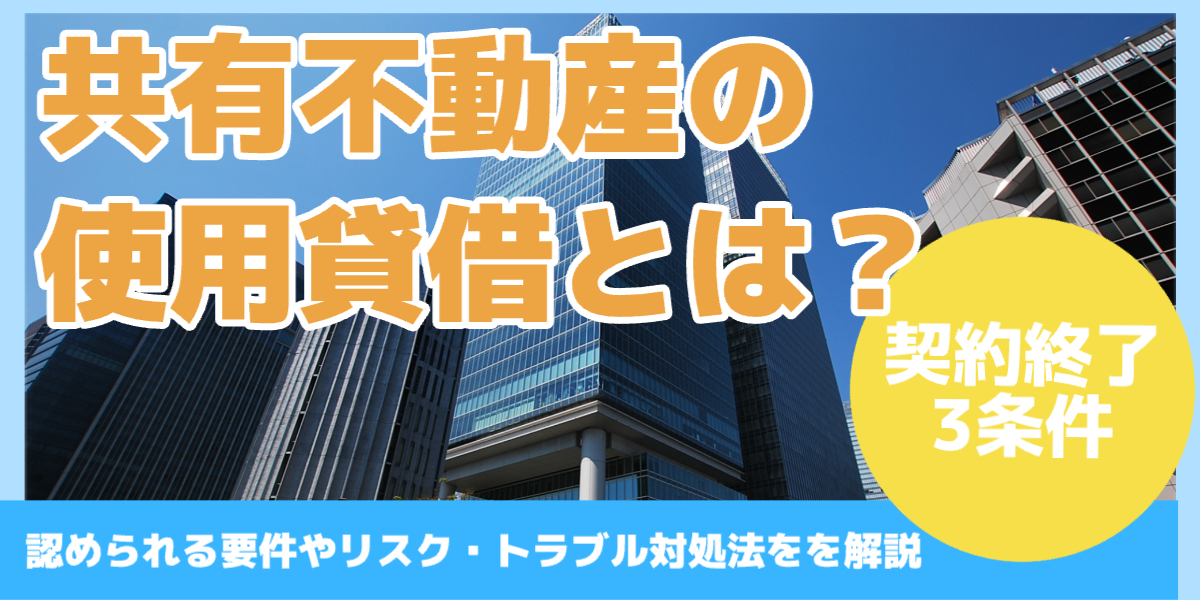
「共有者の一人が、相談なく勝手に友人を住まわせていて困っている」
「家賃を払わず住んでいる人に出ていってもらいたい…」
このような共有不動産に関する悩みを抱えている人は少なくありません。
共有者間の合意に基づき、不動産を無償で貸し借りする契約を「使用貸借」といいます。口約束でも成立するため、当事者間の認識のズレから深刻なトラブルに発展しやすいのが特徴です。
本記事では、共有不動産における使用貸借の基本から、成立要件やリスク、トラブル対処法まで弁護士が網羅的に解説します。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産における「使用貸借」とは?基本情報を解説
共有不動産における使用貸借とは、共有不動産を特定の人が無償で利用する契約のことです。
親族間での利用や、一時的な居住を認める場合によく見られます。しかし、契約内容が曖昧なままでは、後々のトラブルの原因になりかねません。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫まずは使用貸借の定義と、有償の「賃貸借」との違いを正確に理解しましょう。
使用貸借とは|「無償」で貸す契約
使用貸借とは、貸す側が借りる側に物を無償で貸し、相手方が使用後に返還することを約束する契約のことを指します(民法第593条)。
賃貸借契約と異なり、「好意による貸し借り」という性質が強い契約形態です。
共有不動産の場合、共有者全員または持分価格の過半数の同意を得て、特定の共有者や第三者に不動産を無償で貸し出すケースがこれに該当します。
共有者の同意は、口頭でも成立しますが、後のトラブル防止のためには「共有者全員の署名・押印を含む書面(覚書など)」で残すことが望ましいです。
書面化しておくことで、誰が・どの範囲まで・どの期間貸すのかを明確にでき、後日の無断使用や占有継続を防止できます。
賃貸借(賃貸)との違い|賃料(家賃)の有無
使用貸借と賃貸借の最も大きな違いは、賃料(家賃)の発生があるかどうかです。
使用貸借は無償での貸し借りを前提としていますが、賃貸借は借主が貸主に対価として賃料を支払います。
この違いにより、契約の解除条件や借主の権利保護の度合いは、以下のように大きく異なるのが特徴です。
| 契約形態 | 賃料(対価) | 契約の成立 | 借主の保護 |
|---|---|---|---|
| 使用貸借 | なし(無償) | 当事者の合意 | 比較的弱い |
| 賃貸借 | あり(有償) | 当事者の合意と賃料の定め | 借地借家法により強く保護される |
共有持分の使用貸借の主な特徴
共有持分の使用貸借には、いくつかの特徴があります。
これらの特徴を知らなければ、意図せず不法占拠とみなされたり、逆に立ち退きを求められなくなったりする可能性もゼロではありません。
ここでは、とくに重要な4つの特徴を解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
使用借契約書を作成することなく使用できる
使用貸借契約は、貸主と借主の口頭での合意でも成立します。必ずしも書面での契約は必要ありません。
そのため、親族間などで「とりあえず無償で住んでいいよ」といった軽いやり取りから始まるケースが多く見られます。
しかし、契約期間や使用範囲が不明確になりやすく、後々のトラブルの火種となりやすい点には注意が必要です。
借主が共有者以外の第三者でも認められる
使用貸借の借主は、共有者に限りません。共有者間で適切な合意がなされていれば、共有者以外の第三者(親族や知人など)に不動産を無償で貸し出すことも可能です。
ただし、誰にどのような条件で貸すかについては、共有者間でしっかりと意思疎通を図る必要があります。
一人の共有者が他の共有者の同意を得ずに第三者へ貸す行為は、民法上の「管理行為」または「変更行為」に該当し、原則として持分の過半数による同意または共有者全員の同意がなければ無効となる恐れがあります(民法第252条)。
無断貸与が発覚した場合、他の共有者から損害賠償請求や明け渡し請求を受けるリスクがあるため、事前に必ず同意を得ることが重要です。
使用貸借の事実があれば不法占拠に該当しない
たとえ口約束であっても、「無償で使ってよい」という合意(使用貸借契約)があれば、その占有は法的に正当化されます。
そのため、他の共有者が一方的に占有者に対して「不法占拠だ」と主張しても、すぐに出ていってもらうことはできません。
占有している側に正当な権利があるかどうかは、使用貸借の合意の有無が重要な判断基準となります。
使用貸借の事実があれば賃料の請求ができない
使用貸借は「無償」が前提の契約です。したがって、貸主は借主に対して、原則として賃料やそれに相当する金銭(賃料相当損害金)を請求できません。
後から「やっぱり家賃を払ってほしい」と思っても、賃貸借契約に切り替える合意がない限り、請求は困難です。
もし家賃収入を得たいのであれば、最初から賃貸借契約を結ぶ必要があります。
共有不動産の使用貸借が認められる要件
共有不動産を使用貸借として貸し出す場合、共有者の一人の判断だけではできません。民法上の「管理行為」または「変更行為」に該当するため、他の共有者の同意が必要になります。
同意の範囲は、貸し出す期間によって異なる可能性があります。
この要件を満たしていない場合、契約内容を他の共有者に主張できない可能性があるため注意しましょう。
短期の使用貸借は「持分割合の過半数の同意」が必要
短期の使用貸借は、共有物の「管理行為」にあたります。
管理行為とは、共有物の保存や利用、またはその価値を維持・向上させるための日常的な行為を指します。共有者全員のうち、持分の価格に従って過半数の同意を得なければ実行できません(民法第252条)。
ここで重要なのは、「頭数」ではなく「持分割合」で判断するという点です。共有者が複数いる場合でも、単純に人数の多数決で決められるわけではありません。
そのため、相続や投資物件などで共有状態が生じている不動産の場合、誰がどの程度の持分を持っているのかを正確に把握したうえで手続きを踏むことが重要です。
長期の使用貸借は「共有者全員の同意」が必要
長期間にわたる使用貸借は、共有物の「変更行為」と見なされる可能性があります。変更行為とは、共有物の物理的な形状や法的な権利関係を根本的に変える行為のことです。
長期にわたる使用貸借契約は、その期間中に他の共有者が自由に共有物を利用できなくなります。そのため、実質的には共有物の権利関係を大きく変更するものと評価され、「変更行為」となりやすいのが特徴です。
民法第251条により、変更行為には共有者全員の同意が不可欠です。全員の同意なく長期の使用貸借契約を結んだ場合、他の共有者から契約の無効を主張されるリスクがあります。



契約締結前に、共有者全員から書面で明確な同意を得ることが不可欠です。
以下の記事では、共有不動産のトラブルについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有持分とは?所有するリスクや主なトラブル事例、回避策を解説
共有不動産の使用貸借を無断で行った場合どうなるか
共有持分を持つ一人の共有者が、他の共有者の同意を得ずに物件全体を第三者へ貸した場合、無断使用(共有物の不法占有)とみなされます。
民法第249条および第252条では、共有物の管理や使用について「共有者全員の同意」が必要とされており、個々の持分権者が単独で物件全体を使用・貸与することはできません。
たとえば、共有不動産を一人の共有者が勝手に知人へ貸した場合、他の共有者の同意がない限り、無権限での使用貸借契約と判断され、貸借契約自体が無効となる可能性があります。
また、その使用により他の共有者が本来受けるべき使用利益を失うため、不当利得返還請求や損害賠償請求の対象となる可能性もあるでしょう。
そのため、共有持分を利用して他人に貸す際は、必ず共有者全員の同意を得ることが重要です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有持分の使用貸借が終了する条件
一度成立した使用貸借契約を終わらせるための条件は、民法で定められています。主な終了条件を理解しておくことで、将来的な立ち退き交渉などをスムーズに進めることが可能です。
契約が終了する主な条件は、以下の3つです。
以下、それぞれ詳細に解説します。
契約で定めた期間が満了したとき
使用貸借契約を結ぶ際に、あらかじめ期間を定めていた場合、その期間が満了すれば契約は自動的に終了します(民法第597条)。
たとえば「子どもが大学を卒業するまで」といった形で期間を決めていた場合、その時期の到来とともに契約は終了し、貸主は返還を請求できます。
このように期間を区切ることで、貸主は将来的な使用予定に合わせた管理がしやすくなり、トラブル防止につながります。明確な目的に基づく使用貸借では、期間の設定が重要です。
使用貸借の目的に従った使用収益が終了したとき
使用貸借契約を結んだ時に、期間は定めていなかったけど、使用貸借の目的を定めていた場合、その目的にしたがった使用収益を達した場合には終了します(民法第597条2項)。
また、目的にしたがった使用収益に足る必要な期間が経過したときも同様に終了するとされています(民法第597条2項ただし書)。
単に建物を所有する目的といった抽象的な目的では足りず、何のために建物を所有するかのように具体的な目的を定めた上で、その目的にしたがった使用収益が終了したかどうかになります。
目的は契約で明示しなくても問題はありませんが、何のために使用貸借契約を締結したのか、目的を明確にしておいた方が、トラブル防止にはつながるでしょう。
借主が死亡したとき
使用貸借は、貸主と借主の個人的な信頼関係に基づく契約とされています。
そのため、借主が死亡した場合、その時点で契約は終了します(民法第597条3項)。
使用貸借の権利は相続の対象にはならず、借主の相続人が引き続きその不動産に住み続ける権利はありません。
貸主は、相続人に対して建物の明け渡しを請求することが可能です。
共有持分の使用貸借を解除・終了させたいときの手続き
共有持分の使用貸借を解除・終了させる場合、主に以下の手続きが必要です。
- 1. まずは共有者・使用者と協議を行う
- 2. 合意に至らない場合は「解除通知」を送付
- 3. 明け渡しが行われない場合は法的手段
解除を希望する場合は、共有者全員と使用者との協議が原則です。使用貸借契約の当事者が共有者の一人であっても、他の共有者に影響を及ぼす場合があるため共有持分全体の扱いを明確にする必要があります。
話し合いでは、以下の点を確認しましょう。
- 使用を認めた経緯(いつ・誰が・どの範囲を使用しているか)
- 使用目的(居住用・駐車場など)
- 使用終了を求める理由(売却、利用計画の変更など)
- 解除の時期と明け渡し期限
協議で合意できない場合は、書面による解除通知を送付します。民法第598条などに基づき「いつでも解除できる」性質を持ちますが、相手に一定の猶予期間を与えることが望ましいです。
それでも使用者が明け渡しに応じない場合は、使用貸借契約の終了を前提に、明渡請求訴訟を提起することになります。弁護士に相談のうえ、証拠(契約書・通知書・写真・会話記録など)を整理しておくとよいでしょう。
共有持分を使用貸借で貸し出す3つのリスク
親しい間柄だからといって安易に共有不動産を無償で貸してしまうと、予期せぬリスクに見舞われることがあります。無償であるがゆえに、かえって権利関係が曖昧になり、深刻なトラブルに発展しかねません。
ここでは、使用貸借に伴う代表的な3つのリスクを解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
1.無償が原則のため賃料請求による家賃収入が得られない
使用貸借は無償が原則のため、賃料請求による家賃収入を一切得られません。
ただ、不動産を所有している限り、固定資産税や修繕費などの維持管理コストは発生し続けます。
これらの費用は、所有者である共有者が負担しなければなりません。
収益化の機会を失うだけでなく、維持費の負担だけが残るため、経済的なデメリットは大きいといえます。
2.目的や期間が曖昧だと簡単に契約解除・退去を求められない
口約束で始まった使用貸借では、利用目的や契約期間が不明確なケースも珍しくありません。
民法では、期間の定めがない場合「契約に定めた目的に従い、使用収益を終えた時」に契約が終了するとされています。
しかし、目的が「住むため」といった曖昧なものだと、いつ「使用収益を終えた」のか判断が難しく、貸主からの契約解除が認められない場合があります。



正当な理由なく退去を迫ることは、権利の濫用とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
3.相続が発生すると権利関係がさらに複雑化する
共有者や借主の状況に相続が発生すると、権利関係は一層複雑になります。
使用貸借の相続による権利関係の主な変化は、以下のとおりです。
| 貸主(共有者)が死亡した場合 | 使用貸借契約は終了せず、貸主の地位が相続人に引き継がれます。 |
|---|---|
| 借主が死亡した場合 | 使用貸借契約は終了します。ただ、借主の相続人が退去に応じないトラブルが発生する可能性があります。 |
新たな相続人が増えることで、当事者間の話し合いがまとまりにくくなる可能性があるため注意が必要です。



相続が発生して権利関係が複雑になった場合は、適切に対処するためにも早めに弁護士に相談しましょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有持分の使用貸借を巡ってよくあるトラブル例
共有持分の使用貸借では、当事者間の認識のズレや、権利範囲の誤解からさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
ここでは、実際の相談でよく見られる4つの典型的なトラブル例を紹介します。
自身の状況と照らし合わせ、問題が深刻化する前に対策を検討しましょう。
ケース1:共有者の一人が単独で他人に貸している
よくあるトラブル例の一つが、共有者の一人が他の共有者に無断で自分の知人や親族に不動産を無償で住まわせるケースです。
前述の通り、使用貸借契約を結ぶには、短期であっても持分割合の過半数の同意が必要です。同意要件を満たしていない場合、その契約は他の共有者に対して効力を主張できません。
そのため、この場合、他の共有者は占有者に対して明け渡しを請求したり、貸し出した共有者に対して損害賠償を請求したりすることが可能です。
ケース2:使用貸借の範囲を超えた使用をする
当初の合意にはなかった使い方をされるトラブルも、共有持分の使用貸借でよくあるトラブルです。
具体的には、単に居住する目的で貸したにもかかわらず、借主が無断でリフォームをしたり、事業用の事務所として利用したりするケースが考えられます。
このような契約違反があった場合、貸主は契約の解除を主張できる可能性があります。
ただし、どの程度の違反で解除が認められるかは、個別の状況によって判断が異なるため、一度弁護士に相談しましょう。
関連記事:共有名義のリフォームで注意すべき点は?同意の範囲や贈与税について弁護士が徹底解説
ケース3:使用貸借終了後の明け渡しを拒否する
契約期間の満了や借主の死亡によって使用貸借が終了したにもかかわらず、借主やその相続人が退去を拒否するケースもよくあるトラブルの一つです。
とくに長年住んでいた場合、借主側が「住み続ける権利がある」と誤解していることが少なくありません。
話し合いで解決しない場合は、法的手続きによる明け渡し請求が必要になります。最終的には、訴訟を提起し、裁判所の判決を得て強制執行を行うことになるでしょう。
共有不動産の使用貸借に関するよくある質問
ここでは、共有不動産の使用貸借について、多くの方が抱く疑問に回答します。後になってトラブルにならないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
使用貸借契約で後から家賃を請求することは可能?
原則として、後から家賃を請求することはできません。使用貸借は「無償」を前提とした契約だからです。
もし家賃を請求したいのであれば、借主と交渉し、双方の合意のもとで賃貸借契約に切り替える必要があります。
相手の合意なく、一方的に家賃を請求する法的な権利はありません。
貸主(共有者)が死亡した場合、使用貸借契約はどうなる?
貸主が死亡しても使用貸借契約は終了せず、貸主としての地位がその相続人に引き継がれます。
したがって、貸主の相続人は新たな貸主として、元の契約内容に基づき借主に対して権利義務を負うことになるのが特徴です。
ただ、契約の内容や性質によって相続人が契約を継続することが著しく不適当と認められる場合は、契約終了を主張できるケースもあります。
貸主が死亡したタイミングで、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
固定資産税は、実際に住んでいる人(借主)が払う?
固定資産税の納税義務は、不動産の所有者(共有者全員)にあります(地方税法第343条)。
実際に住んでいるのが借主であっても、所有者でない限り納税義務は負いません。
固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して課税されます。支払わなければ延滞金が発生するうえ、財産の差し押さえになる可能性もあるため注意が必要です。
なお、共有不動産の場合、共有者全員が持分割合に応じて連帯して納税する義務を負うことも覚えておきましょう。
以下の記事では、共有者が固定資産税を支払わない場合の対処法について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ|共有持分の使用貸借トラブルは専門家に相談して適切に対処しよう
共有持分の使用貸借は口約束で手軽に始められる反面、権利関係が曖昧になりやすく、深刻なトラブルに発展するリスクがあります。トラブルが発生した場合は、契約内容の確認から法的手続きまで、段階的な対応が必要です。
もし当事者間の話し合いで解決が難しい場合や、手続きに不安がある場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として相手方と交渉し、法的に適切な手続きを進めてくれます。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









