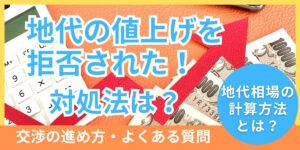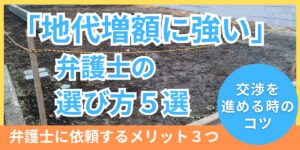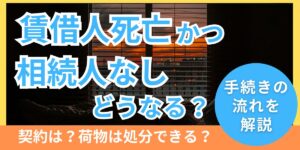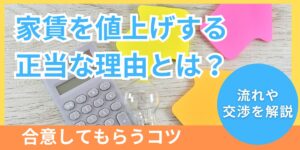【無料相談受付中】24時間365日対応
賃料増額請求の弁護士費用相場はどのくらい?費用計算や安く抑える方法を解説
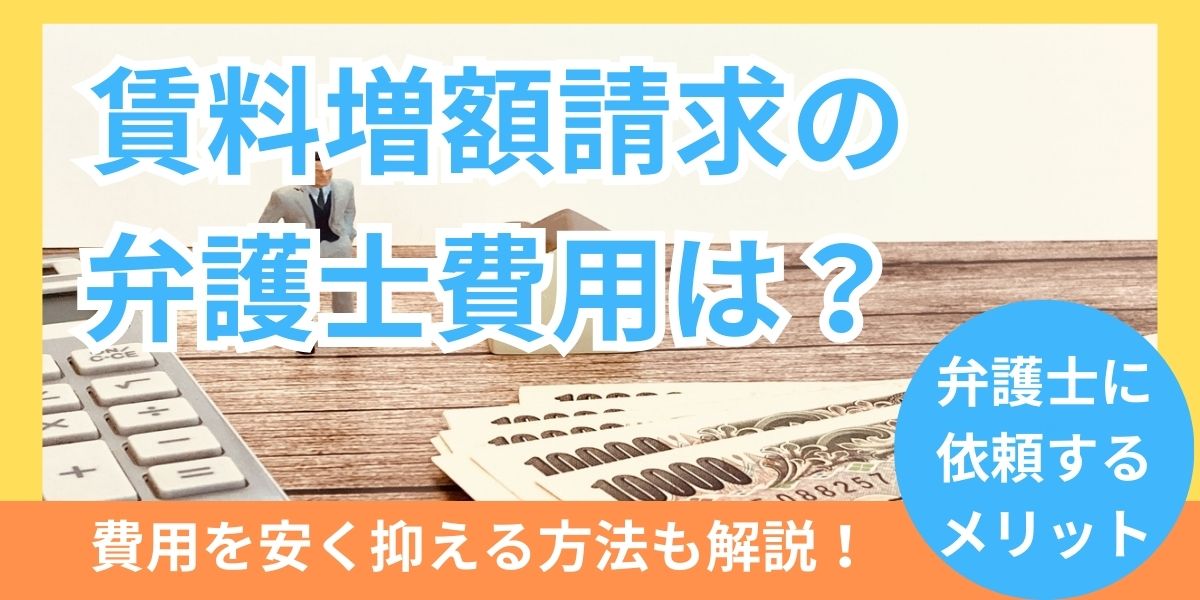
「最近、周辺の家賃相場が上がっている」
「固定資産税が上がったのに、賃料は据え置きのままだ」
所有する物件のオーナー様にとって、賃料が不相当なものとなったとき、賃借人への賃料増額請求は正当な権利です。
しかし、いざ弁護士に依頼しようにも、「費用がいくらかかるか分からない」「費用倒れにならないか」といった不安がよぎるかと思います。
この記事では、賃料増額請求の手続きを弁護士に依頼しようと考えているオーナー様に向けて、次の内容を分かりやすく解説します。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
すでに家賃の値上げを拒否された方は下記記事をご覧ください。
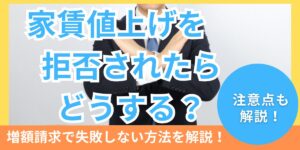
賃料増額請求の弁護士費用

賃料増額請求の手続きを弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります。弁護士費用には、次の4つの種類があります。
平成16年4月1日から、弁護士費用は各法律事務所が自由に決められるようになりました。
そのため、弁護士費用は各法律事務所によって異なりますが、現在でも旧日弁連の報酬基準を参考にしている事務所が多くなっています。
 アクロピース弁護士 佐々木
アクロピース弁護士 佐々木旧日弁連の報酬基準は、それ以前の統一的な報酬基準として利用されていたものです。弁護士費用の相場を知るには、旧日弁連の報酬基準での金額を理解しておくのが良いでしょう。
ここからは、旧日弁連の報酬基準を基に賃料増額請求の弁護士費用の相場について詳しく解説します。
法律相談料|弁護士に相談する際にかかる費用
法律相談料は、弁護士に正式に事件の依頼をする前の法律相談にかかる費用です。
旧日弁連の報酬基準における法律相談料は、30分ごとに5,000円から1万円の範囲内とされており、相場は、30分5,000円(税別)となっています。
初回の法律相談については、無料としている法律事務所も多くあります。
費用の心配をされている方は、無料相談で賃料増額請求が認められる見込みや弁護士に依頼した場合の費用を確認してみるのがおすすめです。
着手金|弁護士に依頼を決定した際、手続き開始時に支払う費用
着手金は、弁護士に手続きを依頼した際にかかる費用です。
賃料増額請求の着手金について、旧日弁連の報酬基準では「増減額分の7年分の額」を経済的利益として、次の計算式で算出されます。
| 経済的利益の額 | 着手金の額 |
| 300万円以下 | 8% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 5%+9万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 |
たとえば、月に4万円の賃料増額を求めるケースにおける着手金は、次のようになります。
経済的利益の額=4万円×12か月×7年=336万円
着手金の額=336万円×5%+9万円=25万8,000円
数は少ないものの法律事務所によっては、着手金を無料として、その分を報酬金に加算して対応しているところもあります。
報酬金|事件が解決(増額成功)した際に、成果に応じて支払う費用
報酬金は、事件が解決したときに発生する費用です。
賃料増額請求の報酬金は、旧日弁連の報酬基準では「増減額分の7年分の額」を経済的利益として、次の計算式で算出されます。
| 経済的利益の額 | 報酬金の額 |
|---|---|
| 300万円以下 | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 |
報酬金は、実際に増額された金額を基準に計算されます。
たとえば、当初は5万円の増額を求めたところ、4万円の増額で合意した場合には、増額分を4万円として報酬金を計算します。
実費|手続きを進める上で実際にかかった費用(交通費、印紙代など)
弁護士に手続きを依頼する場合、弁護士が手続きを進めるに際してかかる実費についても依頼者が負担するのが通常です。
- 内容証明郵便の費用
- 裁判所に納める印紙代、切手
- 弁護士の交通費
- 書類の取得費用 など
多くの法律事務所では、事件を受任する際に1万円から数万円程度の実費を預かり、事件が解決した際に実費を精算した残額を返還しています。
法律事務所によっては、出張時や裁判所に出廷した際の日当を請求しているところもあります。



手続きが長引くと日当の額も高額となる可能性があるため、日当の有無と金額は依頼する際にしっかりと確認するようにしてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
賃料増額請求にかかるその他の費用


賃料増額請求にかかる費用は、弁護士費用だけではありません。
賃料増額請求の手続きを進めるには、弁護士費用以外にも次のような費用がかかります。
ここからは、それぞれの費用の内容について詳しく解説します。
私的鑑定の費用
賃料増額請求の手続において、賃借人や裁判所に増額の根拠を示すには、不動産鑑定士に賃料の鑑定を依頼する必要があります。
私的鑑定の費用とは、自分で不動産鑑定士に鑑定を依頼する際にかかる費用のことです。
費用の相場は、安くても20万円程度となっています。
正式な鑑定書ではなく査定書を作成してもらう簡易鑑定の場合は、5万円から10万円程度が相場となっていますが、通常の鑑定よりは説得力が落ちてしまうでしょう。
調停・裁判にかかる実費
賃料増額請求の調停や裁判を申し立てる場合には、印紙代と切手代がかかります。
印紙代は、訴額をもとに計算されます。
賃料増額請求における訴額は、次の計算式で算出する裁判所が多いようです。
増額分の賃料×(増額請求から申立てまでの期間+12か月)
参照:簡易裁判所に「賃料等調停の申立て」をしたい方のために|裁判所
たとえば、月額4万円の増額を求める事案で、増額を求めてから調停を申し立てるまで3か月かかった事案における訴額は、次のようになります。
4万円×(3か月+12か月)=60万円
訴額が60万円の場合、調停の申し立てにかかる印紙代は3,000円です。
裁判の場合には、6,000円となります。
もっとも、この金額よりも建物の固定資産評価額の2分の1の方が低額の場合には、固定資産税額を基準にする事が出来ます。
参照:手数料額早見表|裁判所
切手代は、5,000円から1万円程度となっております。
裁判での鑑定費用
裁判での鑑定費用は、裁判手続において裁判所が鑑定士を選任した場合にかかる費用です。
鑑定費用は、20万円から50万円程度になることもあります。
鑑定費用を負担するのは鑑定の申出をした方ですが、原告の負担となるケースが多くなっています。
賃料増額請求の費用を抑える方法


賃料増額請求の手続きを進めるには、弁護士費用や鑑定費用など、決して安くない費用がかかります。
費用倒れのリスクを避け、できるだけ費用を抑える方法としては、次の4つが考えられます。
① 調停前の「交渉」で合意を目指す
最も費用を抑えられる方法は、調停や裁判に至る前に、賃借人との「交渉」段階で合意することです。
交渉で合意できれば、裁判所に納める印紙代や切手代、そして高額になりがちな裁判所での鑑定費用(20万~50万円)もかかりません。
ただし、オーナー様ご自身で交渉すると、感情的になってしまったり、法的な根拠を示せずに交渉が決裂したりするリスクもあります。
交渉段階から弁護士に依頼し、法的な根拠(近隣相場、固定資産税の上昇など)を冷静に提示してもらうことが、早期合意への近道となります。
② 「簡易鑑定」を戦略的に活用する
交渉や調停の初期段階では、高額な「正式鑑定(20万円~)」ではなく、「簡易鑑定(5万~10万円)」を活用するのも一つの手です。
簡易鑑定でも、賃借人に「専門家による一定の根拠がある」と示すことができ、交渉のテーブルについてもらいやすくなります。
ただし、賃借人が簡易鑑定で納得せず、訴訟に発展した場合は、結局「正式鑑定」や「裁判所鑑定」が必要になる可能性は残ります。
③「初回無料相談」で費用の見通しを立てる
多くの事務所が実施している「初回無料相談」を最大限に活用しましょう。
無料相談では、以下の点を必ず確認してください。
- そもそも賃料増額が認められる可能性はどの程度か?
- 依頼した場合の「着手金」「報酬金」「実費」の総額見積もりはいくらか?
- 費用倒れ(増額できる見込み額より弁護士費用のほうが高くなる)のリスクはないか?
これらの情報を事前に把握することで、納得した上で依頼するかどうかを判断できます。
費用がかかっても賃料増額請求を弁護士に依頼するメリット


賃料増額請求を弁護士に依頼するメリットとしては、次の3点が挙げられます。
それぞれのメリットの内容について詳しく解説します。
交渉・裁判で最善の結果を得られる可能性が高まる
弁護士は、交渉や裁判手続きの専門家です。専門家に手続きを任せることで、成功率は高まります。
賃借人との交渉では、専門家の見地に基づく説得的な説明ができるので、賃借人が増額に応じてくれる可能性は高くなるでしょう。
調停や裁判においては、状況に応じた最善の主張を行うとともに、適切な証拠の準備もできます。早期の解決、より高額の増額を目指すのであれば、弁護士に手続きを依頼すべきです。
交渉から裁判まですべての手続きを一任できる
弁護士に手続きを依頼すると、交渉から裁判まですべてを任せられます。賃料増額請求の手続きは、慣れていなければ時間も手間もかかる大変なものです。
弁護士に手続きを任せられれば、自分で手続きを進める手間や精神的ストレスから解放されるでしょう。さらに、自分で手続きを進めることによる不備やミスを防ぐこともできるため、手続きをスムーズに進められます。
将来的な利益につながる可能性がある
賃料増額請求の手続きを自分で進めると、増額請求が認められなかったり、認められたとしても金額が低くなる可能性もあります。
弁護士に手続きを依頼して最善の結果を得られれば、弁護士費用を支払ってでも将来的にはプラスになる可能性があります。
たとえば、弁護士に依頼した結果月額5万円の増額が認められれば、年間では60万円のプラスになります。



この場合、数年単位で考えると、弁護士費用を支払っても大きなプラスとなるでしょう。
賃料増額請求が認められるケース


賃料増額請求は、賃貸人だけの都合によって認められるものではありません。
賃料増額請求が認められるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
それぞれの条件について詳しく解説します。
賃料が不相当となったとき
賃料増額請求について規定している借地借家法11条1項および32条1項は、賃料増額請求が認められる条件について下記と規定しています。
土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき
賃料が不相当か否かを判断するには、相当な賃料を計算する必要があります。
賃料の計算方法として用いられることが多いのは、差額分配法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法の4つです。
各事例について、どの計算方法を用いるべきなのか、具体的な金額がいくらかを判断するには、不動産鑑定士の協力が必要となります。
家賃の値上げに関する正当理由について、より詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:家賃を値上げする正当な理由は3つ!流れや交渉に合意してもらうコツを解説
賃料を増額しない特約がない
借地借家法11条1項ただし書および32条1項ただし書は、下記と規定しています。
一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う
そのため、賃貸借契約を締結した際に一定期間賃料を増額しない特約を設けていたときには、その期間内に賃料増額請求をすることができません。



ただし、特約を結んだ際に予測できなかったような地価の変動により賃料が不当に低額となった場合には、特約の期間中であっても賃料増額請求が認められる可能性はあります。
賃料改定から一定の期間が経過している
法律で明確に「何年間は改定できない」と決まっているわけではありませんが、前回の賃料改定からあまりにも短い期間(例:1年未満など)での再度の増額請求は、信義則の観点から認められにくい傾向があります。
明確な基準はありませんが、少なくとも前回の改定から2~3年程度の期間が経過していることが一つの目安となるでしょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
賃料増額請求の手続きと費用発生のタイミング
「費用がかかるのは分かったけれど、いつ、どの段階で支払うの?」という疑問がある方も多いでしょう。
賃料増額請求は、いきなり裁判になるわけではありません。
法律(調停前置主義)により、まずは調停で話し合う必要があり、一般的には「①交渉 → ②調停 → ③訴訟」の順で進みます。
交渉段階(内容証明郵便)
まずは、賃借人に対し内容証明郵便で増額通知を送り、交渉するところから始めます。
弁護士に依頼する場合、この段階で「着手金」が発生します。
| 概要 | 弁護士が代理人として、法的根拠を示し賃借人と交渉します。 |
| 発生費用 | 着手金、内容証明郵便実費 |
| 目安期間 | 1~3ヶ月 |
調停段階(調停前置主義)
交渉で合意できない場合、簡易裁判所に「賃料増額調停」を申し立てます。
裁判所の調停委員を介して、話し合いでの解決を目指します。
| 概要 | 調停申立書を作成し、裁判所で話し合います。 |
| 発生費用 | 調停申立実費(印紙代、切手代)、弁護士の日当(裁判所に出廷するため) |
| 目安期間 | 6ヶ月~1年 |
訴訟段階
調停でも合意できず「不成立」となった場合、最終手段として「訴訟(裁判)」に移行します。
訴訟では、裁判所が双方の主張や鑑定結果に基づき、適正な賃料を判決で決定します。
| 概要 | 裁判所に訴状を提出し、法廷で主張・立証を行います。 |
| 発生費用 | 訴訟実費(印紙代)、鑑定費用(裁判所鑑定の場合)、追加着手金(※事務所による。調停から移行する場合は不要な事務所も多い) |
| 目安期間 | 1年~1年半程度 |
賃料増額の弁護士費用に関するよくあるご質問
鑑定費用は最終的に誰が負担するのですか?
鑑定費用の種類によって異なります。
| 私的鑑定(自分で依頼する鑑定) | 依頼した側(オーナー様)が全額負担します。 |
| 裁判所鑑定(裁判所が選任する鑑定) | 訴訟の判決において、負担割合が決められるのが一般的です(例:オーナー7割、賃借人3割)。または、和解の条件として負担割合を定めることもあります。 |
増額請求が認められなかった場合(失敗した場合)の費用はどうなりますか?
着手金と実費(鑑定費用含む)は、結果にかかわらず(増額に失敗しても)返金されないのが一般的です。
ただし、報酬金は「成功報酬」であるため、増額請求が全く認められなかった(増額0円だった)場合は発生しません。
弁護士費用を賃借人(相手方)に請求できますか?
原則として、できません。
日本の裁判制度では、不法行為など一部の例外を除き、弁護士費用は「敗訴者負担」とはならず、各自が依頼した弁護士の費用をそれぞれ自己負担することになっています。
関連記事:地代増額に強い弁護士の選び方とは?
まとめ
今回は、賃料増額請求の費用にかかわる問題として、次の内容について解説しました。
- 賃料増額請求の弁護士費用は増額分の賃料が基準となる
- 賃料増額請求の手続きでは弁護士費用以外に鑑定費用がかかる
- 弁護士に手続きを依頼すると費用をかけてでも将来的な利益につながる可能性がある
自分で手続きを進める場合でも鑑定費用はかかりますし、自分ではせっかくの鑑定結果を上手く活用できない可能性もあります。
賃料増額請求の問題は、弁護士までご相談ください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応