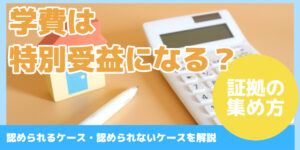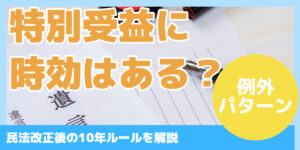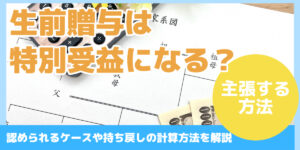【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分は弁護士に相談すべき?制度の仕組みや計算方法・依頼すべきケースを解説|遺産相続の寄与分の相場とは

「寄与分を主張するには弁護士に依頼したほうがいい?」
「寄与分を主張して、他の相続人が納得してくれるか不安」
遺産分割協議において、寄与分を主張するために、弁護士へ相談すべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
被相続人の財産の維持・増加に対して特別な貢献をした相続人には、公平な遺産分割にするために「寄与分」の制度が適用される場合があります。
しかし、寄与分として認められる行為や、上乗せされるべき金額を判断するのは容易ではなく、弁護士に依頼すべきケースも多いです。
本記事では、寄与分の仕組みや遺留分との違い、弁護士に依頼すべきケースを解説します。
公平な相続を実現するための一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分とは?遺産相続における基本知識
遺産分割では「介護や事業の手伝いをしてきたのに、取り分が他の相続人と同じで納得できない」と感じる方が少なくありません。そのようなときに活用できるのが、寄与分の請求制度です。
ここでは、寄与分の基本や遺留分、特別寄与料との違いを解説します。まずは、寄与分がどのようなときに主張できるのか確認しましょう。
寄与分とは「被相続人に特別な貢献をした相続人の取り分を増やす制度」
寄与分とは、被相続人に特別な貢献をした相続人の取り分を増やす制度です。(参照:民法|第904条の2)
(寄与分)
第九百四条の二 第一項
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。引用:民法|第904条の2
特別な貢献とは、被相続人の財産の維持・増加を支えた貢献のことです。例えば、亡くなった両親の介護を長年担ってきた方や、被相続人の事業を無償で支え、その人の財産を維持・増やした人などが該当します。
特別な貢献をした相続人は、寄与分を請求することで、通常の法定相続分にプラスして寄与分の財産を取得できる場合があります。
関連記事:寄与分とは?認められる条件や請求方法をわかりやすく解説
遺留分や特別寄与料との違い
寄与分とよく似た言葉に「遺留分」や「特別寄与料」があります。どれも相続の場でよく目にする言葉で混同しやすいため、事前に確認しておきましょう。
| 制度名 | 請求できる人 | 概要 |
|---|---|---|
| 寄与分 | 法定相続人 | 財産維持や増加に特別な貢献をした分を取り分に上乗せするもの |
| 遺留分 | 法定相続人 | 法定相続人に最低限保障されている取り分 |
| 特別寄与料 | 相続人以外の親族(親族以外は認められない) | 法定相続人以外の人が、被相続人の財産の増加・維持に貢献した場合に請求できる取り分 |
まず遺留分とは、相続人が相続時に最低限もらえる取り分のことです。兄弟姉妹を除く配偶者や子どもなどが対象となります。(参照:民法|第1042条1項)
特別寄与料は、相続人以外の親族(長男の妻が長年介護をしていたケースなど)が対象です。相続人でなくても、貢献度に応じて金銭を請求できます。(参照:民法|第1055条1項)
これに対して寄与分は、長年の介護や住宅ローンの肩代わり、無償での事業手伝いなど、特別な貢献をした相続人を正当に評価するための制度です。(参照:民法|第904条の2)
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫それぞれの違いを理解しておくことで、自分の立場に合った制度を検討しやすくなります。
遺留分については、以下の記事でも解説しています。計算方法や具体例を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介
関連記事:寄与分と遺留分の関係性の記事を見る
関連記事:寄与分と遺留分はどっちが優先?よくあるケースからわかる関係性を徹底解説
弁護士依頼前にチェック!寄与分が認められる条件4つ
寄与分が認められるには、いくつかの条件を満たす必要があります。ただ単に親の面倒を見ていた、生活を支えていただけでは必ずしも寄与分に当たるとは限りません。
具体的な条件は、以下の4つです。
どれか1つに該当すれば認められるわけではなく、上記4つを満たす必要があります。寄与分を主張を弁護士に依頼する前に、ここで解説する4つの視点をチェックしましょう。
法定相続人であること
まず大前提として、寄与分を主張できるのは法定相続人に限られます。配偶者や子どもなど相続権を持つ立場でなければ、寄与分は認められないため注意が必要です。
例えば、長男の妻が長年介護をしていた場合、法定相続人ではないため寄与分を主張できません。
このようなケースでは、特別寄与料と呼ばれる別制度で請求することになります。(参照:民法|第1055条1項)
自分の立場によって請求できるものが異なるため、まずは相続人かどうかを確認してみましょう。
法定相続分は何か知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:法定相続分とは?法定相続人の順位と計算方法や遺留分との違いを解説!
相続人の尽力によって被相続人の財産状態が改善・保持されたこと
寄与分が認められるには、相続人の行動が財産の増加や保持につながっていることが条件です。
例えば、以下のようなケースは、被相続人の財産の増加や改善、保持として認められる可能性があります。
- 法定相続人であること
- 相続人の尽力によって被相続人の財産状態が改善・保持されたこと
- 特別の寄与として認められること
- 金銭を受け取らずに無償で貢献していたこと
これらはいずれも、相続人の尽力によって「財産が増えた」「減らずに済んだ」と説明できる行為です。
寄与分を考える際は、どのように財産にプラスの効果があったのかを整理しておくと、弁護士に相談したときに判断がスムーズになるでしょう。
寄与分の主張が認められるケースは、以下の記事でも解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
関連記事:相続で生前に貢献した人への増額は?相続人以外にも認められるのか寄与分の仕組みを解説
特別の寄与として認められること
通常の親子の扶養義務を超えるレベルの貢献でなければ、寄与分は認められません。同居や生活の面倒を見る程度では「日常的な扶養」と判断されやすく、寄与分として評価されない可能性が高いです。
扶養義務を超えて「特別な寄与」とみなされやすい行為には、以下のようなものがあります。
- 数年間にわたり、毎日介護や療養看護を続けた
- 自分の仕事を制限し、長期間にわたり事業を支えてきた
- 家業を無償で担って売上や経営の維持に大きく貢献した
- 高額の金銭を出資し、返済を求めずに財産の増加を助けた
「通常想定される親族の助け合い」を超えているかどうかが判断のポイントです。何が特別寄与にあたるのかは判断しづらいため、証拠を集めて弁護士に調査を委ねましょう。
金銭を受け取らずに無償で貢献していたこと
特別な貢献を無償で行わなければ、寄与分として評価されません。
給与や謝礼を受け取っていた場合は、寄与分を主張できないため注意しましょう。
例えば、被相続人の介護をしていて介護費用や給料をもらっていた場合、その対価とみなされて寄与分は認められにくくなります。
ただし、一部の交通費や生活費の補填など少額の補助であれば、無償で貢献していたと判断されるケースもあります。



事前に証拠を整理し、過去に金銭を受け取っていなかったかどうか確認しておくことが大切です。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
寄与分が認められにくいケース
寄与分が認められにくいのは、相続人の貢献が「通常の扶養や同居の範囲」にとどまる場合です。例えば、親と同居して生活費の一部を負担しただけでは、財産の維持や増加に寄与したとは判断されにくいです。
また、介護の対価として給与をもらっていた場合も、寄与分と評価されることはありません。
さらに、短期間だけの支援も長期的かつ継続的に財産維持に寄与したと認められない限り、寄与分の対象にはならないとされています。
このように、日常的な協力や一時的な支援、金銭を受け取った上での支援は寄与分として認められないケースの代表例です。



主張する際は、寄与の内容や期間を具体的に示すことが重要です。
寄与分を主張するために必要な証拠
寄与分を認めてもらうには、特別な貢献があったことを示す証拠を準備する必要があります。
証拠として有効とされているのは、以下のような書類や資料です。
| 証拠になる書類・資料 | 詳細 |
|---|---|
| 領収書・通帳の記録 | 療養費や生活費を自ら負担したことを示すもの |
| 介護日誌・メモ | 介護の内容や期間を具体的に記録したもの |
| 医療機関・介護施設の書類 | 通院付き添いや介護サービス利用に関する証明 |
| 給与明細・事業記録 | 無償で被相続人が営む事業に従事していたことを裏付ける資料 |
| 第三者の証言・陳述書 | 親族や医療従事者などによる客観的な証言 |
これらを組み合わせることで、日常的な扶助ではなく、特別の寄与であったことを立証しやすくなります。



ただし、どの資料が有効かの判断や裁判所への提出方法は専門的な知識を要するため、証拠集めの段階から弁護士に相談して進めるとより確実です。
相続における寄与分の計算方法とは?どのように算定する?
弁護士に依頼する前に「寄与分によって自分はどれくらい取り分を増やせるのだろう」と気になる方もいるのではないでしょうか。
寄与分には一律の計算式や相場があるわけではなく、相続人の貢献度や期間、財産への影響などを踏まえて個別に算定されます。
ここでは、基本的な計算方法や相場が決まっていない理由、過去の判例から見る請求相場を見ていきましょう。寄与分の金額を具体的にイメージしておくと、自分の主張が現実的かどうか判断しやすくなります。
基本的な計算方法
寄与分の算定は、被相続人が亡くなった時点の財産総額を基準にします。そこから寄与分にあたる金額を控除し、残りを相続人で法定割合に従って分ける流れです。
計算式は、次のように整理できます。
(相続財産の総額 − 寄与分) × 各相続人の法定相続分+ 寄与分
例えば、遺産が3,000万円で寄与分が500万円と認められたケースは以下のとおりです。
- 相続財産:3,000万円
- 控除後の金額:3,000万円 − 500万円 = 2,500万円
- 法定相続分:2,500万円を各相続人で分配
- 寄与した人:上記の取り分に加えて500万円が上乗せされる
このケースでは、他の相続人の取り分は500万円を差し引いた残りの2,500万円を法定相続分で分け、寄与した人はさらに500万円を加算されます。
寄与分の相場が定まっていない理由
寄与分には、はっきりとした相場が存在しません。
一口に「寄与」といっても、人によって行為の内容や期間、財産への影響度が異なります。かかった期間・労力・金額・成果が大きく変わるため、一律の基準を設けられないのです。
裁判所はそれぞれの事情を総合的に考慮し、個別に金額を判断しています。実際に寄与分を主張するときは、証拠や状況を整理して具体的に示す必要があるでしょう。
判例から見る寄与分の認定額相場
ここでは、過去の判例に基づいて寄与分の認定額の相場を見ていきましょう。
東京高裁平成22年9月13日決定の判例では、相続人の妻が13年以上にわたり入浴の世話や失禁処理などを行い、日常生活を支え続けました。
家政婦を雇うような重い介護を無償で担った点が評価され、相続財産の維持に役立ったと判断されて200万円の寄与分が認められています。(参照:裁判所|寄与分に関する裁判例 東京高裁平成22年9月13日決定・家裁月報63巻6号82)
また、被相続人が脳梗塞で常時介助を必要とする状態になり、妻だけでなく相続人の妻や孫も長期にわたり介助を分担した判例もあります。
入浴やトイレの付き添いなど欠かせない生活介助を無償で行った結果、家族全体の負担を大きく軽減したと評価され、170万円の寄与分が認められました。(参照:裁判所|寄与分に関する裁判例 東京高裁平成12年3月8日決定・家裁月報52巻8号35)
過去の判例では、長期間にわたる介護や生活支援でも、認められる金額は数百万円程度にとどまっています。
実際の寄与分は、労力に見合うほど高額に認められるとは限らず、相続財産全体とのバランスや貢献の種類などによって金額が決まります。



自分のケースでどの程度が妥当なのか判断する場合は、弁護士の見解を参考にして検討しましょう。
寄与分の主張で弁護士に依頼すべき5つのケース
寄与分を主張するには、証拠の整理や法律的な主張が欠かせません。どの行為が特別な貢献にあたるのか、財産にどれほど影響を与えたのかを示す必要があり、判断には法律知識が求められます。
寄与分の主張で弁護士に依頼すべきケースは以下の5つです。
また、寄与分に関する複雑な法律問題を円滑に進めるには、弁護士に依頼して適切に手続きを進めることが大切です。
協議で主張が認められず調停や裁判に移行しても、弁護士に依頼すれば代理人として心強い味方になってくれるでしょう。
実際、日本弁護士連合会の調査によると、遺産分割調停で弁護士が関与する割合は2018年で79.7%、2023年で80.5%となっています。2018年からは80%前後で推移しており、弁護士が関与ケースが多数を占めています。(参照:日本弁護士連合会|遺産分割調停事件における代理人弁護士の関与状況)
これから紹介するケースに当てはまる方は、公平で穏便な遺産分割を行うためにも、弁護士への相談を検討してみましょう。
遺産分割協議が難航している
遺産分割協議が難航し、他の相続人との間で感情的な対立が生まれそうな場合は弁護士に依頼しましょう。
寄与分を主張しても「家族として当然だ」と一蹴されることもあります。他の相続人から寄与分の不当な主張や要求をされているケースも、弁護士に依頼して解決することが望ましいです。
当事者だけで話し合うと感情的になりやすく、精神的な負担が増えてしまいます。弁護士が間に入れば、第三者の視点から冷静に話し合えるため、余計な衝突を避けやすくなるでしょう。
依頼者にとっても「自分の味方がいる」という安心感は、話し合いを進める上で大きな支えになります。
寄与分を証明する証拠の集め方がわからない
寄与分を証明する証拠を何から集めるべきかわからない方は、弁護士に早めに相談しましょう。
寄与分を認めてもらうには「どんな貢献をしたのか」を裏付ける証拠が欠かせません。しかし、介護日誌や診療明細、通帳記録など、何をどこまで集めれば良いのかは一般の方には分かりにくいものです。
また、証拠が不十分だと、寄与分が認められず不利な結果に終わる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、証拠の有効性を確認してくれるだけでなく、どのような資料を追加で集めるべきかアドバイスしてもらえます。
主張の説得力が増し、寄与分が認められる可能性を高められるでしょう。
自分ひとりで交渉するのは負担が大きいと感じている
寄与分の交渉をひとりで進めるのが難しい方、精神的な負担を感じている方は、弁護士への依頼を検討しましょう。
例えば、以下のようなケースでは精神的な負担が大きくなる傾向があります。
- 遺産に不動産や事業など複雑な財産が含まれるケース
- 仕事や育児で忙しく、手続きに時間を割けないケース
- 交渉や手続きの大変さに負担がかかっているケース
寄与分を請求するには、申立書の作成、裁判所への提出、相続財産の調査、証拠提出など多くの手続きが必要です。これらを一人でこなすのは時間も労力もかかり、書類の不備があればやり直しになってしまいます。
弁護士に依頼すれば、必要な資料を効率よくそろえ、全体の流れを管理しながら手続きを進めてもらえます。余計な負担を抱え込まずに済み、解決までの時間も短縮しやすくなるでしょう。
すでに調停・審判に進んでいる
遺産分割協議で寄与分を主張したときに話がまとまらず、調停や審判に進んでいる場合は弁護士に早めに依頼しましょう。
家庭裁判所での調停や審判で代理人として対応できるのは、弁護士だけです。法律の知識がないまま一人で臨むと、自分の言い分をうまく伝えられず、不利な結果になってしまう可能性があります。
特に調停や審判では、過去の判例や法的な論理をもとに主張を整理する必要があるため、専門知識が欠かせません。
弁護士に依頼すれば、代理人としてあなたの立場を代弁し、判例や法律を踏まえた適切な主張を展開してくれます。寄与分を正当に評価してもらえる可能性が高まるだけでなく、安心して手続きを進められます。
寄与分以外の相続トラブルも発生している
寄与分以外の相続トラブルも抱えている場合は、弁護士に依頼すべきケースのひとつです。
相続問題は寄与分だけでなく、遺留分侵害額請求や相続税対策、不動産の共有処分など、複数の争点が絡み合います。
一つひとつを別々に解決しようとすると手間も時間もかかりますが、弁護士に相談すれば包括的に整理してもらえるため、効率良く進められます。



すでに起きている問題だけでなく、将来的に新たな相続トラブルが発生した場合も、同じ弁護士に継続して相談できるのは大きな安心材料です。
相続を弁護士に任せるメリット・デメリットは、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:相続を弁護士に任せるメリット・デメリットとは?後悔しない弁護士の選び方も解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分の主張を弁護士に依頼したときの流れ
寄与分の主張を弁護士に依頼すると、証拠集めから調停・審判まで一貫してサポートを受けられるため効率的に手続きを進められます。
弁護士に依頼した場合の一般的な流れは、以下の通りです。
上記の流れを知っておくと、依頼後の見通しが立てやすくなります。
自分の寄与分に関する問題は今後どのように扱われていくのかイメージするためにも、以下で具体的な流れを確認しましょう。
寄与分の主張を裏付ける証拠を集める
寄与分を主張するには、まずどのように財産の維持や増加に貢献したのかを示す証拠を集める必要があります。証拠がなければ、生前に本当に貢献していたのかが伝わらず、主張が認められないためです。
例えば、以下のようなものが証拠に該当します。
- 被相続人のカルテ・診断書
- 要介護認定を証明する書類
- 介護の状況を示す日記や写真
例えば、介護施設に入れず自宅で10年間介護を続けた場合、被相続人のカルテや診断書、介護記録などを集める必要があります。
こうした資料をそろえることで、後の協議や調停で主張するときに説得力が増します。
必要な証拠はどのように貢献していたかによって異なるため、弁護士に何から集めれば良いか相談してみましょう。
遺産分割協議で寄与分を主張する
証拠をそろえたあとは、相続人全員で行う遺産分割協議の場で寄与分を主張します。この段階で合意が得られれば、家庭裁判所に進むことなく円満に解決できます。
ただし、相手が寄与分を認めない場合も少なくありません。そのため、主張内容を整理し、法的に説得力を持たせる準備をしておくことが大切です。
弁護士に間に入ってもらい、交渉をスムーズに進められるようにしておきましょう。
なお、寄与分は時効はありませんが、主張できるのは相続開始を知った日から10年以内です。(参照:民法|第904条の3)
期限を過ぎると主張できず、取り分が本来の法定相続分になってしまうため、早めに手続きを行いましょう。
協議で合意が得られない場合は遺産分割調停を申し立てる
協議で話がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では裁判所が間に入り、中立的な立場で話し合いを進めてくれます。
遺産分割調停を申し立てる際は、申立書と添付書類を管轄の家庭裁判所に提出します。添付書類は相続人の立場によって異なるため、詳細は裁判所のホームページでもご確認ください。
弁護士に依頼していれば、判例や法律をもとに適切に主張してもらえます。
自分の思いを感情的に話すだけでは不利になりやすいため、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
調停でも解決しなければ審判に移行する
調停が不成立の場合、家庭裁判所が審判を下します。裁判所がそれぞれの言い分や主張を考慮し、取り分を決定するフェーズです。
証拠が不十分だと、相続人同士の話し合いで「本当にその支援が財産の維持や増加につながったのか」と疑われてしまい、主張が通りにくくなります。
寄与分を主張する際には、STEP1で集めた証拠を提出し、貢献の内容を丁寧に説明していくことが大切です。
審判結果に納得いかない場合は即時抗告を申し立てる
審判で下された判断に納得できない場合は、即時抗告で不服を申し立てることができます。
即時抗告とは、家庭裁判所の審判に対して上級の裁判所(高等裁判所)が改めて審理する制度です。
申立期限は審判書を受け取ってから2週間以内と定められており、期限を過ぎると即時抗告できなくなるため注意が必要です。(参照:裁判所|即時抗告)
即時抗告では、調停や審判で提出した証拠や主張を見直し「どの部分が不当なのか」「法的判断に誤りがあるのか」を整理する必要があります。
例えば、介護にかかった実費や労力が正しく考慮されていない場合や、証拠の評価に疑問が残る場合などは抗告理由になり得ます。
即時抗告は時間と費用がかかるため、現実的にどこまで争うかを冷静に判断することも欠かせません。審判結果が最初と変わることもあります。



即時抗告を検討する際には「このまま審判結果を受け入れるのか、即時抗告した場合のリスクを比較した上で決断することが大切です。
相続トラブルの主張を弁護士に依頼するときの費用はどのくらい?
寄与分の主張が絡む相続トラブルについて弁護士に依頼すべきか検討している方は、費用がどのくらいかかるか気になるかもしれません。
寄与分の主張を含め、弁護士に相続トラブルについて相談や依頼をするときの費用相場は以下のとおりです。
| 項目 | 費用相場 | 補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 無料~30分5,000円程度 | 初回無料相談を実施している法律事務所も多い |
| 着手金 | 20万〜50万円程度 | 法律事務所や案件の複雑さによる |
| 成功報酬 | 得られた財産の10〜15%程度 | 経済的利益に応じて変動する |
| 実費 | 5万円〜7万円程度 | 交通費・郵便代・印紙代など。案件の進行に応じて必要になる |
| 日当 | 移動距離や拘束時間によって金額が変動 | 裁判所への出廷や遠方での対応が必要な場合は加算 |
上記はあくまで目安であり、実際は案件の内容によって異なります。



ご自身のケースでどのくらいの費用になるかの詳細は、初回相談の際、担当の弁護士にご相談ください。
寄与分の弁護士依頼に関するよくある質問
被相続人と同居していた場合、寄与分の請求が認められますか?
結論として、単に同居していただけでは寄与分にはなりにくいとされています。同居に加えて、特別な貢献が必要とされているためです。
例えば「長期的に介護を担った」「住宅ローンを肩代わりした」などの、被相続人の財産を維持、あるいは増加させたと認められることが条件です。
そのためには、医療費の支出記録や介護日誌、不動産契約の資料など、客観的に裏付けられる証拠を提示する必要があります。
寄与分に上限はありますか?
寄与分には法律上の上限があり、相続開始時の財産から遺贈分を控除した額を超えることはできません。
(寄与分)
第九百四条の二 第三項
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
つまり、寄与分の請求で相続財産をすべて取得することは認められていません。
実際の金額は、相続人同士の協議や調停・裁判で決まるため、専門的な判断を得るためにも弁護士の関与が重要になります。
寄与分主張整理表とは何ですか?
寄与分主張整理表とは、調停や審判でどのような寄与をしたのかを体系的に示すための書類です。
相続人の氏名や続柄、介護や事業手伝いの内容、期間や方法を時系列でまとめ、財産の維持・増加につながった具体的事実と証拠を添えて整理します。



書き方には法律的な視点が求められるため、弁護士と相談しながら作成することが望ましいです。
まとめ|寄与分を確実に受け取るなら早めに弁護士に相談しよう
寄与分は、相続人が介護や事業支援などの特別な貢献を行ったときに、遺産の取り分を増やせる制度です。
ただし「法定相続人であること」や「無償で長期間の貢献を続けたこと」といった条件を満たす必要があり、誰でも認められるわけではありません。
さらに金額の計算に明確な基準はなく、過去の事例や判例をもとに判断されるのが実情です。
主張を認めてもらうには、証拠の整理や調停・裁判での立証が欠かせません。専門知識を持つ弁護士に早めに相談すれば、寄与分を適切に主張できる可能性が高まります。



寄与分を受け取りたい方は、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を進めていきましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応