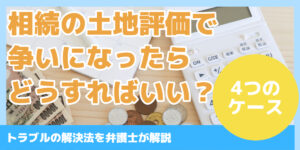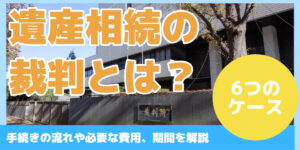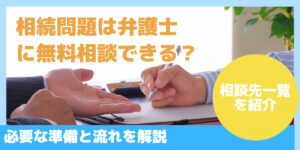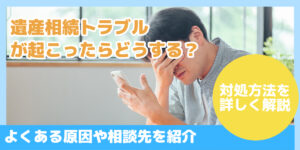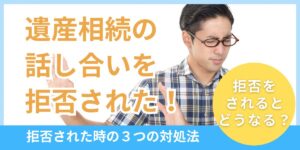【無料相談受付中】24時間365日対応
生前整理のやり方とは?始めるタイミングやメリット・デメリットをわかりやすく解説
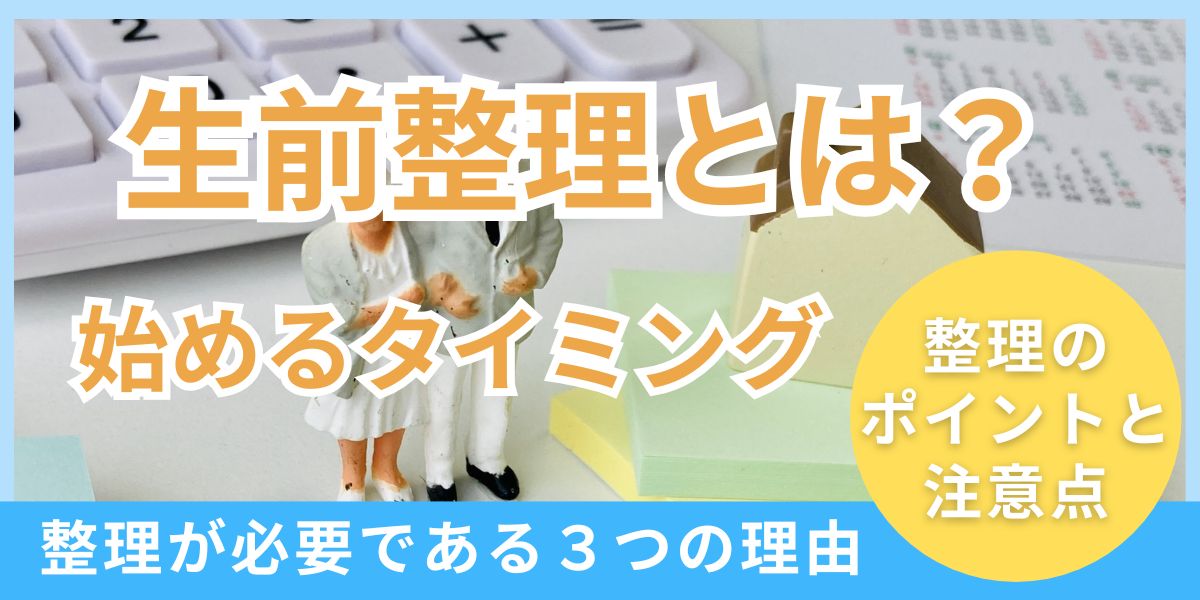
近年、自分が生きている間に身の回りのものや財産を生前に整理する人が増えています。
いわゆる生前整理です。
故人の遺産や遺品の整理は通常遺族が行うことになるでしょう。
しかし、自分の財産の整理を生前に行っておけば、遺産相続時の家族の負担を軽減できます。
生前整理を行うのは、自分の死後に残される家族の負担を軽減するためでもあり、本人自身のためでもあります。
本記事では、生前整理の必要性やメリット、進め方と注意点などを解説します。
生前整理の進め方で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
初回60分の相談は無料です。
\ 相談実績7000件(突破)/
【無料相談受付中】24時間365日対応
生前整理とは

生前整理とは、人生の終末を見据えて、本人が生存中に自分の身の回りのものや財産を整理することです。
生前整理を行っておけば、遺産相続時の家族の負担を軽減できます。
本人自身も、本当に必要なものだけに囲まれたスッキリした生活が可能になるでしょう。
さらに、整理を行うことが遺産相続を考えるきっかけとなり、遺言書の検討・作成も進めやすくなります。
似た用語として「遺品整理」がありますが、自分の死後に家族が行うもので、整理する人や時期・目的が違います。
生前整理を行う必要性と3つのメリット

生前整理は自分と家族の負担を軽減するだけでなく、自分自身が前向きに生きるためにも必要なことです。
生前整理を行うメリットは、主に3つあります。
家族の負担を軽減できる
まず、家族の遺産相続・遺品整理の負担を減らせることです。
自身が亡くなった場合、残された家族が、葬儀に続き遺産や遺品の整理をすることになりますが、遺産や遺品の整理は思いのほか手間がかかる大変な作業です。
そのため、処分業者に依頼する場合もありますが、そうなると費用がかかります。
さらに、預貯金や不動産などの遺産相続は、故人の意向が明確でない場合、相続人間で意見が対立することもあるでしょう。
不要なものを処分し、遺言を書いておくなどしておけば、家族はトラブルなくスムーズに対応できます。
遺産相続手続きについては、詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:親の遺産相続手続きの方法は?死亡後の手続きや優先順位
相続トラブルを防ぎ財産を引き継げる
生前整理をしておけば、大切な財産や思い出の品を相続時にトラブルなく、引き継ぐことができるでしょう。
配偶者や子どもに財産の所在をきちんと伝えておかないと、相続人同士で争いが起こりかねません。
たとえば、遺産分割協議後に新たな遺産が見つかると、遺産分割協議をやり直す必要があるだけでなく、「財産を隠した」とトラブルになる可能性もあります。
生前整理をして、財産や書類の保管場所を家族にきちんと伝えておけば、相続人同士で揉めるリスクを事前に防ぐことができます。
遺産相続のトラブルの原因と予防するコツについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:遺産相続で揉める人と揉めない人の差は何?トラブルの原因と予防するコツを解説
自身の気持ちがスッキリし前向きなれる
生前整理をすることで、物理的にスッキリするだけでなく、精神的にもスッキリするものです。
不要物の断捨離によりストレスが減るだけでなく、生前整理をしておくことで「相続でトラブルにならないか」との不安も解消されるでしょう。
大事な財産の整理が済んでいると思えば、心理的に余裕が生まれ、新たな目標が見えてくる期待も持てます。
生前整理は、家族のためであるとともに、自分自身の気持ちの整理にもなるでしょう。
生前整理を行うデメリット
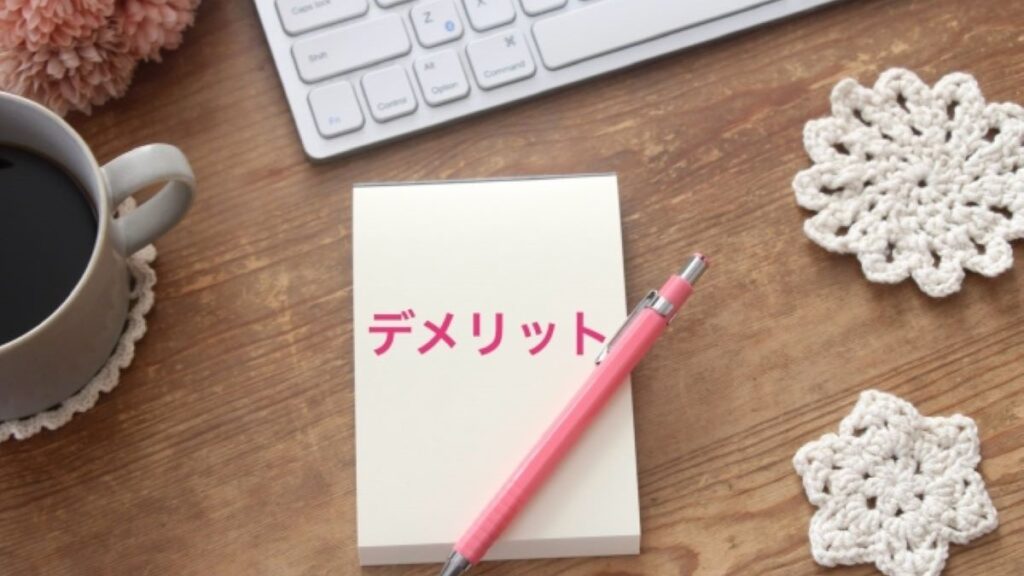
生前整理にはデメリットもあります。
主なデメリットは、次の2点です。
時間と労力がいる
生前整理には、時間と労力がかかります。
身の回りのものの整理や、財産の正確な把握・整理は、手間のかかる面倒な作業です。
何が必要で何が不要かは、すぐに決断できない場合もあります。時間的な余裕をもって計画的に進めなければなりません。
費用がかかる
生前整理をするためには、費用がかかります。
たとえば、粗大ゴミや不用品が多く、自分一人では整理が難しい場合もあるでしょう。
不用品買取業者に処分を依頼できますが、思いのほか費用がかかることがあります。
不要な不動産を処分する場合も、仲介手数料や譲渡益課税(譲渡所得税・住民税など)が発生することもあるでしょう。
中には買い叩きや不当に高額な代金を請求する悪質なケースもあるかもしれません。
複数業者から見積もりを取るなどして、比較検討する必要があります。
生前整理を進める手順

生前整理をスムーズに進める手順は次の通りです。
1.やることリストの作成
まず、生前整理でやるべきことのリストを作りましょう。
リスト化することで、作業の目的や手順を認識して効率よく進められます。
たとえば、次のようなリストです。
- 身の回りの物品整理
- 財産の整理、財産目録の作成
- データ、アカウント情報の整理
- その他の身辺整理など
2.必要なものと不要なものの分別・処分
必要なもの・不要なものを分別し、不要なものを処分しましょう。
たとえば、次のような自分なりのルールを決めて着手するとスムーズに整理できます。
- 一定期間使用しなかったものは処分する
- 利用していない口座やカードは解約し、できるだけ集約する
パソコンなどの不要なデータも削除し、大事なデータはきちんとわかるように記録媒体に保存するなどの工夫も必要です。
3.財産の整理と財産目録の作成
預貯金・不動産などの財産をリスト化した財産目録を作成しておきましょう。
プラス財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も記録する必要があります。
財産目録があれば、遺産相続時に家族が財産を調べる手間が減り、トラブル防止にも役立つでしょう。
財産目録は、印刷しておくか、パソコンなどのデータファイルとしてパスワードとファイルの保存場所などを明確にしておくことが大事です。
4.エンディングノートの作成
エンディングノートを作ることも大事です。
エンディングノートは、万が一のときの延命措置の可否や葬儀・形見分けなどの希望、家族へのメッセージなどを記し家族に残すものです。
パソコンのパスワードやスマホのロック解除の仕方なども書き残しておくとよいでしょう。
書式も記載内容も自由です。ただし、法的拘束力はありません。
5.遺言書を作る
遺言書の作成も重要です。
誰にどの財産をどれだけ渡すかを記載しておきましょう。
正式な遺言書があればトラブルのリスクが減ります。
公証役場で保管する「公正証書遺言」にすれば、法的効力がある遺言書の作成が可能です。
遺言書については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事:【例文付き】遺言書の書き方とは?必須項目や注意点を解説
6.相続税対策も必要
課税遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続人が相続税を申告・納税する義務があります。
相続税の基礎控除額と税率は、次の通りです。
| 相続税 | 基礎控除:3000万円+600万円×相続人数 課税相続財産額が基礎控除を超える場合、申告が必要 | 税率10%~55% 法定相続分に対する累進税 |
|---|
出典:国税庁|No.4155相続税の税額
生前贈与や生命保険非課税枠、住宅取得等資金贈与の非課税特例活用などの相続税対策をしておけば、相続税額を抑えられます。
弁護士法人アクロピースは、税理士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携があるため、スムーズな手続きができます。
生前贈与と課税の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事:生前贈与を非課税で行う6つの方法と契約書の書き方のポイントを徹底解説
生前整理を始めるタイミング

生前整理を始める時期は特に決まりはありません。
いつ始めてもよいものですが、人生を見つめなおすきっかけともなるため、ライフイベントや区切りのよい年代などを目安にするとよいでしょう。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
【健康なうちに始める:30代・40代~】
健康なうちに余裕を持って取り組むことも重要です。
重い家具の移動や時間がかかる整理は、根気と体力が必要なため、健康なうちに始めましょう。
パソコンや銀行口座などのID・パスワード整理も重要です。
【子どもの就職・結婚などを機に始める:50代~】
たとえば、モノの整理、不用品処分などを行いましょう。
【定年退職頃:60代後半~】
時間的余裕もできるため、丁寧に整理を進められます。
新しいスタートに向け身辺を整理し、エンディングノート・遺言書も作成しておきましょう。
いつかやろうではなく、今始めるという意識が重要です。
生前整理を行うときのポイント・注意点
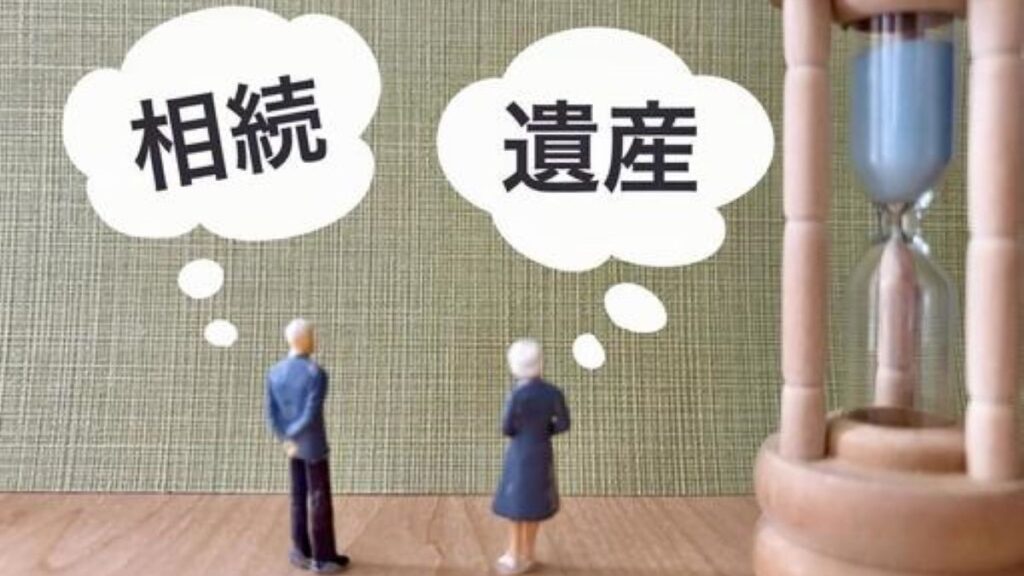
生前整理を行うときのポイント・注意点は、次の通りです。
- 家族と一緒に整理する
家族と思い出を語る機会になるうえ、財産の分配の意向などを共有できます。
- いつかやろうではなく今始める
「暇になったら」などと後回しにせず、早めに行動を起こしましょう。
- 少しずつ進める
一度に一気に整理しようとすると、挫折するかもしれません。無理せずに少しずつ進めることが重要です。
- 前向きに取り組む
生前整理はネガティブなイメージを持つかもしれませんが、人生を振り返り、今後の生き方を考えるよいきっかけです。
生前整理をしておけば身の回りもスッキリし、気持ちも晴れやかになるでしょう。
まとめ
生前整理の進め方についてまとめます。
- 生前整理は生存中に自分の身の回りのものや財産を整理すること
- 家族の負担を軽減するだけでなく、自分自身が前向きに生きるためにも必要
- 生前整理を行うメリットは、家族の負担を軽減し相続トラブルを防げる
- 生前整理の手順は、やることリストの作成、必要なものと不要なものの分別・処分、財産整理と財産目録の作成、エンディングノートや遺言書を作ることなど
- 生前整理を始める時期は、ライフイベントや区切りのよい年代などを目安にするとよい
- 生前整理は、家族と一緒に行う
- いつかでなく今始める・少しずつ進める・前向きに取り組むこと
生前整理は思いのほか手間暇がかかる大変な作業です。思い立ったときに早く始めましょう。
生前整理など相続についてわからないことや揉めごとがあるときは、相続分野に精通している弁護士に早めに相談することをおすすめします。
弁護士法人アクロピースは、相続問題に強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
初回60分の相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
【無料相談受付中】24時間365日対応