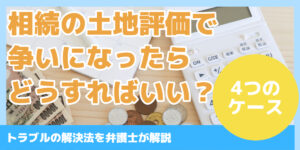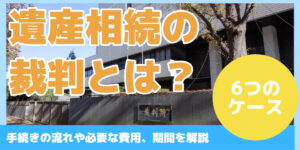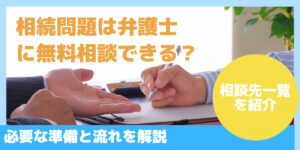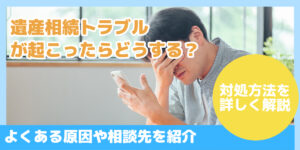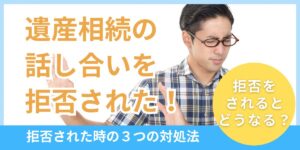【無料相談受付中】24時間365日対応
相続の手続き期限6ヶ月以内にやるべきこと!具体的な手続き方法も解説
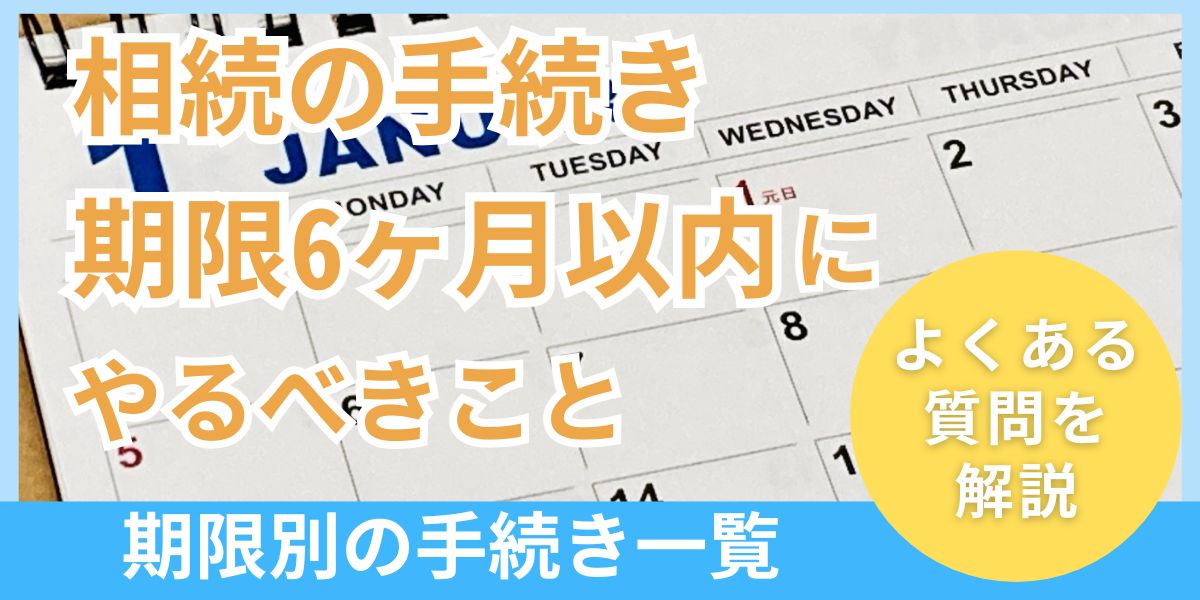
相続手続きにおいては、被相続人が亡くなった悲しみの中で、相続手続きを進めていくのは精神的に大きな負担となります。
しかし、相続の手続きには期限が決められているものが多くあるのです。
期限を過ぎると取り返しがつかない手続きもあるため、相続手続きの期限には十分に注意しなければなりません。
この記事では、これから相続手続きを始めようとしている方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
この記事を最後までご覧いただければ、期限ごとに必要な相続手続きを一覧で確認できます。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫相続手続きで何から始めたら良いかと迷っている方や手続きの漏れがないのか不安に感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
6ヶ月以内に期限が来る相続手続きの一覧


被相続人が亡くなってから6ヶ月以内に期限が来る相続手続きの一覧は、次のとおりです。
| 7日以内に期限が来る手続き | 死亡診断書の受取・提出 火葬許可申請書の提出 |
| 14日以内に期限が来る手続き | 世帯主の変更届 国民年金の受給停止 |
| 3ヵ月以内に期限が来る手続き | 相続放棄 限定承認 |
| 4ヶ月以内に期限が来る手続き | 準確定申告 |
それぞれの手続きの内容について詳しく解説します。
7日以内に必要な相続の手続き
被相続人が亡くなってから7日以内に済ませるべき手続きは、次のとおりです。
- 死亡診断書の受取・提出
- 火葬許可申請書の提出
死亡診断書とは、被相続人の死亡を証明する診断書のことです。
被相続人が病院で亡くなった場合には、最期を看取った医師が死亡診断書を作成します。
自宅で亡くなった場合でも、生前に病院にかかりつけの病院があるときには主治医が死亡診断書を作成するのが通常です。
死亡診断書は、死亡届と一体となった書類です。
医師から死亡診断書を受け取ったあとは、被相続人が亡くなってから7日以内に市町村役場に提出しなければなりません。
なお、事故死や突然死など、生前に病院の診察を受けていなかった場合には、死亡診断書の代わりに死体検案書が作成されるので、死亡診断書と同じく7日以内に市町村役場への届出を行ってください。
火葬許可申請書は、遺体を火葬するための申請書です。
火葬許可申請書の提出について、法律上の期限はありませんが、死亡診断書と同時に市町村役場に提出するのが通常です。
火葬許可申請書の提出なしでは葬儀の後の火葬ができなくなりますので、忘れずに提出するようにしてください。
14日以内に必要な相続の手続き
14日以内に必要な手続きは、次のとおりです。
- 世帯主の変更届
- 国民年金の受給停止
世帯主が亡くなったときは、14日以内に世帯主の変更届を提出しなければなりません(住民基本台帳法25条)。
国民年金の受給停止手続きも、被相続人が亡くなってから14日以内に済ませる必要があります。
受給停止手続きを行うには、受給権者死亡届に年金手帳と受給者が亡くなったことがわかる書類を添付して年金事務所に提出します。
年金の受給停止手続きを行わず、被相続人が亡くなってからも年金を受け取り続けると、不正受給で処罰される可能性もあるため、十分に注意してください。
相続放棄・限定承認【3ヶ月以内の手続き】
相続放棄もしくは限定承認する場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に家庭裁判所での申述手続きを行わなければなりません(民法915条1項)。
相続放棄とは、一切の権利・義務についての相続を放棄する手続きのことを言います。
相続放棄する場合には、プラスの財産であるとマイナスの財産であるとを問わず、すべての権利を放棄しなければなりません。
限定承認とは、相続財産におけるプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐ相続の方法です。
相続放棄や限定承認の期限を過ぎると、相続を単純承認したものと見なされます。
単純承認してしまうと、被相続人に多額の負債があった場合でもそれを引き継がなければなりません。
被相続人に負債がある場合には、期間内に相続財産の調査を進めて、相続放棄や限定承認の手続きをするのか、単純承認するのかを慎重に判断する必要があります。
なお、手続きの期間が過ぎる前であれば、家庭裁判所の手続きで期間を伸長することも可能です。
また、後で負債が判明したように、放棄の期限が過ぎたあとでも相続放棄をすることができることもありますが、可能な限り期限内に調査を行い、相続放棄するかどうか決めるのが良いでしょう。
相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:相続放棄の手続きの流れは?相続放棄の基本・申述費用・必要書類
準確定申告【4ヶ月以内の手続き】
準確定申告は、被相続人が亡くなって相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、手続きをしなければなりません。
準確定申告とは、年の途中で亡くなった人の確定申告手続きのことです。
準確定申告の手続きを行うには、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得税の額を計算し、申告と納税を済ませる必要があります。



期限を過ぎると加算税や延滞税を課される可能性があるため、手続きが必要な場合には早めに済ませるようにしてください。
6ヶ月以降に期限が来る相続手続きの一覧


被相続人が亡くなってから6ヶ月以降に期限が来る相続手続きの一覧は、次のとおりです。
| 10ヶ月以内に期限が来る手続き | 相続税の申告・納付 |
| 1年以内に期限が来る手続き | 遺留分侵害請求 |
| 3年以内に期限が来る手続き | 相続登記 |
それぞれの手続きについて詳しく解説します。
なお、改正後の遺留分侵害額請求の流れについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてご覧ください。
相続税の申告・納付【10ヶ月以内の手続き】
相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなって相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、手続きをしなければなりません。
手続きの期限を過ぎると、延滞税や加算税などの追徴課税を課される可能性があります。
相続税は、常に発生するわけではありません。
国税庁の「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、被相続人の亡くなった数に対して、相続税が課税された人の割合は9.9%でした。
相続税を課税されない人の割合が大きいのは、相続税に基礎控除があるためです。
相続財産が基礎控除の範囲内の場合、相続税は発生せず申告手続きも必要ありません。
相続税の基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が4人いる場合には、基礎控除の額が5400万円となり、遺産総額が5400万円以下であれば相続税がかかりません。
相続税については、基礎控除以外にもさまざまな控除や特例による税額軽減の制度があります。
特例を利用する場合は相続税が発生しない場合でも申告手続きが必要となるため注意が必要です。
なお、申告内容の間違いや手続き後の事情の変化により、更生による相続税の還付が可能な場合には、5年10ヶ月以内に手続きを済ませる必要があります。
期限を過ぎると還付を受けられなくなってしまうため、更生手続きが可能な場合には早めに手続きを済ませるようにしてください。
遺留分侵害額請求【1年以内の手続き】
遺留分侵害額請求を行う場合には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った日から1年以内もしくは相続開始から10年以内のいずれか早く到来する期間内に請求しなければなりません(民法1048条)。
最低限の取り分(遺留分)を持つ相続人が、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害した人に対して、その遺留分に相当する金銭の支払を請求する手続きのこと
遺留分侵害額請求は、1年以内に遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をした証拠を残しておくためには内容証明郵便を利用して手続きを進めるべきです。
遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:【遺留分侵害額請求とは】対象となる財産・計算・手続きの方法
相続登記【3年以内の手続き】
相続登記は、相続の開始と相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを済ませなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。
相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きのこと
期限を過ぎると、10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
2024年4月1日に相続登記が義務化されました。
なお、相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。



2024年4月1日よりも前の相続登記については、同日から3年以内に手続きを済ませなければなりません。
明確な期限のない相続手続きの一覧


次の相続手続きについては、法律上の明確な期限はありません。
ただし、手続きを進めなければ他の期限がある手続きが遅れてしまったり、権利関係が確定せずに不安定な状態が続いてしまったりする可能性があります。
そのため、期限がない手続きであっても、できる限り早めに手続きを進めるべきです。
それぞれの手続きの内容を解説します。
遺言書の検認手続き
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときには、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
検認手続きについて法律上の期間制限はありませんが、遺言書の検認なしでは遺言に基づいた相続手続きを始められないため、遺言書を発見したら速やかに検認手続きを済ますべきです。
検認手続きの前に遺言書を開封してしまった場合は過料の制裁を受けることになり、最悪の場合には相続の権利を失ってしまうこともあります。
遺言書の種類や検認手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法(種類別)・見つけた場合の対応方法(検認手続き)
遺産分割協議
他の相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺産分割協議もできる限り速やかに進めるべきです。
相続人全員の同意で遺産の分割方法や割合を決める手続きのこと
遺産分割協議にも法律上の期間制限はありません。
しかし、遺産分割協議で誰が遺産を取得するのかが決まらなければ、相続税の申告や相続登記など、期間制限のある手続きを進めるのが難しくなってしまいます。
遺産分割協議について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:遺産相続でもめた場合の対処法・遺産分割協議のスムーズな進め方
預貯金の名義変更
預貯金の名義変更についても、誰が口座を相続するのかが決まり次第、手続きを進めるようにしてください。
被相続人の預貯金を引き出すには、預貯金の名義変更が必要です。
預貯金の名義変更にも法律上の期間制限はありません。
しかし、名義変更を済ませなければ、預金の払戻しを受けることもできず、せっかくの相続財産を活用できなくなってしまいます。



また、10年以上の長期間放置すると、休眠口座に指定されてしまう可能性もあります。
関連記事:相続での預貯金の名義変更について解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
相続手続きの期間制限についてよくある質問


ここでは、相続手続きの期間制限についてよくある質問に回答します。
期限内に相続の手続きを終えられなかったらどうなりますか?
期限内に手続きを終えられなかった場合、手続きの種類に応じてさまざまな不利益が発生します。
たとえば、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、相続放棄ができなくなり多額の負債を相続してしまう可能性があります。
遺留分侵害額請求の期限を過ぎてしまったときは、遺留分を侵害されている場合でも一切の請求ができなくなってしまうのです。
準確定申告や相続税といった税金の申告については、期限を過ぎると加算税や延滞税が課されます。
相続税の金額が大きい場合には、多額の追徴課税を課される可能性もあるため期限には十分に注意しなければなりません。
どうしても期限に間に合わないときはどうしたら良いですか?
相続放棄や限定承認については、3ヵ月の期限が過ぎる前であれば家庭裁判所で期限の伸長手続きが可能です。
相続税の申告については、遺産分割協議が調う前であっても相続分にしたがって申告を済ますことができます。
相続手続きが間に合うかどうか不安な場合には、早めに専門家に相談することが重要です。
関連記事:相続問題は弁護士に無料相談できる?



期間が過ぎる前に専門家に相談すれば、急いで手続きを進めてもらうこともできますし、期限を伸ばす方法があれば提案もしてもらえます。
まとめ
今回は、相続手続きの期限を理解するために、次の内容について解説しました。
- 相続手続きを進めるには各手続きの期限を守らなければならない
- 相続手続きの期限を過ぎると、多額の負債を負ったり、遺産を受け取れなくなったりなどの不利益を受ける可能性がある
- 相続手続きに不安のある方は、早めに専門家に相談すべき
相続手続きでお困りの方は、弁護士への相談がおすすめです。
アクロピースでは、60分間の無料相談を実施しておりますので、相続手続き全般などお気軽にお問い合わせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応