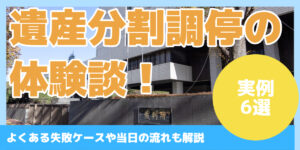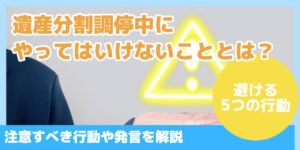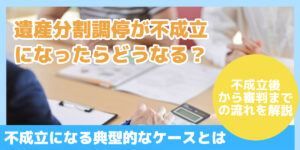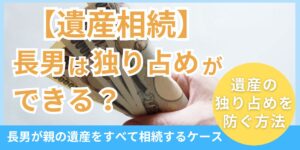【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停の費用はいくら?不動産鑑定にかかる費用や弁護士費用や裁判費用など誰が払うのかも解説
「遺産分割調停を申し立てたいけれど、裁判所や弁護士にどのくらい費用がかかるのか不安」
「不動産の評価を依頼した場合、鑑定費用を誰が負担するのか知りたい」
家庭裁判所での遺産分割調停を検討しており、このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
遺産分割調停を申し立てる際は、裁判所での申し立て費用だけでなく、弁護士や司法書士への依頼料、不動産鑑定士の報酬も考慮する必要があります。
本記事では、遺産分割調停に必要となる費用の内訳を整理し、家庭裁判所に納める実費から専門家に依頼する際の相場まで詳しく解説します。
遺産分割調停の裁判所費用は1万円前後と少額:収入印紙や切手代などの実費のみで、手続き自体のハードルは高くない。
弁護士費用は数十万〜数百万円と幅がある:着手金・報酬金が中心で、遺産額や争点の多さによって総額が大きく変動する。
費用は原則「各自負担」で相手に請求できない:申立費用や弁護士費用を相手方に負担させることは通常できず、自己負担が前提となる。
不動産が争点になると鑑定費用が追加発生する:評価額で揉めた場合、20万〜60万円程度の不動産鑑定費用が別途かかる可能性がある。
自己対応は“費用倒れ”のリスクがある:専門知識不足により寄与分・特別受益を見落とすと、弁護士費用以上の不利益を被るおそれがあるため、早期相談が合理的。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫費用の内訳を細かく紹介しているため、遺産分割調停で悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停にかかる費用の全体像
遺産分割調停を進めるにあたって必要となる費用は、大きく分けて「家庭裁判所へ納める実費」と「専門家へ支払う報酬」の2種類に分類されます。手続き自体にかかる実費は比較的低額で済みますが、弁護士や司法書士への依頼費用については、遺産額や依頼する業務範囲によって大きく変動する点が特徴です。
調停完了までに想定される費用の全体像と金額の目安は以下のとおりです。
| 費用項目 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所に納める費用 | 1万円程度 | 調停を申し立てるために必要な収入印紙代や切手代など |
| 弁護士費用 | 数十万円~数万円程度(案件によって変動) | 相談料、着手金、報酬金、実費など案件に応じて変動 |
| 司法書士費用 | 5万円~20万円程度 | 書類作成や一部手続きのサポートにかかる費用 |
| 不動産鑑定費用 | 20万円~60万円程度 | 相続財産に含まれる不動産を評価・鑑定するための費用 |
裁判所に納める実費は基本的に定額である一方、専門家費用や鑑定費用は個別の事情により総額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
資金不足で手続きが停滞することを避けるためにも、ご自身のケースではどの費用が発生しそうか、あらかじめシミュレーションしておくことおきましょう。



監修者コメント
遺産分割調停において、費用への不安から弁護士依頼を躊躇される方は少なくありません。
しかし、専門家のサポートがないまま不利な条件で合意してしまい、結果的に弁護士費用以上の損失を被るケースが散見されます。本記事では、費用の内訳や負担ルールに加え、どのような場合に専門家に依頼すべきかの判断基準を解説します。適正な遺産獲得のためのガイドとしてご活用ください。
遺産分割調停の申し立てで家庭裁判所に納める費用【4項目】
遺産分割調停の申し立てのために家庭裁判所に納める費用は、以下の4項目です。
何にいくらかかるのか理解し、今後の資金計画の見通しを立てましょう。
収入印紙代|被相続人1人につき1,200円
調停を申し立てる際の手数料として、被相続人(亡くなった方)1人につき1,200円分の収入印紙が必要です。
この費用は法律で定められており、申立書に収入印紙を貼付する形で家庭裁判所に納付します。印紙が貼られていない申立書は受理されないため、漏れのないよう準備してください。(参照:法務省|遺産分割調停)
収入印紙は以下の場所で購入できます。
- 郵便局
- 法務局
- 一部のコンビニ
また、相続手続き全体を通して見ると、遺産分割調停以外にも収入印紙が必要になる場面(不動産登記や他の裁判所手続きなど)が想定されます。手続きのたびに購入する手間を省くため、少額の印紙は多めに手元に用意しておくと、いざという時に役立つでしょう。
連絡用の郵便切手代|申し立てする家庭裁判所によって異なる
調停手続きにおいて、裁判所が当事者に書類を送付するための費用として、郵便切手代(予納郵券)をあらかじめ納める必要があります。(参照:法務省|遺産分割調停)
必要な切手の金額や内訳(84円切手が何枚、10円切手が何枚など)は家庭裁判所ごとに異なりますが、一般的には数千円程度で収まるケースが大半です。
例えば、東京家庭裁判所の場合、以下の金額が目安です。(参照:法務省|予納郵便料等一覧表 (令和7年1月版))
- 相手方が5名までなら3,000円
- 10名までなら6,000円分
相続人の人数が増えるほど必要な切手代も加算されるため、関係者の人数が確定した段階で確認することをおすすめします。
なお、手続き終了後に余った切手は返還されますが、審理が長期化して郵送回数が増えた場合は、追加納付(追納)を求められる可能性があります。正確な金額については、管轄の家庭裁判所のウェブサイトや窓口で最新の運用を確認してください。
書類取得費用|数千円~数万円
遺産分割調停を申し立てるためには、多くの添付書類をそろえる必要があります。戸籍謄本や住民票、遺産に関する証明書などの取得にかかる費用の目安は、合計で数千円~数万円程度です。
以下に、主な書類の取得費用の目安をまとめました。
| 主な書類 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 除籍・改製原戸籍謄本でも可 | 1通 450円※除籍・改製原戸籍謄本は750円 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続関係を確認するために必要 | 1通 450円 |
| 相続人全員の住民票 | 現住所や本籍地の確認用 | 1通 200円~400円 |
| 残高証明書(遺産に預貯金がある場合) | 金融機関で発行可能 | 300円~1,000円程度 |
| 不動産登記事項証明書(遺産に不動産がある場合) | 書面かオンライン請求によって金額が異なる | 書面で請求:600円 【オンライン申請】郵送で受け取り:520円窓口で受領:490円 |
| 固定資産税評価証明書(遺産に不動産がある場合) | 市区町村役場で発行可能 | 1通 200円~400円 |
これらの書類は、相続人の人数や相続財産の種類によって必要枚数が増えるため、合計すると数万円になるケースも珍しくありません。
また、戸籍謄本や住民票、遺産の証明書類などは、市区町村や発行する機関によって異なります。上記はあくまで相場のため、事前にどれくらいかかるのか問い合わせておくと良いでしょう。
家庭裁判所までの交通費|居住地によって異なる
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てると、期日ごとに裁判所へ足を運ぶ必要があり、その際に交通費が発生します。特に以下のようなケースでは交通費や宿泊費だけで数万〜数十万円単位の出費となるリスクも想定しておく必要があります。
- 遠隔地で、新幹線や飛行機を利用する必要がある
- 調停が長期化し、何度も出頭しなければならない
- 宿泊が必要になる
上記に該当する場合は、交通費も考慮した資金計画を立てておくことが大切です。
なお、ご自身での出頭が難しい場合は、弁護士を代理人に立てることで、ご本人の出頭を免除あるいは回数を減らすことが可能です。



ただし、その場合は弁護士の日当や交通費が別途発生するため、どちらが経済的・精神的に有利かを含めて検討することをお勧めします。
遺産分割調停にかかる弁護士費用【6項目】
遺産分割調停の代理人を弁護士に依頼する場合、その費用構造は主に6つの項目で成り立っています。
弁護士費用の総額は案件の内容や複雑さによって変動するため一律ではありませんが、あらかじめ内訳を把握することで概算を見積もることが可能です。主な費用項目と相場の目安は以下の通りです。
| 費用項目 | 費用の目安 | 内容 |
| 法律相談料 | 無料~30分5,000円程度 | 初回の相談にかかる費用(無料の事務所も多い) |
|---|---|---|
| 着手金 | 20万円~50万円程度 | 依頼時に支払う初期費用(結果に関わらず発生) |
| 報酬金 | 獲得額の6~16%程度 | 調停成立時、経済的利益に応じて支払う成功報酬 |
| 実費 | 5万円~7万円程度 | 収入印紙代、切手代、交通費、コピー代など |
| 日当 | 1日3万円~5万円程度 | 弁護士が裁判所へ出頭・出張する際の手当 |
| 遺産調査費用 | 10万円~30万円程度 | 遺産の内容や相続人を調査するための費用 |



このように、初期費用としてまとまった金額が必要な「着手金」に加え、解決時に支払う「報酬金」が費用の大半を占める傾向にあります。
関連記事:遺産分割調停は弁護士なしでできる?依頼するメリットや調停の進め方を弁護士が解説
遺産分割調停にかかる司法書士費用
遺産分割調停の申し立て書類作成を司法書士に依頼する場合、依頼内容に応じた報酬が発生します。
一般的な費用の目安は5万円~20万円程度ですが、依頼範囲や相続財産の内容によって変動するため、事前の見積もりが重要です。相続登記の報酬に関するアンケート(2018年実施)では、不動産登記の代理業務で5万円前後が相場となっています。(参照:日本司法書士連合会|報酬に関するアンケート)
ここで注意したいのは、司法書士は調停の代理人になれない点です。司法書士と弁護士の業務範囲には、以下のような明確な違いがあります。
| 専門家 | 業務範囲 | 特徴 |
| 弁護士 | 代理人として交渉・出頭が可能 | 書類作成だけでなく、依頼者の代わりに調停期日で主張や交渉を行える |
|---|---|---|
| 司法書士 | 書類作成代行のみ | 申立書の作成は代行できるが、調停の場には本人が出席しなければならない |
司法書士はあくまで書類作成のプロであり、調停の場における法的な主張や相手方との交渉を代行する権限を持ちません。司法書士への依頼が向いているのは「申立書の作成だけ任せたい」「調停には自分で出席し、発言できる」というケースに限られます。



相続人同士の対立が激しく、法的な駆け引きが必要な場面では、交渉権を持つ弁護士への依頼が望ましいと言えるでしょう。
遺産分割調停にかかる不動産鑑定費用
遺産に含まれる不動産の評価額について相続人間で争いがある場合、裁判所選任の不動産鑑定士による鑑定が行われることがあります。
費用の相場は20万円~60万円程度ですが、対象となる不動産の形状や権利関係の複雑さによって増減するため、一律ではありません。
鑑定を行う最大のメリットは、客観的な適正価格(時価)を算出することで、評価額を巡る水掛け論を解消できる点にあります。ただし、費用対効果を考慮し、実務では費用を抑えられる簡易的な評価方法で合意形成を図るケースも少なくありません。
それぞれの評価方法における費用と特徴の違いは、以下の通りです。
| 評価方法 | 費用の目安 | 特徴 |
| 不動産鑑定(本鑑定) | 20万円~60万円 | 法的拘束力が強く、調停・審判での証拠能力が高い |
| 簡易査定(不動産業者) | 無料~数千円 | 市場価格の目安を知るには有効だが、証拠能力は低い |
| 固定資産税評価額 | 数百円(証明書代) | 公的な価格だが、実勢価格(時価)より低くなる傾向がある |
正式な鑑定は証拠価値が高い反面、コストの負担も大きくなります。



解決までの見通しや予算に応じて、どの評価方法を採用すべきか慎重に検討することが望ましいでしょう。
遺産分割調停にかかる費用は誰が払う?
遺産分割調停にかかる費用は、原則として各自負担です。申立てに必要な実費は申立人が、弁護士報酬は依頼者自身が支払うことになり、相手方に法的な支払い義務を課すことは通常できません。
ただし、実務上は相続人全員の合意に基づき、以下のように柔軟な取り扱いがなされるケースも存在します。
| 費用項目 | 原則的な負担者 | 例外的な対応・調整 |
| 裁判所実費(印紙・切手) | 申立人 | 最終的な遺産取得分から精算する合意が可能 |
|---|---|---|
| 弁護士費用 | 依頼者本人 | 相手方への請求は原則不可(不法行為等を除く) |
| 不動産鑑定費用 | 申立人 | 相続人全員で按分(折半)するケースが多い |
特に不動産鑑定費用は高額になりがちなため、当事者間で折半する、あるいは相続財産の中から支出するといった解決が図られる傾向にあります。



後々の精算トラブルを防ぐためにも、費用負担の割合について調停の早い段階で取り決めておくことが望ましいでしょう。
遺産分割調停の費用で損をする失敗パターン
遺産分割調停は、単に申し立てれば希望通りに解決するわけではなく、判断を誤ると経済的な損失を被る恐れがあります。よくある失敗として、以下の3つのパターンが挙げられます。
| 失敗パターン | リスクの内容 |
|---|---|
| 費用倒れ | 獲得できた遺産よりも弁護士費用の方が高くなってしまう(少額遺産など) |
| 不利な合意 | 知識不足のまま自分で調停を行い、本来主張できる寄与分や特別受益を見落とし、法定相続分より少ない遺産で合意してしまう |
| 長期化によるコスト増 | 調停不成立で審判へ移行し、解決までの時間と追加費用がさらに膨らむ |
このように、目先の節約のために自分だけで対応した結果、専門家に依頼する以上の損失を出してしまうケースは珍しくありません。
最善の結果を得るためには、調停に踏み切る前に弁護士による費用のシミュレーションを受け、費用対効果を冷静に見極めておくことが重要です。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産分割調停に踏み切る前に確認すべき3つのポイント


遺産分割調停を申し立てるには、前提として解決しておかなければならない課題があります。具体的には、以下の3点がクリアになっていないと、調停が不成立になったり、別の裁判手続きが必要になったりする恐れがあります。
円滑な解決のために、それぞれのチェックポイントを確認しましょう。
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
相続人全員の合意・参加が確定しているか
遺産分割は「相続人全員の合意」が成立要件です。連絡が取れない人や判断能力が不十分な人が一人でもいる場合、そのままでは手続きを進められません。
特に以下のような事情があるケースでは、本人の代わりに遺産分割協議に参加する代理人を選任する手続きが別途必要になります。
| 状況 | 必要な対応・代理人 |
| 行方不明者がいる | 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任、または失踪宣告を申し立てる |
| 認知症の人がいる | 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる |
| 未成年者がいる | 親も相続人の場合、利益相反となるため特別代理人を選任する |
これらの準備を怠ると申立てが受理されない、あるいは合意が無効になる可能性があるため、早めの対処が重要です。
関連記事:
相続人の一人が遺産分割協議に応じない理由と対処法!放置リスクも解説
相続人に障害者がいる場合はどうする?控除の活用や兄弟が関わる相続パターン、生前対策を弁護士が解説
遺産の分割方法を示した書類(遺言書・協議書)などがないか
遺産分割調停は、あくまで「遺産の分け方が決まっていない」場合に行う手続きです。もし有効な遺言書が見つかれば、原則としてその内容に従って承継されるため、そもそも調停を行う必要自体がなくなります。
まずは自宅の仏壇やタンス、貸金庫などをくまなく探し、遺言書の有無を徹底的に調査してください。万が一、調停開始後に遺言書が見つかると、それまでの議論が白紙に戻るリスクがあります。
なお、遺言書の種類によって保管場所や発見後の対応が異なります。
| 種類 | 保管場所の例 | 発見後の対応 |
| 自筆証書遺言 | 自宅の金庫・仏壇など | 開封せずに家庭裁判所で「検認」を受ける。 (参照:裁判所|遺言書の検認) |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 検認不要でそのまま手続きに使用可能 |
関連記事:遺言書の効力はどこまで?いつから効力が発生する?書き方や無効なケースも解説
遺産の内容が確定しているか
調停を始めるには、どの財産を分けるのか(遺産の範囲)が当事者間で一致している必要があります。
「あるはずの預金がない(使い込み疑惑)」「名義は長男だが実質は父の土地だ(遺産の所有権争い)」といった対立がある場合、調停では解決できません。遺産分割調停は確定した遺産の分け方を話し合う場であり、所有権の存否自体を判定する権限がないためです。
遺産分割においてよくあるトラブルと適切な手続きの例は以下のとおりです。
| トラブルの内容 | 適切な解決手続き |
| 遺産の使い込み | 不当利得返還請求訴訟など(民事裁判) |
|---|---|
| 遺産の所有権争い | 遺産確認訴訟(民事裁判) |



こうした根本的な争いがある場合は、調停の前に民事裁判を行い、遺産の範囲を法的に確定させるプロセスが必要となります。
関連記事:遺産相続の裁判とは?手続きの流れや必要な費用、期間を弁護士が解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
弁護士法人アクロピースが解決した遺産分割調停の事例
当事務所「弁護士法人アクロピース」では、遺産分割に関する複雑なトラブルを解決へと導いてきた実績が多数ございます。
ここでは、実際に当事務所が介入し、調停や交渉を通じて円満解決に至った2つの事例をご紹介します。
- 音信不通だった前妻の子どもと遺産分割を成立させた事例
- 兄の使途不明金を突き止めて遺産分割調停で解決した事例
「自分たちだけでは話し合いが進まない」「相手の主張に納得がいかない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
音信不通だった前妻の子どもと遺産分割を成立させた事例
被相続人の前妻との間に子どもがいることが発覚したものの、その一人と連絡がつかず、遺産分割協議がストップしてしまった事例です。
ご依頼者様は早期解決を望んでいましたが、当事者だけでは接触すらままならない状況でした。
| 項目 | 内容 |
| ご依頼者 | Bさん(被相続人の子) |
| 相手方 | Fさん(被相続人の前妻との子・音信不通) |
| 争点 | 連絡が取れない相続人を交えて、どう分割協議を進めるか |
| 解決の結果 | 弁護士が介入し、法定相続分での遺産分割が成立 |
当初、Fさんは突然の連絡に警戒し「詐欺ではないか」と疑念を抱いていたため、話し合いに応じてもらうこと自体が困難でした。そこで当事務所の弁護士が間に入り、相続の法的根拠や手続きの透明性を丁寧に説明する書面を送付しました。
粘り強いアプローチの結果、Fさんの誤解が解け、最終的には全員の合意のもとで遺産分割協議書を作成することができました。専門家が第三者として介入することで、相手方の警戒心を解き、スムーズな合意形成を実現できた事例です。
事例ページ:前妻の子との音信不通を乗り越えて、法定相続分で遺産分割を成立させたケース
兄の使途不明金を突き止めて遺産分割調停で解決した事例
同居していた兄が被相続人の預金を管理していましたが、死後に多額の使途不明金が発覚した事例です。
兄は「介護費用に使った」と主張しましたが、具体的な証拠がなく、ご依頼者様は到底納得できるものではありませんでした。
| 項目 | 内容 |
| ご依頼者 | Bさん(被相続人の子) |
| 相手方 | Cさん(被相続人の子・兄) |
| 争点 | 引き出された数千万円の預金の使途と、遺産への持ち戻し |
| 解決の結果 | 使途不明金の半額以上を遺産として認定させ、和解成立 |
当事務所はまず金融機関から取引履歴を取り寄せ、不自然な出金の事実を客観的に特定しました。その上で遺産分割調停を申し立て、介護記録や当時の生活状況と照らし合わせながら「介護費用としては過大である」と論理的に主張を展開しました。
調停委員もこちらの主張の正当性を認め、結果として使途不明金の大半を遺産に組み戻す形での解決に至りました。



泣き寝入りせず、客観的な証拠に基づいて主張することで、正当な権利を守ることができることを示した事例です。
事例ページ:父の通帳から消えた数千万円、兄の使途不明金を追及し調停で解決した事例
遺産分割調停の費用に関するよくある質問
遺産分割調停で負けたらどうなりますか?
調停に「勝ち負け」はありませんが、不成立の場合は家庭裁判所の審判手続に移行します。(参照:法務省|遺産分割調停)
審判では裁判官が法的に分割方法を決定するため、ご自身の希望が必ずしも反映されるとは限らず、その決定には強制力があります。
客観的な証拠が不足していると不利な結果になる可能性があるため、調停の段階から弁護士のサポートを受け、法的根拠に基づいた主張を準備しておくことが重要です。
遺産相続調停にどれくらいの期間がかかりますか?
一般的には6ヶ月から1年程度かかるケースが多いです。
調停は月に1回程度のペースで行われるため、相続人の人数が多い場合や財産調査が難航する場合は、1年以上に及ぶことも珍しくありません。
期間を短縮するためには、申立ての初期段階から弁護士等の専門家に相談し、必要書類の収集や法的な主張の整理をスムーズに進めておくことが有効です。
遺産分割調停中にやってはいけないことは何ですか?
相続財産を勝手に処分したり、一部の財産を隠したりする行為は厳禁です。これらは相手方の不信感を招くだけでなく、裁判所の心証を悪化させ、後の審判で不利な判断材料とされる恐れがあります。
調停はあくまで話し合いによる合意形成を目指す場です。調停委員の指示に従い、誠実かつ冷静に事実情報を開示する姿勢が、円滑な解決への近道となります。
遺産分割調停はどのような流れで進みますか?
家庭裁判所に申立書を提出し、指定された期日に出頭します。当日は調停委員が間に入り、相続人双方から事情や希望を聴取して調整を図ります。
話し合いがまとまれば調停調書が作成され終了となりますが、合意に至らない場合は自動的に審判手続きへ移行し、裁判官が分割方法を決定する流れが一般的です。
この流れを理解し、証拠書類などを計画的に準備しましょう。
遺産分割調停の費用を安く抑える方法はありますか?
トラブルが深刻化する前に弁護士へ依頼することで、結果的に解決までの期間を短縮し、トータルの費用を抑えられる可能性があります。
手元の資金に不安がある場合は、費用の分割払いに対応している事務所を選ぶのも一つの方法です。
また、収入や資産が一定基準以下であれば「法テラス」の民事法律扶助制度を利用し、弁護士費用の立替えを受けることも検討しましょう。(参照:法テラス|民事法律扶助業務)
まとめ|遺産分割調停の費用を把握した上で弁護士に早めに相談しよう


遺産分割調停には、裁判所への申立費用だけでなく、弁護士・司法書士・不動産鑑定士への依頼料など、多様な費用が発生します。
総額は数万円で収まる場合もあれば、専門家に依頼することで数十万円以上かかるケースもあります。そのため、どの程度の金額を負担するのかを事前に把握し、無理のない範囲で資金計画を立てることが大切です。
特に相続人の数が多い場合や、財産に不動産や使用不明金が含まれる場合には、調停が長期化しやすく、専門的な知識と証拠整理が不可欠です。
法的知識に加え、遺産相続問題を解決してきた経験や実績がある弁護士を味方につけるなら、調停はさらに有利にスムーズに進んでいくでしょう。
前述の通り調停委員会は、第三者の目線で公平な遺産分割の割合を提示してくれます。どちらが一方の味方をしてくれるわけではありません。調停を申し立てるなら、できるだけ有利な形で早期解決を目指すことが重要です。



遺産分割問題の解決実績が豊富な弁護士に相談し、円満解決を目指しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応