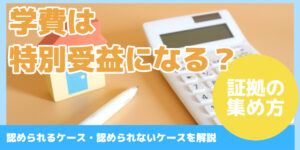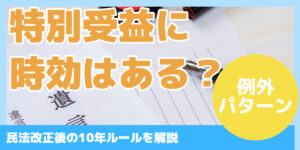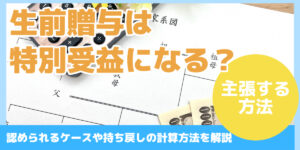【無料相談受付中】24時間365日対応
遺贈は特別受益になる?該当するケースを弁護士が解説

「亡くなった親の遺言書を見たら、兄にだけ多くの財産が遺贈されていた」
「親の面倒を見てきた自分にはほとんど財産が残らないなんて、不公平ではないか」
このような悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
遺言による特定の相続人への遺贈は、残された家族間に深刻な亀裂を生むことがあります。
この記事では、遺贈が特別受益にあたるかの判断基準や例外となるケース、持ち戻しの具体的な計算方法まで、弁護士が解説します。
相続で感じた不公平感を払拭するためにも、ぜひ最後までご覧ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
【結論】特定の相続人への遺贈は「特別受益」にあたる可能性がある
特定の相続人に対する遺贈は、「特別受益」となる可能性があります。
遺贈とは、被相続人(亡くなった方)が、遺言によって特定の人に無償で財産を譲り渡す行為のことです。
また、特別受益とは、相続人間の公平を図るため、特定の相続人が受けた「特別な利益」を一旦遺産に加算し、相続分を再計算する制度を指します。(参考:民法|903条)
例えば、「兄には価値の高い自宅不動産をすべて遺贈し、他の兄弟には現金100万円のみわたす」といったケースでは、そのまま遺産分割を実施すると不公平が生じます。
この場合、兄への遺贈分が「特別受益」にあたり、その遺贈は一旦遺産に加算して計算する「持ち戻し」を行うのです。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫ただし、被相続人の意思を尊重すべきケースや、そもそも公平を議論する対象ではなく、特別受益による持戻し計算をしないケースも存在することには注意が必要です。
遺贈が特別受益にあたらない(持ち戻ししない)6つの例外ケース
特定の相続人への遺贈は原則として特別受益にあたります。しかし、以下のようなケースでは例外的に特別受益と扱われず、持ち戻しの計算対象になりません。
それぞれをくわしく見ていきましょう。
被相続人から持ち戻し免除の意思表示がある場合
遺言書に「この遺贈は特別受益として扱わないでほしい」といった趣旨の記載があれば、相続人同士の公平性よりも被相続人自身の意思が尊重される場合があります。
これは「持ち戻し免除の意思表示」と呼ばれるものです。
たとえば、「事業を継いでくれる長男に全株式を遺贈する。公平を欠くかもしれないが、これは事業の安定経営のためであり、持ち戻しは免除する」といった遺言があったとします。この場合、他の子供が「不公平だ」と主張しても、被相続人の意思が尊重される可能性があります。
持ち戻し免除の意思表示が認められた場合、遺贈は形式的には特別受益となるものの、持ち戻し免除の意思表示があるため、持ち戻し計算は行われません。
よって、遺贈された財産はそのまま受遺者(遺贈を受ける人)のものとなります。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害するほどの過大な遺贈の場合は、免除の意思表示があっても遺留分を請求される可能性があります。
関連記事:特別受益の持ち戻し免除とは?認められるケースや注意点を弁護士が解説
被相続人が婚姻20年以上の配偶者に自宅を遺贈した場合
婚姻期間が20年以上になる夫婦の一方が、もう一方に居住用の不動産(自宅)を遺贈または生前贈与した場合、持戻しが免除されたものと推定されます。
これは、2018年の民法改正で新設された例外で、適用されるための要件は以下の通りです。(参考:民法|903条4項)
- 婚姻期間が20年以上であること
- 配偶者への遺贈であること
- 遺贈された財産が居住用不動産であること
この規定には、長年連れ添った配偶者に対する感謝の気持ちや、残された配偶者の生活基盤を保障するという被相続人の意思を、法律が推定して保護する目的があります。残された配偶者は住み慣れた家を失うことなく、安定した生活を送りやすくなるでしょう。
よってこのケースでは、被相続人に持ち戻し免除の意思表示がなかった事情が他の相続人らから主張されない限り、特別受益の持ち戻しは不要と扱われます。
相続人以外(孫・内縁の妻・慈善団体など)への遺贈である場合
特別受益の制度は、あくまで「相続人」の間の公平を図るためのものです。そのため、相続人ではない第三者への遺贈は、特別受益の対象外となります。
- 相続人ではない孫(親が健在の場合、孫は代襲相続しない限り相続人にはならない)
- 事実婚・内縁関係のパートナー(法律上の婚姻関係がないため、相続権がない)
- お世話になった知人や介護士
- NPO法人や公益団体などの法人
ただしこのケースも、これらの遺贈によって他の相続人の「遺留分」が侵害された場合、相続人は遺贈を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。


受遺者が遺贈を放棄した場合
遺贈は、被相続人からの一方的な意思表示ですが、それを受け取るかどうかは受遺者(遺贈を受ける人)の意思に委ねられています。
そのため、遺贈を受ける権利(受遺者としての地位)は、遺言執行者や他の相続人に対して明確な意思表示の上で、放棄することも可能です。
例えば、以下のようなケースでは、遺贈の放棄を選択する人もいます。
- 相続人との関係を円満に保ちたいと考えた場合
- 遺贈される不動産の管理が困難であると判断した場合
遺贈を放棄すると、法的にはその権利は相続が開始した時点にさかのぼって消滅するため、相続人は「初めから遺贈を受けなかった」ときと同じ状態になります。
遺贈された財産が少額で「扶養義務の範囲内」とされる場合
遺贈された財産が、被相続人の資産状況や社会的地位に照らして少額である場合、特別受益とならないことがあります。
これは、法律で定められた「扶養義務の範囲内」の延長戦上にある行為だと判断されるためです。(参考:民法|877条)
親が子に生活費の援助をするのが当然の範囲であるように、遺贈であってもその程度が軽微であれば、問題とされない場合があります。
例えば、少額のお小遣いや生活費の援助など他の相続人の相続分に与える影響が無視できるほどの遺贈は、特別受益の対象外です。
明確な金額の基準はなく、ケースバイケースでの判断となることには注意しましょう。
生命保険金や死亡退職金を受け取った場合
生命保険金や死亡退職金は法律上、「受取人固有の財産」と考えられており、原則として特別受益にはあたりません。
これは、保険契約や会社の退職金規程に基づいて、受取人が直接権利を取得するものであり、被相続人の遺産とは別のものと扱われるためです。
しかし、以下のようなケースでは、生命保険金や死亡退職金も例外的に特別受益と見なされることがあります。
- 保険金の額が遺産総額に対して著しく大きい場合
- 相続人全員との関係で著しい不公平が生じる
このように、極端に不公平が生じる場合には、例外的に特別受益として持ち戻しの対象となることがある点は理解しておきましょう。



特別受益にあたるかどうかの判断は非常に専門的で難しいため、弁護士への相談が不可欠です。
関連記事:生命保険は相続財産になる?遺産分割と相続税の扱いを弁護士が解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
【早見表】遺贈が特別受益にあたるかを判断するポイント
特別受益の判断は、法律の条文だけでなく、過去の裁判例や個別の事情が複雑に絡み合うため、専門家でも容易ではありません。
以下はご自身のケースが特別受益にあたる可能性があるかを整理するための表です。あくまで目安としてご活用ください。
| チェック項目 | 判断結果 |
|---|---|
| 遺贈を受けたのは相続人(配偶者・子・親など)か? | はい→特別受益の対象となる可能性あり |
| いいえ→対象外 | |
| 遺贈の金額が大きいか? | はい→特別受益として考慮される可能性が高い |
| いいえ→対象外の可能性 | |
| 遺言書に「持ち戻しを免除する」という趣旨の記載があるか? | はい→対象外の可能性 |
| いいえ→特別受益の対象となる可能性あり | |
| 遺贈の目的が配偶者の生活保障や感謝に限定されているか? | はい→対象外の可能性がある(婚姻20年以上の配偶者への自宅遺贈については推定あり。) |
| いいえ→特別受益の対象となる可能性あり |
この表で「特別受益の対象となる可能性あり」という項目が多いほど、法的に特別受益の主張ができる余地が大きいと言えます。
特に以下の3つの要素が、重要な判断基準です。
- 誰が受け取ったか(相続人か)
- 金額の大きさ(不公平の程度)
- 被相続人の意思表示の有無



もし、ご自身のケースが特別受益にあたる可能性が高いと感じられたなら、次に知るべきは「具体的にどれだけ自分の取り分が変わるのか」です。
遺贈と生前贈与の違い|特別受益の扱いが変わるポイント
「遺贈」も「生前贈与」も、特別受益として扱われる可能性がある点は共通していますが、これらは特別受益として扱われる際の法的根拠や手続きが異なります。
本章では、遺贈と生前贈与それぞれについて、特別受益の扱いが変わるポイントを解説します。
遺贈は原則「目的を問わず特別受益にあたる」
遺贈は、法的に有効な遺言により、相続開始後(死亡時)に効力が生じるものです。
相続人に対して行われた遺贈は、その目的が何であっても原則として特別受益にあたります。遺言によって財産が渡されることは、相続財産の前渡しと同じ効果を持つと評価されやすいためです。
したがって、遺贈はその理由にかかわらず、特別受益として扱われます。
生前贈与は「目的によって特別受益と判断されるかどうかが変わる」
生前贈与は、相続が始まる前に契約が成立する財産の譲渡です。
生前贈与が特別受益と判断されるかどうかは、その「目的」が非常に重要であり、すべての生前贈与が対象になるわけではありません。「生計の資本としての贈与」と評価されるものが特別受益の対象です。
具体的には、以下のような贈与が該当する可能性があります。
- 住宅購入資金の援助
- 事業を始めるための開業資金
- 高額な学費
- 結婚の際の持参金や支度金
これに対して、少額のお小遣いや生活費の援助、一般的なお祝い金などは、親族間の扶養義務の範囲内とみなされ、特別受益にあたらないことが多いです。
このように、生前贈与の場合は、その贈与が子の自立や生活基盤の形成にどれだけ役立ったかが判断の分かれ目となります。
関連記事:学費は特別受益になる?認められるケース・認められないケースを判例付きで解説【弁護士監修】
遺贈を特別受益として主張したいときの流れ【3ステップ】
他の相続人が受けた遺贈を特別受益として主張し、公平な遺産分割を実現したい場合、正しい手順を踏むことが大切です。
特別受益の持ち戻しは、相続開始から10年を経過しない限り、主張することができます(民法904条の3)。
しかし、相続手続きが長期化すると、証拠が失われたり、話し合いがこじれたりするリスクが高まるため、10年にかかわらず、早めに進める必要があります。
以下の3ステップで、特別受益の主張を着実に進めていきましょう。
まずは、特別受益の存在を客観的に示す証拠を集めることが不可欠です。「不公平だ」という感情的な訴えだけでは、他の相続人の納得を得ることは困難です。
誰が見ても特別受益の存在を認められるような証拠を、できる限り集めましょう。
以下に、収集すべき証拠の具体例をまとめました。
| 証拠 | 概要 |
|---|---|
| 遺言書 | 遺贈の事実と内容を証明する最も直接的な証拠 |
| 預貯金の取引履歴(通帳の記録) | お金の流れを確認できる |
| 相続財産目録 | 被相続人の全財産をリスト化したもの |
| 不動産の固定資産評価証明書や路線価図 | 遺贈された不動産の客観的な価値を証明できる |
| 家族間のやり取り | 手紙、メール、LINEなどで、被相続人が生前に贈与の意図を語っていた記録なども補助的な証拠になる |
証拠は、「いつ、どの財産が、誰に、どれだけの価値で」渡されたのかを、第三者が見ても納得できるように明確にすることが大切です。
証拠集めが難しいと感じた場合は、無理せず弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、職権で金融機関に取引履歴の開示を請求するなど、個人では難しい方法で証拠を収集できる場合があります。
証拠が十分にそろったら、相続人全員が参加する「遺産分割協議」の場で、特別受益の持ち戻しを提案します。
話し合いのポイントは以下の通りです。
| 協議のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 感情的にならない | ・相手を非難するような口調は避ける。 ・「不公平だ」「ずるい」といった感情論ではなく、「法律のルールに則って計算しましょう」という冷静な姿勢で臨む。 |
| 証拠を提示して具体的に説明する | ・集めた証拠を示しながら、なぜこれが特別受益にあたるのかを論理的に説明する ・事前に持ち戻し計算のシミュレーションを作成し、「この計算方法で分割するのはどうか?」と具体的な提案をするのも有効 |
| 全員の合意を目指す | ・遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しない ・自分の主張だけを押し通すのではなく、相手の意見にも耳を傾ける姿勢が必要。 |
話し合いで全員が合意に至った場合は、その内容を必ず「遺産分割協議書」という法的な書面にまとめ、後々のトラブルを防ぐために全員が署名・捺印します。
当事者同士の話し合いでは、どうしても感情的な対立が激しくなり、解決が難しい場合があるでしょう。
遺産分割協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所での法的な手続きを検討することになります。
この手続きは、大きく「調停」と「審判」の2つの段階に分かれています。
まずは、あくまで話し合いによる解決を目指す「遺産分割調停」を申し立て、調停を重ねても合意に至らない場合は「審判」へと移行する流れです。
それぞれの特徴を以下にまとめました。
| 手続き | 遺産分割調停 | 遺産分割審判 |
|---|---|---|
| 目的 | 話し合いによる合意 | 裁判官による分割方法の提示 |
| 雰囲気 | 話し合いの延長(非公開) | 裁判に近い(原則非公開) |
| 進行役 | 調停委員(民間の有識者) | 裁判官 |
| 解決方法 | 当事者が譲歩し合意点を探る | 裁判官が証拠に基づき判断を下す |
| 結果 | 合意内容をまとめた「調停調書」 | 裁判官が作成する「審判書」 |
これらの家庭裁判所での手続きでは、法的な専門知識や煩雑な書類作成が求められます。
この段階に進む場合は、ご自身の正当な権利を適切に主張するためにも、相続問題に精通した弁護士に依頼することを強くおすすめします。
関連記事:特別受益の主張は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用を解説【弁護士監修】



弁護士に依頼すれば、集めた証拠を法的に有利な形で整理し、説得力のある主張を組み立てることが可能です。
弁護士法人アクロピースは、相続トラブルの実績が豊富にあります。無料相談も可能なので、問い合わせフォームもしくは、公式LINEから気軽にお問い合わせください。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺贈を特別受益として主張する際の注意点とよくある誤解
遺贈が特別受益にあたる可能性を知っていても、主張の仕方を間違え、かえって相続人間のトラブルを大きくしてしまうケースも少なくありません。
ご自身の権利を正しく実現するため、主張する前に知るべき注意点を理解しましょう。 多くの方が陥りがちな誤解と、正しい考え方を以下にまとめました。
| よくある誤解・間違い | 正しい考え方と行動 |
|---|---|
| 遺贈は必ず特別受益になると思い込む | 例外ケースを理解することが重要。持ち戻し免除の意思表示など、特別受益にあたらない場合も存在する。 |
| 持ち戻し免除の意思表示を自己判断する | 「世話になった」等の文言は専門家の解釈が必要。勝手な判断はトラブルの原因になる可能性がある。 |
| 感情的に不公平さを訴える | 法的根拠と客観的な証拠で淡々と主張することが大切。冷静な姿勢が円満な解決への近道となる。 |
特別受益の主張は、遺言の効力そのものを否定するものではありません。「遺言は有効」という前提の上で、分割方法の調整を求めるのが正しい手続きです。



円満な解決を目指すには、感情的に訴えるのではなく、法的根拠と客観的な証拠に基づいて主張する姿勢を持つようにしましょう。
遺贈と特別受益に関するよくある質問
遺贈と特別受益に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
遺贈による特別受益の持ち戻しに時効はありますか?
特別受益の持ち戻し自体には、法律上の時効はありません。これは、持ち戻しの主張が独立した権利ではなく、あくまでも遺産分割協議における計算方法の一つだからです。
ただし、被相続人が亡くなってから10年が経過した後、新たに特別受益の主張をすることはできません。
また、遺産分割協議書の内容は法的な拘束力を持つため、後から遺贈や生前贈与による不公平に気づいても、協議をやり直すことは原則できません。
遺言の「持ち戻し免除の意思表示」はどのような書かれ方なら有効ですか?
法律上、持ち戻し免除の意思表示に厳格な書式はありません。
意思表示の書かれ方には、遺言書に直接書き記す「明示的な意思表示」と、言動などから推測される「黙示的な意思表示」があります。
特別受益の判断基準はなんですか?
特別受益に該当するかどうかの判断には、明確な金額基準はありません。個別の事情に応じて、「遺産の前渡し」といえるかどうかが総合的に判断されます。
具体的に、どのようなものが該当し、どのようなものが該当しにくいのか、以下の表で比べてみましょう。
| 特別受益に該当しやすい例 | 子の独立や生活基盤の形成に役立つ「生計の資本」としての贈与 | ・事業を始めるための開業資金 ・居住用不動産の購入資金援助 ・高額な学費 |
|---|---|---|
| 特別受益に該当しにくい例 | 親子間の扶養や愛情の範囲内と見なされる、日常的な援助 | ・毎月の少額な生活費の援助 ・一般的な範囲のお祝い金(入学・結婚) ・兄弟全員が同程度の援助を受けている場合 |
その援助がなければ生活できなかったというレベルの扶養義務を超え、他の相続人と比べて不公平感を生むほどの特別な経済的援助であったかどうかが、判断の分かれ目です。



当事者間で意見が対立した場合は、最終的に家庭裁判所が被相続人の資産状況や社会的地位、他の相続人との公平性などを考慮して、特別受益にあたるかを判断します。
まとめ|遺贈が特別受益にあたるかどうかの判断に迷ったら弁護士に相談しよう
特定の相続人への遺贈が特別受益と見なされるのは、持ち戻し免除の意思表示がなく、相続人間の公平を著しく害する場合です。
もし遺言書を見て不公平を感じたら、まずは感情的にならず、遺言と財産の内容を冷静に確認することが重要です。
その上で、ご自身のケースが特別受益にあたるかどうかの判断に少しでも迷うなら、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
早期に手を打つことで、家族間の無用なトラブルを防ぎ、正当な権利を守ることにつながります。



相続問題は、法律論だけでなく、家族間の感情が複雑に絡み合う非常にデリケートな分野です。一人で抱え込まず、あなたの正当な権利を守るためにも、ぜひ一度ご相談ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応