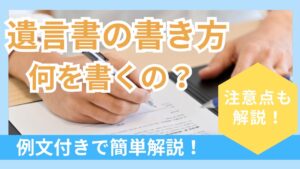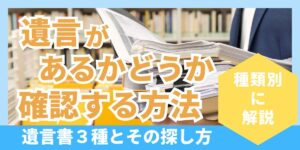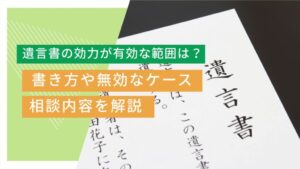【無料相談受付中】24時間365日対応
【遺言書を開けてしまったら】罰則の可能性や検認方法についても解説!
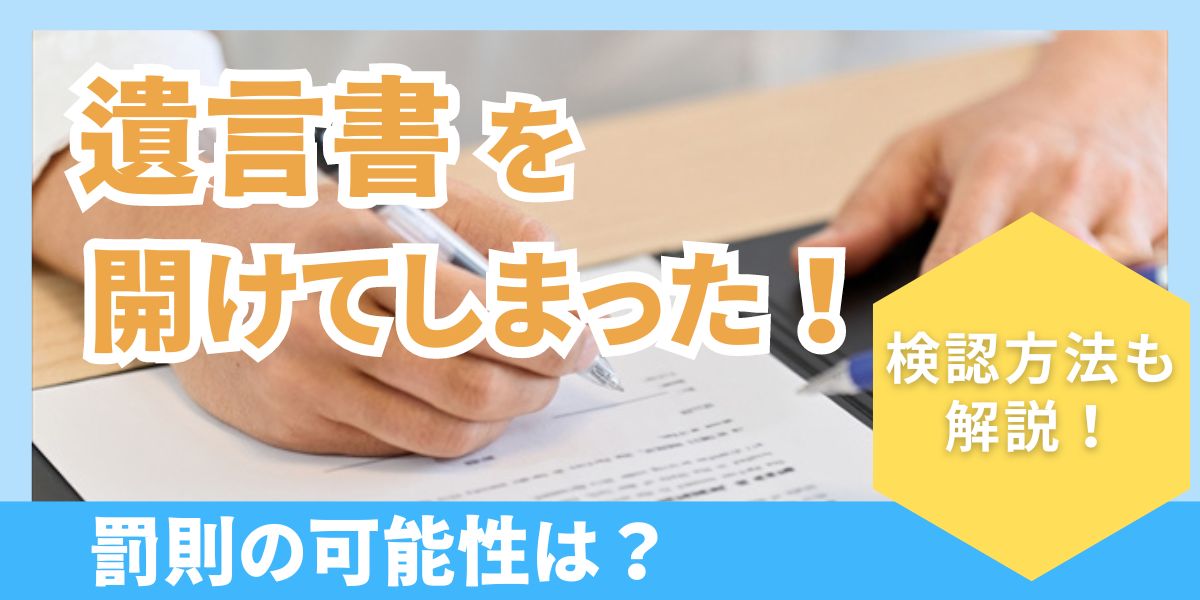
「遺言書を見つけて、その場で開封してしまった」
「親族が勝手に開封してしまった」など
遺言書を勝手に開けてしまった場合、罰則や法律的に問題ないのか不安に感じている方もいるでしょう。
遺言書は開封前に検認手続きを行わなければ、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
本記事では、遺言書を開けてしまったらどうなるのか、開封前に行うべきことなどについて詳しく解説します。
遺言書の検認後の流れも詳しく説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。
遺言書を勝手に開封してしまい悩んでいる方は、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺言書は開封前に検認手続きが必要

遺言書を開封する前には、家庭裁判所による「検認」が必要です。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、保存状態や訂正箇所、日付、署名などを確認する手続きです(民法第1004条1項前段)。
遺言書の偽造や変造を防ぐことを目的としており、遺言の有効か無効かを判断するものではありません。
検認は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで行われます。
遺言書の種類によっては、検認手続きが不要な場合もあります。
以下に、遺言書の種類ごとに検認が必要かどうかを解説します。
| 遺言書の種類 | 検認手続きの必要性 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 不要 |
| 自筆証書遺言(本人保管など上記以外) | 必要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
遺言書の種類ごとの特徴やメリット・デメリットについては、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:遺言書の種類とそれぞれの特徴・メリット・デメリット
遺言書を検認前に開けてしまった場合に起こり得ること
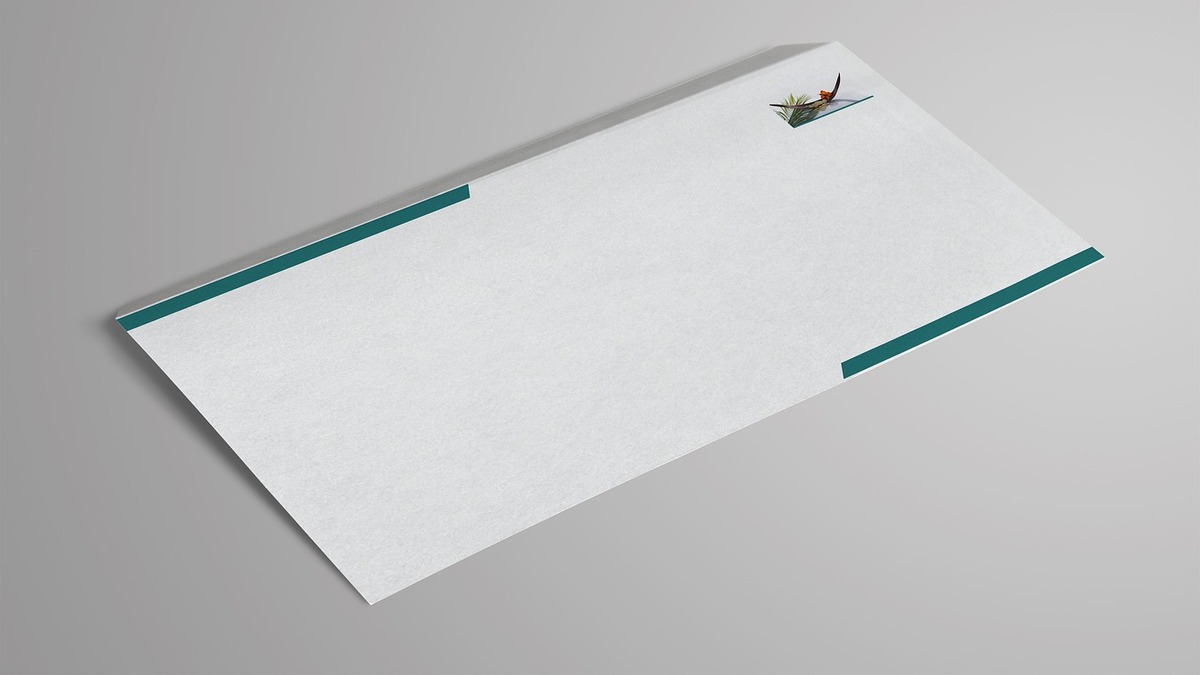
遺言書を勝手に開封した場合、次のようなトラブルが起きる可能性があります。
遺言書を検認前に開封した場合に起こり得ることについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
法律上罰則を受ける可能性がある
遺言書を適切に取り扱わない場合、法律上の罰則を受ける可能性があります。
以下のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料が課されます(民法第1004条および1005条)。
- 検認せずに遺言を執行した
- 家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封した
なお、過料は刑罰ではなく、前科はつきません。
しかし、法律上の罰則を受けたという事実は、その人物の社会的信用に関わることから、なるべく避けるべきことと言えるでしょう。
他の相続人から偽造や変造を疑われる
遺言書を勝手に開封した場合、他の相続人から遺言書の偽造や変造を疑われるおそれがあります。
その結果、他の相続人との信頼関係が損なわれ、遺産分割における合意が難しくなることになりかねません。
また、実際に遺言書を偽造や変造をすることは相続欠格事由に該当するため、相続権を失います(民法891条5号)。
偽造・変造が証明されなければ相続権を失うことはないものの、無用なトラブルを避けるためにも遺言書は勝手に開封してはいけません。
遺言書は検認前に開封してしまっても効力は失われない

検認前に遺言書を開封した場合でも、遺言書は無効になりません。
ただし、遺言書の要件を満たしていない場合は、開封をしたかどうかにかかわらず遺言として有効にはなりません。
たとえば、自筆証書遺言は遺言者自身の手で書かれていること、日付と署名があること、押印がされていることが要件です。
また、遺言書を開封した場合でも、自筆証書遺言(法務局管理ではないもの)と秘密証書遺言は、検認手続きを必ず行わなければなりません。
検認手続きは、遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせ、遺言書の状態を確認するために行われます。
そのため、開けてしまったからといって検認手続きをせずにいると、偽造・変造をますます強く疑われるでしょう。
また、検認を行わない場合、相続手続きに必要な「検認済証明書」を取得できません。
検証済証明書は、遺言書が正当に検認されたことを証明するもので、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更などに必要です。
そのため、遺産分割が進まず、分割協議も進展しません。
遺言書の検認の要否をパターン別に紹介

遺言書の検認が必要なケースと不要なケースは以下のとおりです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【検認が必要】遺言書を開封してしまった
遺言書をうっかり開封してしまったとしても、遺言書が無効になることはありません。
同時に、検認が不要になることもないため、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
遺言書を開封してしまうケースの例は以下のとおりです。
- 封筒をうっかり破いてしまった
- 遺言書があることを聞いていたが、見つけた封筒に「遺言」と記載がなかったために開封してしまった
- 他の家族が遺言書の存在を知っていたが、それを知らされていなかった相続人が無記名の封筒をうっかり開封してしまった
うっかり開封しないように、遺言書が入っていそうな封筒の開封には注意をしましょう。
【検認が必要】遺言書が複数見つかった
遺言書が複数見つかった場合は、全ての遺言書の検認手続きを行う必要があります。
遺言書の内容や日付が異なる場合、古い遺言書と矛盾する箇所については、最新の遺言書の内容が優先されます(民法1023条1項)。
遺言書が複数作成されるケースの例は以下のとおりです。
- 遺産の分配方法を変更したり、新たに相続人を指定したりと、自身の意思を変更したい場合
- 以前に作成した遺言書が紛失したり損傷したりした場合
- 財産の大幅な増加によって、以前の遺言書の内容が適さなくなった場合
- 家族構成の変化(結婚、離婚、子供の誕生など)があった場合
【検認が必要】遺言書に封がされておらず誰でも改変できる状態になっている
自筆証書遺言の場合、遺言書が封がされている必要はありません。
たとえメモや走り書きのような形であっても、日付や署名、押印があり、遺言書の要件を満たしていれば、有効な遺言書と認められます。
このような遺言書も検認手続きが必要です。
遺言書に封をしないケースの例は以下のとおりです。
- 遺言者が急な病気や事故により、緊急に遺言を残す必要が生じた場合、手元にある紙にメモのように遺言を書き残して、封に入れるのを忘れてしまう
- 遺言者が内容を何度も変更し、修正を繰り返している場合、毎回新しい封筒に入れて封をする手間を省くことがある
【検認は不要】公正証書遺言の正本を見つけた
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです(民法969条)。
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がその内容をもとに遺言書を作成します。
遺言者と証人2名が署名・押印することで成立します。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失する心配がありません。
公正証書遺言の正本は原本の写しであり、原本と同じ効力を持つため、相続手続きに使用できます。
また、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
遺言書の検認手続きの方法

遺言書の検認手続きについては、以下3つを押さえておく必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
また、遺言書の検認手続きは弁護士が代理人として行うことができます。
費用について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
関連記事:検認手続きを弁護士に依頼する際の費用
手続きの流れ
検認手続きの流れは以下のとおりです。
- 被相続人の最後の住所地を管轄する地域の家庭裁判所に、相続人や遺言執行者、代理人である弁護士などが家庭裁判所に検認の申立てを行う
- 家庭裁判所に検認期日(検認を行う日)を指定される
- 検認期日に申立人が家庭裁判所に出向く(申立人以外の相続人の立ち会いは必須ではない)
- 遺言書が開封される
- 家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認し、その場で記録を作成する
- 家庭裁判所が検認証明書を発行する
相続人は検認証明書を使用して遺産分割や相続手続きを進めます。
費用
遺言書1通につき、収入印紙800円分が必要です。
これは家庭裁判所に遺言書を提出する際の手数料にあたります。
遺言書が複数ある場合、その数だけ必要な収入印紙の金額が増えることに留意しましょう。
さらに、家庭裁判所から相続人に対して検認期日などの連絡を行うための郵便切手も必要です。
切手の費用は、申立てを行う家庭裁判所によって異なるため、事前に該当する家庭裁判所に確認しましょう。
必要書類
遺言書の検認手続きの必要書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 申立書 | - |
| 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | - |
| 相続人全員の戸籍謄本 | - |
| 遺言者の子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | 子が死亡している場合 |
| 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 | 直系尊属が死亡している場合 ※相続人と同じ代および下の代の直系尊属のみ |
| 父母の出生時から死亡時までの戸籍謄本 | 相続人がいない場合 |
| 兄弟姉妹の出生時から死亡時までの戸籍謄本 | 兄弟姉妹が死亡している場合 |
| 代襲者としての甥姪の死亡の記載のある戸籍謄本 | 代襲者としての甥姪が死亡している場合 |
どの書類が必要か特定したうえで交付手続きを行う必要があります。
時間がかかるため、なるべく早く行動を開始しましょう。
遺言書の検認はなるべく早く始める必要がある

遺言書の検認手続きは、相続放棄や相続税の申告・納付などの期限を踏まえ、なるべく早く始めることが重要です。
相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄を行うかどうかを決定しなければなりません(民法915条1項本文)。
期間を過ぎると、自動的に相続を受け入れることになります。
検認手続きが遅れると、遺言書の内容を確認する時間が短くなり、相続放棄の判断を迅速に行うことが困難になるでしょう。
また、相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日から10ヶ月です。
期限内に正確な遺産の評価を行い、遺産分割を確定する必要があります。
遺言書の内容を確認し、正確な相続財産を把握するためには、検認手続きを早期に行うことが重要です。
遺言書を発見した場合、まず家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立てを行います。
検認手続きが完了するまでには数週間から1ヶ月程度はかかるため、余裕を持って早めに手続きを進めましょう。
遺言書の検認後の流れ

遺言書の検認手続きが完了後、遺言書の内容に従って遺産を分割します。遺言書の検認後は以下の流れで進めましょう。
| 手続き | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.遺言書の内容確認 | 遺言書に記載された相続財産および分割方法などを確認する | 相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって遺産分割の方法や割合などを決めることができる |
| 2.遺言執行者の確認 | 遺言執行者が誰なのかを確認する | ・遺言書に指定がない場合、必要に応じて家庭裁判所が遺言執行者を任命する
・「推定相続人の廃除および廃除の取り消し」と「認知」は遺言執行者がのみが行える |
| 3.財産目録の作成 | 財産の一覧を作成する | ・財産目録には遺言者の全財産が記載する
・遺言執行者は財産目録作成しなければなりません(民法1011条1項) |
| 4.相続財産の確認 | 財産目録と遺言書をもとに、相続する財産を確認する | 財産目録と遺言書の内容に矛盾がないか確認する |
| 5.相続手続きの進行 | 各相続人が相続手続きを進める | 相続税の申告や名義変更などを期限内に行う |
まとめ
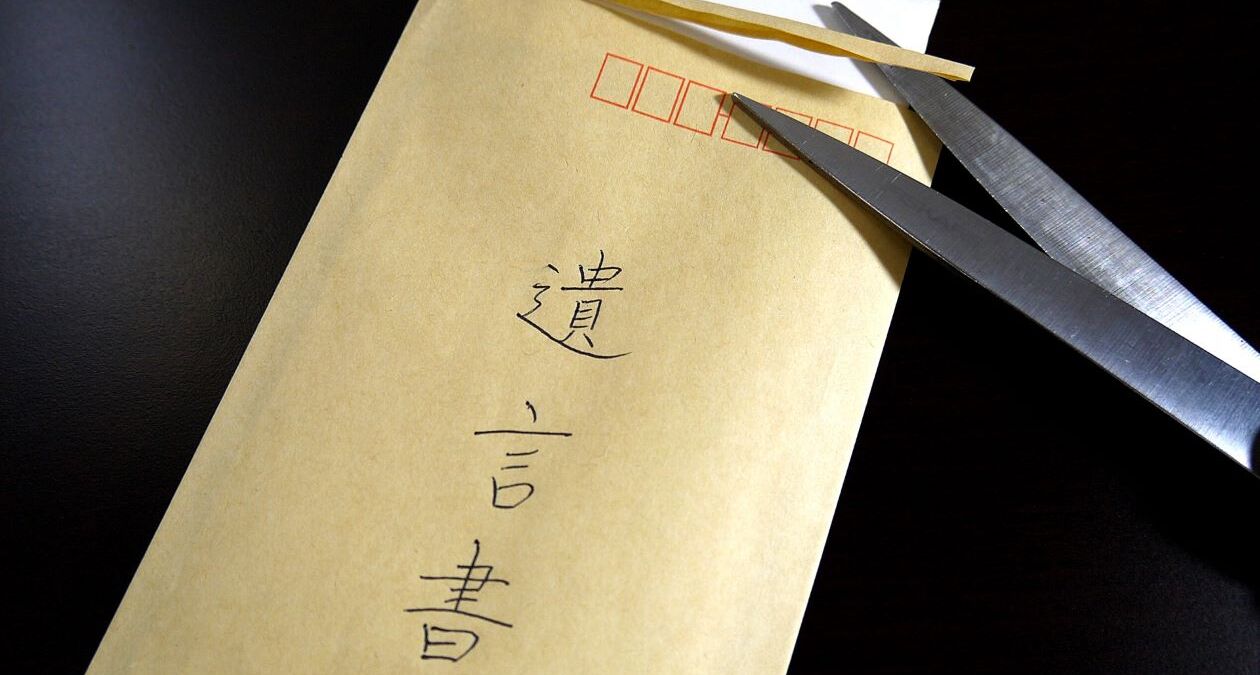
遺言書を開けてしまったとしても、その効力が失われるわけではありません。
しかし、なるべく早く検認手続きを行い、相続手続きを進めることが大切です。
また、遺言書を他の相続人の許可なく開封することは、偽造・変造を疑われる原因になるため、トラブルを避けるためにも適切な方法で相続を進めましょう。
弁護士法人アクロピースは、検認手続きの代行を行っております。
遺産相続に関して全面的なサポートおよび代理人としての手続きなどが可能ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人アクロピースは累計7000件以上の相談実績があり、相続問題に強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
初回60分の相談は無料です。
やっかいな遺産相続の問題にも丁寧にアドバイスいたします。
お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
【無料相談受付中】24時間365日対応