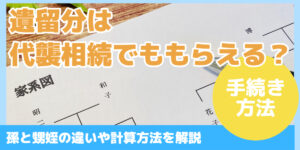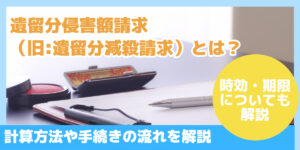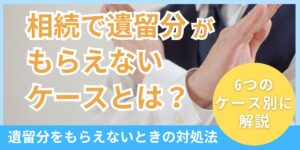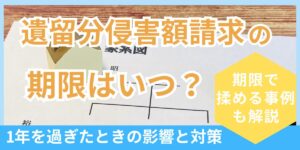【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分を放棄する念書の書き方とは?有効となる条件や例文を解説
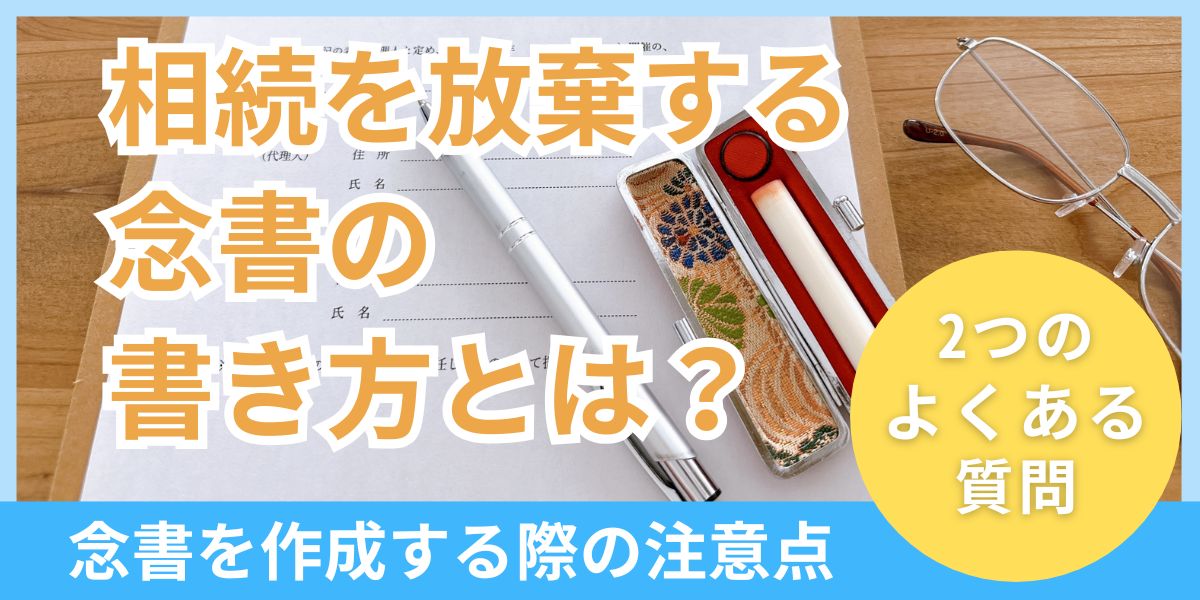
遺留分を侵害されている相続人が「遺留分は請求しない」と発言していたとしても、他の相続人としては「いつ遺留分を請求されるのか」という不安を感じてしまうことでしょう。
「遺留分は請求しない」という約束について、証拠を残しておくためには遺留分を放棄する念書を作成することが考えられます。
この記事では、遺留分放棄の証拠を残しておきたいと考えている方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
遺留分の放棄について正しく理解していなければ、念書を作成したとしても意味のないものになってしまうこともあります。
遺留分の放棄について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
そもそも念書とは?
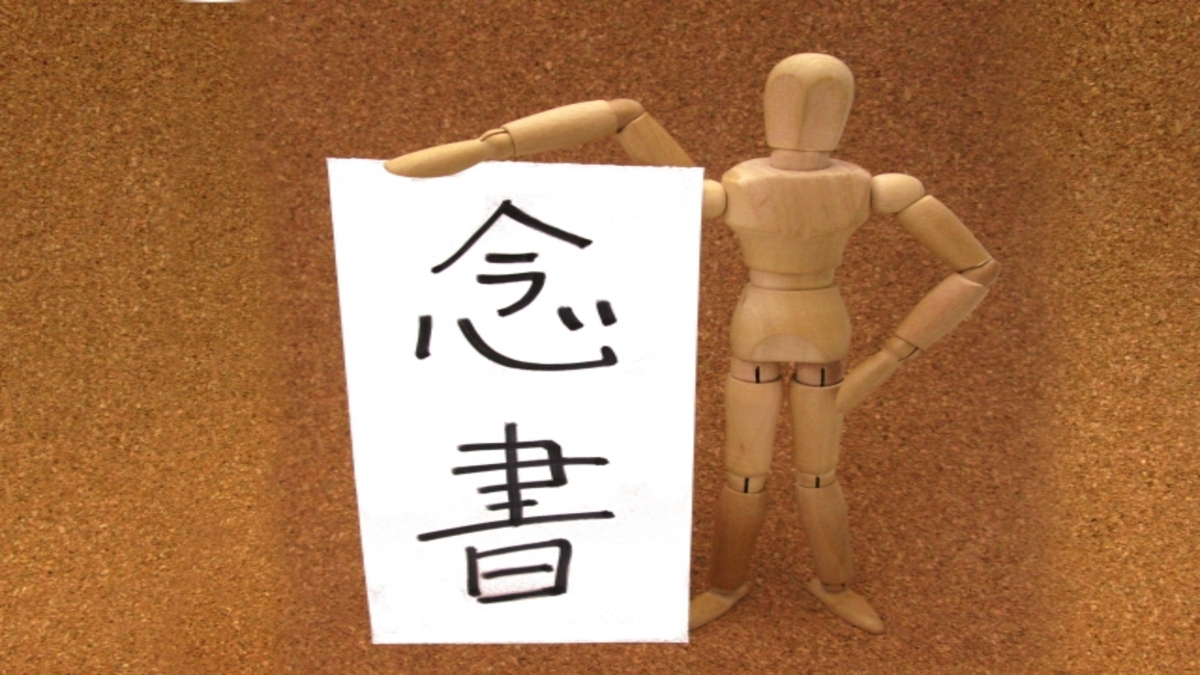
念書とは、その名のとおり念のために作成する文書のことです。
念書は法律上の用語ではありません。
念書が作成される理由は、特定の内容について念のために証拠を残しておくためです。
遺留分放棄の念書は、遺留分の放棄について証拠を残しておくために作成されます。
遺留分の放棄は、遺留分権利者の意思によって決まるもので、必ずしも念書を作成しておく必要はありません。
それでも、念書が作成されるのは、念書を作成した時点で遺留分を放棄する意思があったとの証拠を残しておくためです。
念書の内容が法律や公序良俗に違反する場合や他人が強制して書かせた場合、念書そのものが無効となる可能性があります。
遺留分を放棄する念書がある場合でも、他の相続人が強制して書かせたときは、調停や裁判などで念書の効力を争われる可能性があります。
念書が存在していたとしても、その内容が必ず実現されるわけではない点には注意が必要です。
遺留分を放棄する念書は有効か?

ここでは、遺留分を放棄する念書がそもそも有効であるか否かについて解説します。
念書の有効性は、念書が被相続人の生前に作成されたものなのか死後に作成されたものなのかによって異なります。
被相続人の生前の念書は無効
被相続人の生前に作成した念書は無効となります。
生前の遺留分放棄が認められるのは、家庭裁判所の許可を得た場合のみです(民法1049条1項)。
法律が家庭裁判所の関与がある場合にのみ生前の遺留分放棄を認めている理由は、生前の被相続人が遺留分を持つ相続人に遺留分の放棄を迫ることを防ぐことにあります。
そもそも、遺留分は、遺言によっても奪われないものです。
生前の被相続人により相続人の真意によらない遺留分の放棄を強要されてしまうと、被相続人の意思により遺留分を奪うことになるため、法律が遺留分を認めた意味がなくなってしまいます。
生前に家庭裁判所の許可なしに「遺留分を放棄します」という念書を書いたとしても無効となるため、念書を書いた相続人は、被相続人の死後に遺留分を請求できます。
被相続人の死後の念書は有効
被相続人の死後に作成した念書は、遺留分権利者の真意に基づくものであれば有効です。
被相続人の死後は、家庭裁判所の許可なしに遺留分を放棄できます。
遺留分を請求するか否かは、遺留分権利者が自由に決められます。
遺留分を放棄する念書を作成しなくても放棄の意思は有効です。
遺留分を放棄する念書には「遺留分を放棄したことの証拠を残しておく」という意味があります。
念書を作成しておけば、後から言った、言わないという問題が起こるのを防止できます。
ただし、死後に遺留分を放棄する念書を作成した場合でも、常に有効であるとは限らない点には注意が必要です。
念書の作成経緯や内容によっては、念書の有効性が争われて遺留分を請求される可能性もあります。
遺留分侵害額請求について、より詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?対象となる財産や計算、手続きの方法をわかりやすく解説
遺留分を放棄する念書の書き方

ここでは、遺留分を放棄する念書の書き方を記載事項と例文に分けて解説します。
記載事項
遺留分放棄の念書に記載すべき事項は、次のとおりです。
- 作成日付
- 作成者の住所・氏名・押印
- 被相続人を特定する情報
- 遺留分を放棄する旨
作成日付は、念書を作成した日付を記載します。
念書に署名捺印するのは、作成者である遺留分権利者のみです。
遺留分の放棄は、他の相続人との間の契約ではありません。
契約書の場合には、契約の当事者全員の署名捺印が必要となりますが、遺留分の放棄は遺留分権利者の単独行為なので作成者のみが署名捺印します。
念書は、誰の相続について遺留分を放棄するのかがわからなければ意味がありません。
被相続人を特定する情報としては、被相続人の氏名、出生日、死亡日などを記載します。
遺留分を放棄する念書なので「遺留分を放棄する」、「遺留分侵害額請求を行使しない」など遺留分を放棄する旨の文言も記載してください。
念書の例文
記載事項を踏まえた遺留分放棄の念書の例文は、次のとおりです。
念書
私は、被相続人である甲山一郎(昭和30年1月1日生、令和7年3月1日死亡)の相続手続きにおいて、遺留分を放棄することを約束します。
令和7年3月20日
住所:東京都新宿区高田2-2
氏名:甲 山 花 子 印
氏名については自署したうえで氏名の横に捺印してください。
念書の本文についてはパソコンで作成しても構いませんし、前文を手書きで作成しても問題ありません。
遺留分の放棄について念書を作成する際の注意点

遺留分の放棄について念書を作成する際には、次のとおり多くの注意点があります。
これらの注意点を守らなければ、念書を作成しても効力が認められなくなってしまう可能性があります。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
生前に遺留分放棄の念書を書いても無効になる
被相続人の生前に遺留分放棄の念書を書いても効力は認められません。
被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。
家庭裁判所の許可がなければ遺留分の放棄は認められないので、念書を作成しても、何の意味もないものとなってしまいます。
遺留分放棄の念書が有効となるのは、被相続人の死後に遺留分権利者の真意に基づいて作成された場合のみです。
念書を書いても放棄の意思が取り消される可能性がある
被相続人の死後に遺留分放棄の念書を作成した場合でも、遺留分権利者の意思に反するものであったり、遺留分権利者が意味内容を十分に理解していなかったりしたときには、念書の有効性を争われる可能性があります。
念書は、遺留分権利者の真意に基づいて作成されたものでなければ意味がありません。
他の相続人が強制して作成された念書による放棄の意思は、取り消される可能性があります。
また、他の相続人が強制していなくても、遺留分権利者が念書の意味を理解していなかったり、放棄をした動機に誤りがあったりするなど、意思表示や動機に錯誤が認められる場合にも念書による放棄の意思は取り消される可能性があります。
遺留分放棄の意思表示が取り消されるリスクを減らすには、遺留分権利者に遺留分の意味や放棄の意味、どの程度の遺留分があるのかを十分に理解してもらったうえで、念書を書いてもらうことが重要です。
意味を理解していない相手に念書を書かせても後から効力を争われる可能性があるため、念書を書いてもらう際には十分な説明を行ってください。
遺留分を放棄しても相続人としての権利は残る
遺留分を放棄しても、相続人としての権利は残ります。
相続人としての権利を放棄するには、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きが必要です。
たとえば、被相続人が負債を抱えていた場合、遺留分を放棄したとしても相続人としての権利は残るため、負債の相続を免れることはできません。
また、遺言書がないケースで遺留分を放棄しても、法定相続分と遺留分の差額については相続の権利が残ります。
遺留分を放棄する際には「遺留分のみを放棄するのか」「相続そのものを放棄するのか」を確認したうえで手続きを進めるようにしてください。
相続放棄についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:【相続放棄の手続きの流れ】相続放棄の基本・申述費用・必要書類
生前の遺留分放棄については簡単に撤回できない
生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合、簡単に撤回することはできません。
生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の手続きによって遺留分の放棄が決まった以上、放棄の意思を家庭裁判所の関与なしに撤回することはできなくなります。
遺留分の放棄を撤回するためには、家庭裁判所に対して許可を取り消してもらうための職権発動を求める必要があります。
その際、単に気が変わったというだけで許可が取り消されることはなく、事情の変化により遺留分の放棄が不合理と考えられる場合でなければ許可の取消しは認められません。
念書を作成する際は弁護士に相談する
遺留分放棄の念書を作成する際は弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分放棄の念書には、取消しとなるリスクが多く存在しています。
弁護士に相談すれば、記載内容に漏れのない念書を作成できますし、遺留分権利者の意思を確認したうえで作成手続きを進めることが可能です。
弁護士が遺留分権利者の意思を確認しておけば、後から作成が真意に基づくものではないとして効力を争われるリスクも低くなります。
遺留分を放棄する念書の書き方についてよくある質問

ここでは遺留分を放棄する念書についてよくある質問に回答します。
念書に公証役場で公証人の認証をつけるべきですか?
遺留分放棄の念書は、公証役場で公証人の認証をつけて公正証書化することも可能です。
公正証書とは:私人の嘱託により公証人が作成する公文書
公正証書を作成しておくと、遺留分放棄の念書が遺留分権利者の真意に基づいて作成されたものとの推定が働くため、後から効力を争われるリスクを減らすことができます。
遺留分を放棄する念書は誰が作成するのでしょうか?
遺留分を放棄する念書の作成者は、遺留分権利者です。
遺留分の放棄は、誰かと誰かの契約行為ではなく、遺留分権利者の単独行為です。
遺留分を放棄する念書には、遺留分権利者だけが署名捺印します。
なお、遺留分を放棄する念書を作成する際に、弁護士や他の相続人が文面作成のサポートをすることは、遺留分権利者の意思に反するものでない限り問題ありません。
一方、遺産分割協議は相続人全員で行うものなので、遺産分割協議書を作成する際には相続人全員が署名捺印することになります。
まとめ
今回は、遺留分を放棄する念書の有効性や書き方を理解するために、次の内容について解説しました。
- 遺留分を放棄する念書は生前に書いても無効になる
- 遺留分を放棄しても相続人としての権利は残る
- 生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要
遺留分を放棄する念書は、意味内容を正確に理解したうえで作成しなければ無効となってしまうことも少なくありません。
有効な念書を作成するには、遺産相続の当事者が作成するのではなく弁護士に相談するのがおすすめです。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応