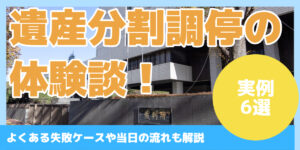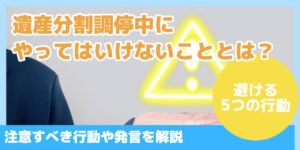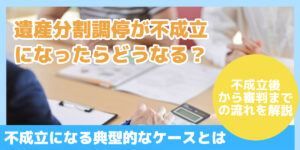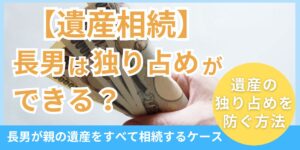【無料相談受付中】24時間365日対応
相続を知らなかった場合はどうする?取るべき対応や相続回復請求権、相続放棄の流れも解説
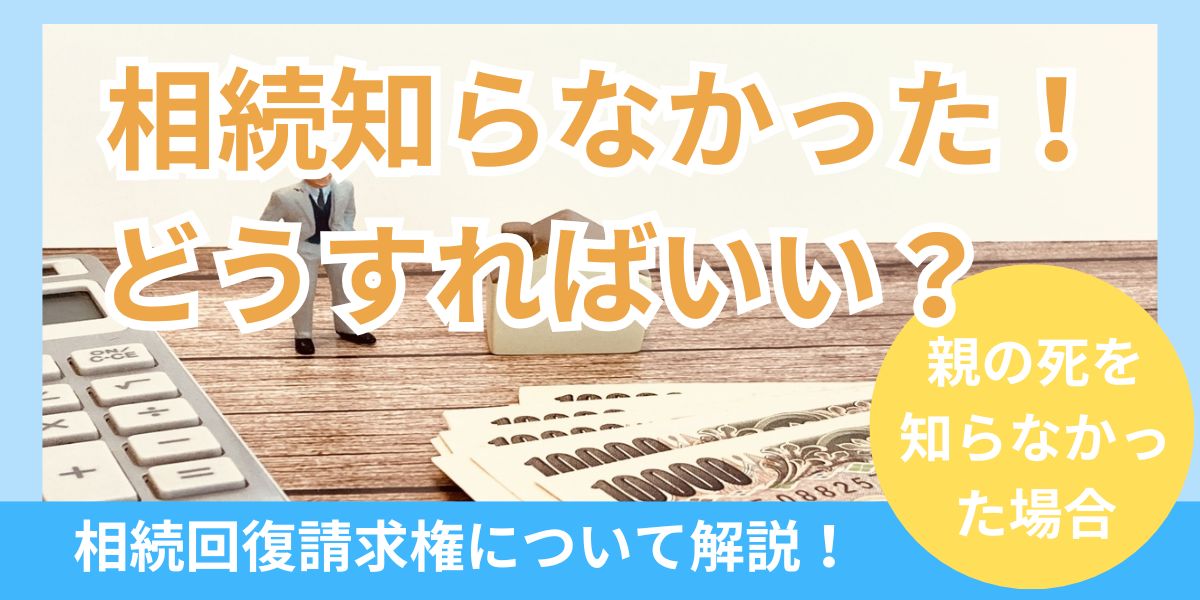
「親の死を知らされず、気付いたときには相続手続きが終わっていた」
「本来受け取れるはずの財産を受け取っていない」
このような理不尽な場面に直面しても、泣き寝入りする必要はありません。
相続は本来、全ての相続人が公平に関わるべきものです。知らない間に権利を奪われていた場合でも、相続回復請求権の行使で権利を取り戻せる可能性があります。
本記事では、相続の発生を知らなかった場合に取るべき対応を分かりやすく解説します。
相続回復請求権の行使方法や相続放棄の流れ、注意点などを紹介しているため、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
相続の発生を知らなかった場合はどうする?2つの選択肢

相続の発生を知らなかった場合に取れる選択肢は、以下の通りです。
どのように対応すべきか確認し、相続権の侵害を受けないようにしましょう。
相続回復請求権の行使で財産を引き継ぐ
相続の発生を知らなかった場合でも、相続回復請求権を主張すれば、本来の相続人としての権利を取り戻せる可能性があります。
相続回復請求権とは、相続権のない人物が相続財産を占有している状況に対して、本来の相続人がその回復を求める権利のことです。
条文として明確に定義されてはいませんが、相続権を侵害された者がその権利の回復を求めるための法的手段として認められています。
相続回復請求権の行使できるのは、以下のようなケースです。
- 自己のした相続放棄が無効であって自らにも相続権があると主張する
- 形式的な養子が実の親の相続に関与していた
- 養子縁組が無効または取り消されたことで相続が妨げられた
このような場合、見かけ上の相続人(表見相続人)によって財産が管理されていても、真正相続人は相続回復請求権を行使することで、本来の取り分を請求できます。
関連記事:養子縁組による相続トラブルとは?よくある5つのケースやリスク・対処法を解説
【注意】相続回復請求権には時効がある
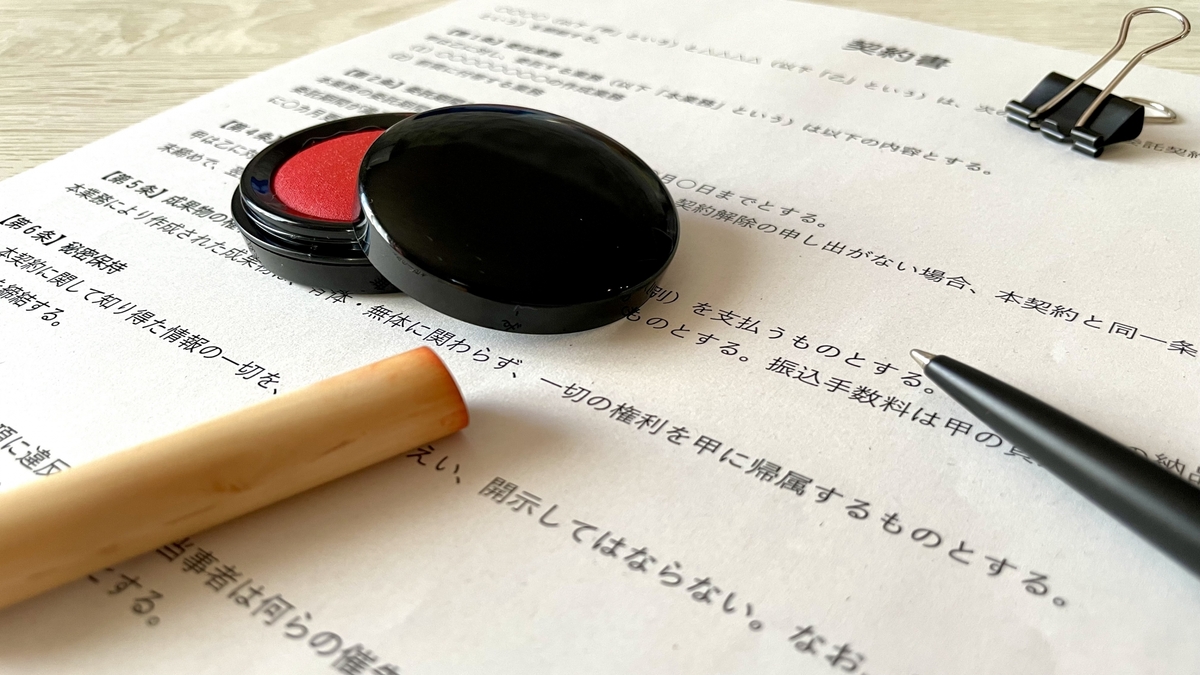
相続人になったことを知った際、知らない間に独占されていた、とわかった場合には、相続回復請求権の主張ができますが、それもできなくなる場合があります。
それが「時効」です。
相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知ったときから5年の経過で時効によって消滅すると定められています。
また、相続開始(被相続人が亡くなった日)から20年の間、権利を行使しなかった場合も同様です。
後者については、まったく相続について知らなかったのですから防ぎようがありませんが、相続権を侵害された事実を知ったときから5年間については、気を配っていれば防ぐことが十分に可能となっています。
相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄の旨を申述する
借金などの負債を含む相続を避けたい場合、プラスの財産であっても受け取りたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述することで成立します。「親の死から3カ月以内」ではないため注意しましょう。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。引用:民法|e-Gov法令検索
両親が1カ月前に亡くなっていたものの、その事実を本日初めて知った場合
→「今日から3カ月以内」が相続放棄を申述できる期限
相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなるため、借金の有無や財産目録を確認してから判断しましょう。
判断に迷う場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の起算日や延長方法については、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:相続放棄の3か月を過ぎた場合はどうなる?起算日や熟慮期間・延長方法も解説
【注意】相続放棄が認められないケース
相続放棄は、申述すれば必ず認められるわけではありません。相続放棄が認められないケースは以下のとおりです。
- 被相続人の預金を引き出して使う
- 不動産を売却する
- 被相続人宛ての光熱費の請求書を支払った
- 遺産分割協議に参加した
- 相続の開始を知った日から3カ月以内に相続放棄を申述しなかった
上記のようなケースでは「相続を承認した」と見なされ、放棄は無効になります。
ただし、相続の開始を知った日から3カ月以内に相続放棄を申述しなかったケースでは、正当な理由があれば認められる可能性があります。必要に応じて弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
いずれも相続放棄を考える場合は、財産に手を付ける前に状況を整理し、裁判所への申述を早めに行う必要があります。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
親の死を知らなかった場合の相続はどうなる?

親が亡くなったことを知らなかった場合でも、法定相続人である以上、相続手続きをしなければなりません。
相続には、財産だけでなく借金などの負債も含まれます。そのため、放置すると突然見覚えのない督促状が届く可能性があります。
親と疎遠になっていた場合は、亡くなったことを知らずに相続の手続きが遅れ、結果として負債を引き継いでしまう事態も起こりかねません。
負債を引き継ぐと経済的な負担が大きいため、相続放棄などの手続きを早めに進める必要があります。
自分が相続人になったことを知った際には、まずは相続財産の全容、他の相続人がいるかどうか、自分の置かれている状況などをしっかり把握しましょう。
親あり・配偶者なし・子なし・兄弟ありの場合の相続はについては、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【配偶者なし子なし親あり兄弟あり】の人の遺産は誰が相続するのかわかりやすく解説!
関連記事:相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたらどうする?不利にならない対処法を弁護士が解説
知らないうちに遺産分割協議が終了していた場合の対応法
前提として、遺産分割協議は相続人全員の合意があって初めて成立します。1人でも話し合いに加わっていない、もしくは同意していない相続人がいる場合、その協議は無効とされるのが原則です。
自分が相続人であるにもかかわらず、知らないうちに遺産分割協議が終わっていた場合、以下の手順で協議のやり直しを求めましょう。
受け取れるはずの財産を取り戻すためにも、適切に対応することが大切です。
相続発生の事実を確認する
遺産分割協議のやり直しを求める前に、相続が本当に発生していたかどうかを確認しましょう。
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取り寄せる
- 死亡の事実と相続人の範囲を確認する
これらの情報は、後の交渉や裁判で相続人の一人としての権利を侵害されたことを証明する根拠になります。
自分で必要な公的書類を集めることも可能ですが、確実性を求めるなら弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
話し合いで遺産分割協議のやり直しを主張する
相続発生の事実を確認したら、遺産分割協議が無効であることを相手に伝え、やり直しを求めましょう。
感情的な対立を避けるには、冷静かつ法的根拠に基づいて話し合いを進めるのがポイントです。
万が一断られた場合は、自分が相続人であることを伝えた上で、協議には全員の同意が必要であると主張しましょう。
ただし、当事者同士で遺産分割協議のやり直しについて話し合うと、トラブルに発展する可能性があります。お互いが冷静に話し合えるよう、間に弁護士を入れるようにしましょう。
やり直しに応じない場合は調停・訴訟を起こす
話し合いで協議のやり直しに応じてもらえない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟を検討する必要があります。遺産分割調停では、他の相続人全員を相手方に指定して申し立てるのが一般的です。
調停では、裁判所が事情を詳しく確認した上で解決案の提示や助言を行い、合意による解決を目指します。
もし調停で合意できなければ、自動的に審判(訴訟手続き)へ移行し、裁判官が遺産の性質や事情をふまえて分割方法を決定する流れです。
参照:裁判所|遺産分割調停
相続問題に関する調停・訴訟を検討している際は、相続問題に強い弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人アクロピースでは、遺産分割や相続放棄、遺留分侵害など、相続をめぐるあらゆる問題に対応しております。
豊富な実績と専門地位をもとに適切な解決策を提案いたしますので、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。
相続を知らなかった場合の相続放棄の進め方7ステップ
財産調査で相続放棄するかどうか決める
まずは、財産調査でプラス・マイナスの財産を明確にし、相続放棄するかどうか判断しましょう。負債が大きいと分かった場合は、放棄することでその責任を逃れられます。
財産調査では、被相続人の通帳や不動産の登記情報、借入金の明細などの確認が欠かせません。見落としがあると、気付かぬうちに負債を背負ってしまう可能性があるため注意しましょう。
財産の調べ方は、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
相続放棄の申述に必要な費用を確認する
相続放棄の手続きには、一定の費用がかかります。スムーズに手続きを終えられるよう、書類を作成する前に準備しておきましょう。
具体的に発生する費用は、以下の通りです。
- 収入印紙:800円
- 連絡用の郵便切手:400~500円程度(※裁判所によって異なる)
- 被相続人の戸籍謄本の交付手数料:750円
- 住民票(戸籍の附票でも可)の交付手数料:300円程度(※都道府県によって異なる)
- 相続を放棄する人の戸籍謄本の交付手数料:450円
参照:裁判所|相続の放棄の申述
連絡用の郵便切手や住民票の交付手数料は、管轄の裁判所・都道府県によって金額が異なります。詳しくは、各ホームページにてご確認ください。
必要書類を用意する
次に、必要書類を用意します。必要書類は、被相続人との関係性によって異なります。
例えば、亡くなった人が自分の親であれば、以下の書類を準備します。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄申述書は、裁判所のホームページにてダウンロードできます。必要書類と記載方法は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:
上申書を作成・提出する
被相続人の死を知らず、相続の発生を認識していなかった場合は、上申書で「相続の開始を知ったのが最近である」と説明しましょう。
上申書とは、何らかの事情があって相続開始を知るのが遅れたことを、裁判所に説明するための文書です。
- 両親と音信不通だった場合
- 死亡通知が届かずに気づかなかった場合 など
上申書を添えれば、裁判所が「正当な理由があって期日内に放棄できなかった」と納得し、放棄を認めてもらえる可能性があります。
上申書は、A4サイズ1枚程度でまとめ、以下の項目を簡潔かつ事実に基づいて記載します。
- 相続を知った具体的な日付
- 経緯
- 連絡がなかった理由
作成は自分でもできますが、不備による不承認を回避するなら専門家に依頼した方が良いでしょう。
書類一式を家庭裁判所に提出する
次は、集めた書類を家庭裁判所に提出します。不備があると差し戻されるため、書類の記載内容や添付資料は丁寧に確認してください。
手続きが正しく行われれば、裁判所で審査が進められます。
早めの提出すれば余裕を持って対応できるため、準備が整い次第すみやかに提出しましょう。
相続放棄申述受理通知書が届く
申述書を提出して審査に通ると、家庭裁判所から相続放棄申述受理所が郵送で届きます。これにより、相続放棄が正式に認められたことになります。
通知書が届くまでには、提出から1〜3週間ほどかかるのが一般的です。
通知書は今後相続トラブルが起きた際に、自身が放棄済みであることを証明する重要な書類です。失くさないよう大切に保管してください。
他の相続人に相続放棄の旨を連絡する
相続放棄が認められた後は、他の相続人にその旨をきちんと伝えることが大切です。
「放棄後に他の相続人に通知しなければならない」といった明確な決まりはありません。しかし、通知しておかないと誤解やトラブルの原因につながる可能性があるため、できるだけ知らせるようにしましょう。
たとえば、あなたが相続人の順位で先にいた場合、放棄によって次順位の親族が新たに相続人となるため、連絡がなければ相続が滞る可能性があります。
スムーズな相続手続きのためにも、誠実な対応を心がけましょう。
相続を知らなかった場合の対応についてよくある質問
兄弟が勝手に相続していた場合はどう対応すべきですか?
まずは、遺産分割のやり直しを求めましょう。相続は相続人全員の合意が必要であり、一部の相続人だけで勝手に進めた手続きは無効になるためです。
被相続人の戸籍を確認し、自分が相続人であることを証明した上で、兄弟に対して協議に参加していない旨を伝えます。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
遺産相続の連絡がこない場合は何をすれば良いですか?
まずは、親や兄弟など被相続人に該当しうる人の死亡の有無を確認します。
その後、市区町村役場で戸籍謄本や住民票除票を取得し、相続が開始しているかを調べましょう。
自分が相続人であると分かった場合、他の相続人に連絡し、遺産分割協議に参加していないことを伝えてください。
感情的な対立を防ぐためにも、弁護士に相談して適切な対処法を確認すると良いでしょう。
相続開始を知った日を証明するにはどうしたら良いですか?
書面で相続開始を知った日を証明しましょう。
たとえば、以下のような書類が証拠になります。
- 銀行や消費者金融から届いた被相続人の借金の督促状
- 市役所から届いた固定資産税の未納通知
- 親族や知人から送られてきた死亡の連絡や遺産に関する手紙
- 弁護士から届いた遺産分割協議への参加要請の通知
こうした書類を裁判所に示せば、相続開始を知った日を証明できる場合があります。
自分が相続で損をしないよう、こうした書類は手元に残しておきましょう。
まとめ|相続の発生を知らなかった場合でも相続権は消えない!まずは専門家に相談を

相続が発生していた事実を知らなかったとしても、正当な相続人であれば権利は消えません。
遺産分割協議が自分の知らぬ間に行われていた場合でも、協議のやり直しや相続放棄など、状況に応じた対応が可能です。
今回の記事のまとめは、以下の通りです。
- 相続の発生を知らなかった場合は、相続するか放棄するか選択する
- 遺産分割協議は完了していても、正当な同族人であればやり直しを主張できる
- 話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所で調停や審判を申し立てられる
- 相続を知った日から3カ月以内であれば、相続放棄の申述が可能である
- 相続人としての権利は簡単には消えないため、泣き寝入りせず主張すべきである
判断に迷うときは、一人で抱え込まず弁護士や司法書士など相続の専門家に相談しましょう。
関連記事:相続問題は弁護士に無料相談できる?
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応