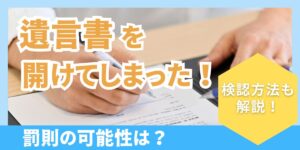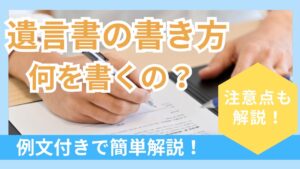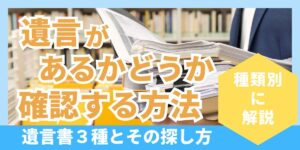【無料相談受付中】24時間365日対応
遺言書が無効になる判例は?無効申し立てをしたい場合の費用も解説
自身の死後の財産の行方を指定したい場合は、遺言書を作成することになります。
遺言書を作成することで、長男に自宅を、次男には預貯金をといった具合に、自らの意思で財産を相続させることができます。
そして遺言書というのは、決して作成が難しい書面ではなく、「自筆証書遺言」という形式であれば、今この場で作成することもできるほど手軽です。
しかし、手軽な反面、自筆証書遺言は法的不備が見つかれば簡単に無効になってしまうという一面もあります。
無効になってしまえば、せっかく作成した遺言書も意味がありません。
今回は、遺言書はどういった場合に無効になるのか?自筆証書遺言の落とし穴として、その典型的な判例をいくつかご紹介いたします。
法的不備のない遺言書を作成し、スムーズな相続を実現させるためにも、以下のパターンを頭に入れて作成へと臨みましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応

遺言書が無効になる場合の判例
-
- 1.パソコンで作成してしまう
近年では、たくさんの方がパソコンを利用するようになりました。
それゆえ、遺言書をパソコンで作成してしまおうといった発想に至る方が多くいらっしゃいます。
しかし、自筆証書遺言はあくまでも全文が自筆でなければならず、パソコンで作成したものはすべて無効として取り扱われます。
パソコンでの作成が認められているのは、秘密証書遺言の場合です。
秘密証書遺言は公証役場にて作成できる遺言形式の1つで、自筆証書遺言とは異なるので勘違いしないようにしましょう。
-
- 2.日付を書き忘れる
遺言書に日付がなかったとしても、内容さえ確認できれば問題がないのではと思いがちです。
しかし、遺言書は、それがいつ書かれたものかが重要であり、民法でも日付を自筆するように規定されています。
もし、遺言書が2通見つかった場合、どちらも法的に有効であれば、日付が新しい方が優先されることになります。
しかし、日付がなければ、どちらが新しいものかわからなくなってしまうのです。
このような事態を防ぐためにも、遺言書に日付は必須です。
なお、ここでいう日付は、年月日を特定できれば問題ないとされています。
たとえば、「私の〇歳の誕生日」といった記載であれば、年月日の特定が可能なため有効と判断されます。
一方で、「〇年〇月吉日」、といったように特定ができない場合は、すべて無効にされてしまうため注意が必要です。
もっとも無難なのは、「〇年〇月〇日」と細かに記載することです。
-
- 3.間違った訂正
全文を自筆でとなると、途中で書き間違いがあってもおかしくはありません。
この際、間違えた部分を黒塗りにしたり、二重線を引いたりする方がいますが、これは間違った訂正です。
よって、当然ながらその遺言書は無効となります。
遺言書を訂正する場合は、訂正箇所の指示と訂正した旨を記載し、さらに署名押印が必要になります。
たとえば、「長男」と記載した部分を「次男」に訂正したい場合、長男の部分に二重線を引いてから次男と記載します。
そして、空いたスペースに「〇行目2字削除2字加筆」と記載し、さらに署名押印をするということ。もはやそれだけで遺言書自体が見づらくなってしまいます。
こうした点からも、間違った場合はいっそのこと新しく書き直してしまうのが無難です。
無理に訂正すると不備を招く恐れがあるため注意しましょう。
-
- 4.特定が困難な記載
遺言書というのは、第三者からみても内容が特定できなければなりません。
たとえば、不動産であれば登記簿謄本に記載されている所在や地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、すべてを正確に記載しておく必要があります。
「〇〇県の田舎の土地」といった大雑把な書き方では、本人や相続人が理解できていても第三者には理解ができません。
となれば、当然、法務局などで行う名義変更の手続きができなくなってしまいます。
預貯金であれば、〇〇銀行だけでなく支店や、預金口座の種類や口座番号まですべて記載するようにしましょう。
以上は、方式の不備や内容が不明確という理由になりますが、それ以外にも遺言書が無効になる判例はあります。
- 遺言能力がない状態で作成されている
- 錯誤、詐欺、強迫により作成されている
- 内容が公序良俗に違反している
- 偽造されている
このような場合は、取り消すことが可能になります。
関連記事:遺言書作成の注意点について解説
遺言書の無効を申し立てる場合の費用は?
残された遺言書を無効にしたい場合には、遺産分割協議・調停・訴訟といった手続きを取ることができます。
調停や訴訟で遺言書の無効を申し立てる場合は、裁判所に納める費用と、弁護士費用が必要になります。
まず、裁判所に納める費用は、収入印紙代と郵便切手代です。
収入印紙代は、遺言の内容や取得できる遺産の額によって変わります。
弁護士費用は、着手金と成功報酬が必要になり、相場は以下のとおりです。
- 着手金の目安
| 経済的利益 | 着手金額 |
| 300万円以下 | 請求額の8.8% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 請求額の5.5%+9万9000円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 請求額の3.3%+75万9000円 |
| 3億円超 | 請求額の2.2%+405万9000円 |
(※日弁連の旧報酬基準に従った目安)
- 成功報酬の目安
| 取得する遺産額 | 報酬金額 |
| 300万円以下 | 回収額の17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 回収額の11%+19万8000円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 回収額の6.6%+151万8000円 |
| 3億円超 | 回収額の3.3%+811万8000円 |
(※日弁連の旧報酬基準に従った目安)
調停や訴訟は、費用だけではなく、時間や労力もかかります。
遺言書を無効にしたい場合、まずは遺産分割協議でしっかりと交渉することから始めるのが良いでしょう。
遺言書は弁護士に任せるのも手
このように、自筆証書遺言というのは作成が手軽である一方、ちょっとしたことで無効になってしまいます。
もちろん上記以外の事柄が理由で無効になってしまう可能性だってあります。
しかし、一生に一度しかない遺言を無効にされてしまうのは心苦しいものです。
より確実に遺言の内容を実現させたいのであれば、やはり弁護士に書面をチェックしてもらうのが賢明です。
遺言書作成後、安心して日々を過ごすためにも、自身の自筆証書遺言に自信が持てないという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
法的不備のない有効な遺言書を一緒に作りましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応