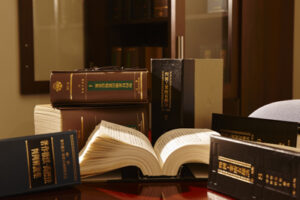【無料相談受付中】24時間365日対応
代償分割とは?代償金の決め方や相続税について弁護士が徹底解説

「実家は兄が継ぐことになったけど、私の取り分はどうなるんだろう…」
「遺産が不動産しかなくて、どう公平に分ければいいか分からない。」
代償分割とは、不動産など分けにくい財産を公平に分ける代表的な方法です。
この記事では、不動産の分割方法に悩んでいる人に向けて、「代償分割」の仕組みからメリット、税金などの重大な注意点、具体的な手続きの進め方までを解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫後悔のない遺産分割を進めるためにも、ぜひ本記事を参考に、代償分割が自身の状況に適しているかを見極めてみましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
代償分割とは
代償分割は、不動産といった現実に分割しにくい遺産がある場合に、不動産を相続する特定の相続人が、他の相続人に金銭を支払って遺産を分割する方法です。
この仕組みを正しく理解することが、適切な遺産分割方法を選択する第一歩となります。以下、基本情報について詳しく解説します。
代償分割の仕組みと目的
代償分割とは、遺産分割において、相続人の一人が不動産や事業用資産などの特定の財産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に対して「代償金」と呼ばれる金銭などを支払う方法です。
例えば、遺産が評価額1億円の実家の土地・建物のみで、相続人が長男と次男の二人だったとします。この場合に、長男が実家をすべて相続するとすると、法定相続分としては2分の1ずつであるにもかかわらず、次男は財産を得られず公平ではありません。
代償分割をすることで、長男が実家の土地・建物を相続する代わりに、次男に対して代償金として5,000万円を支払います。
結果として、長男は実家(1億円)から代償金(5,000万円)を差し引いた5,000万円相当の価値を、次男は現金5,000万円を取得することになり、両者ともに公平な価値の財産を受け継ぐことが可能です。
「自宅を残したい」「家業を継承したい」といった想いを尊重しつつ、他の相続人の法定相続分に相当する権利も金銭によって満たせる合理的な解決策といえるでしょう。
他の遺産分割方法(現物分割・換価分割・共有分割)との違い
遺産分割には代償分割以外にもいくつかの方法があり、それぞれに特徴があります。
家庭裁判所での調停や審判では、一般的に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の順で検討されることが多く、代償分割は現物分割が難しい場合の次善策として位置づけられています。
各方法との違いを理解し、ご自身の状況に適した選択をすることが重要です。各方法を比較検討するために、メリット・デメリットを以下の表にまとめました。
| 分割方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 遺産を各相続人が取得する割合で現実に分割して、各相続人に割り当てる。 | ・手続きがシンプルで迅速 | ・各相続人の取得価値に差が出る可能性がある ・土地を分筆すると価値が下がる可能性がある |
| 代償分割 | 特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う。 | ・財産を売却せずに残せる ・金銭で調整するため公平を保ちやすい ・共有状態を回避できる | ・財産を取得する相続人に十分な資力が必要 ・財産の評価額で揉める可能性がある |
| 換価分割 | 遺産を売却して現金化し、その金銭を分配する。 | ・1円単位で公平に分割できる ・評価額で揉めることがない ・納税資金を確保しやすい | ・売却に手間や費用(税金等)がかかる ・市場価格によっては希望額で売れない |
| 共有分割 | 一つの財産を複数の相続人で共有名義にする。 | ・一時的に公平な分割に見える ・分割協議がまとまらない場合の一時的な解決策になる | ・将来の売却や活用に全員の同意が必要でトラブルの元凶になりやすい ・相続発生のたびに権利者が増え、複雑化する |



自身のケースでどの分割方法を選択すべきか悩んでいる場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
代償分割のメリット
代償分割は、他の分割方法では解決が難しい問題を乗り越えられる多くの利点を持っています。
特に不動産が絡む相続においてメリットは大きく、円満な解決への道を開く鍵となり得るでしょう。
ここでは、代償分割がもたらす4つの主要なメリットを詳しく解説します。
不動産などを売却せずに分けられる
代償分割の代表的なメリットは、被相続人が遺した大切な財産を売却することなく、そのままの形で次世代に引き継げる点です。
多くの人にとって、親が住んでいた実家は単なる資産ではなく、家族の思い出が詰まったかけがえのない場所です。換価分割を選べば公平な分配は可能ですが、その代償として家そのものを失ってしまいます。
代償分割であれば、例えば長男が実家を相続して住み続け、他の兄弟にはその価値に見合った代償金を支払うことで、思い出の場所を守りながら、全員の経済的な権利も尊重することが可能です。
これは、家業で使っていた店舗や工場、収益を生む賃貸アパートなどを特定の相続人が引き継ぐ事業承継の場面でも同様に有効です。
相続人間の公平を保ちやすい
遺産分割において重要な要素の一つが「公平性」です。
現物分割では、不動産のように土地によって価値が異なる財産を分ける際に、どうしても不公平感が生じやすくなります。
一方で代償分割は、分割しににくい不動産などを取得した相続人が、その価値(例えば時価)に基づいて算定された代償金を他の相続人に支払うことで、最終的に各相続人が受け取る経済的価値を均等に調整することが可能です。
金銭という明確な尺度でバランスを取るため、相続人それぞれが「自分の取り分が不当に少ない」と感じるリスクを大幅に軽減し、感情的な対立を避け、円満な合意形成を促す効果が期待できます。
不動産の共有状態を回避できる
遺産分割協議がまとまらない場合に陥りがちなのが、不動産を複数の相続人の「共有名義」にしてしまうことです。これは問題を先送りにするだけで、将来さらに深刻なトラブルの火種となり得ます。
共有不動産は、売却や大規模なリフォーム、賃貸契約など、管理・処分に関する保存行為以外の意思決定に共有者全員または過半数の同意が必要となります。共有者間の必要な同意が得られなければ何も進められず、不動産が有効活用されないまま放置される「塩漬け」状態になりかねません。
代償分割は、特定の相続人が単独で所有権を取得するため、このような共有状態に起因する将来の紛争リスクを根本から回避できます。次世代に負の遺産を残さないための賢明な選択といえるでしょう。
共有名義の不動産については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有不動産の相続はどうなる?手続きの流れや共有名義のメリットデメリットを弁護士が解説
相続税の「小規模宅地等の特例」が使える可能性がある
相続税には、被相続人の自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という強力な節税制度があります。
この特例を適用するには、「配偶者が相続すること」や「被相続人と同居していた親族が相続し、申告期限まで居住し続けること」など、誰がその不動産を取得するかにより異なる要件が定められています。
ただ、換価分割(売却して分ける)の場合、「所有し続ける」という要件を満たせないため、特例を利用できません。
また、共有分割(複数人で所有する)の場合は、特例の対象とならない相続人がいると、その人の持分には特例が適用されません。
代償分割を活用すれば、この特例の適用要件を満たす相続人が単独で土地を相続することが可能です。これにより、他の相続人との公平性を保ちながら、相続税全体の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
もし換価分割や共有分割を選んでしまうと、この特例の適用が受けられず、多額の相続税を納めることになるケースもあるため、税務上のメリットは非常に大きいといえるでしょう。
出典:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(国税庁)
代償分割の注意点
代償分割は多くのメリットを持つ一方で、いくつかの重要な注意点が存在します。これらのリスクを事前に理解し、適切に対処しなければ、かえって深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。
特に「資金力」「評価額」「税金」の3つのポイントは、代償分割を検討する上で避けては通れない課題です。
財産を取得する人に十分な資力(現金)が求められる
代償分割を成立させるための絶対的な前提条件は、不動産などの財産を取得する相続人に、他の相続人へ支払う代償金を捻出できるだけの十分な資力(現金や預貯金)があることです。
不動産の価値が高額であれば、代償金も数千万円単位になることは珍しくありません。
もし、この資金を準備できなければ、代償分割という選択肢は事実上利用不可能です。
相続人間の合意があれば分割払いも可能ですが、支払いが滞れば新たな紛争の原因となるため、支払い能力については慎重かつ現実的な判断が求められます。
遺産の評価額で揉める可能性がある
代償金の額は、対象となる遺産の評価額を基準に算出されるため、この評価額をいくらにするかという点で相続人間の意見が対立し、協議が難航するケースが非常に多く見られます。
不動産の評価は以下のように複数の基準が存在し、それぞれ金額が異なります。
- 実際に市場で取引される価格である「時価」
- 相続税計算の基準となる「相続税評価額(路線価など)」
- 固定資産税の基準となる「固定資産税評価額」
一般的に、代償金を支払う側は評価額を低くしたいと考え、受け取る側は高くしたいと考えるため、利害が真っ向から衝突します。
この問題を解決するためには、第三者である不動産鑑定士に鑑定を依頼するなど、客観的で公平な評価基準を設けることが不可欠です。
手続きを誤ると贈与税がかかるリスクがある
代償分割で最も注意すべきは、税務上のリスク、特に贈与税の問題です。
遺産分割の一環として支払われる代償金には、原則として贈与税はかかりません。しかし、手続きに不備があると、税務署から「相続とは関係のない個人間の贈与」とみなされ、相続税よりもはるかに税率の高い贈与税が課される危険性があります。
このリスクを回避するために最も重要なのが、相続人全員で作成する「遺産分割協議書」です。この書類に、「誰がどの財産を取得する代償として、誰に、いくらの代償金を、いつまでに支払う」という内容を明確に記載しなければなりません。
また、取得した財産の価値を大幅に超える過大な代償金を支払った場合も、贈与税の対象となる可能性があります。



専門家のアドバイスのもと慎重に進めることが大切です。
代償分割を積極的に検討したい3つのケース
代償分割は、どのような相続においても万能な解決策というわけではありません。しかし、特定の状況下では、他のどの方法よりも優れた解決策となり得ます。
ここでは、代償分割の利用を特に積極的に検討すべき代表的な3つのケースについて具体的に解説します。
遺産の大部分が実家などの不動産の場合
被相続人が遺した財産が、現金や預貯金は少なく、その価値の大部分を実家の土地・建物といった不動産が占めているケースは少なくありません。
このような場合、現物分割で公平に分けることは物理的に不可能で、かつ共有分割では後にトラブルに発展する可能性が高いです。かといって換価分割で売却してしまえば、家族の思い出の場所が失われてしまいます。
代償分割は、このような状況でこそ真価を発揮します。
相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人にはその価値に見合った現金を支払うことで、不動産という「資産」と、そこに含まれる「家族の価値」を両立させながら、円満に分割することが可能です。
相続人の一人が事業を引き継ぐ(事業承継)場合
被相続人が会社を経営していた場合、その事業の継続は家族にとって重要な課題です。
事業承継を円滑に進めるためには、後継者となる相続人に、会社の議決権を左右する自社株式や、事業に不可欠な工場・店舗などの事業用資産を集中して相続させる必要があります。
これらの資産が他の相続人に分散してしまうと、経営の意思決定が滞り、最悪の場合、事業の存続が危ぶまれる事態にもなりかねません。
代償分割を活用すれば、後継者は事業に必要な資産をすべて引き継ぎ、その代わりに他の相続人へ代償金を支払うことで、経営権を確保しつつ他の相続人の経済的な権利も守れます。
相続人の一人が被相続人と同居していた家に住み続けたい場合
被相続人と長年同居してきた配偶者や子どもにとって、その家は単なる住居ではなく、生活の基盤そのものです。
相続が発生したからといって、いきなり住み慣れた家を売却し、立ち退かなければならない事態は避けたいと考えるのが自然でしょう。
このようなケースで代償分割は極めて有効な手段となります。家に住み続けたいと希望する相続人が、他の相続人に対してそれぞれの相続分に相当する代償金を支払うことで、住居を確保することが可能です。



自身のケースが代償分割に適しているかわからない場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
【ステップで解説】代償分割の進め方と手続きの流れ
代償分割を円滑に進めるためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。
ここでは、相続人同士の合意形成から相続税の申告まで、代償分割を行う際の具体的な流れを5つのステップに分けて分かりやすく解説します。
各ステップでやるべきことを正確に理解し、計画的に進めていきましょう。
ステップ1:相続人全員で代償分割に合意する
すべての遺産分割の基本ですが、代償分割を行うには、まず法定相続人全員の合意が大前提となります。特定の相続人が一方的に決定できるものではありません。
まずは相続人全員が集まる「遺産分割協議」の場で、代償分割という方法を選ぶ理由やメリットを丁寧に説明し、理解を求めることが重要です。例えば、「この家に住み続けたい」「事業を継ぎたい」といった具体的な想いを伝えることで、他の相続人の共感を得やすくなるでしょう。
ステップ2:遺産の評価額を決め、代償金の金額を算出する
相続人全員が代償分割を行うことに合意したら、次に代償金の基礎となる遺産の評価額を決定します。
前述の通り、不動産などの評価方法は複数あり、どの方法を用いるかで金額が大きく変わるため、このステップはトラブルになりやすいポイントです。
公平性が高いとされるのは、不動産鑑定士など第三者の専門家による「時価」評価です。相続人全員が納得できる評価方法を選び、評価額を確定させます。
その評価額と各相続人の法定相続分に基づき、支払うべき代償金の具体的な金額を算出します。
例えば、評価額6,000万円の不動産を相続人3人のうち1人が取得する場合、他の2人に対してそれぞれ2,000万円ずつの代償金を支払う計算になります。
ステップ3:遺産分割協議書を作成する
相続人全員の合意内容が固まったら、その結果を法的に有効な書面である「遺産分割協議書」に記します。
代償分割を行う場合、この協議書の記載内容は特に重要です。後々のトラブルや予期せぬ贈与税課税を避けるため、以下の項目は必ず明確に記載しましょう。
- 被相続人の情報(氏名、死亡日など)
- 相続人全員が合意した旨
- 誰がどの財産を相続するか
- 「上記の財産を取得する代償として」という文言
- 代償金を支払う人と受け取る人の氏名
- 代償金の具体的な金額
- 支払いの期限と方法(振込先口座など)
相続人全員が署名し、実印を押印することで協議書は完成します。後の不動産登記や預貯金の名義変更手続きにも必要となるため、必ず保存しておきましょう。
以下の記事では、遺産分割協議書がまとまらない場合の対処法について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
ステップ4:代償金を支払い、遺産の名義変更(不動産登記など)を行う
遺産分割協議書に定められた期限までに、代償金を支払う相続人は、指定された方法で他の相続人への支払いを完了させます。
支払いが完了したら、遺産分割協議書を添付して、不動産の名義変更(所有権移転登記)手続きを法務局で行いましょう。預貯金や株式など他の財産についても、同様に名義変更手続きを進めます。
これらの手続きをすべて終えることで、遺産分割は完了です。
ステップ5:相続税の申告・納税を行う
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内と定められています。
代償分割を行った場合、各相続人の納税額は、実際に取得した財産の価値(代償金の授受を反映させた後の金額)に応じて計算されるのが特徴です。
代償金を支払った人はその分課税価格が減り、受け取った人はその分増えることになります。
相続人それぞれが自身の納税額を計算し、期限内に申告・納税を済ませましょう。
出典:相続税の納付(国税庁)



自分で代償分割の手続きができるか不安な場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
代償分割をする際に注意すべき税金は?
代償分割は便利な制度ですが、税金の取り扱いを誤ると、本来不要なはずの多額の税金を支払うことになりかねません。
特に「相続税」「贈与税」「所得税」の3つの税金との関係を正しく理解しておくことが重要です。
以下、それぞれ具体的に解説します。
相続税:代償金の支払いで各相続人の課税価格が変わる
相続税は、遺産総額に対してかかる税金ですが、最終的な納税額は各相続人が取得した財産の価値に応じて計算されます。代償分割を行った場合、この「取得した財産の価値」の計算方法が特殊になります。
- 代償金を支払った人の課税価格:(相続した現物財産の評価額)−(支払った代償金の額)
- 代償金を受け取った人の課税価格:(相続した現物財産の評価額)+(受け取った代償金の額)
例えば、相続税評価額4,000万円の土地を長男が相続し、次男に代償金2,000万円を支払った場合、長男の課税価格は2,000万円(4,000万円-2,000万円)、次男の課税価格は2,000万円となります。
もっとも、相続税評価額ではなく、代償分割時の時価に基づく場合には異なる計算方法となります。
このように、代償金の授受によって、相続税の負担が相続人間で実態に合わせて調整される仕組みになっている点が特徴です。
出典:No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算(国税庁)
贈与税:遺産分割協議書への記載がないと高額な贈与税がかかることも
代償分割における最大の税務リスクが、贈与税です。遺産分割協議書に「代償分割であること」を明確に記載せずに金銭のやり取りを行うと、その支払いは遺産分割とは無関係な「個人からの贈与」とみなされる可能性があります。
また、相続した財産よりも高額な代償金の支払いがなされた時も、贈与とみなされてしまう可能性もあります。
贈与税は相続税に比べて税率が非常に高く、基礎控除額も少ないため、もし贈与と認定されれば、想定外の巨額な納税義務が発生します。
このリスクを回避するためには、遺産分割協議書に代償分割の旨を正確に記載し、適切な代償金の支払いをすることが大切です。代償分割を安全に行うためにも、必ず頭に入れておきましょう。
所得税(譲渡所得税):代償金を「遺産以外の資産」で支払うと課税対象になる
代償金は通常、現金で支払われますが、支払う側に十分な現金がなく、代わりにその人がもともと所有していた不動産や株式などを渡すケースも考えられます。この場合、税務上は「代償債務の履行のために、自己の資産を時価で売却(譲渡)した」とみなされます。
そのため、もし渡した資産の時価が、その資産を取得したときの価格を上回っていた場合、その差額(譲渡益)に対して所得税(譲渡所得税)が課税されます。この税金は、代償金を支払った側(資産を渡した側)に課されるものです。
例えば、取得価格1,500万円の土地を、代償として時価2,500万円で渡した場合、差額の1,000万円が譲渡所得となり、所得税の課税対象となります。



現金以外の資産で代償金の支払いを検討する際は、譲渡所得税のリスクも必ず考慮に入れましょう。
出典:No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算(国税庁)
代償金が支払えない場合の対処法
「実家を相続したいが、代償金を一括で支払う現金がない」という問題は、代償分割を検討する上で最も大きな壁となります。
ただ、代償金の支払い能力に問題がある場合でも、いくつかの対処法が存在します。状況に応じて最適な方法を組み合わせることで、解決の道筋が見えてくるかもしれません。
金融機関で代償分割ローンを組む
代償金の支払いを目的としたローン商品を取り扱っている金融機関があります。これらは「遺産分割ローン」や「相続関連ローン」といった名称で提供されており、相続した不動産そのものを担保にすることで、まとまった資金を借り入れることが可能です。
住宅ローンに比べると金利は高くなる傾向にありますが、自己資金が不足している場合には非常に有効な選択肢となります。まずは取引のある金融機関に相談してみるとよいでしょう。
生命保険金(死亡保険金)を活用する
被相続人が生前に、不動産を相続させたい相続人を受取人とする生命保険に加入していた場合、その死亡保険金を代償金の支払いに充てられます。これは、被相続人が将来の相続を見越して行うことができる、計画的な納税・代償金対策の一つです。
生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という相続税の非課税枠が設けられています。この枠内の保険金は相続税の課税対象にならないため、預貯金で同額の資金を残すよりも相続税全体の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象ではありません。そのため、受取人である相続人が相続財産以上の保険金を代償金として他の相続人に支払うと、「受取人から他の相続人への個人間の贈与」とみなされ、高額な贈与税が課されるリスクが生じます。
相続人同士の合意のもと分割払いを検討する
代償金を受け取る側の相続人全員が同意すれば、一括払いではなく分割で支払うことも可能です。この方法は、金融機関からの借入を避けたい場合に有効です。
ただし、口約束だけでは後々のトラブルの原因になります。遺産分割協議書に、毎月の支払額、支払期間、支払日、遅延した場合のペナルティ(遅延損害金)などを具体的かつ明確に記載しておくことが不可欠です。
信頼関係が前提となる方法ですが、柔軟な解決策の一つといえます。
代償金の代わりに他の相続財産を渡す
もし遺産の中に不動産以外にも預貯金や有価証券などがある場合、現金の代わりにこれらの財産を他の相続人に多く渡すことで調整する方法も考えられます。
例えば、「私が不動産をすべて相続する代わりに、預貯金と株式はすべてあなたが相続する」といった合意などが挙げられます。
これは実質的には現物分割に近い形ですが、代償分割の考え方を応用したものです。
各財産の評価額を算出し、全員が納得できるバランスを見つけることができれば、現金を用意せずとも公平な分割が実現できるでしょう。
他の分割方法と組み合わせる
一つの方法に固執せず、複数の分割方法を組み合わせるハイブリッドなアプローチも有効です。
例えば、遺産の中に複数の不動産がある場合、一つは代償分割を、もう一つは売却して換価分割を行い、その売却代金の一部を代償金の支払いに充てる方法です。
このように、遺産全体の状況を俯瞰し、それぞれの財産に適した分割方法を柔軟に組み合わせることで、複雑な問題も解決できる場合があります。
「代償金が支払えないかもしれない」と不安に感じている場合、すぐに代償分割を諦める必要はありません。一度弁護士に相談し、適切な判断を仰ぐことで安心して手続きができるでしょう。
代償分割でよくあるトラブルと回避方法
代償分割は合理的な方法ですが、実務では次のようなトラブルが起こりやすいです。事前に注意点を押さえておくことで、紛争を未然に防げます。
代償金の支払いが滞る
分割払いにしたものの、支払う相続人の資金繰りが悪化して滞納するケースがあります。遺産分割協議書に「支払い期日」や「遅延損害金」を明記するだけでなく、担保設定を検討すると安心です。
不動産の評価額をめぐる対立
相続税評価額・固定資産税評価額・時価など評価方法が異なるため、「高い/安い」と意見が割れやすいです。公平性を保つためには、不動産鑑定士など第三者の専門家による評価を採用するとよいでしょう。
税務処理の誤りによる課税リスク
遺産分割協議書に「代償分割」と明記しないと、贈与税課税を受ける可能性があります。書面の不備が後の大きな負担につながるため、専門家にチェックを依頼することが有効です。このように、代償分割は「制度を知っている」だけでは十分でなく、手続きの正確さと資金計画が成否を分けます。
代償分割を弁護士に相談するメリット
代償分割は、相続人間の公平と資産の承継を両立できる優れた方法ですが、その手続きは複雑で、法律や税務に関する専門的な知識が不可欠です。
家族だけで進めようとすると、思わぬトラブルや不利益を被るリスクがあります。
相続問題に精通した弁護士に相談することで、これらのリスクを回避し、安全かつ円滑に手続きを進めることが可能です。
正確な遺産分割協議書の作成でトラブルを未然に防げる
代償分割の成否は、法的に有効で抜け漏れのない「遺産分割協議書」を作成できるかどうかにかかっています。特に、代償分割であることを明記し、贈与税課税のリスクを完全に排除する条項は極めて重要です。
弁護士に依頼すれば、個別の事情に合わせて、将来起こりうる紛争を未然に防ぐための条項(支払いが遅れた場合の遅延損害金や、不動産への抵当権設定など)を盛り込んだ、盤石な遺産分割協議書を作成できます。
これにより、法的な安定性が確保され、安心して手続きを進めることが可能になるでしょう。
適正な代償金額の算定をサポートしてもらえる
代償分割で最も揉めやすいのが、不動産などの評価額と、それに基づく代償金の算定です。
感情的な対立が生まれやすいこの問題に対し、弁護士は法律の専門家として冷静かつ中立的な立場で交渉を仲介してくれます。
必要に応じて、信頼できる不動産鑑定士と連携し、客観的で公平な評価額を提示することで、相続人全員が納得できる合意形成をサポートします。
当事者同士では行き詰まりがちな協議を、専門的な知見をもって円滑に進めることができるのは、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。
複雑な税務申告をミスなく任せられる
代償分割には、相続税だけでなく、贈与税や所得税といった複数の税金が複雑に絡み合います。これらの税務問題を正しく処理するには、高度な専門知識が必要です。
弁護士であれば、提携する税理士とも緊密に連携しており、法務面だけでなく税務面も考慮した分割プランを提案できます。
また、遺産分割協議書の作成から、それに伴う相続税申告までをワンストップで任せられるため、手続きの漏れやミスを防ぎ、依頼者の負担を大幅に軽減することが可能です。



不動産相続のトラブルを解消したいと考えているなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
不動産にまつわるトラブルの弁護士費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:不動産にまつわるトラブル解決のための弁護士費用目安と依頼のメリット
代償分割をスムーズに進めるために弁護士へ相談すべきタイミング
代償分割は家族間の合意形成に加え、法律・税務の専門知識が不可欠です。次のような状況では、早めに弁護士への相談を検討してください。
| タイミング | 背景 |
|---|---|
| 代償金の支払い能力に不安があるとき | 資金調達の方法(ローン・分割払い)を誤ると、新たな紛争の火種になります。 |
| 不動産の評価額で意見が割れているとき | 「路線価で計算するか」「実勢価格を採用するか」で何百万円も差が生じることがあります。 |
| 税金への影響が心配なとき | 贈与税や譲渡所得税のリスクを知らずに手続きを進めると、想定外の課税が発生する可能性があります。 |
| 協議がまとまらず調停を検討しているとき | 調停に移行すると法的な主張・証拠が求められます。初動の段階から弁護士に整理してもらうことで有利に進めやすくなります。 |
「いつ相談すべきか」が分かると、読者は安心して次の行動に移れます。記事内のCTAとも自然につながり、相談誘導の訴求力が高まる構成になります。
代償分割に関するよくある質問
代償分割を検討するにあたり、多くの方が抱く疑問について回答します。具体的な疑問点を解消し、より深く理解を深めていきましょう。
代償金の支払いに期限はある?
法律で代償金の支払期限が一律に定められているわけではありません。期限は、相続人全員の話し合いによって自由に決められます。
ただし、後々のトラブルを避けるため、決定した支払期限は必ず遺産分割協議書に「令和〇年〇月〇日限り」といった形で明確に記載することが重要です。
もし期限を定めなかった場合、民法の一般的な債権の消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年)が適用される可能性があります。
ただ、解釈が分かれるリスクもあるため、明確な期日を設定することが賢明です。
代償分割でかかる相続税は誰が支払う?
相続税は、遺産全体に対して一度計算された後、各相続人が最終的に取得した財産の価値に応じて、それぞれが納税義務を負います。
代償分割の場合、代償金を支払った人は、相続した財産の評価額から支払った代償金の額を差し引いた後の価値に対して、相続税を納めます。逆に、代償金を受け取った人は、受け取った代償金の額に対して相続税を納めることになります。
相続人一人ひとりが、自身の取得分に応じた相続税を個別に支払うということを覚えておきましょう。
代償金の支払いにローンは組める?
代償金の支払いにローンを組むことは可能です。
多くの金融機関が、代償金の支払いを目的としたローン商品を提供しています。相続で取得する不動産を担保に入れることで、必要な資金を借り入れることが可能です。
自己資金だけでは代償金の支払いが難しい場合でも、ローンを活用することで代償分割を実現できる可能性があります。
金利や返済条件は金融機関によって異なるため、複数の機関を比較検討しましょう。
まとめ|円満相続をするためにも、代償分割の悩みは専門家に相談することが大切
この記事では、代償分割の仕組みからメリット・デメリットや具体的な手続き、そして税務上の注意点までを解説しました。
代償分割は、不動産など分けにくい遺産がある場合に、資産を維持しながら相続人間の公平性を保つことができる非常に有効な手段です。
円満な相続を実現する強力な味方になる一方で、一歩間違えれば深刻なトラブルや想定外の税負担を招く可能性があるため注意しましょう。
ただ、適切に手続きができなければ税務リスクがあるため、少しでも不明点がある場合は専門家に相談することが大切です。



ご家族だけで進める前に、ぜひ一度、相続の専門家である弁護士に相談してみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応