【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の売却方法は?流れや共有名義買取の費用・税金を解説
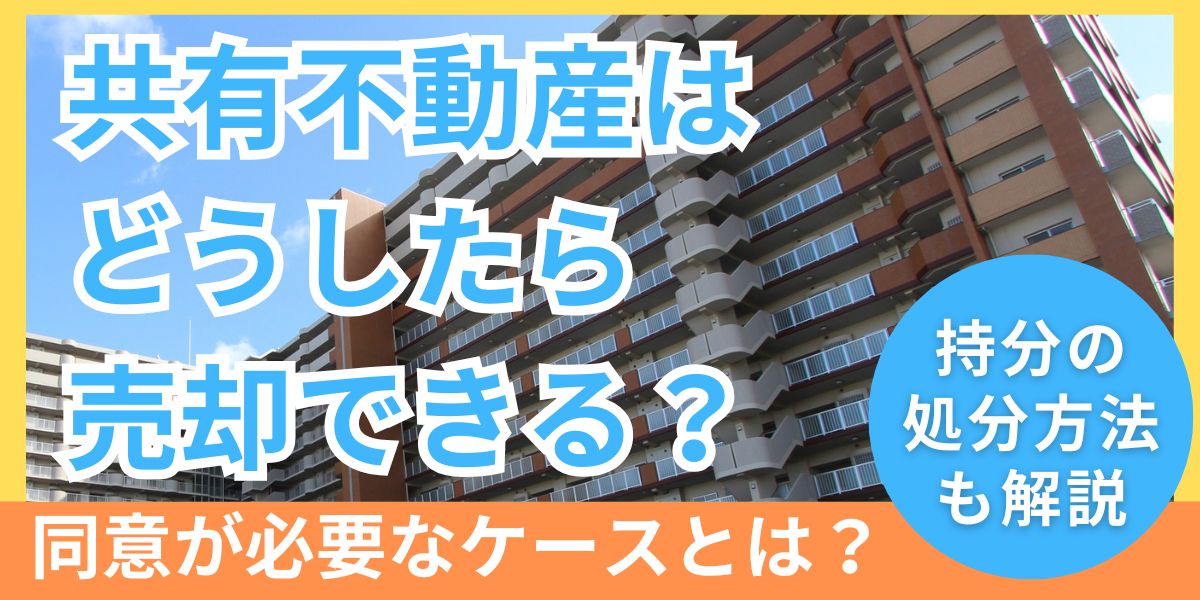
相続や離婚などで共有名義の不動産を持っていると、売却したくても「勝手に売れるのか」「手続きは複雑ではないか」と悩んでしまうことがあります。
結論として、共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。全員の同意が得られない場合、持分だけを個別に売却することも可能です。
ただし、持分のみを第三者へ売却すると売値が低くなるばかりでなく、他の共有者との人間関係も悪化してしまう恐れがあります。
この記事では、共有不動産の売却方法や流れ、よくあるトラブル事例を解説しています。
共有不動産を売却するために必要な書類や費用についても解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産は売却すべき?売るメリット・デメリットとは
共有不動産の売却には、メリットもあればデメリットも存在します。
売却を検討している方は、どのような場面で売却が有利になるのか、逆に注意すべき点は何かを理解しておくことが大切です。
以下で具体的に、共有不動産を売却するメリットとデメリットを整理していきましょう。
共有不動産を売却するメリット
共有不動産を売却することで、多くのメリットが得られます。
最も大きな利点は、単独での持分売却と比べて、高値での売却が期待できることです。
共有者全員の同意を得て不動産全体を売却すれば、買い手も安心して購入でき、市場の適正価格で取引が進みやすくなります。
さらに、売却によって共有関係を解消できるため、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能です。不動産の維持管理費用や固定資産税の負担、利用方法などをめぐって意見が対立するリスクを根本的に排除できます。
また、不動産を現金化することで、共有者それぞれがまとまった資金を手にでき、自由に活用できるようになります。これにより、将来の選択肢が大きく広がるといったメリットも生まれるでしょう。
関連記事:共有不動産の現金化ついて解説
共有不動産を売却するデメリット
共有不動産を売却するには、デメリットも存在します。
最大の懸念点は、共有者全員の合意を得るのが非常に難しいことです。
共有者の中には、売却に反対する人、価格に不満がある人、あるいは連絡が取れない人がいる場合があり、一人でも同意しなければ売却を進めることができません。そのため、話し合いが長引き、売却までにかなりの時間を要する可能性があります。
また、交渉がこじれると、弁護士への相談や裁判による解決が必要となり、さらに時間と費用がかさむことも珍しくありません。
さらに、売却には仲介手数料、登記費用、測量費用などのコストが発生し、これらを共有者全員で分担する必要があります。
最終的に、売却益が出れば譲渡所得税も課税されるため、手元に残る金額が想定より少なくなる可能性も考慮しなければなりません。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫共有不動産の売却を検討する際は、メリットだけでなくデメリットも考慮しておくことが大切です。
共有不動産の売却に全員の同意が必要な理由


共有不動産とは、2名以上の名義人が所有権を持つ物件を指します。
結論として、自分の持分だけなら売却できますが、不動産全体を売るには共有者全員の同意が必要です。
売却ができないほか、居住・賃貸・担保に入れるといった活用も、個人の判断だけでは行えません。
具体的な売却方法を確認する前に、まずはなぜ全員の同意が必要なのかを理解しましょう。
共有不動産の処分と変更行為には全員の同意が必要
共有不動産の売却について民法第251条では、共有物の変更には共有者全員の同意が必要であると定めており、売却もこれに該当します。
(共有物の変更)
第二百五十一条
1 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用:民法|第251条
最高裁判所も昭和42年2月23日の判決でこの解釈を支持しており、この判決は、共有不動産の売却には全共有者の同意が不可欠であるという原則を確立しました。(参照:裁判所|最高裁判決昭和42年2月23日判決)
共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要で、単独名義の不動産売却にはない、ハードルがあります。
共有持分だけなら同意なしで売却できる
共有不動産において、各共有者が保有する所有権の割合を「共有持分」と呼びます。
民法第206条の規定により、共有者は自己の持分を売却する際に、他の共有者の同意は必要ありません。
(所有権の内容)
第二百六条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
引用:民法|第206条
しかし、共有持分の単独売却は不動産全体の時価と比較して1/2〜1/3程度にとどまる傾向があります。
共有持分の売却価格が安い理由は、共有持分だけを取得しても管理や処分の際に他の共有者の同意が必要で、利用に制限があるからです。
共有持分は利用価値が制限されているため、買い手がつきにくいのが現状です。



多くの場合、共有持分の買取業者が、時価よりも大幅に安い価格で買い取っています。
共有不動産を売却する4つの方法


共有不動産の売却は、他の共有者の同意が必要など、単独所有の物件に比べて制約があります。
しかし、適切な方法を選択すれば、他の共有者との関係を維持しつつ円満に売却が進められます。
共有不動産を売却する主な4つの方法は、以下の通りです。
関連記事:共有不動産を現金化する5つの方法とは?売却の手順や費用・注意点を徹底解説
共有者全員の同意のもと売却する
共有不動産を共有者全員の同意のもと売却できれば、通常の不動産取引と同様の販売が可能です。
この方法では、市場価格で売却ができるため、高値で売れる可能性があります。
共有者全員の同意による売却の手順は、以下の通りです。
共有不動産の売却に全員の同意が得られれば、一般的な不動産市場で販売でき、共有者との良好な関係も維持できます。
共有者へ持分を売却する
共有不動産の売却手段として、自己の持分を他の共有者に売却する方法があります。
共有者への持分売却は、次の手順で行います。
共有持分を他の共有者に売却する際、売主と買主が合意していれば、その他の共有者に同意を求める必要はありません。
しかし、売却後の共有者同士の関係を円満に保つために、事前に他の共有者にも持分の売買について伝えておくことが望ましいでしょう。
第三者へ共有持分を売却する
共有不動産の売却において、全員の合意が得られない場合でも、個人の共有持分を第三者に売却する選択肢があります。
共有持分は単独所有の不動産と比べて権利関係が複雑であるため、一般的な不動産市場で買い手を探すのが難しい状況があります。
しかし、専門の共有持分買取会社が存在するため、第三者に共有持分を売却する場合は、それらの会社に買取を依頼するケースが多いです。
共有不動産の持分を第三者へ売却する具体的な手順は、以下の通りです。
一部の買取会社は、購入した共有持分を利用して、他の共有者に高値で買い取るように迫るケースもあります。
買取会社への共有持分の売却は、他の共有者と関係を悪化させる危険性もはらんでいるため慎重に行ってください。
共有物分割請求訴訟を経て売却する
共有不動産の売却で共有者間の合意が得られず、他の共有者が持分を買い取ってくれないときは、民法第256条1項に基づく共有物分割請求訴訟を通じて売却する方法があります。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条
1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
引用:民法|第256条1項
共有物分割請求訴訟を経て共有不動産を売却する流れは、以下の通りです。
共有物分割請求訴訟で裁判所が下す現物分割と代償分割、換価分割の内容は次の通りです。
| 現物分割 | 共有不動産を共有持分割合に応じて物理的に分ける方法 |
| 代償分割 | 一部の共有者が他の共有者に金銭を支払い、不動産全体を取得 |
| 換価分割 | 共有不動産を第三者に売却し、売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分ける方法 |



共有分割請求を弁護士に依頼するメリットは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有物分割請求を弁護士に依頼するメリットは?相談から解決までの流れ
関連記事:共有名義のマンションを売却するには?売却方法や費用・注意点を弁護士が解説
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産が土地のみなら分筆も可能


所有している共有不動産が土地の場合、分筆してから売却するのも選択肢の一つです。
分筆とは、登記簿上で1つの土地を複数に分け、それぞれを独立した土地として登記する手続きです。
たとえば、200㎡の土地を兄弟2人で1/2ずつ共有している場合、100㎡ずつに分けて登記するといったイメージです。分筆後は各区画が単独名義となるため、個人の判断で土地の有効活用や売却がしやすくなります。
しかし、共有不動産の分筆には課題も存在し、土地の方角、接道状況、形状などの要因により、持分割合に応じた公平な分割が難しい場合があります。
そのため、共有不動産の売却で分筆を検討する際は、不動産分野に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
弁護士は分筆の実現可能性や課題を把握し、適切なアドバイスを行います。



相談だけでなく、必要に応じて測量士や不動産鑑定士、土地家屋調査士と連携しながら分筆手続きをサポートしてくれる点もメリットです。
共有不動産を第三者に売却する手順6ステップ
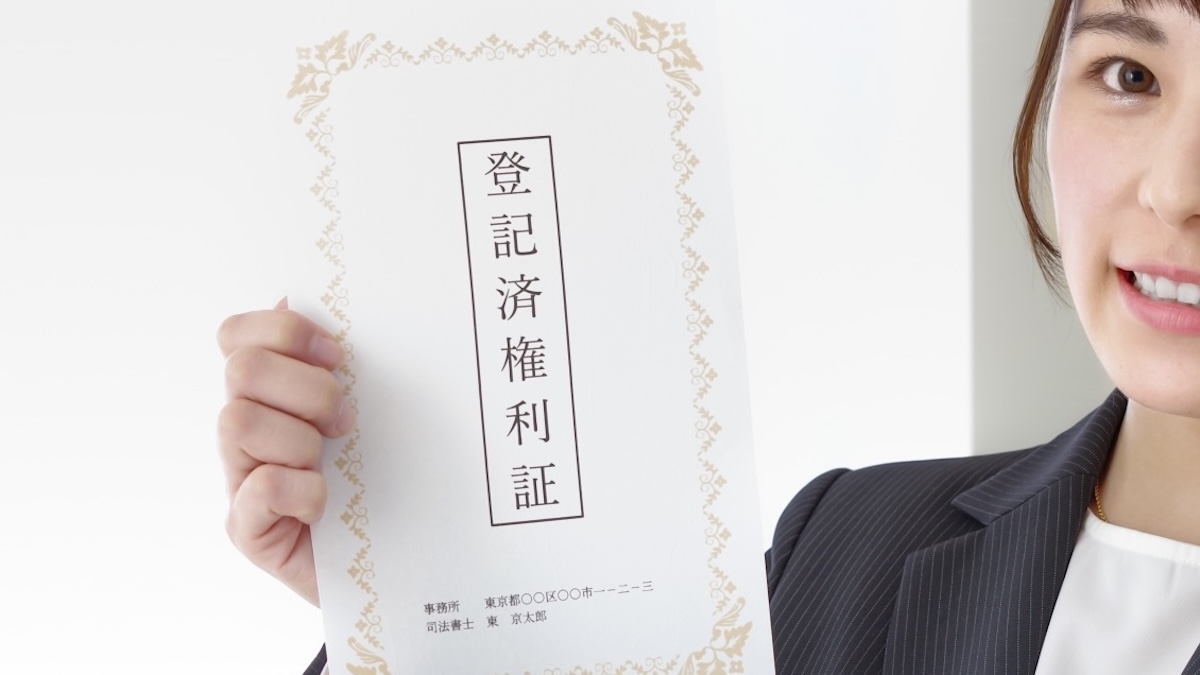
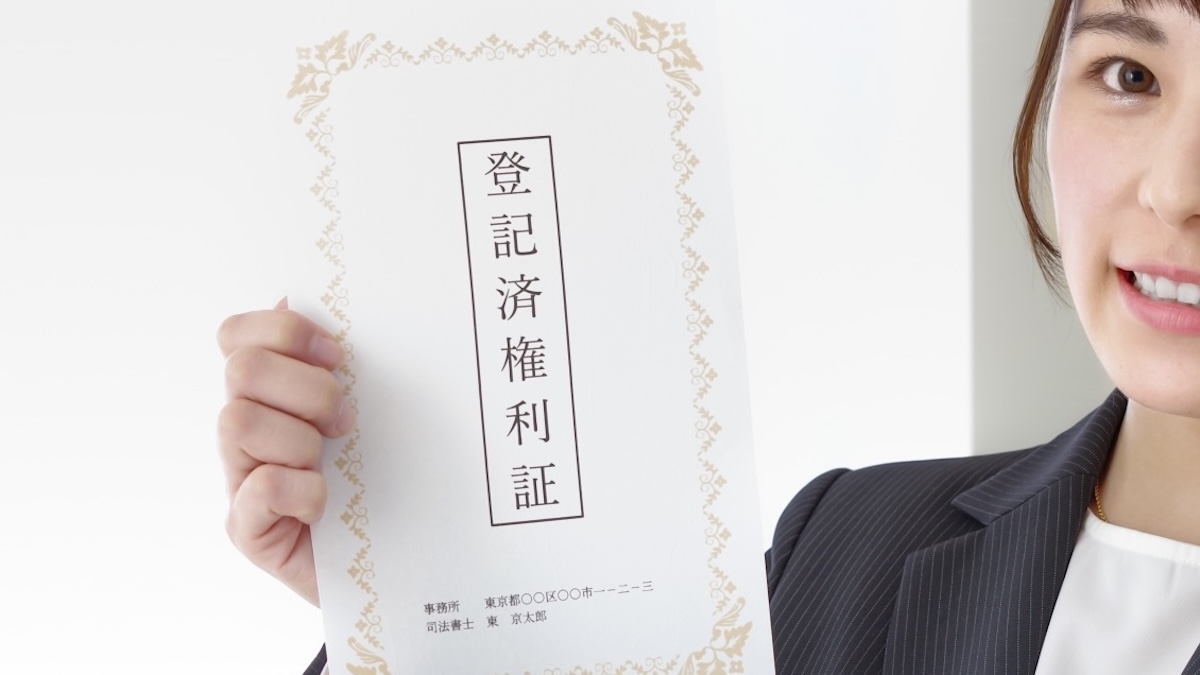
共有不動産は、共有者全員の合意を得てから第三者に売却する方法が最も経済的なメリットを受けられます。
共有不動産を第三者に売却する手続きをスムーズに進められるよう、事前にどのような流れで進めるのか確認しましょう。
共有者全員が売却に同意する
共有不動産の売却には、全共有者の同意が不可欠です。
売却活動を始める前に、共有者が誰なのかを正確に把握しなければいけません。
相続などにより共有持分権者が多数存在し、権利関係が複雑化しているケースがあるためです。
後から新たな共有者が判明すると、売却手続きのやり直しを強いられる可能性があるため、共有者の特定は慎重に行ってください。
また、共有不動産売却の成功には、共有者間の意見をまとめる調整役が必要です。
調整役は共有者の利害を調整し、合意形成を導きます。
調整役には不動産と法律の両面に精通した弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士なら、法律の専門知識と交渉力で、難易度の高い共有不動産の売却手続きを滞りなく実行してくれます。
共有不動産の売却に必要な書類を用意する
共有不動産の売却には、不動産に関する書類と共有者それぞれが用意するものがあります。
不動産に関する書類には、以下のものがあります。
| 不動産に関する書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記識別情報(登記済権利証) | 不動産の所有者であることを証明する書類 |
| 地積測量図・境界確認書 | 土地の面積と隣地との境界を示す書類 |
共有者それぞれが用意するものには、次のものがあります。
| 共有者それぞれが用意するもの | 内容 |
|---|---|
| 実印と印鑑証明 | 印鑑証明は3カ月以内に発行されたもの |
| 住民票(共有者の現住所を確認するための書類) | 3カ月以内に発行されたもの |
| 身分証明書(本人確認のための書類) | マイナンバーカードや運転免許証など |
必要書類に不足があると、売買契約が締結できないため忘れずに準備してください。
不動産会社に共有不動産の査定を依頼する
必要書類を用意したら、不動産会社に査定を依頼します。査定では、周辺の売買事例や土地の形状、建物の状態などをもとに、売却額を算出します。
可能であれば、複数の不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。
会社によって得意分野や査定額が異なるため、比較することで納得のいく売却プランを立てやすくなります。
地域の販売実績が豊富な会社は、自社の広告や顧客ネットワークを活用した売却活動を行ってくれる可能性があります。早期売却につなげるためにも、信頼性の高い不動産会社に依頼しましょう。
査定額が出たら共有者にも伝え、同意を得てから次のステップに進みましょう。
買主と売買契約を締結する
売買契約の締結には、全共有者が契約書に署名し、実印の押印が求められます。
契約時や代金決済時には、原則として共有者全員が立ち会います。
しかし、仕事の都合や遠方居住など、やむを得ない事情で出席できない場合もあるでしょう。
そのようなときは、委任状を作成し、他の共有者や弁護士への委任が可能です。
売却で得られた収益を共有者で配分する
共有不動産の売却後、得られた収益の配分は、原則として、共有者間の合意によって決定されます。
しかし、持分割合を無視して収益を配分すると、贈与税が課せられる可能性があるので注意が必要です。
持分割合よりも過剰に収益を受け取った共有者は、他の共有者から贈与を受けたとみなされるケースがあります。
共有不動産の売却収益を配分する際は、各共有者の持分割合を十分に考慮し、適切な分配が重要です。
共有不動産の譲渡に関わる贈与税については、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:共有不動産の放棄と譲渡による贈与税の課税
譲渡所得税の確定申告を行う
共有不動産の売却で生じた譲渡所得には、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税は確定申告で納付します。
譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。
- 譲渡所得 = (売却金額 × 持分割合)- {(取得費用 × 持分割合) + (売却費用 × 持分割合)}
- 算出された譲渡所得に、所有期間に応じた税率を適用
- 各種控除や特例を考慮して最終的な税額を決定
確定申告は名義人ごとに個別に行う必要があります。



共有者は自分が受け取った収益に応じた譲渡所得税を計算し、申告しなければなりません。
関連記事:共有持分を譲渡する4つの方法とは?手続きや税金・注意点をプロが解説
共有不動産の売却相場は市場価格より安くなる傾向がある
不動産の共有持分を売却する場合、通常の不動産売買よりも相場が低くなるケースが多いです。
共有不動産を売却する場合、共有者全員に同意が必要なため流動性が低く、購入希望者にとって扱いづらい物件と見なされやすい傾向があります。
単独所有の物件と比べて市場価格よりも割安で取引されるケースが多く、売却相場は売却先によって異なりますが、市場価格の1/2~1/3程度とされます。
売却を検討している方は、この点を踏まえて査定を依頼し、条件を比較して検討すると良いでしょう。
共有持分を売却する時の相場や高く売る方法については、以下の記事でも解説しています。あわせてチェックしてみてください。
関連記事:共有持分売却相場はどのくらい?市場価格より安い理由と高く売る方法を解説
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有不動産の売却にかかる費用・税金【4項目】


共有不動産を売却には、費用や税金が発生します。主に発生する費用・税金の項目は、以下の通りです。
| 費用項目 | 概要 | 税額・費用の相場 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書作成時に必要となる税金 | 契約金額に応じて変動する 200円~48万円 ※令和9年3月31日までは軽減税率が適用されています |
| 不動産会社への仲介手数料(一例になります) | 仲介に入った不動産会社へ支払う費用 | 売買価格に応じて変動する 【売買価格が200万円以下】 取引額の5%(+消費税) 【売買価格が200万円超~400万円以下】 取引額の4%+2万円(+消費税) 【売買価格が400万円超】 取引額の3%+6万円(+消費税) |
| 抵当権抹消登記費用 | 売却する不動産に抵当権が設定されている場合に支払う費用(抹消手続きに必要) | 土地・建物それぞれに1,000円 |
| 譲渡所得税 | 売却で利益が発生した場合に課される税金 | 不動産の所有期間によって変動する 【所有期間5年以下(短期譲渡所得)】 所得税:30.63%・住民税:5% 【所有期間5年以上(長期譲渡所得】 所得税:15.315%・住民税:9% |
印紙税と仲介手数料は、売買金額が高くなるにつれて増額します。
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって変動します。5年以内に売却すると短期譲渡所得になるため、税率が高めになります。



税負担を少なくするのであれば、5年経過してから売却した方が良いでしょう。
参照
国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
国税庁|抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税
国土交通省|<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ
国税庁|土地や建物を売ったとき
共有不動産売却のトラブル事例3選


複数の共有者が関わる共有不動産の売却は、トラブルが多く発生しています。共有不動産の売却で起こりがちなトラブル事例には、以下のケースがあります。
よくあるトラブルを確認することで、事前に対策を立てやすくなります。
共有者間で十分に話し合い、必要に応じて不動産会社や弁護士に相談しながら進めましょう。
売却価格でもめてしまった
共有不動産の売却において、共有者間で売却価格の合意が得られないケースも少なくありません。
共有不動産の売却価格でもめてしまった事例です。
ある共有者は高値での売却を望む一方で、別の共有者は早期売却を優先し低めの価格設定を主張して、売り出し価格が決まらないというものがあります。
こうした意見の相違は、不動産市場の好機を逃すリスクを発生させます。
共有不動産の売却では、意見のすり合わせが随所に必要で、成功させるには各共有者の利害を調整し、Win-Winの解決策を見いだすことが重要です。
共有者の所在がわからない
共有者の所在不明は、共有不動産の売却にとって大きな障壁です。
共有不動産を売却の際、共有者の一人が行方不明になっていたという事例があります。
共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要なため、所在のわからない共有者の戸籍や住民票を調査しましたが、居場所が判明しませんでした。
そのため、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てました。
選任された不在者財産管理人に同意を求めて、ようやく共有不動産の売却ができたのです。
この事例では、結果的に共有不動産を売却できました。
しかし、不在者管理人の選任には通常3カ月〜6カ月の期間を要するため、その間に好条件での売却チャンスを逃していたかもしれません。
他の共有者が持分を買取会社に売却してしまった
共有不動産の売却で発生したトラブルの事例には、共有者の一人が持分を買取会社に売却してしまったというものがあります。
買取会社は、購入した共有持分を最大限に活用しようとします。
そのため、他の共有者に手に入れた持分の購入を迫ったり、逆に持分の売却を提案したりして、心理的なストレスを受ける場合もあるのです。
さらに、買取会社が不動産の分割や競売による換価を求め、共有物分割請求訴訟を提起するケースも見受けられます。
共有物分割請求訴訟によって、共有者の意図しない形で不動産が処分される可能性もあります。



もし、買取会社からしつこく営業を受けたときは、迷わず弁護士に相談してください。
共有不動産の売却はトラブル回避のために弁護士に相談する


共有不動産の売却では、トラブルに発展しやすく、スムーズに進めるためにも前もって弁護士に相談するべきです。
共有不動産が抱える問題には、所有者が自由に不動産を利用したり、処分したりできない点が挙げられます。
さらに、共有状態を放置して、相続などで権利関係が複雑化し、共有者の特定が困難になると個人で解決するのは不可能です。
そのため、共有不動産の問題は、弁護士に相談して早期に解決策を提示してもらうのがベストな方法といえます。
不動産問題に精通した弁護士は、法律と不動産の両面から問題を分析し、依頼者に最適な解決策を提案できます。共有不動産の売却プロセスをスムーズに進め、適正価格での販売を後押しします。



弁護士は共有者全員の利益を守りつつ、適切な売却方法を見いだします。迷ったらまずは相談してみてください。
共有不動産の売却に関するよくある質問
共有名義の不動産を売却する際は3,000万円控除は適用されますか?
3,000万円の特別控除は、居住用の不動産(マイホーム)を売却した場合に適用される制度です。
共有名義の場合、不動産1つに対してではなく、共有者1人ごとに最大3,000万円まで控除が適用されます。
たとえば、夫婦で1/2ずつの共有名義になっている家を売却した場合、夫と妻それぞれに3,000万円の控除が適用されるため、合計で6,000万円までが非課税になる計算です。
マイホームを売却する際は、税負担を軽減するためにも特別控除の適用条件を確認しましょう。
共有持分の評価額はどのように決まりますか?
共有持分の評価額は、対象となる不動産全体の市場価格をもとに、自身の持分割合をかけて算出するのが基本です。(参照:国税庁|第1章 総則)
ただし、持分のみでは単独で利用・売却ができないため、一般的には単独所有の不動産と比べて市場価値が低くなります。
買取業者に売却する場合は、その利用制限を考慮して、路線価や固定資産税評価額などを参考に、市場価格よりも低い金額で取引されることが多いです。
共有持分を買取ってくれる買取業者の目的は何ですか?
共有持分を専門に買い取る業者の主な目的は、最終的にその不動産全体を単独所有することです。
持分のみでは活用が難しいですが、他の共有者から持分を買い集める、あるいは共有物分割請求訴訟を起こすなどの手法によって、最終的に不動産全体の売却や活用を目指します。
これにより、市場価値が回復した不動産を再販し、利益を得ることを目的としています。
共有持分買取業者については、以下の記事でも解説しているので参考にしてください。
まとめ|共有不動産は全員が同意し売却するのがもっとも価値が生きる


複数の名義人がいる共有不動産の売却手順と、トラブル事例について解説しました。
- 共有不動産の売却には全員の同意が必要だが、持分だけなら個人の判断で可能
- 共有不動産は共有者内で売買する方法や土地のみなら分筆して売却する方法もある
- 共有者で同意が得られない場合は、共有物分割請求訴訟によって売却を目指すこともできる
- 共有不動産の売却には、印紙税や仲介手数料などがかかる
- 共有不動産の売却では、売り出し価格の設定でもめたり、所在がわからない共有者がいたりするなどトラブルが多く発生している
共有不動産の価値を最大化しトラブルのない売却を実現するためには、弁護士に相談して最適な方法を選択しましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応








