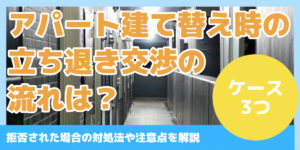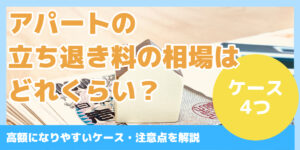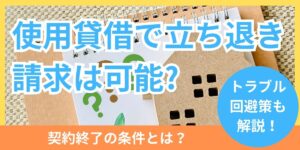【無料相談受付中】24時間365日対応
居座り続ける入居者を強制退去させることはできる?条件や流れ・費用について解説
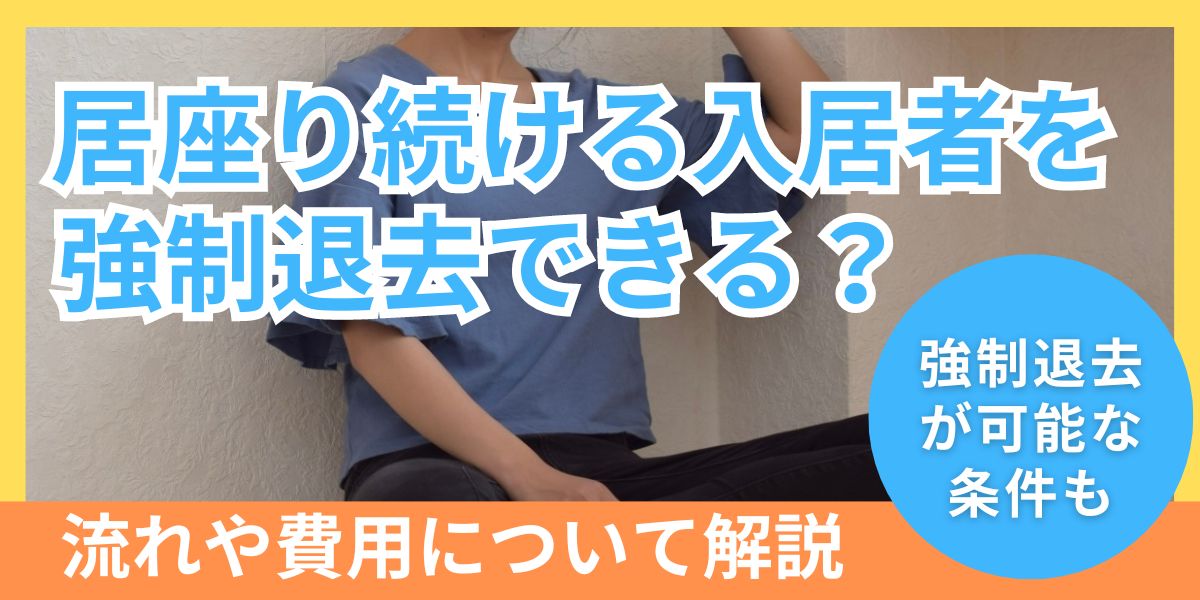
- 家賃滞納者が退去しない
- 強制退去の手続きがわからない
このようなお悩みはありませんか?
家賃滞納や契約違反が続くと、入居者に対して大家としてはやむを得ず退去を求めることがあります。
しかし、退去するよう求めたにもかかわらず、居座り続ける入居者への対応は複雑です。
本記事では、強制退去の流れや費用、居座り続ける入居者への対処法をわかりやすく解説します。
-佐々木 一夫-
- 家賃滞納などを理由とする強制退去は、訴訟を経て判決を得た後に初めて法的な手続きが可能となり、鍵交換や荷物処分などの“実力行使”はできません。
- 強制退去を検討する際は、滞納賃料の回収も視野に入れ、契約解除の通知から訴訟提起までの一連の手続きを迅速かつ正確に進める必要があります。
- 滞納者への心理的・法的なプレッシャーをかけ、スムーズな物件の明け渡しを実現するため、経験豊富な弁護士に手続きを一任することが最善です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
強制退去ができる条件とは

強制退去ができる条件には、入居者の契約違反が含まれます。
たとえば、入居者が家賃を滞納していたり、無断で増改築をしたりなどが契約違反にあたります。
契約違反により、大家と入居者の信頼関係が破綻していると、契約解除が可能です。
信頼関係が破壊されていると認めて貰うには、以下のような事情が必要となります。
- 長期間の家賃滞納(一般的には3か月以上とされる)
- 支払いの意思が見られない
- 滞納した家賃を支払う能力がないと判断される
- 無断での増改築
- 近隣住民に迷惑をかけるような騒音や暴言
- 暴力行為
- 違法な営業活動
- 虚偽の情報を基に契約を締結した
- 暴力団関係者である
- 犯罪行為をおこなった

明渡しのカギは信頼関係破壊の立証です。滞納は“金額×期間×催告への反応”で評価され、騒音等は記録化(日時・動画・苦情票)が有効。違反類型ごとに証拠の取り方を変えると、解除の説得力が一段上がります。
強制退去ができる条件については、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:強制退去が可能な条件について解説
関連記事:強制退去でアパートを明け渡してもらう条件について解説
強制退去には裁判が必要


入居者に賃貸物件から退去してもらいたい場合、法律にのっとり強制退去をおこなう必要がありますが、賃貸借契約が解除されていることが前提です。
賃貸借契約を解除するには、入居者に契約違反があることが必要です。
たとえば、長期間にわたる家賃の滞納や無断での改築などの契約違反がある場合です。
次に、大家は入居者に対して賃貸借契約を解除する通知を行うとともに退去の要求をおこないます。
入居者が従わない場合、裁判所に明け渡しを求めて訴訟を提起することになります。
訴訟で勝訴すると、強制退去の手続きを進められます。



解除→明渡訴訟→執行が正規ルートです。解除通知は内容証明で到達日を残し、訴訟では解除原因の具体化(滞納表・警告履歴・写真や録音)を徹底。自力での排除は不法行為リスクが高いので厳禁です。
参考:裁判所|民事執行
居座り続ける入居者を退去させるまでの流れ
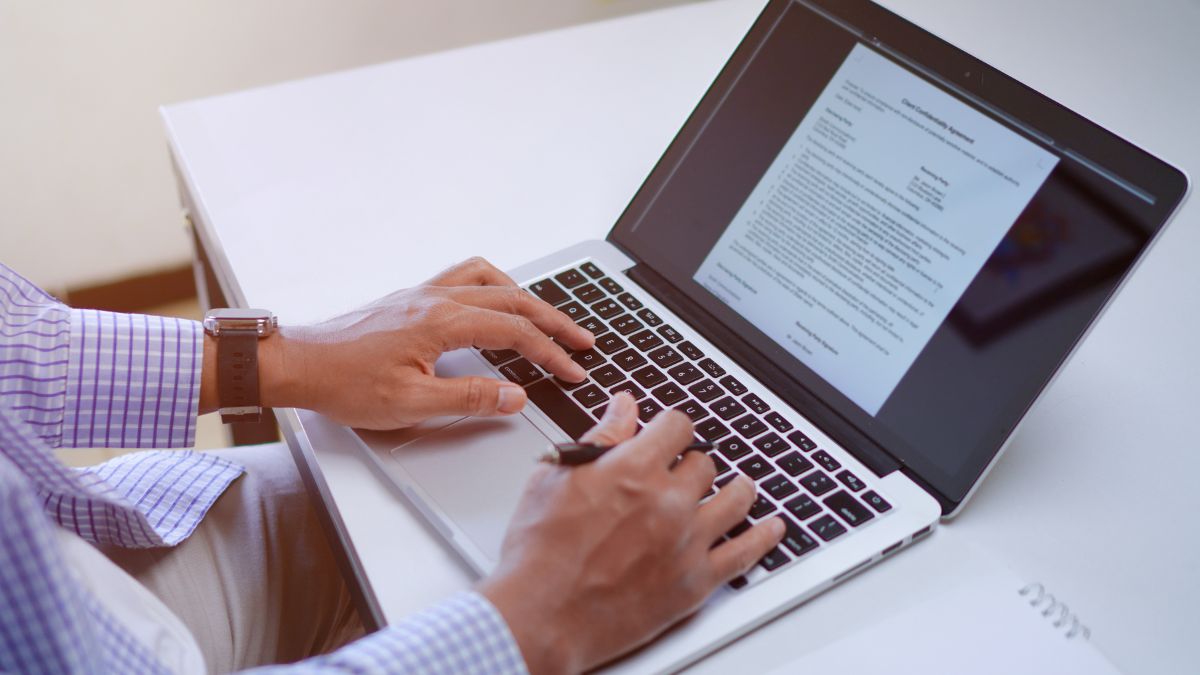
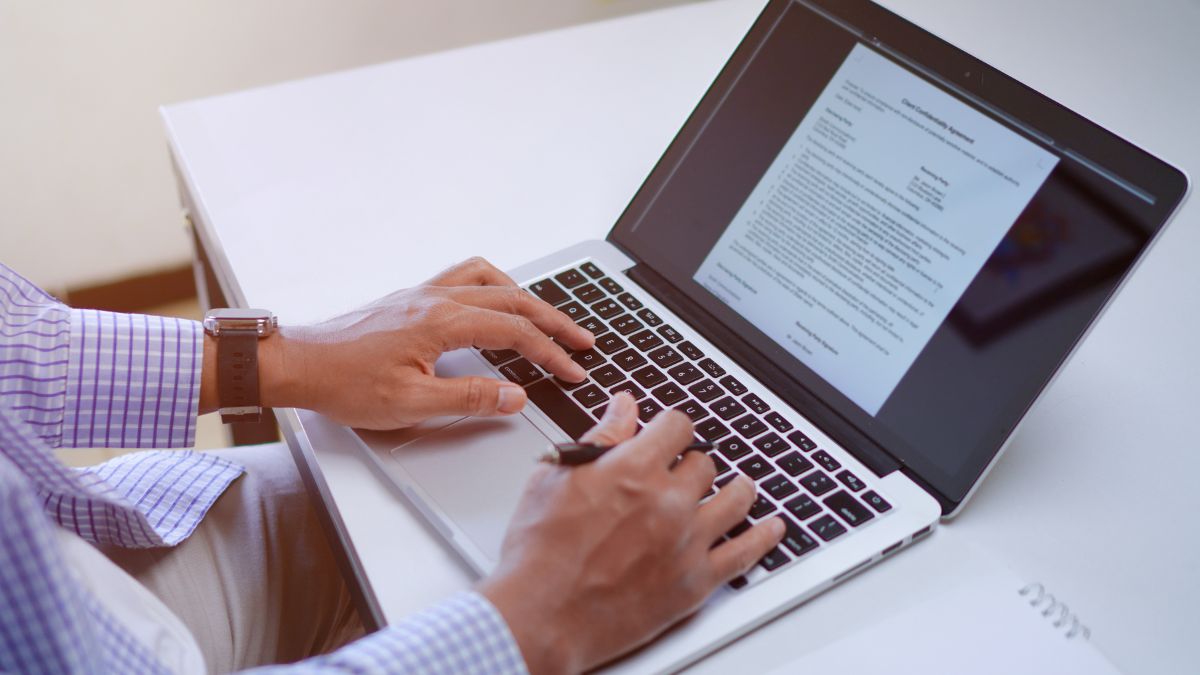
入居者が退去を拒否した場合、大家は法的な手段により強制的に退去させることが可能です。
入居者を退去させるためには、段階的な手続きを踏む必要があります。
以下に、強制退去についての具体的な流れを説明します。
- 口頭や文書で改善要求や家賃の催促
- 内容証明郵便での家賃の催促と契約解除の通知
- 連帯保証人への連絡
- 裁判での明渡請求
- 強制執行
1.口頭や文書で改善要求と家賃の催促
まずは、未払い賃料の支払いを要求したり、契約違反や近隣トラブルの原因を改善したりするよう、口頭や手紙で何度も促します。
この段階では、入居者とのコミュニケーションを重視し、問題解決を図ることが重要です。
穏やかな対応を心がけることで、トラブルの拡大を防げます。
2.内容証明郵便での家賃の催促と契約解除の通知
口頭や手紙での催促が効果を発揮しない場合、内容証明郵便を利用して家賃の催促をおこないます。
また、賃貸借契約の解除通知もあわせて行い、正式に契約を解除する旨を伝えます。
内容証明郵便は、送付した内容と送付日を証明するもので、証拠として有効です。
賃貸借契約を解除する意思表示をしたことを証明してもらえるので、解除する時は内容証明郵便で発送するのがよいでしょう。



これにより、入居者に対して圧力をかけることが可能です。
3.連帯保証人への連絡
入居者が期日までに支払いをおこなわない場合、連帯保証人に対しても家賃の支払いを督促します。
ただし、予告なく保証人に連絡すると、入居者が感情的になる可能性があります。
そのため、事前に入居者に対して保証人への請求を予告しておくことが望ましいでしょう。
予告することで、関係者間の信頼関係を保ちながら問題解決を図ります。
4.賃貸契約解除と裁判での明渡請求
上記の手続きをおこなっても明け渡さない場合、明渡請求の訴訟提起をおこないます。
訴訟では、契約違反があったことを示す証拠を示し、裁判所に対し退去を命じるよう求めます。
訴訟には時間と費用がかかりますが、強制的に退去を求めるには必要な手段です。
裁判所の勝訴判決を得ることで、強制退去の準備が整います。
5.強制退去
明渡請求訴訟で勝訴した場合、裁判所に強制退去の申立てをおこないます。
その後、裁判所の執行官が入居者を強制的に退去させる手続きを実行します。
強制退去の過程では、入居者の荷物の処分や保管も必要となるため、事前に倉庫を借りておくなど、準備をしておきましょう。
以上の手続きを踏むことで、居座り続ける入居者を法的に退去させられます。
それぞれの段階で適切な対応をおこない、トラブルを最小限に抑えることが求められます。



実務は“段階的エスカレーション”。①任意交渉→②内容証明(相当期間付催告+解除予告)→③保証人連絡→④明渡訴訟→⑤強制執行。各段階で証拠化(送達記録・面談メモ)を残すほど、次のフェーズがスムーズに進みます。
参考:裁判所|引渡命令の申立てから強制執行の申立てまでの手続の流れ
関連記事:強制退去の費用について解説
強制退去にかかる期間


明け渡しを認める判決後に強制執行を申し立てた場合の強制退去にかかる期間は、一般的に約1か月と2週間です。
内訳を以下に示します。
- 強制退去の申立てから明渡しの催告まで:約2週間
- 明渡しの催告があった日から明渡しの断行(※)まで:催告があった日から1か月を経過する日(参照:民事執行法 第168条の2)
(※)「断行」とは強制退去を実際におこなうことです。
ただし、事案によっては早期に明渡しが実現することもあります。
たとえば、入居者が自発的に退去する場合や、裁判所が迅速に手続きを進める場合などで、結果として、全体の期間が短縮されることもあります。
強制退去の手続きには時間を要するため、早めに対応を開始することが大切です。



執行は催告(概ね2週間)→断行(原則1か月後)が目安。訴訟期間は事案で上下するため、早期から仮執行宣言付き判決や仮処分の要否まで弁護士と設計しておくと、全体のリードタイムを短縮できます。
関連記事:強制退去の期間について解説
強制退去にかかる費用


強制退去にかかる費用は下記のとおりです。
- 裁判の費用
- 弁護士への費用
- 強制退去させるための費用
裁判の費用
裁判を起こす際には、訴訟提起の執行段階と執行段階でそれぞれ費用がかかります。
裁判の費用は、主に以下の2種類です。
- 予納郵便切手代:6,000円
- 印紙代:不動産の固定資産税額によって異なる
- 予納金:6万5,000円
- 郵券および印紙代
弁護士への費用
弁護士への費用は、事案や弁護士によって異なります。
一般的には着手金として30〜40万円程度かかります。
着手金とは、弁護士が案件を受任し、解決に向けて活動を開始するための費用です。
ほかにも、以下のような費用が発生する場合があります。
- 報酬金:事件解決後に支払う成功報酬
- 日当:弁護士が裁判所に出廷する際に支払う費用
- 事務手数料:登録や書類作成などの事務作業にかかる費用
依頼する際には、費用の見積もりを確認し、予算を立てることが重要です。
強制退去させるための費用
強制退去させるための費用の具体例を以下に示します。
- 荷物を運び出す人件費
- トラックの費用
- 荷物の保管費用
たとえば、ワンルームの場合にかかる費用は、約10万円です。
家族が同居している場合には、約20〜50万円です。



ただし、家の規模や状況によってはさらに高額になることもあります。
強制退去後の荷物は処分できない
強制退去をおこなった後に残された入居者の荷物は、個人の財産であるため、勝手に処分できません。
荷物の保管や処分には法的手続きが必要となり、注意が必要です。
作業員が執行官の指示の元で荷物の搬出
↓
事前に借りてある倉庫などに保管
↓
期限内に引き取りがなければ執行官が売却や廃棄
所有者の同意なく荷物を処分すると、法的トラブルになる可能性があるため、適切に対応しましょう。
動産執行で売却
動産執行は、賃借人の財産(動産)を差し押さえ、売却して債務を回収する手続きです。
建物とは独立した、室内にある物が目的外動産にあたります。
たとえば、エアコンやテレビなどの家具家電です。
ただし、民事執行法 第131条に基づき、差押えの対象となるのは、法律で「差押禁止財産」とされていない動産のみと定められています。
差押禁止財産とは、生活に必要な必需品や、入居者が事業をおこなっている場合の事業に必要な設備や器具などを指します。
そのため、生活に支障をきたさない動産のみを売却できますが、法的な手続きが必要です。
動産執行の手続きや注意点についても、弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。



費用は裁判費用+弁護士費用+執行実費の三層。執行実費は人員・車両・保管料で増減します。見積り時は“部屋の広さ/荷物量/生活用品の有無”を具体化し、保管期間も想定して資金計画を立てましょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
居座り続ける入居者へ強制退去にかかる費用を請求できる?


強制退去にかかった費用は、原則として入居者の負担となります。
民事執行法 第42条には「強制執行の費用で必要なものは債務者の負担とする」と定められています。
そのため、大家は強制退去にかかった費用を入居者に請求することが可能です。
請求できる費用は下記のとおりです。
- 裁判費用
- 強制退去させるための費用
しかし、入居者に対し、強制退去にかかった費用を請求できても、実際に回収できるかどうかは別問題です。
とくに、経済的に困窮している入居者からは費用を回収するのが難しい場合があります。
さらに、入居者と連絡がつかない場合にも、費用の回収は困難です。
そのため、事前に弁護士や専門家に相談し、費用回収の見込みについても確認しておくことが重要です。



原則債務者負担でも、“回収できるか”は別問題。判決・和解に費用条項を入れ、保証金・滞納金との相殺設計や給与・預金の差押ルートを先に確認しておくと、回収可能性が上がります。
強制退去を弁護士に頼むメリット


強制退去は、時間と費用がかかる複雑な手続きです。
強制退去を弁護士に依頼することには費用がかかりますが、多くのメリットが得られます。
弁護士に依頼するメリットは、下記のとおりです。
- 交渉を任せられ、精神的な負担を軽減できる
- 費用も時間もかからない別の方法が見つかる可能性がある
- 早期に解決できる可能性がある
- 法的なトラブルを回避できる
交渉を任せられ、精神的な負担を軽減できる
弁護士は、入居者との交渉を代行できます。
弁護士は、法律に基づいて適切な交渉をおこなうため、大家が不利な条件で和解してしまうリスクを減らせます。
また強制退去は、大家にとって精神的な負担が大きい手続きです。
弁護士に依頼することで、交渉だけでなく、手続きに関する一切の事務を任せられるため、精神的な負担を軽減できます。
費用も時間もかからない別の方法が見つかる可能性がある
状況に応じて、調停など、費用と時間がかからない代替案を提案してくれる可能性があります。
また、強制退去をおこなう場合でも、最も費用対効果の高い方法を選択し、不要な支出を抑えることが可能です。
弁護士の経験と知識を活用することで、効率的かつ効果的な解決策を見つけられます。
参考:日本司法支援センター 法テラス|住まい・近隣トラブルに関するよくある相談
早期に解決できる可能性がある
弁護士に依頼することで、早期に問題を解決できる可能性が高くなります。
弁護士は、強制退去に関する専門知識と経験を持っているため、手続きをスムーズに進められます。
具体的には、下記のとおりです。
- 強制退去に必要な手続き
- 書類作成
- 裁判所との連絡 など
法的なトラブルを回避できる
強制退去は、法的な手続きであるため、誤った対応をすると法的なトラブルに発展する可能性があります。
弁護士は強制退去の手続きを熟知しており、交渉をスムーズに進められます。
手続きの遅延やミスを防げ、迅速かつ確実な強制退去が可能です。



“強く速く、しかし適法に”。弁護士が入ると非弁リスク回避はもちろん、最短ルート(和解条項の設計、退去期日・違約金・残置物処理の合意)での着地が狙えます。執行前の任意明渡しへの転換も有効です。
関連記事:強制退去でアパートを明け渡してもらう条件は?手続きの流れや費用、注意点も解説
強制退去時の注意点


強制退去をおこなう際には、以下のような点に注意する必要があります。
- 実力行使は避ける
- 強制退去まで時間がかかる
実力行使は避ける
実力行使とは、大家が自ら入居者を退去させる行為です。
具体的には、下記のような行為が実力行使に該当します。
- 勝手に部屋に入って動産類などを処分する
- 鍵を勝手に変える
- 入居者に暴力をふるう
上記の行為をおこなうと、不法行為とみなされ、大家側が損害賠償を請求される可能性があります。
損害賠償請求されるだけでなく、刑事事件にまで発展する可能性も否定出来ません。
そのため、強制退去を進める際は、必ず法的手続きを遵守し、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
強制退去まで時間がかかる
強制退去の手続きには時間がかかります。
- 裁判所への申立て
- 判決
- 強制退去
各段階で一定の期間が必要となるため、裁判所に訴訟を提起してから最短でも4か月、場合によっては1年以上かかることもあります。
早めに手続きを開始し、計画的に進めましょう。
実力行使を避け、時間がかかることを理解した上で、計画的に進めると、トラブルを最小限に抑えられます。



自力救済はNG(鍵交換・締め出し・動産処分は危険)。残置物は執行官の管理下で保管→売却/廃棄という法的フローが基本です。感情的対立を避け、全連絡は記録化するのが安全運用です。
関連記事:居住権を主張して居座り続ける相手を退去させるには?
強制退去の条件に関するよくある質問
強制退去ができないケースとは?
家賃滞納があっても、その期間が1〜2ヶ月程度と短く、借主との「信頼関係が破壊された」とまでは言えない場合、法的な契約解除や強制退去は認められにくい傾向にあります。
また、どれだけ悪質な入居者であっても、大家さんが裁判所を通さずに勝手に鍵を交換したり、荷物を運び出したりする行為は「自力救済」として法律で禁止されています。
強制退去を実現するには、正当な法的手続きと裁判所の許可が不可欠です。
入居者と連絡がとれない場合の対処方法は?
連絡が取れないからといって、安否確認などの正当な理由なく無断で室内に立ち入ると、住居侵入罪などに問われるリスクがあります。
まずは連帯保証人への連絡や現地訪問を行い、それでも反応がない場合は内容証明郵便を送付します。
相手が行方不明で書類が届かない場合でも、裁判所の掲示板に掲示することで相手に届いたとみなす「公示送達」という制度を利用し、訴訟手続きを進めることが可能です。焦らず法的手順を踏みましょう。
夜逃げされたらどうすればよい?
荷物を残したまま入居者が行方をくらませた場合でも、契約自体は継続しているため、勝手に荷物を処分したり部屋を明け渡した扱いにすることはできません。
法的には、明け渡し訴訟を起こして判決を得てから、強制執行の手続きで残置物を処理する必要があります。
放置している間も家賃は発生せず損失が拡大してしまうため、夜逃げが疑われる時点で早急に弁護士へ相談し、法的な明け渡し手続きに着手することをおすすめします。
まとめ:強制退去の条件についてのご相談は弁護士まで


強制退去は、あくまで最終的な手段です。
悪質性が高い場合を除き、裁判所もすぐに立ち退きを命じるような判決を下すことはありません。
お互いの妥協案などを話し合い、解決へと導くことが大切です。
もし、強制退去に関するトラブルが発生した場合は、弁護士に相談することで、法的手続きを適切に進められます。
弁護士は、強制退去に必要な交渉や手続きを代行し、トラブルを最小限に抑えるためのアドバイスを提供してくれます。



勝ち筋は証拠固め→適式解除→迅速提訴→和解or執行。初動で時系列と証拠を整え、費用・期間・回収の見通しを数値で把握しましょう。早い相談ほど、コストとリスクを下げられます。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応