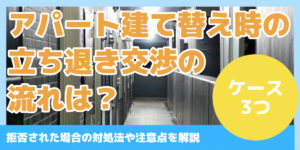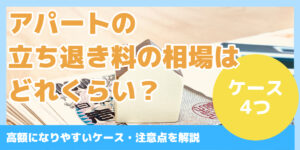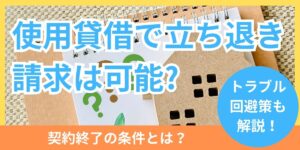【無料相談受付中】24時間365日対応
強制退去の流れを7つのステップで解説!注意点やかかる費用を確認
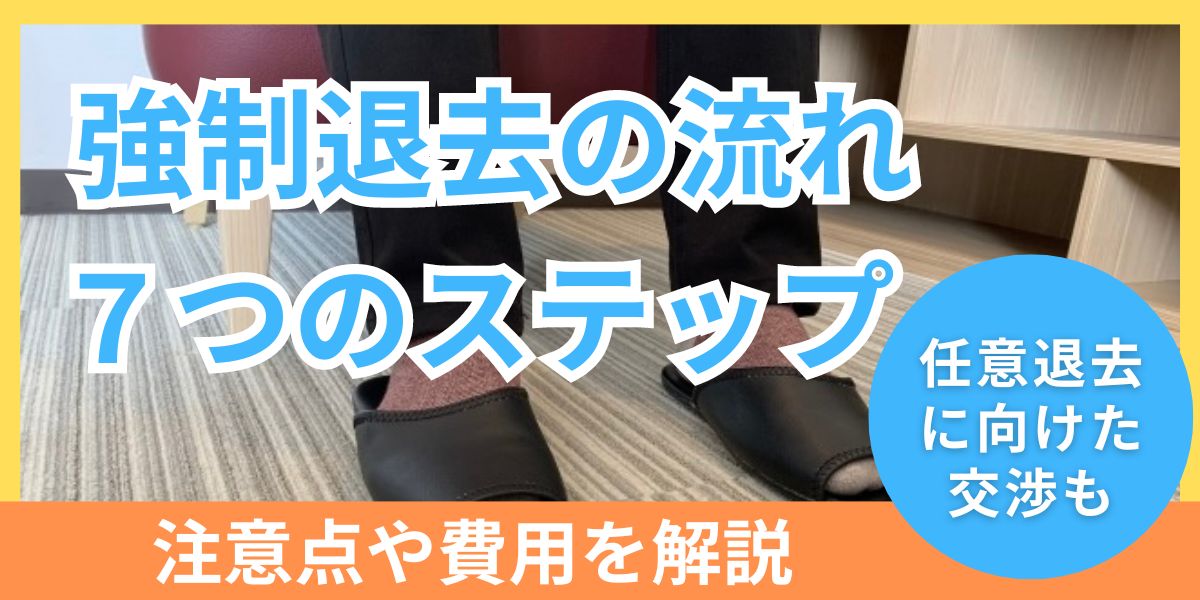
強制退去と聞くと、「自分の経営している賃貸物件でそのようなことはあり得ない」と思っている大家もいるのではないでしょうか。
しかし、裁判所が毎年公表している「司法統計年報」によると、令和5年に地方裁判所で新たに申し立てられた不動産の強制執行数は5,609件にも上ります。
さらに申し立てされているものの、審理中で強制退去執行がなされていないものが2,786件もあるのです。
この数値を見てもわかるように、強制退去は他人事ではなくどこでも起こりうるものであり、さらに審理が長引く可能性もあります。
賃貸物件を経営している大家は万が一のトラブルに備えて、ぜひご確認ください。
強制退去問題でお困りの場合は、専門家に依頼するのが解決への一番の近道です。
弁護士法人アクロピースでは、不動産に強い弁護士が法的アドバイス、強制退去手続きや裁判も承ります。
初回60分の相談は無料です。
ぜひお気軽にご連絡ください。
\7000件以上の相談実績/
【無料相談受付中】24時間365日対応
強制退去の流れを7つのステップで解説
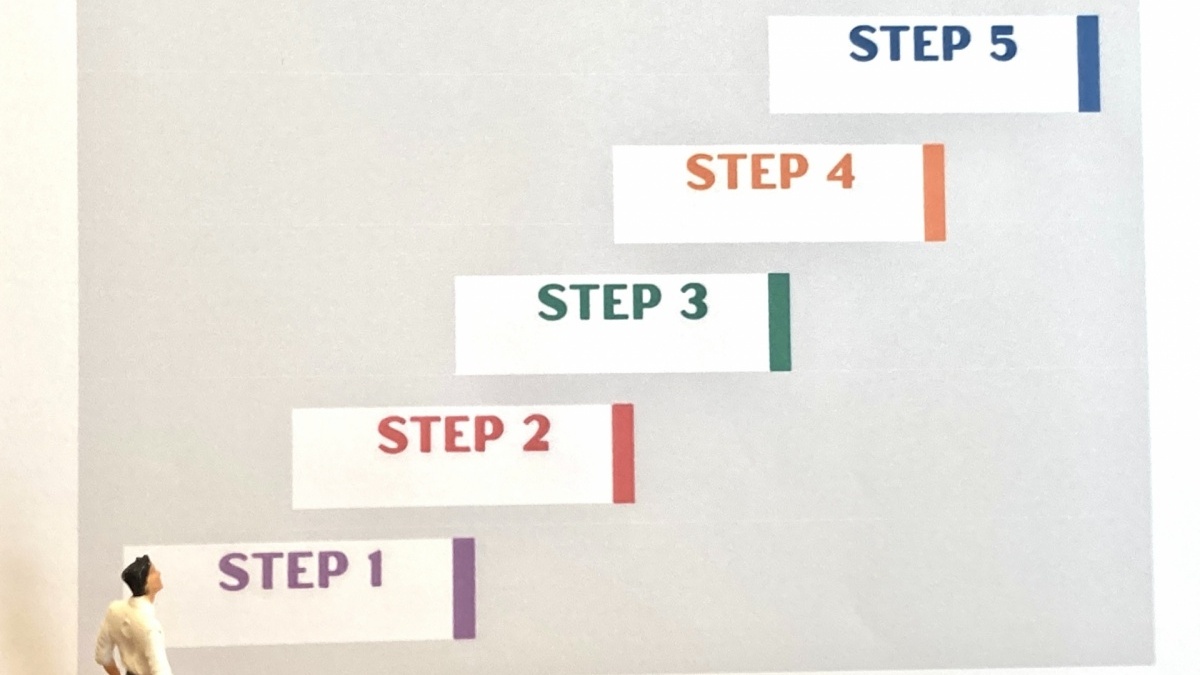
家賃滞納や他の入居者への迷惑行為などで、強制退去させたい借主がいる場合は、手順を追って強制退去の手続きを取る必要があります。
強制退去の流れは次の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1.借主にトラブルの早期解決を求める
まずは電話や手紙、借主宅への訪問を行い、トラブルの早期解決を求めましょう。
もしかすると借主にやむを得ない事情があるかもしれません。
借主と大家で直接話し合うことで、トラブル解決の糸口が見つかることもあります。
ここで、借主が家賃滞納や明らかな契約違反をしているからといって、実力行使で追い出そうとすると、大家が罪に問われてしまう恐れがあります。
《大家が罪に問われる行為》
- 借主が留守中に大家が部屋の荷物を出してしまう
- 借主の部屋のカギを付け替える
- 借主が出ていくまで大家が部屋に居座る
借主と話し合いをするときは、あくまでも冷静に事実確認と注意にとどめておきましょう。
また、借主に家賃の支払いの督促や騒音などトラブルの注意を何度も行うことで、強制退去するための証拠づくりにもなります。
ステップ2.連帯保証人に連絡
大家が借主に対して再三の家賃の支払いの督促やトラブルに対する注意をしても、借主からの反応がなかった場合は、連帯保証人に連絡しましょう。
借主が家賃滞納をしている場合は、連帯保証人に立替てもらうよう請求できるためです。
このとき連帯保証人として家賃保証会社が入っている場合、借主が家賃滞納をするとすぐに立替えてくれるでしょう。
立替え後は、家賃保証会社が大家の代わりに家賃を取り立てますが、借主が支払い期限までに立替えた家賃を支払わず一定の期間が経過すると、ブラックリストに記録されます。
ステップ3.内容証明郵便で契約解除の予告
大家が家賃の支払いやトラブルの改善を訴えても、借主に何の反応もない場合は、配達証明付き内容証明郵便で契約解除の予告を行いましょう。
配達証明付き内容証明郵便とは以下の内容を日本郵便が証明する制度です。
《配達証明付き内容証明郵便が証明する項目》
- 誰が誰に対して送付したか
- いつ送付したか
- どのような内容の文書を送付したか
- 文書がいつ到達したか
そのため、配達証明付内容証明郵便を受け取った借主の「手紙を見ていない」「郵便が未達になっている」というような言い逃れはできません。
また、強制退去の法的手続きに必要な「正当な事由」の証拠にもなります。
内容証明郵便は、賃貸借契約の解除の最終通告です。
借主が内容証明郵便を受け取っても対応しない場合、大家または家賃保証会社は、強制退去の法的手続きへ進みます。
ステップ4.賃貸契約を解除する
内容証明郵便で記載した期日までに、借主が家賃の支払いやトラブルの改善などに応じない場合、賃貸契約を解除し強制退去の法的手続きの準備を始めます。
ステップ5.明け渡し請求訴訟
賃貸借契約を解除したのにもかかわらず、借主が退去しない場合は裁判所にて明け渡し請求の訴訟を提起します。
このとき、大家は不動産の明け渡しはもちろんのこと、未払いの家賃・滞納家賃に伴う遅延損害金の請求も合わせて行いましょう。
明け渡し請求訴訟には、以下の書類が必要です。
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価額証明書
- 代表者事項証明書(原告または被告が法人の場合)
- 予納郵便切手
- 収入印紙
- 証拠書類(建物賃貸借契約書、内容証明郵便、配達証明書など)
弁護士や司法書士などの専門家へ訴訟の代理を依頼するときには、訴訟委任状も用意します。
ステップ6.裁判
裁判では、大家と借主が相互に主張・立証します。
裁判では、和解、つまり話し合いによる解決の可能性がないかについても並行して検討されます。
裁判で大家と借主の話し合いがまとまらない、借主が裁判に出廷しないケースでは、裁判所が判決を下します。
ステップ7.強制退去執行
明け渡し請求訴訟で大家が勝訴しても、借主が退去するとは限りません。
このときは、債務名義をもって強制執行を申し立てましょう。
債務名義とは、強制執行をする根拠となる債権・債務を記載した文書のことで、明け渡し請求訴訟の判決が確定した後に手続きができます。
強制執行は、たとえ借主が留守であっても、容赦なく実施されます。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫裁判所の職員(執行官)の指揮の下、借主の部屋の家財道具を全て運び出して建物内を空の状態にしたうえ、鍵の交換まで行って、明け渡しを終えます。
悪質な契約違反があるときは「建物明渡断行の仮処分」の手続きができる


借主が悪質な契約違反をしており、一刻も早く借主を賃貸住宅から退去させたい場合は、建物明渡断行の仮処分の手続きを行い借主を退去させることが可能です。
「建物明渡断行の仮処分」の手続きができるのは、最も緊急性が高い場合に限られ、民事保全法23条2項に規定されている内容を証明する必要があります。
民事保全法23条2項
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
建物明渡断行の仮処分では、実質的には、明け渡し請求の訴訟で強制退去が認められたことと同じことを実現できます。
建物明渡断行の仮処分が認められる具体的なケースは、次の通りです。
- 借主の行為が執行妨害的であると評価される場合
- 借主が暴力や暴言で大家を脅し賃貸住宅に住み続ける場合
- 借主が賃貸住宅を既に退去済で大家都合でその賃貸物件を早急に使用すべき事由がある場合
- 賃貸物件の取り壊しなどで他の入居者が退去に同意しているのにもかかわらず、借主だけが退去に同意せず大家に損害が発生している
- 公益性のある事業を遂行する上で、賃貸物件の早期明渡が必要だが借主が退去を拒否している場合
通常、借地借家法で守られている借主を裁判を経ずに強制退去させることができるため、建物明渡断行の仮処分が認められるケースは非常にまれです。
建物明渡断行の仮処分を遂行したい場合は、その仮処分を遂行するための証拠が必要になります。



大家1人ではその証拠集めは困難なので、専門家に相談するのがおすすめです。
弁護士法人アクロピースにでは、初回60分間の相談を無料で行っています。
建物明渡断行の仮処分を遂行など、あなたにとって最善の解決方法を提案いたします。
お気軽にご相談ください。
\初回60分間の相談は無料!/
【無料相談受付中】24時間365日対応
強制退去させるときの注意点


家賃滞納や騒音トラブルなど、迷惑行為をする借主を大家が強制退去させるときに注意すべき点が3つあります。
強制退去の手続きを謝ると、大家が罪に問われたりトラブルが大きく拗れて収拾がつかなくなったりする恐れがあるため、強制退去を検討する前に確認しておきましょう。
実力行使をすると大家が罪に問われる
借主が家賃を支払わない、迷惑行為で他の入居者から苦情が出ているからといって、大家が実力行使で追い出そうとすると、罪に問われる恐れがあるため注意が必要です。
たとえば、大家の以下の行動は刑事罰が科される可能性があります。
| 実力行使の内容 | 問われる可能性がある罪 |
|---|---|
| 大家が騒音主の大学生の部屋のカギを勝手に変える | 住居侵入罪 |
| 大家が騒音主の大学生の家財道具を処分する | 窃盗罪・器物損壊・住居侵入罪 |
| 大家が騒音主の大学生の部屋に居座る | 不退去罪 |
大家が再三にわたって、家賃支払いの督促や迷惑行為の注意をしても、借主が聞く耳を持たない場合は、借主に怒りをぶつけず専門家へ相談しましょう。
借主が行方不明になっても強制退去の手続きをする
借主が滞納した家賃を支払わず、行方不明になったとしても大家は法的手順に従い、強制退去の手続きをする必要があります。
借主の承諾なしに部屋に立ち入ったり、家財道具を処分したりすることは実力行使にあたり、大家が刑事罰を科される恐れがあるからです。
借主が行方不明の場合でも、電話や手紙での督促や注意を行い、連帯保証人に連絡を取るところまでは同じです。
ただ、借主が行方不明の場合は「賃貸借契約を解除する」という書面が送付できません。
この場合は「意思表示の公示送達申請」という手段を取ります。
意思表示の公示送達申請は、借主が行方不明で連絡が取れないときに、大家の意思表示を到達させるための手続きです。
内容証明郵便で送付し戻ってきた郵便物など必要書類を持って、裁判所で手続きすると「公示送達」が認められ、手続を進めることができます。
強制退去が執行されるまでには時間がかかる
借主の強制退去が執行されるまでには、大家の予想以上に時間がかかることがあるため、注意が必要です。
令和5年の裁判所の統計データを確認してみましょう。
- 令和5年度におこなわれた不動産の強制執行は5,433件
- 訴状が出されているものの、審理中で強制執行がされていないものが2,786件
- 令和5年時点で強制執行の審理期間が10年以上のものが5件ある



強制執行を裁判所に申し立ててから終結するまでの審理期間は1年以内がほとんどですが、中には10年以上審理が続いているものもあります。
強制退去にかかる費用は高額になる


強制退去には、法的手続きや引っ越しなどさまざまな費用が必要で、高額になりがちです。
強制退去にかかる費用項目とその相場は、次の通りです。
| 費用項目 | 費用相場 |
|---|---|
| 費用相場 | 1,300円~ |
| 裁判費用 | 2万円~4万円 |
| 強制退去執行費用 | 30万円~50万円 |
| 弁護士に依頼する場合の費用 | 30万円~40万円 |
大家が手続きを1人でおこなう場合でも40万円以上、弁護士に依頼する場合は100万円近く必要になります。
ここからは、強制退去にかかる費用項目をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
内容証明書費用は1,300円~
大家と借主の信頼関係の破綻を証明し「賃貸借契約の解除」を勧告するために必要な内容証明郵便作成費用は、1,300円~になります。
「誰が・誰に・どのような内容の文章を送付したか」を証明する配達証明付内容証明書郵便は、基本の郵便料金に加えて、以下の費用が追加されます。
《配達証明付内容証明郵便の内訳》
- 基本の郵便料金
- 一般書留の郵便料金
- 内容証明の加算量(1枚目480円、2枚目以降290円)
- 配達証明料
たとえば、定形郵便物で内容証明郵便を送付する場合の計算方法は次の通りです。
定形郵便物(25g)84円+一般書留 480円+内容証明郵便 480円+配達証明 350円=1,394円
郵便物の重さや内容証明郵便の枚数が増えるごとに郵便料金は上乗せされます。
裁判費用は2万円~4万円
強制退去をするときに必要な明け渡し訴訟を提起するために必要な費用は、2万円~4万円になります。
その内訳は次の通りです。
《明け渡し訴訟の請求を裁判所でするのに必要な費用》
- 訴状に添付する印紙代(強制退去させる賃貸住宅の固定資産額によって変動 10,000~30,000円)
- 予納郵便切手(約6,000円)
- 大家と借主の信頼関係の破綻の証明となる資料にかかる費用(数千円)
強制退去に必要な明け渡し訴訟を裁判所に提起するときには、訴状に添付する印紙代が必要です。
訴訟に添付する印紙代は、賃貸住宅の固定資産税評価額に応じて手数料が変動します。
その他にも強制退去に必要な証拠となる資料(建物の登記事項証明書など)の取り寄せに数千円かかります。
強制退去執行費用は30万円~50万円
裁判所で明け渡し訴訟を請求し、勝訴した後にかかる強制退去執行費用の相場は30万〜50万円にもなります。
その内訳は次の通りです。
《強制退去執行にかかる費用》
- 執行官への予納金の基本額:65,000円(物件や相手方が増すごとに25,000円を加算)
- 解錠技術者費用:1回 2万円~5万円
- 借主の家財道具の搬出費用:数万円~100万円
- 廃棄処分費用:数万円~10万円
借主の家財道具の搬出費用や廃棄処分費用は、一般の引っ越し代の3倍程度の費用がかかります。
借主の強制退去執行にかかる費用は、大家負担になるため、大家は万が一のトラブルのため日頃から積立金や保険に加入しておくといざというときに慌てずに済むでしょう。
弁護士費用に依頼する場合は30万円~50万円
弁護士に強制退去の手続きを依頼する場合、上記3つの費用にさらに30~50万円が追加されます。
強制退去にかかる弁護士費用の内訳は次の通りです。
| 費用項目 | 費用 |
|---|---|
| 相談料 | 初回は無料もしくは30分あたり5,500円~ |
| 着手金 | 10万円~20万円 |
| 報酬金 | 30万円~ |
上記の料金はあくまでも目安の費用です。



弁護士事務所によって、着手金と報酬金は大きく異なるため依頼前に弁護士事務所に確認しましょう。
強制退去にかかる費用をできるだけ抑える方法


強制退去にかかる費用は、高額で大家が自力で裁判手続きをしたとしても40万円~、弁護士に依頼すると100万円近くの費用がかかります。
1回の強制退去でこれだけの費用がかかると、賃貸物件の経営にも大きな影響が出てしまうでしょう。
強制退去にかかる費用をできるだけ抑える方法は、次の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
強制退去にかかる費用を借主に請求する
強制退去にかかる費用は、民事執行法第42条に基づき、借主に請求することができます。
民事執行法第42条
強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
しかし、借主に支払い能力や差し押さえ可能な家財道具がない場合、費用を回収できないこともあります。
強制退去にかかる費用は「必ず借主に支払ってもらえる」とは限りません。
借主に立ち退き料を支払い任意退去してもらう
強制退去にかかる費用を抑えるため、大家が立ち退き料を支払い任意退去してもらうことも検討しましょう。
法的手続きを経て強制退去させるまでには1年ほどかかり、さらに強制退去執行には高額な費用がかかるためです。
立ち退き料を支払い任意退去させることができれば、退去までの期間を大幅に短縮でき、費用も借主の引っ越し費用のみで済むため、強制執行にかかる費用より安く済むでしょう。
しかしながら、任意退去させる場合、借主とよく話し合い契約を交わさないと立ち退き料のみ取られて借主が退去しない事態になる可能性もあります。



このような事態にならないよう、弁護士など専門家に相談してから借主と任意での退去に向けて話を進めていくとよいでしょう。
立ち退き料の相場やスムーズに交渉する方法は以下の記事からご確認ください。
まとめ


借主の強制退去はすぐにできるものではなく、大家の労力と時間がかかるため、可能な限り借主と話し合い、トラブルの改善や家賃の督促を行う必要があります。
大家が再三注意をしても、借主がトラブルの改善や家賃の支払いに応じない場合は、強制退去の検討が必要です。
- 借主を強制退去させるには法的手続きが必要
- 強制退去をするには約100万円近い費用が必要
- 借主を強制退去させるには約1年近くかかる
- 強制退去にかかる費用は借主に請求できるが必ず支払ってもらえるとは限らない
強制退去にかかる期間は約1年、さらに100万円近い費用が必要なので大家が法的手続きを取るときは、覚悟して臨まなければならないでしょう。
費用を抑えて早く借主を退去させたい場合は、不動産トラブルに強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
強制退去の法的手続きはもちろんのこと、強制退去を避け借主を任意退去させるための法的アドバイスも行っています。
大家が焦って借主に対し実力行使をしてしまう前に、お早めにご相談ください。
\初回60分間の相談は無料!/
【無料相談受付中】24時間365日対応