【無料相談受付中】24時間365日対応
親子共有名義の不動産は親が死亡したらどうなる?相続手続きや相続税を解説
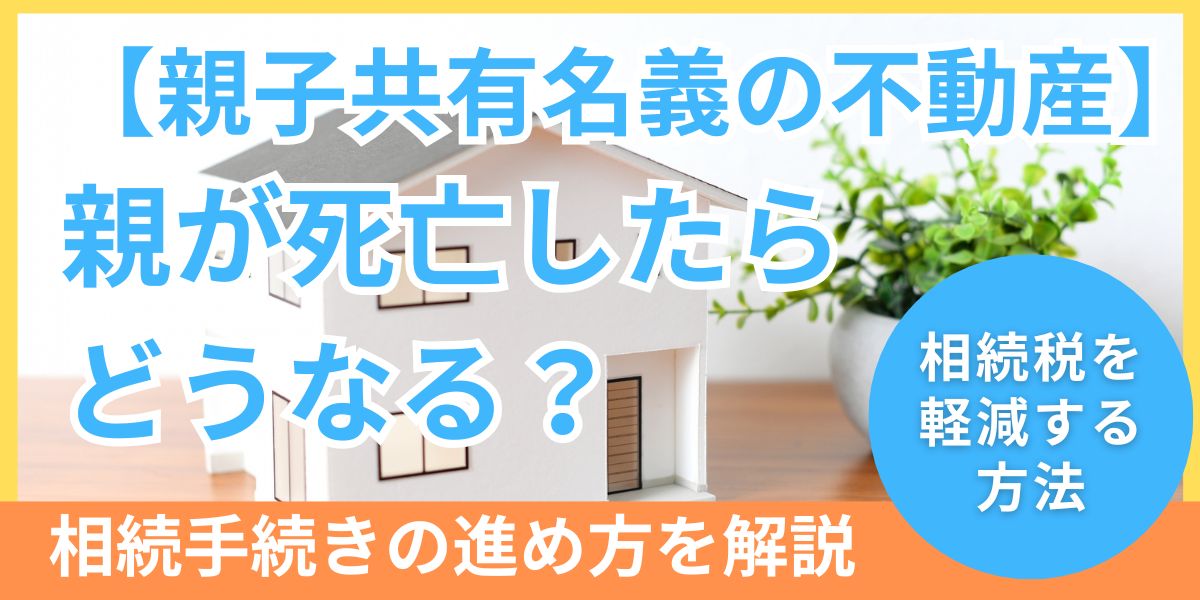
親子共有名義で不動産を購入したが親が死亡した場合、共有名義の不動産や相続税はどうなるか心配という方もいるでしょう。
- 親の持分は親が死亡したら自分のものになるのか
- 相続手続きや相続税はどうなるのか
親子共有名義で取得した不動産の親の共有持分は、遺言がなければ原則共同相続人の共有になります。
親が死亡したときは、他の相続財産と同じく、遺産分割協議で分割方法を決めなければなりません。
親子共有名義の不動産の名義変更を含む相続手続きや相続税について解説しているので、親子共有名義の不動産の相続で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
親子共有名義の財産は親が死亡した場合どうなる

死亡した親が有していた共有持分は、原則として相続財産となり相続人が共同で相続します。
共有者である子は、親の相続人として親の共有持分を相続できますが、他に兄弟姉妹がいる場合や親の配偶者が生存している場合は、兄弟姉妹や配偶者も相続人となるのです。
共有者である子が、持分を優先的に相続できるわけではなく、他の相続人との間で遺産分割が必要になります。
たとえば、親の配偶者はすでに死去しており、子が2人いる場合を考えてみましょう。
遺言がない場合、原則、親の持分だった遺産は子が均等に相続することになります。
その場合、遺産分割をめぐって兄弟姉妹に軋轢が生じ、裁判所で争うケースもあり得るでしょう。
関連記事:兄弟での不動産共有名義は危険?起こり得るリスク・解消方法を弁護士が解説
親が死亡したときの親子共有名義の財産の相続手続きの進め方

親子共有名義の相続手続きは、通常の相続手続きと同様です。
以下の順番に確認しましょう。
遺言書の有無の確認
被相続人が死亡した場合、まず被相続人が遺言書を作成していたかどうかの確認が必要です。
遺言書がある場合は、原則として相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されます。
遺言には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言の場合は、公証役場に照会すると、遺言書の有無の確認が可能です。
一方、自筆証書遺言は自宅などにある場合が多いですが、法務局で保管されていることもあります。
法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすれば、保管の有無がわかります。
封印されている自筆証書遺言は勝手に開封することが禁じられており、家庭裁判所で検認の手続きが必要なため注意しましょう。
相続人調査
誰が相続人かを明らかにするために、相続人調査も必須です。
遺言書がない場合、相続人が複数いれば遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議は相続人全員の参加・合意が必要です。
そのため、相続人を正確に調査し特定しなければなりません。
相続人調査は、故人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得して、相続人の範囲・順位を確認するものです。
相続財産調査
相続人調査と並行して相続財産の調査も行わなければなりません。
遺産分割協議で被相続人の遺産を分けるために、全相続財産を調べる必要があります。
預貯金は金融機関に、不動産は法務局や市区町村役場に照会すれば、相続財産が存在するか確認できるでしょう。
遺産分割協議
相続人調査と相続財産調査が完了すれば、遺産分割協議が可能です。
共有名義の不動産がある場合は、共有名義人である相続人が親の共有持分を相続する例が多いですが、親の共有持分を相続するためには他の相続人の同意が必要です。
共有不動産が主な相続財産の場合、共有名義人である相続人が共有持分を取得したいのであれば、相応の対価(代償金)を支払うことで他の相続人の同意を得て、親の共有持分を相続することもあり得るでしょう。
共有不動産の扱いを始め、遺産分割協議が難航しそうなときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割協議の進め方については、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:相続でもめた場合はどうする?遺産分割協議のスムーズな進め方
相続登記
遺産分割協議が成立した場合、協議内容に従い相続財産を取得する手続きを進めます。
不動産の相続登記・預貯金などの名義変更のときに、相続人全員による、署名及び実印による捺印のある遺産分割協議書が必要になるため、作成しておきましょう。
親子共有名義の不動産は、親の持分の相続人に名義を移転する手続き(相続登記)を行います。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されている(遺産分割成立日から3年以内、不動産登記法76条の2)ので、注意しましょう。
遺産分割の内容が複雑な場合は、不備を避けるため遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼することもおすすめです。
出典:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~|東京法務局
預貯金や不動産の名義変更については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてぜひご覧ください。
関連記事:相続で預貯金の名義変更をするには?期限や株式・不動産の名義変更についても解説
親子共有名義の不動産相続にかかる税金

不動産を相続する場合、相続税などの税金が課される可能性があります。
親子共有名義の不動産相続でかかる税金について、計算例を含めて解説します。
不動産相続でかかる税金
不動産を相続した場合にかかる可能性のある主な税金は、次の通りです。
| 税目 | 概要 | 税率 |
|---|---|---|
| 相続税 | 課税相続財産額が基礎控除を超える場合、 相続税の申告が必要 基礎控除:3000万円+600万円×相続人数 | 10%~55% 法定相続分に対する累進税 |
| 登録免許税 | 名義変更の相続登記時にかかる税金 | 不動産価額の0.4% |
| 譲渡所得税 ・住民税 | 相続した不動産の売却益にかかる税金 譲渡所得税(国税)と住民税(地方税) 被相続人が5年以上保有:長期譲渡所得、5年未満の保有:短期譲渡所得 | ・長期譲渡所得:約20% 国税約15%+地方税5% ・短期譲渡所得:約40% 国税約30%+地方税9% |
出典:No.4155相続税の税額|国税庁
親子共有名義の不動産の相続では親の持分に相続税がかかる
親子の共有名義で不動産を取得していた場合に、親が亡くなったときに相続税が課されるのは、親の持分割合に相当する部分だけです。
不動産を親子共有にしておけば、親が単独名義で所有していた場合よりも相続税が安くなります。
親子共有名義にした結果、相続財産に含まれる不動産価額が減少し、遺産総額が相続税の基礎控除額未満になれば、相続税がかからないケースもあるでしょう。
親子共有名義の場合に親が死亡したときの相続税の計算例
親子共有名義の場合に親が死亡したときの相続税について、モデルケースで計算例を照会します。
ケース
被相続人:父親
相続人:長男のみ
相続財産:共有名義不動産:5,000万円(評価額1億円の1/2、長期保有)
預貯金等:3,000万円
被相続人の相続財産総額:不動産の共有持分5,000万円+預貯金3,000万円=8,000万円
相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×1人=3,600万円
課税遺産総額:8,000万円―3,600万円=4,400万円
相続税の税率:20%(控除額200万円)
相続人である子の相続税額:4,400万円×20%-200万円=680万円
参考:No.4155相続税の税率|国税庁
親子共有名義の不動産にかかる相続税を軽減する方法
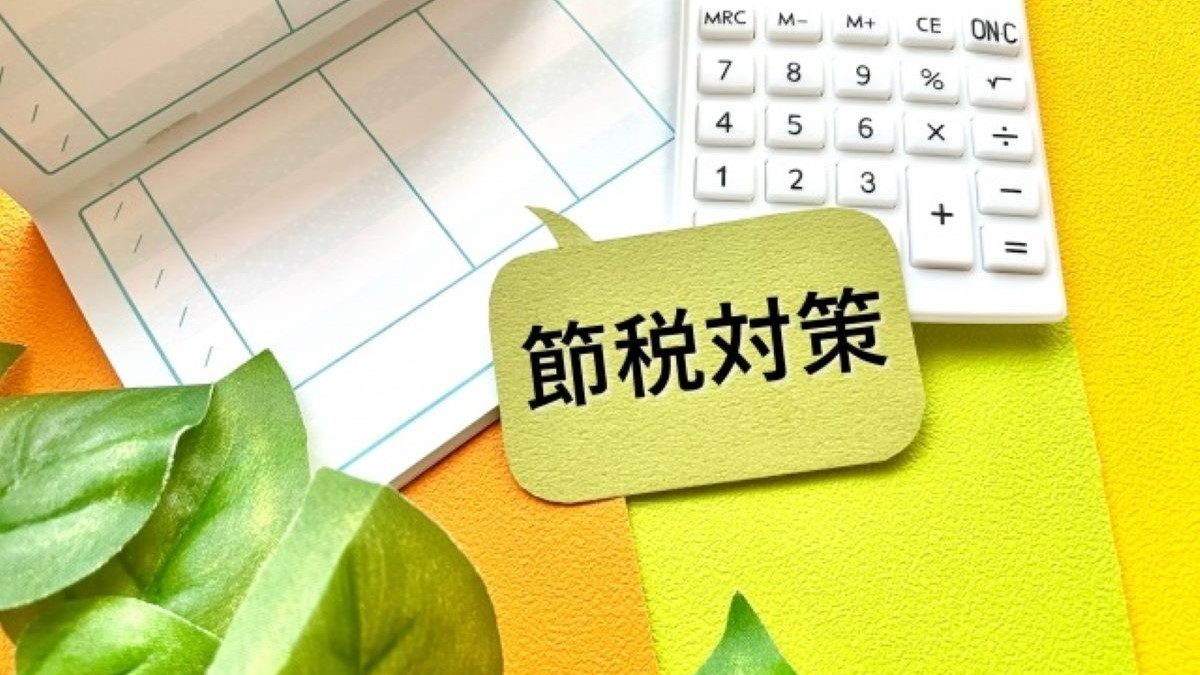
親子共有名義の不動産にかかる相続税を軽減する方法を紹介します。
小規模宅地等の特例を使うことで、相続する不動産が小規模宅地等の特例の適用対象であれば、最大で80%評価額を減額できます。
対象となる宅地と減額割合の例
| 対象となる宅地 | 用途、上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定事業用宅地等 | 自営業の事務所など、400㎡まで | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 賃貸マンションなど、200㎡まで | 50% |
| 特定居住用宅地等 | 戸建ての自宅など、330㎡まで | 80% |
住宅として使用または貸し付けているケースでは、小規模宅地等の特例に該当する場合も多いでしょう。
ただし、減額は土地(分譲マンション等は敷地権)に限られ、住宅価格分は対象外です。
出典:No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有持分の相続時は共有名義を解消する方がよい

共有持分の相続時は、不動産の共有名義をできるだけ解消する方がよいでしょう。
共有持分を法定相続分通りに相続すると、共有者の人数が増えかねません。
共有者が多いと、たとえば、次のようなトラブルがに発展する恐れがあります。
- 相続後に不動産の活用や処分方法をめぐる争いが起きる
- 固定資産税や維持管理費は連帯債務になるが負担をめぐって揉める
- 共有名義を放置すると、子や孫までもがトラブルに巻き込まれかねない
上記のようなトラブルになるリスクを減らすためにも、不動産の共有名義はできるだけ解消した方がいいでしょう。
関連記事:共有名義の解消方法を解説
不動産相続は弁護士に頼るべき4つの理由

相続する財産に不動産が含まれている場合は、弁護士のサポートを検討しましょう。
不動産の相続手続きは非常に複雑である
これまで解説したとおり、不動産の相続は非常に複雑であり揉めるケースも少なくありません。
共有者が多いと不動産の活用方法や管理費負担などをめぐる争い・トラブルが起こるおそれがあるためです。
特に不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人同士で揉めやすいものです。
まして共有持分が絡む不動産の相続は、分割方法や代償金支払いをめぐって紛争になることもよくあります。
このような複雑な問題を相続人だけで解決することは容易ではありません。
しかし、弁護士のサポートを得れば、面倒でミスの許されない手続きも、法的知識と経験を踏まえた迅速な対応により、期限内に確実に処理してもらえるでしょう。
共有不動産の相続について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
生前の相続対策でトラブルを回避できる
不動産の相続は複雑ですが、トラブルを極力回避するため、弁護士の力を借りれば生前に相続対策を講じておくことも可能です。
たとえば、次のような遺言書を作成するなど適切な相続対策を講じておけば、相続人が揉めずに済み、親としても安心できるでしょう。
- 親の共有持分は共有持分を持つ子に相続させる
- 親の共有持分を相続しない他の相続人には、その分多くの預貯金等を相続させる
- 2が困難な場合、親の共有持分を相続する子は他の相続人に相応の代償金を支払う
弁護士であれば、当事者の意向を踏まえて、無効とされるリスクのない遺言書を作成できます。
共有不動産の共有者以外の相続人の遺留分にも配慮した適切な内容で作成できるので、相続が発生しても、共有持分の扱いや遺留分に関する争いを回避しやすくなるでしょう。
相続手続きをスムーズに進められる
弁護士に依頼すれば、相続手続きをスムーズに進められます。
相続手続きは初めての方には難しく、何から手を付けてよいかわからないまま、時間がすぐに経過することも珍しくありません。
しかし、相続手続きには申告期限があるものも多く、相続開始後すぐに準備を始めて手続きを進めていく必要があります。
相続人は、相続が起こると、行政機関への届出・金融機関への連絡などやるべきことが多々あり精神的負担も大きいでしょう。
相続開始後に相続人がしなければいけない手続きの例
- 被相続人の死亡届(7日以内)
- 国民健康保険・国民年金関係の届出等(14日以内)
- 相続放棄の申立(3か月以内)
- 所得税の準確定申告(4か月以内)
- 相続税の申告・納付(10か月以内)
- 相続登記(3年以内)
そのため、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議などの煩雑で難しい相続関係調査や相続手続きは、弁護士に依頼した方がメリットが大きいでしょう。
弁護士ならワンストップで解決できる
弁護士に頼めば複雑で難しい共有不動産の相続問題もワンストップで解決できます。
通常の相続であれば、司法書士や税理士に依頼することで済む場合もありますが、
共有名義の不動産の相続は複雑な法律問題が絡むため、司法書士や税理士だけでは対応が難しいケースも少なくありません。
弁護士であれば、これらの問題を含む相続問題にワンストップで迅速に対応し、解決できます。
また、弁護士と司法書士は、法律上扱うことができる業務範囲が次のように異なります。
| 弁護士 | 法律や裁判のスペシャリスト 相続人調査・遺産調査 遺産分割協議の調整、遺産分割調停・審判の代理 相続税の申告 その他幅広い相談・依頼を受けられる |
|---|---|
| 司法書士 | 登記の専門家 法律問題について有料で相談を受けることはできない 代理人として交渉・裁判を行うことも原則不可 遺産分割協議の調整や遺産分割調停・審判の代理、相続税の申告はできない |
弁護士にしかできない業務は多々あります。簡単そうに見えることでも、重大な法律問題になる場合もあるため、相続手続きはまず弁護士に相談しましょう。
弁護士と司法書士の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:遺産相続は弁護士と司法書士のどっちに相談する?行政書士との業務内容の違いも解説
まとめ
親子共有名義の不動産について、親が死亡した場合の相続手続きや相続税についてまとめます。
- 共有者である子が親の共有持分を優先的に相続できるわけではない
- 他の相続人との間で遺産分割が必要
- 親の共有持分の相続手続きは通常の相続手続きと同様、遺言書の有無の確認、相続人・遺産の調査、遺産分割協議、相続登記などが必要
- 親の共有持分を相続する場合は親の持分に相続税・登録免許税などがかかる
- 売る場合は譲渡所得税・住民税が課される可能性がある
- 親の共有持分にかかる相続税を軽減するには、小規模宅地等の特例を使うなどの方法がある
- 共有者が多いと不動産の活用や処分・管理費負担をめぐって揉める
- 子や孫までもがトラブルに巻き込まれかねないため、相続時に共有名義を解消する方がよい
- 不動産の相続を弁護士に依頼すべき理由は、相続手続きが複雑・生前の相続対策でトラブル回避できる
- 相続手続きをスムーズに進められる・ワンストップで解決できる
親子共有名義の不動産の相続手続きや相続族税の申告は、複雑で手間もかかるため、弁護士法人アクロピースまでお気軽にご相談ください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









