【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義の不動産売却はトラブルに要注意!回避策とスムーズに売る方法
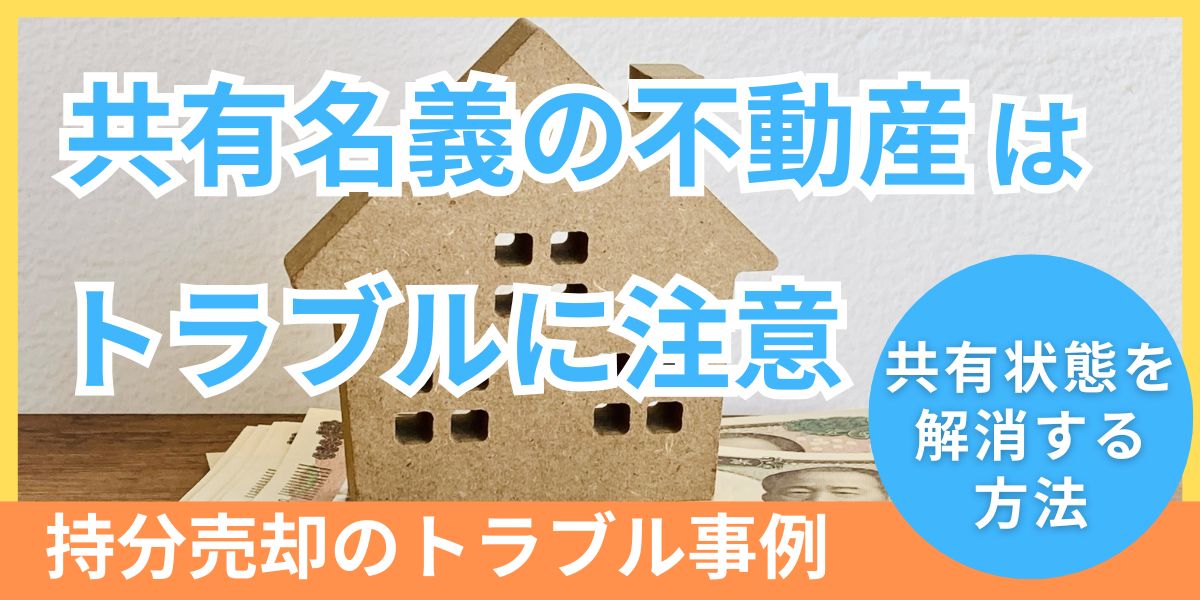
共有名義の不動産売却は、トラブルが起こりやすい状況にあります。
「共有者間で意見が合わず売却が進まない」
「価格交渉が難航する」
「一部の共有者が行方不明で手続きが滞る」
また、共有不動産を放置すると、相続が発生するたびに持分が細分化され、ますます売却の合意が困難になってしまいます。
しかし、早急に適切な対策を講じれば、共有名義の不動産売却をスムーズに進められ、共有状態を解消できるでしょう。
本記事では、共有名義の不動産売却トラブルを防ぐ、具体的な対策を解説します。
共有名義の不動産が引き起こした「トラブル事例」も紹介していますので、最後までお読みください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義の不動産を持っているだけで起こる問題

共有名義の不動産を持っていると、共有者同士が活用方法で意見が衝突するなど、揉めごとが発生するリスクが高まります。
共有名義の不動産によって起こりうる主なトラブルは、以下の通りです。
不動産の活用方針で共有者間の意見が割れやすい
共有名義の不動産は、活用や処分について共有者間の意見が一致しないと、適切な運用が困難になるケースがあります。
共有不動産に関する行為は、以下のように区分され、それぞれ必要な同意の程度が異なります。
| 行為 | 内容 | 同意の程度 |
| 保存行為 | 共有物の修繕・不法占拠者への明渡請求 | 各共有者単独で対応可能 |
| 管理行為 | 共有物を賃貸するなど | 共有者の持分価格の過半数の同意が必要 |
| 軽微な変更行為 | 外壁や屋根などの修繕 | 共有者の持分価格の過半数の同意が必要 |
| 軽微でない変更行為 | 共有物の売却・増改築など | 共有者全員の同意が必要 |
共有名義の不動産は、管理や変更行為の内容に応じて、共有者の同意が必要です。
意見の取りまとめが困難な場合には、売却の機会を逃したり、適切な維持管理ができなくなったりするリスクがあります。
相続のたびに共有者が増え権利関係が複雑化する
共有名義の不動産は、共有者の死亡により持分が相続人に引き継がれるため、権利関係が複雑化し適切な活用に支障をきたす恐れがあります。
相続人には子どもだけでなく配偶者も含まれるため、共有者が離婚や再婚していた場合、面識のない人が新たな共有者となる可能性があるのです。
共有者が増えるほど、売却時の合意形成に手間がかかり、管理や売却をより困難にします。
所有しているだけで固定資産税がかかる
共有名義の不動産は、利用の有無にかかわらず固定資産税が発生します。
民法第253条第1項により、共有者は持分割合に応じて固定資産税を支払う義務を負います。
以下は、親から相続した空き家を兄弟3人で共有している場合の、固定資産税の負担をめぐって発生したトラブル事例です。
| 空き家には誰も住んでおらず、賃貸にも出していないため収益を生んでいません。しかし、毎年、固定資産税の納税通知書が、代表者である長男宛に送付されます。本来は3人が持分割合に応じて固定資産税を負担すべきですが、納税通知書が代表者である長男宛に届くため、長男が全額を支払う状況が続いています。長男は他の兄弟に対し、持分割合に相当する負担を求めましたが、支払いに応じないためトラブルとなり、兄弟関係が悪化しました。 |
共有不動産は、利用の有無にかかわらず固定資産税の支払い義務があるだけでなく、共有者間の負担調整がうまくいかない場合は、トラブルに発展する可能性もあります。
関連記事:兄弟での不動産共有名義について解説
共有名義の不動産を売却する際に発生しやすいトラブル
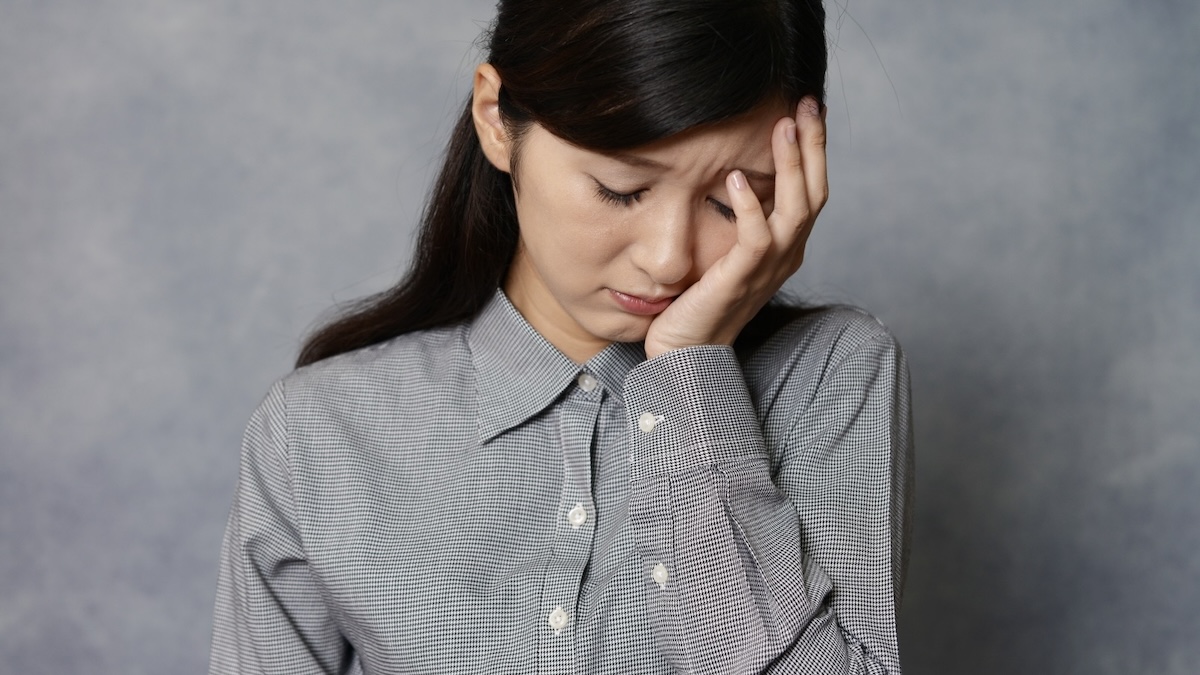
共有名義の不動産を売却する際、共有者間での意見の対立や手続きの複雑さが原因で、売却が滞るケースがあります。
共有名義の不動産売却でよくあるトラブルは、次の通りです。
共有者全員の同意が得られない
共有不動産の全体の売却は、民法第251条1項の規定により、共有者全員の同意が必要です。
つまり、共有名義の不動産は、一人でも反対する共有者がいると、売却手続きが進められません。
また、共有名義の不動産売却は合意形成が長引くと、市場の変化による価値の下落や買い手の減少などで、当初想定していた価格で売却できなくなるという危険性をはらんでいます。
共有名義の不動産は、売却に共有者全員の同意を取り付けなければいけないため、売却が思うように進まないこともあるでしょう。
売却価格で折り合いがつかない
共有者間で売却価格の折り合いがつかないと手続きが進まず、資産を適切なタイミングで処分できないリスクが生じます。
共有不動産の売却には、全共有者の同意が必要となるため、価格に関する合意が得られなければ売却自体が進みません。
その結果、市場環境の変化に対応できず、本来得られるはずの売却益を逃す可能性があります。
一部の共有者が行方不明で交渉が進まない
共有名義の不動産は、共有者の中に行方不明者がいると、全員の合意が得られないため売却できません。
このような場合、裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てて売却する方法があります。
ただし、不在者財産管理人の選任の申立てには、行方不明者の所在不明を証明する必要があり、手続きには時間と費用がかかるなど、迅速な売却の妨げになっています。
共有状態が長引き、持分が細分化されるほど、連絡が取れない共有者が発生するリスクが高まるため、できるだけ早期に共有状態の解消を図りましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の売却方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
関連記事:【共有不動産を売却する方法】同意が必要なケース・売却に必要な書類・費用
共有名義の不動産の持分売却で起こったトラブル事例

共有名義の不動産の持分売却は、他の共有者との関係悪化や思わぬ問題が生じるなど、トラブルの原因になっています。
以下に挙げるのは、実際に起こった持分売却で発生したトラブルの事例です。
事例1.持分を買い取った会社からしつこい営業を受けた
買取専門会社に持分を単独で売却しました。
その後、持分を買い取った会社は、他の共有者にも売却を促す営業を執拗に行いトラブルになってしまったのです。
買取専門会社は、共有不動産を単独所有にするために強引な交渉を続け、その結果、他の共有者は強い心理的ストレスを受けてしまいました。
買取専門会社は、市場価格よりも低い価格で、他の共有者から持分を買い取ろうとすることもあります。
持分を単独で買取専門会社に売却してしまった人が、他の共有者から恨まれてしまい、人間関係が悪化するケースも少なくありません。
共有名義の不動産を買取会社へ売却したときのトラブルについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【共有持分買取業者への売却】起こりうる6つのトラブル・トラブル回避法
事例2.共有不動産に住む他の共有者に持分の買取を依頼したが、売却価格で揉めてしまった
親族と土地や建物を共有しています。
固定資産税などの維持費を支払っているものの、共有者である親族が居住しており、自分は全く利用できない状況が続いていました。
そこで、親族に持分の買取を依頼したところ、市場価格よりもはるかに低い金額を提示され、交渉が難航してしまったのです。
最終的に親族との関係が悪化し、対立が深まってしまいました。
このままでは不公平な状況が続いてしまうため、弁護士に適正価格の査定を依頼し、公平な価格での売却交渉を進めてもらう必要があります。
事例3.共有物分割請求訴訟を起こされた
共有名義の不動産をめぐり、他の共有者から共有物分割請求訴訟を提起され不安を感じてしまい、どのように対処すべきか困惑しました。
訴訟の結果、裁判所の判決により不動産の共有状態を解消する方法が決定され、換価分割(不動産を売却し、売却代金を共有者間で分配する方法)が採用されました。
共有物分割請求訴訟は、裁判所の判断によって「換価分割」「現物分割」「代償分割」のいずれかが決定されます。
共有者から共有物分割請求訴訟を提起された場合、早期に弁護士へ相談し、適切な対策を講じる必要があります。
法律事務所の中には、相談料や着手金無料のところもあるため、積極的に活用するとよいでしょう。
共有名義の不動産を買取会社へ売却したときのトラブルについては、以下の記事をご覧ください。
共有持分買取業者への売却トラブル回避法!持分現金化は弁護士に相談すべき理由
不動産の共有状態を解決する方法
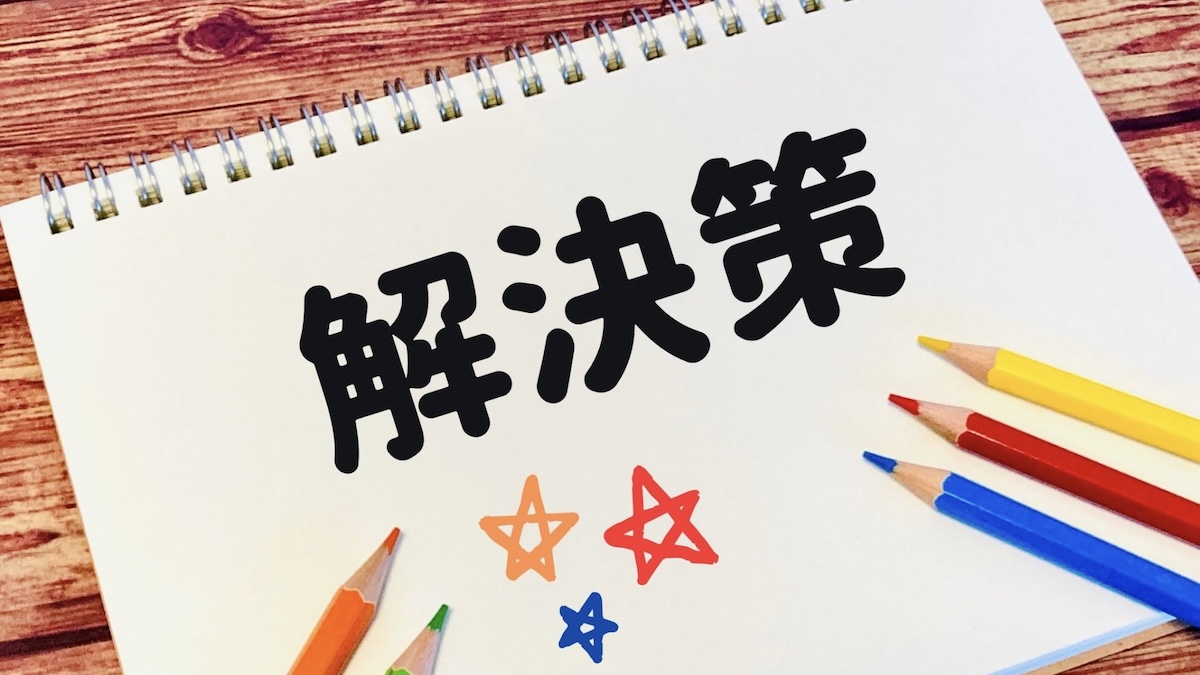
共有名義の不動産は、売却や持分の扱いをめぐる課題が発生しやすいため、適切な方法による共有状態の解消がトラブル回避につながります。
共有不動産の問題を円満に解決する主な方法は、以下の通りです。
関連記事:共有名義の解消方法とは?手続きについてもわかりやすく解説
共有者全員の合意を得て不動産全体を売却する
共有名義の不動産の解決策として、共有者全員の合意を得て、不動産全体を第三者へ売却する方法があります。
不動産全体を売却するメリットは、市場価格で売却できる可能性が高い点です。
個別に持分を売却する場合、流動性の低さから時価よりも安い価格でしか買い手がつかないケースが多いですが、不動産全体を売却すれば、市場価格での取引が期待できます。
関連記事:共有名義のマンションを売却するには?売却方法や費用・注意点を弁護士が解説
共有名義の不動産が土地であれば分筆も検討する
共有名義の不動産が土地のみであれば、分筆により、共有状態を解消する方法があります。
登記簿上の一つの土地を複数の区画に分け、それぞれを独立して登記する手続きです。
共有名義の土地を分筆できれば、各共有者が単独名義で所有できるため、売却や活用の自由度が高まります。
ただし、分筆には一定の条件があり、すべての土地で実施できるわけではありません。
分筆するには、土地の面積が十分に広いことに加え、接道条件や形状、高低差などの要件を満たす必要があります。
これらの要件をクリアできないと分筆は認められず、共有状態を解消できないのです。
他の共有者が売却や買取に応じないなら共有物分割請求訴訟を提起する
共有物分割請求権は、共有者であれば行使できる権利です。
話し合いによる解決が難しい場合、共有物分割請求の調停申立てや訴訟の提起によって、裁判所に分割方法を決定してもらいます。
裁判所の判断により「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかの方法が選ばれます。
競売による換価分割が命じられた場合でも、単独で持分を処分するよりも高値で売却できるケースが多く、共有者にとってメリットが大きい場合があるのです。
共有物分割請求は法律の専門知識が必要なため、弁護士に相談してください。
共有物分割請求について詳しく知りたい人は、こちらの記事をお読みください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有物分割請求の種類・共有物分割請求訴訟の判決
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット

共有不動産の解消には共有物分割請求が有効であり、この権利を行使する際は、弁護士への依頼が賢明です。
共有名義の不動産は、共有者全員の合意が得られないと売却ができませんが、共有物分割請求を行えば、裁判所の判断により共有状態を解消できる可能性があります。
共有物分割請求を弁護士に依頼するメリットは、次の通りです。
弁護士が代理人として交渉するため、直接の対立を避けられる
弁護士に代理人を依頼すれば、スムーズに共有物分割請求の交渉が進められます。
共有物分割請求の相手は親族の可能性が高く、身近な関係だからこそ話し合いが感情的になり、交渉が難航する場合があるのです。
弁護士は、法律に基づいた客観的な視点で話し合いを進められるため、当事者同士の直接的な衝突を避け、共有不動産のスムーズな問題解決を図ります。
共有物分割請求の弁護士への依頼は、心理的ストレスの軽減やトラブル拡大の防止につながります。
調停や訴訟に発展した場合でも適切に進められる
共有物分割請求の話し合いがまとまらない場合、調停や訴訟へと進む可能性があります。
このような場合でも弁護士に依頼していれば、引き続き調停や訴訟に対応してくれるのです。
弁護士は裁判所への調停申立てから訴訟の提起まで任せられ、法的な主張を的確に行います。
相手が交渉に応じないときや対立が深刻な場合でも、弁護士のサポートによって迅速かつ適切な解決が期待できます。
市場価格に基づいた適正な価格で売却できる
共有物分割請求を弁護士に依頼すれば、市場価格での売却を目指せます。
共有不動産の適正価格での取引を実現するには、物件の査定が必要です。
弁護士は法的な側面でサポートしながら、必要に応じて不動産鑑定士などの専門家と連携し、市場価格に基づいた売却価格を算定します。
弁護士は他の専門家と協力しながら、依頼者の利益が最大化するように問題を解決します。
共有物分割請求が着手金無料で依頼できる法律事務所がある
共有物分割請求を検討する際、弁護士費用が気になる方も多いでしょう。
そこで、初回の相談料が無料で、着手金も無料のプランを提供する法律事務所の利用を検討してください。
初回相談無料や着手金無料プランを提供する法律事務所なら、初期費用の負担が少なく済むため、安心して問題解決を依頼でき、共有状態の解消が図れます。
共有物分割請求の流れは、次の記事も参考にしてください。
関連記事:【共有物分割請求訴訟の手続きの流れ】訴訟のメリット・デメリット
まとめ|共有名義の不動産問題はトラブルが発生する前に弁護士に相談しよう
共有名義の不動産売却のトラブル事例とそれを避けるための対処法について解説しました。
- 共有不動産の所有には「活用方法の意見の食い違いによる関係悪化」「相続による権利関係の複雑化」「固定資産税の支払い」などのマイナス面がある
- 共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要
- 共有不動産の持分売却で起こるトラブルには、買取のしつこい営業を受けたり、共有物分割請求訴訟を提起されたりなどの事例がある
- 不動産の共有状態を解決する主な方法には「共有者全員の同意を得て、市場価格で売却する」「土地のみなら分筆で単独所有にする」「共有物分割請求により裁判所に分割方法を決定してもらう」などがある
- 相談料・着手金無料の法律事務所なら、初期の負担が少なく済むため費用が心配な人でもためらわず依頼できる
共有名義の不動産は、共有状態が長引くほど共有者が増え同意を取り付ける難易度が上がるため、弁護士に依頼して早急に解決しましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









