【無料相談受付中】24時間365日対応
共有物分割訴訟の期間はどれくらい?手続きの流れや控訴した場合の期間、事前協議・調停・競売まで解説
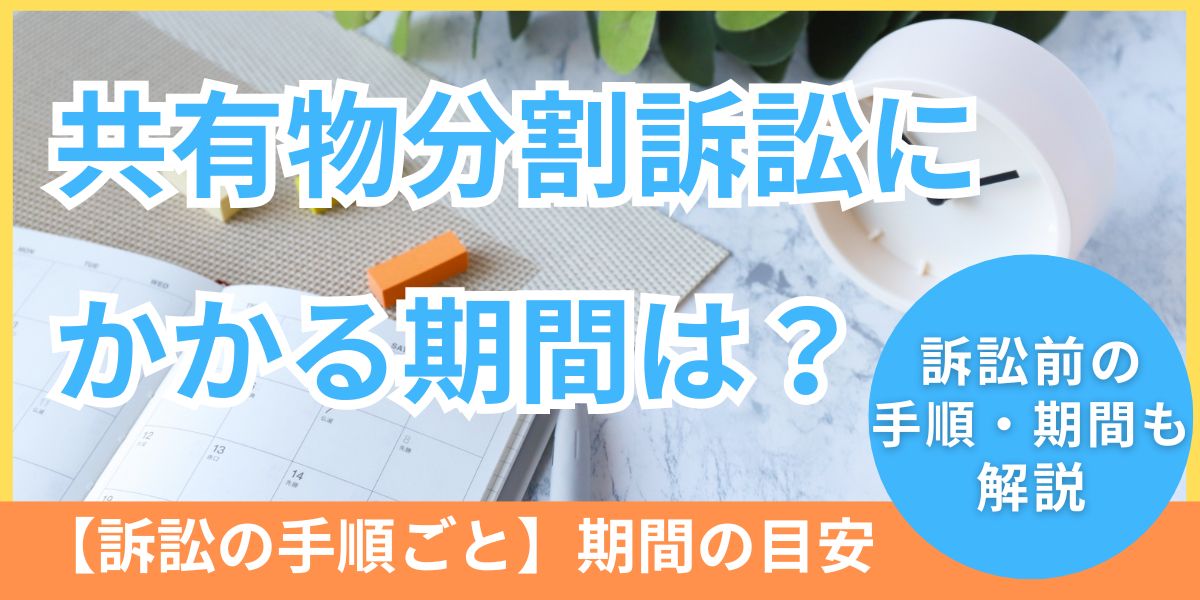
訴訟の経験がない方は、共有物分割訴訟はどれくらい期間がかかるのか、どのように進めればよいのか、気になることでしょう。
共有者はいつでも他の共有者に共有物の分割を請求できますが、分割協議がまとまらなければ訴訟に頼らざるを得ません。
本記事では、共有物分割訴訟について、事前の協議や競売になる場合を含めて、手続きの手順と期間の目安を解説します。
不動産の共有物の分割で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産トラブルに強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\7000件以上の相談実績/
受付時間:24時間365日対応
共有物分割訴訟はどれくらいの期間がかかる?(期間の目安)

共有物分割訴訟にかかる期間が全体としてどのくらいかかるかは、ケースバイケースです。
主なケースごとの平均的な期間の目安は次の通りです。
詳しく説明します。
比較的短期間で解決できるケース:分割訴訟提起~判決まで約半年
単なる共有物分割請求だけの問題であれば、訴状提出から判決が出るまで半年くらいでしょう。
一概には言えませんが、問題となることは、現物分割の可否、取得希望者の有無、和解の可能性などです。
検討すべき課題はそれほど多くはなく、比較的短期間で解決できるケースもあります。
当事者に訴状が送られ初回期日が開かれるまで約1か月、その後、ほぼ1か月に一度のペースで期日が入れられます。
1回の期日で終わることもありますが、2・3回はかかる可能性があるでしょう。
競売になるケース:分割訴訟提起~競売完了まで約8か月~1年程度
競売になるケースでは、共有物分割訴訟の期間を含めると、分割訴訟提起から競売が完了するまで約8か月~1年程度です。
共有物の分割方法は、裁判所の判断で換価分割(共有不動産の全体を売却し、売却利益を持ち分に応じ分け合う)になることがあります。
換価分割になった場合は競売の申立てが必要で、競売が完了するまでさらに約半年の期間が必要です。
共有物分割訴訟の期間と競売期間を合わせると、1年近くになるでしょう。
さらに長期化するケースもある:分割訴訟提起~2年以上
長期化し2年以上かかるケースもあります。
たとえば、途中で新たな相続が発生することがあると、法定相続人を再度調査するために、期間を要することもあるでしょう。
また、遺言書や遺産分割協議書の効力が争われ難航することもあります。
控訴や上告をする場合などは、さらに長期化する可能性もあります。
共有物分割訴訟前の協議の期間

共有物分割請求は、通常まず共有者間で協議や調停を行い、協議が整わなければ裁判所に訴訟提起という手順になります。
共有物分割請求の手順と期間の目途は次の通りです。
共有物分割請求についての詳しい解説は、次の記事をご覧ください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリットを紹介
共有物分割協議:3~4か月程度
まず、事前の協議段階で3~4か月程度かかります。
共有物分割請求は、原則、いきなり裁判所に訴訟を提起することは認められません。
まず共有者間で協議を行う必要があります。
ただし、共有者が最初から分割に反対しており話し合いに応じる姿勢が全く見られないときは、協議不能として直接訴訟を提起することも認められるでしょう。
協議の形式は特に決まりはなく、分割方法も共有者が合意すれば自由に決められます。
ただし、訴訟に備え協議を行った事実を立証できるよう協議申入は内容証明郵便にしましょう。
共有物分割調停:6か月~1年程度
共有物分割調停は6か月~1年程度かかるでしょう。
当事者での話し合いがまとまらない場合、裁判所に調停を申し立てることができます。
共有物分割調停は協議の一環です。
共有分割請求は調停前置主義は採られていないため、調停申立ては必須ではありません。
調停は裁判官と調停委員が共有者の要望を調整する手続きで、協議の場合と同様に共有者全員の参加が必須です。
第三者である裁判官・調停委員が仲介するため、冷静な話し合いを行いやすいでしょう。
ただし、あくまで協議による合意を目指す手続きのため、当事者の歩み寄りが前提です。
共有者全員が裁判所が提示する調停案に同意した場合、調停が成立し調停調書に基づき共有物が分割されます。
関連記事:共有物分割調停とは?手続きの流れ・費用・弁護士の依頼タイミングを徹底解説
共有物分割訴訟:6か月~1年程度
訴訟提起後は第1審で6か月~1年程度の期間がかかる場合が多いでしょう。
共有者間で協議が調わないときは、裁判所に対して共有物分割訴訟を提起できます(民法258条1項)。
共有物分割訴訟には共有者全員が原告又は被告の立場で参加しなければなりません。
共有物分割訴訟は、分割方法の妥当性を証拠を用いて立証するなど、専門的な知識が必要です。
そのため、共有物分割訴訟を数多く取り扱った経験・実績がある弁護士に相談して進める方がよいでしょう。
当事務所アクロピースについては、下記よりご確認いただけます。
共有物分割訴訟の具体的な手順と期間

ここからは、共有物分割訴訟の具体的な手順とおよその期間の目途を解説します。
1.共有物分割訴訟を提起
共有物分割訴訟は、必ずしもその前に調停を申し立てている必要はありません。
協議不調・協議不能の要件に該当すれば、訴訟を提起できます。
訴訟提起準備として、訴状を作成し、証拠や必要書類を揃える必要がありますから、2~3か月程度かかることが多いでしょう。
共有物分割訴訟を提起する場合の必要書類と管轄裁判所は、次の通りです。
| 必要書類 | 訴状の正本・副本 収入印紙・郵券代 証拠書類写し その他、固定資産評価証明書・登記事項証明書など |
|---|---|
| 管轄裁判所 | 次のいずれか(民事訴訟法4条1項、5条12号) いずれかの被告の住所地などを管轄する裁判所 不動産の所在地を管轄する裁判所 |
2.訴状の送達・呼出状の送付(訴訟提起から約1か月後)
共有物分割請求訴訟を裁判所に提起した場合、訴状が被告に対して送達されます(民事訴訟法138条1項)。
特別送達という郵便物です。
訴状には1回口頭弁論期日の呼出状が同封されています(民事訴訟法139条)。
第1回期日は原告と裁判所とで予め決定します。
原告・被告双方は、呼出状に記載された口頭弁論期日に備えて、主張・立証の準備を進めなければなりません。
3.第1回口頭弁論期日(訴訟提起から約1~2か月後)
第1回口頭弁論期日では、原告が提出した訴状と、被告が提出した答弁書の内容を陳述します。
訴訟における主張・立証に当たっては、主張内容を「準備書面」にまとめて裁判所に提出するのが一般的です。
訴訟において主張する事実は、証拠に基づいて立証する必要があります。
4.第2回以降口頭弁論期日(約1か月おきに複数回)
その後、複数回の訴訟期日(口頭弁論や弁論準備手続期日等)において、原告・被告の双方が適切と考える共有物分割方法について主張・立証を行います。
口頭弁論期日等は約1か月おきに開かれるのが通例です。
共有物分割請求訴訟の場合、事案の内容・複雑さにもよりますが、概ね3~6回程度の口頭弁論期日等が実施され、審理終結となります。
5.裁判所による判決(審理終結後2・3か月)
審理終結の2・3か月後に、裁判所が適切と考える共有物の分割案を判決として言い渡します(民事訴訟法251条第1項参照)。
裁判所の判決による分割方法は、次のような種類があります。
- 代償分割:共有者の1人が不動産を単独取得、他の共有者に持分相当の代償金を支払う
- 現物分割:持分割合に応じて物理的に分割する(土地は分筆可能、建物は分割困難)
- 換価分割:競売にかけ落札代金を持分割合によって分配する
代償分割は2023年の民法改正で明文化され(民法258条2項)、同時に共有物の分割方法の検討順序も次のように明文化されました(民法258条3項)。
- 現物分割又は代償分割
- 換価分割
民法258条(裁判による共有物の分割)(1項略)
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
出典:e-Govポータル|民法
判決の言い渡し前に、裁判所が和解を勧めることもあります。
関連記事:土地トラブルは訴訟で解決すべき?費用や期間・手続きの流れを弁護士が徹底解説
6.判決の確定又は控訴(判決受領後2週間以内)・上告
判決に不服がある当事者は、判決書の送達を受けてから2週間以内に、高等裁判所に対して控訴できます(民事訴訟法281条1項、285条)。
また、高等裁判所の判決については、最高裁判所に対して上告の提起及び上告受理申立てを行うことも可能です(民事訴訟法311条1項、318条1項)。
控訴(上告)期間内に不服申立てがない場合は判決が確定し、原告・被告双方に対する法的拘束力が生じます。
その後、確定判決に従って共有物の分割が行われます。
7.共有不動産の競売申立て・配当
共有物分割訴訟で競売命令が出た場合、競売手続を進めるためには、共有物の分割を求める者が、改めて地方裁判所に不動産競売を申し立てる必要があります。
競売による換価分割は、代償分割・現物分割ができない場合の分割方法です。
和解できずに判決まで進んだ場合に実施されます。
- 裁判所の執行官が、対象不動産の「現況調査報告書」を作成
- 不動産鑑定士が対象不動産を鑑定評価し「評価書」を作成
- 裁判所が評価書をもとに不動産の売却基準額を決め、「物件明細書」を作成
- 入札期間と開札期日・売却決定期日を決め、入札・開札
- 最高価格で入札した人が不動産の購入権を得る
- 裁判所は最高価格落札人への売却許可を決定、落札者は定まった代金納付
- 競売により支払われた代金を共有持分割合に応じて分配
共益費用などの支払いを差し引いた残額が共有者に配当されます。
共有物分割訴訟について詳しいことは、次の記事をご覧ください。
関連記事:共有物分割請求訴訟とは?メリット・デメリットなどをわかりやすく解説
共有物分割請求は弁護士に相談を!

共有物分割請求は最終的に訴訟に発展するケースが多いでしょう。
分割方法の選択・主張のため綿密な準備が必要ですが、特に訴訟手続は複雑な手順があるため、専門的な立場からの対応・検討が必要です。
また、訴訟の前段階となる協議も、当事者同士だけでは冷静な話し合いが難しく、合意に至らないことも多いでしょう。
そのため、共有物分割請求は、早い段階から弁護士に相談して対応することをおすすめします。
弁護士は、資料の収集・作成、手続代行など、共有物分割請求の協議・調停・訴訟の各段階で必要な作業を全面的にサポートし、代行することが可能です。
当事務所アクロピースについては、下記よりご確認いただけます。
共有物分割請求については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリットを紹介
まとめ
共有物分割訴訟の期間についてまとめます。
- 分割訴訟の期間はケースバイケース
- 訴訟提起後、提起簡単な場合は判決まで約半年
- 競売になるケースは競売完了まで8か月~約1年、長引くと2年以上かかる場合もある
- 共有物分割訴訟の提起前の手順と期間の目途は、共有物分割協議が1~2か月程度
- 共有物分割調停が6か月~1年程度、その後に共有物分割訴訟となる
- 共有物分割訴訟は訴訟提起後、訴状の送達・呼出状の送付(約1か月後)
- 第1回口頭弁論期日(約1~2か月後、以降約1か月おきに複数回の期日)
- 判決(審理終結後2・3か月)、競売申立て・配当へと進む
- 共有物分割請求は最終的に訴訟になるケースが多い
- 複雑な手順もあり専門的な立場からの対応・検討が必要、早い段階から弁護士に相談して対応すべき
訴訟の経験がない方は共有物分割訴訟はどのように進めるのか、どれくらい期間がかかるのかと不安になるのは当然のことです。
共有不動産の問題で不安や悩みがあるときは、不動産に関するトラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
不動産トラブルに強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\合計7000件以上の相談実績/
受付時間:24時間365日対応









