【無料相談受付中】24時間365日対応
準共有持分とは何なのか?共有持分との違いや分割請求の流れを解説
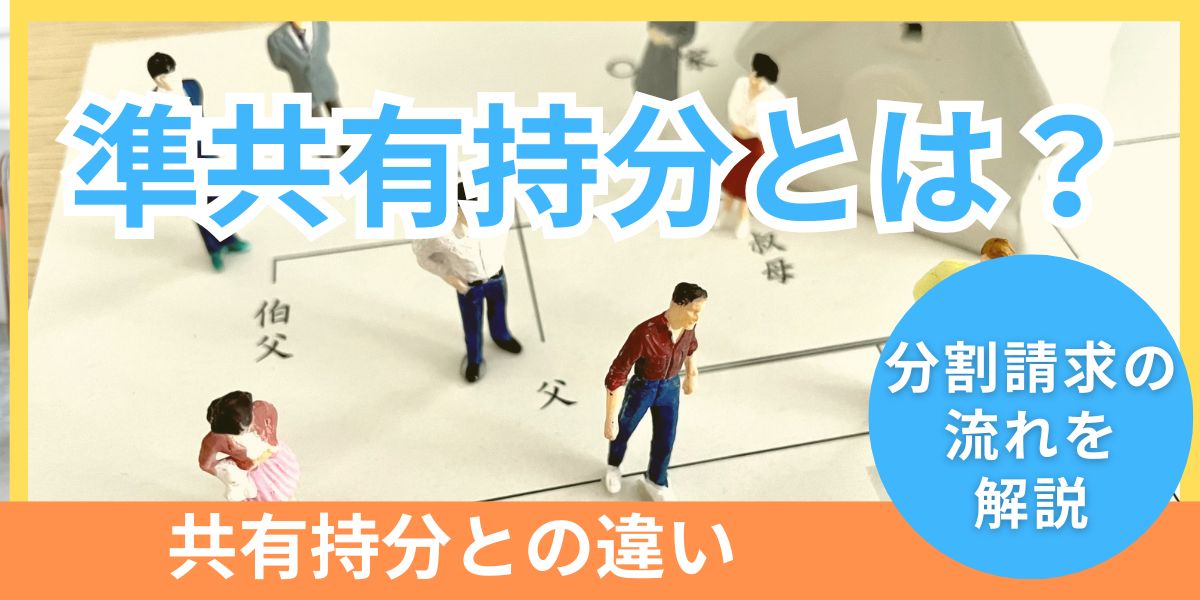
親からの相続で準共有持分を取得した方の中には、次のような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
「準共有持分とは何なのか」
「準共有持分でトラブルを起こしたくない」
準共有持分は共有持分とは違う性質を持っているため、それぞれの違いや法律上のルールを知らなければ、トラブルに発展するおそれがあります。
準共有持分が持つ特徴や分割請求の流れを理解すれば、準共有者間のトラブルを回避できるでしょう。

準共有持分を相続した方や分割請求を検討している方は、この記事を最後まで読んで参考にしてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
準共有持分とは?


準共有持分とは、所有権以外の財産権を複数人で共有している場合の権利の割合です。
通常の共有持分が物の所有権を分け合うのに対し、準共有は権利そのものを分け合うことが特徴です。
準共有が認められる代表的な権利には、借地権や地上権、抵当権などがあります。
たとえば、複数人で借地権を所有している場合、土地の所有者とは別に、借地人たちがその権利を準共有することになります。
準共有も共有と同様、準共有者間でトラブルが起こるケースが多いため、不安がある場合は専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
共有持分と準共有持分の違い
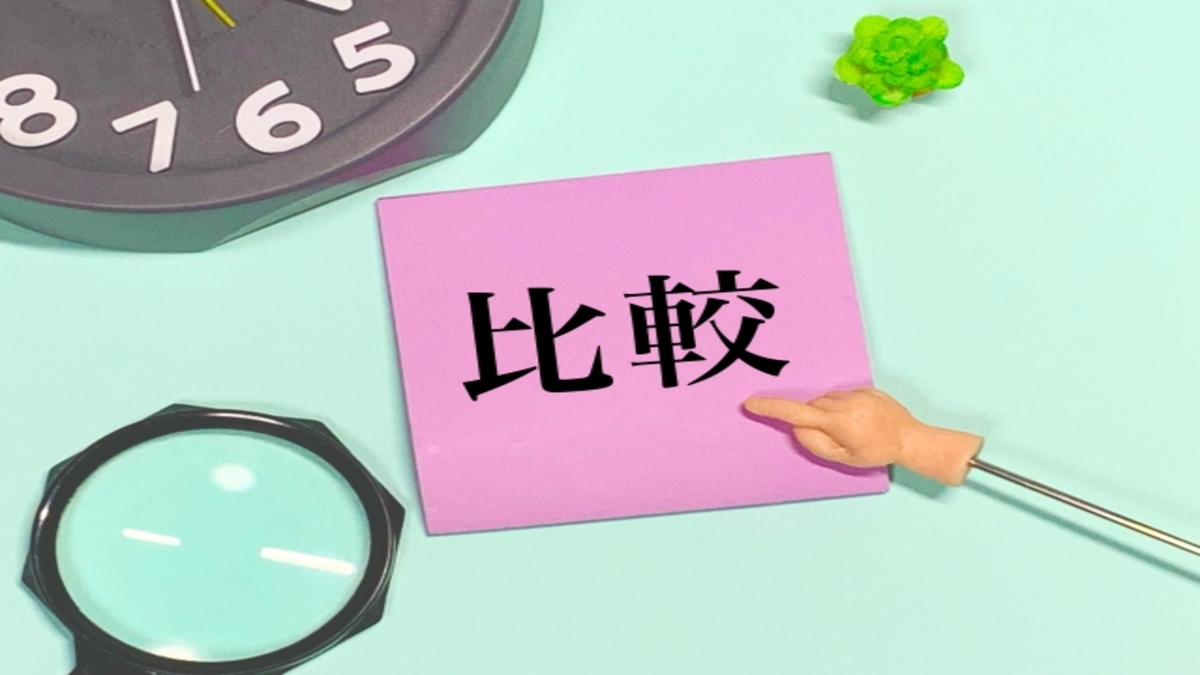
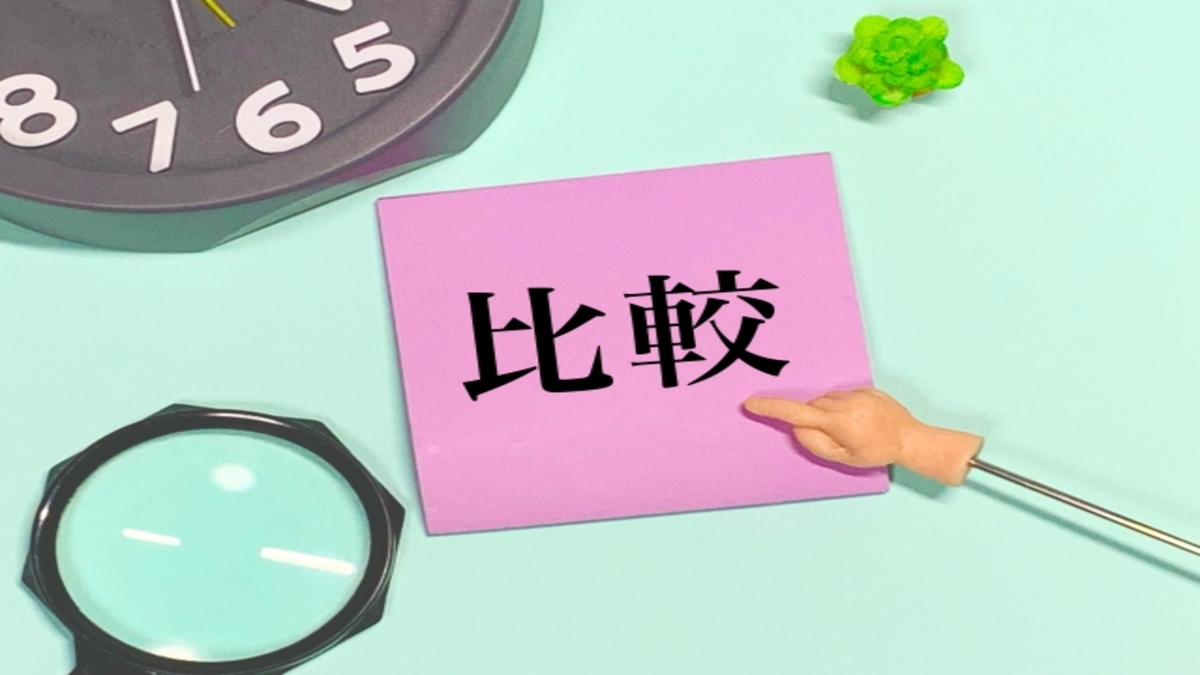
共有持分と準共有持分の違いは、対象となる権利の性質です。
共有持分は、不動産や動産などの物理的に存在するものに対する所有権を複数人で分け合う場合に用いられます。
一方、準共有持分は所有権以外の財産権など、物質が存在しない権利を複数人で所有する際に適用されます。
準共有持分が用いられる主な権利は以下のとおりです。
- 抵当権
- 地上権
- 地役権
- 賃借権
- 特許権
- 著作権
たとえば、不動産を兄弟で相続した場合、その不動産は共有状態となります。
一方、借地権を兄弟で相続した場合は、その借地権が準共有の対象です。
このように、共有は「物」を対象とし、準共有は「権利」を対象とする点が大きな違いです。
ただし、法律上は民法第264条により一部を除き準共有持分にも共有持分と同じ規定が適用されます。
また、民法以外の特別法により、共有持分とは異なる扱いがなされることもありますので、その権利の性質により注意が必要な場合もあります。
共有持分と準共有持分は対象となる権利が違いますが、基本的には同じルールが適用されると理解して良いでしょう。
以下の記事では、共有持分について詳しく解説しています。
気になる方はあわせて参考にしてください。
関連記事:【共有持分とは?】デメリット・トラブル事例と避ける方法
準共有持分に対する法律上のルール


準共有持分に適用される法律上のルールは、基本的に共有持分と同じです。
ここからは、次の4つのルールについて詳しく解説します。
準共有持分を所有している方は、ここで法律上の規制を把握しておきましょう。
準共有物の使用
準共有物の使用は、各準共有者の持分に応じて行えます。
原則、準共有者間の合意によって準共有物の使用方法が決まりますが、合意が得られない場合は持分の価格に従い、その過半数で決定すると考えられています。
ただし、中には法律で使用方法が定められている場合もあるため、使用方法が明確でない場合は弁護士への相談がおすすめです。
準共有物の管理や保存
準共有物の管理は、準共有者それぞれの持分の価格に従い、その過半数で決定されます。
借地の日常的な管理や短期の転貸などが管理行為の代表例です。
一方、保存行為は各準共有者が単独で行えます。
準共有物の保存行為とは準共有物の現状や価値を維持するための行為で、具体的には不法占拠者への明け渡し請求や、大規模な修繕を除いた準共有物の修理や修繕などです。
準共有物の管理や保存にかかる費用は、原則として各準共有者が持分に応じて負担します。
ただし、特別な合意事項がある場合は、その合意に従うことになります。
準共有物の処分や変更
準共有物全体の処分や変更には、原則として準共有者全員の合意が必要です。
準共有物の処分とは準共有物全体の売却や贈与などのことで、準共有物の変更とは準共有物の性質を大きく変える行為のことです。
たとえば、準共有している借地権全体を売却したり、特許権の内容を大きく変えたりするケースが挙げられます。
ただし、準共有物の変更が軽微な場合は、準共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定できることもあります。
具体例としては、準共有している建物の小規模な改装などです。
一方、それぞれが所有している自己の準共有持分については、他の準共有者の合意がなくとも自由に処分できます。
しかし、この場合でも準共有物自体の使用や管理に影響を与えるような処分は行えません。
そのため、所有している準共有持分を処分する際は、他の準共有者の合意が不要とはいえ、適用される法律を慎重に確認しましょう。
準共有持分の相続
準共有持分も、共有持分と同じく相続の対象です。
相続が発生した場合、被相続人の準共有持分は相続人に引き継がれます。
たとえば、借地権を準共有していた親が亡くなった場合、その準共有持分は子どもたちに相続されます。
注意点は、これにより準共有者の数が増加し、権利関係がより複雑になる可能性があることです。
準共有者の数が増えることで、処分や管理などの意思決定が難しくなります。
準共有関係が複雑化したことによるトラブルを避けるためには、遺言や生前贈与などで準共有持分の相続人を限定することや、準共有物全体の売却を検討してみましょう。
共有不動産の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
準共有持分の分割請求の流れ
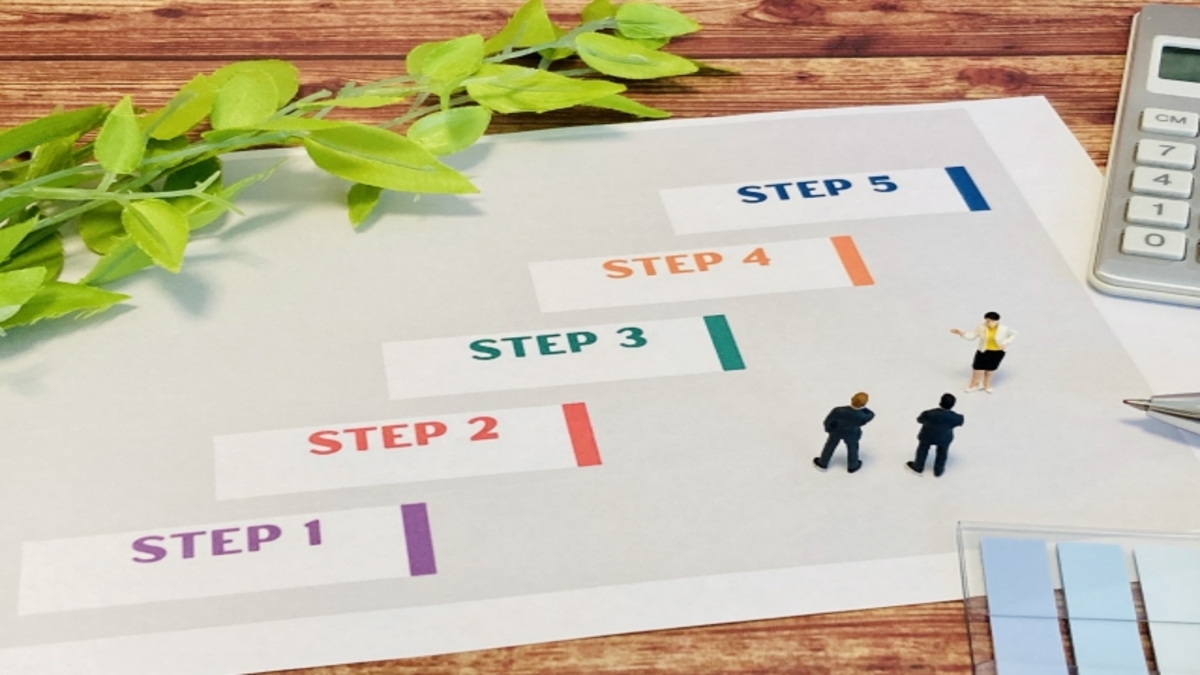
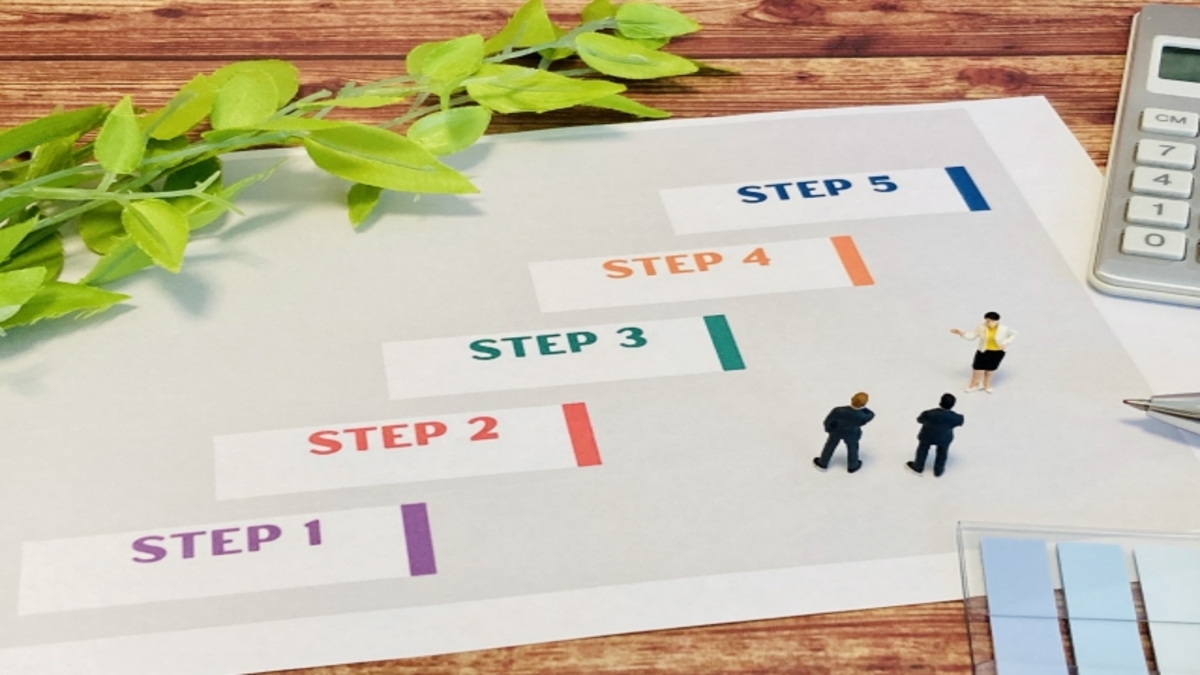
準共有持分のトラブルを避けるための対策として、準共有持分の分割請求が挙げられます。
準共有持分の分割請求とは、準共有状態を解消するための手続きです。
準共有持分の分割請求は次の流れで進みます。
ここからは、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
準共有者間で協議を行う
準共有持分の分割請求は、まず準共有者同士で話し合いを行います。
この段階で合意が得られれば、裁判所を介さずに解決できるため、時間や費用がかからずに済みます。
話し合いがまとまった場合は、内容を明確にするために合意書を作成しておくと安心です。
たとえば、AとBで借地権を準共有している場合、AがBの持分を買い取ることで準共有状態を解消できます。
ただし、それぞれが納得したり意見が対立したりした場合は、協議だけでは解決できません。
準共有者同士が直接話し合うことが難しい場合でも、弁護士が代理で交渉して話がまとまるケースもあります。
準共有物の分割調停を申し立てる
話し合いによる解決ができない場合は、裁判所に準共有物の分割調停を申し立てることも一つでしょう。
調停では、裁判官や調停委員が間に入り、公平な立場から当事者間の意見を調整します。
第三者が間に入ることで、感情的になることを抑え、冷静な話し合いができるでしょう。
ただし、調停はあくまで話し合いの場であるため、最終的な合意には準共有者全員の同意が必要です。
なお、準共有物の分割請求では「調停前置主義」が採用されていないため、調停を経ずに直接訴訟を提起することも可能です。
準共有物の分割請求訴訟を提起する
話し合いで解決できない場合は、準共有物の分割請求訴訟を提起します。
準共有物の分割請求訴訟とは、裁判所があらゆる事情を考慮して最適な分割方法を判断する手続きです。
具体的には「現物分割」「競売による換価分割」「代償分割」などがありますが、準共有の性質や特別法により現物分割ができないこともあります。
たとえば、賃借権や抵当権は現実的に分割することはできないため、他の分割方法が提案されます。
なるべく希望に近い結果を得るためにも、準共有物の分割請求に強い弁護士のサポートを受けながら裁判を進めていくようにしましょう。
共有物分割請求訴訟の手続きは、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はあわせてチェックしてください。
関連記事:【共有物分割請求訴訟の手続きの流れ】訴訟のメリット・デメリット
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
準共有持分の分割請求を弁護士に依頼するメリット3選


準共有持分の分割請求は複雑な法的手続きが必要ですが、弁護士のサポートを受けることで次のメリットが得られます。
準共有持分の分割請求を検討している方は、ここで紹介するメリットを参考にしてください。
法に基づいた最適な解決方法をアドバイスしてもらえる
準共有持分の分割請求を弁護士に相談すれば、法律に基づいた解決方法を助言してもらえます。
準共有持分の分割には「現物分割」「競売による換価分割」「代償分割」の3つがあり状況に応じた方法を選ばなければいけませんが、弁護士のサポートがあれば最適な選択肢が見つかるでしょう。
さらに、弁護士の豊富な経験と知識に基づいて、交渉や裁判になった場合の見通しも立てやすくなります。
これにより、法的に妥当な落としどころを知った上で交渉に臨めるため、スムーズな解決が期待できます。
代理人として対応してもらえる
弁護士に依頼することで、相手方との直接交渉を避けられる点もメリットです。
特に、準共有者間の関係が良好でない場合や、交渉に不慣れな方に向いている方法です。
弁護士が代理人として交渉を行うことで、感情的な対立を避け、客観的な立場から話し合いを進められます。
たとえば、相続で発生した準共有持分の分割では、親族間の感情的なもつれが原因でトラブルに発展することがあります。
この場合、弁護士が間に入ることで冷静な話し合いができるでしょう。
さらに、弁護士は相手方の不当な要求に対して適切に対応するなど、法的知識を活かした交渉ができるため、準共有持分の分割請求を安心して任せられます。
法的手続きのサポートが受けられる
弁護士に依頼すれば、準共有持分の分割請求に必要な法的手続きをサポートしてもらえます。
準共有持分の分割請求に必要な手続きは、主に次のとおりです。
- 調停の申し立て
- 訴訟の提起
- 必要書類の作成・提出
- 手数料の納付
- 裁判所への出頭
ケースによっては、準共有者の中に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人選任申立てや、認知症の準共有者がいる場合の成年後見人選任や特別代理人選任の申立てなども弁護士がサポートしてくれます。
上記の手続きを自力で行おうとすると、膨大な時間と労力がかかるだけでなく、ミスが起こるリスクもあります。
さらに、裁判所とのやり取りも弁護士が担当するため、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えられることもメリットです。
弁護士に準共有持分の分割請求を依頼することで手続きの負担が軽減され、スムーズな問題解決が図れるでしょう。
まとめ|準共有持分に関するトラブルは弁護士への相談がおすすめ
この記事では、準共有持分と共有持分の違いや法律上のルール、準共有持分の分割請求を行う流れについて解説しました。
- 準共有持分とは所有権以外の財産権を複数人で共有している場合の権利の割合のこと
- 準共有が認められる権利には、抵当権や地上権、地役権や賃借権などが挙げられる
- 共有持分は物理的に存在する不動産や動産の所有権を複数人で分け合う場合に用いられる一方、準共有持分は所有権以外の物質が存在しない権利を複数人で所有する場合に適用される
- 準共有物の使用は準共有者の持分に応じて行えるが、管理は過半数の同意が必要であり、準共有物全体の変更や処分には準共有者全員の同意が求められる
- 準共有持分の分割請求は、まず準共有者間で話し合いを行い、協議がまとまらない場合は分割調停・分割請求訴訟の提起へと進む流れで行われる
- 準共有持分の分割請求を弁護士に依頼すれば、法に基づいたアドバイスや法的手続きのサポートが受けられ、代理人として対応してもらえる
準共有持分は実体のないものを共有する分、トラブルに発展しやすい傾向にあります。
これまで関係が良好だった親族とも、準共有持分を相続することで関係が悪化するおそれがあります。
準共有持分によるトラブルを避けるためには、弁護士による準共有持分の分割請求サポートがおすすめです。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









