【無料相談受付中】24時間365日対応
共有物分割訴訟とは?共有状態解消が必要なケースと手続き・費用を解説
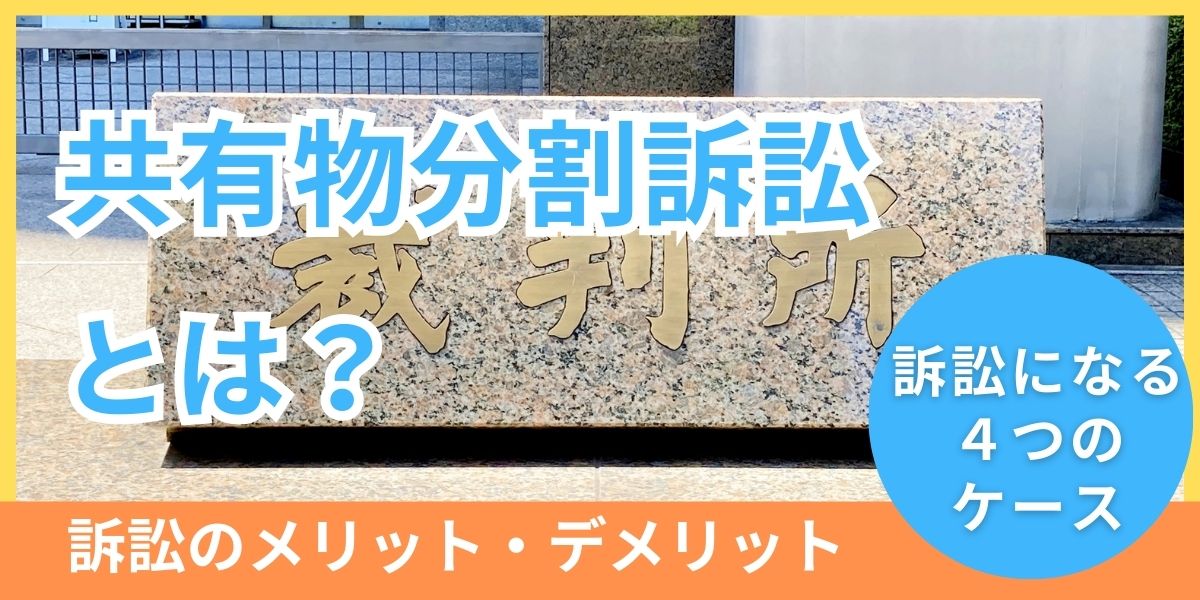
「共有物分割訴訟」とは共有状態にある不動産の分割を求める訴訟です。
しかし、共有物分割訴訟とあまり馴染みがなく、実際にどのような訴訟なのか、条件や手続きがよくわからないため、不安に思う方もいるでしょう。
共有物分割訴訟は判決に強制力があり、共有状態を解消する有効な方法ですが、時間や費用がかかるうえ、共有者との関係悪化などのリスクもあります。
本記事では、共有物分割訴訟とはどのような訴訟なのか、訴訟が必要となるケースと訴訟提起の条件や手続き・費用などをわかりやすく解説します。
不動産の共有状態解消の方法、分割で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産トラブルに強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\7000件以上の相談実績/
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有物分割訴訟とは

共有物分割訴訟とは、裁判所の判決によって不動産の共有状態の解消を図る方法です。
不動産の共有者が共有状態の解消を求める「共有物分割請求」の最後の方法です。
共有名義の不動産は利活用や売却処分などを巡り共有者間で意見がわかれ、トラブルになることがよくあります。
たとえば、不動産全体の売却や建替えは共有者全員の同意がなければできません。
話し合いがまとまらないときは、共有物分割訴訟を起こし、裁判所の判断を求めることになるでしょう。
アクロピースは、依頼者の方の負担を減らし、安心してご依頼いただくために、共有物分割請求を着手金無料でお受けしています。
共有物分割請求については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリットを紹介
共有物分割が必要になるケースとは

共有物の分割が必要になるのは、次のような場合です。
例1:不動産を独占して使用する共有者がいる場合
典型例は、不動産を独占して使用する共有者がいる場合です。
たとえば、兄弟が法定相続分に従って遺産分割し不動産を共有にしたが、使っているのは兄だけという場合です。
自分は管理費を負担させられるだけで、売却や活用のメリットがないと考える弟が、共有物分割請求をすることがあるでしょう。
関連記事:共有不動産の使用貸借とは?認められる要件やリスク・トラブル対処法を弁護士が解説
例2:共同で不動産を購入し共有名義にしていた場合
もう1つの典型例は、共同で不動産を購入し共有名義にして使用していた場合です。
たとえば、夫婦が共同で資金を出して購入した共有名義の不動産の分割問題があります。
離婚して転居することになった夫が、引き続き住む妻に、自分の持分の買取りを求めることもよくあることです。
しかし、妻が応じなければ、夫は共有物分割請求をして共有状態の解消を求めることになるでしょう。
共有物分割訴訟になる主な4つのケース

共有物分割請求が揉めて訴訟になる典型的な4つのケースを紹介します。
1.共有物分割協議に共有者が応じない
他の共有者が分割協議に応じない場合は、最終的に訴訟に訴えざるを得ないでしょう。
共有物分割訴訟では、和解が成立した場合を除き、裁判所が共有物の分割方法を決めることになります。
裁判所の判決には強制力があります。
話し合いに応じなかった共有者も、裁判所の判決で示された方法によって共有状態を解消しなければなりません。
2.共有物分割協議がまとまらない
共有物分割協議で意見がまとまらない場合も同様です。
共有物分割訴訟では最終的に裁判所が分割方法を決定するため、意見がまとまらない状態でも共有状態を強制的に解消できます。
なお、訴訟を起こした後でも、共有者間で話し合い和解すれば、共有状態を解消できます。
3.不動産を独占する共有者がいる場合
不動産を占拠する共有者がいる場合です。
不動産が共有状態の場合、各共有者は不動産全体を使用する権利を持っています。
そのため、不動産を占拠している共有者がいても直ちに追い出せないのが原則です。
そこで、この場合に自己の持分を有効活用するために考えられる方法としては、共有物分割請求訴訟を提起することです。
共有物分割請求訴訟を提起することで、裁判所に共有状態の解消方法を決定してもらえます。
不動産を独占する他の共有者がいる場合で、他の共有者に資力がある場合には、他の共有者に持分を取得させる代わりに代償金を支払わせるという方法で判決が出る可能性が高いでしょう。
または、独占する共有者に対し、賃料相当額について不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられます。
4.不動産を現金化したいが共有者が賛同しない
不動産を現金化したいが、共有者が売却に反対している場合です。
共有物分割訴訟で換価分割の判決が下されれば、共有者の意思に関係なく不動産全体が競売にかけられます。
強制的に現金化できますが、落札価格は相場の5割から7割程度が一般的とされています。
場合によっては、市場価格の3割程度とかなり低くなることもあり、裁判費用や手間がかかる割に手元に残る現金が多くないことに注意が必要です。
なお、自己の持分だけであれば、他の共有者の同意を得なくても単独で売却できます。
共有持分の購入希望者は多くないが、現金化したいのであれば、自己の持分だけを売却することも選択肢になるでしょう。
共有物分割請求訴訟を起こす前提条件

共有物分割請求訴訟を起こすことができる条件があります(民法258条1項)。
次のいずれかに該当する場合です。
- 共有物の分割について共有者間で協議が調わないとき
- 協議ができないとき
つまり、不動産の共有者であっても、いきなり共有物分割訴訟を起こすことは原則できません。
まず共有者間で分割協議を行い、解決できないときは調停、調停が不成立の場合は訴訟という手順になります。
ただし、調停は前置とされておらず、必須ではありません。
また「共有物分割協議」は、物理的に同時に同一場所で行う必要はありません。
電話やメールなどの利用も可能です。
ただし、訴訟を提起する場合、協議が調わない事実を証明する必要があるため、内容証明郵便を送付して証拠を残しておくとよいでしょう。
関連記事:共有物分割調停とは?手続きの流れ・費用・弁護士の依頼タイミングを徹底解説
共有物分割訴訟の判決による3つの分割方法

共有者の協議で分割する場合は全員の合意があればどのような分割方法も可能ですが、共有物分割訴訟の判決による分割方法は、次のいずれかになります。
| 現物分割 (民法258条2項1号) | 共有不動産の現物を持分に応じて物理的に分割し、分割後の不動産を単独名義で所有する |
|---|---|
| 代償分割 (民法258条2項2号) | 共有者が他の共有者の持分を取得し、その分の債務を負担し、他の共有者に持分相当の代償金を支払う |
| 換価分割 (民法258条3項) | 不動産を競売にかけ、落札代金を持分に応じて分配する |
民法の改正(2023年)によって、代償分割ができると法文上明示されました(民法258条2項2号)。
また、共有物の分割方法の選択の優先順序も次のように明確にされています(民法258条3項)。
- 現物分割又は代償分割
- 換価分割
まず現物分割か代償分割を検討し、どちらもできないとき、又は分割によって著しく価格が低下するおそれがあるときに換価分割を選択することになります。
関連記事:現物分割について解説
関連記事:代償分割について解説
関連記事:換価分割について解説
共有物分割訴訟にはメリットとデメリットがある

共有物分割訴訟のメリットは大きいが、デメリットもあります。
| 共有物分割訴訟のメリットとデメリット | |
|---|---|
| メリット | 裁判所に委ねられる:当事者同士の合意が困難な場合も裁判所が法律に則り分割方法を決定してくれる。 |
| 共有状態を解消できる:裁判所の判決によって、共有者の同意が得られない場合も強制的に共有状態を解消できる。 | |
| デメリット | 時間と手間がかかる:訴えの提起から約半年で第1審判決が出るが、控訴されると数年以上かかる。 |
| 費用がかかる:弁護士費用や裁判費用が必要。 | |
| 希望の分割方法になるとは限らない:判決は裁判官の公平な判断に基づき分割方法が決められる。 | |
| 換価分割では配分が少ない:競売の落札代金は低額になることも多く、分配額は少ない可能性がある。 | |
デメリットが大きいと思うのであれば、訴訟を避け、譲り合うか、自分の共有持分だけ売却する方がよい場合もあるでしょう。
共有物分割訴訟について詳しいことは、次の記事をご覧ください。
関連記事:共有物分割請求訴訟とは?メリット・デメリットなどをわかりやすく解説
共有物分割請求の手順

共有物分割請求の手順は、以下の通りです。
| 1.共有者間で協議 | まず当事者で協議を試みる。 訴訟に備え協議申入れは内容証明郵便で行う。 |
|---|---|
| 2.調停申立 | 協議が進まない場合は、調停を申し立てる。 第三者が入った冷静な話し合いになれば、協議がまとまりやすい。 |
| 3.訴訟を提起 | 協議・調停で解決しないときは訴訟を提起する。 協議を行い、不調となれば、2の調停を経ずに訴訟提起も可能。 |
| 4.呼出状の送付 | 訴訟提起から約1か月後に呼出状が送付される。 |
| 5.口頭弁論 | 共有者の主張を審理する。 口頭弁論が複数回行われることもある。 |
| 6.和解又は判決 | 裁判官が判決を下す。 判決前に裁判官の勧告で和解することもある。 和解の場合、双方の主張を反映して解決できるケースも多い。 判決に不服の場合は控訴可能。 |
話し合いで解決できればベストですが、話し合いが難しそうなときは、協議段階から弁護士に相談した方がよいでしょう。
共有物分割請求の手順について詳しいことは、次の記事をご覧ください。
関連記事:共有物分割請求訴訟の手続きの流れ!メリット・デメリットなどをわかりやすく解説
共有物分割訴訟にかかる費用相場
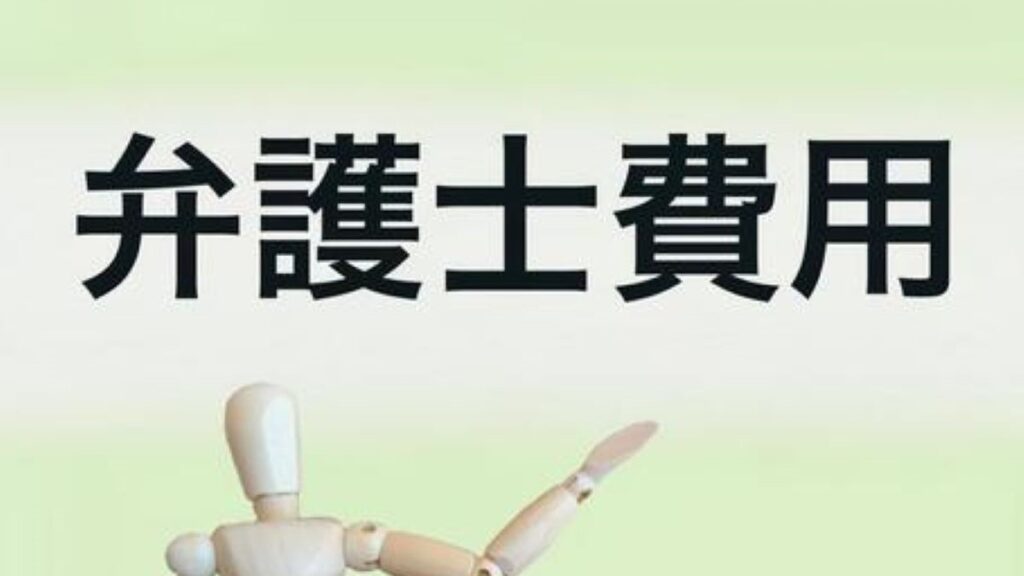
共有物分割請求訴訟に要する費用は、約50~150万円程度が目安になるでしょう。
内訳は、次の通りです。
- 弁護士費用(着手金・報酬金など):約40~60万円
- 訴訟費用(印紙代・切手代など):約5万円
- 不動産鑑定費用(不動産鑑定士による鑑定費用):約20~30万円
当事務所アクロピースについては、下記よりご確認いただけます。
共有物分割請求にかかる弁護士費用について詳しくは、次の記事をご覧ください。
関連記事:共有物分割請求にかかる弁護士費用は?相場や具体例、安く抑える方法を解説
共有物分割訴訟をせずに共有状態を解消する方法もある
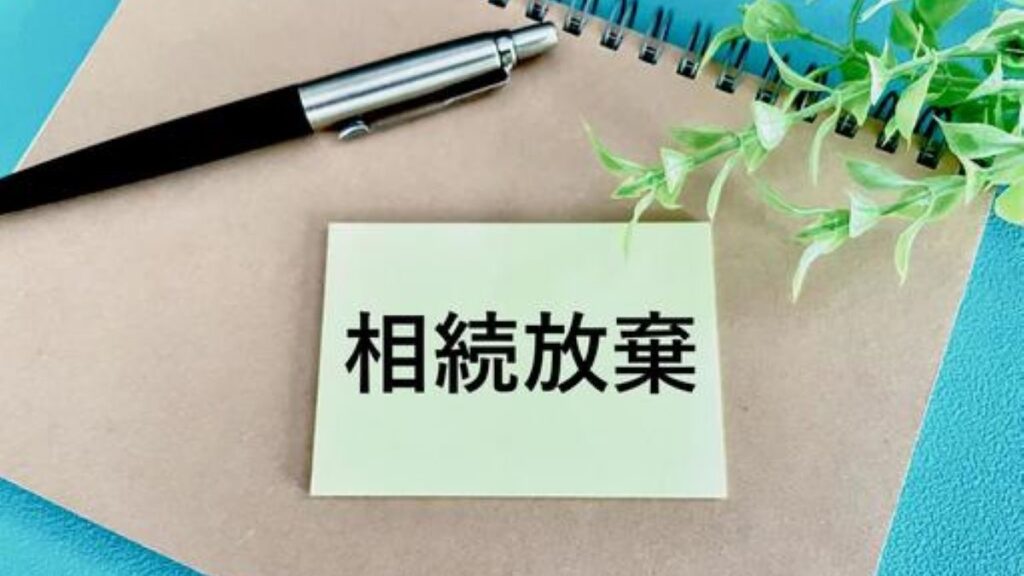
共有物分割訴訟は時間と費用がかかるため、他の方法で共有状態を解消する方がよい場合もあります。
- 【持分の放棄】
-
- 持分を放棄し、他の共有者に権利移転登記すれば、対価は得られませんが共有状態を解消できます。
- 持分放棄によって管理の苦労や固定資産税負担がなくなります。
- ただし、管理の手間や税などの負担がなくなるのはあくまでも放棄が完了した後(原則、権利移転登記後)です。
- 放棄手続完了前に発生した税・費用等の負担義務は残るため注意が必要です。
- 【持分を他の共有者へ売却・贈与】
-
- 共有者に自分の持分を売却するか贈与するのも選択肢になります。
- 贈与は贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
- 【持分を第三者に売却】
-
- 共有者との交渉が難しい場合や迅速な現金化が必要な場合に有効な方法です。
- 自分の持分のみを売却する場合、他の共有者の同意は不要ですが、売却後にトラブルになることもあるため注意しましょう。

持分放棄については、次の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事:持分放棄のやり方!権利移転登記手続に必要な書類や費用・注意点を解説
共有物分割訴訟の4つの注意点

共有物分割訴訟を提起する場合に注意すべき点がいくつかあります。
これまでご説明した点を含めて注意点をまとめておきましょう。
- 1.共有者全員を当事者にする必要
-
訴訟には共有者全員に当事者(被告)として参加してもらう必要があります。
- 2.相続財産は共有物分割訴訟ができない
-
相続に関する事件は家庭裁判所の管轄のため、地方裁判所の管轄である共有物分割訴訟はできません。
家庭裁判所で遺産分割調停・審判を行うことになるでしょう。
- 3.いきなり訴訟は起こせない
-
協議不調が共有物分割訴訟の要件のため、まず共有者間で共有物分割協議を行う必要があります。
協議で解決できないときに調停(必須ではない)又は訴訟と進みます。
- 4.共有状態を解消する他の方法もある
-
共有状態を解消する方法は、たとえば以下の方法です。
持分放棄:対価(金銭)を得ずに持分(所有権)を失う
共有持分の売却:自分の意思だけででき、対価も得られる
関連記事:遺産分割審判の流れは?弁護士費用や審判確定時の対処についても紹介
共有物分割訴訟は弁護士に早く相談した方がよい!
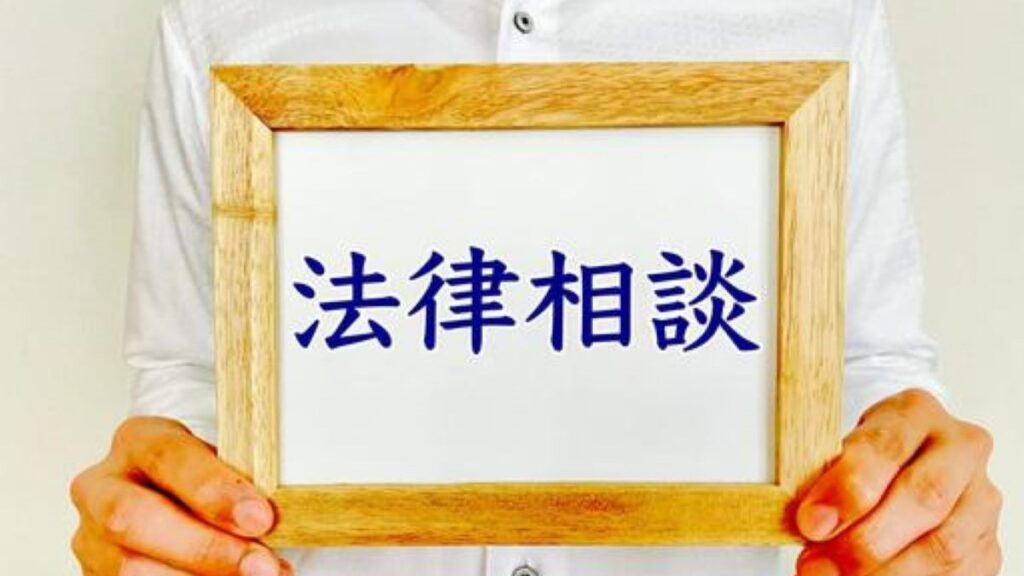
共有物分割訴訟は専門的な立場からの対応・検討が必要です。
訴訟の前段階となる協議は、当事者だけでは冷静な話し合いが難しく、合意に至らないことも多いでしょう。
共有物分割訴訟に移行しそうな共有物の分割請求は、協議を検討する早い段階から弁護士に相談すべきです。
弁護士は、資料の収集・作成、手続代行など、共有物分割請求の協議・調停・訴訟の各段階で必要な作業を全面的にサポートし、代行もできます。
共有物分割請求の弁護士に依頼するメリットについては、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリットを紹介
当事務所アクロピースについては、下記よりご確認いただけます。
まとめ
共有物分割訴訟についてまとめます。
- 共有物分割訴訟とは、不動産を共同相続した場合や共同で不動産を購入し共有名義にしていた場合などに、裁判所の判決によって共有状態の解消を図る方法
- 共有物分割訴訟を起こせるのは協議が不調かそもそも協議不能のとき
- 判決の分割方法は現物分割・代償分割・換価分割のいずれかになる
- 分割訴訟のメリットは、裁判所に委ねられる・共有状態を解消できること
- デメリットは時間と費用がかかる、希望が通るとは限らないことなど
- 共有物分割請求の手順は、分割協議、分割調停申立て、分割訴訟提起、口頭弁論、判決と進む
共有物の分割など共有不動産の問題で不安や悩みがあるときは、不動産に関するトラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
不動産トラブルに強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\合計7000件以上の相談実績/
【無料相談受付中】24時間365日対応









