【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義不動産は売却できない?よくあるトラブルと持分売却方法を解説
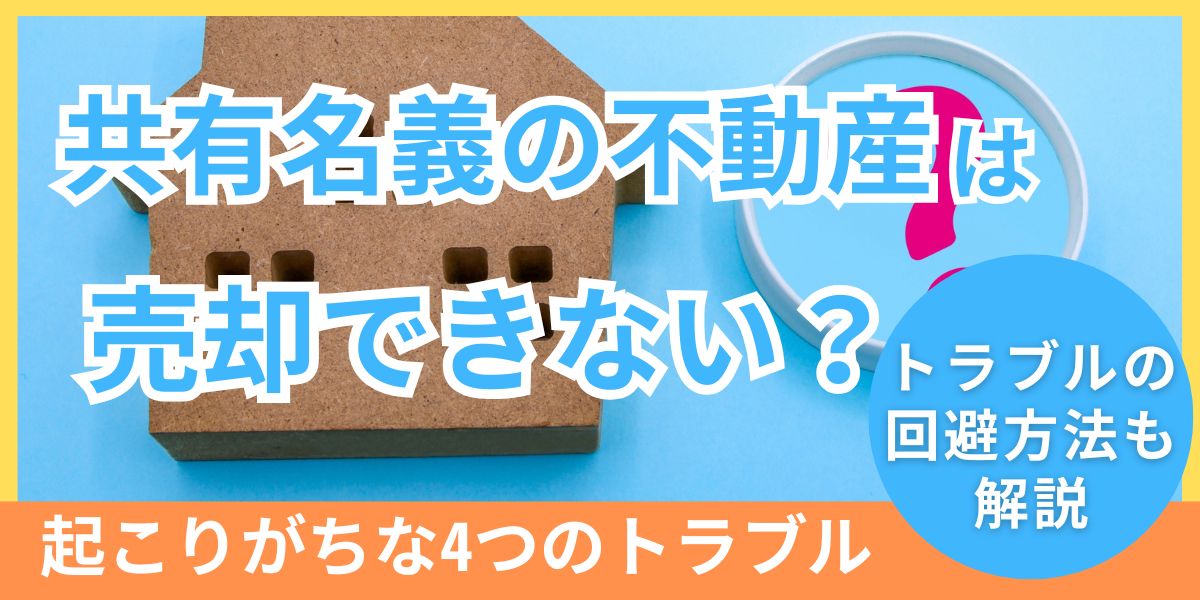
親から相続した不動産や、夫婦共同で購入した共有名義の不動産売却を検討しているが、共有名義不動産は売却できないという話を耳にして、悩むこともあるでしょう。
- 共有名義不動産は本当に売却できないのか?
- 共有名義不動産をトラブルなく売却する方法は?
共有名義の不動産は共有者全員の合意がなければ売却できませんが、本人の有する共有持分は反対者がいても売却できます。
ただし、他の共有者との間でトラブルが生じる可能性があることに注意が必要です。
共有名義の不動産の売却の可否、よくあるトラブルや、売却方法・トラブル回避法などを解説しますので、不動産の共有持分の売却で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義の不動産は売却できない?

最初に、共有名義の不動産は本当に売却できないのかという点について説明します。
そもそも共有名義(不動産)とは、所有者が複数人いることです。
たとえば、親が死去し実家を兄弟で相続した場合や夫婦共同でマンションを購入した場合などに、共有名義となります。
共有名義不動産の売却の可否について結論を先にいうと、次の通りです。
ただし、共有持分の売却は、通常の不動産売却と異なり、トラブルに発展することも多いため注意が必要です。
全体の売却は共有者全員の同意が必要だが共有持分のみの売却は可能
共有不動産全体の売却は共有者全員の同意が必要ですが、共有持分のみの売却は可能です。
共有名義の不動産は、目的物の全体に対して共有者が持分に応じて所有権を有します。
共有不動産全体を売却するためには、共有者全員の同意が必要で、反対する人が一人でもいる場合、売却はできません(民法251条1項、最高裁昭和42年2月23日判決参照)。
| 最高裁昭和42年2月23日判決「共有物の変更が共有者全員の同意を必要とすることは民法251条の定めるところであり、共有物についての処分をもまた同様に解すべきものである」出典:裁判所|昭和42年2月23日最高裁判所第一小法廷判決 |
一方、自分の持分の売却は所有権の内容であり、自由に処分できます(民法206条)。
共有者が有する持分権は、単独で持つ所有権の内容と違いはありません。
共有持分は、他の共有者の同意は不要で、各共有者が自由に処分できるのです。
共有持分のみを売却することで共有関係を解消でき、売却益があれば取得できます。
共有持分の売却を検討した方がよい場合がある
共有持分の売却を検討した方がよい場合もあります。
たとえば、次のような場合です。
例:実家を相続したが、持ち家があるため将来も使う予定がない。
一方で、持分割合に応じ管理費(固定資産税等の税金や修繕費)の負担義務がある。
活用予定がないのに負担がある場合は、持分を売却し共有状態を解消した方がよい。
例:各共有者の意向が、売却したい・住みたい・アパートを建て有効活用したいなどと対立し、話し合いが困難。
トラブルから解放されたい場合は、持分を売却し共有状態を解消した方がよい。
例:長男が実家に住んでいる場合、持分に見合う家賃相当額の支払を求めることもできるが、親族間で家賃分配交渉はし難い。
自分の持分を売却して少しでも売却益を得た方がよい場合もある。
共有持分については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:共有持分について解説
関連記事:共有持分売却の記事を見る
共有名義の不動産の売却で起こりがちなトラブル4つ

共有名義の不動産の売却をめぐって起こりがちなトラブル例を4つ紹介します。
共有者から売却の同意が得られない
共有名義の相続不動産の売却で多いのは「共有者の同意が得られないため不動産全体を売却できない」というトラブルです。
共有名義の不動産全体を売却するためには、共有者全員の同意が必要で、1人でも反対すれば不動産全体を売却することはできません。
共有者の同意が得られない場合、自分の持分だけであれば売却できますが、共有不動産の一部の持分のみを買い取る相手は限られており、悪質な業者に遭遇するリスクや、他の共有者とのトラブルの可能性があるため注意が必要です。
買取業者による強引な営業
自分の共有持分を買取業者に売却すると、買取業者が他の共有者に強引な営業をすることがあります。
たとえば、次のようなことがあり得るでしょう。
- 他の共有者全員の持分も買い取って、物件全体の所有権を獲得しようとする
(共有持分より物件全体をまとめて売却する方が、より高く売れる可能性がある場合)
- 物件全体を買い取れそうもないときは、買取業者が買った持分を他の共有者に買い取らせようと迫る
(共有者が見知らぬ他人となることは不安で、精神的な負担などから応じざるを得ない事態もあり得る)
逆に、他の共有者が見ず知らずの第三者に持分を売却した場合、買取業者が自分に売却を迫ってくることもあり得るでしょう。
共有持分買取業者の利用の注意点については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:共有持分買取業者とは?利用する注意点・依頼するメリット、デメリット
共有物分割請求訴訟を起こされることがある
共有持分を買取業者に売却した場合、上記のように、共有物分割訴訟を買取業者が他の共有者に対して提起する懸念もあります。
「共有物分割請求」とは、共有者の1人が物件の共有状態の解消を求めることです。
判決内容によっては、不動産を手放さざるを得なくなるケースもあるでしょう。
共有物分割請求訴訟について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
関連記事:【共有物分割請求訴訟の手続きの流れ】訴訟のメリット・デメリット
共有者間の関係が悪くなる
共有者間の関係が悪くなることもあり得るでしょう。
たとえば、1人の共有者が建物をすべて全部使用しているが、使用していない共有者に共有分の賃料を支払っていないことがよくあります。
その場合、使用していない共有者は、持分を持っているメリットがないと考え、自分の持分を売ろうとすることもあるでしょう、
使用している共有者に共有持分を買い取ってもらえればよいのですが、現に住んでいる共有者は買うよりも、そのままただで住み続けようと思うかもしれません。
一方、持分を保有し続けるメリットがない共有者は、第三者へ売却するかもしれません。
持分売却は本来自由ですが、売却によって購入者から賃料を請求されるなど、デメリットが多いと考える共有者との関係が悪くなる恐れがあります。
関連記事:共有不動産の使用貸借とは?認められる要件やリスク・トラブル対処法を弁護士が解説
共有名義の不動産の売却方法

ここからは、不動産の共有持分の売却方法について解説します。
他の共有者に売却する
不動産の共有者に買い取ってもらう方法です。
共有者が親族の場合は、買い取ってもらえないか相談してみることをおすすめします。
不動産の適正な価値を把握するためには、不動産業者に査定を出してもらうか、不動産鑑定士に鑑定を依頼するとよいでしょう。
不動産鑑定は有料ですが、不動産業者による査定よりも信用性が高いと評価される傾向があります。
共有者全員で売却する
共有者が全員合意のうえで不動産全体を売却することができれば、望ましい方法といえます。
一部の共有持分のみでなく、不動産を一括して売却できれば、市場の相場価格に近い価格で売り出せる可能性があるため、メリットは大きいでしょう。
売却代金は、共有持分の割合に従って分け合うことが一般的です。
関連記事:共有名義のマンションを売却するには?売却方法や費用・注意点を弁護士が解説
土地を分筆して売却する
共有名義の不動産が土地の場合は、分筆することで単独名義に変更できます。
分筆とは、1つの土地を複数に分割して登記することです。
土地を単独名義にすれば、自分だけの意思で土地の売却や有効活用が可能になります。
ただし、分筆したために分筆後の各筆の土地の形や使い勝手に差が出るとトラブルになるため、分筆の仕方には注意が必要です。
共有物分割請求訴訟を提起する
共有物分割請求訴訟とは、共有名義不動産の分割の可否・方法を裁判所の判断に任せる訴訟です。
裁判所が下す分割方法は、以下の3つのいずれかになるでしょう。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割(競売)
共有物分割請求訴訟を起こせば、最終的に分割までこぎつけることができます。
ただし、分割方法は希望通りにならない可能性がある点に注意しましょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
買取業者への売却
手っ取り早く売却したい方は、買取業者も売却先の一つといえます。
しかし、買取業者の場合、早く売れるかもしれませんが、買取価格が著しく安くなる傾向があるため、おすすめはできません。
共有持分買取業者への売却トラブルの回避法については、下記の記事を参考にしてください。
関連記事:共有持分買取業者への売却で起こりうるトラブル6つ・トラブル回避法
共有名義不動産の売却時のトラブルの回避方法

共有名義不動産(共有持分)の売却時のトラブルを防ぐ方法を紹介します。
遺産分割時に共有にしない
共有持分のトラブルを防ぐには、基本的に「遺産相続時に不動産を共有名義にしない」ことが有効です。
不動産を共有にせずに分ける方法としては、以下の3つの方法があります。
- 現物分割:土地の場合、分筆して分ける方法
- 代償分割:共有者の1人が他の共有者の持分を代償金を支払って取得し不動産名義を単独所有にする方法
- 換価分割:共有不動産の全体を売却し、売却利益を持ち分に応じ分け合う方法
どの方法によるべきかは、弁護士に相談して検討する方がよいでしょう。
共有物分割を行う(共有物分割請求)
共有状態になっている場合は、共有物分割請求(民法256条1項)を行うことも有効です。
共有物分割請求とは、共有者の1人が他の共有者に「共有状態の解消」を申し出ることです。
まず、共有者同士で協議を行い、解決しないときは裁判所に共有物分割請求訴訟を提起しましょう。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリット
共有物分割請求が認められた場合、「現物分割・代償分割・換価分割」のいずれかの方法で共有関係を解消することになります。
| アクロピースは、依頼者の方の負担を減らし、安心してご依頼いただくために、共有物分割請求を着手金無料でお受けしています。 当事務所アクロピースについては、下記よりご確認いただけます。 【弁護士法人アクロピース】圧倒的な経験と実績で不動産分野の悩みを解決 |
共有物分割請求については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリットを紹介
当事者で合意してから売却活動に移る
トラブルになることを避けたいのであれば、基本は当事者で合意後に売却活動に移ることです。
しかし、共有者が売却に最初から反対していれば、そもそも売却自体が難しいでしょう。
また、当初売却に合意しても、売却を進めている間に、突然「金額が不満だ」「売りたくない」などと言い出し、意見が対立することもよくあります。
売却金額や期間の目途を含めて、当事者でまずしっかり話し合って合意してから売却することができれば、それに越したことはありません。
共有名義の不動産売却をめぐるトラブル対策は弁護士に相談を

共有名義の不動産売却をめぐるトラブルで困ったとき、どう対応すべきかわからないときは、不動産に強い弁護士に相談しましょう。
不動産の共有トラブルがあると、兄弟姉妹や夫婦など、身内でも関係が壊れてしまうことがあります。
弁護士に早く相談すれば「共有状態にしない方法」や「共有状態を解消する方法」がわかり、未然にトラブルを防ぐことができ、持分売却後の正しい対処方法も教えてもらえます。
たとえば、次のようなトラブルがある場合は、早く弁護士に相談すべきです。
- 共有者と不仲で話し合いができない
- 共有者の一人が住み続けている
- 売却に強固に反対する共有者がいる
- 住んでいないのに税金を払わされ続けている
上記のような場合は、自分の持分のみを売却し、共有関係から離脱した方がよい場合もあります。
| 弁護士法人アクロピースなら、共有不動産に強く、交渉・裁判手続きはもちろん、その後の税務・登記手続きまですべてお任せいただけます。 |
共有名義の不動産売却をめぐるトラブル対策については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:共有持分買取業者への売却トラブル回避法!共有持分を現金化する際にすべきこと
共有名義不動産を売却する場合の価格相場

共有名義不動産を売却する場合の価格相場について説明します。
共有名義不動産を売却する場合の価格は、ケースによって異なります。
他の共有者に売却する場合:
他の共有者に売却すと、市場相場に近い価格で売買することが可能な場合もあります。
共有者の持分を買い取って単独名義にすれば、不動産の利用価値が上がりメリットが大きいと考える場合も多いからです。
ただし、共有者は近親者の場合が多く、柔軟に対応せざるを得ない場合もあるでしょう。
第三者に売却する場合
第三者に売却する、持分のみの売却は市場相場の半分以下になることも多いでしょう。
持分のみを第三者が買い取っても、そのままの状態では他人と共有することになり、自由に利用できないためです。
なお、物件全体を売却したいと考えても、他の共有者の同意が必要なため、他人同士の場合は話し合い自体が困難なことが多いでしょう。
共有名義の不動産の売却時にかかる税金と負担

共有名義不動産の共有持分を売却するときにどのような税金や費用がかかるのかを説明します。
| 税金・費用 | 税率等 |
| 譲渡所得税・住民税 | 長期保有(5年超):20%(所得税15%、住民税5%)短期保有(5年以下):39%(所得税30%、住民税9%)・※居住用不動産の場合、10年超所有の軽減税率の特例、3,000万円特別控除などの特例がある。 |
| 登録免許税 | 土地:固定資産税評価額×15/1000 令和8年3月31日までの軽減措置(本則は20/1000)建物:固定資産税評価額×20/1000 住宅用家屋3/1000 性能などに応じた各種軽減措置あり※通常、購入者が負担する |
| 登記費用 | 司法書士事務所ごとに異なるが、5万円前後※通常、購入者が負担する |
| 収入印紙 | 譲渡価格による。参照:国税庁|印紙税額の一覧表(その1) |
まとめ
共有名義不動産は売却できないかについてまとめます。
- 全体の売却は共有者全員の同意が必要だが共有持分のみの売却は可能
- 共有持分の売却を検討した方がよい場合もある
- 売却をめぐり起こりがちなトラブルは、共有者の同意が得られない・買取業者による強引な営業・共有物分割請求訴訟を起こされる・共有者間の関係が悪くなることなど
- 共有持分の売却方法は、他の共有者に売る・共有者全員で売る・土地を分筆する・共有物分割請求訴訟を提起するなどがある
- 共有名義不動産の売却時のトラブルを防ぐには、遺産分割時に共有にしない・共有物分割を行う(共有物分割請求)・当事者で合意してから売却活動に移るなどがポイント
- どう対応すべきかわからないときは、不動産に強い弁護士に相談した方がよい
共有名義の不動産は共有者全員の合意がないと売却できませんが、自分の持分は売却可能です。
ただし、持分の売却は共有者とトラブルになることもあり、価格も安くなりがちです。共有持分の売却について不安があるときは、共有不動産の問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
不動産のトラブルは協議をスムーズかつ有利に進めるテクニックだけではなく、専門的な不動産知識や交渉に必要な適切な判断など、様々な対応が必要不可欠です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









