【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義の不動産を単独名義に変更するには?手続きの流れや費用を解説【弁護士監修】
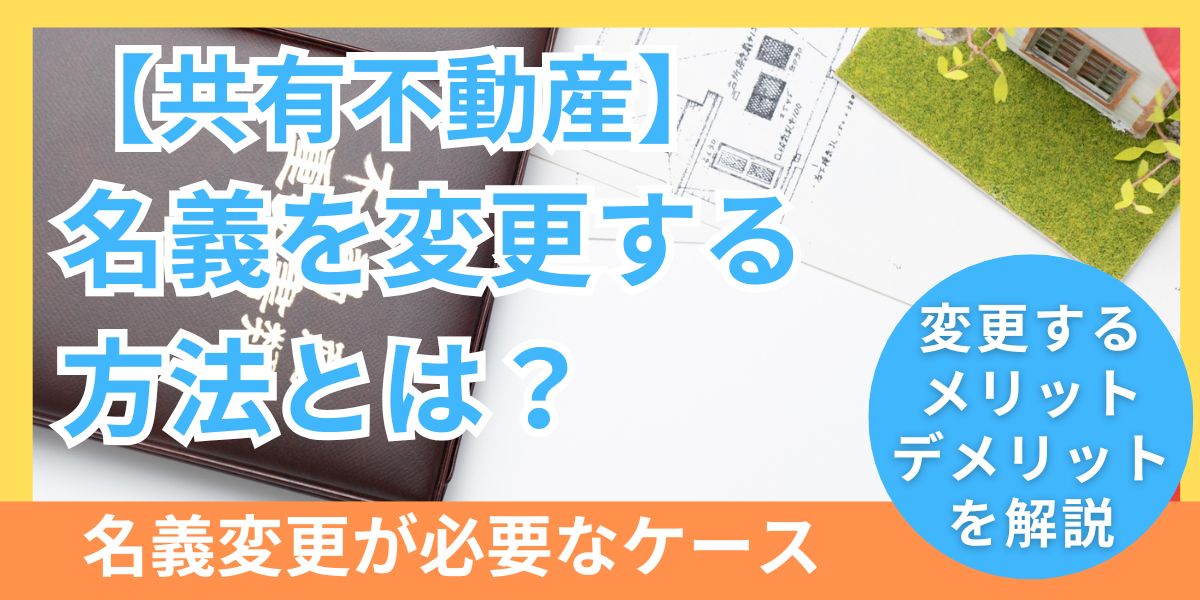
共有名義の不動産を所有している方の中には以下のように悩んでいる方もいるでしょう。
「共有不動産を所有しているが手放したい」
「共有名義を単独名義に変更することはできる?」
「不動産を共有名義から単独名義にするときはどんな費用がかかる?」
共有不動産が抱えるリスクは、適切な名義変更を行うことで解消される可能性があります。
この記事では、共有不動産の名義を単独名義に変更する方法や具体的な費用について解説します。
これから共有不動産の名義変更を検討している方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産を単独名義に変更する3つのケース

共有不動産の名義は、主に以下のケースで変更することがあります。
ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。
相続
共有不動産の名義を変更する1つ目のケースは、相続の場面です。
相続の場面では、だれがどのような割合で財産を相続するのかを話し合うことになりますが、1つの不動産を複数の相続人で共有するケースもあります。
しかし、場面によってはその共有不動産の名義を変更したいと考える相続人もいるのです。
たとえば、「相続分に応じた割合で相続人全員で相続したが、管理を行っている相続人の単独名義に変更したい」というケースや「相続により遠方の親戚と共有名義になってしまい、コミュニケーションを取るのが大変なため単独名義に変更したい」などのケースが考えられます。
法定相続割合の持分で共有名義にした後、遺産分割協議により単独名義に変更すると贈与税はかかりません。
しかし、遺産分割協議による登記をした後に単独名義に変更する場合は、売却や贈与などを行わなければならないため、贈与税や不動産取得税の課税対象となってしまいます。
相続の場面で名義変更を行う場合は、タイミングにも気をつけなければいけません。
共有不動産を相続したケースについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
離婚
離婚により共有不動産の名義を変更するケースもあります。
離婚をすると夫婦は赤の他人となるため、共有不動産にしておくとさまざまなトラブルが発生するおそれがあるからです。
たとえば、どちらか一方がローンを滞納して家が競売にかけられてしまったり、知らない間に第三者に持分を売却したりすると、トラブルの原因になってしまいます。
共有名義の不動産を売却して分配するのであれば問題ありませんが、どちらか一方が住み続ける場合は、共有名義から単独名義へ変更しておくほうが安心です。
ただし、住宅ローンが残っている場合は同時にローンの名義も変更する必要があるため、債務者変更手続きや借り換え、手放す側が一括返済するなどの方法を検討しなければなりません。
子どもへの譲渡
親子で購入した二世帯住宅などを子どもへ譲渡する場面でも、名義変更を行うことがあります。
親子の共有名義で住宅を購入したものの、親の病気や認知症の発症などをきっかけに子どもの単独名義に変更するケースがあるのです。
ただし、この場合でも贈与や売却の手段により単独名義にする必要があるため、贈与税や不動産取得税の課税対象となります。
その際に契約書を作成しないことがありますが、後にトラブルの原因となってしまうため、親子間の贈与や売買であっても契約書を作成することをおすすめします。
また、共有名義の住宅ローンを組んでいる場合は、債務者変更手続きや借り換えを行わなければないことに注意してください。
関連記事:共有持分を譲渡する4つの方法とは?手続きや税金・注意点をプロが解説
共有不動産を単独名義に変更する6つの方法

共有不動産の名義の変更する方法には、以下の6つが挙げられます。
それぞれの方法を選ぶケースや、注意点を紹介します。
贈与|所有している持ち分を他の人に譲る
贈与により、名義を変更することができます。
不動産の共有持分の贈与とは、自分が所有している持分を他の人に譲ることです。
贈与は、当事者間の口頭による合意でも有効であり、有償・無償問わず成立します。
そのため、単独所有する側に資金力がないケースで利用されることがあります。
ただし、贈与の場合は、贈与を受けた側に贈与税が課税されることに注意しなければなりません。
たとえば、Aさん、Bさん、Cさんの共有不動産を贈与によりAさんの単独所有に変更する場合は、Aさんに贈与税がかかります。
対象不動産の評価額の10%〜55%と、高額の贈与税が発生することを理解しておきましょう。
また、口頭のみで取引をすると後にトラブルが発生する可能性があるため、贈与を行う場合は贈与契約書を作成するのが一般的です。
もし複数の共有名義人がいる場合は、各共有者と贈与契約書を作成することとなります。
共有持分の放棄|単独名義にする人以外の共有持分を放棄する
単独名義にする人以外の共有持分を放棄することで、名義の変更ができます。
たとえば、Aさん、Bさん、Cさんの共有不動産をAさんの単独所有にするために、BさんとCさんが持分の放棄を行います。
贈与や売却と違い、この方法は共有者が自由に行うことができるため、共有者間の関係が良くないときに利用することがあります。
しかし、他の共有者に告知することなく持分を放棄してしまうとトラブルになる恐れがあるため、スムーズに手続きを進めるためには事前に共有者に相談しておくことがおすすめです。
この方法は、法律上の解釈として原始取得(新たに権利を取得すること)と考えられているため、贈与にはなりません。
しかし、税法上は無償で移転したと取り扱われ「みなし贈与」となり、贈与税が発生するケースがあるため、税負担に注意が必要です。
関連記事:持分放棄のやり方!権利移転登記手続に必要な書類や費用・注意点を解説
売却|所有している持ち分を共有者に売却する
共有不動産の持分を売却することで、名義変更をすることができます。
たとえば、Aさん、Bさん、Cさんの共有不動産を売却によりAさんの単独所有にするためには、BさんとCさんがAさんに自身の持分を売却することとなります。
不動産を譲る側に資金力があり、お金により平和的に解決したい場合に利用される方法です。
注意点として、持分を売却したことにより利益を得た場合、所有期間に応じて譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税の所有期間に応じた税率は、以下のとおりです。
| 所得区分 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% (所得税:30%/住民税:9%/復興特別所得税:0.63%) |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% (所得税:15%/住民税:5%/復興特別所得税:0.315%) |
また、時価より著しく低い金額で売却すると贈与としてみなされてしまい、贈与税がかかります。
売却により名義変更する場合は、適正な価格に設定することを意識しましょう。
以下の記事では、共有持分の売却相場について詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
関連記事:共有持分売却相場はどのくらい?市場価格より安い理由・高く売る方法
財産分与|夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に分配する
財産分与をすることで、共有不動産の名義を変更できます。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚の際に分配することです。
婚姻中に共有名義の不動産を購入していた場合、財産分与を行いどちらかの単独名義にします。
財産分与の請求期限は、離婚が正式に成立してから2年間と定められています。
また、財産分与の登記を行うためには、遺産分割協議書や離婚調停証書、審判書などの財産分与の内容について記された書類が必要です。
財産分与による名義変更でも、共有名義の住宅ローンを組んでいるのであれば、ローンの名義も単独名義にしなければなりません。
単独名義にすることが難しい場合は、売却して現金を分配することも検討してみましょう。
関連記事:共有名義ローンは夫・頭金は妻の離婚における財産分与の問題点を解説
分筆|共有している土地を分割して別々に登記する
共有状態の土地を解消する場合、分筆するのも選択肢の一つです。
分筆とは、共有している土地を複数に分け、それぞれ独立した不動産として登記する手続きです。たとえば、200㎡の土地を100㎡ずつ分けて、それぞれが単独で管理・活用できるようにするケースが代表例です。
ただし、分筆には土地の測量が必要で、土地家屋調査士への依頼が必須です。また、分け方によっては片方の土地の形状や立地条件が悪くなり、資産価値が下がる可能性もあります。
早い段階で専門家に相談し、自分に合った名義変更方法かどうかを確認しましょう。
共有物分割請求訴訟|裁判所に分割方法を裁定してもらう
共有者との話し合いがまとまらない場合、共有物分割請求訴訟を検討する必要があります。
共有物分割請求訴訟とは、共有不動産を分けたいのに話し合いで合意できない場合に、裁判所に分割方法を決めてもらうための手続きです。
共有物分割請求訴訟を起こせば、裁判所が現物分割(物理的に分ける)や代償分割(誰かが他の共有者に金銭を支払って取得する)などの方法を判断します。
ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、最終手段と考えるのが一般的です。分配方法は裁判所が決めるため、希望通りの結果にならない可能性もあります。
できるだけ事前に弁護士へ相談し、交渉による解決の可能性を探りましょう。
関連記事:共有物分割請求訴訟の手続きの流れ!メリット・デメリットなどをわかりやすく解説
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産を単独名義に変更するメリット

不動産を共有名義から単独名義に変更するメリットは、主に以下の2点です。
それぞれを詳しく解説します。
共有者間のトラブルを回避できる
共有不動産の名義変更を行えば、共有者同士のトラブルを避けることができます。
共有不動産には持分が設定されているものの、その割合分しか利用できないというわけではありません。
たとえば、ある不動産をAさん、Bさん、Cさんが1/3ずつで共有していても、Aさんが不動産全体を利用することが可能です。
とはいえ、Aさんを強制的に追い出すことはできません。
また、離婚したにもかかわらず不動産を共有名義で所有している場合は、処分方法を巡って意見が合わないこともあるでしょう。
共有不動産を解消することで、他の一人の共有者のみが不動産全体を利用して、自分が不動産を利用することができない、処分方法を好きに決められない、などのトラブルを防ぐことができます。
共有持分が絡むトラブル事例やトラブルを避ける方法は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:【共有持分の基礎知識】売却・相続・私道が絡むトラブル事例も紹介
共有不動産を管理・処分する手間が軽減する
共有状態を解消することで、管理や処分の手間を省けるというメリットがあります。
共有不動産の場合、不動産を売却したり賃貸に出したりする際は、共有者全員の同意が必要です。
しかし、共有者間の意見が合わないと希望通りに不動産を活用できない可能性があります。
たとえば、Aさん、Bさん、Cさんが共有している中古住宅の場合、AさんとBさんが売却したいと言っても、Cさんがそれに反対すると売却は実現しません。
その点、単独名義であれば、自分の意志のみで売却や賃貸などの処分方法を決めることができます。
不動産をスムーズに処分・管理したい方は、単独名義にするのがおすすめです。
共有不動産を単独名義に変更するデメリット・注意点

不動産を共有名義から単独名義に変更する際は、以下2点のデメリットがあるため、注意して手続きを進めましょう。
トラブルなく手続きを進められるよう、事前に注意点を押さえておくことが大切です。
名義変更には共有者全員の同意が必要となる
前述のとおり、名義変更には共有者全員の同意が必要となります。
民法第251条では、他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えられないと明記されています。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。引用:e-Gov法令検索|民法
たとえば、兄弟で共有している土地を一人の名義にしようとしても、もう一人が同意しなければ登記変更はできません。
そのため事前に全員と話し合い、協議が整った上で手続きを進めるようにしましょう。
関連記事:兄弟での不動産共有名義について解説
登記申請書の書き方が複雑になる
登記申請書の書き方が複雑になる点に注意しましょう。
登記申請書には、登記の目的や持ち分を記載する欄があります。共有不動産を単独名義に変更する場合、登記する前と後それぞれの持ち分を正確に記載しなければなりません。
たとえば「持ち分2分の1を共有者AからBへ移転」と記載する際に、誤ってBの持ち分を「1分の1」と記載すると、内容に矛盾が生じてしまいます。
登記に慣れていない方は、申請書の作成でつまずくことが多いです。スムーズに受理されるよう、始めから司法書士に相談しましょう。
共有不動産を単独名義に変更する手続き4ステップ

共有不動産の名義を変更する流れは、以下の4ステップです。
まず、名義変更登記を行うための書類を集めます。
登記に必要な代表的な書類は以下のとおりです。
- 登記原因証明書情報
- 登記済権利証または登記識別情報
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 固定資産評価証明書
- 実印
- 免許証などの必要書類
- 離婚協議書、財産分与契約書、戸籍謄本(離婚による財産分与の場合)
ただし、ケースによって必要書類が異なるため、事前に司法書士などの専門家や法務局に確認しておくと安心です。
次に、登記申請書類を作成します。
登記申請書類とは、登記を申請する際に法務局へ提出する書類です。
登記申請書類は、専用の用紙があるわけでありません。
自身で作成する場合は、法務局のホームページで公開されている申請書の様式や記載例を参考にしてください。
しかし、登記申請書類に不備があると手続きがスムーズに進みません。
書類の作成に不安がある方や手続きを行う時間が取れない方は、専門家への依頼を検討しましょう。
登記申請書類の作成が完了すれば、法務局に登記申請を行います。
登記申請を行う方法には、以下の3つがあります。
- 窓口申請
- 郵送申請
- オンライン申請
このうち、オンライン申請は主に専門家が利用する方法のため、自身で申請を行う場合は、窓口または郵送で申請しましょう。
申請書を法務局へ提出したあと、一般的に1週間から10日ほどで登記手続きが完了し、登記識別情報が発行されます。
登記識別情報とは、従来の権利証に代わるもので、不動産の登記名義人であることを証明する12桁の符号が記載された書類です。
登記識別情報は登記完了日以降に窓口で受け取れる他、事前に申請すれば自宅や勤務先に郵送してもらうことも可能です。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
不動産を共有名義から単独名義への変更するときの費用・税金
共有名義から単独名義に変更する際に発生する費用・税金は、主に以下の6項目です。
名義の変更方法や不動産の価値によって、発生する費用・税金が異なるため、事前に内容を把握しておきましょう。
司法書士に支払う報酬|4万円~16万円程度
不動産を共有名義から単独名義に変更するには、登記手続きを行う必要があります。手続きには法的知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に支払う報酬(依頼料)は、登記内容ごとに異なりますが、合計で4万円~16万円程度が相場です。
登記内容ごとの費用相場は、以下の通りです。
- 所有権移転登記:2万~10万円
- 抵当権抹消登記:1万~3万円
- 住所変更登記:1万~3万円
報酬の額は、依頼する司法書士によって異なります。信頼できる司法書士に依頼し、手続きをスムーズに進めましょう。
登録免許税|登記の種類によって変動する
登録免許税とは、不動産の登記を法務局に申請する際に課される税金です。「課税標準額×税率」で計算され、不動産の区分や登記の種類によって税率が異なります。
具体的な税率は、以下の通りです。
| 土地 | ・売買:2.0%(令和8年3月31日までの軽減税率なら1.5%) ・贈与・交換・収用・競売など:2.0% ・相続:0.4% |
|---|---|
| 建物 | ・売買・競売:2.0% ・相続:0.4% ・贈与・交換・収用など:2.0% |
| 土地・建物に共通する税率 | ・抵当権設定登記:0.4%(令和9年3月31日までの軽減税率なら0.1%) ・抵当権抹消登記・住所変更登記:1つの不動産につき1,000円 |
参照:
国税庁|No.7191 登録免許税の税額表
税務署|土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
津地方法務局|抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税
たとえば、土地の相続で名義変更を行う場合、登録免許税は評価額の0.4%になります。
税額は数万円から数十万円に及ぶ場合もあるため、事前に不動産の評価額と登記内容をもとに、納税額を試算しておきましょう。
司法書士に相談すれば、正確な見積もりを確認できます。
印紙税|200円~48万円(契約金額によって変動する)
不動産の持ち分を売買や贈与で譲渡する場合、印紙税が課されます。印紙税とは、不動産の売買契約書などの文書を作成した際に課される税金です。税額は200円~48万円となっており、不動産の契約金額によって変動します。
具体的な税率は、以下の通りです。
| 金額 | 税率 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円以上50万円以下 | 200円 |
| 50万円以上100万円以下 | 500円 |
| 100万円以上500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円以上1千万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円以上5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円以上1億円以下 | 3万円 |
| 1億円以上5億円以下 | 6万円 |
| 5億円以上10億円以下 | 16万円 |
| 10億円以上50億円以下 | 32万円 |
| 50億円以上 | 48万円 |
参照:
国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
国税庁|「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
本則税率であれば200円~60万円ですが、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されています。
なお、印紙税は契約書に収入印紙を貼付して納付します。貼り忘れや金額ミスがあると、過怠税が課されるため注意が必要です。
(参照:国税庁|印紙を貼り付けなかった場合の過怠税)
不動産取得税|不動産の評価額×3~4%(売買・贈与のみ)
不動産取得税は、不動産を購入・贈与などで取得したときに課される地方税です。相続では課税されませんが、売買や贈与で名義変更をする場合は必ず発生します。
不動産取得税は「不動産の評価額×税率3~4%」で計算され、名義変更をする不動産が土地か建物か、住宅用地かによって税率が異なります。
区分ごとの税率は、以下の通りです。
| 区分 | 不動産取得税の税率 |
|---|---|
| 土地 (住宅地・田・畑など) | 3% |
| 家屋 (住宅・店舗・倉庫など) | 3% |
| 住宅用地ではない土地・建物 | 4% |
土地・家屋の本則は4%ですが、令和9年3月31日までは軽減税率3%が適用されます。たとえば、評価額が2,000万円の住宅用土地を取得した場合、不動産取得税は「2,000万円×3%」で60万円です。
参照:総務省|不動産取得税
譲渡所得税|不動産の所有期間によって変動する
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、以下の計算式で算出します。
課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取得費に含まれるのは購入時の税金や造成費用、譲渡費用には仲介手数料や印紙税が該当します。マイホームの譲渡や国の公共事業のための譲渡など、一定の条件を満たせば特別控除が受けられます。
課税所得が確定したら、不動産の所有期間に応じた税率を掛けて贈与税を算出する仕組みです。税率は以下の通りです。
| 所有期間5年以下(短期譲渡所得) | ・所得税:30.63% ・住民税:9% |
|---|---|
| 所有期間5年以上(長期譲渡所得) | ・所得税:15.315% ・住民税:5% |
※平成25年~令和19年までは、復興特別所得税2.1%が上乗せされています。
名義変更に伴い持ち分を売却する場合は、譲渡益の有無と所有期間を確認しましょう。
参照:
国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
国税庁|No.3255 譲渡費用となるもの
国税庁|No.3252 取得費となるもの
国税庁|土地や建物を売ったとき
贈与税|不動産の課税評価額によって変動する
不動産の持ち分を共有者間で贈与した場合、贈与を受けた側に贈与税が課されます。税額は以下の式で計算します。
不動産の課税評価額-110万円(基礎控除)×税率-控除額
税率は贈与の相手や年齢により「一般税率」と「特例税率」に分かれます。兄弟間や配偶者間では「一般税率」が、18歳以上の子が親から受ける贈与には「特例税率」が適用される仕組みです。
具体的な税率は、以下の通りです。
| 区分 | 不動産の課税評価額 | 税率 |
|---|---|---|
| 一般税率 (兄弟間や配偶者間での贈与) | 200万円 | 10%(控除額なし) |
| 300万円以下 | 15%(控除額10万円) | |
| 400万円以下 | 20% (控除額25万円) | |
| 600万円以下 | 30%(控除額65万円) | |
| 1,000万円以下 | 40%(控除額125万円) | |
| 1,500万円以下 | 45%(控除額175万円) | |
| 3,000万円以下 | 50%(控除額250万円) | |
| 3,000万円以上 | 55%(控除額400万円) | |
| 特例税率 (18歳以上の子が親から受ける贈与) | 200万円 | 10%(控除額なし) |
| 400万円以下 | 15%(控除額10万円) | |
| 600万円以下 | 20% (控除額30万円) | |
| 1000万円以下 | 30%(控除額90万円) | |
| 1,500万円以下 | 40%(控除額190万円) | |
| 3,000万円以下 | 45%(控除額265万円) | |
| 4,500万円以下 | 50%(控除額415万円) | |
| 4,500万円以上 | 55%(控除額640万円) |
参照:
国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
贈与税は高額になりやすいため、事前に評価額と税額を試算しておきましょう。
共有不動産を名義変更するときによくある質問
共有名義から単独名義に変更すると贈与税はかかりますか?
無償で他の共有者の持分を取得した場合、贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税は、不動産の課税評価額から110万円の基礎控除・特別控除額を引いた残額に対して10〜55%の累進課税がかかります。不動産の評価額が高額になると、税額も大きくなる仕組みです。
ただし、110万円以下の贈与であれば非課税になります。110万円以上の贈与であっても、特別控除を活用すれば税額を軽減できるケースもあります。
税金に関する知識が必要なため、詳しくは税理士に相談すると良いでしょう。
共有名義から単独名義への変更は自分でできますか?
自分で手続きすることも可能ですが、専門的な知識と正確な作業が求められるため、完了するまでに時間がかかります。
名義変更をする際は、登記申請書や登記済権利証などの書類を用意しなければなりません。不備があれば、法務局に受理されず再提出になる可能性があります。
費用を抑えたい場合に自力での手続きを選ぶ人もいますが、不備による手戻りを防ぐには司法書士への依頼が確実です。
家の名義変更を頼むといくらかかりますか?
名義変更には、登録免許税や司法書士報酬などの費用が発生します。一般的には数万円から数十万円が相場です。
たとえば、相続による変更なら登録免許税は固定資産評価額の0.4%、司法書士費用は5万~10万円前後が目安です。
例えば不動産評価額が1,000万円なら税額4万円に加え、司法書士への報酬を支払うイメージです。
まとめ|共有不動産の名義変更は状況に応じて使い分けよう
共有名義から単独名義に変更するにはさまざまな方法はあるため、自分のおかれた状況によって使い分けることが大切です。
- 共有不動産の名義を変更する主な場面として、相続や離婚、子どもへの譲渡などが挙げられる
- 名義変更を行う方法は、贈与や共有持分の放棄、売却や財産分与があり、場面に応じて使い分ける必要がある
- 共有不動産の名義を変更すると、共有者間のトラブルを回避したり、処分する手間を軽減したりするメリットがある
- 名義変更は、必要書類を集め、登記申請書類を作成し申請した後、登記識別情報を受領する流れで行われる
- 共有不動産の名義変更で必要な費用は、名義変更の方法や登記の種類によって変動する
共有不動産の名義変更を確実に進めるためには、事前に弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが大切です。
準備不足によるトラブルを防ぎ、スムーズな名義変更を実現しましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









