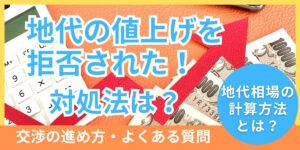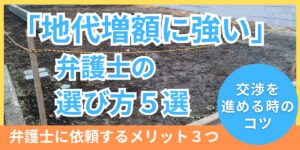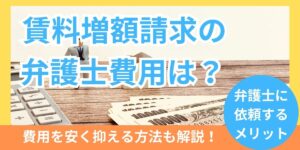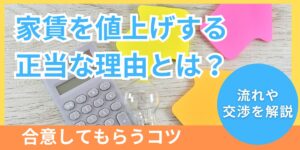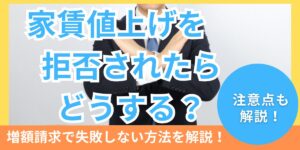【無料相談受付中】24時間365日対応
賃借人死亡の場合で相続人なしの時|契約や荷物への対応はどうすべきかを解説
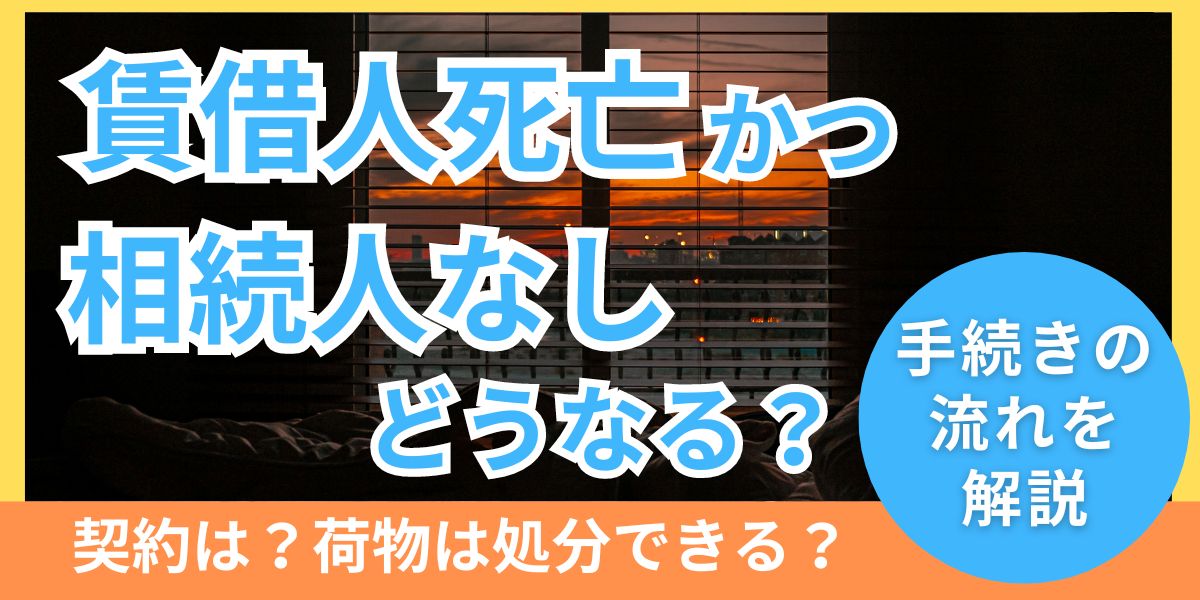
賃貸物件を所有している方の中には、亡くなった賃借人に相続人がいないケースで「契約関係はどうなるのか?」「荷物を処分しても良いのだろうか?」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
賃貸借契約は、賃借人が死亡しても自動的に解除されることはありません。
また、荷物を勝手に処分すると、民事・刑事上の責任を問われる可能性もあります。
相続人のいない賃借人について賃貸借契約の解消や残置物の処分を進めるには、相続財産清算人の選任手続きが必要です。
契約関係や荷物の処理を適切に進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士法人アクロピースは、不動産問題に関する豊富な経験を活かして、賃貸借契約の解消や残置物の処分をサポートいたします。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\7000件以上の相談実績/
【無料相談受付中】24時間365日対応
亡くなられた方に相続人がいない場合の
賃貸借契約や残置物の取扱いについて

賃借人が亡くなられた際、賃借人に相続人がいれば相続人が賃貸借契約や残置物(部屋に遺された荷物)の所有権を引き継ぎます。
しかし賃借人に相続人がいない場合、賃貸人としては、賃貸借契約や残置物の取扱いについて話し合う相手がおらず、対応に苦慮することになります。
亡くなられた方に相続人がいない場合の法律関係については、次の3つの点を理解しておくと良いでしょう。
これらの点を理解しておけば、賃貸借契約や残置物をどのように取り扱うべきかの判断ができるようになります。
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
賃借人が死亡しても賃貸借契約は終了しない
無償で不動産などを貸し付ける使用貸借契約の場合、借主の死亡によって契約が終了します(民法597条3項)。
一方、賃貸借契約は、民法597条3項を準用していないため賃借人が死亡しても契約は終了しません(民法622条)。
賃借人に相続人がいる場合、賃貸借契約は相続人に引き継がれます。
この際、賃貸人が賃貸借契約の解除を希望するのなら、相続人との交渉が必要です。
賃借人に相続人がいないケースでは、賃貸借契約の解除をするための交渉相手が存在しません。
そこで、被相続人(賃借人)の財産について管理権を持つ相続財産清算人の選任が必要となるのです。
相続財産清算人を選任すれば、相続財産清算人が裁判所の許可を得たうえで賃貸借契約を解除することが可能となります。
残置物の取扱いについて
賃借人が死亡したとしても、賃貸物件の中に残された荷物(残置物)を勝手に処分することは許されません。
賃借人に相続人がいる場合、相続人が残置物の所有権を引き継ぎます。
賃借人に相続人がいないときには、相続財産清算人を窓口として残置物の取扱いについて話し合う必要があります。
賃貸人としては、賃借人に相続人がいるのかを調査したうえで、残置物の取扱いについて誰と話し合うのかを判断しなくてはなりません。
残置物を勝手に処分すると、民事上の損害賠償責任を負うだけでなく、器物損壊罪といった刑事上の責任を問われるおそれもあります。
高齢で相続人のいない賃借人については残置物の取扱いについて準委任契約を締結しておくなど、賃貸借契約を締結する段階での配慮が必要となるでしょう。
相続人がいない場合、相続財産法人が権利を引き継ぐ
賃借人に相続人も特別縁故者(内縁の妻など)もいない場合、賃借人の権利義務は相続財産法人のものとなります(民法951条)。
相続人のいない賃借人の賃貸借契約や残置物の所有権は、この相続財産法人が引き継ぎます。
相続財産法人の財産を勝手に処分すると、民事上・刑事上の責任を問われるおそれがあるため注意が必要です。
相続財産法人の財産を処分するには、相続財産清算人を選任しなければなりません(民法952条)。
賃貸人としては、相続財産清算人を選任したうえで、賃貸借契約や残置物の取扱いについて話し合う必要があるのです。
相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、相続財産の調査や管理・換価処分を行い、相続財産法人を清算する役割を果たす人のことです。
2023年4月1日の民法改正によって、相続財産管理人から相続財産清算人へと名称が変更されました。
相続財産清算人は、選任されるとすぐに相続財産の調査を行い、財産目録を作成します。
相続財産清算人の基本的な権限は、相続財産の保存・管理行為です。
さらに、裁判所の許可を得たうえで相続財産の処分行為も行えます。
賃貸借契約の解約や荷物の処分は処分行為に該当するため、相続財産清算人としては、賃貸人との話し合いに加えて裁判所の許可を得たうえで、契約や荷物の取扱い方法を決めることになるでしょう。
なお、滞納している家賃がある場合には、相続財産管理人に支払ってもらうことが可能です。
相続財産清算人と相続財産管理人の違いについて、詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。
相続財産清算人の選任方法

相続財産清算人を選任するには、裁判所への申立手続きが必要です。
ここでは、相続財産清算人の選任方法について、次の3つの項目に分けて解説します。
相続人の調査
相続財産清算人は、相続人がいない場合に選任されるものです。
そのため、相続財産清算人選任の申立てを行う前提として、相続人の有無を調査する必要があります。
相続人の調査を行うには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなくてはなりません。
被相続人が複数回婚姻している、養子縁組をしているなど戸籍関係が複雑なケースでは、相続財産の調査も大変な作業となります。
戸籍による相続人の調査は、今後の手続きにおける前提となるものなので調査漏れや間違いは許されません。
相続人の調査に不安を感じる方、手続きに手間をかけられない方は、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
相続財産清算人選任の申立て手続きの必要書類
相続財産清算人選任の申立て手続きには、次の書類が必要です。
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票
- 被相続人の財産関係の資料
- 被相続人と申立人との利害関係を証明する資料 など
相続財産清算人選任の申立てに必要な書類は、被相続人の戸籍、申立人と被相続人との関係などによって異なります。
申立てに必要な書類の選別は、専門的知識がなければ難しいです。
そのため、相続財産清算人選任の申立てを検討している方は、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
相続財産清算人選任の申立て手続きの流れ
相続財産清算人選任の申立てから財産の清算までの流れは、次のとおりです。
- 裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行う
- 裁判所によって相続財産清算人が選任される
- 相続財産清算人が財産の調査、保存、管理、処分などの業務を行う
- 相続財産を清算し、残った財産を国庫に帰属させる
申立書類の準備ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行います。
家庭裁判所では申立書類をもとに調査を行い、相続財産清算人の選任が必要と判断されれば相続財産清算人が選任されます。
相続財産清算人としては、弁護士や司法書士が選任されるケースがほとんどです。
相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人は、財産の調査、保存、管理、処分などの業務を進めます。
このタイミングで賃貸借契約の解除や残置物の処分について交渉することが可能です。
最終的に相続財産清算人は、清算後に残った財産を国庫に帰属させて手続きが終結します。
手続きを進めるうえでの注意点

賃借人の残置物を処分するために相続財産清算人選任の手続きを行う際は、次の3つの点に注意してください。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
相続人の調査、申立書類の準備に手間と時間がかかる
相続財産清算人選任の申立てをするには、前提として相続人の調査と申立書類の準備が必要です。
相続人の調査を行うには、被相続人の戸籍を漏れなく調査する必要があるため、手間も時間もかかる作業となります。
素人が調査を行うと、読み間違えや記載の見落としなどで正確な調査を行えない可能性もあるでしょう。
さらに、申立てを行う際は、申立書の作成だけでなく、戸籍や利害関係を証明する資料などの準備が必要となります。
申立書類の不備があると手続きは進まず、申立てを却下されることもあります。
申立費用や予納金などの費用がかかる
相続財産清算人選任の手続きを進めるには、費用がかかります。
費用を負担するのは申立人で、手続きが終了しても支払った費用が戻ってくることはありません。
相続財産清算人選任の申立てには、次の費用がかかります。
- 収入印紙 800円分
- 郵便切手 1,000円から2,000円程度
- 官報公告費用 5,075円
また、添付資料である戸籍謄本の取得にも数千円から1万円程度の費用が必要となるでしょう。
十分な相続財産が残されていないケースでは、相続財産清算人の経費や報酬に充てるための予納金も必要です。
予納金の額は、10万円から100万円ほどとなっています。
通常の申立て費用はともかく、予納金が必要となるケースでは、高額の費用負担を覚悟しなければなりません。
自分で手続きを進めるのが難しいなら弁護士に相談する
相続財産清算人選任の申立てを行うには、手間や時間がかかるだけでなく、専門的知識がなければ手続きを進めるのが難しい場面も少なくありません。
自分で手続きを進めるのが難しいと感じるのなら、専門家である弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
弁護士への依頼には、費用の面で不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、先ずは相談から始めてみてください。
まとめ

今回は、相続人のいない賃借人が亡くなった場合の後処理の方法として、次の内容について解説しました。
- 賃借人が亡くなっても賃貸借関係は解除されない
- 残置物を勝手に処分すると損害賠償責任や刑事責任を問われるおそれがある
- 契約関係を解消したり残置物を処分したりするには相続財産清算人の選任が必要となる
契約関係の解消や残置物の処分でお悩みの方は、弁護士までご相談ください。
相続財産清算人の選任手続きは資料の収集や申立書の作成など手間のかかる作業です。
手続きをスムーズに進めるには、専門家に依頼することをおすすめします。
弁護士法人アクロピースでは、これまでに培ってきた不動産問題に関する経験を元に、お客様の状況に合った形で相続財産清算人の選任手続きをサポートいたします。
必要に応じて、不動産鑑定士や土地家屋調査士と連携しながらご対応いたします。
相続財産清算人の選任手続きをスムーズに進めたい方は、弁護士法人アクロピースまでお気軽にお問い合わせください。
\初回60分の相談は無料/
【無料相談受付中】24時間365日対応