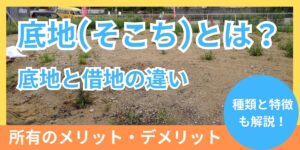【無料相談受付中】24時間365日対応
賃貸に20年住んだ場合の所有権・居住権は?時効取得の条件と修繕費の負担区分を解説
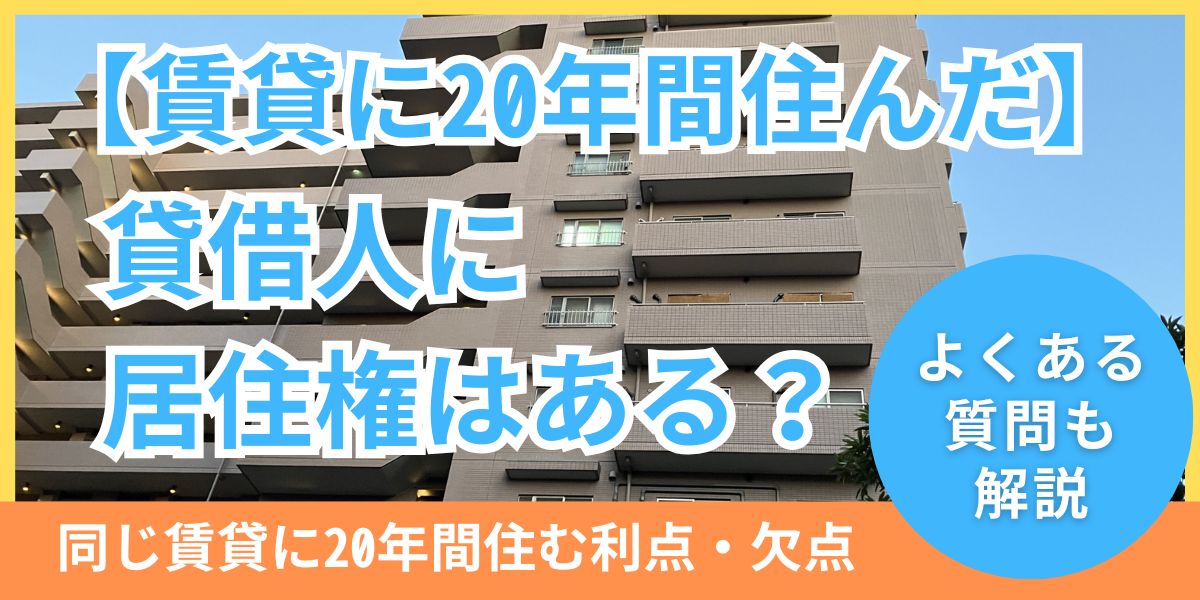
「今の賃貸マンションに20年以上住み続けているけれど、自分のものになったりしない?」
「急に立ち退きを迫られたら、長期間住んでいる実績を主張して拒否できる?」
長年同じ賃貸物件に住んでいると、愛着とともにこのような疑問や不安が湧いてくるものです。「20年住めば時効で自分の家になる」という噂を耳にすることがありますが、賃貸契約においては法的なハードルが高いのが現実です。
しかし、所有権は得られなくとも、20年という居住実績は退去時の修繕費用や立ち退き交渉において、借主にとって有利な材料となるケースが多くあります。
本記事では、長期居住者の権利関係や、20年住んだからこそ得られる金銭的なメリットについて、法律の専門的な視点からわかりやすく解説します。
所有権の時効取得:賃貸物件に20年居住しただけで所有権を時効取得できるケースは一般に想定しにくい。
長期居住の防御力:20年の居住実績は、貸主からの立ち退き要求に対する正当事由の判断において、借主側に有利に働く要素となり得る。
原状回復費用の負担:壁紙などの設備は経年劣化により価値が減少するため、20年住めば退去時の借主負担は大幅に軽減される可能性が高い。
弁護士に相談するメリット:賃貸物件からの立ち退きなどをめぐるトラブルは1人で対応するのは難しい。トラブル対応を弁護士に相談することで、早期解決が図れる。
長期間の賃貸借契約にまつわるトラブルは、個別の事情や契約内容によって判断が大きく分かれます。
弁護士法人アクロピースでは、不動産問題に精通した弁護士があなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切な解決策をご提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
賃貸に20年住んでも賃借人に新たな居住権の発生や所有権の時効取得はない

賃貸物件に20年住んでいたとしても、新たに居住権が発生することや、物件の所有権を得ることはありません。
民法は取得時効の要件を、所有権と所有権以外の財産権に分けて規定しています。
賃貸物件の所有権や他の財産権の時効取得は次のようになります。
以下で説明する通り、賃貸物件の所有権は時効取得の対象にはならず、持ち家になることはありません。
詳しく説明しましょう。

賃貸契約において「家賃を払い続けている」という事実は、他人の所有物であることを認めている証拠になります。
そのため、どれだけ長く住んでも所有の意思が認められず、所有権の時効取得は原則として成立しません。
誤った知識で大家さんと交渉するとトラブルが悪化するため、まずは正しい権利関係を理解することが重要です。
賃借人が所有権を時効取得することはない
所有権の取得時効(民法162条)の成立要件は、次のすべての条件を満たすことです。
- 他人の物を
- 所有の意思をもって
- 平穏かつ公然と占有する
- 20年(善意かつ無過失の場合は10年)占有を継続する
賃貸物件の借主(賃借人)は、賃貸借契約を結んで物件を使用する権利(賃借権)を持っています。
しかし、「所有の意思をもって」利用しているわけではないため、20年住んだとしても所有権を時効取得することはありません。
また、賃借人は毎月賃料を支払いますが、賃料を支払うこと自体が自分の物であることや所有の意思を否定するものです。
所有権以外の財産権の時効取得はあり得るがハードルは高い
所有権以外の財産権についても、取得時効が成立する場合があります。
要件は、次の通りです(民法163条)。
- 自己のためにする意思をもって
- 平穏かつ公然と財産権を行使する
- 20年(善意かつ無過失の場合は10年)経過後にその財産権を取得する
所有権以外の財産権とは、地上権・地役権などの物権だけでなく、賃借権もあり得ます。
「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能である」とする判例もあります(最高裁昭和43年10月8日第三小法廷判決)。
しかし、賃借権の時効取得はハードルが高く容易ではありません。
賃貸の場合はすでに賃借権に基づく居住権がありますが、新たに居住権が発生することはありません。
アクロピースでは居住権など不動産問題全般のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
20年住んだ賃借人の「居住権」と立ち退き要求への対抗


居住権は法律に明文の規定はありませんが、他人が所有する家に継続して居住できる権利を「居住権」ということがあります。(自分の家に住む権利は所有権の当然の内容で通常居住権とはいいません)
法的に明確な定義がないとはいえ、日本の法律では、住む場所という生活の基盤を守るために借主(入居者)の権利を手厚く保護しています。
とくに20年と長期にわたって平穏に生活してきた場合、貸主側から一方的に契約を解除することが難しくなるのが特徴です。長期間の契約遵守の実績により、法的な保護がより強固になっていると理解しておきましょう。
ここからは、居住権について、次の3点を説明します。
居住権については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:居住権はどのくらい強い権利ですか?賃借権承継で不動産オーナーが知るべきこと
賃借人の居住権(賃貸借契約に基づく賃借権)
賃借人には賃貸借契約に基づく居住権(賃借権)があります。
賃借人には、賃料責務の不履行や無断転貸のような信頼関係を裏切る重大な契約違反などをしない限り、賃貸借契約を解除されないという借地借家法による強力な保護があります。
なお、賃借人が亡くなった場合も、相続人が賃貸借契約に係る権利義務を相続する(民法896条本文)ため、賃借権に基づく居住権は消滅しません。
同居人の居住権(居住用建物の賃貸借の承継)
賃貸物件の賃借人が死亡した場合に契約関係がなかった同居人の継続居住を認める「居住用建物の賃貸借の承継」(借地借家法36条)の規定があります。
これは、次の3つの条件を満たす場合に認められるものです。
- 賃借人が相続人なしで死亡した
- 同居者が賃借人と事実上の夫婦関係または養親子関係にあった
- 同居者が、賃借人の死亡を知ってから1か月以内に賃貸人に反対の意思表示をしていない
憲法で補償される25条生存権に基づく権利の1つとして、居住権を認めたものとされています。
配偶者の居住権
民法改正によって新たに「配偶者居住権」という制度が創設され、2020年4月1日から施行されました。
これは持ち家の所有者が死去した場合に、その配偶者の継続居住を認めるものです。
被相続人が亡くなった後も引き続き賃料の負担なく住み続けられる権利で、遺産分割協議等によって取得することができます(民法1028条)。
賃貸に20年住むメリットとデメリット


同じ賃貸物件に20年も住み続けることには、メリットもデメリットもあります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
賃貸に20年住むメリット
賃貸に20年住むメリットは次の通りです。
- 引越しの手間や費用がかからない:
-
引っ越すとなれば、引越し先の物件探しや荷造り、転居届などの手間がかかり、引越代などの費用も発生します。
短期間に引越しを繰り返せば相当な負担になりますが、同じ物件に住み続ければ、これらの手間と費用は不要です。
- 退去費用が安くなる可能性がある:
-
賃貸物件から退去する場合、原状回復費用などの退去費用が必要です。
しかし、長期間住み続けることで耐用年数を過ぎたものは経年劣化とされ、原状回復が大家側の負担となる可能性があります。
耐用年数(例:壁紙6年、給排水設備15年など)を超えるものが増えれば、自己負担分が減り、退去費用が安くなる可能性があるのです。
賃貸に20年住むデメリット
一方で、賃貸に20年住むデメリットもあります。
- 設備が古いまま:
-
賃貸の設備は、賃借人が替わるタイミングで更新されるのが通例です。
他の部屋より使い勝手や機能が劣るものを使い続けることになる可能性があります。
- 他の人より家賃が高い場合がある:
-
家賃は経年劣化や家賃相場によって変わりますが、既存の家賃に反映されるとは限りません。
新規募集家賃は下げるが、すでに住んでいる方の家賃は変えない場合もあるでしょう。
ただし、立地や経済環境などによっては、新規募集家賃の方が高い場合もあります。
賃貸に20年住んだ場合の原状回復費用は?
長く住んだ賃貸を退去する際に気になるのが、原状回復費用(敷金の返還)です。
「20年分の汚れがあるから、高額なクリーニング代や修繕費を請求されるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、実は長く住めば住むほど、借主が負担すべき費用は安くなるのが特徴です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、建物や設備の価値は時間が経つにつれて減少する(減価償却)という考え方が採用されています。
具体的には、以下のようなルールが目安となります。
- 壁紙(クロス)などの耐用年数は6年
- 6年経過時点で、その設備の残存価値は「1円」
- 20年住んでいる場合、通常の使用による劣化や経年劣化分の価値はほぼゼロとみなされる
20年住んだ部屋の壁紙が日焼けで黄ばんでいても、その価値はすでに償却されているため、張り替え費用を借主が負担する必要は原則としてありません。
しかし、特別損耗(故意・過失による損傷)には注意が必要です。いくら長く住んでいても、借主の不注意や手入れ不足で生じたダメージは、賠償の対象となるリスクがあります。
| 損耗の種類 | 具体例(借主負担になる可能性が高いもの) | 20年居住後の負担の考え方 |
|---|---|---|
| 通常損耗・経年劣化 | ・家具設置による床の凹み ・日照による畳やクロスの変色 ・画鋲の穴(下地を傷つけない程度) | 原則負担なし(価値が償却されているため) |
| 特別損耗(故意・過失) | ・タバコのヤニによる変色や臭い ・ペットによる柱のキズや臭い ・掃除を怠ったことによる風呂場のカビ ・引越し作業でつけた壁の穴 | 負担が発生する可能性あり(ただし、経年劣化分を考慮して減額される場合もある) |
このように、20年住んだからといって「何をしても請求されない」わけではない点に注意が必要です。
20年住んだ賃貸の修繕費の負担は貸主?借主?
ここでは、20年住んだ賃貸物件でよくある具体的な損傷ケースについて、修繕費用の負担が「貸主(大家)」と「借主(入居者)」のどちらになるのかを解説します。
ご自身の部屋の状況と照らし合わせて確認してみましょう。
ケース1:日焼けした畳・フローリング(貸主負担)
窓際の日差しによって畳が変色したり、フローリングの色が褪せてしまったりするケースです。これは自然現象による経年劣化に該当するため、修繕費用は原則として貸主の負担となります。
入居者が通常の生活をしていても避けられない損傷です。20年も住んでいれば、畳や床材自体の耐用年数を超えているケースも多く、借主が張り替え費用を出す必要性は低いといえます。
しかし、雨の吹き込みを放置して窓枠や床を腐らせてしまった場合は「善管注意義務違反」として借主負担になる可能性があります。
ケース2:家具を置いて凹んだ床(貸主負担)
冷蔵庫・テレビ台・ベッドなどの重い家具を20年間同じ場所に置くと、床に凹みが生じます。
これも、生活する上で家具を置くことは必須であるため、通常損耗として扱われます。原則として、貸主の負担となるのが特徴です。
カーペットの設置跡なども同様です。これらは次の入居者のために貸主側で行うグレードアップや修繕の一環とみなされます。
ケース3:飼い猫がつけた柱の傷(原則借主負担)
ペット可の物件であっても、飼い猫や犬が柱で爪とぎをしてできた傷や、おしっこによるシミ・臭いは残ります。これは特別損耗(故意・過失)に分類されるため、原則として借主の負担です。
ペットによる損傷は、通常の使用を超えた使い方とみなされます。たとえ20年住んで建物の価値が下がっていたとしても、柱そのものの交換や特殊な消臭クリーニングが必要な場合、修繕費を請求されるリスクが高いです。
柱などの構造部分は壁紙と違って減価償却の期間が長いため、高額請求になりやすいポイントです。
ケース4:エアコンや給湯器の故障(原則貸主負担)
入居当初から設置されていたエアコンや給湯器が、20年経って動かなくなったり故障したりすることは珍しくありません。設備機器の寿命による故障であるため、修理・交換費用は貸主の負担となります。
賃貸物件の設備は、貸主が借主に提供・維持管理する義務があります。20年前の設備であれば耐用年数を大きく超えているため、借主が修理代を払う必要はありません。
しかし、フィルター掃除を20年間一度もしなかったことが原因で故障したなど「明らかな管理不足」がある場合は、費用の一部を請求される可能性があります。



自分のケースで修繕費の負担が必要か知りたい場合は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人アクロピースでは、不動産問題に精通した弁護士があなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切な解決策をご提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
賃貸に20年以上住む賃借人に貸主は退去を求められるか


契約違反がない場合に立ち退きを求める場合、半年前の予告が必要(借地借家法第26条1項本文)で、かつ、正当事由が必要(借地借家法第28条)です。
正当事由の有無は、貸主が立ち退きを求める必要性と賃借人の使用の必要性を比較して判断されます。
正当事由に該当し得るのは次のような場合です。
- 貸主が使用する必要がある:
-
他に借りられる家がない緊急性が必要です。
- 生計のために売却する必要がある:
-
収益物件として売却できる場合は認められない可能性が高いでしょう。
- 建物の老朽化により建替え・取壊しの必要がある
-
倒壊の危険性がある場合などに限られる傾向があります。
- 貸主が立退料を提供したときは正当事由の補完となり得る:
-
正当事由が認め難いときでも、適正な立退料を払うことで立ち退き要求が認められることがあります。
20年以上経過で老朽化を理由とする立ち退きが認められることもありますが、立退料が前提となる可能性が高いでしょう。
ただし、入居者の悪質な契約違反や違法行為があった場合は、立退料を支払う必要はありません。
立退料は、移転先の契約費用(家賃・敷金・礼金・手数料等約50万円)に引越費用(荷物の量、移転先等により異なる)となる場合が多いが、迷惑料が付加されることもあります。
立ち退きの正当事由については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
賃貸のトラブル対応を弁護士に依頼するメリット


賃貸物件からの立ち退きなどのトラブル対応を弁護士に依頼するメリットは以下のようなことがあります。
- 冷静に対応できる
- 交渉の不安が解消される
- 労力と時間を節減できる
- 合理的な立退料を算定できる
一方で、弁護士に依頼すれば当然のことですが、費用がかかりますが、賃貸からの立ち退きなどをめぐるトラブルは1人で対応するのは難しい問題です。
弁護士に相談して、早期解決を図りましょう。
弁護士法人アクロピースなら、共有不動産に強く、交渉・裁判手続はもちろん、その後の税務・登記手続まですべてお任せいただけます。
共有名義の不動産売却をめぐるトラブル対策については、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
Q1. 無料相談だけでも利用できますか?
相談だけでも全く問題ありません。正式な依頼に至らなくても、弁護士と話すだけで「自分のケースで立ち退きを拒否できる見込みがあるか」「請求されている修繕費が妥当か」といった法的な見通しを立てられます。
Q2. 弁護士費用はいつ、どのタイミングで決まりますか?
必ず契約前に明確な見積もりが提示されます。「相談したらいつの間にか費用が発生していた」ということは絶対にありませんのでご安心ください。
Q3. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その場で依頼を決める必要はありません。提案された解決方針や費用、そして弁護士との相性を確認し、じっくり検討してみてください。
関連記事:共有持分買取業者への売却トラブル回避法!持分現金化は弁護士に相談すべき理由
関連記事:共有不動産と知らず相続した土地の時効取得条件について
賃貸に長く住んでいる場合の居住権に関するQ&A


賃貸に長く住んでいる場合の居住権に関するQ&Aを紹介します。
1.長く住んでいる賃貸物件には「居住権」があるのか?
「20年以上住んでいるけど、オーナーから立ち退きを求められた。退去しなければならないのか」「20年以上も住んでいるのだから住権が発生するのでは?」などと思う方もいるでしょう。
賃貸契約がある場合、賃借人は賃借権に基づき、契約に従って住み続けることができます。
しかし、長く住んだからといって新たに居住権が発生することはありません。
重大な契約違反などがあれば、退去を求められることもあります。
2.賃貸契約を繰り返し更新して20年経った場合の借家人の法的な立場はどうなる?
「賃貸契約を繰り返し更新して20年も経つと借家人の法的な立場は強くなるのでは」と思う方もいるでしょう。
大家さんから退去を求められた場合、これまで賃貸借契約が更新されてきたことは、立退要求の正当事由の考慮事項の1つの要素にはなります。
しかし、20年経ったという事実だけで賃借人に特別の権利が発生することや賃借人の地位に対する保護の程度が強くなることはありません。
3.「居住権」という新しい制度ができたと聞くが、賃借人の立場が強くなったのか?
民法改正によって「配偶者居住権」が新設され、2020年4月1日から施行されています。
この制度は、夫婦が持ち家に住んでいた場合に、所有権を持つ配偶者が死去しても、配偶者は引き続き住む権利があるとする制度です。
通常の賃貸物件の賃借人やその配偶者の居住に関する権利を認めた規定ではありません。
配偶者居住権については下記の記事をご覧ください。
関連記事:配偶者居住権をわかりやすく解説!発生する場合やメリットについて
まとめ|賃貸に20年以上住んでいるなら一度弁護士に相談しよう
本記事では、賃貸物件に20年以上住み続けた場合の権利関係や、時効取得の可能性、退去時の費用負担について解説しました。
賃料を支払っている以上、所有の意思がないとみなされ、どれだけ長く住んでも物件が自分のものになることはありません。
しかし、壁紙などの設備は経年劣化により価値が減少するため、退去時の修繕負担はガイドラインに基づき大幅に軽減される可能性があります。
「立ち退き料に納得がいかない」「高額なリフォーム代を請求された」といったトラブルに直面した際は、一人で抱え込まずに専門家に相談しましょう。
弁護士法人アクロピースでは、不動産トラブルに強い弁護士が、あなたの長年の居住実績を正当に評価し、守るべき権利を主張します。
初回60分の無料相談も実施しているので、今後の見通しや最善の解決策についてぜひ相談してみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応