【無料相談受付中】24時間365日対応
共有持分を譲渡する4つの方法とは?手続きや税金・注意点をプロが解説

「共有持分を譲渡したいけど、どうすればいいかわからない」
「他の共有者とトラブルにならずに手続きを進めたい」
共有持分の不動産について、上記のような悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。共有持分の譲渡は、専門的な知識が必要で、かつ手続きも複雑なため、1人で解決するのは負担の大きい問題です。
本記事では、共有持分の基本的な知識から、具体的な4つの譲渡方法、手続きの流れを解説します。注意点や税金についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有持分の4つの譲渡方法
共有持分を譲渡するには、主に以下の4つの方法があります。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、ご自身の状況や目的、他の共有者との関係性を考慮して最適な方法を選ぶことが重要です。
「共有持分」について、理解を深めたい方は下記記事を参考にしてみてください。
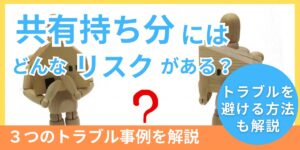
専門の買取業者など第三者に売却する
共有持分を譲渡する方法の一つに、自身の共有持分のみを専門の買取業者や個人投資家などの第三者に売却する方法があります。
この方法のメリットは、他の共有者の同意が不要で、スピーディーに手続きを進められる点です。以下のような場合に有効な選択肢といえるでしょう。
とにかく早く現金化して共有関係から抜け出したい場合のようなときは、有効な選択肢となることもあるでしょう。
ただし、買い主は権利関係が複雑な不動産を取得するため、将来的なリスクを考慮して買取価格を決定します。そのため、不動産の市場価格から算出した持分割合の価格よりも、大幅に安くなる傾向がある点には注意が必要です。
共有不動産の売却については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有名義のマンションを売却するには?売却方法や費用・注意点を弁護士が解説

他の共有者に譲渡(売買・贈与)する
自身の共有持分を、他の共有者に対して売却または贈与する方法も選択肢の一つです。
他の共有者が持分を買い取ることで、その共有者は不動産に対する権利の割合を高められます。将来的には単独所有を目指せるため、他の共有者にとってもメリットがある提案といえるでしょう。
売買と贈与のそれぞれ特徴は、以下の表のとおりです。
| 売買の場合 | 他の共有者と価格交渉を行い、売買契約を締結します。 市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。 |
|---|---|
| 贈与の場合 | 無償で持分を譲ります。 受け取った側に高額な贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。 |
この方法は、相手に十分な資金力がある場合に有効です。円満に共有関係を解消できる可能性が高い方法の一つといえるでしょう。
以下の記事では、共有名義の不動産を単独名義に変更する手続きについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
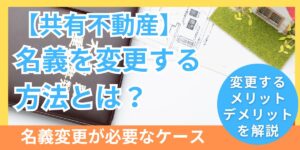
共有持分の権利を放棄する
共有持分の権利そのものを放棄することも選択肢の一つです。持分を放棄すると、その権利は民法の規定に基づき、他の共有者に帰属します(民法第255条)。
共有持分の権利を放棄する際は、以下の3点を覚えておきましょう。
- 放棄には対価(お金)は発生しない
- 登記手続きには他の共有者の協力が必要
- 放棄により持ち分が増える共有者に贈与税が課される可能性がある
この方法は、固定資産税の負担などから逃れたいものの、売却するほどの手間や費用はかけたくない場合に適しています。
持分放棄後は、放棄による所有権移転を登記しておかないと、第三者に対して権利関係を主張できなくなります。また、登記名義が残ったままの状態では、実務上、固定資産税の課税通知が届くなどのトラブルが生じるおそれがあります。
放棄する場合でも、放棄する前に他の共有者と所有権移転登記の協議をし、可能であれば司法書士に依頼して確実に登記できるように進めましょう。
出典:e-Gov法令検索|民法
共有持分の放棄について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

「共有物分割訴訟」で共有関係を解消する
当事者間の話し合いで解決できない場合、裁判所に共有物分割訴訟を提起して、法的な手続きによって共有関係を解消する方法も挙げられます。
共有物分割訴訟を提起すると、裁判所が分割方法を決定します(民法第258条)。その際、候補となる主な分割方法は以下の3つです。
| 現物分割 | 不動産そのものを物理的に分割する方法 |
|---|---|
| 代償分割 | 共有者の1人が不動産全体を取得し、他の共有者に持分相当額の金銭を支払う方法 |
| 換価分割 | 不動産全体を売却し、その代金を持分割合に応じて分配する方法 |
共有物分割訴訟は、共有関係を確実に解消できる手段です。しかし、訴訟に発展するため時間や費用がかかります。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫まずは協議による解決を目指し、それが難しい場合は共有物分割訴訟で解決を図ると考えるべきでしょう。
出典:e-Gov法令検索|民法


以下の記事では、共有物分割訴訟にかかる弁護士費用について詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。
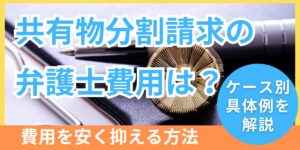
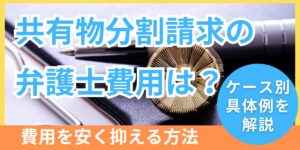
【ステップで解説】共有持分の譲渡手続きの流れ
共有持分の譲渡は、適切な手順を踏んで進めることが重要です。ここでは、専門の買取業者に売却する場合を例に、一般的な手続きの流れを5つのステップで解説します。
ステップ1|譲渡方法を決定して専門家に相談する
まずは、前述した4つの方法の中から、どの方法で譲渡を進めるかを決定します。以下のように自身の状況や希望を整理し、適切な選択肢を検討しましょう。
- 「早く現金化したい」→買取業者への売却
- 「高く売りたい」→他の共有者への売却や共有物分割協議
- 「対価は不要」→持分の放棄
専門家に相談すれば、法的なリスクや手続きの細部について的確なアドバイスを提供してくれます。
ご自身の意向に沿った解決だけなく、最適な解決策がどの方法なのかもアドバイスを受けられるので、専門家と相談しながら進めるのが良いでしょう。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
ステップ2|不動産の査定と当事者間での価格交渉を行う
次に、対象となる不動産の価値を把握するために査定を依頼します。その際、以下の査定額を参考に売却価格の交渉を行うことも重要です。
- 不動産全体の市場価格
- 共有持分のみの買取価格
相手が買取業者の場合は、複数の業者から査定を取り、条件を比較検討します。相手が他の共有者の場合は、客観的な査定結果を基に、冷静に話し合いを進めましょう。
感情的な対立を避け、双方が納得できる価格で合意を目指すことが大切です。
専門家に依頼をすることで、不動産業者を通じて適切な不動産価格の査定を算出してもらえるだけでなく、感情的な対立を避けながら合意を目指しやすくなるでしょう。
ステップ3|必要書類を準備する
売却価格について合意ができたら、契約と登記手続きに必要な書類を準備します。一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 実印と印鑑証明書
- 登記済権利証または登記識別情報通知
- 固定資産評価証明書
これらの書類は、契約や所有権移転登記の際に法務局へ提出します。
不備があると手続きが滞るため、事前にリストアップし、計画的に準備を進めましょう。
ステップ4|売買(または贈与)契約を締結する
準備した書類を基に、売買契約書(または贈与契約書)を作成し、当事者間で契約を締結します。契約書には、以下の内容を正確に記載することが大切です。
- 対象不動産の情報
- 売買代金(または贈与である旨)
- 支払条件
- 所有権移転の時期
- 契約不適合責任に関する定め
とくに、契約内容は後のトラブルを防ぐための重要な証拠となります。内容に不明な点や不安な点があれば、契約前に専門家に確認しましょう。
契約書の内容に双方が合意したら、署名・捺印して契約を正式に成立させます。
ステップ5|代金決済と所有権移転登記を申請する
売買契約締結後、買い主から売主へ売買代金の支払い(決済)が行われます。決済は、銀行振込などで行われるのが一般的です。
代金の受領を確認したら、速やかに所有権移転登記の手続きを法務局で行います。
所有権移転登記は、不動産の権利関係を公に示すための重要な手続きです。この登記をもって、法的に所有権が買い主に移転したことになります。
関連記事:兄弟での不動産共有名義は危険?



登記が完了すれば、共有持分の譲渡に関する一連の手続きは終了です。
共有持分の譲渡が難しいと言われる理由
共有持分の譲渡は、通常の不動産売買と比べて「難しい」と言われることがあります。
その理由は、主に以下の3つです。
それぞれ具体的に解説します。
買い手が見つかりにくい
共有持分の譲渡が難しいとされる理由は、買い手が限定されることです。
以下のような権利上の制約があるため、一般の個人が居住目的や投資目的で購入するケースは稀です。
- 不動産を利用するには他の共有者との調整が必要
- 不動産全体を売却するには他の共有者全員の同意が必要
結果として、買い手は共有持分を専門に取り扱う不動産業者や、将来的に不動産全体の所有を目指す他の共有者に限られることが多くなります。
共有持分の売却に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。
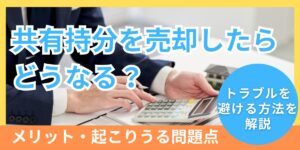
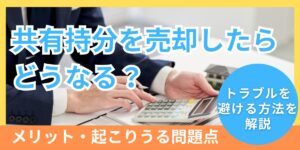
納得できる値段で売れにくい
買い手が見つかりにくいという事情は、売却価格にも影響します。
買い手は、不動産を自由に使えないことの権利関係の複雑さや、共有状態を解消するには他の共有者との交渉が必要になるといった将来的なリスクを考慮せざるを得ません。
そのため、共有持分の買取価格は、不動産全体の市場価格に持分割合を掛けた金額よりも低くなるのが一般的です。



高値での売却を期待していると、現実とのギャップに直面する可能性があるでしょう。
他の共有者との対立やトラブルが発生する恐れがある
共有持分の譲渡は、他の共有者との人間関係に影響を与える可能性があります。
とくに、自身の持分を第三者である専門の買取業者に売却する場合は注意が必要です。買取業者は、他の共有者に対して共有持分の売却を迫ったり、逆に共有者の持分を売却するよう迫ったりすることが多いです。
また、第三者が共有者となったことで、他の共有者が納得せず、共有者との関係が悪化することもあるでしょう。
事前に他の共有者へ説明するなど、可能な限りの配慮をすることが望ましいですが、第三者が介入することで、これまでの関係が崩れて、必ずしも円満に解決できるとは限りません。
他の共有者との対立やトラブルが発生をすることに懸念があるなら、弁護士に相談することが大切です。弁護士であれば、状況に応じて適切な解決方法を提案してくれるでしょう。
共有名義の不動産のトラブルについては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有名義の不動産売却はトラブルに要注意!回避策とスムーズに売る方法
共有持分を譲渡する際の「他の共有者への通知・連絡義務」はある?
共有持分を第三者へ譲渡する際、事前に他の共有者に通知・連絡する義務はありません。各共有者は自分の持分を自由に処分できる権利を持っており、共有者全員の同意や承諾は原則不要です。
ただし、他の共有者に無断で持分を売却することで、共有関係に第三者が入りトラブルに発展するケースも多いのが実情です。そのため、譲渡前に他の共有者へ意向を伝え、理解を得ておくことが望ましいです。
とくに相続などで共有者が多い場合、疎遠な関係者が知らない第三者と共有関係になることを避けたいと考える場合も珍しくありません。後々の関係悪化を防ぐうえで、事前の連絡は重要です。



義務ではないものの、信頼関係の維持とスムーズな手続きを進めるためには、誠実な情報共有が不可欠といえるでしょう。
共有持分の譲渡をする際の注意点
共有持分の譲渡をスムーズに進めるためには、いくつか重要な注意点があります。後悔しないためにも、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
それぞれ、具体的に解説します。
他の共有者への通知・説明を行う
自身の持分を譲渡するのに他の共有者の同意は不要ですが、事前の通知や説明は行いましょう。
何の連絡もなしに譲渡を進めると、他の共有者に不信感を与え、将来的なトラブルの原因になりかねません。
とくに買取業者等の第三者に売却をする場合には、共有者にも共有持分の買い取り等が迫られる可能性もありますので、事前に伝えておくのが望ましいでしょう。
誠実な対応を心がけることで、無用な対立を避け、円満な解決につながる可能性が高まります。
自身の持分割合を明確にしておく
譲渡手続きを始める前に、正確な自分の持分割合を把握しておくことが不可欠です。持分割合は、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)で確認できます。
相続を繰り返している場合など、認識していた持分割合と登記上の割合が異なっているケースも珍しくありません。
持分割合が売却価格や税金の計算の基礎となるため、必ず最新の登記事項証明書で確認しましょう。
住宅ローンの残債の有無を確認する
対象の不動産に住宅ローンが残っている場合は、手続きが複雑になります。住宅ローンを組む際、不動産に抵当権が設定されている可能性があるためです(民法第369条)。
抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に、金融機関が不動産を競売にかける権利のことを指します。金融機関の承諾なしに名義変更(譲渡)すると、ローン契約違反になる可能性があるため注意が必要です。
住宅ローンが残っている状態で譲渡を検討する場合は、まず金融機関に相談し、抵当権をどう扱うかについて協議しましょう。



自己判断で進めず、専門家と金融機関を交えて対応することが大切です。
出典:e-Gov法令検索|民法
譲渡所得が発生した場合は確定申告をする
共有持分を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
- 取得費:不動産を購入したときの代金や手数料
- 譲渡費用:売却時にかかった仲介手数料や印紙税など
この譲渡所得が発生した場合は、不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、税務署で確定申告を行い、納税する必要があります。
申告を忘れると追徴課税の対象となるため、忘れずに行いましょう。
また、マイホームとして使用していた不動産の持分を売却した場合、一定の条件を満たせば「3,000万円特別控除」などの特例が適用される可能性があります。
ただし、共有持分全体の一部譲渡では要件を満たさないケースもあるため、事前に税理士へ確認が必要です。
不安な場合はすぐに弁護士など専門家に相談する
共有持分の譲渡は、法律や税金、不動産取引の知識が複雑に絡み合います。
少しでも手続きに不安を感じたり、他の共有者との交渉が難航しそうだと感じたりした場合は、ためらわずに専門家に相談することが重要です。
主な専門家は、以下のとおりです。
- 弁護士:法律問題や共有者間のトラブル解決の専門家
- 司法書士:登記手続きの専門家
- 税理士:税金計算や確定申告の専門家
早期に相談することで、問題を未然に防ぎ、時間的・精神的な負担を軽減できるでしょう。
共有持分を譲渡したあとの「税金と確定申告」の実務ポイント
共有持分を譲渡して利益が出た場合、確定申告を行う必要があります。
確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日までに行い、納税手続きは共有者全員がそれぞれ自身で実施しなければなりません。
確定申告には、主に以下の書類が必要です。
- 確定申告書B様式
- 分離課税用申告書
- 売買契約書の写し
- 譲渡所得の内訳書
- 取得時の売買契約書と領収書
申告を怠った場合は、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。当初から大幅に増額されてしまうため、忘れずに申告するようにしましょう。
共有持分の譲渡は複雑な計算を伴うため、税理士へ相談するとよいでしょう。
共有持分の譲渡で発生する可能性がある税金
共有持分を譲渡する際には、さまざまな税金が発生する可能性があります。どのような税金が、誰に、いつかかるのかを事前に理解しておくことが重要です。
譲渡所得税|売却した場合にかかる税金
共有持分を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に、売主に課される税金です。
譲渡所得の金額や、不動産の所有期間によって税率が異なります。
課税譲渡所得金額の計算式は、以下のとおりです。
課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)
その後、課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
※土地や建物を売った年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
贈与税|贈与した場合にかかる税金
共有持分を無償で譲渡(贈与)した場合に、贈与を受けた側(買い主)に課される税金です。
年間の基礎控除額(110万円)を超える価値の贈与を受けた場合に申告・納税の義務が生じます。税率は、基礎控除後の課税価格に応じて超過累進税率で計算されるのが特徴です。
詳しくは、国税庁の情報を参考にしてみてください。
出典:国税庁|贈与税のしくみ
登録免許税|登記をする際に必要な税金
不動産の所有権が移転したことを登記する際に、取得した側(買い主)が法務局に納める税金です。
税額は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。
売買・贈与・相続など、所有権移転の原因によって税率が異なる点に注意が必要です。
| 売買 | 固定資産税評価額の2.0% (令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5%) |
|---|---|
| 贈与 | 固定資産税評価額の2.0% |
| 相続・法人の合併または共有物の分割 | 固定資産税評価額の0.4% |
不動産取得税|取得した側にかかる税金
売買や贈与によって不動産を取得した際に、取得した側(買い主)に対して一度だけ課される都道府県税です。
不動産取得税の納税額の計算方法は、以下のとおりです。
納税額=不動産の評価額×税率(4%)
※税率は原則4%ですが、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。
登記後、しばらくしてから都道府県から納税通知書が送られてきます。見落とさないよう、覚えておきましょう。
出典:総務省|不動産取得税



不動産取得税は相続では非課税ですが、贈与による取得の場合は課税されます。
共有持分の譲渡に関するよくある質問
ここからは、共有持分の譲渡に関するよくある質問に回答します。適切に手続きを進めるためにも、事前に疑問点をなくしておきましょう。
共有持分の譲渡の際、他の共有者の同意は必要?
自身の共有持分のみを譲渡する場合、他の共有者の同意は必要ありません。民法上、各共有者は自己の共有持分を自由に処分できると定められています。
ただし、不動産全体を売却する場合は、共有者全員の同意が必須です。
他の共有者の同意は必要なくても、無断で売却をするとトラブルの原因となります。持分を譲渡する前に、他の共有者へ一言伝えておくことが大切です。
住宅ローンが残っていても譲渡できる?
金融機関の承諾があれば可能ですが、手続きは複雑になります。
住宅ローンが残っている不動産には、金融機関の抵当権が設定されているためです。まずはローンを組んでいる金融機関に相談する必要があります。
自己判断で進めず、専門家と金融機関を交えて協議しましょう。
弁護士にはどのタイミングで相談すればいい?
弁護士には、できるだけ早い段階での相談をおすすめします。とくに、以下のような状況であれば、すぐに相談を検討しましょう。
- 他の共有者との関係が悪く、話し合いが難しい
- 提示された条件に納得できない
- 共有物分割請求など法的手続きを検討している
- 手続き全体に不安があり、専門的なサポートを受けたい



弁護士に早期に相談することで、交渉を有利に進められたり、法的なリスクを回避できたりするなど、多くのメリットがあります。
また、弁護士に相談することで、弁護士と提携している司法書士や税理士を紹介してもらえて、登記や税金もまとめて手続きを行える可能性があります。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
まとめ|共有持分の譲渡に関する悩みは専門家へ相談し、適切に対処しよう
共有持分は不動産の所有権の割合であり、単独で譲渡可能です。ただ、他の共有者への配慮や税金の申告が必要な点には注意しましょう。
共有持分の譲渡は、法律や税務が絡む複雑な手続きです。1人で抱え込まず、まずは早い段階で弁護士や専門の不動産業者など、信頼できる専門家に相談することが大切です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









