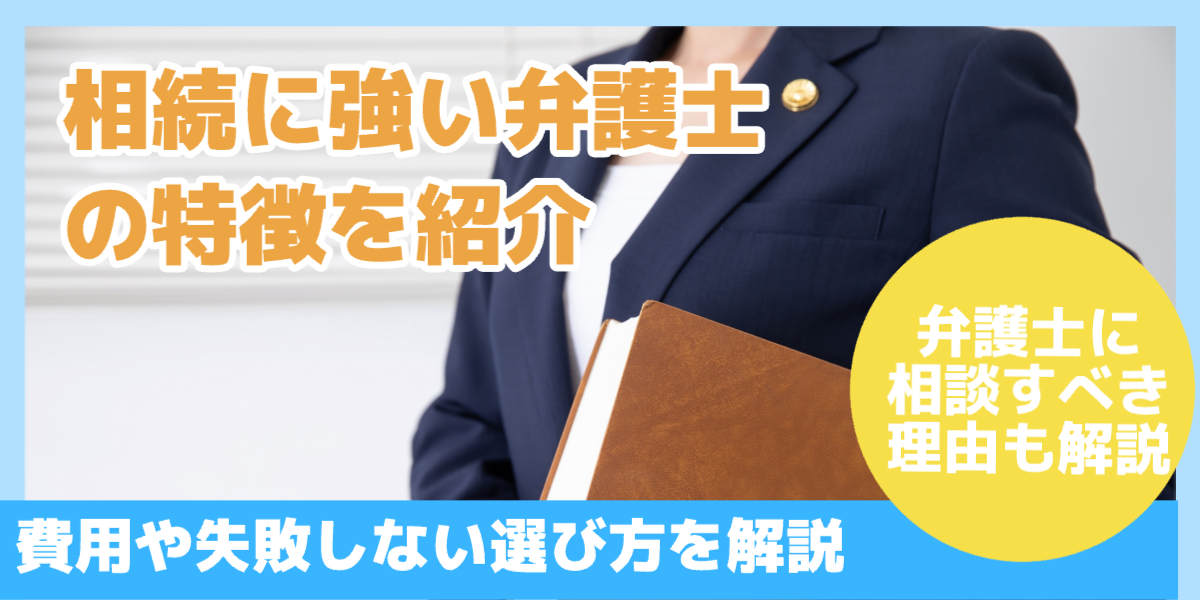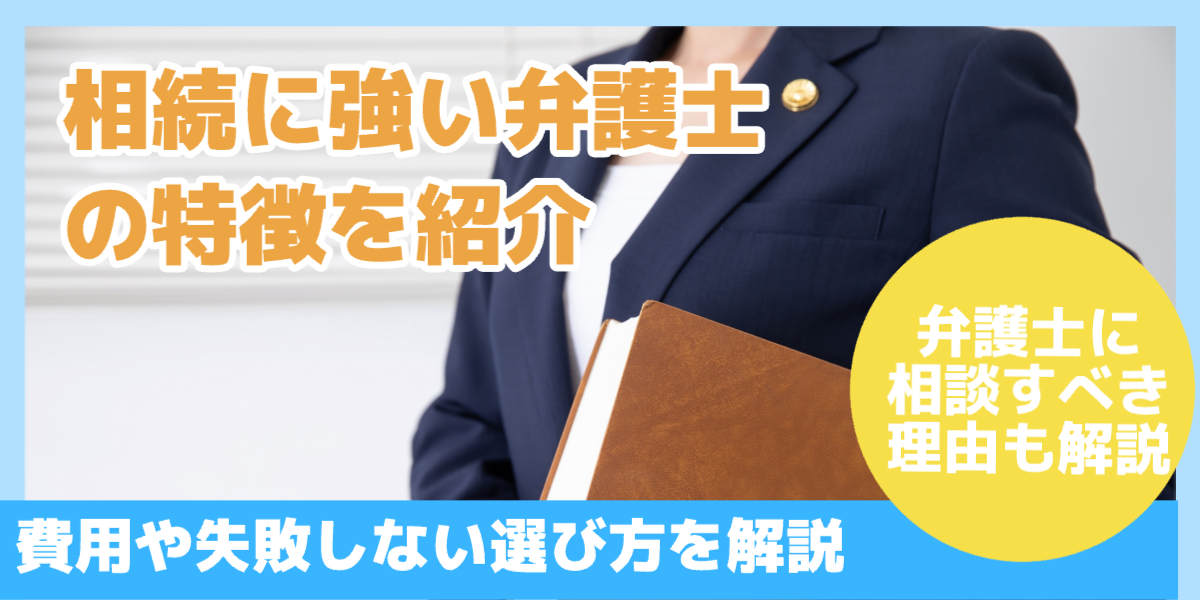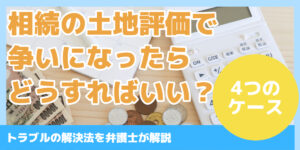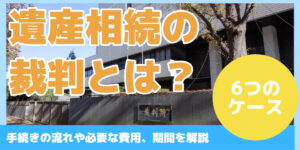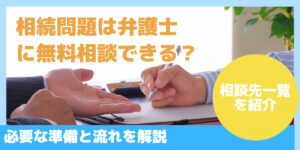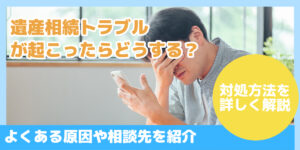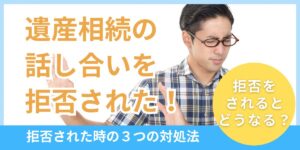【無料相談受付中】24時間365日対応
死亡した人の銀行口座をそのまま使うことはできる?使い続けるとどうなるか引き落としなどの問題点・必要な手続きを解説
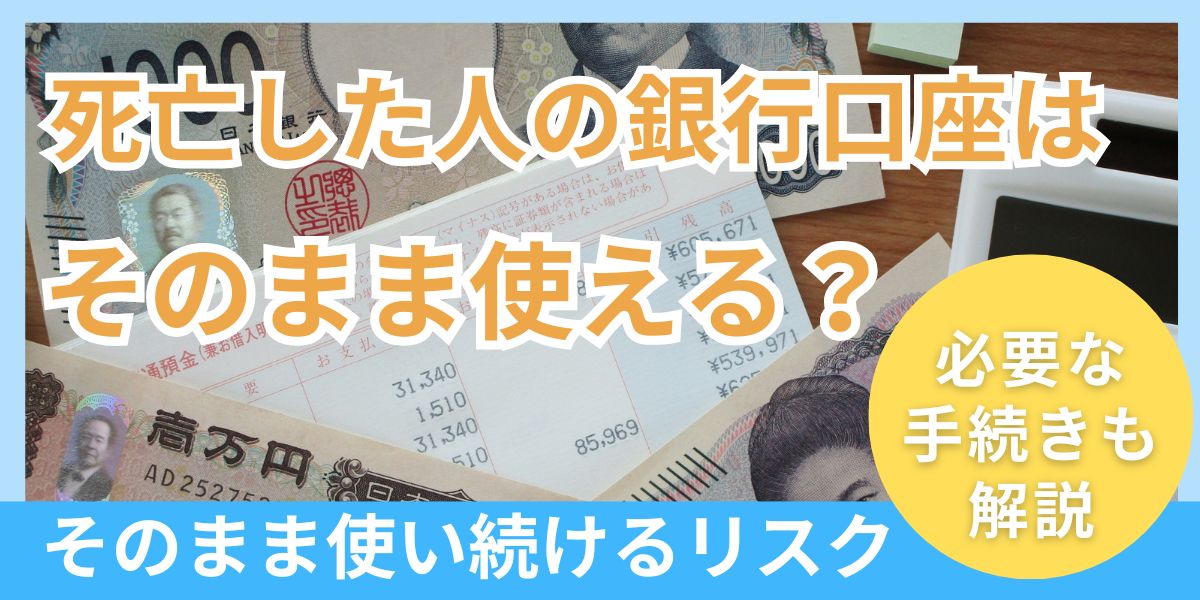
死亡した人の銀行口座については、そのまま使い続けるのではなく相続手続きが必要です。
そのまま使い続けると、相続トラブルの原因となったり、刑事責任を問われたりする可能性もあります。
この記事では、死亡した人の銀行口座をどうすべきかお悩みの方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
死亡した人の銀行口座を管理している人は、すぐに相続手続きを始めてください。
手続きをスムーズに進めるために、この記事をぜひ最後までご覧ください。
アクロピースでは口座の相続手続きなど相続問題全般のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
死亡した人の銀行口座はどうなる?

死亡した人の銀行口座については、相続手続きや払戻しまでの期限が設定されておらず、放置していても罰則はありません。
ただし、銀行口座の相続手続きを放置すると、相続放棄や相続税の申告などの期限のある相続の手続きが進められなくなる可能性があります。
たとえば、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内とされています。
誰が預金を相続するのか、預金残高がどのくらいかがわからなければ、相続税の申告を進めることができなくなってしまうでしょう。
銀行が口座名義人の死亡を確認すると、口座は凍結されます。
相続人が銀行に被相続人の死亡を報告する義務はありませんが、報告すると口座の不正利用の心配はなくなります。

銀行口座には使用期限がありませんが、相続税の申告期限は10か月以内と定められています。預金の残高を早めに確認することが、申告漏れのリスクを防ぐ第一歩になります。
関連記事:相続で預貯金の名義変更をするには?期限や株式・不動産の名義変更についても解説
死亡した人の銀行口座をそのまま使うとどうなる?


死亡した人の銀行口座をそのまま使い続けると、次のようなリスクがあります。
リスクを避けるためには、早急に銀行口座の相続手続きを済ませるべきです。
ここでは、それぞれのリスクの内容について詳しく解説します。
相続放棄ができなくなる
死亡した人の銀行口座から引き出したお金を自分のために使うと、相続を単純承認したものとみなされて、相続放棄ができなくなります。
相続放棄とは、相続財産の承継を一切放棄する手続きです。
被相続人の預金は相続財産の一部なので、預金を使ったあとの相続放棄は認められません。
相続するか、相続放棄するかは、相続財産を調査したうえで判断すべきです。
相続財産の調査前に相続を単純承認してしまうと、被相続人に大きな負債が発覚した場合でも相続放棄ができなくなってしまいます。
死亡した人の銀行口座をそのまま使い続けると、後になって相続放棄したいと思っても相続放棄ができなくなってしまうリスクがあります。
相続争いの原因となる
相続財産は、誰が相続するかが決まるまでは相続人全員の共有財産となります。
共有財産である預金を勝手に使うと、相続争いの原因となります。
死亡した人の銀行口座を利用して他の相続人の取り分まで引き出してしまうと、不当利得返還請求や損害賠償請求を受ける可能性があるため注意が必要です。
相続争いを避けるには、勝手に銀行口座を利用せず、緊急の必要があるときには引き出し額と使途を他の相続人に明確に説明できるようにしておきましょう。
刑事責任を問われる可能性がある
相続人であっても、被相続人の銀行口座を勝手に使用する権利はありません。
死亡した人の銀行口座を使うと、窃盗罪や横領罪などの刑事責任を問われる可能性があります。
被相続人の同居の親族については、親族相盗例が適用されるため刑事責任を問われることはありません。
しかし、親族以外の人や同居していない親族が死亡した人の銀行口座を使用する場合、親族相盗例が適用されないため刑事責任を問われる可能性があるのです。
死亡した人の銀行口座を使い続けるリスクについて、詳しくはこちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:死亡した人の預金をおろすと罪になるのか?よくある相談例・解決策



被相続人の口座を無断で使ってしまうと、相続放棄ができなくなったり、刑事責任を問われる可能性があります。たとえ家族であっても、ルールに従って手続きを進めることが大切です。
銀行口座の持ち主が死亡したときに必要な手続き
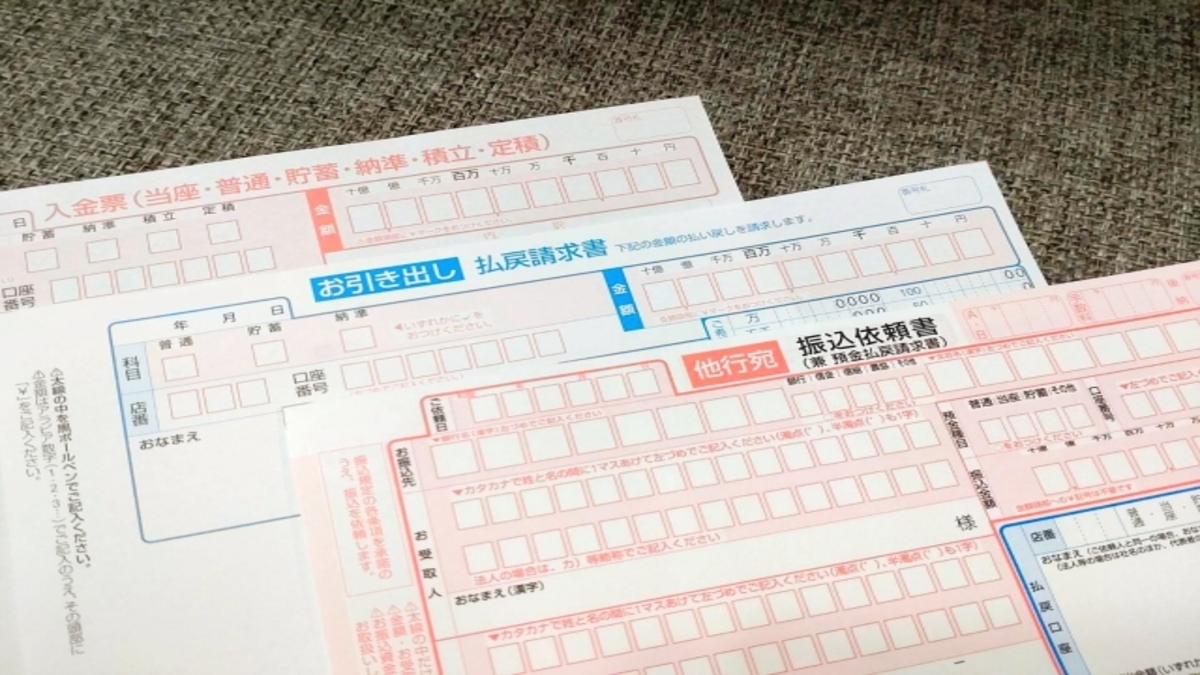
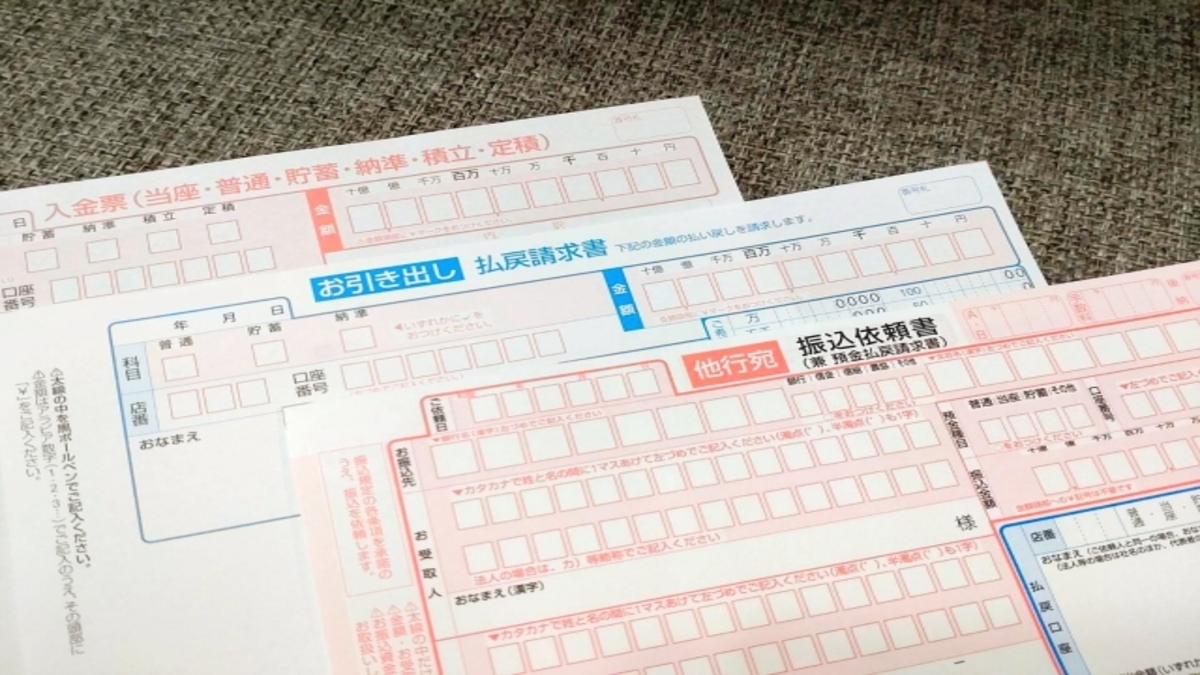
銀行口座の持ち主が死亡した場合、最終的には相続手続きで誰が預金を相続するかを決める必要があります。
相続手続きには時間がかかる場合もあるので、まずは次の手続きを進めてください。
それぞれの手続きについて解説します。
引き落とし口座の変更
死亡した人の銀行口座から、家賃や公共料金などが引き落とされている場合には、引き落とし口座の変更をしてください。
銀行口座が凍結されると、通常の引き出しだけでなく引き落としもできなくなってしまいます。
引き落とし口座の変更をしなければ、各種料金の支払いが滞納してしまいます。
通帳を確認して引き落としが記録されている場合には、それぞれの引き落とし先に連絡して、解約や口座変更の手続きをしてください。
銀行への報告
銀行に名義人が亡くなったことを報告すると、銀行口座が凍結されます。
死亡した人の銀行口座を使い続けることには、相続争いの原因になる、刑事責任を問われるなどのリスクがあります。
名義人の死亡を銀行に報告する義務はありませんが、リスクを回避するためにも、銀行への報告は忘れずに行ってください。



銀行への報告は義務ではありませんが、口座凍結によって不正利用を防ぐ意味があります。早めに報告しておくことで、後々のトラブルを避けやすくなります。
死亡した人の銀行口座から問題なく預金を引き出す方法


死亡した人の銀行口座をそのまま使い続けることには、さまざまなリスクがあります。
銀行口座から問題なく預金を引き出す方法としては、次の3つの方法があります。
銀行口座の相続手続きを済ませれば、すべての残高を引き出すことが可能です。
相続手続きを済ませる前に預金を引き出したい場合には、仮払い制度や仮処分の利用を検討してみてください。
それぞれの方法について、詳しく解説します。
預貯金の仮払い制度を利用する
相続手続きの前に預金を引き出す方法としては、相続預金の仮払い制度があります(民法909条の2)。
相続預金の仮払い制度を利用すると、相続手続き前であっても各相続人が単独で預金の一部について払戻しを受けられます。
払戻しを受けられる金額の上限は、次の金額のうちいずれか低い額です。
- 預金残高×1/3×法定相続分
- 150万円
たとえば、預金残高が1,200万円で払戻しを希望する相続人の法定相続分が2分の1の場合は、200万円(1,200万円×1/3×1/2)と150万円を比較して、低い金額の150万円を上限とする払戻しを受けられます。
払戻しの上限額は各金融機関ごとに設定されているため、複数の金融機関に銀行口座がある場合には、金融機関ごとに上限額の払戻しを受けられます。
預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる
仮払い制度の上限を超えた金額を引き出したい場合には、預貯金債権の仮分割の仮処分が認められれば、法定相続分に相当する金額の引き出しが可能です(家事事件手続法200条3項)。
預貯金債権の仮分割の仮処分が認められるための要件は、次のとおりです。
- 遺産分割の審判もしくは調停が係属中であること
- 預貯金債権を行使する必要性があること
- 他の共同相続人の利益を害するものでないこと
仮分割の仮処分は、遺産分割の審判もしくは調停が申立てがあったことが要件となっており、裁判外での遺産分割協議が長引いているだけでは利用できません。
預貯金債権を行使する必要性としては、条文で相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支払いなどが挙げられています。
銀行口座の相続手続きを済ませる
遺言や遺産分割協議で誰が預金を相続するかが決まれば、銀行の相続手続きを済ませることで問題なく預金を引き出せます。
仮払い制度や仮処分は、相続手続き前に緊急の必要性がある場合に利用するものです。
遺産分割協議がスムーズに進められるのであれば、遺産分割協議で誰が預金を相続するかを決めたうえで、銀行での相続手続きを済ませるのが良いでしょう。
銀行口座の相続手続きについては、次の項目で詳しく解説します。



仮払い制度や仮処分は緊急時の対応策に過ぎません。根本的な解決は遺産分割協議や遺言に基づいて相続人を確定し、銀行の正式な相続手続きを行うことです。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
銀行口座の相続手続きの流れ
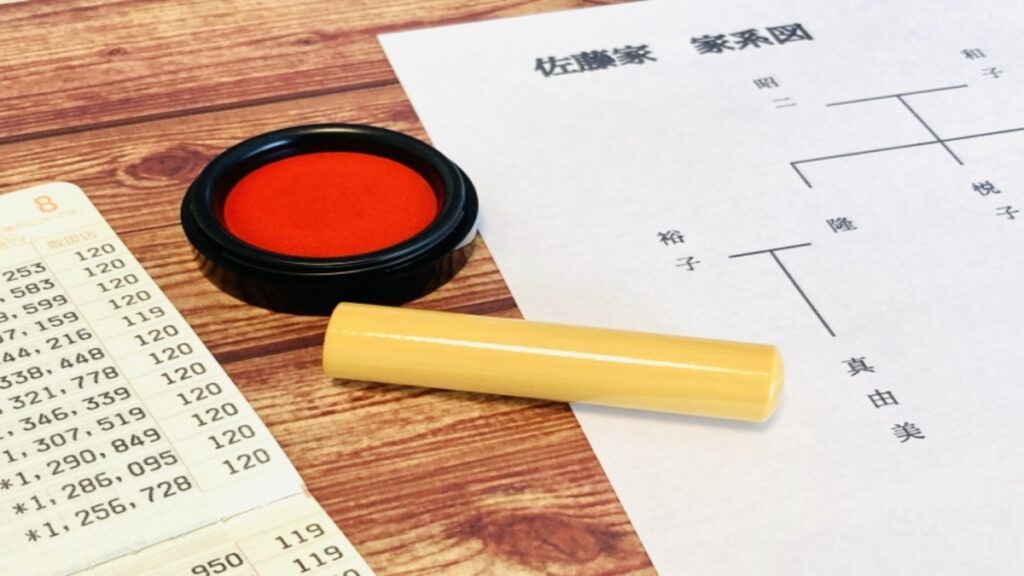
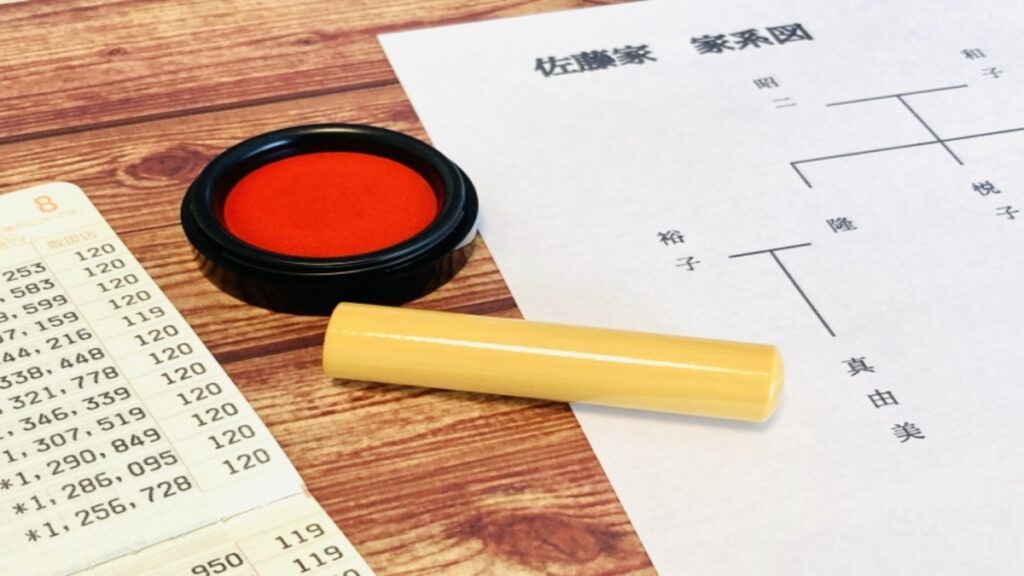
銀行口座の相続手続きの流れや必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議を終えているか否かによって異なります。
ここでは、次の3つの場合に分けて相続手続きの流れと必要書類を解説します。
このうち3つ目の方法は、相続人全員の共有財産として引き出す方法で、基本的にはおすすめできません。
遺言書がない場合には、遺産分割協議を終えてから銀行口座の相続手続きを進めるのがおすすめです。
遺言書がある場合
遺言書がある場合の必要書類は、次のとおりです。
金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、あくまで一例としてご確認ください。
- 銀行所定の相続手続依頼書
- 預金通帳・キャッシュカード
- 遺言書
- 遺言書の検認調書(自筆証書遺言の場合)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(被相続人の死亡がわかるもの)
- 銀行口座を相続する人の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の印鑑登録証明書(遺言執行者がいる場合)
遺言書が自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
必要書類を提出すると、口座の解約もしくは名義変更により被相続人の預貯金を取得できます。
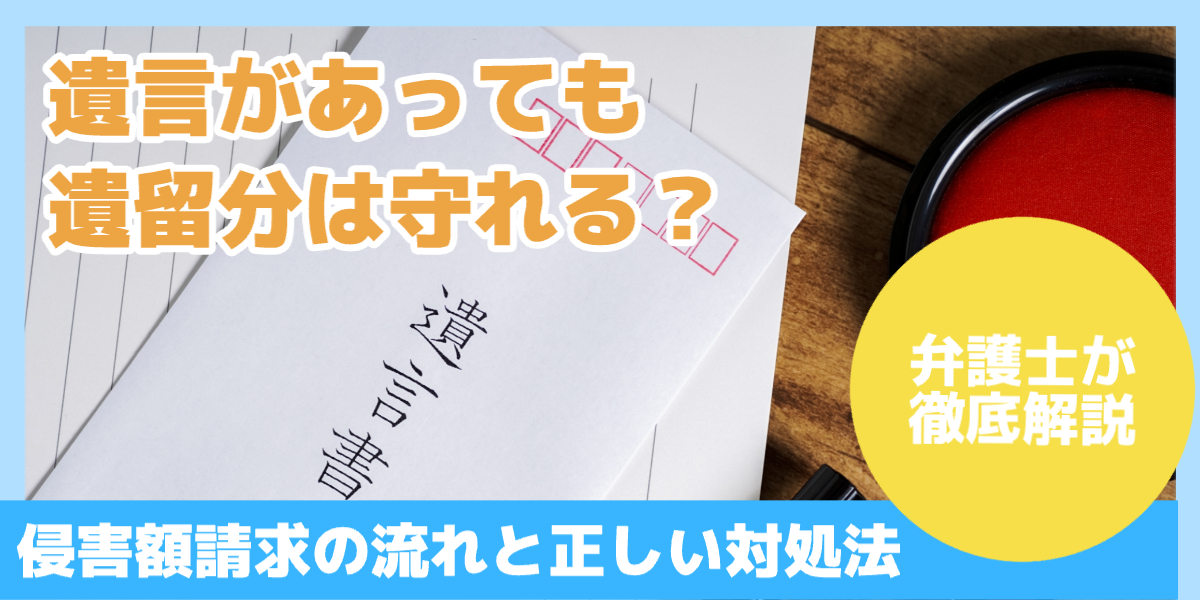
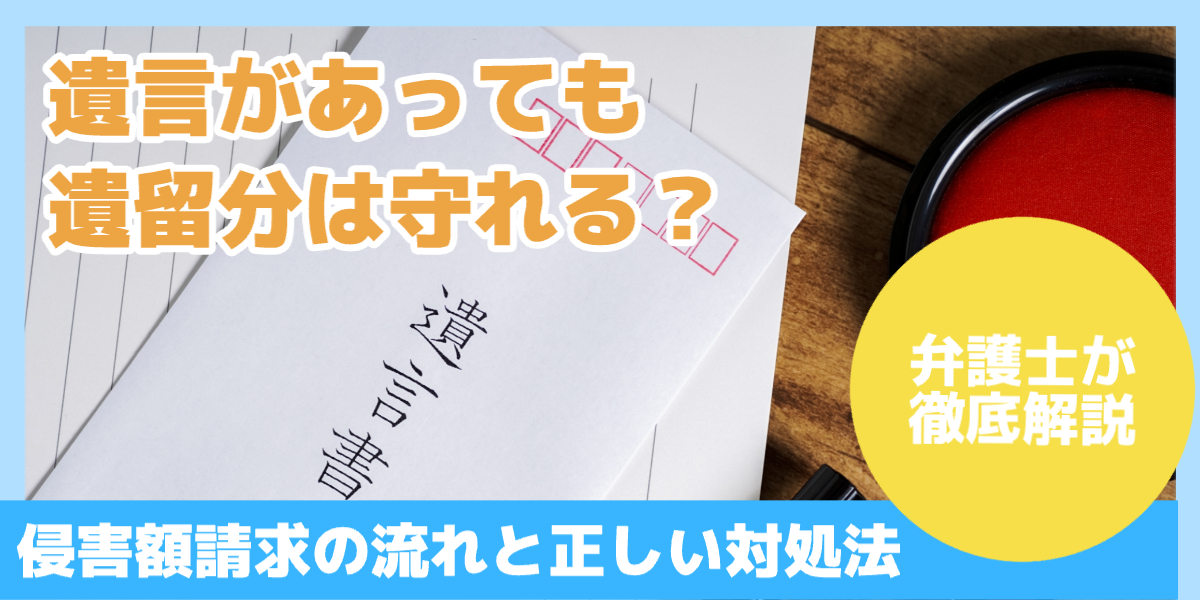
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議を終えている場合の必要書類は、次のとおりです。
金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、あくまで一例としてご確認ください。
- 銀行所定の相続手続依頼書
- 預金通帳・キャッシュカード
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印があるもの)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
遺言書がない場合には、遺産分割協議書で誰が預金を相続するのかを決めたうえで銀行口座の相続手続きを行います。
相続人の戸籍謄本については、印鑑登録証明書の提出のみで足りる場合もあるので、各金融機関にお問い合わせください。
遺言書も遺産分割協議もない場合
遺言書も遺産分割協議もない場合の必要書類は、次のとおりです。
金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、あくまで一例としてご確認ください。
- 銀行所定の相続手続依頼書
- 預金通帳・キャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
遺言書も遺産分割協議もない場合でも、相続人全員の共有財産として相続手続きを進めることは可能です。
しかし、誰が預金を相続するのかが決まる前に相続手続きを済ませてしまうと、誰が預金を管理するかが決まらない、預金を管理していた相続人が預金を使い込んだなどのトラブルが起きる可能性があります。
そのため、銀行口座の相続手続きを急ぐ理由がないのなら、遺産分割協議を終えてから銀行口座の相続手続きをするのがおすすめです。



遺言書や遺産分割協議書の有無によって必要書類が変わるため、まずはどのパターンに当てはまるかを確認してください。金融機関ごとに追加の書類を求められる場合もあるので注意が必要です。
死亡した人の銀行口座をそのままにしても問題がないケース
次の2つの場合には、相続手続きをせずに銀行口座を放置しても問題ありません。
放置して、10年以上取引のない銀行口座は、休眠預金となります。
休眠預金は、民間公益活動に利用されることになるので、放置することのリスクはありません。
相続放棄する場合
相続放棄する場合には、銀行口座を放置しても何ら問題ありません。
むしろ、相続放棄する人が銀行口座を利用すると相続放棄が認められなくなる可能性があるため、余計なことはせずに放置しておくのが良いでしょう。
残高が少ない場合
預金残高が少なく口座の相続手続きを進めるのに手間や費用がかかる場合には、銀行口座を放置しても問題ありません。
銀行口座の相続手続きを行うための必要書類の準備には手間も費用もかかります。
預金残高が少ない場合に相続手続きを進めても、手間や費用に見合わないものとなってしまうでしょう。
銀行口座を放置しても罰則はなく、残高は最終的に民間公益活動に利用されます。
手間や費用をかけてまで相続手続きを進める必要がないのなら、そのまま放置するのも選択肢の1つです。
亡くなった人の預金が少額の場合の対処法については、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:亡くなった人の預金が少額の場合どうする?おろす方法と手続きや必要書類



相続放棄や少額残高のケースでは、あえて手続きをせず放置する選択肢もあります。ただし『放置しても問題がない』のは例外的な場合に限られることを意識しておきましょう。
財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例
財産の状況が分からない中で調査を行い、遺留分を適切に取得できた事例があります。
“被相続人Aさんは遺言を残しており、その内容は多くの遺産をご兄弟のCさんに相続させる内容。
依頼人のBさんはCさんから、Aさんの遺産は借金ばかりなので相続放棄してほしいという連絡を受けたため、相続放棄の依頼をするために弊所にご相談。”
この事例の課題としては、
- 相続放棄をするべきか否か
- 広大な土地の評価方法
があげられます。
そこで
- 初期の段階で「相続放棄ありき」ではなく、財産調査と遺留分の権利保全の提案を行った
- 特に評価が難しい収益不動産について、最も高い活用価値を示す査定資料を用いた説得を行った
というご対応をさせていただき、Cさんより約2,000万円の遺留分を取得する形で調停が成立。
依頼人Bさんにとって円満な解決をすることに成功いたしました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


まとめ
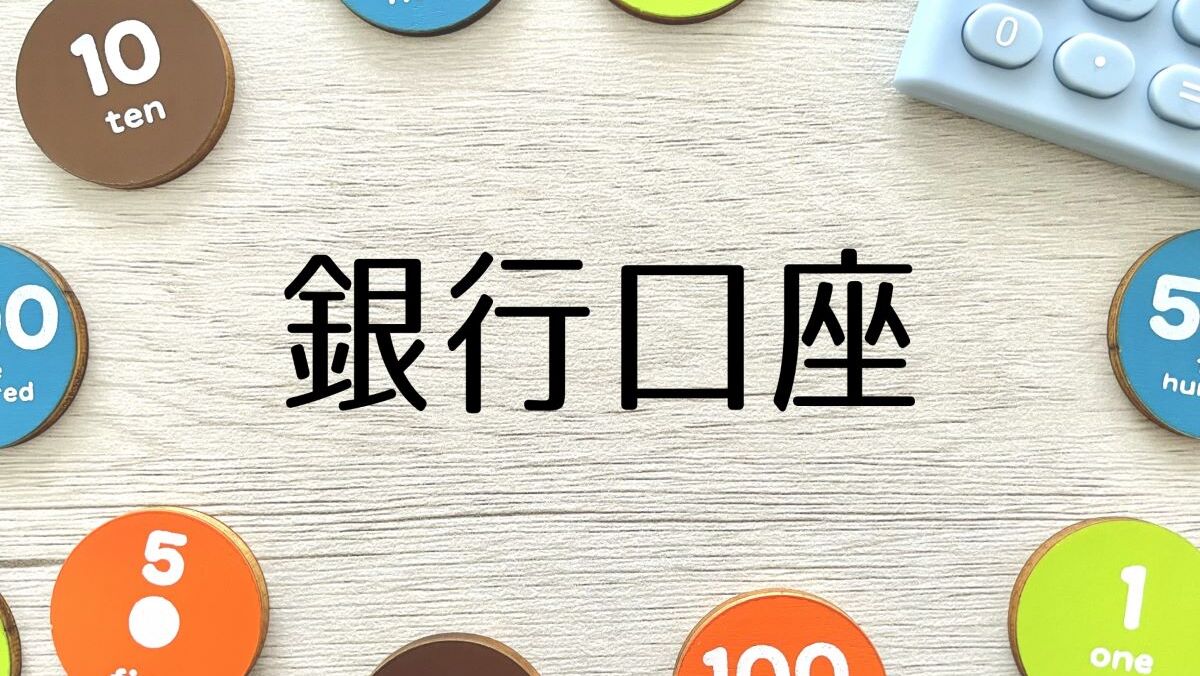
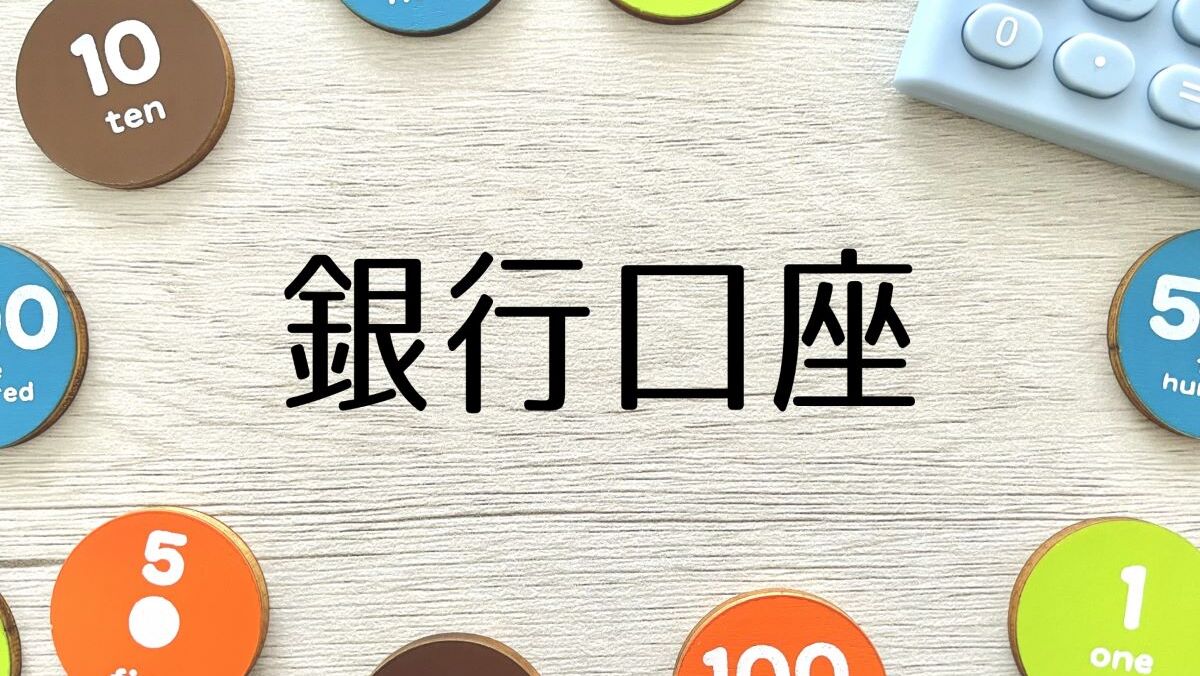
今回は、死亡した人の銀行口座をそのまま使っても良いのかを理解するために、次の内容について解説しました。
- 銀行口座をそのまま使うと相続争いの原因になったり、刑事責任を問われたりするリスクがある
- 相続手続き前に預金を引き出すには仮払い制度、仮処分の申し立てという手段がある
- 遺言書か遺産分割協議で相続人を決めたうえで相続手続きを進める
- 相続放棄する場合や残高が少ない場合は銀行口座を放置しても問題はない
銀行口座の相続手続きを進めるには、遺産分割協議で誰が預金を相続するのかを決める必要があります。
遺産分割協議をまとめるのが難しいときは、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談すれば、遺産分割協議をスムーズに進められます。



相続手続きは複雑に思えるかもしれませんが、弁護士が介入することで円滑に進められるケースが多いです。迷ったときには専門家に相談し、早めに正しい対応をとることが安心につながります。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応