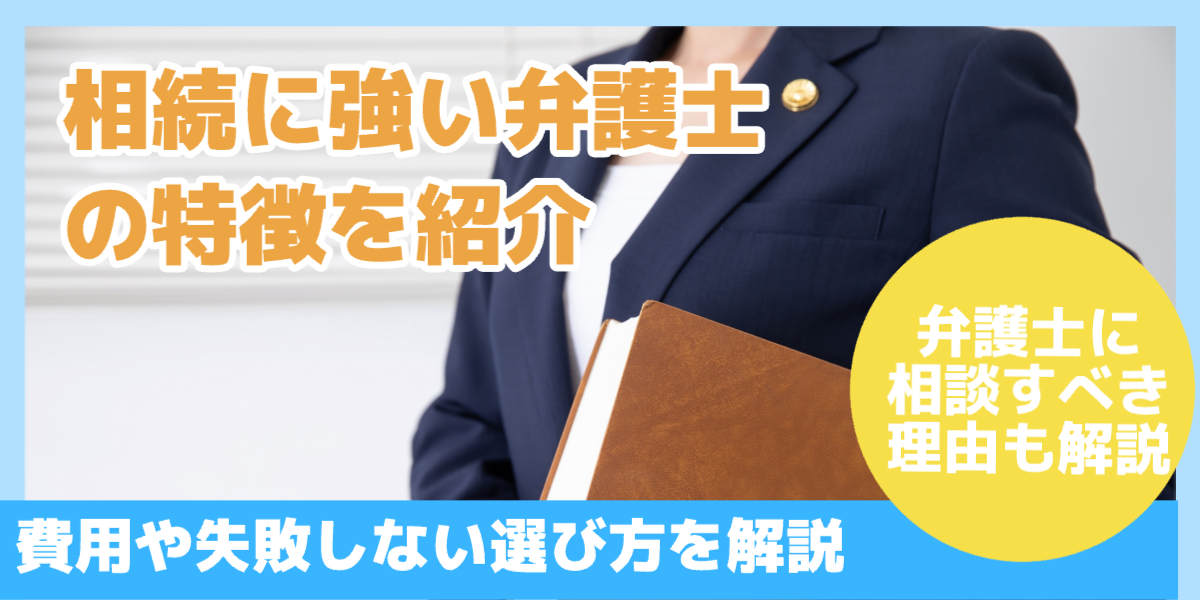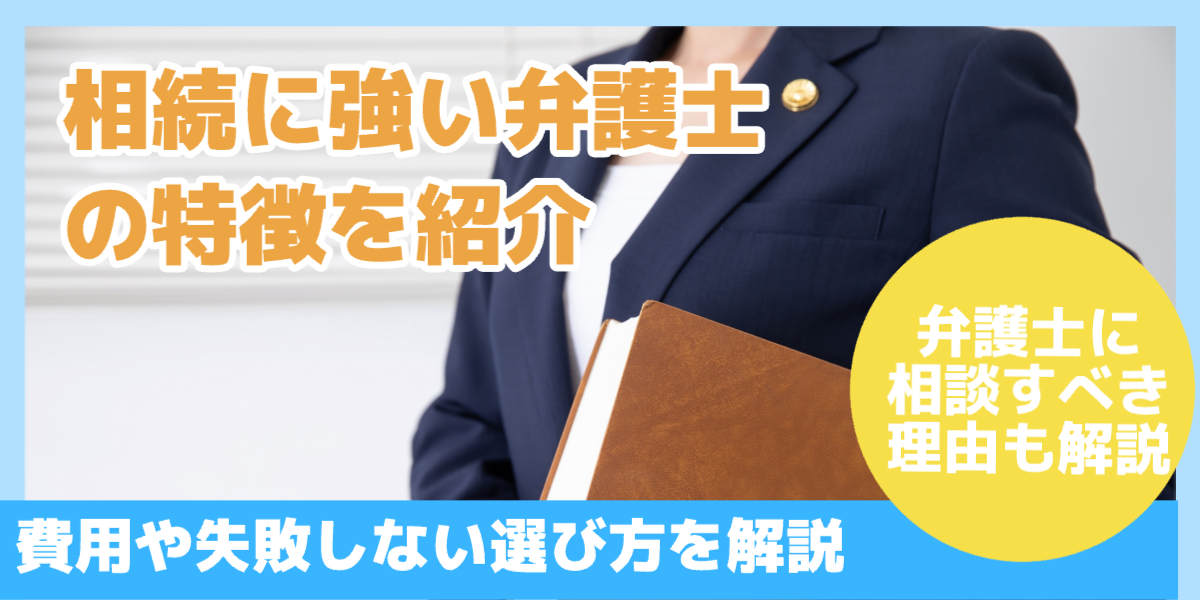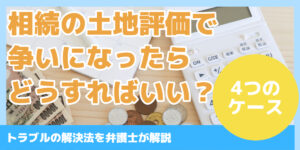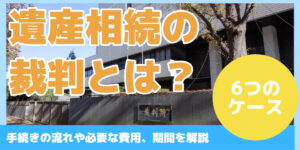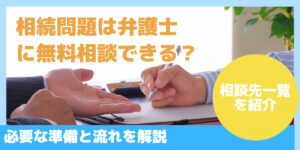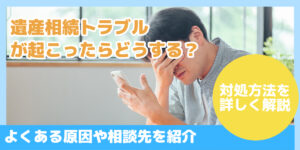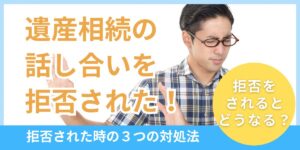【無料相談受付中】24時間365日対応
親が亡くなったら銀行口座はどうなる?相続手続や預金を引き出す際の注意点を解説
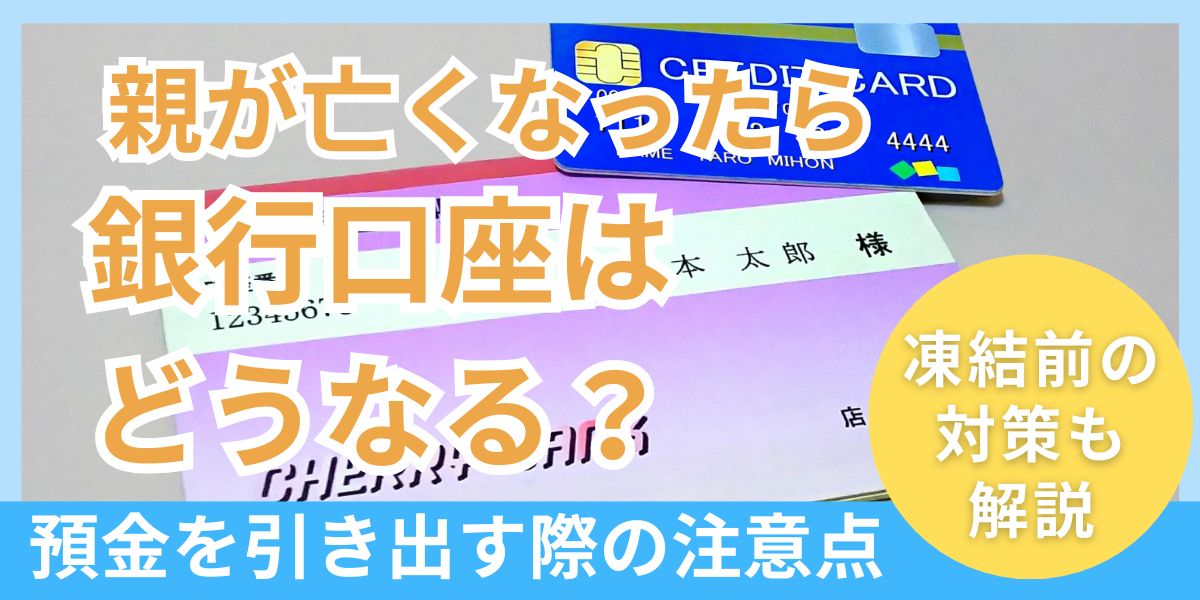
親が亡くなったら銀行預金はどうしたらよいのか、よくわからないという方も多いでしょう。
- 親が亡くなったことを銀行に連絡すべきか?
- 葬儀費用が必要だが預金は引き出せるか
親が亡くなると死亡届の提出などやるべきことはいろいろありますが、銀行への連絡や口座をどうすべきかも、すぐに考えなければなりません。
親が亡くなったら、銀行に連絡すると預金口座はすぐ凍結されます。
葬儀費用など当面必要な出費もあるため、預金を引き出しておくべきかなどについて、あらかじめよく考えておくことが大事です。
親が亡くなったら銀行への連絡をどうすべきかや、預金口座の凍結解除・相続手続きの流れ・注意点を紹介します。
親が亡くなった場合の銀行口座の扱いや必要な手続きなどをわかりやすく解説しているので、銀行口座の凍結や預金の引き出しで悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
アクロピースでは口座の相続手続きなど相続問題全般のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
親が亡くなったら銀行口座はどうなる?
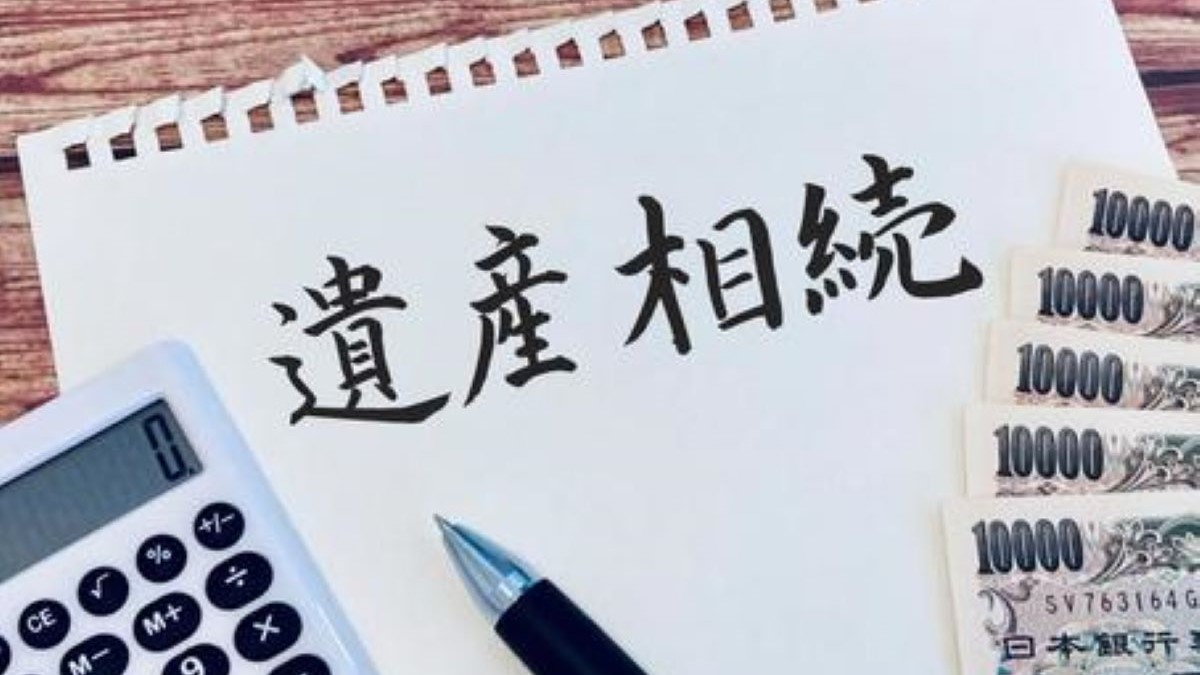
親が亡くなったら銀行口座はどうなるのかについて、以下の5点を解説します。
親が亡くなったら銀行に連絡する
銀行口座の名義人である親が亡くなったら、銀行への連絡が必要です。
銀行に連絡せずに預金を勝手に引き出すと、相続を単純承認したとみなされかねません(民法921条1号)。
後々、マイナス財産が多いことがわかり相続放棄をしたいと思っても、放棄できなくなる恐れがあります。
関連記事:相続での預貯金の名義変更について解説
銀行口座は凍結され預金はおろせなくなる
銀行口座の名義人の死亡を銀行が知ったときは、銀行はすぐに口座を凍結します。
口座が凍結されると、少額でも預金の出金や引き落としはできません。
- 死亡時の相続財産を確定させるため
- 親の預貯金を遺族が勝手に引き出すことを防ぐため
銀行は、親が死亡した事実を遺族からの連絡で知る場合が多いです。
新聞の訃報や営業活動などを通じて銀行が死亡の事実を把握することもあります。
その場合、銀行は遺族に確認したうえで、口座をすぐ凍結するでしょう。
死亡した病院や死亡届を出した役所から情報が流れ、勝手に凍結されることはありません。
しかし、口座が凍結されると電気代などの引き落としもできなくなるため、公共料金等の引落し口座は、口座が凍結される前(銀行に連絡する前)に変更しておいた方がよいでしょう。
亡くなった人の預金をおろす方法や手続きなどは、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:【亡くなった人の預金が少額の場合】おろす方法・手続き・必要書類
凍結された口座はなくならないが相続手続きが必要
亡くなった人の銀行口座はすぐ凍結されますが、なくなるわけではありません。
凍結された銀行口座は、相続人全員の同意で遺産分割協議をすれば相続人が引き継ぐことができ、引き出し、解約も可能です。
詳細は後で解説しています。
凍結前の預金の勝手な引き出しはNG
銀行口座が凍結される前であれば、ATMなどで預金を引き出せますが、勝手な引き出しは基本的に規約違反行為です。
亡くなった人の財産は相続人全員の共有財産であるため、別の相続人から損害賠償請求を受ける可能性もあるでしょう。
預金の引き出しが認められる場合もある
預金の引き出しが認められる可能性があるのは次の場合です。
- 遺産分割前の遺産の処分:相続人全員の同意のうえで引き出す場合(銀行による)
- 遺産分割前の払い戻し(民法909条の2):相続人単独でも可能(一定の限度額までの引き出し)
- 家庭裁判所の仮処分による仮払い(家事事件手続法200条3項):相続人が申立てた場合(相続人の生活費の支弁などの費用で要件に該当する場合に限る)
凍結解除前の預金は、故人の入院時の医療費等や葬儀費用等故人の債務の支払いのためでも、本来、相続人全員が同意のうえで遺産分割協議等を提出し、凍結を解除して引き出す必要があります。
いずれの場合も預金を引き出すことについて、事前に家族や相続人全員にきちんと話をしておくことが重要です。
後で相続トラブルに発展しないよう、使用目的・金額が明瞭な領収書やレシートもしっかり残しておきましょう。(2と3の場合の詳細は、次項で説明します。)

口座は早期に凍結されますが、“凍結=消滅”ではありません。まずは引落口座の変更や未払い費用の整理を進めつつ、相続人全員で今後の方針(仮払い・仮処分・正式手続)を共有することが、後々の紛争予防につながります。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度がある
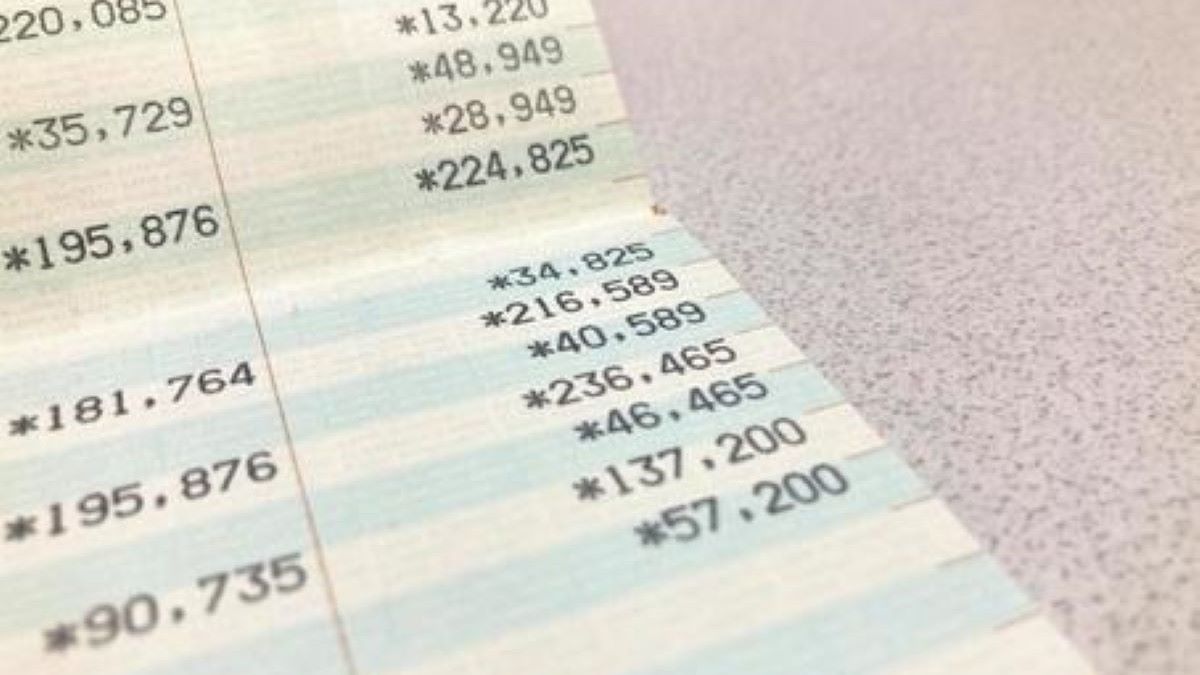
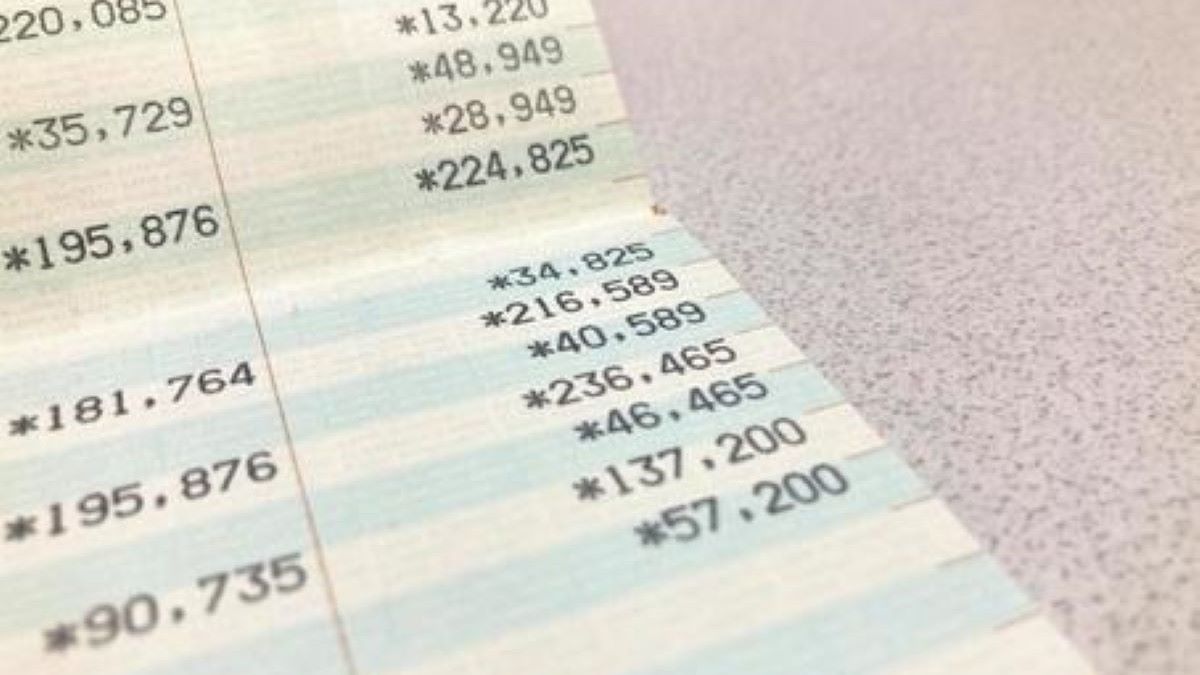
遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度とは、相続財産である預貯金を遺産分割が終わる前であっても、相続人が払戻しできるとする制度です。
民法等の改正(2019年7月1日施行)により設けられました(民法909条の2)。
一定額までであれば、遺産分割前に被相続人の銀行口座から預金を引き出せるようにしたものです。
遺産分割を行い銀行口座の凍結を解除するまでには時間がかかります。
一方で、葬儀費用や当面の生活費のために現金が必要な場合もあるでしょう。
そのため、一定額であれば法定相続人が故人の預貯金を引き出せるようにしたものです。
引き出した預金は、故人の相続財産であることに変わりはないため、使用した金額の領収書や明細を保管しておく必要があります。
ただし、この制度を利用した場合、相続放棄できなくなる可能性がある点に注意が必要です。
引き出す金額によっては、家庭裁判所の仮処分が必要になります。
引き出す金額が一定額以下なら家庭裁判所の仮処分は不要
引き出す金額が一定額以下の場合、家庭裁判所の仮処分不要で、銀行での手続きのみで引き出せます。
手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 被相続人の除籍謄本・戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書
相続人が単独で払い戻し可能な額は、下記の計算式で求められます。
相続人が単独で払い戻し可能な額=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
引き出せる金額は、1金融機関につき上限150万円までです。
引き出す金額が一定額以上の場合は家庭裁判所の仮処分が必要
上記制度による払戻し可能な金額以上を引き出す場合は、家庭裁判所の仮処分が必要です(家事事件手続法200条3項)。
裁判所の仮処分があれば、ほかの相続人の利益を侵しない範囲で、家庭裁判所が認めた金額まで引き出すことが可能になります。
家庭裁判所の仮処分を得るためには、遺産分割の審判または調停の申立てを行い、金額が必要な理由を認めてもらう必要があります。
家庭裁判所の仮処分が出たときは、次の書類を添えて銀行で手続き可能です。
- 家庭裁判所の審判書謄本
- 預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書



仮払い制度は“当面の支出を切らさないための安全弁”です。上限計算(預金額×1/3×法定相続分、かつ金融機関ごとに150万円まで)を押さえ、領収書・明細を必ず保管しておきましょう。相続放棄の可否にも影響し得るため、使う前に弁護士へ相談を。
銀行口座の凍結解除・相続手続きの流れと必要書類


銀行口座の凍結解除・相続手続きの流れと必要書類について説明します。
銀行口座の凍結解除までの主な手続きの流れ
銀行口座の凍結解除・相続(名義変更)までの主な手続きの流れは次の通りです。
- 銀行に親が亡くなった(相続が発生した)ことを連絡
- 銀行から口座相続に必要な届出用紙を入手
- 必要書類(遺言書・遺産分割協議書など)の収集
- 銀行に所定用紙と必要書類を提出
- 口座凍結を解除、名義変更・解約
口座の名義人が死亡した場合、まず取引銀行への連絡が必要です。
その後、銀行で口座凍結解除・相続手続きに必要な書類を確認し、所定の届出用紙をもらいましょう。
必要書類を揃え銀行に提出して相続手続きをすれば、名義変更・口座解約が可能になります。
銀行口座の凍結解除に必要な書類
銀行口座の凍結解除・相続に必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。
金融機関によっても異なりますが、主なものを3つのケースに分けて説明します。
遺言書がある場合
被相続人(亡くなった親、口座名義人)の遺言書がある場合は、次の書類が必要です。
| 相続手続依頼書 | 通常、銀行指定のものがある |
|---|---|
| 遺言書 | 銀行に預けている預金の分割割合・承継者(預金を受け取る人)が明確に記載された遺言書原本 |
| 遺言書の検認済証明書 | 遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認した証明書類 (公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度利用の場合は不要) |
| 戸籍謄本 | 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの) 法定相続人全員の戸籍謄本 (法務局発行の法定相続情報一覧図写しがある場合は不要) |
| 印鑑証明書 | 銀行預金の承継者の印鑑証明書 (遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書も必要) |
| 通帳 | 証書・キャッシュカードなど |
遺産分割協議書がある場合
遺言書はないが、遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成した場合は、次の書類が必要です。
| 相続手続依頼書 | 通常、銀行指定のものがある |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 銀行に預けている預金を誰が受け取るか明確に記載された遺産分割協議書の原本 |
| 戸籍謄本 | 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの) 法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本 (法務局発行の法定相続情報一覧図写しがある場合は不要) |
| 印鑑証明書 | 法定相続人全員の印鑑証明書 (遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書も必要) |
| 通帳 | 証書・キャッシュカードなど |
遺産分割協議書には法定相続人全員の署名捺印が必要です。
印鑑登録証明書は遺産分割協議書に捺印したものが必要です。
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もなく、複数人で共同相続する場合は、下表の書類が必要です。
| 相続手続依頼書 | 通常、銀行指定のものがある |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの) 法定相続人全員の戸籍謄本 (法務局発行の法定相続情報一覧図写しがある場合は不要) |
| 印鑑証明書 | 法定相続人全員の印鑑証明書 |
| 通帳 | 証書・キャッシュカードなど |
ゆうちょ銀行の場合の相続手続き・必要書類については、次の記事をご覧ください。
関連記事:ゆうちょ銀行の相続手続きを行うには?必要書類と手続きの流れを紹介



必要書類は“誰が(相続関係)と“何を(対象財産)”を証明する二本柱。法定相続情報一覧図の活用や、原本返却(写し提出)の可否を早めに確認しておくと、複数口座・不動産手続きまで一気通貫で進めやすくなります。
銀行口座の凍結解除・相続手続きを行うときの注意点


銀行預金の相続手続きは、取引店ではなく事務センターなどで対応する場合があります。
あらかじめ、相続手続きの窓口・電話番号などを確認した方がよいです。
銀行に連絡すると口座はすぐ凍結され、相続手続きが終わるまで預金の引き出しはできません。
葬儀等が一段落したら早めに窓口に出向いて、凍結解除・相続手続きに必要な書類を確認し、準備を始めましょう。
フリーダイヤルやホームページで相続手続きがわかる場合もありますが、直接訪問して窓口で確認した方が間違いありません。
必要書類を揃えるのには時間がかかります、早めに準備しましょう。
必要書類を銀行に提出後も、手続き完了まで2週間~1か月程度を要することもあります。
預金を使う予定がある場合は、あらかじめ銀行に伝えて早めの処理を依頼しましょう。



窓口は“取引店”ではなく事務センター対応になることも。提出前に一度チェックしてもらうと差戻しを防げます。完了まで時間がかかる前提で、葬儀費用等の資金計画は仮払い制度と併用して設計しましょう。
銀行口座が凍結される前にすべき2つの対策


銀行口座が凍結される前、親が生存中にできる対策・講じておくべき対策が2つあります。
銀行口座の凍結解除には手間がかかりますので、事前にしっかり対策をしておきましょう。
必要となる資金の引き出し
葬儀等で必要となるお金を事前に引き出しておきましょう。
親の逝去後でも、相続人全員の合意があれば預金を引き出すことは可能です。
しかし、親が亡くなるとすべきことが多く、落ち着く暇はありません。
親が生存中に葬儀費用の準備やお金の話をするのは不謹慎と思うかもしれませんが、まとまった金額を急きょ手当するのは大変なことです。
事前に準備しておいた方があわてなくて済みます。
できれば、親がはっきりと意思表示可能なうちに、預金の引き出しについて相談し、同意を得て、引き出しておきましょう。
引き出す金額や使途は、医療費や葬儀費用など当面支払いが必須な範囲に限った方がよいです。
あとでトラブルにならないように、家族にもきちんと話しておきましょう。
また、使った場合は、領収書をすべてきちんと保管しておくことが大事です。
口座が多いときは整理しておく
親が複数の銀行口座を持っている場合、できるだけ整理しておいた方がよいです。
口座が多いと手続きがその分増えます。
用意すべき書類が銀行によって異なる場合があり、煩雑です。
口座数を減らしておけば、財産の確定や凍結解除手続きが容易になります。
特に海外に口座を持っている場合は手続きが面倒な場合も多いため、生前中にできるだけ解約した方がよいです。



生前の“資金準備”と“口座整理”は、遺族の実務負担を大きく減らします。引き出しは目的・金額・同意の記録化(メモ・領収書)までセットで。複数口座は集約し、将来の財産把握と相続手続の効率化を図りましょう。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
銀行口座凍結後に解除手続きをしない方がよい場合もある


親の銀行口座が凍結された場合、凍結解除手続きをすぐすべきとは限りません。
手続きせずに、そのままにしておいた方がよいケースもあります。
預金残高が少ない場合
銀行口座残高が少ない場合は、そのまま放っておいた方がよい場合もあります。
銀行口座の凍結解除には多くの書類が必要で、準備に手間と時間がかかるからです。
預金残高を調べ、手間暇かけてまで解除する必要があるか検討した方がよいでしょう。
相続放棄や限定承認をする場合
相続放棄や限定承認を考える場合は、預金に手を付けてはいけません。
預金を自分のために使うと相続を単純承認したことになってしまいます。
口座の解除手続きをするだけでも単純承認したとみなされかねません(民法921条1項)。
相続財産はプラスの資産だけとは限りません。
借金や未払いの税金などのマイナス財産が多ければ、借金を相続することになります。
遺産相続は、単純に全財産を引き継ぐ単純承認以外に、限定承認と相続放棄もできます。
マイナス財産の方が多い場合は、相続放棄か限定承認を選択した方がよいでしょう。
長期間放置すると休眠口座になることもあるので注意が必要
銀行口座を長期間放置すると、休眠預金等活用法によって休眠口座(休眠預金)になるおそれがあります。
銀行口座からの入出金等の取引後10年間移動がない場合、休眠預金として預金保険機構の管理に移されることがあるかもしれません(休眠預金等活用法2条6項、4条1項)。
仮に管理主体が預金保険機構に移っても、相続手続きを進めることは可能で休眠口座の預金の払戻しは可能です。
ただし、手続きはかなり煩雑になるため、早めに相続手続きをしましょう。
参考:預金保険機構|長い間お取引のない預金(休眠預金)



“少額だから今回は動かない”という選択肢もありますが、管理手数料・休眠化・後日の払戻し煩雑化の三点は見落としやすいポイント。相続放棄や限定承認を検討する局面では、一切手を付けないことが肝心です。
複数世代にまたがる相続放棄の実施で多額の債務を回避した事例
相続が複数世代に及び、相続放棄を行って債務を避けられたケースがあります。
“Aさんが亡くなり、多額の債務があることが判明しました。
第一順位の相続人であるBさん・Cさんは、相続放棄を検討されていましたが第二順位の相続人である祖父母Dさん・Eさんもご存命であり、自分たちが放棄するとどうなるか心配とのことで、弊所にご相談”
この事例の課題としては、
- Aさんの負債の相続リスク
- Bさん・Cさんが相続放棄した場合、Dさん・Eさんが相続人になること
- 債権者からの相続人に対する請求対応
があげられます。
そこで
- 相続放棄に必要な戸籍等の書類収集を開始し、相続放棄申述書の作成
- 債権者から4〜5回連絡があるも、相続放棄を予定している旨を丁寧に説明
というご対応をさせていただき、Bさん・Cさんの相続放棄が無事に受理された後、続けてDさん・Eさんの相続放棄の手続きを行い、無事に完了いたしました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。
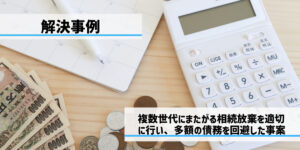
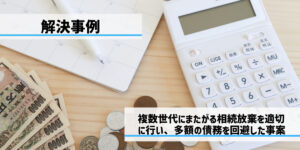
まとめ


親が亡くなったら銀行口座をどうすべきかについてまとめます。
- 親が亡くなったら銀行口座は凍結される
- 凍結前に勝手に預金を引き出すと、相続放棄できなくなり借金を背負うことや、損害賠償請求を受ける恐れがある
- 正しい手続きに沿って預金を払い出すためには、口座の凍結解除が必要だが、遺産分割協議や必要書類の準備に時間や手間がかかる
トラブルを避け、手続きの負担を減らすためには、相続の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。



仮払い・正式手続の使い分けと、相続人間の合意・記録化がトラブル回避の鍵です。判断に迷う場面では、最終的なコストとリスクを比較し、早期に専門家へ。小さな一手が後々の大きな安心につながります。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応