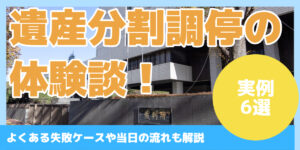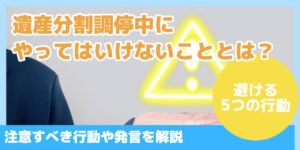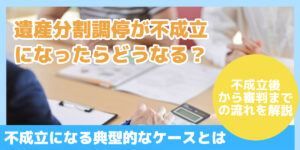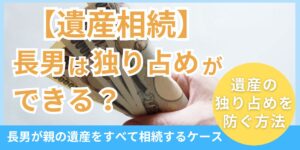【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続の裁判で負けるケースとは?リスクや事前にすべき対策を弁護士が解説
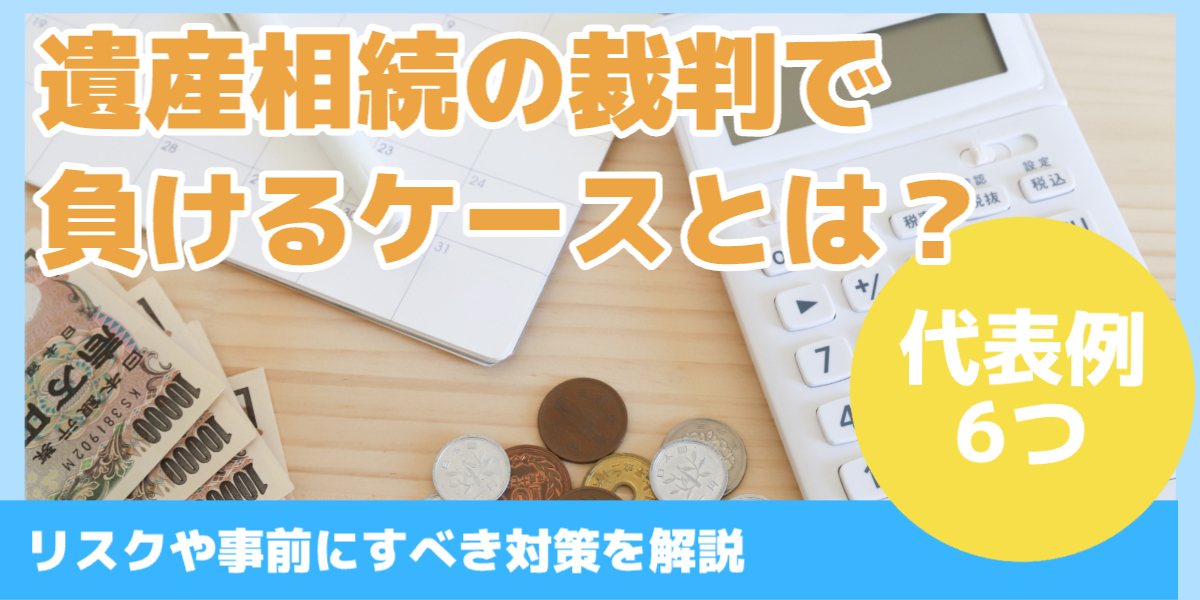
「遺産相続の裁判で負けて、大切な財産を失いたくない」
「裁判で負けないために今からできることはある?」
このような不安や疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
遺産相続裁判では、客観的な証拠不足や法的知識の不足などにより、敗訴となってしまうケースもあります。
裁判に負ければ自分の主張を認められない、あるいは相手の主張に従う必要があり、訴訟費用を負担するといった損失も被ることになるでしょう。
この記事では、遺産相続の裁判で負けてしまうケースや、敗訴の可能性を高める原因を具体的に解説します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続で裁判(訴訟)になる可能性がある6つのケース
前提として法律関係のトラブルは、トラブルの内容によって法律で定められた紛争解決方法によって解決します。特に遺産相続のような家族関係の処理については、調停や審判といった非公開で柔軟な解決ができる手続きが数多くの紛争解決のために用意されています。
遺産相続の争いの内容によっては、裁判(訴訟)によって解決が必要なケースもあります。遺産相続で裁判になる代表例としては、以下の6つです。
本章では、遺産相続において裁判になるケースを詳しく解説します。
関連記事:遺産相続の裁判とは?手続きの流れや必要な費用、期間を弁護士が解説
関連記事:遺産相続トラブルになりやすいケースとは?実例と対処法を弁護士が紹介
関連記事:不動産相続のよくあるトラブル例10選|揉める原因と解決方法・注意点を解説
遺産の範囲を争う場合|遺産確認訴訟
遺産分割を進めるうえで、まず「その財産は、本当に遺産に含まれるのか」という、遺産の範囲そのもので争いになるケースがあります。被相続人(亡くなった方)の名義であっても、実質的には他人の財産である可能性が指摘されることもあるでしょう。
このような財産の帰属を明確にするために行われるのが、「遺産確認訴訟」です。
- 被相続人名義だが、子が入金し、子が資金を管理していた預金(名義預金)
- 被相続人名義だが、長年、別の親族が固定資産税を払い使用していた土地
- 生前に被相続人が「これは〇〇にあげる」と口約束していたとされる美術品
この訴訟により、対象の財産が遺産であると確定すれば、遺産分割の対象に含まれ、遺産ではないと確定すれば、遺産分割の対象から外れることになります。

相続人の範囲を争う場合|相続人の地位不存在確認訴訟
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、その前提となる「誰が法的な相続人なのか」という点で争いが生じるケースがあります。
被相続人の死後、これまで知られていなかった人物が相続人として現れる場合もゼロではありません。
特定の人物が相続人であるか否かを法的に確定させるためには、「相続人の地位不存在確認訴訟」の手続きが必要です。
- 相続欠格に該当する相続人がいる
- 被相続人と特定の人物との親子関係・養子縁組の有効性が疑われる
- 被相続人の婚姻の有効性に争いがある
この訴訟の結果、相続人の範囲が変われば、各相続人の法定相続分も変動します。 遺産分割協議を進める上で、最も根幹となる部分の争いと言えるでしょう。
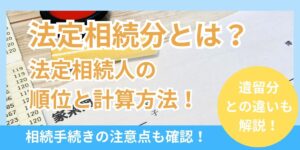
遺言の有効性を争う場合|遺言無効確認訴訟
被相続人が遺言書を残していたとしても、遺言書の内容に納得できない相続人が、その内容や有効性をめぐって「この遺言書は法的に有効なのか」と争いになるケースがあります。
- 遺言作成時に、被相続人が認知症などで正常な判断能力(遺言能力)を欠いていた
- 第三者によって遺言書が偽造された疑いがある
- 特定の相続人が、被相続人を騙したり脅したりして書かせた疑いがある
遺言の有効性を争うケースでは、「遺言無効確認訴訟」を行います。この手続きは、名前のとおり、遺言書の法的な効力を失わせることが目的です。
この訴訟で遺言が無効と判断されれば、遺言書はなかったことになり、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
関連記事:ダメな遺言書とは?トラブル事例や揉めないために考えておくことも解説
遺産の使い込みがあった場合|不当利得返還請求訴訟
被相続人の生前の財産管理をめぐっても、トラブルは起こり得ます。特に、特定の相続人が被相続人の財産を不当に使い込んでいた疑いがある場合は、争いに発展するケースは少なくありません。
- 介護などをしていた相続人が、被相続人の預金を無断で引き出し、生活費や遊興費に使ってしまう
- 被相続人が亡くなる直前に、多額の預金が引き出されている
- 同居していた親族が、被相続人の財産を管理していたが使途不明金が多い
- 被相続人の有価証券や不動産が、不自然な形で売却されている
使い込まれた財産を遺産に戻すよう求めるには、「不当利得返還請求訴訟」という法的手続きが必要です。
この訴訟で使い込みが認定されると、その金額分を遺産に加算して遺産分割をやり直します。 これを「持戻し」と呼び、相続人間の公平を保つための重要な手続きです。
関連記事:遺産を独り占めした人の末路は?相続争いで起こり得るトラブルと独り占めを防ぐ方法
遺留分の侵害があった場合|遺留分侵害額請求訴訟
遺言によって財産の分け方が指定されていても、その内容が「あまりにも不公平だ」と感じる相続人がいる場合、争いに発展することがあります。
法律では、兄弟姉妹を除く法定相続人に、最低限保障される遺産の取り分として「遺留分」を定めています。
遺言や生前贈与によってこの遺留分が侵害されたときに、侵害額に相当する金銭の支払いを求めるのが「遺留分侵害額請求訴訟」です。
- 「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書が見つかった
- 愛人や特定の団体に、全財産を遺贈する旨の遺言があった
- 生前に、特定の子供にだけ多額の資金援助(家や事業の開業資金など)をしていた
この権利は、遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に主張する必要があります。他の訴訟とは異なり、遺産そのものではなく、金銭での解決が原則となります。(参照:裁判所|遺留分侵害額の請求調停)
関連記事:遺留分侵害額請求の期限はいつまで?2つの時効や注意点を弁護士が解説
遺産分割協議の取り消し・やり直しの主張をしたい場合|遺産分割協議無効確認訴訟
一度成立した遺産分割協議であっても、その合意の過程に重大な問題があったとして、後から無効や取り消しを求める争いに発展するケースがあります。
この場合、「遺産分割協議無効確認訴訟」により「あの合意は無効だから、もう一度話し合いをやり直したい」と求めることができます。
- 特定の相続人から、騙されたり脅されたりして無理やり署名・押印させられた
- 後から、協議の当時に知らされていなかった重要な遺産(土地や多額の預金など)が見つかった
- 相続人の一部が、認知症などで正常な判断能力がない状態で協議に参加していた
- 本来参加すべき相続人が、協議から除外されていた
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫この訴訟で協議の無効が認められれば、成立した遺産分割協議は白紙に戻り、改めて相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになります。
遺産相続裁判で負ける可能性が高まる原因とは?
遺産相続の裁判で不利な状況に陥り、負ける可能性が高まるケースでは、いくつかの共通した原因があります。
ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
主張を裏付ける客観的な証拠が不足している
裁判官は、あなたの言い分が事実であるかを客観的な証拠に基づいて判断します。
いくら「こうだったはずだ」と強く訴えても、それを裏付けるものがなければ主張は認められません。 感情的な訴えだけでは裁判に勝つことは難しいでしょう。
- 「遺言書は無理やり書かされた」→遺言者がそのような遺言をする理由がないことを示す証言・日記など
- 「生前に多額の贈与があった」→ 口約束のみで、送金履歴や契約書が存在しない
- 「遺産が使い込まれていた」→ 被相続人の預金取引履歴などを入手できていない
遺産相続の裁判で勝つためには、ご自身の主張が真実であることを証明する証拠を、いかに集められるかが大切です。
例えば、預金取引履歴は相続人として金融機関に開示を求めることが可能です。また、診療記録・介護記録は、医療機関・介護施設に対し遺族として開示請求できます。
また、弁護士に依頼することで、弁護士会照会制度を通じて資料を入手できるケースもあるため、証拠集めに悩んでいる場合は一度ご相談ください。
法的知識がなく適切な判断ができない
遺産相続の裁判は、民法などの法律に基づいて進められます。法律の知識がなければ、自分の主張を法的に正しく組み立てるのが難しくなるでしょう。
また、相手方の主張が妥当なものか、反論すべき点はどこかを見極めることも困難になる可能性があります。さらに、裁判には民事訴訟法などの手続きに関する法律知識も欠かせません。
- 裁判所に提出する書類に不備があり、手続きが滞ってしまう
- 主張すべき法的な権利(時効など)に気づかず、機会を逃してしまう
- 本来は勝てるはずの場面で、相手の言い分に言いくるめられ和解してしまう
法的知識が不足していると、本来勝てるはずの裁判でも適切な対応ができず、不利な結果を招く可能性もあります。
遺産相続の裁判を欠席してしまう
裁判所が指定した期日に、正当な理由なく出席しないことは絶対に避けるべきです。
もし被告(訴えられた側)が欠席すると、原告(訴えた側)の主張をすべて認めたとみなされます。 その結果、「欠席判決」として、相手の請求通りの内容で敗訴判決が下されてしまいます。
一度下された判決を覆すことは、非常に困難です。 病気や仕事など、やむを得ない事情で出席できない場合は、必ず事前に裁判所に連絡し、手続きについて指示を仰ぐ必要があります。
感情的な対応やマナー違反などで裁判官の心証に影響
「心証」とは、裁判において問題となる事実についての裁判官の主観的な認識や確信のことです。
裁判官も人間であり、当事者の法廷での態度を見ています。 判決は証拠と法律に基づいて下されますが、裁判官が抱く印象が、心証の形成に影響を与える可能性があるため無視はできません。
感情的な言動は、裁判官に「この人の主張は信用しにくい」という印象を与え、主張の信頼性を損なうことにつながるリスクがあります。
- 相手方やその代理人弁護士を大声で罵倒する
- 裁判官の発言を遮ったり、指示に従わなかったりする
- 質問に対して感情的に反論し、回答をはぐらかす
上記のような感情的な言動は、裁判官に悪い印象を与え、裁判官が証拠に基づいて「事実がどうであったか」を判断する心証の形成に悪影響を及ぼす可能性があります。
印象が悪いだけで直ちに判決内容に影響するわけではありませんが、有利に働くことは決してありません。法廷では常に冷静さを保ち、敬意を払った態度で臨むことが重要です。
関連記事:遺産相続で揉める人と揉めない人の差は何?トラブルの原因と予防するコツを解説
遺言書に不備がある
遺言書の有効性が争点となる裁判では、遺言書そのものに不備があれば敗訴に直結します。 法律で定められた形式を一つでも欠いていると、その遺言書は無効と判断されます。
遺言書が無効になれば、その内容に沿った遺産相続は実現できません。
- 形式的な不備:自筆証書遺言に日付の記載がない、署名や押印が抜けている
- 内容的な不備:財産が具体的に特定できず、誰に何を残すのか不明確である
- 遺言能力が疑われるケース:作成時に被相続人が重い認知症で、遺言能力がなかったと判断される
これらの不備があると、遺言書そのものが無効と判断され、遺言書の内容を実現できなくなってしまいます。



遺言書に頼った主張をする場合は、その遺言書が法的に問題のない形式であるかどうかが、裁判での勝敗を分ける最大のポイントになります。
遺産相続の裁判で「負ける人」に共通する4つの特徴
遺産相続の裁判において、残念ながら不利な結果に終わってしまう方には、いくつかの共通した特徴が見られます。
ここでは、裁判で負ける人に共通する4つの特徴を解説します。どのような考え方や行動が敗訴につながりやすいのかを知り、事前にできる対策を検討しましょう。
感情的な主張に終始し、客観的な事実を整理できない
裁判は、感情をぶつけ合う場ではなく、証拠に基づいて法的な主張を組み立てる場です。過去の不満や「許せない」という気持ちが先行しすぎると、本来主張すべき論点が見えなくなってしまいます。
- 「兄は昔から親にひいきされていた」といった、証明できない不満を繰り返す
- 出来事を時系列で整理して説明できず、話が脱線してしまう
- 相手への不信感を募らせ、冷静な話し合いを拒絶する
裁判官を説得するには、感情的な訴えではなく、客観的な事実とそれを裏付ける証拠が重要です。
まずは感情と事実を切り分け、何が法的な問題点なのかを冷静に整理しましょう。
証拠の確保や法的主張の準備を怠る
裁判に勝つためには証拠集めや法的主張の組み立てなど、事前の準備が最も重要です。
「裁判を起こせば、あとは何とかなるだろう」という受け身の姿勢では、勝てる裁判も勝てなくなってしまうでしょう。
- 主張を裏付ける客観的な証拠(預金履歴や診断書など)を集めずに裁判に臨んでしまう
- 民法などの法律に基づいた主張の組み立てができていない
- 判例や法律の条文を調べることなく、自分の思い込みだけで戦おうとする
勝訴を勝ち取るためにも、裁判が始まる前の段階から、証拠の確保と法的な戦略の立案を進めましょう。
相手との交渉を拒み、和解を逃す
裁判におけるゴールは、必ずしも判決で完全勝利することだけではありません。裁判の途中で、お互いが譲歩して解決する「和解」も、非常に重要な選択肢の一つです。
しかし、相手への憎しみや「絶対に譲らない」という頑なな態度は、かえってご自身を不利な状況に追い込むことがあります。
- 裁判が長引き、弁護士費用や時間が無駄にかさむ
- 相手から提示された、実は有利だった和解案を蹴ってしまう
- 最終的な判決が、和解案よりも悪い内容になる可能性がある
感情的な対立を乗り越え、現実的な利益を計算できるかどうかが、最終的な満足度を分けるポイントです。
裁判手続きを軽視し、欠席・書類不備を起こす
裁判所は、厳格なルールと期限に基づいて手続きを進めます。これらの手続きを軽視することは、ご自身の権利を自ら放棄するに等しい行為です。
| 内容 | 起こりうる結果 |
|---|---|
| 裁判期日への出廷を欠席する | 相手の主張が100%認められる欠席判決(自動的な敗訴) |
| 書類の提出期限を失念する | 重要な証拠や主張が審理の対象外とされ、考慮されなくなるリスク |
| 裁判所からの指示を守らない・無視する | 裁判官の心証形成に悪影響を及ぼし、不利な進行を招く可能性 |
「知らなかった」「うっかりしていた」という言い訳は、法廷では一切通用しないと心得ましょう。
遺産相続の裁判で負けたらどうなる?敗訴のリスクとは
遺産相続の裁判に臨むにあたり、「負けたらどうなるのだろう」という不安を抱える方もいるでしょう。
万が一敗訴してしまった場合、単に自分の希望が通らないというだけでは済みません。判決によって自分の主張が法的に否定されることに加え、経済的にも大きな負担を強いられる可能性があります。
本章では、遺産相続の裁判で敗訴してしまった場合の主なリスクを解説します。
自分の主張が認められない・相手の主張に従うことになる
遺産相続の裁判で負けてしまうと、自分の主張が認められない、あるいは相手の主張に従うことになります。
自分が何らかの主張をして裁判を起こして負けた場合はその主張が認められなくなります。一方、自分が裁判される側の場合、負けることによって相手の主張に従うことになるでしょう。
判決には法的な強制力があるため、その内容に従わなければなりません。
もし判決で命じられた金銭の支払いや不動産の引き渡しを拒否し続けた場合、相手方から財産を強制的に差し押さえる「強制執行」を裁判所に申し立てられるリスクがあります。
- 勤務先からの給与
- 銀行の預金口座
- 所有している不動産や自動車
- 生命保険など
よって、裁判の判決内容を無視することは許されず、最終的には強制的に財産を失うリスクを伴います。
訴訟費用を負担する
日本の民事訴訟では、かかった訴訟費用は原則として敗訴した側が負担する必要があります。
(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。参照:民事訴訟法|第61条
具体的に「訴訟費用」にあたるのは、以下のような項目です。
| 敗訴者が負担する「訴訟費用」の主な項目 | 目安の金額 |
|---|---|
| 裁判所に訴えを提起する際に納める手数料(収入印紙代) | 数千円~数万円 (訴額に応じて変動) |
| 書類を相手方に送るための郵便切手代 | 約6,000円~ (裁判所や当事者の人数などによって変動) |
| 証人を法廷に呼んだ場合の交通費や日当 | 1人あたり数千円~数万円 (証人の居住地や拘束時間によって変動) |
| 不動産の価値などを調べるための鑑定費用 | 数十万円~数百万円 (対象となる財産の種類や数によって変動) |
注意点として、相手が雇った弁護士の費用は、原則としてこの「訴訟費用」には含まれず、各自で支払うものです。
よって、裁判に負けたとしても、相手の弁護士費用まで支払う義務は基本的にありません。
ただし、敗訴側が実質的に相手方の弁護士費用を一部負担することもあります。
不法行為など損害賠償請求を含む訴訟では、判決で相手方の弁護士費用の一部(通常は請求額の1割程度)が賠償額に上乗せされるケースが存在するためです。



また、ご自身が依頼した弁護士への報酬は、勝敗にかかわらず全額支払う必要があることも覚えておきましょう。
関連記事:遺産相続の弁護士費用は誰が払うかを解説
遺産相続の裁判結果に納得できない場合の対処法
第一審の判決に不服がある場合は、「控訴(こうそ)」という不服申し立てが可能です。
判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に、高等裁判所に対して控訴状を提出する必要があります。(参照:裁判所|判決に不服がある場合はどうしたらいいですか?)
ただし、控訴審では新たな証拠を提出することが制限される場合も多く、第一審の結果を覆すのは容易ではありません。



控訴を検討する際は、本当に逆転の可能性があるのか、弁護士と慎重に協議することが重要です。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産相続の裁判で負けないためにやっておきたい5つの対策法
遺産相続の裁判で不利な判決を避けるには、事前の準備が結果を大きく左右します。感情的な主張を繰り返すだけでは、ご自身の正当な権利を法的に認めてもらうことは困難です。
ここでは、裁判を有利に進めるために実践すべき5つの具体的な対策法を解説します。
現状を整理し、法的主張を明確にする
感情的に対立している時こそ、まずは冷静に事実を整理することが重要です。 何が問題で、最終的にどのような解決を望むのかを明確にしなければ、的確な戦略は立てられません。
ご自身の状況を客観的に把握するためにも、以下の点を整理してみましょう。
- 誰が相続人か:戸籍を取り寄せ、法的な相続人を全員確定させる
- 何が遺産か:預貯金、不動産、有価証券など、プラスとマイナスの財産をリストアップする
- 何が争点か:遺言の有効性、財産の使い込みなど、揉めている核心部分を特定する
- 何を目指すか:ご自身が望む最終的なゴールの具体的なイメージを持つ
これらを整理することで、何を法的に主張すべきかが見えてくるはずです。
必要な証拠を確保する
裁判では、主張が事実であることを証明する「客観的な証拠」が最も重要です。
証拠がなければ、たとえそれが真実であったとしても、裁判官に認めてもらうことはできません。 争いの内容に応じて、必要となりうる証拠を早期に確保することが勝敗を分けます。
- 遺言の有効性を争う場合:被相続人の生前の診断書、カルテ、介護記録、日記など
- 遺産の使い込みを主張する場合:被相続人名義の預金取引履歴、贈与契約書など
- 不動産の帰属を争う場合:登記簿謄本、固定資産税の納税証明書など
証拠は時間が経つと散逸したり、相手方が隠したりする恐れがあるため、早い段階から意識的に収集・保管しておくことが大切です。
相手の主張や反論を予測し、対抗策をシミュレーションする
ご自身の主張を固めるだけでなく、相手の視点に立って物事を考えることも極めて重要です。 相手がどのような主張や反論をしてくるかを事前に予測し、それに対する備えをしておきましょう。
- 相手は、どのような証拠を提出してくる可能性があるか
- こちらの主張の、どの部分を弱点として攻撃してくるか
- 相手の主張に対して、どのような再反論が可能か
事前にシミュレーションしておくことで、裁判の場で冷静に対応できるようになります。あらゆる展開を想定し、複数の対応策を準備しておくことが、裁判を有利に進めるための鍵となるでしょう。
裁判外での「和解」も視野に入れる
裁判の目的は、必ずしも判決で完全に勝利することだけではありません。 裁判の途中でお互いが譲歩し、話し合いで解決する「和解」も有力な選択肢です。
長期化する裁判のデメリットを考えれば、和解が最善の策となるケースは少なくありません。
- 時間と費用の節約:裁判が長引くことによる金銭的、精神的な負担を軽減できる
- 柔軟な解決:判決では実現できない、当事者の実情に合った内容で合意できる
- 関係性の維持:親族間の感情的なしこりを最小限に抑え、将来の関係悪化を防げる
お互いが少しずつ譲歩することで、現実的な解決を図ることも有効な戦略の一つです。
裁判で争うことだけが正解ではないため、現実的な落としどころを探ることも視野に入れておきましょう。
遺産相続に強い弁護士に相談する
これまで挙げた対策法は、いずれも高度な法律知識と実務経験が求められるため、ご自身だけで進めるのは困難です。
遺産相続の裁判で負けないためには、遺産相続を得意分野とする弁護士に依頼することをおすすめします。
- 状況に応じた最適な法的戦略を提案してくれる
- 職権で証拠を収集するなど、証拠集めを強力にサポートしてくれる
- 複雑な裁判手続きや書面作成をすべて代行してくれる
- あなたの代理人として、相手方と冷静に交渉してくれる



一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロである弁護士に相談することが、問題解決への最短ルートと言えるでしょう。
関連記事:相続問題は弁護士に無料相談できる?おすすめの相談先や必要な準備も解説【弁護士執筆】
関連記事:相続に強い弁護士について解説
遺産相続裁判に関するよくある質問
ここでは、遺産相続の裁判に関してよく寄せられる質問にお答えします。
遺産相続の裁判はどのくらいの期間がかかりますか?
遺産相続トラブルの複雑さや争点の数によって、裁判の期間は大きく変動します。よって、一概に「このくらいの期間で終わる」と断言することは困難です。
あくまで目安ですが、一般的には第一審の判決が出るまでに1年から2年程度かかるケースが多いです。
- 遺産の数が多く、その評価に時間がかかる場合
- 遺言の有効性や財産の使い込みなど、複数の争点が存在する場合
- 証人尋問や鑑定など、証拠調べに時間を要する場合
- 相手方が非協力的で、手続きがスムーズに進まない場合
もし第一審の判決に不服で控訴するとなれば、さらに半年から1年以上かかる可能性もあるでしょう。
遺産相続の裁判は弁護士に依頼せず申し立てできますか?
法律上、弁護士に依頼せずご自身で裁判を起こすこと(本人訴訟)は可能です。
しかし、法律文書の作成や法廷での主張・立証などは、いずれも専門的な知識と技術が求められるため、極めてハードルが高いと言えます。
遺産相続裁判で不利な結果になることを避けるためにも、弁護士への依頼をおすすめします。
遺産相続で「負けるが勝ち」とは何ですか?
「負けるが勝ち」とは、裁判で徹底的に争って勝つことを目指すよりも、ある程度の譲歩をして和解などで早期に解決した方が、結果的に得られる利益が大きいという考え方です。
遺産相続の裁判では、すべての要求を通し、勝訴を目指すことだけが「勝ち」ではありません。
こちらが多少の譲歩をしてでも、早期に遺産相続のトラブルを解決させることの方が、実質的なメリットが大きいケースもあるでしょう。
いわゆる「負けるが勝ち」のメリットは以下の通りです。
- 費用が節約できる
- 裁判にかかる時間を短縮できる
- 相続人同士で争う精神的ストレスを軽減できる
- 家族関係が修復できる可能性もある
遺産相続トラブルでは、あくまでも長期的な視点を持ち、「現実的な損得」で判断する冷静さが求められます。
弁護士が第三者として介入することで、双方にとって受け入れ可能な現実的な着地点を導き出す手助けができます。



ご自身で譲歩すべきラインが分からない方はぜひ弁護士に相談することも検討しましょう。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
まとめ|遺産相続の裁判で負けないためには弁護士への相談を検討しよう
遺産相続に関するトラブルは、「調停」という家庭裁判所での話し合いから始まるのが一般的です。しかし、調停が不成立に終わった場合や、争いの内容によっては、初めから裁判(訴訟)によって解決する必要があります。
遺産相続の裁判で敗訴すれば、ご自身の望まない形で遺産が分けられるだけでなく、訴訟費用を負担するリスクも生じます。
このような事態を避けるためには、以下のような事前の準備が不可欠です。
- 法的な主張を明確にし、それを裏付ける証拠を集めること
- 相手の反論を予測し、冷静に対応すること
- 裁判だけでなく「和解」という選択肢も持つこと
これらの対策を確実に行い、裁判を有利に進めるためには、遺産相続問題に強い弁護士のサポートが欠かせません。



親族との争いは精神的な負担も大きいものです。一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士に相談し、最善の解決策を見つける第一歩を踏み出しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応