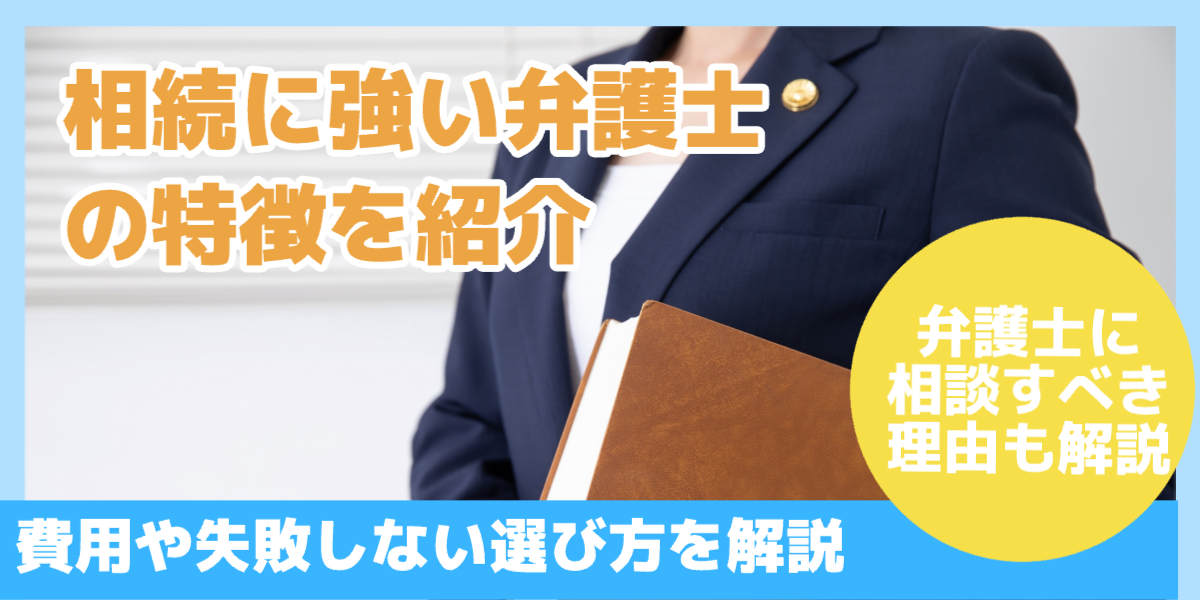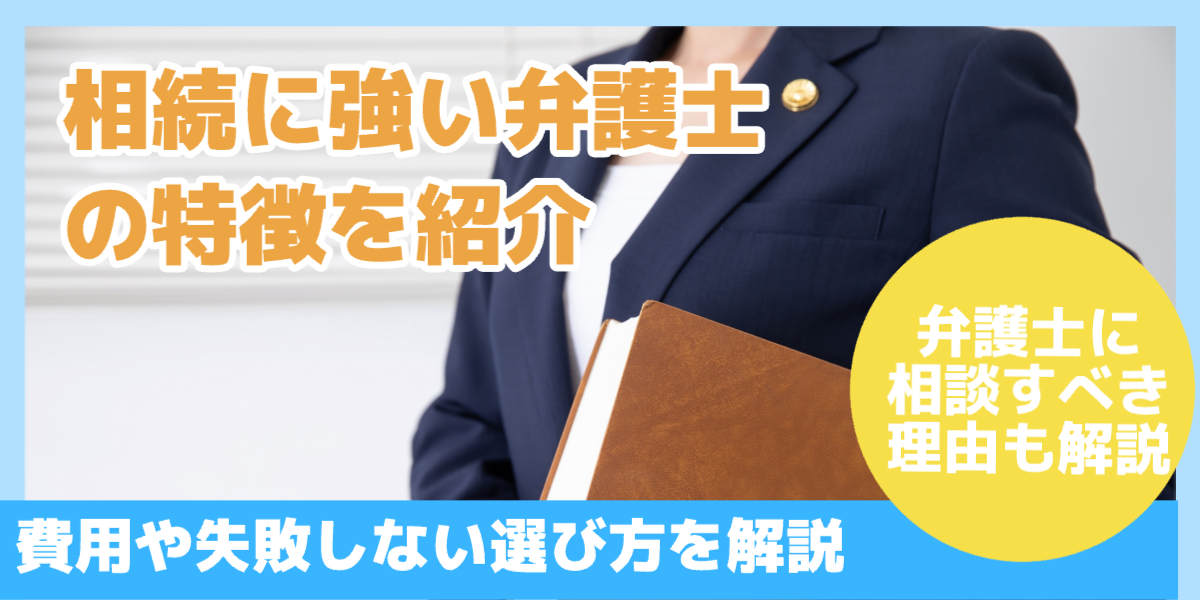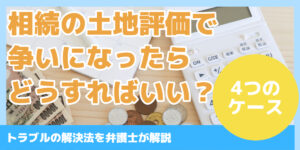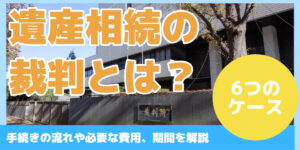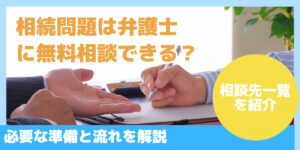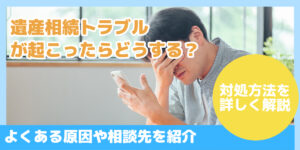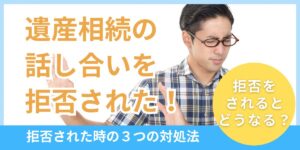【無料相談受付中】24時間365日対応
【チェックリスト】死亡後の手続きの優先順位とは?亡くなったあと遺族がやることや期限について解説
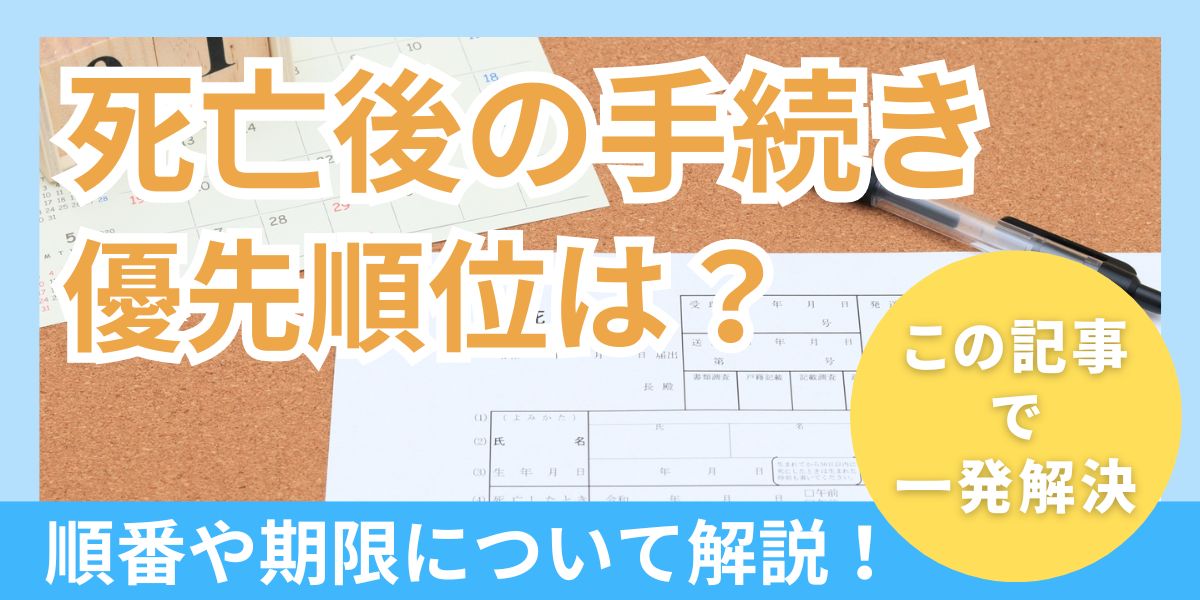
「家族の死後、まず何の手続きから始めればいいのか分からない」
「手続きの期限を過ぎたらどうなるのか」
身近な人の死後に必要な手続きや優先順位について、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
死亡後の手続きには、葬儀直後に済ませるべきものから、数ヶ月以内に判断が必要な相続関連まで、明確な優先順位と期限が存在します。ここを誤ると、過料を科されたり、本来引き継ぐ必要のない借金まで背負ったりするリスクもゼロではありません。
本記事では、数多くの相続案件を扱ってきた弁護士が、死後手続きの全体像を整理し、時期別・優先度別のチェックリストとして解説します。
まずは焦らず、直近でやるべきことから一つずつ確認していきましょう。
死亡直後の役所手続きは期限厳守が鉄則:死亡届(7日以内)や世帯主変更・各種保険の資格喪失(14日以内)が最優先。これらは葬儀と並行して対応する必要がある。
銀行口座の凍結と預金引き出しの注意点:金融機関へ連絡した時点で口座は凍結される。また、安易な引き出しは単純承認とみなされ、借金の相続放棄ができなくなるリスクがあるため要注意。
借金回避のための相続放棄は3ヶ月が勝負:故人の負債が疑われる場合、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しないと借金を背負うことになる。財産調査の期間も含め、早期の決断が必須となる。
遺産分割と相続税申告の期限管理の重要性:相続税申告(10ヶ月以内)に間に合わせるには、スムーズな遺産分割協議の成立が前提。親族間で揉める気配があれば、早期の対策が不可欠。
死後手続きの負担軽減と弁護士相談の活用:膨大な手続きや複雑な相続問題を独力で抱え込むのは危険。期限管理や代理交渉を弁護士に頼ることで、精神的負担とリスクを最小化できる。
身近な人の死後、膨大な手続きや迫りくる期限に不安を感じている方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。煩雑な死後の手続きの代行や相続放棄の判断、遺産分割の交渉までトータルでサポート可能です。
初回60分の無料相談も実施しておりますので、期限が過ぎて手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
【優先順位別】死亡後に行うべき手続き一覧

以下は、死亡後に行うべき手続きの一覧です。
| 順番 | 手続き | いつまでに | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 死亡届の提出 | 死亡後7日以内 | ・死亡届 ・死亡診断書 |
| 2 | 火葬許可証の申請・取得 | 死亡後7日以内 | ・死亡届 ・届出人の印鑑・届出人の身分証 |
| 3 | 住民票の除票の取得 | できるだけ早期に行う | ・来庁者の本人確認書類 ・印鑑 |
| 4 | 世帯主の変更 | 死亡後14日以内 | ・来庁者の本人確認書類 |
| 5 | 健康保険・介護保険の資格喪失 | 死亡後14日以内 | ・各種保険証 |
| 6 | 国民年金・厚生年金の喪失手続き | できるだけ早期に行う | ・資格喪失届出 |
| 7 | 雇用保険の喪失手続き | 死亡後10日以内 | ・資格喪失届 |
| 8 | 雇用保険受給者資格証の返還 | 死亡後1ヶ月以内 | ・雇用保険受給者資格証 |
| 9 | 公共料金の解約または名義変更 | できるだけ早期に行う | ・契約会社により異なる |
| 10 | 生命保険の死亡保険金請求 | 死亡後3年以内 | ・所定の請求書 ・死亡診断書 など |
| 11 | 健康保険・葬祭費の請求 | 死亡後2年以内 | ・葬祭費支給申請書、請求書 ・亡くなった人の被保険者証 など |
| 12 | 健康保険・埋葬料の請求 | 死亡後2年以内 | ・亡くなった人の被保険者証 ・死亡診断書 など |
| 13 | 国民年金・死亡一時金の請求 | 死亡後2年以内 | ・亡くなった人の基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) など |
| 14 | 国民年金・遺族基礎年金の請求 | できるだけ早期に行う(5年以上経過すると時効となる可能性がある) | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・死亡者の住民票の除票 など |
| 15 | 国民年金・未支給年金の請求 | できるだけ早期に行う(5年以上経過すると時効となる可能性がある) | ・亡くなった人の年金証書 ・戸籍謄本 ・受け取りを希望する金融機関の通帳 など |
| 16 | 厚生年金・遺族厚生年金の請求 | できるだけ早期に行う(5年以上経過すると時効となる可能性がある)死亡後1年以内 | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・死亡者の住民票の除票 など |
| 17 | 遺産分割協議 | 期限なしただし、できるだけ早期に行う | ・被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本 など |
| 18 | 相続税の申告・納付 | 死亡後10ヶ月以内 | ・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し ・相続人全員の印鑑証明書 など |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
死亡後~葬儀、7日以内に行う手続き
まずは、優先順位の高い死亡後〜葬儀、7日以内に行う手続きについて詳細を説明します。
死亡届の提出
| 手続き内容 | 届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の自治体窓口に提出する |
|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 必要書類 | 死亡診断書又は死体検案書 |
死亡届は、亡くなった事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。また、他の手続きで必要な場合があるため、提出する死亡届はコピーを取っておくのがおすすめです。
なお、死亡届の提出手続きは、以下のいずれかに当てはまる人が行う必要があります。(参考:法務省死亡届)
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人・土地管理人等
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
火葬許可証の申請・取得
| 手続き内容 | 自治体窓口に火葬(埋葬)許可申請書を提出する |
|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 必要書類 | ・死亡届 ・届出人の印鑑 ・届出人の身分証 |
火葬許可証の申請・取得は、自治体の窓口で死亡届の提出と同時に行うのが一般的です。
自分で作成する必要はなく、一般的には、葬儀社が作成を代行して、葬儀の際に渡してくれることが多いです。
死亡後10~14日以内に行う手続き
続いては、死亡後10~14日以内に行う手続きについて説明します。
住民票の除票
| 手続き内容 | 自治体窓口に交付請求書を提出する |
|---|---|
| 期限 | 特になし |
| 必要書類 | ・窓口に来る人の身分証 ・相続関係を証明する書類(戸籍謄本など) ・除票が必要になった手続き関連の書類など |
転出や、死亡等によって、住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。死亡届を提出してから1~2週間で住民票に反映されて除票になります。
住民票の除票の写しは、今後の各種手続きで必要になる場合があります。死亡届を提出してから1~2週間経った頃に、2~3枚取得しておくと良いでしょう。(参考:中央区ホームページ 住民票の除票がほしいとき)
原則として、亡くなった人の住民票の除票を請求できるのは、相続人のみです。
世帯主の変更
| 手続き内容 | 自治体窓口に世帯主変更届を提出する |
|---|---|
| 期限 | 死亡後14日以内 |
| 必要書類 | 窓口に来る人の身分証 |
世帯主の変更手続きは、死亡後14日以内に行います。ただし、旧世帯主の死亡によって世帯人数が1人になった場合については、届出は不要です。(参考:中央区ホームページ )
健康保険・介護保険の資格喪失
| 手続き内容 | 自治体窓口に資格喪失届を提出する |
|---|---|
| 期限 | 死亡後14日以内 |
| 必要書類 | 各種保険証 |
亡くなった人が加入していた健康保険や介護保険については、資格喪失手続きを行う必要があります。手続きは、親族であれば誰でも可能です。
資格喪失届の提出と同時に、各種保険証も返還しましょう。亡くなった人が企業に勤めていた場合は、会社が手続きを行います。
国民年金・厚生年金の喪失手続き
| 手続き内容 | 自治体または年金事務所に受給権者死亡届(報告書)を提出する |
|---|---|
| 期限 | 特にないが、提出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、返還が必要になる。5年をすぎると時効になる事あり。 |
| 必要書類 | ・亡くなった人の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類 |
年金を受給していた人の死亡後には、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。手続きは、未支給年金を受け取れる遺族が行うのが一般的です。(参考:日本年金機構)
雇用保険の喪失手続き
| 手続き内容 | ハローワークに被保険者資格喪失届を提出する |
|---|---|
| 期限 | 被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内 |
| 必要書類 | ・出勤簿 ・離職理由が確認できる書類など |
被保険者資格喪失届の提出は、原則として会社が行うため、遺族が行う必要はありません。(参考:厚生労働省)
これら期限の厳しい手続きに追われ、心身ともに疲弊してしまうご遺族も多いのが事実です。「何から手をつければ良いか分からない」と焦りや不安を感じている方は、今後の優先順位について弁護士に相談することも視野に入れてみてください。
死亡後1年以内に行う手続き
続いては、死亡後1年以内に行う手続きについて説明します。期限には比較的余裕がありますが、手続き漏れがないように注意しましょう。
公共料金の解約または名義変更
| 手続き内容 | 契約会社に連絡し、解約・名義変更の意思を伝える |
|---|---|
| 期限 | 特にないが、早めが良い |
| 必要書類 | 契約会社により異なる |
亡くなった人と同居している親族がいない場合は、解約手続きが必要です。同居している親族がいて、引き続き使用する場合は、名義変更手続きをしましょう。
生命保険の死亡保険金請求
| 手続き内容 | 生命保険会社に保険金を請求する |
|---|---|
| 期限 | 一般的には死亡から3年以内 |
| 必要書類 | ・所定の請求書 ・被保険者の住民票 ・受取人の戸籍抄本 ・受取人の印鑑証明 ・医師の死亡診断書または死体検案書 ・保険証券 など |
生命保険の死亡保険金請求は、保険受取人が行う手続きです。期限には比較的余裕があるものの、できる限り早めに行いましょう。
なお、もし死亡から3年をすぎてしまった場合でも、事情によっては請求できることがありますので、諦めず請求してみてください。
必要書類は保険会社によって異なるため、詳しくは契約会社に確認してください。(参考:公益財団法人 生命保険文化センター)
健康保険・葬祭費の請求
| 手続き内容 | 自治体窓口で国民健康保険葬祭費支給申請書を提出する |
|---|---|
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
| 必要書類 | ・国民健康保険被保険者証 ・喪主の振込先口座が確認できるもの ・届出者の身分証・喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など) |
亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。手続きは、葬祭を行った喪主本人が行います。(参考:目黒区、大分市)
健康保険・埋葬料の請求
| 手続き内容 | 自治体または健康保険組合に健康保険埋葬料(費)支給申請書を提出する |
|---|---|
| 期限 | 埋葬を行った日の翌日から2年以内 |
| 必要書類 | ・事業主による死亡の証明または亡くなった人と申請者が記載された住民票 ・埋葬に要した費用の明細書および領収書 |
亡くなった人が健康保険に加入していた場合、埋葬料として5万円が支給されます。
請求手続きができるのは、亡くなった人により生計維持されていた人、または実際に埋葬を行った人のみです。(参考:協会けんぽ広島支部)
国民年金・死亡一時金の請求
| 手続き内容 | 自治体または年金事務所に国民年金死亡一時金請求書を提出する |
|---|---|
| 期限 | 死亡日から2年以内 |
| 必要書類 | ・亡くなった人の基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票の写し ・死亡者の住民票の除票・受取先金融機関の通帳等 |
亡くなった人が以下の条件にすべて該当する場合、遺族には死亡一時金を請求する権利が認められます。(参考:日本年金機構)
- 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者である
- 保険料を納めた月数が36月以上ある
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった
国民年金・遺族基礎年金の請求
| 手続き内容 | 自治体または年金事務所に年金請求書(国民年金遺族基礎年金)を提出する |
|---|---|
| 期限 | 亡くなった翌日から5年 |
| 必要書類 | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票の写し ・死亡者の住民票の除票 ・請求者の収入が確認できる書類 ・子の収入が確認できる書類 ・死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 ・受取先金融機関の通帳等 |
国民年金に加入していた人が亡くなった場合、亡くなった人に生計維持されていた以下の条件に該当する人は、遺族基礎年金を請求する権利があります。(参考:日本年金機構)
18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者または「子」
国民年金・未支給年金の請求
| 手続き内容 | 自治体または年金事務所に未支給年金・未支払給付金請求書・死亡届(報告書)を提出する |
|---|---|
| 期限 | 受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年 |
| 必要書類 | ・亡くなった人の年金証書 ・亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等) ・亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の除票および請求する人の世帯全員の住民票の写し) ・受取先金融機関の通帳等 |
年金受給者が亡くなった場合、亡くなった人と生計を同じくしていた以下の条件に該当する人は、国民年金の未支給年金を請求する権利があります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
なお、年金を受ける権利は5年が経過しても事情により受給することができる場合がありますので、万一5年を経過してしまっても諦めずに請求してください。(参考:日本年金機構)
厚生年金・遺族厚生年金の請求
| 手続き内容 | 自治体または年金事務所に年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)を提出する |
|---|---|
| 期限 | 権利が発生して5年 |
| 必要書類 | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票の写し |
亡くなった人が厚生年金保険の被保険者だった場合、生計維持されていた遺族は遺族厚生年金を請求できます。(参考:日本年金機構)
雇用保険・未支給失業等給付金の請求
| 手続き内容 | ハローワークに未支給失業等給付請求書を提出する |
|---|---|
| 期限 | 死亡した日の翌日から6ヶ月以内 |
| 必要書類 | ・雇用保険受給資格者証 ・失業認定申告書 ・死亡が確認できる書類 ・続柄が確認できる書類 ・遺族の方の普通預金の通帳 ・キャッシュカード |
未支給の失業等給付がなかったとしても、亡くなった人が雇用保険受給者資格者の場合は、雇用保険受給者資格証をハローワークに返還しましょう。

大切な方を失い、心身共に疲弊する中にもかかわらず、膨大な手続きが待っています。このページをTODOリストとしてご利用ください。また、次に記載する相続手続もまた膨大な手間がかかります。心身の負担を減らすためにも、相続に関することは専門家に依頼することを強くお勧めします。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
死亡後には相続手続きも必要


死亡に伴う手続きの中でも、相続に関する事項は法的な期限が厳格に定められており、遅滞なく進める必要があります。
特に遺産分割や税務申告は専門的な知識を要する場面が多く、初期段階での判断ミスが後々の不利益につながる可能性も否定できません。
相続手続きの全体的な流れは、以下の通りです。
- 遺言書の有無を確認
- 相続人の調査・確定(戸籍収集)
- 相続財産の調査・評価
- 遺産分割協議
- 名義変更・税務申告
本項では、特に期限管理が重要となる3つの手続きについて解説します。
詳しい実務フローについては、以下の解説記事も併せてご参照ください。
関連記事:親の遺産相続手続きの方法は?死亡後の手続きや優先順位
相続放棄は3ヶ月以内
被相続人に多額の借金がある場合や、相続トラブルに関与したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことが可能です。
この申述期限は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と厳格に定められており、この短い期間内に以下の対応を進めなければなりません。
- プラスの財産とマイナスの財産(負債)の正確な調査
- 家庭裁判所への相続放棄の申述
- 調査が終わらない場合の期間伸長の申立て
資産状況が不明確なまま期限を過ぎたり、誤って財産の一部を処分したりしてしまうと、自動的に相続を承認した(単純承認)とみなされます。
一度単純承認となれば、後から多額の借金が発覚しても放棄することはできません。そのため、財産状況が少しでも不透明な場合は、速やかに調査へ着手することが求められます。
所得税の準確定申告は4ヶ月以内
故人が自営業者や不動産オーナーであった場合、あるいは年金受給額などの所得が一定額以上あった場合は、相続人が代わって所得税の申告を行う必要があります。これを準確定申告と呼びます。
申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
通常の確定申告と異なり、相続人が2人以上いる場合は相続人全員の連署が必要となる点に留意しなければなりません。
| 項目 | 準確定申告の概要 |
|---|---|
| 対象者 | 自営業者、年収2,000万円超の給与所得者など |
| 期限 | 相続開始を知った翌日から4ヶ月以内 |
| 提出方法 | 相続人全員の署名・捺印の上、管轄税務署へ提出 |
相続人間で連絡が取れない、あるいは協力が得られない状況下では、期限内の申告が困難になるケースが見受けられます。
手続きが遅れると延滞税等が課される可能性があるため、対象となるか否かの早期確認が重要です。
参考:国税庁|No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
相続税の申告・納付は10ヶ月以内
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告および納付が必要です。
期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。一見すると猶予があるように思えますが、この期間内に以下のステップをすべて完了させなければなりません。
- 戸籍収集による相続人の確定
- 預貯金や不動産など全財産の調査・評価
- 遺産分割協議の成立(誰が何を相続するかの合意)
特に配偶者の税額軽減や規模宅地等の特例といった以下のような減税措置は、原則として期限内に申告を済ませなければ適用されない点に注意が必要です。
万が一、期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、一旦法定相続分で申告・納税を行い、その上で申告期限後3年以内の分割見込書を提出する対応が求められます。
この場合、特例を使えない高い税額で一時的に納税資金を用意する必要が生じるため、資金繰りへの影響も考慮しなければなりません。



期限直前になって慌てたり、本来使えるはずの控除を逃して損をしたりしないよう、少しでも不安があればお早めに弁護士へご相談ください。
関連記事:遺産相続の話し合いを拒否されたときの対処法について解説
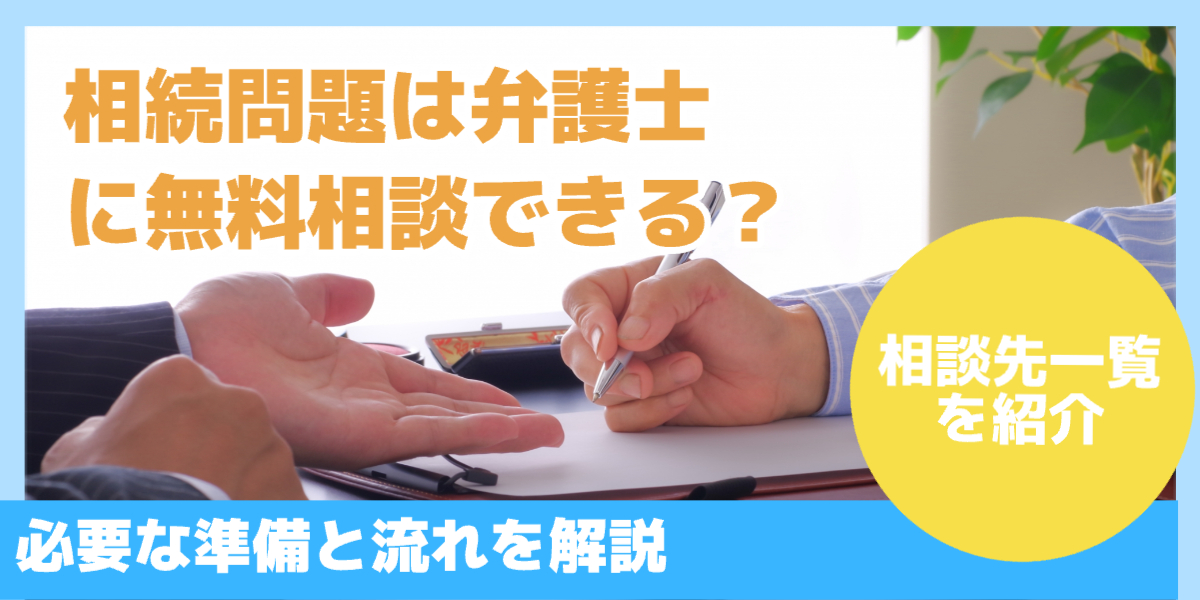
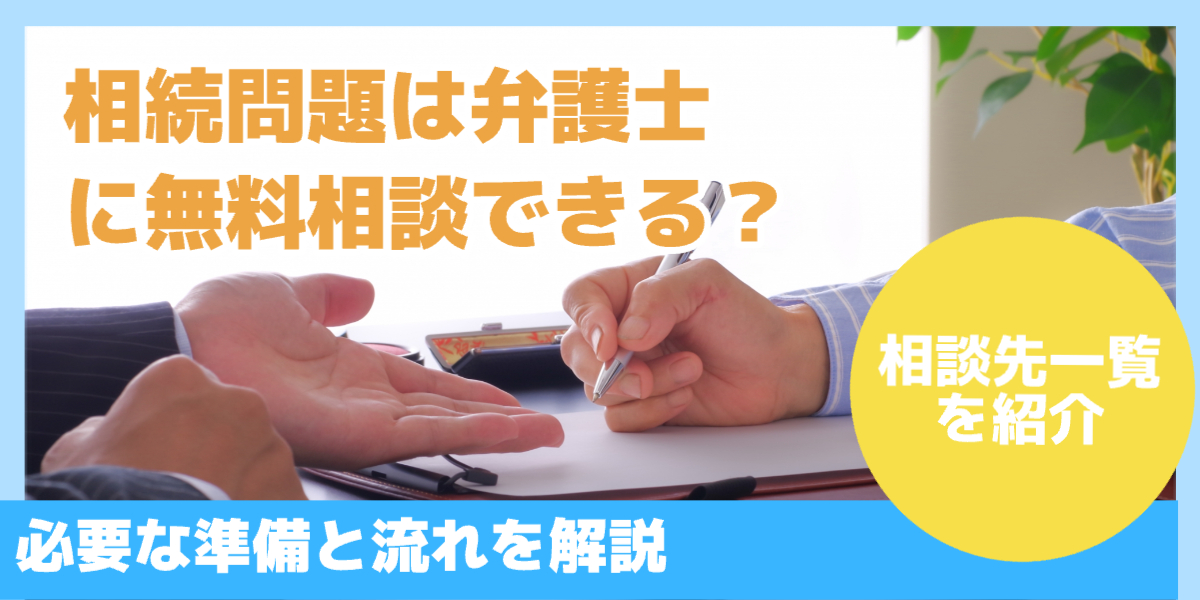
死亡後の手続きを弁護士に依頼すべきケースとは?
死後の手続きは多岐にわたり、個別の事情によってはご自身だけで完結させるのが困難な場面も少なくありません。
特に、金銭的なリスクや親族間の対立が懸念される場合、法的な判断なしに進めると取り返しのつかない事態を招くことさえあります。
弁護士の介入が強く推奨されるのは、主に以下のケースです。
- 借金がある、または資産状況の全容が不明
- 相続人の間で話がまとまらない、または疎遠な親族がいる
- 遺留分(最低限の遺産取得分)の侵害が疑われる
- 手続きをする時間が物理的にない、精神的負担を減らしたい
これらの状況下で無理に自身で対応しようとすると、精神的な疲弊だけでなく、期限超過による不利益を被る可能性も否定できません。
専門家を頼ることは、確実な手続きへの近道であり、ご遺族の心の平穏を守ることにもつながります。
弁護士法人アクロピースでは、代理人としての交渉から事務手続きの代行まで、ご遺族の負担を軽減するサポートを行っています。60分の初回無料相談にて個別の事情をお伺いしますので、おひとりで抱え込まずにお気軽にご相談ください。
空き家放置で相続人18人との遺産分割協議をまとめた事例
財産の状況が分からない中で調査を行い、遺留分を適切に取得できた事例があります。
“被相続人Aさんの遺産分割協議を放置していたが、市から財産である空き家の管理について改善を求める通知を受け、売却などの対応をしようとした。しかし、親類の連絡先がわからず、遺産分割協議を自力で進めることができなかったため相続人の一人である依頼人のBさんが弊所に相談。”
この事例の課題としては、
- 相続人が18人と多数であること
- 空き家状態の解消が行政上求められていた
があげられます。
そこで
- 相続人が18人にものぼる複雑な事案であったが、専門的なノウハウにより迅速に相続人の調査を行い全員と連絡を取る
- 依頼人Bさんの被相続人Aさんへのこれまでの介護の労を全ての相続人に丁寧に説明
というご対応をさせていただき、空き家だったAさんの不動産を売却できるように法的手続きを整え、市からの改善指示にも応えることができました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


死亡後の手続きの優先順位に関するよくある質問
高齢者が死亡した後の手続きは何がありますか?
高齢者が亡くなった際、最優先は7日以内の死亡届の提出と火葬許可証の取得です。これらがないと火葬できません。
その後は、年金の受給停止や未支給請求、埋葬料の申請を行います。
特に注意すべきは相続放棄(3ヶ月以内)と税務申告(準確定申告4ヶ月・相続税10ヶ月)です。期限管理が重要なため、早めに財産調査を開始しましょう。
夫が死亡したら妻がすべき手続きは何ですか?
妻は届出義務者として、7日以内に死亡届を提出します。生活資金確保のため、健康保険等の埋葬料申請や、口座凍結に備えた公共料金の引き落とし先変更も急ぎましょう。
主な期限は、直後の年金確認、3ヶ月以内の相続放棄判断(負債がある場合)、10ヶ月以内の相続税申告です。
各期限から逆算し、優先順位をつけて進めることが大切です。
死亡した人の銀行口座をそのまま使うことはできますか?
原則として、名義人が亡くなった口座をそのまま使い続けることはできません。
金融機関が死亡を知った時点で口座は凍結され、入出金ができなくなるためです。預金を引き出すには、銀行へ連絡し、戸籍謄本などを揃えて正式な相続手続きを行う必要があります。
必要書類は遺言書の有無等で異なるため、まずは取引銀行に問い合わせて案内を受けましょう。
関連記事:死亡した人の銀行口座をそのまま使うことはできる?使い続けるとどうなるか引き落としなどの問題点・必要な手続きを解説
まとめ|死後手続きの優先順位や期限管理に迷ったら弁護士に相談しよう


家族の死亡後にはさまざまな手続きが必要となり、明確な期限が設けられているケースも多いです。
この期限を過ぎてしまうと「借金を背負ってしまう(相続放棄ができない)」「税金の特例が使えない」といった取り返しのつかない不利益を被る可能性があるのも現実です。
本記事を参考に、まずは直近の期限があるものから一つずつ整理していきましょう。もし、財産状況が不明だったり、親族間での話し合いに少しでも不安を感じたりする場合は、一人で抱え込まずに専門家を頼ることも大切です。
死後の手続きや相続トラブルでお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
相続実務に精通した弁護士が、ご遺族の負担を軽減し、円滑な解決に向けて全力でサポートします。 初回60分の無料相談で、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
関連記事:相続争いに疲れたときの対処法について解説