【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義にするメリット・デメリットは?共有名義の土地や不動産のトラブルについて弁護士が解説
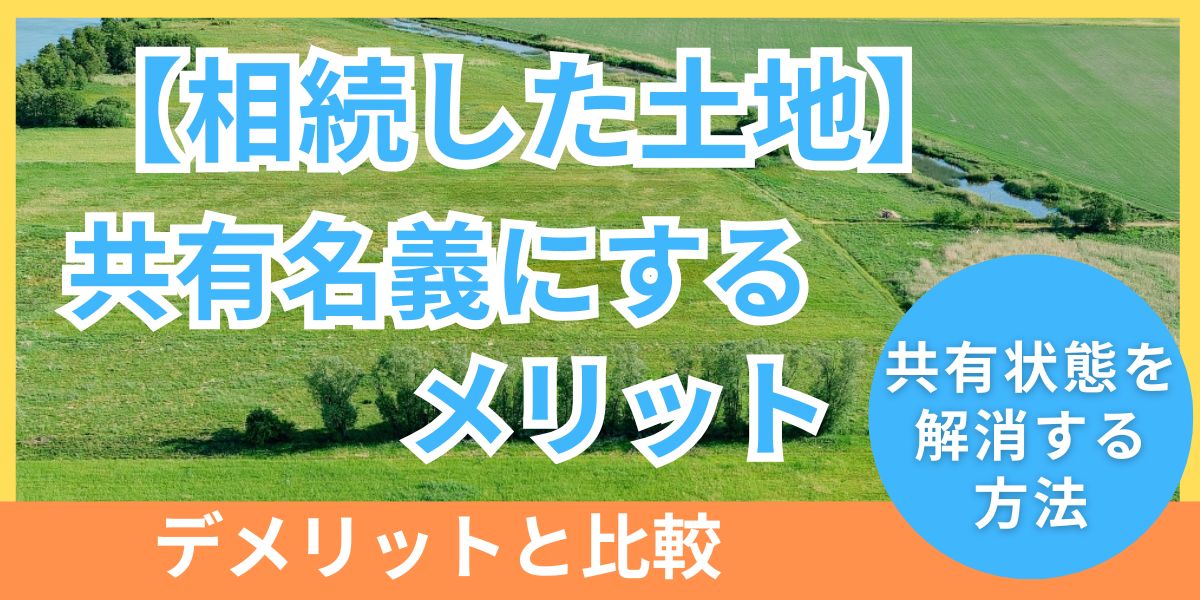
相続した土地を共有名義にすると、公平な分配や節税のメリットがあります。
一方、売却のハードルが高くなるデメリットもあり、土地の共有名義での相続には慎重な判断が必要です。
本記事では、相続した土地を共有名義にするメリットとデメリットを具体的に解説し、最適な相続方法や共有状態を解消する手段についてお伝えします。

「後悔しない土地の相続」を考えるヒントが得られますので、最後までお読みください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
相続した土地を共有名義にするとは?


相続した土地を共有名義にするとは、複数の相続人が共同で所有権を持つ状態を指します。
土地を共有名義にする際、以下の基礎知識を押さえる必要があります。
単独名義と共有名義の違い
不動産を相続する際、一人の相続人が単独で所有する「単独名義」と、複数の相続人が共同で所有する「共有名義」の2種類があります。
単独名義の所有者は、不動産の売却・賃貸・リフォームなどを自由に決定でき、他者の同意を得る必要がありません。
一方、共有名義では、それぞれの所有者(共有者)は持分割合に応じた権利を持ち、不動産全体の活用方針を単独で決められないなどの制約があります。
不動産全体の売却やリフォームするには、すべての共有者の同意が必要です。
関連記事:共有名義のリフォームで注意すべき点は?同意の範囲や贈与税について弁護士が徹底解説
共有名義になる主なケース
不動産が共有名義になる主なケースには「不動産を共同で購入する場合」「相続によって共有名義になる場合」があります。
不動産を共同で購入する場合
複数人が資金を出し合って購入した不動産は、出資額に応じた持分割合による共有名義になります。
たとえば、5,000万円のマイホームを夫と妻がそれぞれ2,500万円ずつ出資して購入した場合、持分割合が各50%の共有不動産として登記されます。
相続によって共有名義になる場合
遺言がなく相続財産に不動産が含まれている場合、相続人間で遺産分割協議を行い、単独で相続するか、共有名義にするかを決定するのが一般的です。
相続人同士の話し合いによって共有名義を選択することもあれば、協議がまとまらず、結果として法定相続分に基づいた相続登記が申請され共有名義になるケースもあります。
共有持分について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:共有持分とは?共有者の権利・トラブル事例
相続した土地を共有名義にする3つのメリット


相続した土地の共有名義には、いくつかの利点があります。
共有名義で土地を相続する主なメリットは、以下の通りです。
公平な相続が可能
土地を遺産相続する際に共有名義にすることは、公平な相続を実現しやすいというメリットがあります。
土地などの不動産は、物理的に分割するのが困難な場合が多く、単独名義で特定の相続人が取得すると、他の相続人との間で不公平感が生じる可能性があります。
しかし、共有名義は、各相続人の法定相続分に応じた持分を設定でき、公平な分配が可能です。
土地の共有名義は、公平な相続を実現するための選択肢として、有効な方法の一つといえます。
居住用財産なら売却時に共有者それぞれが特別控除を受けられる
居住用財産として建物とともに土地を売却する場合、3,000万円の特別控除が受けられます。
共有名義であれば、共有者それぞれがその控除を受けられるメリットがあります。
3,000万円の特別控除は、不動産の譲渡所得税を軽減する制度であり、居住用財産(マイホーム)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円まで差し引くものです。
不動産を売却すると、取得価格と売却価格の差額(譲渡所得)に対して所得税や住民税が課税されます。
しかし、居住用財産であれば、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられ、税負担が軽減されるのです。
単独名義の場合、この控除は1人分(3,000万円)しか適用されませんが、共有名義であれば共有者ごとに3,000万円の控除が適用されます。
ただし、特別控除を受けられる居住用住宅には、原則として売主本人の住居用家屋である必要がありますので、共有者の一人だけが居住する場合には、他の共有者は控除を受けられない可能性があります。
控除を受けられるか否かについては専門家に相談しましょう。
維持費・諸経費を分担できる
相続した土地の共有名義には、維持費や諸経費を共有者間で分担できるというメリットがあります。
土地を所有していると、固定資産税や都市計画税、維持管理にかかる費用(草刈りや雑木の手入れの費用、土壌保全費、不法投棄対策費など)が発生します。
単独名義の場合、これらの費用をすべて1人で負担しなければなりませんが、共有名義であれば、各共有者で分担が可能です。
不動産の共有は、維持費や諸経費を共有者間で分散し、経済的な負担を軽減できるメリットがあります。
相続した土地を共有名義にする3つのデメリット


相続した土地の共有名義にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
土地を共有名義で相続する主なデメリットには、以下の3つが挙げられます。
共有者全員の同意がないと売却できない
共有名義の土地は、活用や処分について共有者間の意見が一致しないと、適切な運用が困難になるケースがあります。
共有名義の土地全体を売却するには、すべての共有者の同意が必要となるため、単独名義の不動産よりも売却のハードルが高いのが現状です。
共有名義の土地では、行為の種類によって必要とされる同意の範囲が異なります。
| 行為の種類 | 具体的な内容 | 必要な同意の範囲 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 共有物の修理や、不法占拠者に対する立ち退き請求 | 各共有者が単独で実施可能 |
| 管理行為 | 共有物の賃貸や維持管理に関する決定 | 共有者の持分割合の過半数の同意が必要 |
| 小規模な改修・変更 | 建物の外壁や屋根の修繕 | 共有者の持分割合の過半数の同意が必要 |
| 重大な変更・処分 | 共有物の売却や増改築などの重要な決定 | 共有者全員の同意が必要 |
共有者の同意が必要な範囲は、行為の内容によって異なり、売却のような重要な決定には、全員の同意がなければ成立しません。
共有者の一人でも反対すると土地全体の売却は不可能となるため、共有名義の土地には有効活用が難しくなるリスクがあります。
関連記事:共有不動産はどうしたら売却できるの?同意が必要なケースと持分の処分方法を解説
共有者が死亡すると相続人が増え権利関係が複雑化する
共有名義の土地は、共有者の死亡によって持分が相続されるたびに権利関係が複雑化します。
共有者が亡くなると、その持分は相続されます。
相続人が複数いる場合、共有持分は細分化され、管理や処分の意思決定に関わる人数が増えて合意形成が難しくなるのです。
特に共有者に面識のない人や連絡がつかない行方不明者が含まれている場合は、売却に必要な全員の合意が一層困難になります。
関連記事:不動産の共有名義人が死亡したらどうなる?誰が相続するか、手続きの流れなどを解説
固定資産税の支払いでトラブルが発生しやすい
共有名義の土地所有には、固定資産税の支払い方法や負担割合をめぐって、共有者間で意見が対立する危険性をはらんでいます。
共有不動産では、各共有者が持分割合に応じて固定資産税を負担するのが一般的です。
しかし、実務上は代表者1人が全額を納付し、他の共有者に持分割合に応じた金額を請求する方法がとられる場合が多いです。
共有不動産の固定資産税には、以下のようなトラブルを招きやすい要因があります。
- 各共有者から代表者へ支払いが遅れる
- 一部の共有者が支払いを拒否する
- 土地を利用している共有者と、利用していない共有者の間で「利用者が多く負担すべき」という考えと「持分割合どおりに負担すべき」という考えが対立する
これらの問題が発生すると、共有者の間で不公平感が広がり、人間関係のトラブルへと発展するケースがあります。
関連記事:共有者が固定資産税を払わないときは?立て替えた際の請求方法や解決策を解説
相続で土地を共有名義にすることはメリットよりもデメリットの方が大きい
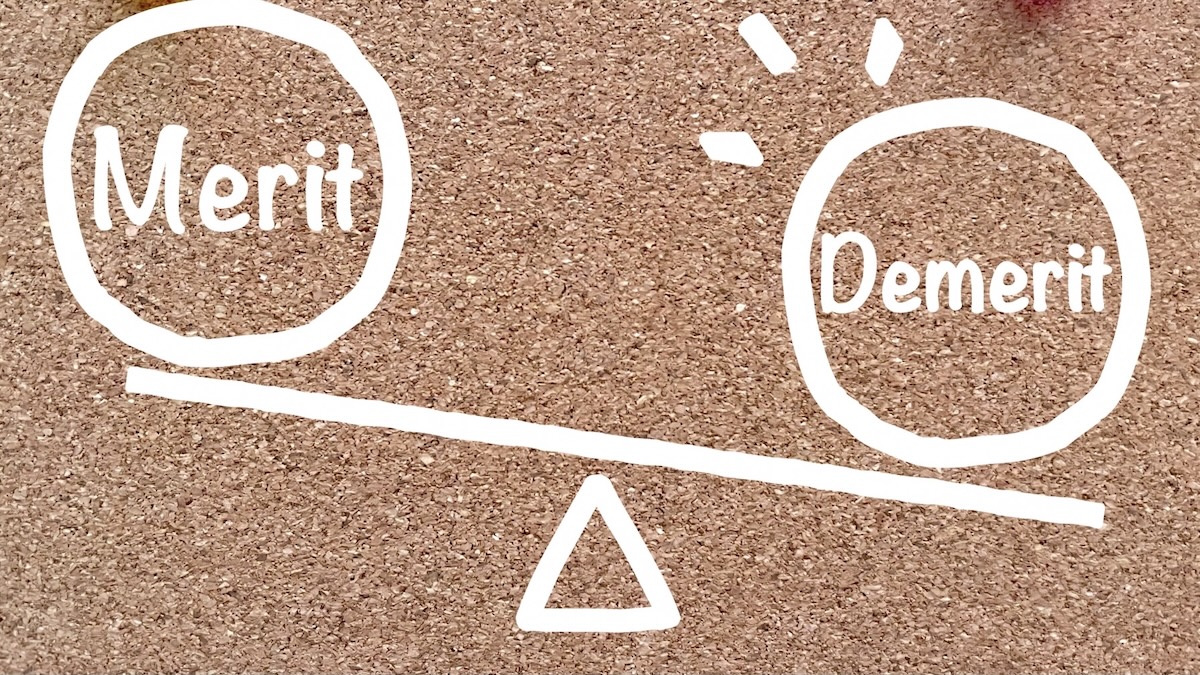
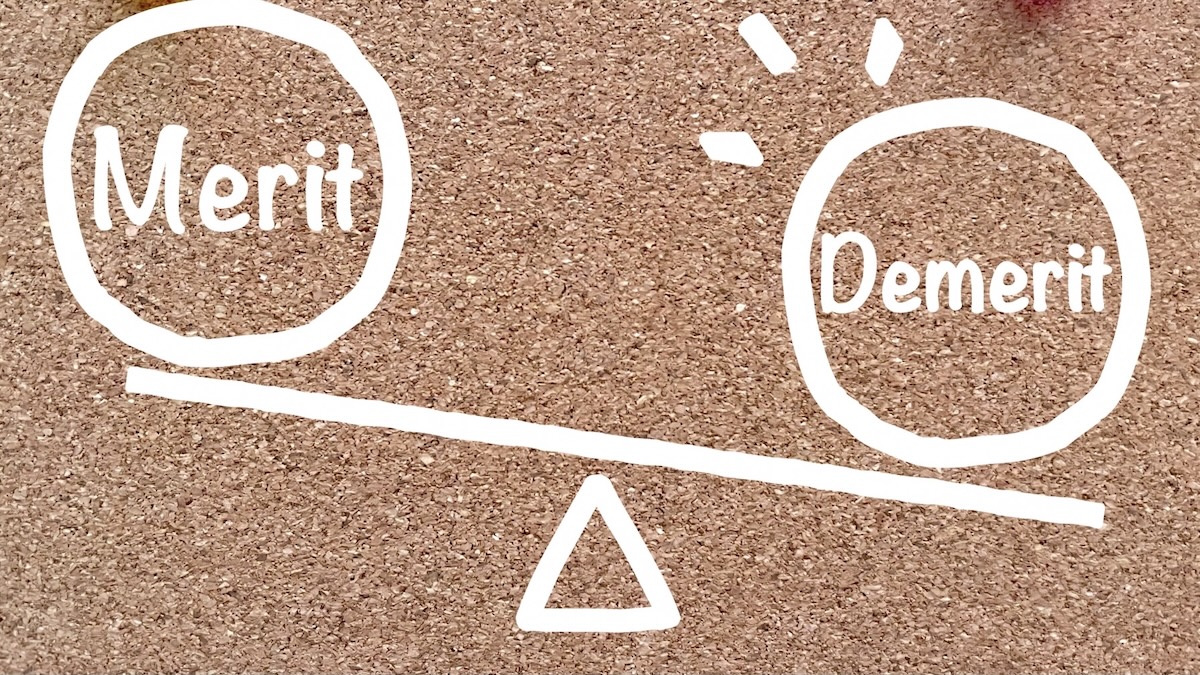
相続による土地の共有名義は、一見すると公平な分配のように思えます。
しかし、長期的には管理や処分が困難になり、トラブルの原因となるケースが多いため、共有名義での相続は慎重な判断が必要です。
以下に、土地を共有名義で相続するメリットとデメリットをまとめました。
| 公平な相続 | ○メリット | 各相続人が法定相続分に応じた持分で、公平な分配が可能 |
|---|---|---|
| 売却時の税制優遇 | ○メリット | 居住用財産として売却する際、共有者ごとに3,000万円の特別控除を受けられる |
| 維持費の負担 | ○メリット | 固定資産税や管理費を共有者間で分担でき、個々の負担が軽減される |
| ×デメリット | 一部の共有者が支払いを拒否すると、特定の共有者に負担が偏る | |
| 活用の自由度 | ×デメリット | 共有者間で意見が分かれると、意思決定が進まず活用の機会を損なう |
| 権利関係の複雑化 | ×デメリット | 共有者が亡くなるたびに相続が発生し、権利者が増えて意思決定がさらに難航する |
共有名義の土地にはメリットも存在しますが、管理や処分の難しさや、共有者間の人間関係が悪化するリスクを考えると、デメリットの方が大きいといえます。
できれば土地を共有名義で相続するのは避け、すでに共有状態であるなら早期に解消するのが望ましいでしょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
土地の共有状態を解消する方法


土地の共有名義は、将来的なトラブルを防ぐため、早めに解消するのがよいでしょう。
共有状態を解消する主な方法は、次の通りです。
共有者全員が同意して共有名義の土地全部を第三者に売却する
相続した土地の共有状態を解消する方法の一つとして、共有者全員の同意を得て、土地全体を第三者に売却する方法があります。
土地全体を売却して代金を持分割合に応じて分配し、共有名義を解消します。
共有者全員の合意を得て土地全部を売却する方法は、通常の不動産と同様に市場価格での売却も可能です。
ただし、すべての共有者の同意が必要で、共有者の人数が多く意向の食い違いがある場合は、合意を得るのが難しく売却の実現が困難になるケースもあります。
共有名義の土地全部の売却には、共有者全員の合意を得るという障壁が存在します。
土地を分筆する
分筆とは、登記簿上一つの土地を複数の土地に分け、それぞれを独立した不動産として登記する手続きです。
分筆後は、各共有者が自分の単独名義で所有できるため、売却や活用の自由度が高まります。
ただし、分筆には他の共有者全員の同意が必要です。
さらに、測量や登記申請などの手続きが必要で、これらの費用も発生します。
また、以下の条件を満たさないと、分筆後の土地に新たに建物を建築できません。
- 自治体が定める最低敷地面積以上である
- 接道条件をクリアしている
- 土地に高低差がある場合、自治体の基準に従い、造成工事や擁壁を設置している
分筆を検討する際は、登記上の手続きだけでなく、分筆後の土地の利用目的に応じて、建築基準法上の条件も考慮する必要があります。
共有者の持分をすべて買い取る
共有名義の土地を解消する方法の一つとして、他の共有者から持分を買い取り、単独名義にする方法があります。
一部の共有者の持分を取得するだけでは引き続き共有状態が継続するため、完全に解消するには、すべての共有持分の買取が必要です。
すべての共有持分を購入すれば、意思決定を単独で行えます。
ただし、この方法を実現するには、他の共有者全員の同意が必須です。
共有者の中には、売却に消極的な人や、持分の価格に納得しない人がいる場合もあり、交渉が難航する可能性があります。
また、すべての土地を買い取る資金力も求められます。
関連記事:共有持分の買取はできる!3つの請求方法と買取成功のポイント・注意点も解説
自分の持分を買取会社など第三者に売却する
相続により共有名義となった土地の持分は、他の共有者の同意がなくても買取専門会社など第三者への売却が可能です。
しかし、持分の売却によって、自身は共有関係から抜け出せますが、土地の共有状態そのものが解消されるわけではありません。
また、持分のみの売却は市場の流動性が低く、買い手が限定されるため、時価よりも安い価格での取引になるケースが多いです。
さらに、買取専門会社が持分を取得した場合、他の共有者に持分の売却や買取の営業をかけるなどにより、トラブルが発生するケースも少なくありません。
共有持分の買取会社が絡むトラブルについての詳細は、こちらの記事をお読みください。
関連記事:【共有持分買取業者への売却】起こりうる6つのトラブル・回避法
自分の共有持分を他の共有者に売却する
自身の共有持分を他の共有者に売却することによって、共有状態から離脱できます。
共有者が3人以上いる場合でも他の共有者の同意は必要なく、当事者だけで売買が可能です。
この方法のメリットは、共有者間での取引であるため、共有持分を買取会社に売却するよりもトラブルのリスクが低い点です。
ただし、共有者は親族同士である場合が多く、売却価格で折り合いがつかないときなどは揉めごとに発展し、人間関係が悪化してしまうケースも見受けられます。
関連記事:共有不動産の持分を売却するとどうなる?起こりうるトラブルと注意点や費用を解説
ほかの共有者に対して共有物分割請求を行う
共有名義の土地を売却したくても、他の共有者の同意が得られず、持分の買取にも応じてもらえない場合、裁判所に共有物分割請求の調停申立てや訴訟を提起する方法があります。
共有物分割には、主に3つの方法があります。
| 現物分割 | 土地を分筆によって分ける |
|---|---|
| 価格賠償 | 特定の共有者が不動産全体を取得し、他の共有者に持分相当額を支払う |
| 換価分割 | 競売にかけて売却代金を分配する |
裁判所は不動産の状況や当事者の主張を考慮して、最も適切な分割方法を判断します。
もし、裁判所から競売による換価分割が命じられた場合でも、単独で持分を処分するより高値で売却できる可能性があります。
ただし、競売による売却は、相場より低い価格となるリスクもあるため、弁護士に相談しながら最適な分割方法を検討してください。
共有物分割請求について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリットを紹介
関連記事:共有物分割請求訴訟の手続きの流れ|メリット・デメリット
共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット
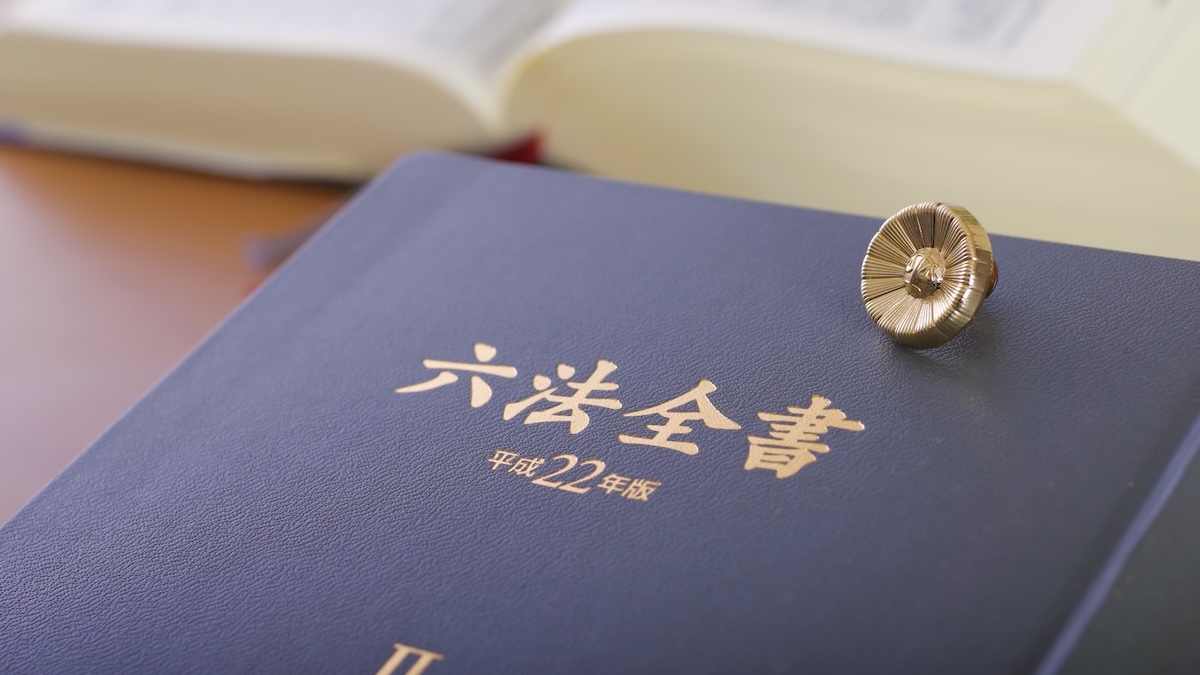
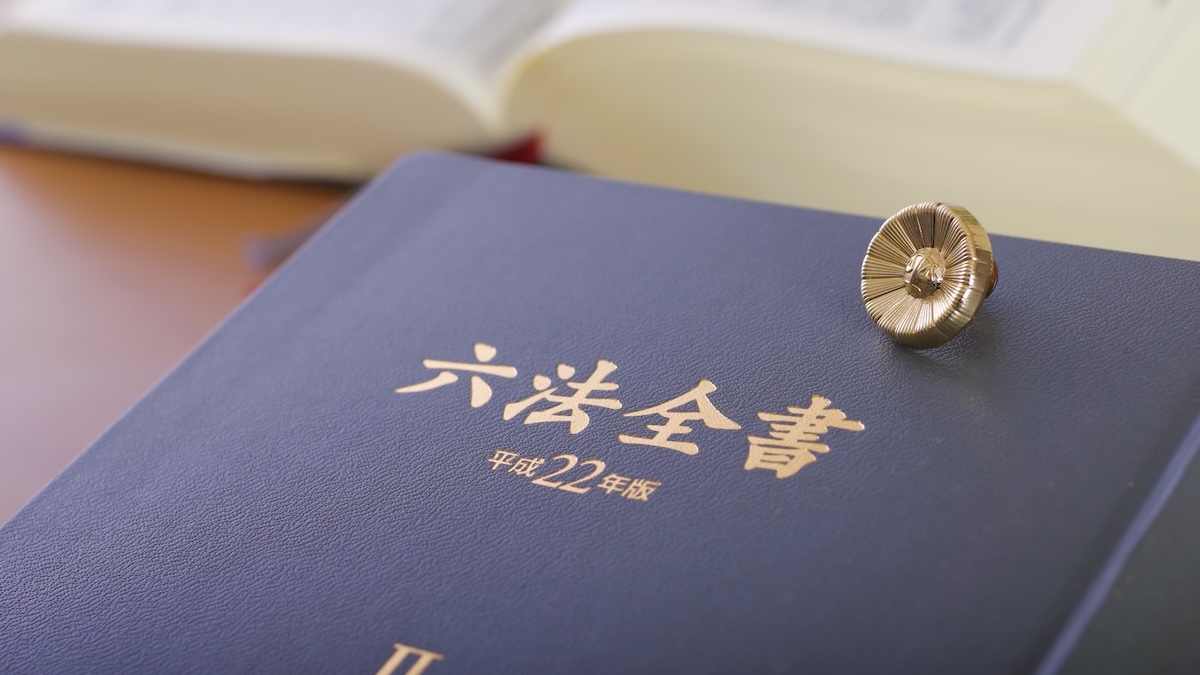
土地の共有状態の解消には、共有物分割請求が有効な手段です。
個人でも手続きは可能ですが、法律の専門知識が求められる場面も多いため、弁護士への依頼を推奨します。
共有物分割請求を弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
| 共有者間の関係悪化を防ぐ | 共有物分割の話し合いは、共有者間で意見が対立するケースも多いため、弁護士の介入によって冷静な協議が可能になる |
|---|---|
| 利益の最大化が可能 | 共有持分のみを売却すると、通常の市場価格より低く評価される場合が多いが、弁護士は適正価格での買取交渉や共同売却を進め、依頼者の利益の最大化を図ってくれる |
| 手続きをスムーズに進められる | 弁護士は以下の手続きを的確に進めてくれる 法的書類の作成 共有不動産の評価額の算定 協議がまとまらない場合の調停や訴訟手続き |
| 精神的負担の軽減 | 弁護士による代理交渉で、依頼者の精神的な負担を軽減する |
土地の共有名義で悩んでいる方は、弁護士へ相談し、共有状態の早期解消を図ってください。
関連記事:共有物分割請求を弁護士に依頼するメリットは?相談から解決までの流れ
関連記事:共有物分割請求にかかる弁護士費用は?相場や具体例、安く抑える方法を解説
相続した土地の共有名義に関するよくある質問
共有者の一人が死亡した場合はどうなりますか?
共有者の一人が亡くなった場合、その方の共有持分は相続人に承継されます。
たとえば兄弟2人で土地を共有していた場合、そのうちの1人が亡くなれば、その共有持分は原則としてその人の配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれます。
結果として、新たに複数の相続人が権利者として登場することになり、土地の権利関係が一層複雑になる可能性があります。
こうした複雑化は、不動産の売却や管理の際の意思決定をさらに難しくし、トラブルの火種となりかねません。
相続が発生する前に、あらかじめ遺言や共有持分の使用方法を合意しておくなどで持分の取り扱いについて明確にしておくことが望ましいでしょう。
共有名義の土地の固定資産税は誰が払うのですか?
固定資産税は、所有者全員に対して課税される仕組みです。
実務上は、自治体から送られてくる納税通知書が代表的な1名に送付され、当該人物が一括で納付するケースが多いです。
その後、他の共有者に対して、持分割合に応じた費用の精算を請求するのが一般的な流れですが、実際には以下のようなトラブルが起こりやすい傾向があります。
- 他の共有者が支払いに応じない
- 支払額の計算方法で揉める(利用の有無や経済状況に基づく主張の違い)
- 一部共有者と連絡がつかない
こうしたリスクを回避するためには、あらかじめ共有者間で費用負担に関する取り決め(契約書等)を作成しておくことが望ましいとされています。
土地を共有名義にすると節税になりますか?
節税につながる場合もありますが、必ずしも共有名義が節税に有利とは限りません。
たとえば、共有名義にすることで有利になる場面としては、共有名義で不動産を売却した場合、共有者ごとに「3,000万円の譲渡所得控除」が適用される可能性があります(ただし、居住用財産であるなど一定の要件あります)。
また、相続税の計算においても、共有名義にしておくことで各相続人の課税価格を調整しやすくなるメリットもあります。
しかし、次のようなデメリットも同時に存在します。
- 共有持分を放棄したことにより、他の共有者に贈与税が発生するケースがある
- 名義を変更したことで実質的に贈与したとみなされると節税にならない可能性があります
節税目的で共有名義にする場合は、税理士や弁護士などの専門家に事前に相談し、制度の趣旨や要件を踏まえた上で慎重に判断する必要があります。
兄弟で土地を相続すると揉めるのはなぜですか?
兄弟間の共有名義は、価値観や生活状況の違いから合意形成が難航しやすく、揉める原因になりがちです。
兄弟間の共有不動産で揉める点としては、以下のような点が挙げられます。
- 一方が「売却したい」、もう一方が「手放したくない」と希望が対立する
- 管理費や固定資産税の負担割合や支払いの有無で対立する
- 土地の使用状況に偏りがあり、不公平感が生まれる
- 兄弟の一方が死亡し、その相続人(姪や甥)との話し合いが困難になる
- 連絡が取れない共有者の存在により、意思決定ができなくなる
また、兄弟間では「話せば分かるだろう」「親の遺志を尊重すべき」といった曖昧な期待感や感情のもつれが絡むことも多く、感情的な対立が複雑に絡み合う傾向があります。
兄弟間での共有相続は、将来的な関係悪化や訴訟リスクも見据え、慎重に検討することが重要です。
トラブルを未然に防ぐためには、遺言書の作成や遺産分割協議による単独名義への変更など、早い段階での対策を講じておくことをおすすめします。
関連記事:兄弟での不動産共有名義は危険?起こり得るリスク・解消方法を弁護士が解説
関連記事:共有不動産を現金化する5つの方法とは?
まとめ|単独で持分を売るよりも高額で現金化できる共有物分割請求は弁護士に相談しよう
土地を共有名義で相続するメリットとデメリット、共有状態の解消方法について解説しました。
【メリット】
- 土地を共有名義にして相続すると法定相続分に応じて持分の設定ができるため、不公平感が少ない
- 共有名義の居住財産の売却には共有者それぞれに特別控除が受けられる
- 共有名義の土地の維持費や諸経費は、共有者の持分割合で分担できる
【デメリット】
- 相続によって共有状態になった土地の売却には、共有者全員の同意が必要
- 相続が発生するごとに共有者が増え権利関係が複雑になってしまう
- 共有名義の土地の固定資産税の支払いは一般的に代表者が全員分を立て替えて支払うが、他の共有者の送金が遅れたり、支払いが滞ったりするとトラブルになる可能性がある
【共有状態の解消方法】
- 土地の共有状態の解消には、共有者全員で同意して第三者に売却する方法や分筆して単独名義にする方法がある
- 共有者間の持分の売買によって単独所有にする方法もある
- 自分の持分を単独で第三者に売却が可能だが、購入者の利用が制限されるという理由で市場価格より安い価格でしか売却できない場合が多い
- 共有者の中に売却に応じてくれず、持分も買い取ってくれない場合は、共有物分割請求訴訟で競売による換価を求められる
共有物分割請求により競売で共有名義の土地を売却できれば、単独で持分を売るよりも高額で現金化できる場合が多く、すべての共有者にメリットがあります。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









