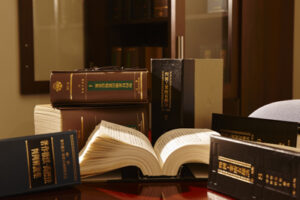【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の相続はどうなる?手続きの流れや共有名義のメリットデメリットを弁護士が解説

「共有名義の不動産の共有者が亡くなったら、相続はどうなるの?」
「共有名義のままで良いのかな……?」
共有名義になっている不動産をどう相続すべきか悩む方は多いのではないでしょうか。
共有不動産を相続する場合、相続人調査や財産調査、登記手続きなど、やるべくことが多くあります。相続時のトラブルを防ぐには、事前に相続の流れや共有名義のメリット・デメリットを把握することが大切です。
この記事では、共有不動産の相続の流れを7ステップで解説します。

共有状態の解消方法である共有物分割請求についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義の不動産は「亡くなった人の法定相続人が相続する」
共有名義の不動産の共有者が亡くなった場合、亡くなった人の法定相続人が相続します。
法定相続人とは、民法で定められた「遺産を受け取る権利がある人」のことです。
配偶者は常に相続人となり、第2順位に亡くなった人の父母・祖父母、第3順位に亡くなった人の兄弟姉妹が優先されます。
(参照:国税庁|No.4132 相続人の範囲と法定相続分)
たとえば夫が亡くなった場合、妻と子どもが法定相続人となり、亡くなった夫の共有持ち分を分けて相続します。
共有名義の不動産は、共有者ではなく法定相続人が相続することを頭に入れておきましょう。
【7ステップ】共有名義の不動産を相続する流れ
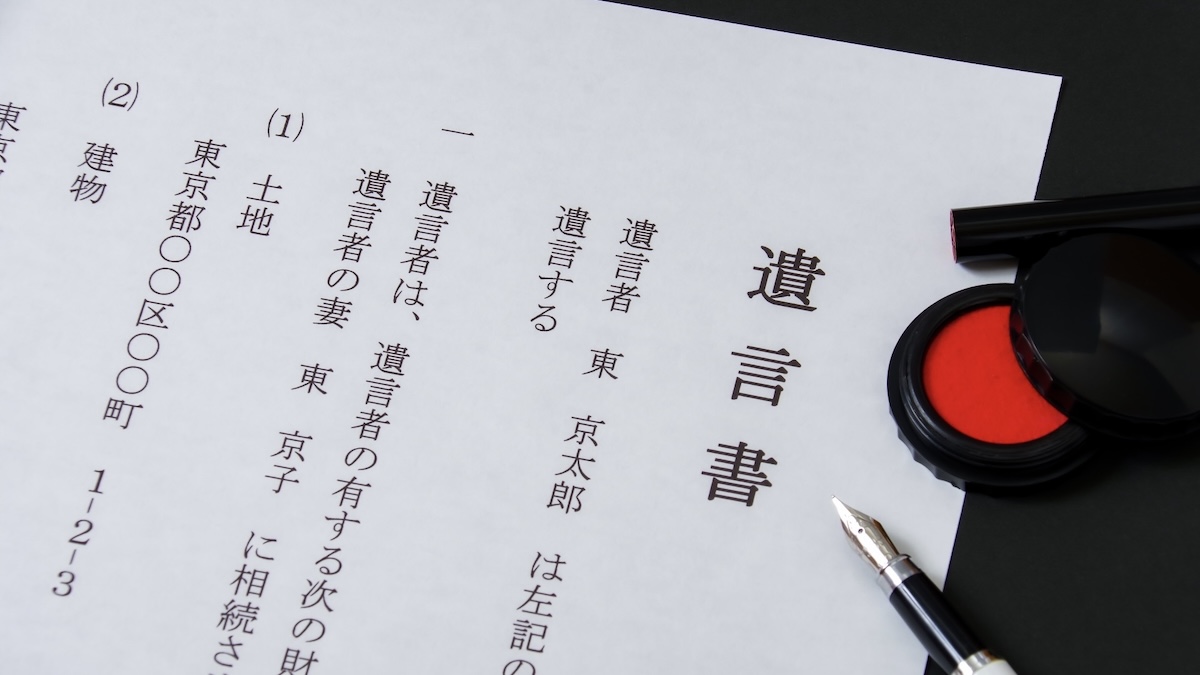
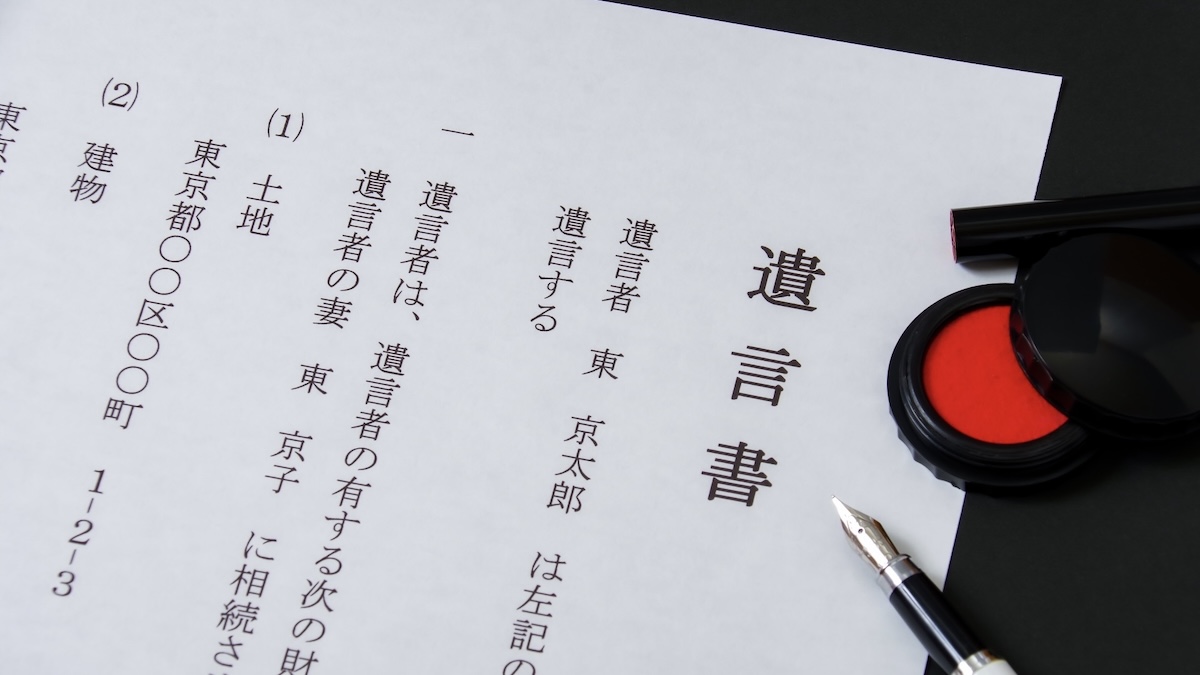
共有不動産の相続では、他の共有名義人ではなく、法定相続人が相続権をもちます。つまり、共有者の一人が亡くなっても、持分が自動的に他の共有者に移転するわけではありません。
被相続人の持分は相続財産として扱われ、手続きが必要です。共有不動産の相続手続きの流れは、以下の通りです。
遺言書があるか調べる
共有不動産の名義人が亡くなった際は、まず、遺言書の有無の確認が重要です。
遺言書が存在する場合、原則として遺言の内容に従って相続登記を行います。
遺言書で一般的に利用されるものには「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれ手続きが異なります。
| 自筆証書遺言 (遺言者が自筆で作成) | 法務局の遺言書保管制度を利用していない場合、登記申請の前に家庭裁判所で検認手続きが必要 検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式を確認し、相続人にその存在を知らせる手続き 法務局の遺言書保管制度を利用している場合、検認は不要 |
|---|---|
| 公正証書遺言 (公証役場で作成) | 家庭裁判所の検認は不要 |
遺言書の内容にもとづく適切な相続登記によって、共有不動産の権利関係を明確にし、円滑な相続手続きが行えます。
相続人調査を行う(遺言書がない場合に限る)
相続人調査とは、戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を確定した上で、相続関係説明図を作成するなど相続人の確定を行う手続きです。
被相続人が遺言を残していない場合、共有不動産の持分を誰がどの割合で相続するかを決めるために、相続人全員で話し合う必要があります。
この話し合い(遺産分割協議)は、法定相続人全員の合意が必要であり、一部の相続人が未確定のままでは成立しません。
相続人調査を怠ると、後から新たな相続人が判明し、合意の見直しや追加の手続きが必要になる可能性があります。
スムーズな相続手続きを進めるためには、正確な相続人調査が重要です。
相続財産調査を行う
相続人調査だけでなく、相続財産調査も実施する必要があります。
財産の内容や価値が分からないままでは、遺産分割協議も相続税申告も進められません。
相続財産には、現金や預貯金、不動産、有価証券のほか、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
(参照:国税庁|No.4105 相続税がかかる財産)
たとえば不動産については、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書を確認し、共有名義かどうか、持分割合も調べておくことが大切です。
財産調査を怠ると、後から未確認の借金が発覚したり、相続トラブルにつながったりするリスクがあります。
見落としがないよう、丁寧に調査しましょう。
遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、相続財産の分割方法を決定するために、法定相続人が行う話し合いです。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必須であり、合意が得られたときは、その内容を文書にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記のほか、預貯金の解約や相続税申告などの相続手続きに必要な書類です。
作成した遺産分割協議書は、今後の相続手続きに備えて適切に保管し、必要な際、すぐに提出できるようにしておきましょう。
遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産の分け方に合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
遺産分割協議書とは、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きなど、各種相続手続きにおいて必要となる書類です。
不動産を共有名義で相続する場合「誰がどの持分を相続するか」などの詳細を明記し、相続人全員の署名・押印を行います。
協議書がないと実務上の手続きが進められず、トラブルに発展するケースも少なくありません。
話し合いの結果を正式な書面に残し、相続時の混乱や誤解を回避しましょう。
期日までに相続税の申告・納付を行う
遺産分割協議が成立したら、相続税の申告・納付を進めてください。
相続税の申告期限は10カ月以内と定められているため、分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分にもとづく申告が必要です。
相続財産の課税対象額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)を超える場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署へ申告し、相続税を納める必要があります。
(参照:国税庁|No.4102 相続税がかかる場合)
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めの対応が重要です。
相続登記をする(※2024年4月から義務化)
不動産の共有者が亡くなった場合、法務局で相続登記を行い、名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する必要があります。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を期日までに提出することで完了します。
なお、相続登記は、2024年4月から義務化されています。これは、相続登記が行われないことで「所有者が不明な土地」が増え、適切に管理されていない土地が社会問題となっているためです。
(参照:東京法務局|相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~)
「相続人が多くて手続きに時間がかかる」などの正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の罰金が科される可能性があります。そのため、相続人は不動産を相続すると知った日から3年以内に登記申請を行いましょう。
また、共有不動産と知らずに相続してしまったときの対処方法は、次の記事をお読みください。
関連記事:【共有不動産と知らずに相続した土地】時効取得条件・必要な証明
不動産の共有名義を解消せずに相続する2つのメリット
共有名義の不動産を相続する際、共有状態を解消するかしないかで迷う人も多いでしょう。解消せずに共有状態を続けることは、一定のメリットもあります。
ここでは、代表的な2つのメリットを解説します。
公平性が生まれる
不動産を共有名義で相続すると、相続人それぞれが持ち分を持つため、分配に対する公平性が生まれます。
例えば、複数人の子どもがいる家庭で現金資産が少ない場合でも、不動産を共有名義にすることで全員が同じ財産を持てる状態になります。
「自分だけ何ももらえなかった」といった不満が生まれにくく、相続手続きが円滑に進みやすくなります。
特定の相続人だけが不動産を引き継ぐことに抵抗がある場合、遺産の分配をめぐる対立を防ぎたい場合は、共有名義での相続を検討してみましょう。
売却時の税負担を軽減できる
将来その不動産を売却する際に、共有者それぞれが3,000万円の特別控除を個別に適用できる点もメリットです。
これは、相続後にマイホーム(居住用財産)を売却した場合に適用される、譲渡所得の控除特例です。
参照:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
たとえば、共有名義で相続したマイホームを母と子で売却した場合、それぞれに3,000万円の控除枠が認められれば、合計で最大6,000万円の控除が受けられます。
不動産を将来的に売却する可能性がある場合は、節税の観点からも共有名義を検討する価値があります。
不動産の共有名義を解消せず相続する5つのデメリット


相続では、不動産が遺産に含まれているケースが多く、複数の相続人で共有する場合も少なくありません。
しかし、不動産の共有は将来的なトラブルを引き起こす可能性があり、できるだけ避けるのが望ましいとされています。
共有不動産の主な問題点として、以下の点が挙げられます。
共有不動産の売却・活用には共有者全員の同意が必要となる
共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
これは、民法第251条1項において、共有物の「変更」には共有者全員の同意が求められるという規定にもとづきます。
(共有物の変更)
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
民法第251条1項には記載されていませんが、売却も変更に該当すると解されます。
最高裁判所も昭和42年2月23日の判決でこの解釈を支持し、共有不動産の売却には全共有者の同意が不可欠であるという原則を確認しました。
(参照:裁判所|最高裁判例)
共有不動産には、単独所有に比べて手続きが複雑であるという課題があります。
共有者の中に反対者や、連絡が取れない人がいると売却が進められず、資産の活用が制限される点が共有不動産の問題点です。
共有不動産の売却について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:共有不動産はどうしたら売却できるの?同意が必要なケース・持分の処分方法
相続のたびに共有不動産の持分が細分化する
共有不動産の所有者が死亡し、その持分を複数の相続人が引き継ぐと、権利関係が複雑化します。
相続を繰り返すうちに、共有者の数が増え、管理や意思決定が難しくなるためです。
さらに、子ども世代や孫世代にまで共有持分が受け継がれると、意見がまとまりにくく、売却や活用が一層難しくなります。
不動産の共有状態が長く続くほど、相続により持分が細分化される可能性があり、有効利用の妨げになるため早期の対策が必要です。
共有持分のリスクについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:共有持分とは?共有不動産のデメリット・トラブル事例
固定資産税や管理費の支払いをめぐってトラブルに発展しやすい
固定資産税や管理費の負担をめぐってトラブルになりやすい課題があります。
誰がいくら負担するかを明確にしていないと、支払いや責任を押し付け合うトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、兄弟で不動産を相続して共有していたものの、誰も管理せず納税を滞ってしまい、結果的に延滞金や差押えに発展するケースも少なくありません。
また、1人が管理費を立て替えても、他の共有者が返金に応じないと関係悪化の原因になります。
こうした金銭トラブルを防ぐには、共有名義にした段階で費用の分担方法や管理のルールを文書で取り決めておくことが重要です。
管理されないまま放置される恐れがある
共有名義の不動産は、管理されないまま放置される場合あがあります。
共有者同士の意見が合わなかったり、誰も主体的に管理しようとしなかったりすると、適切な管理がされなくなります。
結果として、土地や建物が荒れ果ててしまい、近隣住宅に迷惑がかかるトラブルが多発しやすいのです。
不動産の放置は、建物の倒壊リスクを高めたり、害虫・害獣が発生したりするリスクがあります。責任の所在が分かりにくい観点から見ても、共有名義は避けた方が良いでしょう。
他の共有者が持ち分を第三者に売却する可能性がある
他の共有者が、自分の持ち分を許可なく第三者に売却する可能性があります。
共有名義の不動産では、民法第206条に基づき、自分の持ち分を第三者に売却する行為が認められています。
(所有権の内容)
第二百六条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。引用:民法|e-Gov法令検索
しかし、誰かが勝手に売却した場合、意図しない第三者と不動産を共有することになってしまうのです。このような事態になると、活用や売却の話し合いが一気に難航します。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
不動産の共有状態を解消する7つの方法


相続などで不動産が共有状態となった場合、共有者同士の利害が対立すると管理や処分が難しくなるケースがあります。
そのため、状況に応じた適切な方法で、共有状態の解消を図るのが望ましいでしょう。
共有不動産の主な解消方法は、以下の通りです。
共有不動産の全体を第三者に売却する
共有不動産は、共有者全員の同意があれば第三者に売却し、共有状態を解消できます。
共有持分の売却は、単独では買い手が見つかりにくく、価格が市場相場より低くなる可能性があります。
しかし、共有者全員の合意で全体を売却する場合は、通常の不動産売買と同様に手続きを進められるため、市場価格での売却が可能です。
共有者全員の合意が得られないなどの問題がある場合は、不動産問題に実績のある弁護士へ相談するとよいでしょう。
弁護士は、依頼者と他の共有者の間に入って、双方にとってよりよい解決へ導いてくれます。
共有不動産の売却に関する注意点については、次の記事を参考にしてください。
関連記事:共有名義の不動産売却時のトラブルと防止対策!共有持分売却の対処法
土地の分筆で単独名義にする(共有不動産が土地の場合に限る)
共有不動産が土地のみの場合、分筆によって単独名義にできます。
分筆とは、一つの土地を複数の土地に分けて登記する手続きであり、建物には適用されません。
分筆後は、それぞれの所有者が単独名義になるため、土地をより有効に活用できます。
ただし、分筆には共有者全員の同意が必要です。
また、十分な広さがない土地では分筆が難しく、接道状況や形状によって均等に分けるのが困難なケースもあります。
さらに、測量や登記手続きに費用がかかるため、慎重な検討が必要です。
土地の分筆は有効な共有解消手段ですが、条件やコストを考慮し、共有者間で合意を得るというハードルがあります。
他の所有者の持分をすべて購入する
共有不動産の名義を単独にするには、他の共有者全員の持分を買い取る方法があります。
しかし、すべての持分を取得しなければ単独名義とならず、共有者ごとの事情や意向によっては交渉が難航するケースもあります。
他の所有者の持分すべての買取による共有状態の解消は、交渉や資金計画を慎重に進める必要があるでしょう。
自分の持分を他の共有者に売却する
共有不動産の自分の持分は、他の共有者への売却が可能です。
共有者が複数いる場合でも、自分の持分を売却する際に他の共有者の同意は必要ありません。
持分を他の共有者へ売却することによって、不動産の共有状態がもつリスクを手放せます。
しかし、共有者間であっても売却価格が市場相場と大きく乖離していたり、契約内容に問題があったりすると、後にトラブルへ発展する可能性があるため注意が必要です。
自分の持分を第三者に売却する
自分の持分は、他の共有者の同意を得ずに、第三者へ売却ができます。
持分のみを売却する場合、購入者はその持分の権利しか取得できず、単独で不動産を自由に利用できるわけではありません。
そのため、買い手が見つかりにくく、結果的に共有持分を専門とする買取会社に市場価格よりも安く売却せざるを得ないケースが多いです。
持分を買い取った会社が他の共有者に、持分の売却をしつこく迫ったり、自分が所有する持分の買取の営業をかけたりするなどで、精神的なストレスがかかることもあります。
そのため、持分の第三者への売却は、他の共有者との人間関係を悪化させるなどのリスクをはらんでいるのです。
第三者への持分の売却は慎重な判断が求められます。
共有持分の売却について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:共有持分売却するとどうなる?売却先・問題点・トラブルを避ける方法
持分を放棄する
共有不動産の持分の放棄によって、共有状態から離脱する方法があります。
持分の放棄は正当な権利である一方、無償で手放す行為であるため慎重な判断が必要です。
また、登記費用等の負担も生じてきます。
放棄はいつでも可能であるため、権利を手放す前に、弁護士に相談して最適な選択肢を検討してください。
共有持分の放棄についての詳細は、以下の記事もお読みください。
関連記事:「共有持分放棄は早い者勝ち」は本当なのか?手続きの流れや注意点を解説
共有物分割請求を経て売却する
「共有不動産の売却の同意が得られない」「他の共有者が持分を購入してくれない」または「買い取らせてもくれない」など、話し合いだけでは共有状態が解消できないケースがあります。
そのようなときは、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判断にもとづいて競売(換価分割)や代償分割などによって売却する方法があるのです。
共有物分割請求訴訟では、裁判所の判断により、不動産の競売(換価分割)や代償分割、現物分割などの方法が選択されます。
共有物分割請求は、持分のみを不動産会社などの第三者へ売却するよりも、高額で現金化できる可能性があり、大きなメリットが期待できる選択肢です。
共有状態の解消方法については、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:共有名義の解消方法を解説
関連記事:共有不動産の現金化ついて解説
共有不動産の相続手続きと共有問題の解消は弁護士に相談しよう


共有不動産の相続や共有状態の解消は、法律や手続きが複雑になる場合が多いため、弁護士に相談して適切な対応をとる必要があります。
共有不動産の相続問題を弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- 状況に応じた最適な解決方法のアドバイスが受けられる
- 他の共有者の同意が得られなくても、法的手続きにより共有状態の解消が目指せる
- 不動産の適正な価値評価を依頼できる
- 相続人同士のトラブルが発生した際に調整を行ってもらえる
- 相続人の調査から手続きを依頼できる
- 遺産分割調停や審判の手続きを代理人として進めてもらえる
- 土地家屋調査士や不動産鑑定士などの問題解決に必要な専門家の紹介が受けられる
共有不動産の相続や処分に関する問題は、専門的な知識が求められます。
できるだけ早く弁護士に相談して、迅速な解決を目指しましょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有不動産の相続に関するよくある質問
共有不動産の名義人の片方が死亡した場合、誰が相続しますか?
共有者のうち一方が亡くなった場合、その人が所有していた不動産は法定相続人が相続します。
たとえば、夫婦で2分の1ずつ不動産を共有していて夫が亡くなった場合、夫の持ち分は妻と子どもで分けて相続するのが一般的です。
ただし、遺言書や遺産分割協議によって持ち分の配分は変わる場合があるため、状況に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
共有不動産の共有名義人に相続人がいない場合、誰が相続しますか?
共有者に相続人が一人もいない場合の相続先は、遺言書や特別縁故者の有無によって異なります。
遺言書がある場合は、遺言で指定された受遺者に持ち分が移ります。遺言書がなく、相続人もいないときは、家庭裁判所により相続財産清算人が選任され、財産の管理と清算が行われる仕組みです。
(参照:裁判所|相続財産清算人の選任)
その後、特別縁故者(故人の介護をしていた人など)が申し出て裁判所に認められれば、その人が相続します。
(参照:裁判所|特別縁故者に対する相続財産分与)
それでも該当者がいない場合、最終的には国の財産として国庫に帰属します。(民法第959条より)
夫婦共有名義で夫が死亡した場合の相続人は誰ですか?
配偶者と子がいればその双方が相続人になります。
(参照:国税庁|No.4132 相続人の範囲と法定相続分)
たとえば2分の1ずつの共有なら、妻は自分の持分に加え、夫の持分の一部を相続します。
夫の持分のみが相続対象であり、共有名義全体が相続されるわけではない点に注意しましょう。
まとめ|不動産の相続による共有状態の解消は共有物分割請求による解消がおすすめ!
共有不動産の相続手続きの流れと、共有状態の解消方法をお伝えしました。
- 共有不動産の問題点は、売却に共有者全員の同意が必要であることや、相続のたびに持分が細分化され権利関係が複雑になること
- 共有不動産の相続権は共有名義人ではなく、法定相続人がもつ
- 不動産の共有状態を解消する方法には「共有者全員で同意し全体を売却」「他の所有者の持分をすべて購入する」「自分の持分を他の共有者や第三者に売却する」などがある
他の共有者との話し合いがまとまらない場合にできるだけ有利に持分を高額現金化したいなら、弁護士に共有物分割請求を依頼するのがおすすめです。
共有状態は、不動産の有効活用を妨げるリスクがあります。
共有持分の相続で悩んでいるなら、不動産問題に実績のある弁護士に相談してください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応