【無料相談受付中】24時間365日対応
不動産の共有持分とは?所有するリスクや主なトラブル事例を解説
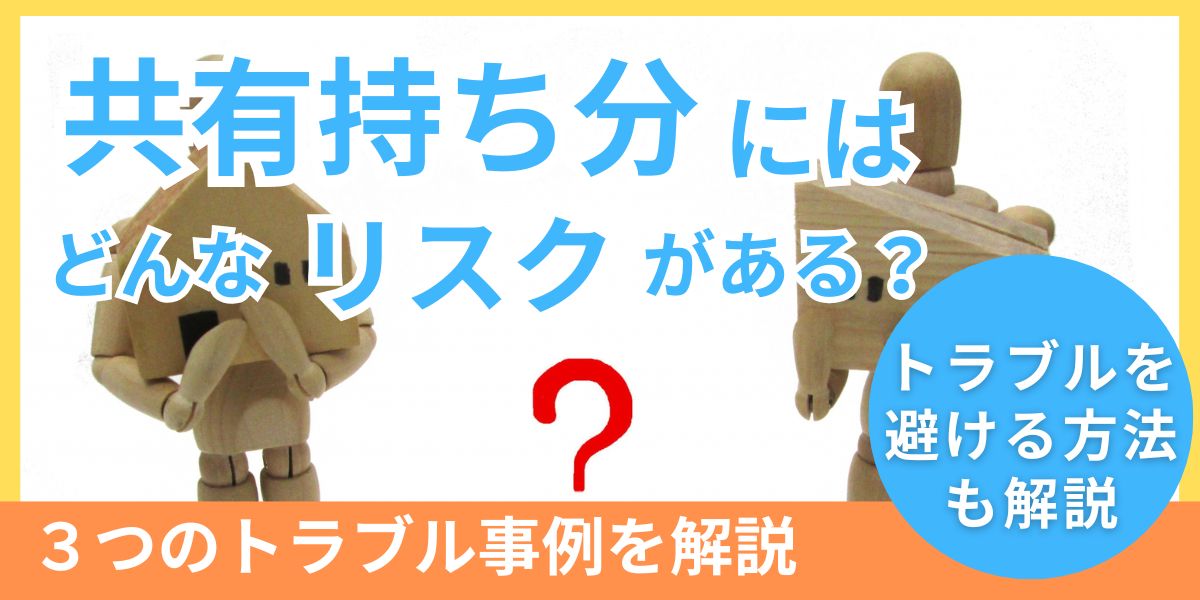
不動産の共有持分の所有には、売却や管理などで他の共有者と意見が衝突し、トラブルが発生するリスクをはらんでいます。
さらに、共有状態が長引くと相続などで権利関係が複雑化し、不動産の有効活用ができなくなってしまうおそれがあるのです。
しかし、共有持分に関する知識を深め、共有状態を解消する具体策を学べば、トラブルを未然に回避する方法が見えてきます。
本記事では、共有持分の仕組みや注意点、さらに共有状態を解消するための手段について解説します。
共有持分は「割合だけの権利」で単独処分には限界がある:売却や賃貸など不動産全体の処分は原則として共有者全員の同意が必要になる。
最大のリスクは「相続による細分化」と「第三者介入」:相続で共有者が増えると合意形成が困難になり、持分売却で見知らぬ第三者が入りトラブル化しやすい。
持分は同意なしで売却できるが価格と関係悪化に注意:法律上は可能でも、時価の1/2〜1/3程度になりやすく、他の共有者に心理的・実務的負担を与える。
トラブル回避の基本は「共有状態を早期に解消すること」:代償分割・換価分割・土地なら分筆による単独名義化が実務上の有効策となる。
揉めそうな段階で弁護士介入が合理的:交渉整理から共有物分割請求まで見据え、資産価値の毀損と長期化を防ぐ判断が重要。
共有持分の私道に関するトラブル事例も紹介していますので、最後までお読みください。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、共有不動産・共有物分割請求について、まずは無料相談から受け付けております。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有持分の基礎知識

複数の人が一つの不動産を共同で所有する場合に各所有者が持つ権利の割合のことを「共有持分」といいます。
共有持分は、不動産の相続や売却、共同購入の場面で頻繁に登場する言葉です。
仕組みを理解しないまま手続きを進めると、思わぬ制約やトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
まずは共有持分の理解を深めるために「共有」と「持分」の意味をしっかり理解しておきましょう。
不動産の共有とは

不動産の
- 複数人で資金を出し合って物件を購入
- 相続により親の所有していた不動産を兄弟姉妹で共有
- 夫婦で共同名義として不動産を購入
- 私道を複数の隣接地主が共同で所有し通行などに利用
共有不動産の管理や処分については、以下のような同意要件が定められています。
| 保存行為 | 共有物の現状を維持するための行為(修繕等)は、各共有者が単独で行える |
|---|---|
| 管理行為 | 共有物の利用や改良のための行為は、持分の価格の過半数で決められる |
| 変更・処分行為 | 共有物の性質を変更し、または処分する行為は、共有者全員の同意が必要 |
共有物の処分には、原則として共有者全員の同意が必要です。
そのため、共有不動産の売却や賃貸にして収益を得ようとする際に、共有者全員の同意を取り付ける必要があり、単独所有のものと比べると活用しにくい特徴があります。
持分とは
「持分」とは、複数人で所有する不動産において、各共有者が持つ所有権の割合です。
持分に基づく権利を「共有持分権」と呼び、各共有者は持分に応じた権利の行使が可能です。
共有持分権には、以下の権利が生じます。
- 不動産から生じる収益(賃料収入など)を持分割合に応じて受け取る権利
- 自分の持分を他人に売却・譲渡できる権利
- 不動産の管理に関する意思決定に参加する権利
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫持分は相続や売買などによって、所有者が変更する恐れもあるでしょう。
共有持分の割合の決め方
不動産を共有する際は、共有持分を共有者で決める必要があります。
共有持分の割合は一律に決まるものではなく、遺言書の有無やシーンによって異なります。
具体的な決め方は、以下の通りです。
共有持分がどのように決まるのか理解しておくと、不動産の購入や相続の場面で話し合いがスムーズに進みやすくなります。以下で何を基準にして割合が決まるのか確認しましょう。
遺言書に記載された持分割合に従う
相続時は、遺言書に記載された持分割合が最優先されます。
遺言書には法的効力があるとされており、被相続人の最終意思を尊重する仕組みとして位置づけられています。
例えば、遺言書に「長男が3分の2、次男が3分の1」と記載されていれば、その通りに不動産登記が行われる仕組みです。
ただし、法定相続人に最低限保証されている「遺留分」が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求が可能です。
遺言書がなければ法定相続分で割合を決める
遺言書がない場合、共有持分の割合は法定相続分に基づいて決まります。
法定相続分とは、民法によって決められている相続人の取り分の割合です。例えば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつ等分します。(参照:裁判所|No.4132 相続人の範囲と法定相続分)
相続人同士の話し合いで別の割合に変更することも可能ですが、合意が得られなければ法定相続分どおりに共有持分が割り当てられます。
遺言書が存在しない場合は、自動的に民法で定められたルールが基準となるのです。
遺産分割協議で持分割合を話し合う
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって自由に持分割合を決定できます。
遺言書がある場合でも、相続人全員から合意を得られれば、話し合いで決めた割合に沿って分け合います。
遺産分割協議は相続人全員の同意が条件で、1人でも反対すれば成立しません。
そのため、協議を進める際は弁護士を交えて話し合いをし、協議書を公正証書にしておくことが望ましいです。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことです。私文書の協議書と比べて信用性が高く、裁判になったときの証拠力も強まります。(参照:日本公証人連合会|Q1. 公正証書とは、どのようなものですか?)
持分割合の登記や相続手続きがスムーズに進みやすくなるため、相続人全員の合意の基で公正証書を作成すると良いでしょう。
共有名義で不動産を購入する場合は出資割合で割合を決める
不動産を共有名義で購入する際は、出資金額を基準にして持分割合を決定します。
例えば、3,000万円の物件を夫が2,000万円、妻が1,000万円負担した場合の持分割合は、夫が3分の2、妻が3分の1です。
出資金額に応じた割合は登記簿に記載され、将来の売却や相続にも影響を及ぼします。
もし実際の出資と異なる割合で登記すると、その差額部分が「贈与」と見なされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。



購入時には資金の流れを明確にし、領収書や振込記録を残しておくことが重要です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有持分を所有している人の4つの権利
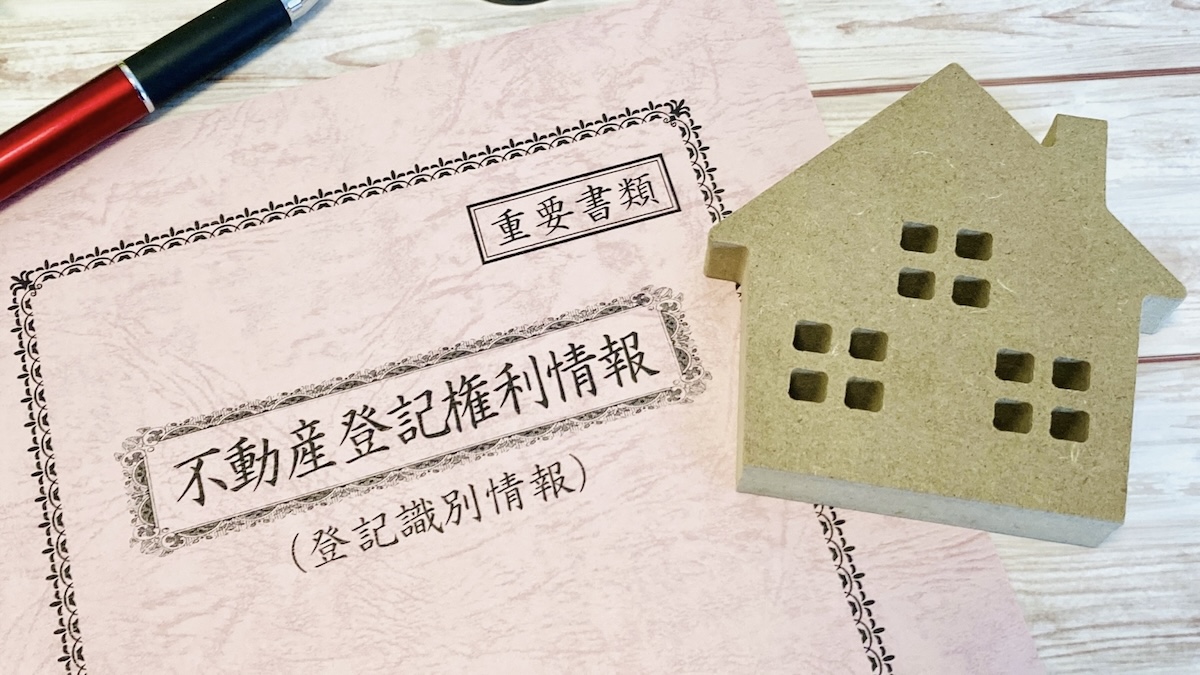
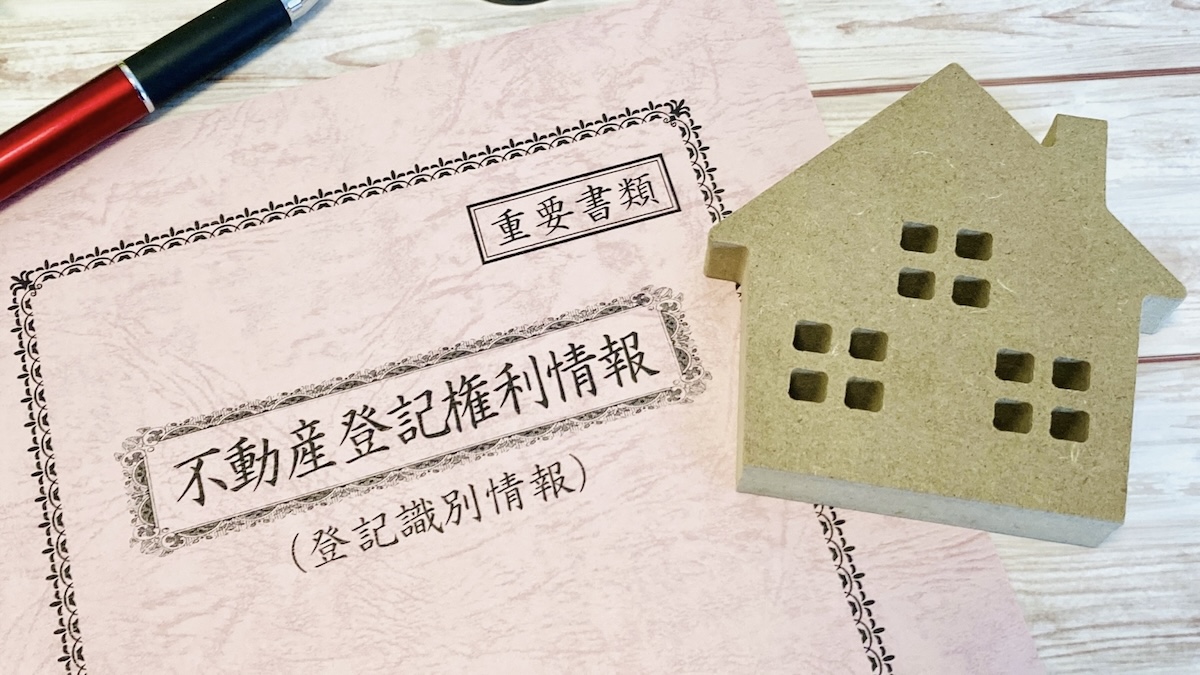
共有持分を所有している人に認められている権利は、以下の通りです。
これらの権利には、制限も課されています。具体的な内容や注意点を把握しておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
以下で共有持分に認められた権利を確認し、リスクを少しでも減らしましょう。
共有物の使用と収益
民法第249条により、共有者は共有物に全体に対して、それぞれの共有持分に応じて使用する権利を有しています。
もし、共有不動産を自己の持分を超えて使用する場合、別段の合意がない限り、他の共有者に対して超えた分の使用対価の支払いが必要です。
また、共有不動産などから得られる賃貸収入は、持分に応じて配分します。
たとえば、兄弟が1/2ずつの持分で共有する不動産の年間賃貸収入が1,000万円の場合、それぞれが受け取れる金額は500万円です。
さらに、他の共有者の権利を尊重するために、共有者は特に注意を払って共有物を使用する義務を負っています。
関連記事:共有不動産の使用貸借とは?認められる要件やリスク・トラブル対処法を弁護士が解説
共有物の管理と保存
民法第252条では、共有物の管理と保存について定められています。
共有物の管理行為とは、共有物を有効に利用、改良するための行為を指し、建物の改装や宅地の整地、第三者への賃貸などが該当します。
管理行為は、共有者の持分の過半数で決定が可能で、共有者の所在が不明な場合でも裁判所の許可を得れば、その他の共有者の持分価格の過半数で管理行為が可能です。
一方、保存とは共有物の現状を維持する行為です。
建物の修繕や不法占有者への明渡請求などが該当し、他の共有者の利益にもつながるため、各共有者が単独での実施が認められています。
持分の売却
民法第206条では、所有者の基本的な権利として不動産の共有持分を自由に処分ができると規定しています。
他の共有者の同意がなくても、自己の持分を第三者への売却が可能です。
しかし、共有持分は権利行使に制限があるなどの理由で、一般消費者の買い手が付きにくいのが現状です。
そのため、共有持分の買い手の多くは専門の買取会社で、売却価格は時価の2分の1から3分の1程度にとどまります。
また、買取会社は共有持分を購入後、その持分を他の共有者に対し高値で購入するよう持ちかけたり、逆に安い価格で売却を迫ったりするなど、トラブルの原因になるリスクがあります。
持分の売却は所有者の権利ですが、実際に売却する際は他の共有者と協議するなど慎重に対応してください。
共有持分を売却する時の問題点やトラブルを避ける方法についてはこちらの記事もご覧ください。
関連記事:共有持分は売却できる?同意なしで売れる理由やトラブル回避のポイントを弁護士が解説
共有物分割請求
民法第258条1項では、共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求ができると定めています。
共有者は共有状態を解消するための話し合いをした上で、共有物分割請求の調停の申立てや訴訟を提起する権利があります。
共有物分割請求訴訟の流れは、以下の通りです。
- 当事者間の話し合い
- 共有物分割請求訴訟を提起する
共有物分割訴訟では、裁判所が以下の方法から分割手段を判断します。
| 分割の方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産を物理的に分割 |
| 代償分割 | 一部の共有者が他の共有者に金銭を支払って取得 |
| 換価分割 | 競売により売却し、代金を分配 |



民法第258条3項では、現物分割または代償分割を優先的に検討し、困難な場合には換価分割を選択するように定めています。
共有物分割請求訴訟については下記の記事で詳しく説明しているのでご覧ください。
関連記事:共有物分割請求訴訟の手続きの流れ!メリット・デメリットなどをわかりやすく解説
共有持分を所有する3つのメリット


不動産の共有持分を所有するメリットは、以下の通りです。
不動産の購入や相続で共有名義にするかどうかの判断基準にしてみてください。
不動産購入時のローン審査に通りやすくなる
不動産を共有名義で購入する場合、ローンの審査が通りやすくなります。
単独では借入可能額が少なく物件が購入できない場合でも、夫婦や親子で共有名義にすれば、それぞれの収入を合算してローン審査を受けられます。借入可能額が増えれば、購入できる物件の選択肢が広がるでしょう。
ただし、共有名義のローンでは連帯債務や連帯保証が用いられ、どちらかが返済不能になるともう一方に責任が及ぶリスクがあります。
公平な遺産分割ができる
公平な遺産相続が期待できる点も、共有持分を所有するメリットの一つです。
不動産は現金のように簡単に分配できないため、相続時に公平な分割をするのが難しい財産です。単独名義にしてしまうと、特定の相続人の取り分が多くなったり、他の相続人が不公平感を抱いたりするケースも少なくありません。
共有持分にすれば法定相続分に従って割合を割り振れるため、相続人それぞれに平等な権利を与えることが可能です。
また、相続財産が不動産しかなく現金化が難しい場合、法定相続分に応じて共有持分を割り振れば、各相続人に平等な取り分を与えられます。
売却時に居住用物件の特別控除が受けられる
共有名義の居住用物件(マイホーム)を売却した場合、一定の条件に該当すれば、居住用財産の特別控除3,000万円が適用されます。(参照:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例)
マイホームを共有している場合、持分ごとに控除が適用されるため、夫婦で共有していれば合わせて6,000万円の控除を受けられる可能性があります。



条件を満たせば、譲渡所得税を大きく節税できる可能性があり、税負担の軽減が可能です。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有持分を所有する3つのリスク


不動産を共有名義にして共有持分を所有することは、一見すると手早く平等に分けられる方法に思えます。
しかし、実際には以下のようなリスクを伴う点に注意が必要です。
こうしたリスクを理解しないまま共有名義にしてしまうと、共有者間での関係悪化や解決困難な対立を招くおそれがあります。
不利益を被らないよう、以下で具体的なリスクを確認しましょう。
不動産を個人の意思だけで売却・活用できない
共有不動産を有効に活用する場合でも、共有不動産の全体の売却をする際は、共有者全員の同意が必要です。
共有者の中に以下のような状況の人が一人でもいると、売却ができなくなってしまいます。
- 売却に反対する共有者がいる
- 連絡が取れない共有者がいる
- 意思能力の問題で同意の意思表示ができない共有者がいる
共有不動産の売却は、単独所有の不動産と比べて手続きが面倒で、高いハードルが存在しています。
共有不動産の売却について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
関連記事:共有不動産はどうしたら売却できるの?同意が必要なケースと持分の処分方法を解説
相続で共有持分が細分化し権利関係が複雑になる
共有持分が相続によって細分化されると、権利関係が複雑化し、共有者間での同意が取りにくくなってしまいます。
たとえば、共有者が亡くなって複数の相続人で共有持分を分け合うと、権利者の数が増え、不動産の管理や処分の意思決定が困難になるケースがあります。
さらに、時間が経過するにつにつれて子世代、孫世代へと相続が重なり、権利関係は一層複雑になってしまうのです。
このような状況は、不動産の売却や建替えなどで全員の同意を得るのが難しく、資産の有効活用を妨げます。
第三者と共有関係になることでトラブルに発展する
見ず知らずの第三者と共有関係になり、意思の不一致から対立が生じやすくなる点に注意しましょう。
例えば、他の共有者が自分の持分を第三者に売却すると、突然全く面識のない人物が新たな共有者として加わります。
不動産の活用方法や売却時期、管理費の負担割合などで意見が食い違えば、話し合いが長引いて物件の活用が進まない事態に陥ることもあります。
また、相手が投資目的の業者や利益重視の人物であれば、条件交渉が難航し、関係が悪化する可能性も高まります。



とくに共有持分買取業者は、将来的な転売や高収益化を目的としている場合が多く、売却や活用を強く迫られるケースがあります。
共有持分が絡むトラブル事例3選


共有不動産の共有持分を所有していると、意見の相違などによりトラブルが発生しやすい傾向にあります。
実際に共有持分が原因で起きるトラブルには、以下のような事例があります。
事前に確認することで、本当に共有名義にすべきなのか判断しやすくなります。以下で具体的な事例を確認しましょう。
相続で共有者が増え売却の合意ができない
よくある事例の一つが、相続により、共有者が増えすぎたことによるトラブルです。
共有者と連絡を取っていない間に共有者が亡くなり、その子どもや配偶者に不動産が相続されているため、売却の同意を取り付けるために苦労した
この事例は、不動産の共有関係が相続によって複雑化する典型的なケースを示しています。
共有不動産の売却にはすべての共有者の同意が必要であり、共有者の死亡によって、相続が発生すると共有関係が複雑化して合意形成が難しくなります。
共有持分の売却によってトラブルに発展する
共有持分を単独で売却して発生したトラブルの事例です。
購入した見知らぬ第三者が共有物件に出入りしたり、共有持分を購入した買取会社から他の共有者にしつこい営業をかけられたりするなどのトラブルが発生した
この事例は共有不動産を単独で売却したときに、他の共有者に発生する可能性のあるトラブルです。
共有持分の購入者は自分が住む目的ではなく、高値で売却するなどの投資目的であるケースが多いです。
特に共有持分専門の買取会社の一部において、購入した持分をより高く売却するために、他の共有者に頻繁に営業して、心理的ストレスを与えるなどの深刻な問題も起きています。
共有持分買取業者への売却トラブル事例については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:共有持分買取業者への売却トラブル回避法!持分現金化は弁護士に相談すべき理由
共有不動産に私道が含まれ管理方法で意見が割れる
共有私道の管理方法で共有者の意見がまとまらなかった事例です。
スムーズに通行するために共有私道を舗装したい人と、現状のままでいいと考える人の間で意見が割れてしまい、工事ができなかった
私道の経年劣化に対する補修や舗装工事といった管理行為で、共有者間で意見の相違が生じてトラブルになる事例がたびたび起こっています。
私道の舗装などの管理行為には、共有持分の過半数の同意が必要です。



工事の必要性や費用負担の問題などから反対意見が出ることがあり、重要な管理行為ができない状況が発生しています。
私道共有持分で起こりやすいトラブルや回避方法を知りたい方は下記の記事をご覧ください。
関連記事:私道共有で起こりやすいトラブルとは?共同所有型(持分共有型)・相互持合型(分筆型)のケース別に解説
共有持分によるトラブルを避ける3つの方法


不動産の共有持分に起因するトラブルを未然に防ぐためには、適切な対応が必要です。
共有持分のトラブルを避けるには、以下の方法を検討しましょう。
共有物分割で共有状態を解消する
不動産の共有状態は、共有物分割によって解消する方法があります。
共有物分割には、主に2つの方法が選択肢として挙げられます。
1つ目は代償分割で、共有者の1人が他の共有者に金銭を支払い、単独で所有権を取得する方法です。
たとえば、相続で兄弟2人が土地を共有している場合、弟が兄に相応の金額を支払って土地を一括取得するといったケースです。
2つ目は換価分割で、共有不動産を売却し、その売却代金を各共有者の持分割合に応じて分配する方法です
換価分割には、不動産の市場価値を適切に反映できる利点があります。
共有不動産が土地のみのなら分筆して単独名義にする
共有不動産が土地のみなら、分筆による共有関係の解消もおすすめの方法です。
分筆とは、一筆の土地を法的に複数の区画に分割し、独立した不動産として登記する手続きです。
分筆によって土地を分割し、それぞれの区画を各共有者の単独所有にすれば、所有権をめぐる複雑な権利関係を整理できます。
各所有者は自己の土地について、他の元共有者の同意を得ることなく、売却や賃貸、担保設定などの判断を自由に行えます。
分筆は不動産の効率的な活用を促進する重要な選択肢です。
共有持分が原因でトラブルになりそうなら弁護士に相談する
共有持分の問題が複雑化する前に、弁護士への相談が解決策として有効です。
弁護士は豊富な法律知識を活かし、依頼者に寄り添って共有不動産の活用や権利関係の整理を支援します。
共有持分のトラブルを解消するために弁護士が取れる施策には、以下のものが挙げられます。
- 他の共有者との交渉を代理で行い、建設的な話し合いを進められる
- 不動産売却に向けた同意取得の手続き
- 共有物分割請求などの法的手段の検討
弁護士は、各共有者の利害関係を調整しながら依頼者にとって最良の解決策を提案します。
特に、共有者間で意見の対立がある場合や、権利関係が複雑化している状況では、弁護士によるサポートが問題解決の鍵となるでしょう。



共有持分に関する助言を不動産問題に強い弁護士から受けることで、トラブルの拡大を防ぎ、利益の最大化が図れます。
共有持分に関するよくある質問
共有持分と区分所有の違いは何ですか?
共有持分と区分所有の大きな違いは、物理的に区切られているかどうかです。
共有持分は、不動産全体を複数人で共同所有し、持分割合だけが決まっていて物理的な区分はありません。
そのため、利用や処分には他の共有者との合意が必要になる場合が多く、意思の不一致でトラブルになる可能性があります。
一方、区分所有はマンションのように建物を構造上区切り、専有部分を単独で所有できるのが特徴です。
自分の専有部分は自由に売却や賃貸ができ、廊下やエレベーターなどの共有部分は管理規約や組合の決議で運営されます。
夫婦で家を購入する場合の共有持分の割合はどのように決まりますか?
夫婦で家を購入する場合の共有持分の割合は、基本的に負担した資金の割合によって決まります。
例えば購入費用のうち夫が1,200万円、妻が800万円を負担した場合、夫の共有持分は6割(10分の6)、妻は4割(10分の4)として登記します。
住宅ローンを利用する場合でも、返済予定額や頭金の負担割合を基準に設定するのが一般的です。
この割合は将来の売却益や相続時の取り分に直結するため、契約前にしっかり話し合って決めておきましょう。
共有持分の移転登記とは何ですか?
共有持分の移転登記とは、不動産の共有者の持分を他の人に移転したときに行う名義変更の手続きです。
売買、贈与、相続、離婚による財産分与などで持分の所有者が変わった場合に必要です。
例えば、兄弟で2分の1ずつ所有している土地のうち、兄の持分を弟が買い取った場合、その持分を弟名義にするために移転登記を行います。
この手続きによって、法務局の登記簿上で正式に所有者が変更され、権利関係が明確になります。
登記を怠ると第三者への対抗力がなくなり、トラブルや権利侵害のリスクが高まるため、持分が移転したら速やかに申請することが大切です。
関連記事:共有不動産を現金化する5つの方法とは?
関連記事:共有名義の不動産の名義の変更について解説
まとめ|共有持分のトラブルが長期化する場合は弁護士に相談しよう


共有持分がトラブルになりやすい実態と、リスクを避ける方法を解説しました。
- 共有不動産には、全体の売却に共有者全員の同意を取り付ける必要があり、有効活用しにくいなどのデメリットがある
- 共有者には共有持分に応じて不動産を使用する権利がある
- 共有持分を単独で売却すると、見知らぬ第三者が出入りするなど他の共有者に心理的ストレスを与える場合がある
- 共有不動産のトラブルを避けるためには、共有物分割による共有の解消や、土地のみなら分筆して単独名義にする方法がある
不動産の共有状態にはリスクがあり、放置し続けると相続などで共有者が増えてしまい解決が困難な状態に陥ります。
共有持分の所有で発生するトラブルを避けるためには、弁護士に相談して早急に共有状態の解消を図ってください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









