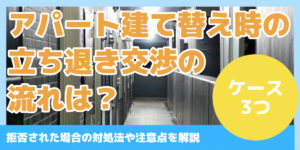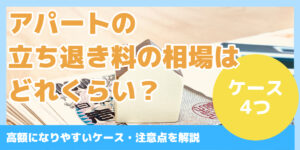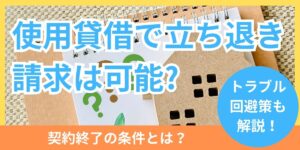【無料相談受付中】24時間365日対応
不法占拠者に対する明け渡し請求とは?手続きの流れや注意点を徹底解説

「家賃を払わないまま元入居者が居座っていて困る…」
「不法占拠の明け渡しの手続きはどうすればいいのだろう…」
上記のような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。不法占拠トラブルは、大家さんにとって深刻な問題の一つです。
この記事では、不法占拠の基本情報から、明け渡しを請求するための法的手続きの流れを解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫やってはいけないNG対応や注意点も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
不法占拠者に対する「明け渡し請求」とは
不法占拠者に対する「明け渡し請求」とは、不動産の所有者などが、不法占拠者に対して物件の占有を解いて引き渡すよう法的に要求することです。
賃貸契約が終了したにもかかわらず退去しない元入居者や、無断で土地や建物を使用している第三者がいる場合に行われます。
この請求は、所有権という正当な権利に基づいて行われます。単に「出ていけ」と要求するだけでなく、法的な手続きを踏んで実行されるのが特徴です。
通常は、まず内容証明郵便などで退去を求め、それでも応じない場合には裁判所に「明け渡し請求訴訟」を提起します。裁判所が所有者側の主張を認めた場合、判決によって不法占拠者に退去命令が下されます。
それでもなお立ち退かない場合には、「強制執行」の手続きを通じて、裁判所の執行官が実際に占有を排除し、物件を明け渡すことが可能です。
関連記事:明け渡し訴訟とは?手続きの流れや費用・期間・必要な準備を弁護士が徹底解説
関連記事:土地トラブルは訴訟で解決すべき?費用や期間・手続きの流れを弁護士が徹底解説
その占有は「不法占拠」?明け渡し請求の対象となるケース
どのような場合に「不法占拠」と判断され、明け渡し請求の対象となるのでしょうか。
ここでは、典型的な3つのケースを紹介します。
自身の状況がこれらに当てはまるか確認し、適切な初動対応を検討しましょう。
賃貸借契約の期間満了後も居座っている場合
賃貸借契約には通常、契約期間が定められています。
この期間が満了し、契約の更新も行われていないにもかかわらず、賃借人が退去せずに居座り続ける場合は、不法占拠に該当すると考えられます。
契約が終了した時点で、賃借人がその物件に住み続ける法的な根拠はありません。したがって、所有者(大家)は物件の正当な権利者として、明け渡しを請求する権利を持つことになります。
場合によっては、内容証明郵便などで正式に退去を求め、それでも応じない場合には、裁判を通じた明け渡し訴訟を提起することも可能です。
賃料不払いによる契約解除後も占有を続けている場合
賃借人が家賃を滞納し、かつ、信頼関係が破壊されたといえる場合は、賃貸借契約を解除できます。
賃貸借契約において、家賃の支払いは契約の根幹をなす義務であり(民法第601条)、賃料不払いがある場合には、債務不履行があるといえます。
そのうえで、当事者の一方が債務を履行しない場合には、相手方は履行の催告をし、その期間内に履行がない場合には、契約の解除ができるとされています(民法第541条)。
もっとも、賃貸借契約は当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるため、賃料の不払いがあっただけで、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊するに至らない場合には、賃貸借契約の解除は認められないとされています。
しかし、長期間の滞納が続くと、貸主と賃借人との間の信頼関係は回復不可能な状態と判断されるため、賃貸借契約の解除が認められる可能性が高まります。
上記の要件を満たす場合に、貸主から内容証明郵便などによって契約解除の通知をしたにもかかわらず、賃借人が物件を明け渡さない場合は「不法占拠」にあたると考えられます。
このような場合、貸主は裁判所に対して「明け渡し請求訴訟」を起こしたうえで、「建物明渡しの強制執行」を申し立てることになります。
賃借人が無断転貸した第三者によって占有されている場合
賃借人が、貸主の許可なく物件を第三者に又貸し(転貸)する行為は、契約違反となります。
無断転貸が原因で契約が解除された場合、実際に物件を占有している転借人(又貸しされた人)の占有も不法占拠にあたると考えられます。



自身のケースが不法占拠に該当するかわからない場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
以下の記事では、強制退去でアパートを明け渡してもらう条件や手続きについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:強制退去でアパートを明け渡してもらう条件は?手続きの流れや費用、注意点も解説
不法占拠者に対する明け渡し請求|交渉から強制執行までの流れ
不法占拠者に対する明け渡し請求は、正しい手順を踏むことが重要です。
感情的な行動は避け、法的なステップに沿って冷静に進めましょう。
ここでは、交渉から強制執行に至るまでの具体的な流れを4つのステップで解説します。
以下、それぞれ具体的に説明します。
関連記事:立ち退き交渉・裁判の流れとは?費用や期間、交渉するポイントも解説
ステップ1:内容証明郵便による明け渡し請求をする
最初のステップとして、不法占拠者に対し内容証明郵便を送付します。
これには、明け渡しを請求する意思を明確に伝え、交渉の記録を残す目的があります。主な目的や記載内容、得られる効果は以下のとおりです。
| 目的 | 請求の意思を公式に通知し、心理的なプレッシャーを与える |
|---|---|
| 記載内容 | 請求者・被請求者・物件情報・請求の根拠・明け渡し期限など |
| 効果 | 後の裁判で「請求を行った」という証拠になる |
この段階で相手が任意に退去すれば、時間や費用をかけずに解決できる可能性があります。
内容証明郵便は、個人でも郵便局で作成・送付が可能ですが、文面の書き方を誤ると法的効果が弱まる恐れがあります。
たとえば、「明け渡し期限を曖昧に書く」「違法な文言を入れる」と、裁判で証拠として認められにくくなる可能性があります。
そのため、初めて行う場合は、弁護士または行政書士に文面作成を依頼するのが安心です。費用は1万円〜3万円ほどが目安になります。



適切に手続きを進めるためにも、この段階で弁護士に相談するようにしましょう。
相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
ステップ2:占有移転禁止の仮処分を申し立て、占有者の固定を図る
訴訟を起こす前に、状況に応じて「占有移転禁止の仮処分」を裁判所に申し立てることも考えましょう(民法保全法第23条)。
これは、裁判の途中で占有者が別の人に変わってしまうのを防ぐための手続きです。
もし裁判中に占有者が変わると、新しい占有者に対して再び裁判を起こさなければなりません。
この仮処分を行っておけば、たとえ占有者が変わっても判決の効力は新しい占有者にも及びます。
これにより、訴訟が無駄になるリスクを回避することが可能です。
ステップ3:建物明け渡し請求訴訟を提起し、勝訴判決を得る
交渉が決裂した場合、地方裁判所に「建物明け渡し請求訴訟」を提起します。
裁判では、所有権の存在や相手の占有が不法であることを証拠に基づいて主張・立証します。主な提出証拠は、以下のとおりです。
- 不動産登記簿謄本
- 賃貸借契約書
- 賃料滞納の事実がわかる資料
- 内容証明郵便
裁判でこちらの主張が認められると、明け渡しを命じる勝訴判決が下されます。
この判決が、次のステップである強制執行の根拠(債務名義)となるため、重要な手続きといえるでしょう。
ステップ4:強制執行を申し立て、不動産の明け渡しを実現する
勝訴判決が出てもなお占有者が退去しない場合、最終手段として強制執行を申し立てましょう。
裁判所の執行官が現地に赴き、占有者を強制的に退去させ、物件内の動産(荷物)を搬出します(民法執行法第168条)。
強制執行の流れは、以下のとおりです。
| 1.明け渡しの催告 | 執行官が占有者に対し、期限を定めて任意退去を促す |
|---|---|
| 2.断行 | 期限内に退去しない場合、執行官が鍵を開けて入室し、荷物を運び出す |
| 3.明け渡し完了 | 物件が所有者の手に戻る |



この手続きにより、法的な強制力をもって物件の明け渡しが実現します。
強制執行の申立ては、物件所在地を管轄する地方裁判所で行います。
その際、申立書に加えて以下の書類を提出し、予納金(6〜10万円程度)を納付しなければなりません。また、断行となり、物件内に荷物等が多くある場合、その搬出を行う業者を手配する費用等が数十万から数百万かかることがあります。
- 判決書(債務名義)
- 送達証明書
- 登記簿謄本 など
執行官が現地に赴き「明け渡し催告書」を交付してから、実際に強制的に退去させるまでには、通常1〜2か月かかります。
強制退去が可能な条件については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
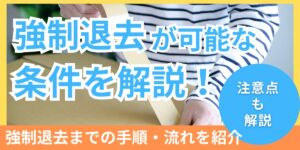
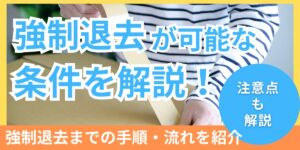
明け渡し請求をスムーズに進めるための事前準備チェックリスト
明け渡し請求をスムーズに進めるためには、感情的に動くのではなく、証拠と手続きを冷静に整えることが重要です。
以下のチェックリストをもとに、手続き前に抜け漏れがないか確認しましょう。
- 占拠の経緯と現状の整理をした
- 占拠の証拠を確保した
- 所有権・賃貸借関係を確認した
- 内容証明郵便による警告・通知の準備をした
まずは、「なぜ占拠状態になったのか」を客観的に説明できるようにしておくことが大切です。その後、「不法に使用されている」ことを裏付ける客観的証拠を集めましょう。
建物・土地の現状を写真・動画で記録したり、郵便物・光熱費の契約状況などから占拠の実態を確認したりすることが大切です。
また、明け渡し請求を行うには、「正当な権利者」であることの立証が必要です。手続きを進める前に、権利関係も明確にしておきましょう。



何から始めるべきかわからない場合は、一度弁護士に相談してみることが大切です。
不法占拠の明け渡しにかかる期間の目安
不法占拠の明け渡し請求にかかる期間は、事案の複雑さや相手の対応によって大きく変動します。
あくまで目安ですが、各段階で必要となる期間は以下の通りです。
| 手続きの段階 | かかる期間の目安 |
|---|---|
| 内容証明郵便の送付・交渉 | 1か月程度 |
| 占有移転禁止の仮処分 | 2週間〜1か月程度 |
| 建物明け渡し請求訴訟 | 6か月〜1年程度 |
| 強制執行 | 1か月〜2か月程度 |
訴訟から強制執行まで進んだ場合、全体で半年から1年以上かかることも珍しくありません。
交渉で早期に解決できれば期間は短縮されます。しかし、手続きが長引く可能性を念頭に置き、早めに専門家へ相談することが重要です。
具体的な期間に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。


不法占拠の明け渡し請求にかかる費用相場と内訳
明け渡し請求には、弁護士費用や裁判手続きの実費など、さまざまな費用が発生します。
あらかじめ費用の全体像を把握しておくことで、安心して手続きを進めることが可能です。
ここでは、主な費用の内訳と相場を解説します。
弁護士に依頼する場合にかかる費用
弁護士に依頼する場合の費用は、主に相談料・着手金・成功報酬で構成されます。
法律事務所によって料金体系は異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 費用の種類 | 概要 | 費用相場(物件の評価額による) |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際に発生する費用 | 30分あたり5,000円〜1万円(無料相談あり) |
| 着手金 | 依頼時に支払う費用。結果にかかわらず返金されない | 20万円〜50万円程度 |
| 成功報酬 | 明け渡しが実現した場合に支払う費用 | 60〜100万円程度 |
訴訟・強制執行とステップが進むごとに、費用が加算されるのが一般的です。ただ、法律事務所によって異なるため、依頼する前に見積もりを確認しましょう。
弁護士に依頼するメリットや費用相場に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
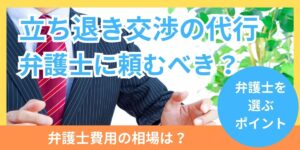
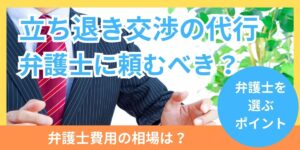
訴訟や強制執行をする場合にかかる費用
裁判所に手続きを申し立てる際には、実費が必要です。実費は、弁護士費用とは別に用意しなければなりません。
主な実費は以下のとおりです。
| 訴訟費用 | ・収入印紙代:訴額(固定資産税評価額の2分の1)に応じて変動 ・郵便切手代:5,000円〜1万円程度 |
|---|---|
| 仮処分費用 | ・収入印紙代:2,000円 ・郵便切手代:数千円程度 ・担保金:数十万円程度 |
| 強制執行費用 | ・予納金:6〜10万円程度 ・鍵の開錠費用や荷物の搬出費用 ・保管費用:数十万円〜100万円以上かかる場合も |



強制執行の際の荷物搬出費用は高額になる可能性があるため、注意が必要です。
不法占拠に対する明け渡し請求でやってはいけないNG対応
不法占拠者に対して、所有者だからといって何をしてもよいわけではありません。誤った対応は、逆にこちらが訴えられるリスクを生みます。
ここでは、不法占拠の明け渡し請求でやってはいけないNG対応を4つ紹介します。
以下、それぞれ詳細に解説します。
鍵を替える・荷物を撤去するなどの自力救済
占有者がいる状態で無断で鍵を交換したり、室内の荷物を勝手に運び出したりする行為は「自力救済」として法律で禁止されています。
自力救済をすることのリスクは、以下のとおりです。
いかに正当な権利があっても、法的手続きを経ずに実力行使することは許されません。必ず裁判所の手続きを通じて解決しましょう。
以下の記事では、強制退去後の荷物の対処法について詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。


暴言や威圧的な態度で交渉をする
相手に対して暴言を吐いたり、脅迫的な言動で退去を迫ったりすることも厳禁です。
「出ていかないとどうなるかわかっているのか」といった発言は、脅迫罪(刑法第222条)や強要罪(刑法第223条)にあたる可能性があります。
交渉の記録は、後の裁判で不利な証拠として使われることも珍しくありません。感情的にならず、あくまで冷静かつ法的な根拠に基づいて交渉を進めることが重要です。
SNSや掲示などで相手を晒す
不法占拠者の氏名や写真をSNSで公開したり、物件の入り口に貼り紙をして非難したりする行為は、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
プライバシーの侵害として、損害賠償を請求されるリスクも非常に高いです。
たとえ相手が不法な行為をしても、私的な制裁(私刑)は認められません。



社会的な信用を失うことにもつながるため、避けましょう。
自身で実施しようとしている対処法が適切かどうか悩んでいる場合は、一度弁護士に相談することが大切です。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
不法占拠に対する明け渡し請求をする際の注意点
不法占拠の明け渡し請求を成功させるためには、いくつか重要な注意点があります。
主な注意点は、以下のとおりです。
これらのポイントを押さえることで、リスクを最小限に抑え、より確実な解決を目指せるでしょう。以下、それぞれ具体的に解説します。
裁判・交渉時の裏付けになるため、交渉の記録と証拠を残す
不法占拠者とのやり取りは、すべて記録として残しておきましょう。
残すべき記録・証拠は、主に以下のとおりです。
- 交渉の日時、内容、相手の発言をまとめたメモ
- 通話の録音データ
- 送受信したメールやメッセージ
- 内容証明郵便や契約書類
これらの記録は、交渉を有利に進める材料になるだけでなく、訴訟になった際に自分の主張を裏付ける証拠となります。
客観的な証拠が多ければ多いほど、裁判官の心証もよくなるでしょう。
不法占拠のトラブルはすぐに弁護士に相談する
不法占拠問題は、法律の知識と実務経験がなければ適切に対応することが困難です。不法占拠のトラブルが発生したら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
- 法的に最適な解決策を提案してもらえる
- 精神的な負担や手間を大幅に軽減できる
- 相手との交渉窓口になってもらえる
- 訴訟や強制執行などの複雑な手続きを任せられる
適切な知識や経験がないまま自力で対応すると、問題をこじらせて時間と費用を余計に浪費する結果になりかねません。



迅速かつ円満な解決を目指すなら、トラブルが発生した初期段階で弁護士に相談することが大切です。
不法占拠者に対する明け渡し請求に関するよくある質問
ここでは、不法占拠者に対する明け渡し請求に関して、多くの方が抱く疑問に回答します。いざというときに不安にならないためにも、事前に確認しておきましょう。
賃料滞納が原因の場合、何か月で不法占拠になる?
明確に「何か月」という決まりはありません。
しかし、実務上の目安としては3か月以上家賃の滞納が続くと、貸主と借主の信頼関係が破壊されたと判断されやすくなり、契約解除が認められるケースが多くなります。
契約が解除された後も借主が退去しない場合は、その時点で不法占拠となり、立ち退きを求める訴訟(明け渡し訴訟)や強制執行が可能です。
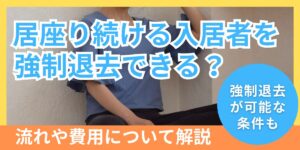
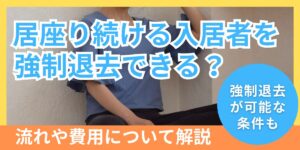
話し合いで解決する場合の注意点は?
話し合いで解決を目指すこと自体は有効ですが、以下の点に注意が必要です。
- 合意内容は必ず書面(合意書や示談書)にする
- 退去の具体的な期限を明記する
- 未払い賃料の支払い方法などを明確にする
- 感情的にならず、冷静に交渉する
口約束だけでは、後でトラブルになる可能性があります。弁護士に依頼し、適切な合意書を準備しましょう。
相手の氏名や素性が不明な場合でも明け渡し請求はできる?
氏名不詳の相手に対しては、事前に占有移転禁止の仮処分を申し立てた上で、明け渡し請求訴訟を起こすことは可能です。
仮処分の申立手続きでは、占有が移転される危険性や、占有者が不明である事情等を詳細に説明する必要があります。
知識がない個人で実施すると、その説明を作成する時間や労力を割かなければならない恐れがあります。



専門家である弁護士の知識と経験に頼り、適切に対処するようにしましょう。
まとめ|不法占拠トラブルは専門家へ相談して迅速な法的対応を心がけよう
不法占拠は、所有者の権利を著しく侵害する深刻な問題です。
しかし、感情的な実力行使は絶対に許されず、法に則った正しい手順を踏む必要があります。自力での対応はリスクも高く、問題を長期化させる原因にもなりかねません。
不法占拠トラブルに直面したら、できるだけ早い段階で不動産問題に強い弁護士に相談することが大切です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応