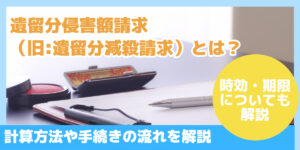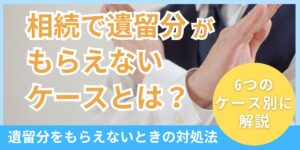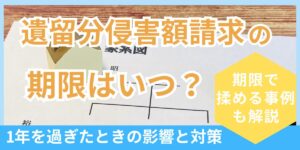【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分は代襲相続でももらえる?孫と甥姪の違いや計算方法を解説【弁護士監修】
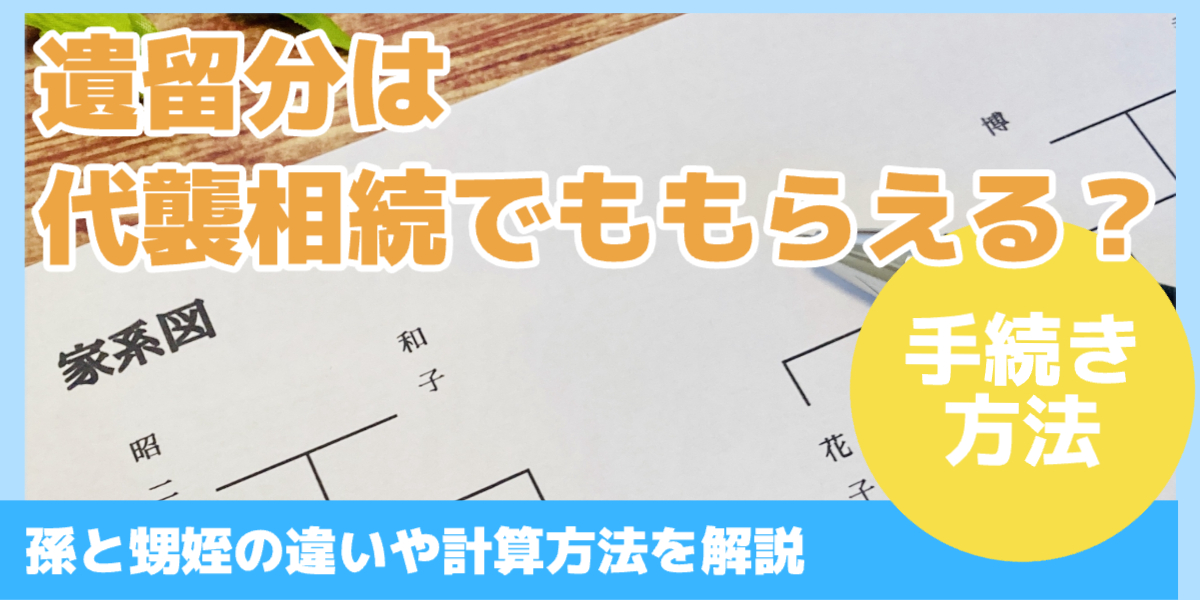
「祖父母が亡くなったけれど、遺言書を見たら自分の相続分が全くなかった…」
「代襲相続人である自分に、遺留分はあるのだろうか?」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
「代襲相続」とは、本来相続人となるはずだった人が被相続人より先に死亡しているなど、特定の理由で相続権を失っている場合に、その人の子ども(被相続人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続できる制度です。
被相続人からみて、代襲相続人の立場が「孫」であれば遺留分が認められますが、「甥・姪」の立場では認められません。
本記事では、遺留分が代襲相続でも認められるケース・認められないケースや、代襲相続における遺留分の請求方法を解説します。
代襲相続で遺留分を請求できるかどうか不安になっている方は、正当な権利を守るためにも、ぜひ最後までお読みください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
「代襲相続」「遺留分」とは
代襲相続と遺留分は、どちらも民法で定められた重要な相続のルールです。
両者を正しく理解するためには、まずそれぞれの制度がどのようなものかを知る必要があります。ここでは、二つの制度の基本を解説します。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(被相続人の子や兄弟姉妹)が、相続が開始する前に亡くなっていたり、特定の理由で相続権を失っていたりする場合に、その人の子ども(被相続人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続する制度のことです。
代襲相続が発生するのは、本来の相続人が以下のいずれかの事由に該当した場合です。
| 事由 | 詳細 |
|---|---|
| 死亡 | 本来の相続人が被相続人より先に死亡した場合 |
| 相続欠格 | 民法第891条の所定の事由により相続権を失った場合 ※本人の意思とは関係なく、自動的に適用される |
| 相続廃除 | 本来の相続人が被相続人への虐待などを理由に、家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪された場合。 |
なお、民法第891条における相続欠格事由は下記のとおりです。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者引用:民法|第891条
重要な点として、本来の相続人が「相続放棄」をした場合には、代襲相続は発生しません。
相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、代襲相続人に引き継がれるべき相続権自体が存在しないからです。
代襲相続は、あくまで相続人となる権利があったものの、それが本人の意思によらない形で失われた場合に、次の世代に権利を引き継がせるための制度です。
代襲相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:代襲相続できない場合は?代襲相続はどこまでで直系尊属についても詳しく解説
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、法律上最低限確保される遺産の取り分のことです。
故人の意思(遺言)は最大限尊重されるべきですが、それによって残された家族の生活が脅かされることがないよう、遺留分として法律で守られています。
裁判所でも、遺留分は「被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないもの」とされています。(参照:裁判所|遺留分侵害額の請求調停)
この制度で最も重要なポイントは、遺留分は兄弟姉妹には認められないという点です。
兄弟姉妹は独立して生計を立てていることが多く、保護の必要性が低いと判断されているため、遺留分の権利者から除外されています。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫よって、子どもの子どもである「孫」が代襲相続人の場合は、遺留分が認められますが、兄弟姉妹の子どもである「甥・姪」が代襲相続人の場合は遺留分が認められません。
遺留分については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを解説
関連記事:【遺産相続が兄弟のみ】の場合相続はどうなる?代襲相続や遺留分などを解説
【結論】代襲相続で遺留分が認められるかは立場で決まる
代襲相続人として遺留分を主張できるかどうかは、自分が被相続人にとってどのような立場にあるか、つまり「孫」なのか「甥・姪」なのかによって明確に分かれます。
本章を参考に、自分の代襲相続のケースで遺留分が認められるかどうかを確認してみましょう。
孫・ひ孫には遺留分が認められる
結論として、孫やひ孫の立場であれば、遺留分は認められます。
これは、代襲相続人が、亡くなった親(被代襲者)が本来持っていた権利を包括的に承継するためです。
被相続人の子(代襲相続人から見て親)には、法律上、遺留分が認められています。そのため、その子が亡くなったことで相続権を代襲した孫は、相続分だけでなく遺留分を受け取る権利もそのまま引き継ぐのです。
さらに、子だけでなく孫も被相続人より先に亡くなっていた場合には、孫の子である「ひ孫」が代わって相続する「再代襲相続」が起こります。この場合も同様に、ひ孫は遺留分を主張することが可能です。
直系の血族である子孫の系統では、この権利が代々引き継がれていきます。
甥・姪には遺留分が認められない
一方で、甥・姪の立場では、代襲相続人であっても遺留分は認められません。
この理由は非常に明確で、被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人から見て親)には、そもそも法律で遺留分が保障されていないためです。
代襲相続は、あくまで「存在する権利」を引き継ぐ制度であり、もともと存在しない権利を引き継ぐことはできません。
「代襲相続人として遺産はもらえるのに、遺留分はない」という点は多くの方が誤解しやすいポイントであるため、理解しておきましょう。
代襲相続で遺留分が認められる人・認められない人
代襲相続で遺留分が認められるケースと認められないケースを、以下の表にまとめました。
| 自分の立場 | 被代襲者(本来の相続人) | 代襲相続 | 遺留分 |
|---|---|---|---|
| 孫 | 親 | できる | ある |
| 甥・姪 | 叔父・叔母 | できる | ない |
「代襲相続できること」と「遺留分があること」はイコールではありません。
例えば、「全財産を特定の人物に遺贈する」という内容の遺言があった場合、代襲相続人が孫であれば遺留分を主張して最低限の財産を受け取れます。
しかし、代襲相続人が甥・姪であった場合は、遺留分を請求できない点に注意が必要です。



表を参考に、代襲相続で遺留分が認められるか認められないかを改めてチェックしておきましょう。
代襲相続の遺留分を計算する方法【3ステップ】
代襲相続で遺留分を主張できる場合、「具体的にいくら請求できるのか」という点が気になる方もいるかもしれません。
本章では、遺留分の計算方法について、具体例とともに解説します。遺留分としていくらもらえるのか計算してみてください。
遺留分算定の基礎となる財産を計算する
まずは遺留分を計算する元となる財産の総額を確定させましょう。
計算式は「(相続開始時のプラスの財産-債務)+一定の生前贈与」です。
預貯金や不動産、株式といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引き、特定の生前贈与を財産に「持ち戻して」加算します。
特に重要なのが、相続人に対して行われた「特別受益」にあたる贈与です。これは、遺産の前渡しと考えられるような、結婚資金や事業資金、住宅購入資金などの援助が該当します。
(参照:裁判所|遺産分割Q&A)
相続人全体の遺留分の割合(総体的遺留分)を計算する
次に、ステップ1で算出した基礎財産のうち、相続人全体として法律上確保される遺留分の割合(総体的遺留分)を計算します。
総体的遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のように決まっています。
(参照:民法|第1042条)
| 相続人の構成 | 割合 |
|---|---|
| 相続人が配偶者や子(またはその代襲相続人)を含む場合 | 基礎財産の1/2 |
| 相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合 | 基礎財産の1/3 |
| 相続人が兄弟姉妹(またはその代襲相続人)のみの場合 | 0(遺留分なし) |
自分のケースと照らし合わせ、総体的遺留分の割合がどうなるかチェックしましょう。
自分の個別的遺留分を計算する
最後に、相続人全体の遺留分(総体的遺留分)に、本来の相続人(被代襲者である自分の親)の法定相続分を掛け合わせ、自分の遺留分額(個別的遺留分)を算出します。
相続人全体の遺留分(総体的遺留分)×本来の相続人(被代襲者である自分の親)の法定相続分
もし代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者が受け取るはずだった遺留分を、さらに代襲相続人の人数で均等に割ります。
【計算例】祖母が亡くなり、祖母の長男と亡き次男の子(孫)が相続人になるケース
以下の状況において、孫が代襲相続する場合の計算方法を解説します。
- 被相続人:祖母
- 相続人:長男、亡き次男の子(孫・代襲相続人)1名
- 遺産総額:6,000万円(債務や特別な贈与はないものとする)
- 遺言内容:「全財産を長男に相続させる」
1つずつ順番にみていきましょう。
債務や特別な贈与はないため、基礎財産は 6,000万円です。
相続人が子(長男と次男)のみのため、総体的遺留分は「遺産全体の2分の1」です。
6,000万円×1/2=3,000万円
この3,000万円が、相続人全体で保障される遺留分の総額です。
まず、被代襲者である次男の法定相続分(兄弟で均等)は1/2です。
3,000万円×1/2=1,500万円
代襲相続人は孫1人のみのため、この「1,500万円」が、孫の個別的遺留分です。
ただし、遺産に不動産や非上場株式などが含まれる場合、その評価方法を巡って争いになることが少なくありません。



どの評価額を採用するかで請求額が大きく変わるため、正確な遺留分を算出するには、弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
代襲相続の遺留分が侵害されていたらどうする?
遺留分は、自動的にもらえる権利ではありません。
遺留分が侵害されていることがわかった場合、権利を取り戻すためには、遺産を多く受け取った相手方に対して「遺留分侵害額請求」という手続きを自ら行う必要があります。
権利を取り戻す「遺留分侵害額請求」の進め方
遺留分侵害額請求は、いきなり裁判になるわけではなく、段階的に進めていくのが一般的です。
まずは当事者間の話し合いによる穏便な解決を目指し、そこで合意に至らない場合に、内容証明郵便の送付や家庭裁判所での調停といった法的な手続きへと移行していきます。
大まかな流れを以下の表にまとめました。
| 手続き内容 | 概要 |
|---|---|
| 1:当事者間での交渉 | まずは遺産を多く受け取った相手方と直接話し合い、穏便な解決を目指します |
| 2:内容証明郵便の送付 | 交渉がまとまらない場合、「遺留分を請求する」という明確な意思を内容証明郵便で送付します |
| 3:家庭裁判所での調停 | 内容証明を送っても相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます |
| 4:訴訟の提起 | 調停でも合意に至らない場合の最終手段です |
まずは話し合いから始め、段階的に法的な手続きへ進むのが基本的な流れです。各ステップには、それぞれ法的な意味合いや注意点があります。
請求に関する各ステップの詳細は、以下の記事で詳しく紹介しています。合わせてご覧ください。
関連記事:【弁護士監修】遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは?計算方法や時効・手続きの流れをわかりやすく解説
【注意】代襲相続の遺留分請求には時効がある
遺留分侵害額請求権には、権利が消滅してしまう「時効」があるため、迅速な行動が不可欠です。時効には2種類あり、どちらか早い方が到来すると権利を失ってしまいます。(参照:裁判所|遺留分侵害額の請求調停)
- 相続の開始と、遺留分が侵害されていることを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
特に「知った時から1年」という期間は非常に短いものです。遺言書の存在を知り、遺留分が侵害されていると認識した時点から、時効のカウントダウンは始まります。
権利を守るためには、少しでも疑問を感じたら、すぐに専門家へ相談することをおすすめします。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
代襲相続人が遺留分侵害額を請求するときの注意点
代襲相続人が遺留分を請求する際、特に注意すべき点は以下の3つです。
- 遺産の全体像を正確に把握するのが難しい
- 時効の起算点の判断が難しい
- 他の相続人との争いに発展しやすい
代襲相続人は被相続人と疎遠なケースも多く、遺留分侵害額を算出する前提となる「遺産の正確な把握」が、最初の壁になります。
また、通常よりも相続関係が複雑なため「知った時から1年」という時効の起算点の判断が難しく、意思表示が遅れて請求権を失うリスクもあるでしょう。
さらに、土地や株といった遺産の評価額をめぐって他の相続人と意見が対立しやすく、交渉がまとまらなければ調停や訴訟に至る可能性も考えられます。



これらの問題が生じた場合、ご自身での解決は困難なケースが少なくありません。速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。
代襲相続の遺留分トラブルを弁護士に相談すべき3つの理由
遺留分侵害額請求は自分で行うことも可能ですが、法律の専門家である弁護士に依頼すると以下のメリットを得られます。
特に代襲相続が絡むケースでは、その複雑さから弁護士のサポートが有効です。順番に解説します。
正確な遺留分額を算出できる
遺留分の計算は一見シンプルに見えても、その基礎となる財産の評価が非常に複雑です。
特に不動産や非上場株式が含まれる場合、評価方法が複数存在し、どの方法を選ぶかによって算出される金額が大きく変わる可能性があります。また、知識がないまま計算を進めると、本来得られるはずだった金額よりも大幅に少なく請求してしまうリスクもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、法的に正当な財産評価を行い、過去の生前贈与(特別受益)についても徹底的に調査し、自分が受け取るべき最大限の権利を確保することが可能です。
弁護士に依頼すると以下のような費用は発生しますが、かかった費用以上に多くの遺留分を得られるケースも少なくありません。
| 費用項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 法律相談料 | 無料~30分5,000円程度 |
| 着手金 | 20万〜50万円程度 |
| 成功報酬 | 弁護士の関与によって得られた財産の10〜15% |
| 実費 | 約5万~7万円※案件によって異なる |
| 日当 | 約3万円~5万円 |
| 遺産調査費用 | 15万〜30万円程度 |
※具体的な費用は法律事務所により変動
なお、遺留分侵害額請求の場合、弁護士法人アクロピースでは、遺留分侵害額請求をする側でも、された側でも、いずれも着手金無料です。
弁護士法人アクロピースの報酬体系について詳しくはこちらをご覧ください。
相手方との交渉や煩雑な手続きをすべて任せられる
遺留分の問題は、金銭だけでなく長年の家族関係や感情が複雑に絡み合います。そのため、当事者同士で直接交渉すると、関係がさらに悪化してしまうケースが少なくありません。
しかし、弁護士が代理人として間に入ると、感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が可能になります。
調停や訴訟に必要な書類の作成や裁判所とのやり取りなど、遺留分侵害額請求に必要な手続きをすべて任せられるため、精神的な負担を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。
時効管理と有利な解決が期待できる
遺留分侵害額請求には「知った時から1年」という非常に短い時効があります。仕事や日々の生活に追われる中で、「気づいたら時効が過ぎていた」という事態は絶対に避けなければなりません。
弁護士に依頼すれば、時効の管理を徹底し、権利が消滅するリスクを防ぎます。
また、豊富な知識と交渉経験を駆使して、最も有利な条件での解決を目指します。



専門家が介入することで相手方も真摯に対応せざるを得なくなり、結果的に早期解決につながることも多いのです。
遺留分と遺留分侵害額請求に強い弁護士の選び方については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
関連記事:遺留分請求に強い弁護士とは?選び方や安く抑える方法を現役弁護士が解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
「遺留分と代襲相続」に関するよくある質問
親が相続放棄した場合、代襲相続での遺留分は主張できる?
親が相続を放棄している場合は、代襲相続の遺留分は主張できません。
法律上、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。そのため、相続権自体が発生せず、代襲相続も起こりません。
したがって、その子どもが遺留分を主張することもできないため注意が必要です。
遺言書に「代襲相続しないように」と書かれていたら従うべき?
遺言書に「代襲相続しないように」と書かれていたとしても、従う必要はありません。
代襲相続などだれが相続人となるかについては民法で定められており、相続人が誰になるのか個人の意思である遺言によって変更することはできません。
そのため、遺言書に「代襲相続させない」といった記載があったとしても、その部分に法的な効力はなく、正当な代襲相続人として、相続する権利を主張できます。
遺言書による遺留分トラブルについては、以下の記事も参考にしてください。
代襲相続人は遺留分を放棄できる?
代襲相続人が、自分の意思で遺留分を放棄することは可能です。
代襲相続人は、亡くなった本来の相続人(親など)の権利義務をそのまま引き継ぐため、遺留分を受け取る権利だけでなく、放棄する権利も認められています。
ただし、相続開始のタイミングによって遺留分を放棄するために必要な手続きが異なるため、注意が必要です。
- 相続開始後(被相続人の死後):遺留分を侵害している相手に対して、「権利を主張しない」という意思表示をすれば、権利を放棄できます
- 相続開始前(被相続人の生前):不当な圧力を防ぐため、家庭裁判所の許可が必須となります
遺留分放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ|代襲相続の遺留分トラブルは弁護士へ相談しよう
遺留分の代襲相続は、自分がどの相続人の立場であるかによって大きく異なります。
孫の場合は遺留分がありますが、甥・姪の場合はありません。
これは、代襲相続が「相続人としての地位(親が持っていた権利)」を引き継ぐ制度であり、甥・姪は遺留分が認められない兄弟姉妹を代襲相続するためです。
もし、遺留分が請求できるのに侵害されていた場合、「遺留分侵害額請求」によって取り戻すことが可能です。ただし、請求には「1年」という短い時効があるため、遺留分侵害の事実を知ったら、迅速に行動することをおすすめします。
代襲相続の場合、立場によって取り分が異なり、金額の算出方法も複雑です。



もし不安な点がある、トラブルを抱えているなどの場合はぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人アクロピースは、相続問題の解決実績が豊富です。ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、法的な観点から最善の解決策を得るお手伝いをいたします。
初回のご相談は60分無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。