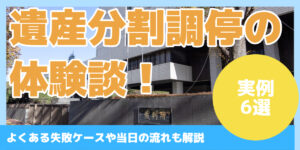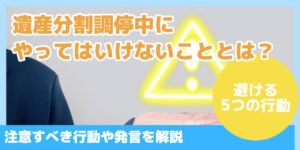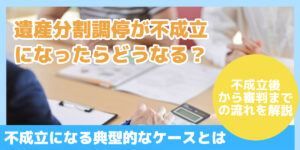【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続で長男は独り占めできる?兄弟間でよくあるトラブルや対処法を解説
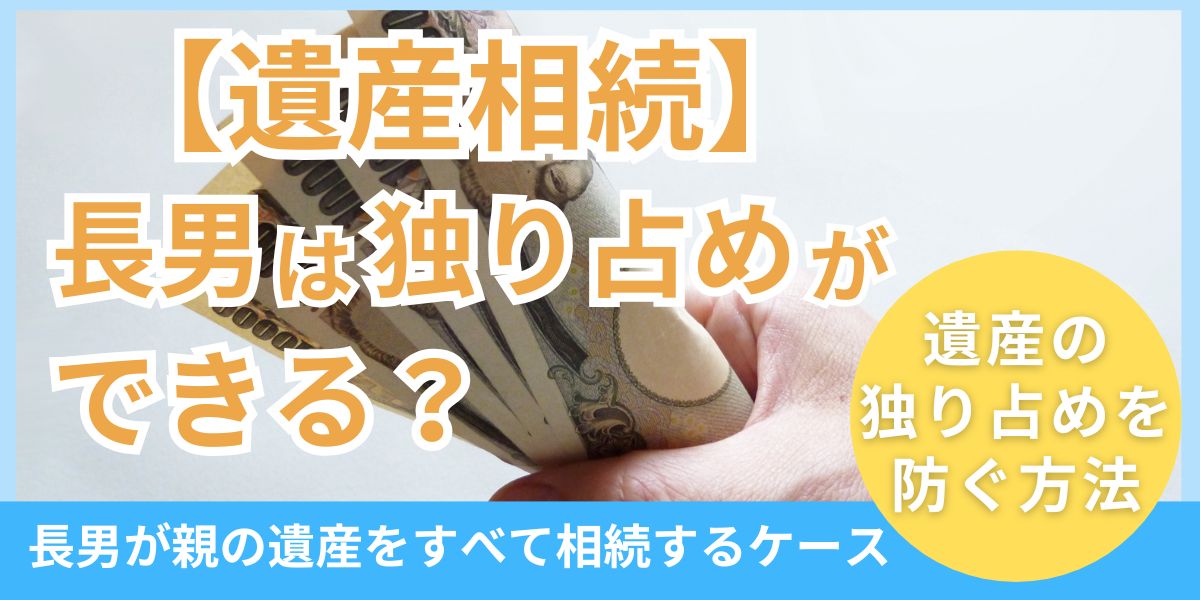
遺産相続では、長男から「親の財産はすべて自分が相続する」と主張され、兄弟間でトラブルになるケースがあります。
しかし、現行の法律では遺産相続を長男が独り占めすることは認められていません。
本記事では、遺産相続で長男による独り占めを主張された場合の正しい対処法をお伝えします。
特定の人に偏って遺産相続がなされ、遺留分を侵害されたときの対応方法についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
長男でも親の遺産を独り占めできない

遺産相続では「自分は長男だからすべての財産を相続する権利がある」と主張するケースがあります。
しかし、現在の民法ではそうした考え方は認められません。
長男が親の遺産を独り占めできない理由は、以下の通りです。
家督制度は廃止されている
かつての日本では、長男が戸主として家族を代表し、財産や家業を継承する「家督相続」という制度が存在していました。
そのため「遺産相続=長男の独り占め」という考えも成り立っていたのです。
しかし、家督相続制度は1947年の民法改正により廃止され、現在は法定相続制度が適用されています。
現行制度では、すべての法定相続人が平等に相続権を持ち、長男だけが優先的に財産を受け取る仕組みは存在しません。
今なお家督相続のイメージを引きずった主張がなされるケースもありますが、その言い分は法的根拠に欠けています。
民法に定められている相続制度が適用される
現行の相続制度は、民法に基づく法定相続制度に従って行われます。
相続人の順位と相続分は法律により定められており「長男だから遺産を独り占めできる」といった主張は認められません。
配偶者は常に相続人となり、以下の順位の者とともに遺産を分け合います。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子ども(配偶者ともに相続する) |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属(子どもがいない場合に相続する) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(子どもと親がいない場合に相続する) |
子ども同士の法定相続分は平等です。
遺産相続は、すべての相続人の権利を尊重した上で、公平に分配されるべきです。
法定相続分については、こちらの記事もお読みください。
関連記事:法定相続分とは?法定相続人の順位と計算方法や遺留分との違いを解説!
遺産分割の流れ

遺産分割とは、相続が発生し、遺言書が存在しない場合に、法定相続人がそれぞれの取り分に応じて遺産を分けるための手続きです。
遺産は、原則として相続人全員で協議し、合意に基づいて分配されます。
遺産分割の一般的な流れは、次の通りです。
1.遺言書の有無を確認する
遺産相続が発生したら、遺言書が残されているか確認する必要があります。
遺産分割では相続人全員による話し合い(遺産分割協議)よりも、原則として遺言書の内容が優先されるからです。
法的に有効な遺言書が存在する場合は、その内容に従って遺産を分配します。
一方で、遺言書がない場合は、法定相続人全員で協議を行い、遺産の分け方を決定しなければいけません。
遺産相続を法律に則って正しく行うために、遺言書の有無の確認から始めてください。
2.遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、遺言書が存在しない場合に、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。
誰がどの財産を相続するか、どのように分けるかを協議によって決定します。
遺産分割協議は、すべての相続人の同意がなければ成立しません。
特に「長男だからすべての遺産を相続する」といった一方的な主張があると、話し合いが難航する可能性があります。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、法定相続分を正しく理解した上で、冷静な話し合いが求められます。
遺産分割協議がまとまらないときの対処法は、以下の記事をお読みください。
関連記事:遺産分割協議がまとまらない!スムーズに解決するための方法とは
3.話し合いで解決できないときは遺産分割調停を申立てる
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てます。
遺産分割調停の申立てにより、第三者の立場にある調停委員を交えて合意形成に向けた調整が可能です。
調停では、各相続人の主張や希望する分割方法、分配の割合などを聴き取り、公平な解決を目指します。
遺産相続で長男による独り占めを防ぐには、遺産分割調停による公的な話し合いの場の活用も有効です。
4.調停でも解決できない場合は遺産分割審判に移行する
遺産分割調停で合意が得られず、話し合いがまとまらない場合は「遺産分割審判」へ移行します。
審判では、家庭裁判所が相続人それぞれの主張や法定相続分などを踏まえて、遺産の分け方を裁判所が判断します。
「長男がすべてを相続するべきだ」といった偏った主張は認められず、民法に則った分割が行われるのです。
たとえ、相続人同士の対立が深刻であっても、最終的には裁判所の判断により、法的に妥当な解決がなされます。
遺言と異なる遺産分割については、次の記事を参考にしてください。
関連記事:遺言と異なる遺産分割の判例!遺産分割協議の進め方も詳しく解説
長男が親の遺産をすべて相続するケースとは

現行の民法においても、特定の条件を満たせば長男が親の遺産をすべて相続するケースが存在します。
以下は、長男がすべての遺産を相続する主な場合です。
遺産分割協議で法定相続人全員が同意した
遺産分割協議で法定相続人全員が合意すれば、法定相続分にかかわらず、遺産を特定の一人に相続させることが可能です。
協議の結果、法定相続人全員が長男がすべての遺産相続することに同意した場合、その内容は遺産分割協議書にまとめられ、法的に有効な手続きとして認められます。
しかし、法定相続人のうち一人でも反対すれば合意は成立せず、長男の単独相続は実現できません。
遺産分割は、あくまで相続人全員の協議と合意に基づいて進めるのが原則です。
遺言に「すべての遺産を長男に譲る」とか書かれていた
遺言書に「すべての遺産を長男に相続させる」と明記されている場合、その内容に基づいて遺産が分割されるため、実際に長男がすべての財産を相続するケースがあります。
遺産は被相続人の固有の財産であり、生前に自らの意思を示した遺言書によって、その分割方法が指定できます。
ただし、遺言が法的に有効であることが前提です。
また、遺言書の内容が、他の法定相続人の遺留分を侵害している場合「遺留分侵害額請求」によって侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを求められる可能性があります。
遺言が有効であっても、長男が遺産をすべて相続できるかどうかは「法的な手続きを正しく踏んでいるか」「他の相続人の権利を侵害していないか」によって決まります。
遺産を独り占めするとどうなるかについては、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:遺産を独り占めした人の末路は?起こり得るトラブルと独り占めを防ぐ方法
遺言で財産が一人に集中しても「遺留分」で正当な取り分は守られる
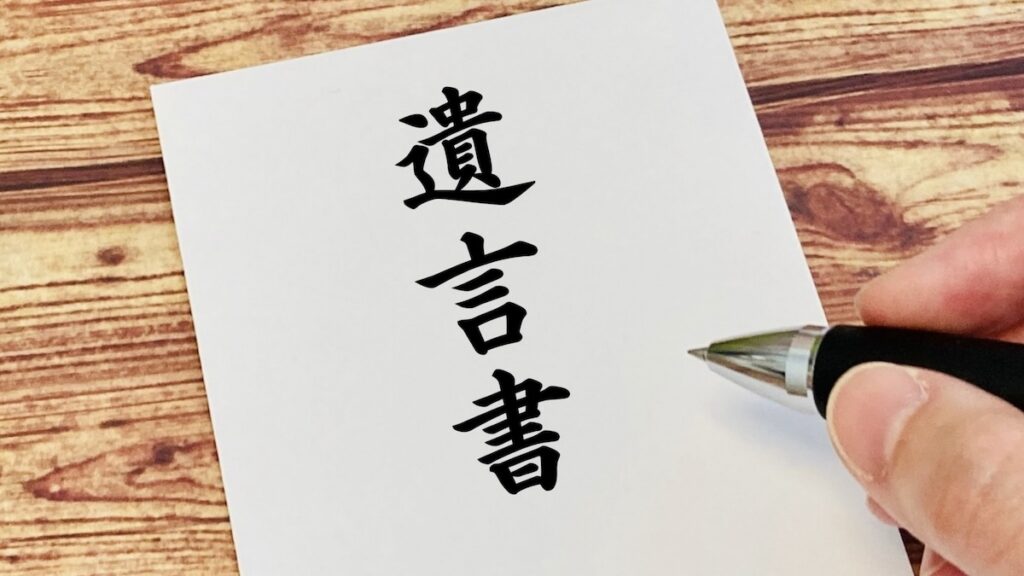
遺言で「すべての遺産を長男に相続させる」と指定されていたとしても、他の相続人がまったく財産を受け取れなくなるわけではありません。
民法第1046条では、一定の法定相続人には「遺留分侵害額請求権」が認められており、侵害された遺留分に相当する金銭の請求が可能です。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の意思による遺言や生前贈与があった場合でも、配偶者・子ども・親などの一定の法定相続人に保障されている最低限の遺産取得分です。
遺留分は、被相続人が自由に財産を処分できる権利と、相続人が最低限の財産を受け取る権利のバランスを保つために設けられています。
遺留分制度により「すべての財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の相続人がまったく財産を受け取れないという事態は避けられます。
遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されていた場合は「遺留分侵害額請求」によって、その分を金銭で請求が可能です。
遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
関連記事:遺留分侵害額請求をわかりやすく解説!計算方法や請求のやり方、注意点も
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された法定相続人が、その不足分に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。
相続人が被相続人の遺産から受け取るべき「法定相続分」に対して、一定の割合が遺留分として認められています。
遺留分が認められる相続人とその割合は、以下の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
| 配偶者と子(孫)※1 | 配偶者:1/4、子(孫)合計:1/4 |
| 子(孫)のみ | 子(孫)合計:1/2 |
| 配偶者と両親 | 配偶者:1/3、両親合計:1/6 |
| 両親(祖父母)※2のみ | 両親(祖父母)合計で1/3 |
| 兄弟姉妹 ※3のみ | なし |
※1孫は、子がすでに亡くなっている場合の代襲相続に限り遺留分が認められる
※2祖父母は、両親がすで亡くなっている場合に遺留分が認められる
※3兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分侵害額請求権は、相続において著しく不公平な財産配分が生じないように、一定の法定相続人の権利を守る役割を果たしています。
遺留分侵害額請求権についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?対象となる財産や計算、手続きの方法をわかりやすく解説
遺留分侵害額請求の流れ
遺産相続で長男が遺産を独り占めし、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、以下の手順で遺留分相当額の金銭が請求可能です。
1. 内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする
遺留分を侵害している相手に対して、遺留分を請求する意思を明確に伝えます。
遺留分侵害額請求の方法は法律で定められていませんが、証拠として残るように内容証明郵便で通知するのが一般的です。
内容証明郵便による請求は、将来的に調停や訴訟となった場合にも、有効な証拠となり得ます。
2.話し合いで解決できないときは家庭裁判所に調停を申立てる
相手方と話し合いによって解決を試みますが、相続は親族間の感情的な問題も絡みやすく、合意に至らないケースも少なくありません。
そのような場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申立てます。
交渉に不安がある場合は、弁護士に依頼して代理で交渉を進めてもらう方法も検討してください。
3.調停が成立しないときは遺留分侵害額請求訴訟を提起する
調停で合意に至らなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
遺留分侵害額請求訴訟では、裁判所が事実関係や法的根拠をもとに、遺留分の有無やその金額についての判断を下します。
遺留分侵害額請求の流れについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:遺留分の請求の仕方!流れや条件についてくわしく解説
長男による親の遺産の独り占めを防ぐ方法
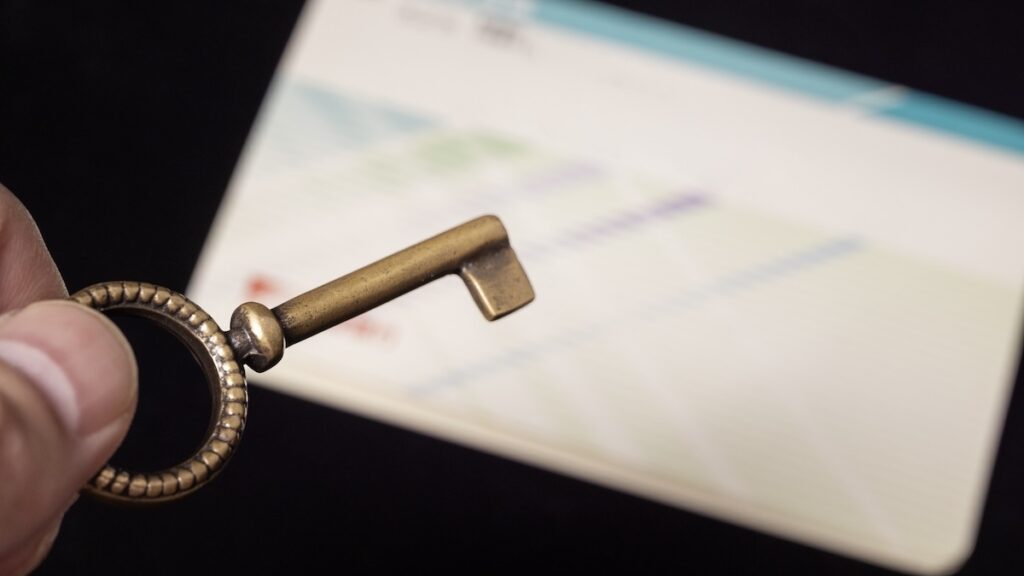
遺産相続の場面で、長男が「自分がすべて相続する」と主張してきたとしても、その言い分を阻止する手段があります。
親の遺産の独り占めを防ぐ主な方法は、以下の通りです。
遺言書の有効性を確認する
長男が親の遺言を根拠に遺産を独り占めしようとした場合、まず確認すべきは遺言書の有効性です。
遺言書があっても、法律で定められた方式を満たしていなければ無効と判断される場合があります。
| 遺言書が無効になる可能性がある事例 | |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 証人が2名に満たなかった |
| 証人になれない人が立ち合いをしていた | |
| 遺言能力のない人が作成した | |
| 強迫されて作成した | |
| 自筆証書遺言・秘密証書遺言 | 自筆で作成されていない |
| 作成日が明確に記載されていない | |
| 署名・押印がない | |
| 訂正方法に誤りがある | |
| 共同(2名以上)で作成されている | |
| 遺言能力のない人が作成した | |
| 強迫されて作成した | |
形式に不備がある遺言書は、無効の可能性があります。
遺言により特定の人に偏った相続が行われたときは、有効性を法的な観点で確認しましょう。
遺言書の有効性について書かれた記事は、以下をお読みください。
関連記事:遺言書の効力はどこまで?いつから効力が発生する?書き方や無効なケースも解説
口座を凍結する
親が亡くなった際、遺産を勝手に引き出されないようにするためには、口座の凍結が有効です。
口座を凍結すれば、親からキャッシュカードを預かっていた人がいたとしても、預貯金が勝手に引き出されるのを防止できます。
口座の凍結を申し出る際は、金融機関の窓口で名義人の死亡を伝えます。
手続きには、以下の書類が必要です。
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
- 相続関係を証明できる戸籍謄本
- 本人確認書類(顔写真付き)
口座を凍結する際は、相続手続きの準備として残高証明書や取引明細書を併せて取得しておくと、のちの遺産分割協議でも役立ちます。
生前に使い込みしていたら不当利得返還請求する
親の財産を管理していた長男が、生前に自分のために勝手に預金を使い込んでいた場合、他の相続人は「不当利得返還請求」が可能です。
不当利得返還請求とは、正当な理由なく利益を得た相手に対し、損失を被った側がその返還を求める法的手段です。
不当利得返還請求は、以下の流れで行われます。
| 1.使い込みの証拠を集める | 預金通帳や出金記録などから、使途不明金の有無や金額を確認する |
|---|---|
| 2.請求の意思を通知する | 内容証明郵便を使って、返還を求める意思を正式に相手へ伝える |
| 3.協議・合意書の作成 | 話し合いを行い、返還内容に合意できれば合意書を交わす |
| 4.訴訟を提起する | 協議がまとまらない場合は、不当利得返還請求訴訟を提起し、裁判所に判断を仰ぐ |
不当な使い込みがあったときは、早期に対応することが、適正な遺産相続の実現につながります。
兄弟間の相続トラブルは弁護士に解決を依頼する

遺産相続において、兄弟間で深刻なトラブルが発生するケースは少なくありません。
兄弟間の相続トラブルは、弁護士へ相談・依頼が有効です。
以下に挙げるのは、相続問題の解決を弁護士に依頼するメリットです。
- 民法の相続制度を理解していない長男にわかりやすく説明できる
- 遺産分割協議の交渉を依頼できる
- 遺産分割協議に関する手続きを任せられる
- 遺留分侵害額請求の手続きも行える
兄弟間で相続問題が生じたら、早期の弁護士への依頼が円満解決へと導きます。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
まとめ|長男がすべての遺産の相続を主張してきたら弁護士に相談しよう
親の遺産相続の話し合いは、近しい間柄であるからこそ感情的になってしまい、こじれてトラブルに発展しやすい側面があります。
この記事では、兄弟間で起こりうる相続問題を取り上げ、対処法を解説しました。
- 戦前は家督制度により、長男が親の遺産をすべて相続するケースがあったが、現在の民法では、兄弟は平等に遺産を相続する
- 親が亡くなったときの遺産分割の流れは、1.遺言の有無の確認、2.遺産分割協議、3.遺産分割調停、4.遺産分割審判
- 現行民法で長男がすべての遺産を相続するケースは、遺言にその旨が記載されている場合と遺産分割協議で法定相続人全員の同意がなされた場合
- 遺言によって長男に遺留分が侵害された兄弟は、遺留分侵害額請求により、侵害された相当額を金銭で返還を求められる
- 長男による遺産の独り占めを阻止する方法には「遺言の有効性を確かめる」「口座を凍結する」「不当利得返還請求」がある
兄弟間の相続問題は、対立が深まる前に弁護士に相談して、スムーズな解決を図りましょう。
相続問題でお悩みなら、相続トラブルに強い弁護士法人アクロピースにお気軽にご相談ください。
初回60分の無料相談も可能なので、問い合わせフォームもしくは、公式LINEから気軽にお問い合わせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応