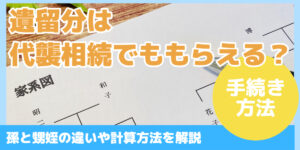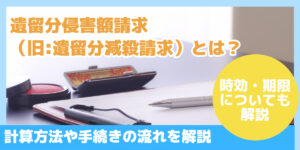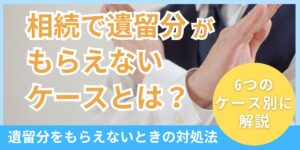【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分の請求の仕方!流れや条件についてくわしく解説
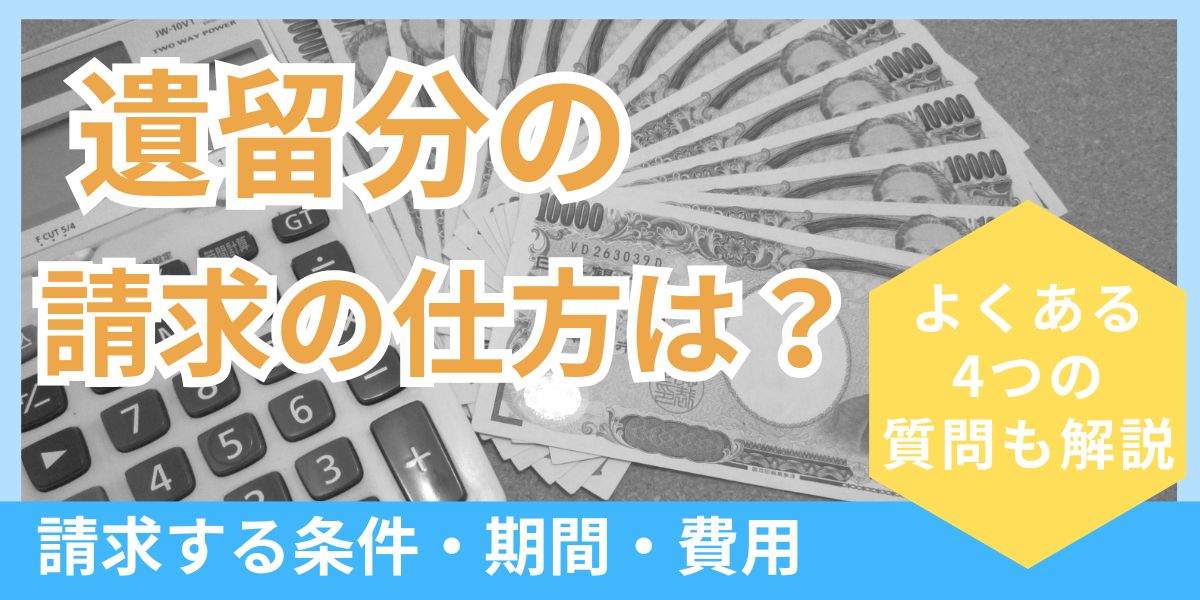
遺留分を請求するには、遺留分侵害額請求の手続きが必要です。
遺留分とは何かを理解している方の中にも、具体的な請求方法がわからずにお困りの方もいらっしゃるでしょう。
遺留分侵害額請求では、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺留分の侵害があるのなら、正しい請求方法を理解して手続きを進めるのがおすすめです。
この記事では、遺留分の請求を検討している方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
遺留分の制度を理解しているだけでは具体的な請求手続きを進めるのは難しいでしょう。
実際に遺留分の請求を検討しているのであれば、この記事をぜひ最後までご覧ください。
遺留分侵害額請求で相手方との交渉を始める際は、内容証明郵便の送付からスタートするのが一般的です
遺留分侵害額請の手続きで悩んでいる方は、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
初回60分の相談は無料です。
LINEからも24時間365日無料で相談の問い合わせがきますので、お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
今すぐご相談したい方は、お電話がおすすめです!
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分について、詳しくはこちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:【遺留分とは何か】わかりやすく解説!法定相続分との違い・計算方法・具体例
遺留分の請求の仕方とは

遺留分侵害額請求で遺留分を請求するには、次の4つの段階があります。
相手方との交渉を始める際は、内容証明郵便の送付からスタートするのが一般的です。
ここでは、それぞれの段階に分けて遺留分を請求する方法を解説します。
内容証明郵便を送付する
遺留分侵害額請求の手続きを進めるには、最初に内容証明郵便で遺留分を請求する意思を相手方に伝えます。
配達証明付き内容証明郵便は、郵便局が書類の内容、差出人や受取人、受取の日時などを証明してくれるサービスです。
遺留分侵害額請求には時効があります。
時効の期間は、相続の開始と遺留分の侵害があったことを知ってから1年間と短いです。
話し合いの途中で時効が完成してしまうといった事態を防ぐには、最初の内容証明郵便を送付してください。
いったん遺留分侵害額請求権を行使すると、そこから発生する金銭支払請求権の時効は5年となります。
「1年以内に遺留分侵害額請求がなかったので時効が成立している」という不要な争いを防ぐため、内容証明郵便で遺留分を請求した事実を残しておくことが重要です。
遺留分侵害の相手方との交渉
内容証明郵便を送付したあとは、すぐに調停には進まず、相手方との話し合いで解決を目指すのが一般的です。
話し合いで合意できたときには、必ず合意書を作成するようにしてください。
合意書がなければ、後から話し合いが蒸し返されてしまう可能性もあります。
合意書の作成方法や記載内容に不安がある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
話し合いで合意できないときには、裁判所を利用した調停や訴訟手続での解決を目指すことになります。
遺留分侵害額請求の調停
遺留分侵害額請求の調停は、調停委員立ち会いのもと、話し合いでの解決を目指す手続きです。
訴訟を提起する前に調停を経なければならないという調停前置主義により、最初は原則として、調停を申し立てることになります。
調停を申し立てるには、申立書のほか遺産の内容を示す資料、戸籍などを添付書類として準備する必要があります。
調停を申し立てる裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所もしくは双方の合意で決めた家庭裁判所です。
調停期日では、調停委員が双方から交互に話を聞いて意見の調整を図ります。
直接の話し合いでは冷静に進められないことも、調停委員が仲介することで円滑に進められる可能性があるでしょう。
双方が調停案に合意できたときには、調停が成立して調停調書が作成されます。
調停調書に記載された内容は、裁判の判決と同様の効力を持ちます。
遺留分侵害額請求訴訟
調停で解決できないときは、訴訟で決着をつけることになります。
訴訟では、当事者が合意できないときでも、裁判所が判決で請求の可否を判断します。
訴訟手続を進めるには、主張を整理して伝え、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。
交渉や調停での手続きよりも専門的な知識が求められるため、調停まで弁護士に依頼していなかった場合でも、訴訟手続きは弁護士に依頼すべきです。
訴訟は和解によって終結することもありますが、和解できない場合には判決が出されます。
判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴することも可能です。
判決で遺留分に相当する金銭の支払いが命じられた場合、その判決が確定すれば、相手方がそれに従わないときは強制執行で相手方の財産を差し押さえることもできます。
遺留分侵害額請求の手続きについて、詳しくはこちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?手続き・注意点
遺留分を請求する条件

遺留分は、誰でも請求できるものではありません。
誰が遺留分を請求できるかを判断するには、遺留分を請求できる人と遺留分の侵害とは何かを理解する必要があります。
ここでは、遺留分を請求する人と遺留分を侵害されていることの2つに分けて、遺留分を請求する条件を解説します。
遺留分を請求できる人
遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です(民法1042条1項)。
法定相続人の一覧は、次のようになっています。
- 配偶者
- 直系卑属(子どもや孫)
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分を請求することはできません。
関連記事:遺留分は相続人が子供のみの場合どうなる?子供2人のみの場合の割合や計算例・侵害額請求の手順を弁護士が解説
遺留分を侵害されていること
遺留分を侵害されていることとは、相続で取得する財産が遺留分よりも少ない状態のことです。
たとえば、相続人が妻と長男の場合、妻の遺留分は相続財産の4分の1となります。
相続財産が4000万円であれば、妻の遺留分は1000万円です。
このケースで、妻に500万円、長男に3500万円の財産を相続させる旨の遺言書が遺されていた場合、妻は、500万円分の遺留分が侵害されています。
そのため、妻は、長男に対して遺留分侵害額請求として500万円の支払いを求めることが可能です。
遺留分の請求にかかる期間の目安

遺留分を請求する際に最も重要なのは、時効完成前に内容証明郵便を送付することです。
遺留分侵害額請求は、相続の発生と遺留分侵害の事実を知ってから1年で時効になります。
相手方との交渉には期限がありません。
一般的には、交渉開始から2〜3か月経っても進展が見られないときは裁判所での手続きに移行することになります。
調停や訴訟は、1か月から1か月半に1回のペースで期日が開催されます。
調停で決着するまでは、半年から1年程度かかるケースが多いでしょう。
裁判にまで移行すると、調停と裁判を併せて1年以上かかることも珍しくありませんので、早めに請求を行うようにしましょう。
遺留分の請求にかかる費用

遺留分の請求にかかる費用は、調停や裁判にかかる費用と弁護士費用に分けられます。
ここでは、それぞれの費用の内訳を解説します。
調停や裁判にかかる費用
調停の申立てにかかる費用は、1200円の収入印紙と5000円ほどの郵便切手代です。
郵便切手代は、手続きを申し立てる裁判所によって金額が変わるので、詳しい金額は裁判所に問い合わせてみてください。
裁判にかかる費用は、訴額に応じた収入印紙と5000円ほどの郵便切手代となっています。
遺留分侵害額請求の訴額とは、裁判で相手方に支払いを求める金額のことです。
具体的な金額は、下記のサイトで確認できます。
参照:手数料額早見表:裁判所
たとえば、遺留分侵害額請求の請求金額が1000万円の場合、収入印紙の金額は5万円となります。
弁護士費用
遺留分侵害額請求の手続きを弁護士に依頼する場合には、着手金と報酬金がかかります。
着手金は、依頼の際に支払う費用です。
報酬金は、事件が解決した際に支払う費用となっています。
着手金は、日弁連の旧規定を基準に算定している事務所が多くなっています。
具体的な金額は、次のとおりです。
| 経済的利益の額(請求額) | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 請求額の8.8% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 請求額の5.5%+9万9000円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 請求額の3.3%+75万9000円 |
報酬金は、実際に相手から回収できた金額をベースに計算されるケースが多いでしょう。
日弁連の旧規定における報酬金の額は、着手金の2倍の金額となっています。
たとえば、遺留分侵害額請求で1000万円を請求して全額を回収できた場合、着手金と報酬金の金額は次のようになります。
- 着手金:1000万円×5.5%+9万9000円=64万9000円
- 報酬金:1000万円×11%+19万8000円=129万8000円
弁護士費用については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事;【遺留分の請求】にかかる費用の内訳や具体例安く抑える方法も解説
遺留分を請求する方法についてよくある質問

ここでは、遺留分侵害額請求についてよくある質問に回答します。
遺留分を請求する方法について疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
遺留分侵害額請求で物の返還を求めることはできますか?
遺留分侵害額請求では、物の返還を求めることはできません。
2019年7月1日の民法改正以前は、遺留分減殺請求により物の返還を求めることができました。
しかし、遺留分の請求により物の返還を認めると、相続財産の共有状態が生じるという問題があります。
遺留分権利者としても、金銭の支払いさえ受けられれば満足できる人がほとんどです。
そのため、遺留分侵害額請求では、物の返還ではなく遺留分に相当する金銭の支払いだけが認められています。
遺留分は口頭でも請求できますか?
遺留分は口頭でも請求できます。
しかし、遺留分侵害額請求の時効は1年です。
口頭では遺留分を請求した証拠が残らなくなるため、時効の完成を避けるためには内容証明郵便で請求した証拠を残しておく必要があります。
遺留分を請求する際に弁護士に依頼すべきですか?
遺留分の請求手続きを弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 交渉成立による早期解決が期待できる
- 交渉、調停、訴訟といった一連の手続きをすべて任せられる
- 専門的知識に基づく適切な主張・立証ができる
弁護士に依頼するか否かで、相手から取り戻せる金額が大きく変わることも珍しくありません。
遺留分侵害額請求は自分で行うこともできますが、専門知識がない方の場合かなり大変といえるでしょう。
遺留分侵害額請求について不安のある方は、まずは弁護士にご相談ください。
遺産のうち遺留分の割合はどのくらいですか?
遺産に占める遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって変わります。
具体的には、次のようになります。
- 直系尊属のみが相続人の場合 遺産の3分の1
- それ以外の場合 遺産の2分の1
相続人が複数いる場合、それぞれの遺留分は、全体の遺留分に自分自身の法定相続分を乗じた割合となります。
遺留分の割合について、詳しくはこちらの記事も併せてご覧ください。
まとめ
今回は、遺留分の請求の仕方を理解するために、次の内容について解説しました。
- 遺留分侵害額請求では遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる
- 遺留分を請求する際は最初に内容証明郵便を送付する
- 交渉で解決できないときは、調停や訴訟で決着をつける
遺留分の請求を検討している方は、弁護士への相談がおすすめです。
相手方との交渉をスムーズに進めるには、法律の専門家である弁護士に交渉を任せるのが良いでしょう。
遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼するか否かで相手から取り戻せる金額が大きく変わることも珍しくありません。
権利を守るためには、知識と力が必要です。
遺留分侵害額請求について不安のある方は、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
初回60分の相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
今すぐご相談したい方は、お電話がおすすめです!
【無料相談受付中】24時間365日対応