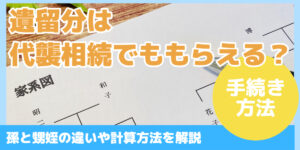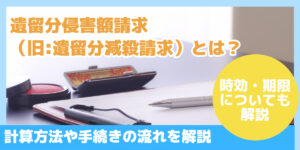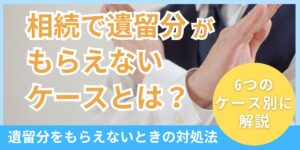【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分を支払わないとどうなる?支払い拒否のリスク、現金がないときの対処法を解説
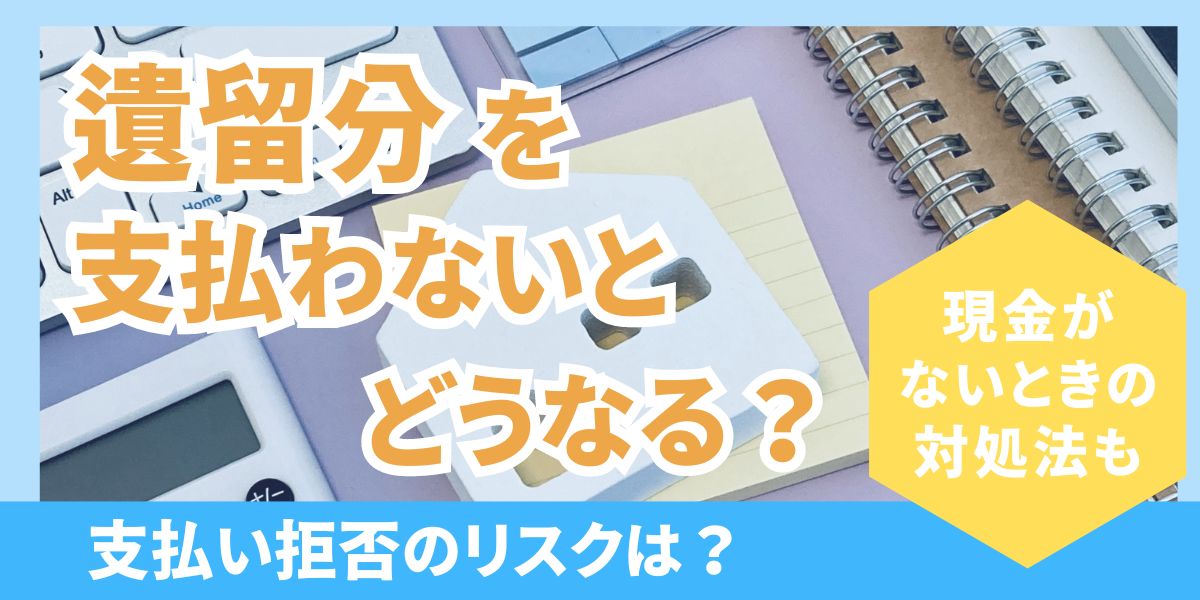
贈与や遺贈によって被相続人から財産を受け取っていた場合、遺留分権利者から遺留分侵害額請求が行われれば、正当な遺留分を支払わなければいけません。
しかし、何らかの理由で「遺留分を払いたくない」「支払いを拒否したい」「支払いたくても現金がない」という方もいるのではないでしょうか。
今回は、遺留分を支払わないとどうなるのか、支払いを拒否するリスクや支払わずに済むケース、現金がないときの対処法について解説します。
本記事では、遺留分を支払う側向けの記事のため、「遺留分は必ずもらえるのか?」と不安に思っている方はこちらの記事を参考にしてみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
正当な遺留分なら支払い拒否はできない

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども・父母)に対して保障された最低限の取り分を指します。
遺言によっても奪うことができない権利なので、支払い拒否はできません。
ただし、だからといって請求されるがままに金銭を支払うことは避けるようにしてください。
正当な遺留分の請求であれば支払う義務があります。
しかし、相手方の主張が必ずしも正しいとは限りません。
よくよく調べたら、遺留分を支払わなくて済んだというケースもあります。
遺留分侵害額請求をされたら、慌てずに落ち着いて、冷静に対処することが大切です。
遺留分侵害額請求されたときに「やるべきこと」
- 相手方と話し合いの機会を設ける
- 相手のことをよく調べる
- 主張の正当性を確認する
遺留分侵害額請求されたときに「やってはいけないこと」
- 遺留分侵害額請求を無視する
- 何も調べず、相手方の言い分通りの金銭を支払う
遺留分を支払い拒否するとどうなる?考えられる2つのリスク

遺留分侵害額請求を無視したり、支払いを拒否したりすると、どのようなことが起こるのでしょうか。
続いては、遺留分を支払わないとどうなるのか、考えられるリスクについて説明します。
調停や訴訟を申し立てられる
遺留分侵害額請求は、内容証明郵便で送られてくることがほとんどです。
無視し続けると、調停や訴訟を申し立てられる可能性があります。
遺留分侵害額の請求調停は、家庭裁判所にて行われます。
調停とは、調停委員が当事者間の話し合いをサポートしてくれる司法制度です。
調停で解決しなかった場合は、最終手段である遺留分侵害額請求訴訟に進むことになります。
遺留分侵害額請求訴訟で遺留分の請求が認められた場合は、それに従うしかありません。
強制執行により財産を差し押さえられる
遺留分侵害額請求訴訟で遺留分の支払いを命ずる判決が出たにも関わらず、それを無視し続けると、相手方が強制執行の申立て手続きを行う可能性があります。
強制執行が行われると、裁判所が債務者の財産を強制的に回収できるようになるため、預貯金や給与などの財産の差し押さえが行われます。
関連記事:遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説
遺留分を支払い拒否できる4つのケース

遺留分侵害額請求権は、法律で認められた権利です。
正当な遺留分侵害請求であれば、相手方に遺留分に相当する金銭を支払う義務が生じます。
しかし、以下のようなケースに該当する場合、相手方の請求額をそのまま支払うことはしなくて済むかもしれません。
遺留分侵害額請求の時効を過ぎている
遺留分侵害額を請求できる期限については、民法に以下の定めがあります。(民法1418条)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
既に時効が成立している場合、相手方の遺留分侵害額請求に応じる必要はありません。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
生前に特別受益がある
相手方に特別受益がある場合も、遺留分侵害額請求を拒否できる可能性があります。
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈等の利益のことです。
相続発生前10年以内に相続人に対して贈与や遺贈が行われている場合、遺留分を算定するための基礎財産額に特別受益分を加えなくてはなりません。
相手方が、特別受益があることを棚に上げて遺留分を請求している場合は、しっかりとその旨を主張しましょう。
特別受益については、以下の記事もぜひ参考にしてください。
推定相続人の廃除をされている
被相続人による推定相続人の廃除によって、そもそも相続権をはく奪されている場合、遺留分の権利も同様に失うことになります。
推定相続人の廃除とは、「遺留分を有する推定相続人に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続権を失わせる制度」のことです。
(遺言による推定相続人の廃除)
引用:民法 | e-Gov 法令検索
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
たとえば、以下のようなケースで認められています。
- 長年浮気を繰り返して、家庭を顧みなかった配偶者
- 親の預貯金を無断で繰り返し使ってきた子ども
- 家庭内暴力を繰り返してきた子ども
遺留分侵害額請求をしてきた相手方が、被相続人によって推定相続人の排除をされている場合、その請求に応じる必要はありません。
相続欠格が適用される
相続欠格とは、「民法891条の相続欠格事由に該当する相続人が、相続権をはく奪される制度」のことです。
相続欠格となれば、相続する権利を失います。
相続権を失い相続人でなくなった以上、遺留分も有しません。
ただし、上述の推定相続人の廃除、相続欠格の場合には、代襲相続が開始するため、これらの者の直系卑属が遺留分権利者となるため注意が必要です。
【民法891条の相続欠格事由】
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格は推定相続人の廃除とは違い、被相続人の意思に関係なく適用されます。
また、被相続人が相続欠格となった者に「遺産を相続する」という遺言を残したとしても、遺産を相続することはできなくなります。
このように、遺留分侵害額請求をされた場合でも、支払わずに済むケースはあります。
しかし、遺留分侵害額請求に正当性があるかどうかの判断は、相続に関する専門的な知識がなければ、なかなか難しいといえるでしょう。
関連記事:遺留分は代襲相続でももらえる?孫と甥姪の違いや計算方法を解説【弁護士監修】
遺留分を支払う現金がないときの対処法2選

相手方の遺留分侵害額請求が正当なものである場合、その請求に応じなければなりません。
無視を続けると調停や訴訟を起こされ、最悪の場合は強制執行によって財産を差し押さえられてしまいます。
また、遺留分は金銭で支払うのが原則です。
しかし、さまざまな事情で「すぐに支払える現金がない」というケースは珍しくありません。
遺留分を支払う現金がないときは、どのように対処すれば良いのでしょうか。
ここでは、具体的な対処法について説明します。
遺留分の分割払いを交渉する
どうしても現金での一括払いが難しい場合には、相手方に分割払いの交渉をしてみましょう。
当事者間で同意が得られれば、分割回数や支払い期間に制限はありません。
相手方が納得してくれれば、長期分割払いも可能です。
裁判所に遺留分支払い期限の許与を求める
相手方が早急に支払うように求めてきた場合には、裁判所に期限の許与を求めることができます。
裁判所によって支払い期限の延長が認められれば、相手方も強く請求してくることはないでしょう。
とはいえ、相手方との交渉や裁判所への申し立て手続きを全て自力で行うのは、簡単なことではありません。
手続きをスムーズに進めるためにも、一度弁護士に相談するのがおすすめです。
遺留分の支払いで不動産しかないときの対処法

相続財産が不動産しかない場合でも、遺留分は金銭で支払わなければなりません。
不動産を手元に残しておきたいのであれば、遺留分相当額の金銭は自己資金から支払いましょう。
遺留分相当の自己資金を用意できない場合は、不動産の売却や不動産担保ローンによる借入などの検討が必要です。
不動産の現金化に時間がかかる場合は、前述の通り、裁判所に期限の許与を求めることも一つの方法です。
関連記事:遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求の方法と注意点を詳しく解説
遺留分を請求された場合の適切な対処法

遺留分を請求された場合、安易に無視したり、放置したりしてはいけません。
まずは、以下の3点を確認し、「相手方の請求に応じるべきか」を判断しましょう。
- 遺留分侵害額請求権に時効が成立していないか
- 相手方の請求額が妥当であるか
- 相手方が本当に遺留分権利者なのか
「相手方の請求に応じるべき」と判断した場合は、期限内に遺留分を支払うようにしてください。
「相手方の請求が不当である」と感じた場合、まずは弁護士に相談のうえ、相手方との話し合い(任意交渉)での解決を目指すのが一般的です。
相手方との関係性によっては、弁護士を通じて交渉を行うほうがスムーズなケースも多いです。
話し合いによって解決できない場合は、調停や訴訟を検討することになるため、早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺留分の支払い拒否に関してよくある質問
遺留分と遺言書ではどちらが強いですか?
遺留分は、相続人の中でも一定の地位にある人に認められる最低限の持ち分です。遺言書によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺留分の範囲で金銭請求ができます。
たとえば、遺言書で「財産はすべて長男に相続させる」と記載されていたとしても、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)には一定の遺留分が保障されているため、遺留分侵害額請求が可能です。
ただし、遺留分を侵害しているかどうかは、相続財産の評価や特別受益の有無など、複雑な要素を含む場合が多く、自力での判断が難しいケースも少なくありません。
遺言書の内容が一方的に不利と感じる場合でも、遺留分を侵害しているか、請求したときにどのくらいの金額が回収可能かを含めた事前の精査が重要です。
遺言と遺留分の優劣に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:遺留分を認めない遺言|弁護士が解説
遺留分を渡さなくていい方法はありますか?
遺留分は法律で保障された権利であるため、正当な請求を無条件に拒否することはできません。
ただし、以下のような方法を生前に講じておくことで、将来的に遺留分の請求を回避できる可能性があります。
- 推定相続人に遺留分の放棄を家庭裁判所で認めてもらう
- 相続人の廃除を家庭裁判所に請求する(虐待や重大な非行がある場合)
生命保険金等、相続財産に含まれにくい形に財産を移転する(遺産全体との割合によっては贈与の場合と同視され、持ち戻しが必要となる可能性あり)
実際に「遺留分を渡さなくて済む方法」は状況により異なるため、適切な法的判断と手続きの選択が不可欠です。
くわしくは以下の記事でも対策方法を解説していますので、ぜひご参照ください。
関連記事:遺留分を渡さなくていい方法はある?生前からできる6つの対策
生前贈与に対して遺留分侵害額請求されることはありますか?
はい、生前贈与も遺留分侵害額請求の対象になる場合があります。
相続開始前の贈与であっても、相続財産の価額に加算して遺留分を算定する際の「基礎財産」に含まれるケースがあります。
特に、以下のような条件に該当する場合は注意が必要です。
- 相続人に対する贈与で、相続開始前10年以内にされたもの
- 「生計の資本として」に該当するもの(親族間の扶養義務の範囲を超えるもの。生活資金援助、不動産贈与など)
このような生前贈与は、相続人間の不平等を生じさせるため、持ち戻しが認められることがあります。
遺留分の計算方法については、下記の記事でもわかりやすく解説していますので、参考にしてください。
兄弟からの遺留分請求|生前贈与を主張し大幅減額した実例
遺言などで財産を多く受け取った場合、他の相続人から「遺留分」を請求されることがありますが、言われるがまま支払う必要はありません。相手方が過去に親から援助を受けていれば、交渉で支払額を減らせる可能性があります。
“依頼人Bさんの親御さんのAさんの死後、Cさんが、Bさんに遺留分侵害額請求をしてきました。
Bさんは、実家の家業を継ぎ、献身的に両親を介護していましたが、Cさんは家のことにはほとんど関わりがありませんでした。
過去の資料を丁寧に拾い上げることで、実質的にCさんの生前贈与を裏付け、請求額の大幅減額に成功”
この事例では、
- 依頼者の記憶を頼りに「留学費用・住宅資金」等の贈与事実を掘り起こしたこと
- 被相続人Aさんの遺言書や日記・メモまで徹底的に調査・分析し、贈与の裏付けを行ったこと
により、当初の請求額から大幅な減額ができました。 理不尽な請求を受けても、過去の家族間のやり取りの中に解決のヒントが隠されていることがあります。請求を受け入れる前に弁護士へご相談ください。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。

遺留分を払うべきか迷ったら法律の専門家に相談しよう

今回は、遺留分を支払わないとどうなるのか、リスクや正しい対処法について解説しました。
- 正当な遺留分侵害額請求の場合、支払い拒否はできない
- 遺留分を支払わずに済むケースもある
- 現金がない場合は分割払い交渉をする
- 資産が不動産しかない場合は売却やローンを検討する
正当な遺留分侵害額請求であれば、支払わないという選択肢はありません。
一方で、請求されるがままに支払うこともおすすめできません。
突然、遺留分侵害額請求の内容証明が届いたら、焦ってしまう気持ちはよく分かります。
しかし、そんなときこそ落ち着いて、まずは法律の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応