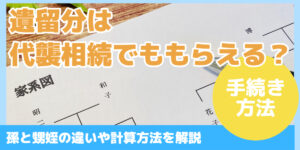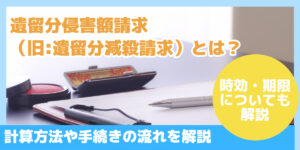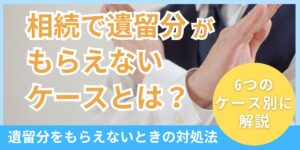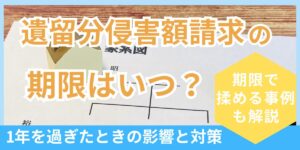【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分は相続人が子供のみの場合どうなる?子供2人のみの場合の割合や計算例・侵害額請求の手順を弁護士が解説
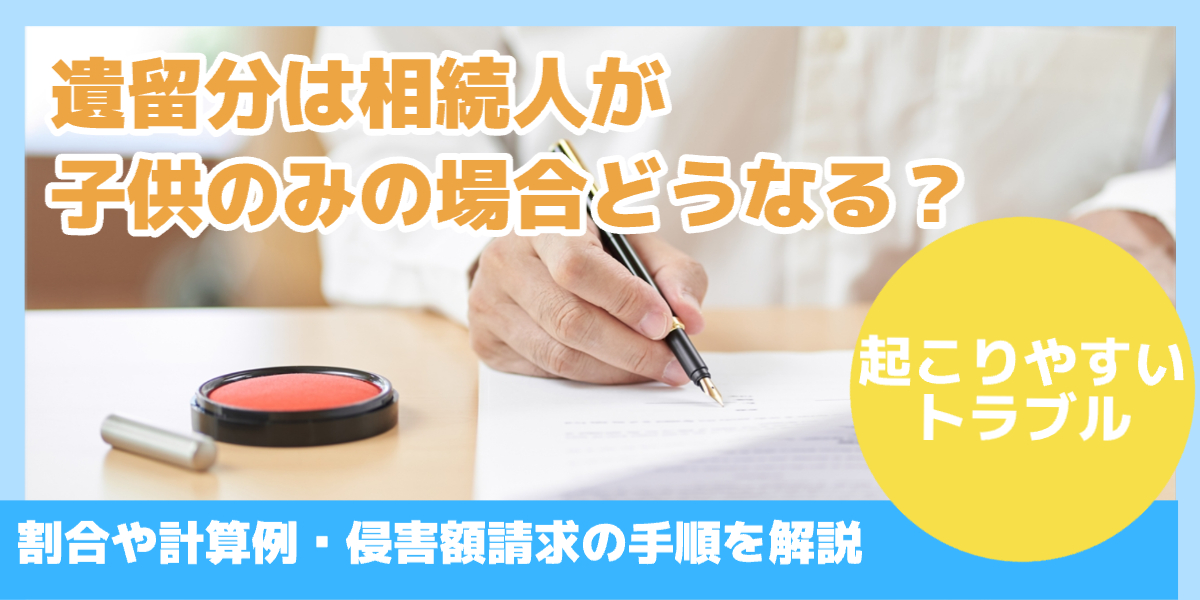
「相続人が子供のみだと遺留分はどうなるの?」
「子供1人あたりの遺留分を計算したい」
親が亡くなり、相続人が子供のみとなる場合、1人あたりの遺留分がどのくらいになるのか疑問に思っていませんか。
相続人が子供のみの場合、遺留分の割合は遺産全体の1/2です。複数人いる場合は、この1/2をさらに人数で割り、遺留分を計算します。
遺留分は法律で認められた最低限の取り分であり、もし他の相続人に相続財産が偏っている場合は「遺留分侵害額請求」をすることが考えられます。
本記事では、相続人が子供のみのケースでの遺留分の計算方法や、遺留分が侵害されていた場合の対処法を解説します。
-佐々木 一夫-
- 遺言の記載内容を確認し、自分の取り分が少ないと思ったら、遺留分を侵害されていないかをしっかりと確認すべきです。
- 遺留分が侵害されているかや、請求できる金額がいくらになるかなどは、家や土地の値段の見積もり、生前にもらったお金(贈与)、借金の有無で大きく変わります。通帳や契約書などの資料集めも必要なので、「最初の調査」から弁護士に任せると安心です。
- 足りない分を取り戻す請求には期限があります。期限切れにならないよう、また正しく請求ができるように早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分とは?子供にも認められる「遺産の最低限の取り分」
遺留分とは、法律で保障された相続財産の最低限の取り分を指します(民法1042条)。
親の遺言書に「特定の兄弟にすべての財産を譲る」と書かれていたり、一部の子どもが親から生前に高額な贈与を受けていたりする場合、自分の遺留分にあたる金銭を請求できる権利です。
遺留分を主張できるのは「兄弟姉妹を除く相続人」で、被相続人の子供にも認められています。
| 相続人の種類 | 遺留分の有無 |
|---|---|
| 子供 | あり |
| 配偶者 | あり |
| 直系尊属 | あり |
| 兄弟姉妹 | なし |
「配偶者」「子(直系卑属)」「直系尊属(父母・祖父母など)」が対象で、兄弟姉妹やその子(甥・姪)には遺留分が認められません。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫基礎知識として、遺留分が保証される範囲を正確に把握しておきましょう。
関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介
相続人が子供のみの場合の遺留分の割合|2人のみ3人のみの場合も解説
相続人が子供のみの場合、遺留分の割合は遺産全体の1/2です。複数の子がいる場合は、この1/2を人数で均等に分けます。
例えば、子が1人であれば1/2(50%)、子が2人であれば1人あたり1/4(25%)ずつです。
| 子供の数 | 遺留分 |
|---|---|
| 1人 | 遺産総額の1/2 |
| 2人 | それぞれ遺産総額の1/4 |
| 3人 | それぞれ遺産総額の1/6 |
| 4人 | それぞれ遺産総額の1/8 |



この割合は民法で定められており、遺言で減らすことはできません。人数が増減すれば個々の取り分も変わるため、事前にシミュレーションしておくと安心です。
相続人に子供がいる場合の遺留分の計算方法
相続人に配偶者と子供がいる場合と子供のみの場合とでは、遺留分の計算方法が異なります。
配偶者と子供2人のケースの計算方法
相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者の遺留分が4分の1、子供1人当たりの遺留分が8分の1になります。
相続財産3,000万円の場合、遺留分は以下のように計算します。
3,000万円×1/4=750万円(配偶者の遺留分)
3,000万円×1/8=375万円(子供1人あたりの遺留分)
子供2人のみのケースの計算方法
相続人が子供のみの場合、遺留分は「(相続財産+持戻し対象の贈与 − 債務)× 遺留分率(1/2)× 法定相続分」で求めます。
相続財産3,000万円で、相続人である子供が2人の場合、遺留分は以下のように計算します。
3,000万円×1/2=1,500万円(遺留分全体)
1,500万円×1/2=750万円(1人あたりの遺留分)
遺留分率は2分の1であるため、まず遺産総額3,000万円の半分である1,500万円が全体の遺留分額です。これを子2人で均等に分けるため、法定相続分は2分の1ですから、一人あたりの遺留分額は750万円となります。
また、相続財産に不動産が含まれる場合は、その相続人が亡くなった日の時価を算定して遺留分額に反映します。
評価方法としては、固定資産税評価額や不動産鑑定士による時価評価が用いられることが一般的です。
不動産の評価は相続人の間で争いになりやすいものです。第三者の専門家に依頼することで公平性が担保され、後々のトラブル防止につながります。



遺留分は、金銭以外の相続財産の有無によって金額が変わることがあるため、公的評価や専門家による査定を利用するのがおすすめです。
子供以外の遺留分の割合も知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:遺留分の割合と計算方法を徹底解説|生前贈与がある場合の具体例付きでわかりやすく解説
相続人が子供のみで遺留分が変動するケース
遺留分は状況によって変動します。代表的な要因は以下の通りです。
相続人の範囲・人数による変動(子供1人・2人・3人の場合)
遺留分は割合(子供のみの場合は1/2)が法律で決まっていますが、相続人の人数によって一人あたりの取り分は変わります。
例えば、子1人なら遺留分は遺産総額の1/2ですが、子2人ならそれぞれ1/4、子が3人ならそれぞれ1/6です。
さらに、相続人に被相続人の配偶者が加われば、法定相続分の割合に応じて遺留分も変動します。遺留分の1/2を被相続人の配偶者に、残り1/2を子供たちで分け合うことになるのです。



人数による違いを事前に把握しておくと、請求額の予測が立てやすくなり、無用な対立を避けられるでしょう。
生前贈与や特別受益で財産が減っている場合
被相続人が生前に行った大きな贈与は特別受益として扱われ、遺留分の計算に影響します。
例えば、子の住宅購入資金や事業資金として多額の金銭を援助していた場合、その分を相続財産に加算して計算します。
一方、生活費や教育費など通常必要とされる支出は特別受益に含まれません。
財産が減っている原因を確認するには、通帳記録や契約書などの証拠が重要です。
不明な点は放置せず、早めの調査と記録の整理を進めましょう。
関連記事:生前贈与で遺留分はどうなる?請求の流れと注意点を弁護士が解説
被相続人に債務がある場合
被相続人に借入や未払い債務がある場合、その金額は遺留分計算の基礎から差し引かれます。
例えば、相続財産が3,000万円、債務が500万円であれば、計算基礎額は2,500万円となります。
債務の確認は、借入契約書や返済履歴、金融機関からの明細などを調べることが大切です。
債務の存在を見落とすと、実際より多い遺留分を請求してしまい、返還や紛争の原因にもつながります。



請求額の見通しを建てるためには、遺留分が変動する以上の原因について、早めの調査をすることが肝要です。
関連記事:遺留分は必ずもらえるかを解説
相続人が子供のみの場合に起こりうる遺留分のトラブル
相続人が子供のみの場合、遺留分を巡ってトラブルが起こるケースは珍しくありません。特に、親が遺言書を作成していたり、特定の子供に生前贈与していたりすると、他の子供の遺留分が侵害され、トラブルに発展しやすくなります。
相続人が子供のみの場合に起こりやすいトラブルの例は以下の3つです。
本章を参考に、相続人である子供間で起こりやすい問題やその原因を理解しておきましょう。
遺言書の内容を巡る対立
親が特定の子供に「全ての遺産を相続させる」といった内容の遺言書を作成していた場合、他の子供の遺留分が侵害されます。
遺言書があっても、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、自身の最低限の取り分を確保できます。
しかし、遺産をすべて受け取った子供が遺留分の支払いを拒否したり、交渉に応じなかったりする場合もあるでしょう。



これにより兄弟姉妹間での話し合いが難航し、感情的な対立が激化するケースは少なくありません。
遺言書の内容により、遺留分が侵害されたとわかったら、早い段階で弁護士に相談し、冷静に対応を進めることが重要です。
関連記事:遺言書でできることは?できないことや書いたほうが良い場合も紹介
関連記事:遺言書の効力はどこまで?いつから効力が発生する?書き方や無効なケースも解説
生前贈与・特別受益の評価に関する争い
遺留分を計算する際は、被相続人が生前に行った贈与も対象です。
しかし、親が特定の子供に対し、結婚資金や住宅購入の援助を行っていた場合、それが「贈与」にあたるのか、遺留分算定の対象となるのかで揉めることがあります。
また、贈与の時期や金額、それが特別受益にあたるのかどうかなど、法的な判断が難しいケースもあるでしょう。
このような場合、贈与を受けていない子供は「不公平だ」と感じ、遺産分割や遺留分請求の場でトラブルに発展しやすくなります。
相続人である子供間でこのようなトラブルを避けるためにも、親の生前の贈与や援助について、他の兄弟姉妹と事前に共有しておくことが大切です。
関連記事:【弁護士監修】生前贈与は特別受益になる?認められるケースや持ち戻しの計算方法を解説
関連記事:特別受益とは?持ち戻しの計算方法や特別受益として扱われる贈与のパターンを分かりやすく解説
財産の評価・分け方での意見の食い違い
遺産の大半が不動産や非上場株式など、分割しにくい財産である場合、トラブルに発展する可能性が高まります。
遺留分の支払いは原則現金です。ただし、不動産を売却して現金化する場合は、売却価格や時期について意見が割れることも考えられます。
また、不動産の評価額を巡っても、相続人同士で意見が一致しないケースも少なくありません。特定の子供が「実家を売りたくない」と主張したり、評価額が低すぎて他の子供が反発したりする可能性があります。
公平な遺産分割を実現するためにも、事前に弁護士へ相談し、遺産の評価額を客観的に把握しておくことが重要です。



相続人が子供のみの場合の遺留分を巡るトラブルは、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分が侵害されているときの対処法
遺留分が侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足分を金銭で取り戻せます。
遺留分侵害額請求権とは、相続開始時に遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭を請求できる権利です。
遺留分侵害額請求が可能なのは、被相続人が行った遺贈や一定の生前贈与によって、相続人が受け取る遺留分が不足している場合です。
請求先は、財産を多く取得した他の相続人や第三者となります。
この請求はあくまで金銭による精算であり、物そのものを返してもらう制度ではありません。明確な法的根拠が必要なため、事前に準備を整えておきましょう。
遺留分侵害額請求の前に必要な準備
請求を行う前に、相続財産の全体像を把握することが不可欠です。
まずは不動産の登記事項証明書や預金口座の取引履歴、株式や債券などの資産明細を確認しましょう。さらに、被相続人が生前に行った贈与や、負債の有無も調査します。
これらの情報を基に遺留分額を正確に算出し、必要書類や証拠を揃えておくことで、交渉や裁判で有利に進められます。
この準備段階から弁護士に依頼すると、調査漏れや計算ミスを防ぎやすくなるでしょう。
関連記事:遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは?計算方法や時効・手続きの流れをわかりやすく解説
事前調査
まずは遺言の有無の調査と相続人調査を行います。
遺言については、公正証書遺言であれば公証役場で調べることができます。自筆遺言の場合は、公証役場で保管されている場合と自宅等で保管されている場合があります。心当たりの場所を捜索しましょう。
相続人の人数や構成によって、取り分が変わってきます。被相続人の出生から死亡までの戸籍を役所から取り付けて、相続人を調査しましょう。
財産調査
不動産は法務局で登記簿を取得し、所在地や所有者、評価額を確認します。預貯金については、金融機関に対して取引履歴の開示請求を行い、過去の入出金状況を調べます。
また、大きな現金引き出しや不自然な振込があれば、その理由を突き止めることも重要です。



証券口座や保険契約、貸付金なども忘れずにチェックしておきましょう。
生前贈与や負債の確認
生前贈与や債務は、遺留分の計算額に直接影響します。通帳の履歴、贈与契約書、借用証書などを入手して正確に把握しましょう。
これにより、公平で根拠のある請求が可能になります。
関連記事:生前贈与を非課税で行う6つの方法と契約書の書き方のポイントを徹底解説
必要書類と証拠の収集
請求の根拠を示すために必要な書類は多岐にわたります。代表的なものは、以下の通りです。
- 不動産登記事項証明書
- 預金取引明細
- 贈与契約書
- 借用証書
- 保険契約書
これらの一部は公的機関や金融機関への照会で取得できます。証拠が揃っていないと、相手方からの反論に対応できなくなるため、可能な限り早い段階で収集を始めましょう。
遺留分侵害額請求の流れ
請求には時効があります。時間に余裕があると思っていても、調査や交渉には想定以上の時間がかかるため、できるだけ早く行動することが重要です。
- 遺言の確認・相続人調査
- 財産調査
- 遺留分額の算定
- 請求先の確定
- 内容証明郵便での請求通知
- 協議・交渉
- 調停・審判による解決
相続財産や贈与の有無、債務の額を調査して遺留分額を算定したら、請求相手に内容証明郵便で正式に通知します。
相手方と協議を行い、合意できればそこで終了ですが、合意に至らなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも決着しなければ審判に移行する流れです。
関連記事:遺留分の調停について解説
関連記事:遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求の時効は、遺留分の侵害を知った日から1年以内です。また、相続開始から10年が経過すると、侵害を知らなかった場合でも権利は消滅してしまいます。



この期限を過ぎると請求ができなくなるため、権利を侵害されていると感じたら早急に調査と行動を開始しましょう。
遺留分の時効については以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
関連記事:遺留分侵害額請求の期限はいつまで?2つの時効や注意点を弁護士が解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分のトラブルで弁護士に相談する4つのメリット
遺留分を巡るトラブルは、相続人同士の感情的な対立や複雑な手続きが絡み合うことが多く、個人での解決には限界があります。
こうした問題に直面した際は、相続に強い弁護士へ相談しましょう。弁護士に依頼するメリットは主に以下の4つです。
本章を参考に、ご自身の相続で弁護士に依頼すべきを検討してみてください。
関連記事:相続を弁護士に任せるメリット・デメリットとは?後悔しない弁護士の選び方も解説
相続人関係調査・財産調査・証拠収集を代理でしてもらえる
遺留分侵害額の請求をおこなうには、まず正確な相続人関係と遺産の全体像を把握する必要があります。
しかし、個人で役所や金融機関、法務局などに問い合わせて、故人の相続関係や財産状況を漏れなく調査するのは非常に手間がかかる作業です。
弁護士は金融機関や法務局への照会、資料の取得などを代理で行ってくれます。
不動産登記事項証明書や預金取引明細、生前贈与の有無などを漏れなく調査できるため、請求の正当性を裏付けやすくなるでしょう。



個人で行うよりも効率的で、証拠の抜けや漏れを防げます。
感情的な対立を避けられる
遺留分を請求する際は、相手方との交渉が不可欠です。しかし、相続人同士で直接やり取りをすると、感情的な対立が激化し、話し合いがこじれてしまうことも少なくありません。
弁護士が代理人として交渉にあたることで、相続人同士が直接向き合うことを避けられるのがメリットです。
また、法的な根拠に基づいた冷静かつ論理的な話し合いが可能になるため、円満な解決につながりやすくなるでしょう。
交渉・内容証明郵便・調停対応・訴訟対応まで一括で任せられる
遺留分に関する交渉は、内容証明郵便の送付から始まり、話し合いがまとまらない場合は調停、さらには裁判へと移行することもあります。
弁護士には遺留分の請求から交渉、調停や訴訟まで一貫して依頼可能です。手続きを段階ごとに別々の専門家に頼む必要がなく、時間や手間を大幅に削減できます。
また、弁護士は交渉から調停、訴訟に至るまで、状況に応じて最適な戦略を立て、一貫した対応を取ってくれます。
これにより、手続きがスムーズに進み、より良い解決を目指せるのもメリットです。
関連記事:遺留分請求に強い弁護士に関する記事を見る
期限を過ぎないよう進行管理ができる
遺留分侵害額の請求には「相続の開始と遺留分を侵害する贈与があったことを知ってから1年」という時効が定められています。
複雑な手続きや慣れない書類作成に追われるうちに、この重要な期限をうっかり過ぎてしまうリスクは少なくありません。
弁護士は時効や手続きの期限を正確に把握し、計画的に進めてくれます。
証拠収集や書面作成のスケジュールを管理してもらえるため、期限切れによる遺留分請求権の権利喪失を防ぎ、安心して手続きを進められるでしょう。



遺留分侵害額請求を正確に進めるためには、専門知識が不可欠です。他にも、感情的対立を避けられる、膨大な手間を削減できる等、弁護士に依頼するメリットは高いと言えます。
関連記事:遺留分侵害額請求の期限について解説
関連記事:相続トラブルで後悔しない弁護士の選び方とは?口コミなど確認すべきポイントを解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分に関するよくある質問
相続人が子供のみで、遺言書があっても遺留分請求は可能ですか?
遺言書があっても、遺留分侵害額請求は可能です。
遺留分は民法で保障された権利であり、遺言書によって奪うことはできません。
例えば「全財産を長男に相続させる」と記載された遺言があっても、他の子供や配偶者は遺留分を請求できます。
遺言の内容が遺留分を侵害しているかどうかを判断するには、財産の評価や贈与の有無も含めて計算する必要があります。
遺言書と遺留分の関係については、以下の記事を参考にしてください。
遺留分侵害額請求は個人でもできますか?
法律上は個人でも遺留分侵害額請求が可能です。内容証明郵便を送付し、協議や調停を進めることで請求手続きを進められます。
しかし実務では、財産調査や評価方法の選定、証拠収集など高度な知識が必要となる場面が多くあります。
不動産や生前贈与が絡む場合は特に計算が複雑になるため、弁護士など専門家への依頼を検討するのがおすすめです。
相続人が配偶者と子供2人のみの場合、遺留分はどうなりますか?
相続人が配偶者と子供2人のみの場合、遺留分の全額は遺産全体の1/2です。さらにそこから法定相続分によって分けられます。
遺産全体から見ると、配偶者は1/4、子供はそれぞれ1/8が遺留分として保証されます。
例えば遺産が4,000万円であれば、配偶者の遺留分は1,000万円、子供はそれぞれ500万円です。
続柄や人数によって割合が変わるため、事前にシミュレーションしておくと安心できるでしょう。
関連記事:遺留分侵害額請求の期限に関する記事を見る
まとめ|相続人である子供同士の遺留分トラブルは弁護士に相談しよう
相続人が子供のみのケースにおいて、遺留分の割合は遺産全体の1/2です。相続人である子供が複数いる場合は、1/2を人数で割って計算します。
もし自分の遺留分が侵害されている場合、期限内に「遺留分侵害額請求」を行うことで、遺留分にあたる金銭をもらえます。
遺留分は民法で保障された権利ですが、適切に行使するためには迅速かつ正確な対応が欠かせません。
「計算方法がわからない」「財産内容が不明」「相手が協力しない」などの不安がある場合は、早めに相続に詳しい弁護士へ相談し、円滑かつ安心できる解決を目指しましょう。



「計算方法がわからない」「財産内容が不明」「相手が協力しない」などの不安がある場合は、早めに相続に詳しい弁護士へ相談し、円滑かつ安心できる解決を目指しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応