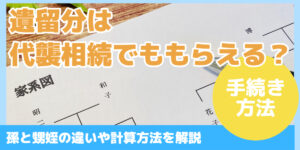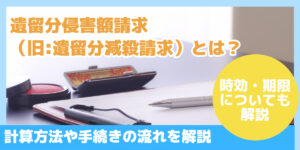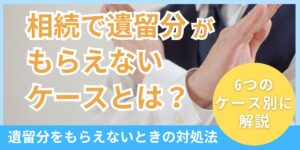【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産が不動産しかない場合の遺留分はどうなる?現金での支払い可否や請求の流れを弁護士が解説

「遺産は不動産しかないのに遺留分をお金でもらうことは可能か?」
「遺留分の額や遺留分侵害額はどのように決めるのか?」
遺産が不動産(家・土地)しかない方は、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。
結論として、遺産が不動産だけでも、遺留分侵害があれば現金の支払いを請求できます。しかし、相手が現金を持っていない場合、遺留分を支払ってもらうことは簡単ではありません。
本記事では、遺留分が不動産しかない場合の遺留分の扱いや評価方法、請求方法、注意点などを解説します。
遺産が不動産しかない場合の遺留分で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分とは

まずは「遺留分とは何か」について、以下の3点から詳しく解説します。
民法上認められた最低限の遺産の取り分
遺留分は、遺言や生前贈与・遺贈があっても侵害できない相続分です。
遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に、民法上認められた最低限の遺産の取り分のことです(民法1042条)。
遺言などにより遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることにより、遺留分を取り戻すことができます(民法1046条1項)。
たとえば、子2人が法定相続人の場合に、全財産を子だけに相続させるとの遺言があっても、もう一人の法定相続人は、遺留分として1/4(法定相続分(1/2)×遺留分(1/2))を主張できるのです。
遺留分の割合は、次の通り定められています(民法1042条1項)。
- 直系尊属(親や祖父母など)のみが相続人である場合:遺留分算定対象財産の1/3
- それ以外の場合:遺留分算定対象財産の1/2
※遺留分算定対象財産=遺産+贈与財産-債務(民法1043条)

遺留分があるのは兄弟姉妹以外の法定相続人
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です(民法1042条1項)。
(遺留分の帰属及びその割合) 民法 第千四十二条 一 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。引用:民法|第1042条1項
具体的には、次の相続人が遺留分権利者となります。
- 配偶者(常に遺留分権利者)
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(子と子の代襲相続人がいない場
関連記事:遺留分は相続人が子供のみの場合どうなる?子供2人のみの場合の割合や計算例・侵害額請求の手順を弁護士が解説
遺留分は遺言などにより侵害されることがある
遺留分は、遺言や贈与などによって侵害されることがあります。
遺留分が侵害されている状態とは、民法で認められている遺留分より、相続によって取得する財産が少ない状態のことです。
遺言で法定相続分と大きく異なる相続分の指定があると、法定相続分より少ない財産しか相続できない、あるいは相続分がない場合もあり得ます。
たとえば、500万円の遺留分がある相続人が、遺言で300万円分しか相続分の指定を受けなかった場合、200万円分の遺留分が侵害されるのです。

遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使すれば権利を回復できます。
関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを解説
遺産が不動産しかない場合に遺留分は現金でもらえる?


遺産が不動産しかない場合に遺留分を金銭でもらえるかは、2019年7月施行の民法改正の前か後かで違います。
2019年7月1日以降の相続の場合|現金での支払いが可能
遺産が不動産しかない場合でも、不動産価額のうち遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けることができます。
従来は共有による移転登記が原則で金銭を受け取ることはできませんでしたが、金銭的解決を望む当事者の実情に合わせ、民法改正により金銭請求を可能としたのです(民法1046条)。
たとえば、相続人が子2人(息子・娘)、遺産が不動産しかない場合(評価額1億円)を考えてみましょう。
息子が不動産を相続する旨の遺言があっても、相続人である娘は遺留分(1/2×1/2=1/4)があり、遺留分侵害額(2,500万円)に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺留分については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。


2019年6月30日までの相続の場合|持分移転登記の請求が原則(現物分割)
遺留分は原則として金銭ではなく、共有持分をもって清算することとされていました(遺留分減殺請求)。
遺産が不動産しかないときは、遺留分に相当する共有持分の移転登記を請求することが原則だったのです。
しかし、移転登記を請求された側が、不動産を共有にしたくない場合もあるでしょう。
その場合、例外的に、遺留分権利者に遺留分相当の金銭を支払えば、移転登記請求を免れられます。
一旦共有となった不動産は、共有物分割調停や訴訟により共有関係を解消することや、不動産全体を売却して持分に応じて代金を配分する方法もありますが、手間や期間がかかるなどの煩わしさがあります。
遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額の算定方法【2ステップ】


遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額の算定は、次の手順で行います。
遺留分に相当した金銭を受け取れるよう、具体的な評価方法を把握しましょう。
ステップ1.不動産価額の時価を評価する
遺産が不動産だけの場合、相続が発生したときの不動産の時価を評価しなければなりません。
不動産の評価方法はいくつかあり、方法によって評価額が変わります。
どの評価方法を使うかについて、当事者間で協議が必要です。
| 主な評価方法 | |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 自治体が課税のために設定した価額。地価公示価格の70%程度 |
| 相続税路線価 | 国税庁が公表している土地の1㎡あたり価格。公示価格の80%程度 |
| 地価公示価格 | 国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日に公示する価格。不動産取引の指標となる正常な価格 |
| 取引事例価格 | 実際に売買が行われた事例価格。個別事情によって大きく異なる |
| 不動産鑑定評価額 | 不動産鑑定士が鑑定評価した価格。原則として正常価格 |
参考:国土交通省|不動産鑑定評価基準
ステップ2.遺留分相当額を算定する
不動産(遺産)の価格を算定した後は、遺留分割合を乗じて遺留分相当額を算定します。
遺留分の額=遺産総額×遺留分の割合
たとえば、遺産総額が5,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合、遺留分の計算方法と金額は以下の通りです(民法1042条1項、2項)。
- 配偶者の遺留分:5,000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1,250万円
- 子1人の遺留分:5,000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(1人分)=625万円



遺留分権利者が請求を行う段階では、請求額を具体的に明示する必要はありません。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産が不動産しかない場合の遺留分の支払方法


遺留分は金銭支払いが原則ですが、遺産が不動産だけの場合、支払う資金をすぐに準備できないこともあるでしょう。
手元に資金がない場合は、当事者が合意すれば不動産を分ける(持分共有又は現物分割)ことも可能です。
どの方法によるかは、遺留分権利者と支払い義務者(請求された人)で協議して確認する必要があります。
| 遺留分の支払方法 | ||
|---|---|---|
| 金銭を支払う(原則) | 代償分割 | 請求された人が不動産を残しておきたい場合、預貯金等があれば自分の財産から遺留分相当額を支払う |
| 換価分割 | 請求された人が不動産を保有する必要がなく、遺留分を支払う資産がない場合は、不動産を売却して代償を支払う | |
| 延納・分割払い | 遺留分侵害額をすぐに支払えない場合は、遺留分権利者の同意を得て支払期日延期や分割払いにする 裁判所に支払期限延長請求も可(民法1047条5項) | |
| 不動産を分ける | 共有持分 | 請求された人と遺留分権利者との持分共有にする |
| 現物分割 (分筆) | 土地だけであれば、遺留分相当を分筆する | |
遺産が不動産しかない場合の遺留分の4つの注意点
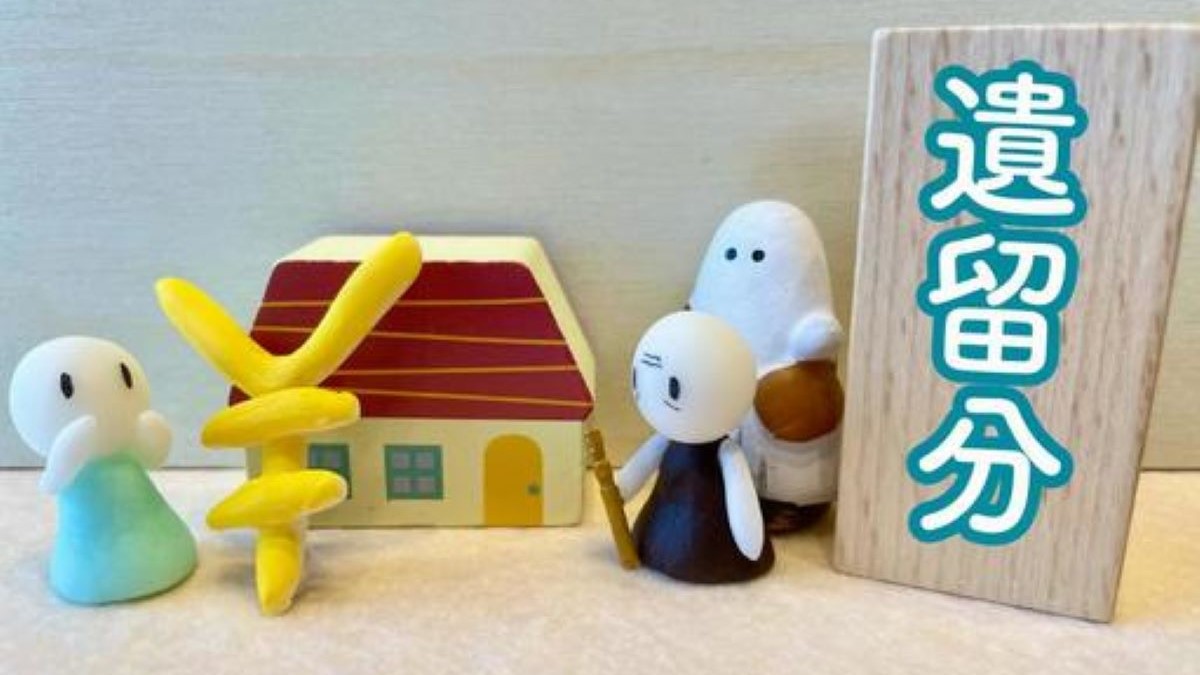
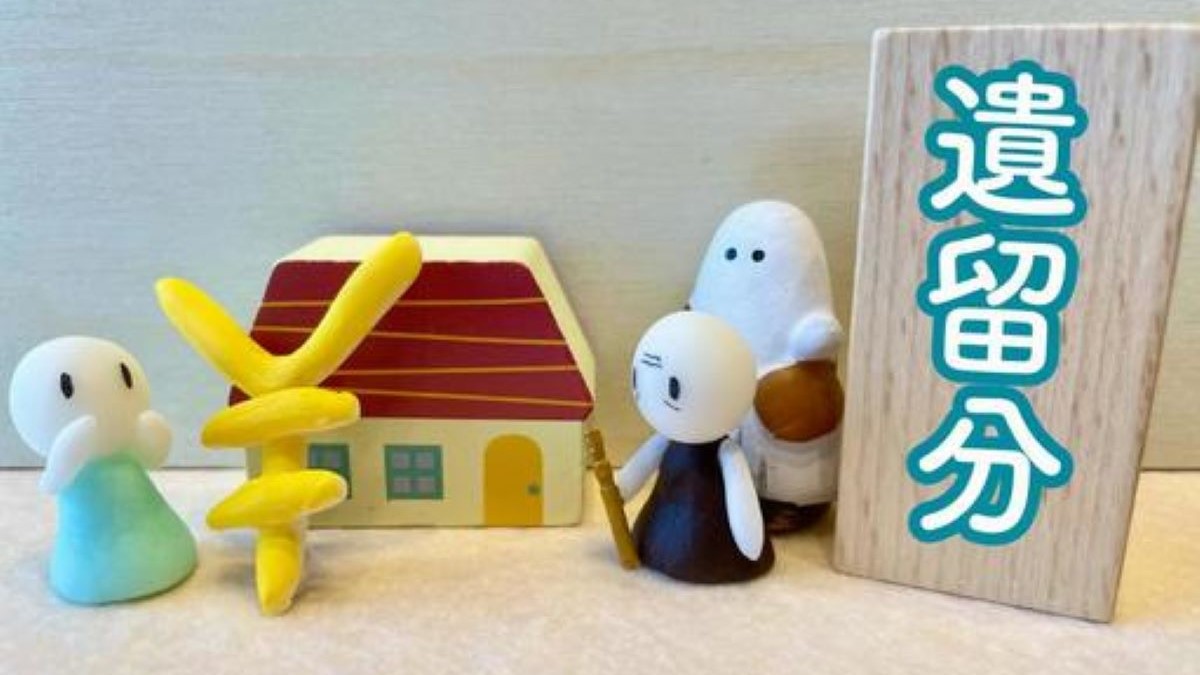
不動産は分割が難しい資産のため、金銭と違い特別の手続きが必要になる場合や問題が生じることもあります。
特に注意すべき点を紹介します。
相手が同意すれば不動産の現物分割や持分共有にできる
手元に現金がない場合は、相手が合意すれば現物での支払いも可能です。
遺留分に相当する共有持分を提供する方法で支払うこともできます。
遺留分侵害額請求の調停の場合も、当事者が話し合いで解決するため、相手が合意すれば不動産の現物分割・持分共有も可能です。
しかし、遺留分侵害額訴訟では、裁判所は金銭支払い命令しか出せないため、不動産の現物分割や共有はできません。
現物分割や共有を希望するのであれば、訴訟になったとしても、最終的には和解で解決することが求められます。
不動産を共有にするのはトラブルになるリスクがあるため避けた方がよい
遺留分侵害額について金銭を払わずに、不動産を共有にする方法もありますが、不動産の共有はトラブルになるリスクがあり推奨できません。
たとえば、次のようなトラブルが起こるリスクがあります。
- 売却したくても共有者の同意が得られない
- 管理費や税金の負担割合でもめる
- 共有者の1人が不動産を独占的に使用する
- 共有者が所在不明になり管理や処分に困る
- 共有者に相続が発生して共有者の数が増える
不動産の処分は共有者全員の同意が必要なため、売却を希望しても他の共有者の同意を得られなければ売却できません。
タイムリーに処分できない不動産の共有は、トラブルになる可能性が高いです。
また、不動産は持っているだけで、固定資産税等の税金や維持管理費が発生します。
トラブルや費用負担を避けるため共有状態を解消しようとしても、共有者同士の話が整わなければ、共有物分割訴訟を提起しなければならないのも面倒なことです。
不動産の評価額を明確にする
不動産の評価方法・評価額は、相続人の間で揉めやすいので注意が必要です。
不動産の評価額によって遺留分の額は変わるため、不動産の評価額を明確にする必要があります。
遺留分を請求する相続人は高く評価し、請求を受ける人は低く評価する傾向があります。
たとえば、親が亡くなり、子2人(長男A・次男B)が相続人、遺産は親が住んでいた不動産(土地と建物)だけで、遺言で長男Aが不動産を相続したケースを見てみましょう。
不動産の評価によって、次のように遺留分に違いが出てきます。
- 高めに評価した場合:取引事例や地価公示価格ベースで8,000万円
Bの遺留分=不動産価格×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=2,000万円
- 低めに評価した場合:固定資産税評価額を基に5,600万円(公示価格の7割程度)
Bの遺留分=不動産価格×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1,400万円
遺留分は不動産の評価額によって大きく変動します。
評価方法について合意できない場合は、調停や訴訟により決定することになります。
不動産しかない場合でも遺言で遺留分を奪うことはできない
「○○の遺留分を認めない」などの遺言があっても、一定範囲の相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言は被相続人の意思として基本尊重されますが、遺留分は不公平な遺産相続を防ぐことを目的とするもので、遺留分を認めないことはできないのです。
ただし、相続人が相続時前10年以内に生前贈与を受けていた場合は、遺留分の請求は可能ですが、遺留分侵害が認められないケースもあります(民法1044条1項・3項)。
遺言の趣旨が、すでに生前贈与を行っているため遺留分を認めないという場合は、生前贈与の内容によっては、遺留分侵害額請求権に制限がかかる可能性があるのです。



遺留分請求できるかどうかは複雑な判断になるため、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
不動産の遺留分侵害額の請求の流れ
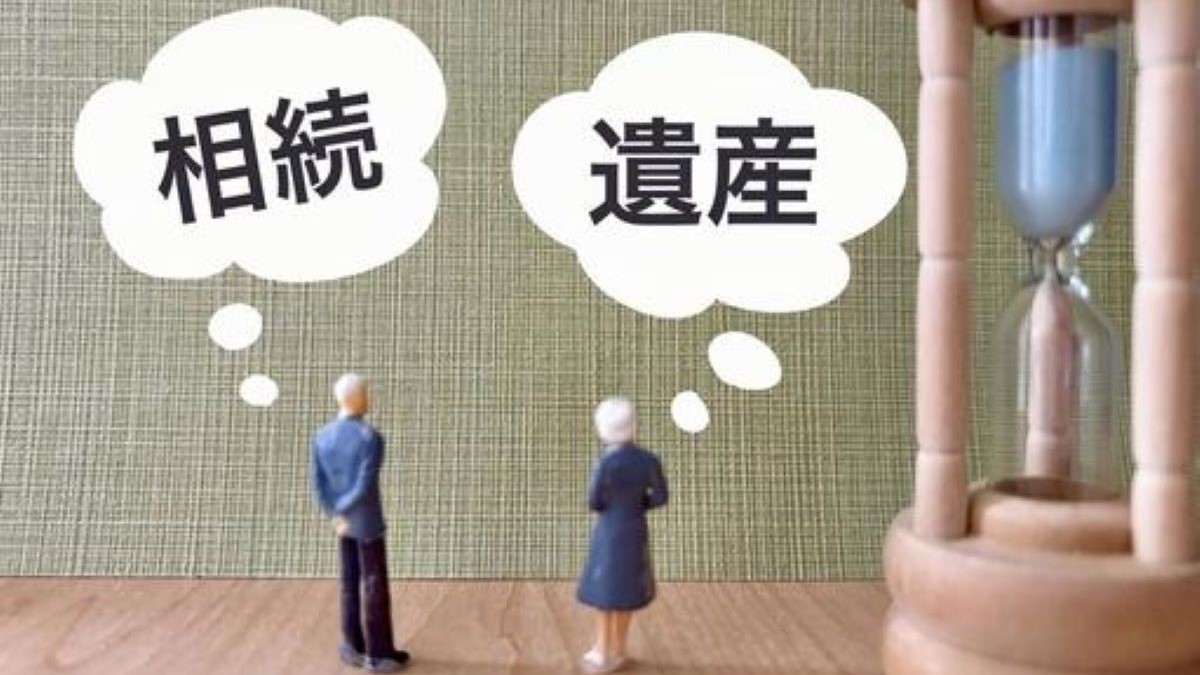
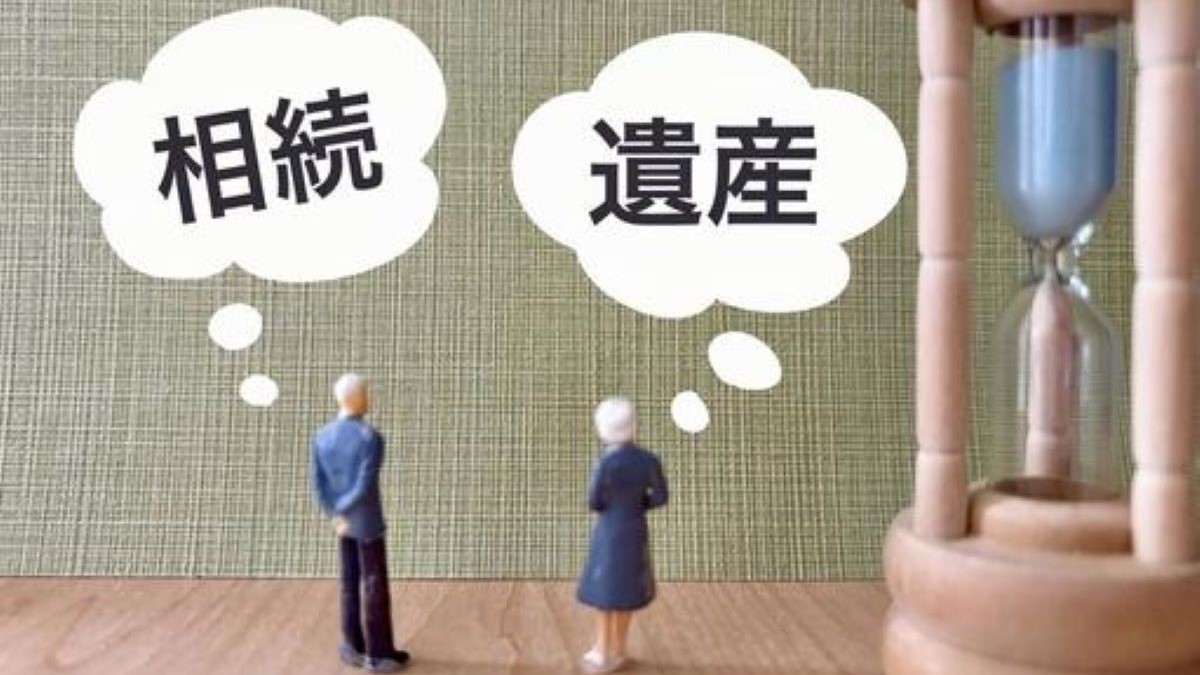
不動産の遺留分侵害額の請求の流れは、おおむね次のとおりです。
- 相続人同士で話し合う:
不動産の場合は遺留分の金額も大きくなるため、相続人との話し合いが重要。
相続人との関係が良好で円満な解決を目指すのであれば、まず口頭で遺留分を請求し話し合った方がよい。 - 遺留分侵害額請求書を送る(内容証明郵便):
遺留分は相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈を知った時から1年経過すると、請求できなくなる(民法1048条)。
遺留分請求を行った証拠を残すため、話し合いをしている間でも、早めに遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で送付する。 - 遺留分侵害額請求調停を申し立てる:
話し合いがまとまらない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てる。
調停では、調停委員が双方の主張を聞き、当事者間での交渉を仲介してくれるため、当事者が歩み寄りやすい場合も多い。 - 遺留分侵害額請求訴訟を提起する:
調停がまとまらない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起する。
訴訟では、遺留分侵害の事実を立証する必要がある。専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することがおすすめ。
不動産の遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット


遺留分の扱いは、話し合いで円満に解決できればベストです。
しかし、遺産が不動産しかない場合、評価額の判断など、遺留分の計算方法や、請求の具体的方法・支払い方は複雑で、妥当かどうかは専門的な知識・判断が求められます。
話し合いがまとまらず、調停や訴訟に移行した場合は、さらに相当の時間と労力がかかることになります。
遺留分に関する問題を円滑に解決するためには、請求する人も・請求された人も速やかに弁護士に相談した方がよいです。
不動産の遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する具体的なメリットは次の通りです。
- 相手への対応を任せられる:
遺産を巡る話し合いは感情的な言い合いになり、まとまらないことも多いが、弁護士が入ることで相手の納得も得られやすく、問題解決がしやすくなる。 - 遺留分を正確に算出して請求できる:
遺留分の計算は難しいが、弁護士に依頼すれば、専門知識を駆使して正確に計算できるため、取りこぼしなく請求できる。 - 調停や訴訟にも適切かつ迅速に対応できる:
話し合いがまとまらないときは、迅速に調停や訴訟に移行し、法的知識を活用し適切かつ迅速に対応してもらえる。
遺産が不動産しかないときの遺留分についてよくある質問
公正証書遺言があっても遺留分の請求はできますか?
公正証書遺言が有効でも、配偶者・子(代襲含む)・直系尊属の遺留分は守られます。
これらの相続人は、遺言や生前贈与で取り分が減らされていれば、遺留分侵害額請求(お金での請求)が可能です(民法1042条、民法1046条)。
遺産が不動産しかない場合でも、不動産の評価額を基準に金銭で清算するのが原則です。交渉では、支払方法(分割・期限延長)や担保提供などの条件面も検討できます(民法1047条)。
請求には短い時効(知ってから1年/開始から10年)があるため、早めに証拠整理と方針決定を行いましょう(民法1048条)。
遺留分がもらえないケースはありますか?
あります。代表例は次のとおりです。
境界事例が多く、評価方法の選択や贈与の算入で結論が変わることがあります。早期に専門家へご相談ください。
遺留分侵害額請求を無視されたらどう対応すべきですか?
無視は放置した側にも不利益を拡大させます。請求側は次の順で着実に手続を前進させましょう。
不動産しかない事案は、換価分割・融資・共同売却など資金化の選択肢を並行検討すると解決が進みやすくなります。
早めに証拠(評価資料・贈与関係・負債)を揃え、実現可能なプランで交渉しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
住み慣れた自宅からの「追い出し」を阻止|処分禁止仮処分で解決を導いた実例
相続後、相続人が他の相続人から退去を迫られるなど、不動産を巡る深刻な対立が生じることがあります。相手方が強硬な手段に出ようとしている場合でも、適切な法的措置を講じることで権利を守り、有利な条件で解決できる可能性があります。
“依頼者が居住している不動産について、他の相続人が追い出しを画策している事案でした。不動産が勝手に処分されると住む場所を失う恐れがあったため、弁護士が迅速に『処分禁止仮処分』の手続きを行いました。”
この事例では、
- 被相続人Aさんの遺言書や日記・メモまで徹底的に調査・分析し、贈与の裏付けを行ったこと
- 遺言の信頼性や不動産の時価、占有権限など多角的に法的主張を構築し、感情的対立ではなく戦略的に問題解決に導いたこと
により、一方的に追い出されることなく、正当な権利としての金銭を確保する形で解決に至りました。
不動産の処分や立ち退きを巡るトラブルは緊急性を要します。相手方の動きに不安を感じたら、手遅れになる前に弁護士へご相談ください。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。
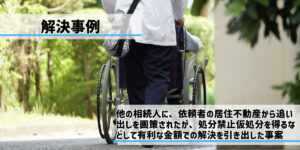
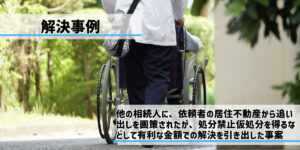
まとめ|遺産が不動産しかないときの遺留分トラブルは弁護士に相談しよう
遺産が不動産しかない場合の遺留分についてまとめます。
- 遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に民法上認められた最低限の遺産の取り分
- 不動産しかない場合、従来は現物分割が原則だったが、現在は金銭支払いが原則
- 不動産の評価方法によって遺留分侵害額は大きく変わる可能性がある
- 遺産が不動産しかない場合、双方が合意すれば持分共有や現物分割も可能だが、共有にするのは避けた方がよい
- 不動産の遺留分侵害額の請求の流れは、協議、調停、訴訟となるが、弁護士に依頼すれば適切かつ迅速な解決が期待できる
遺留分の計算や請求は、不動産や法律に関する専門的な知識が必要です。
相続は、面倒な手続きが多く、厄介なトラブルも起こりやすいものですが、スムーズに解決したいものです



相続について、わからないことやもめごとがあるときは、相続問題に詳しい弁護士に早めに相談しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応