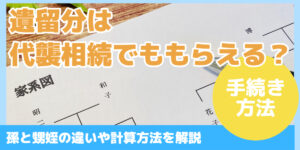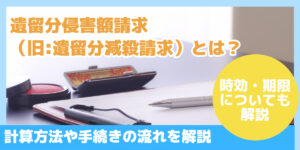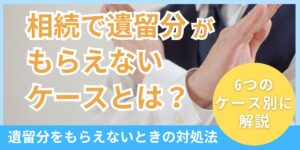【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分侵害額請求の時効は時効は5年?10年?起算点や時効中断の方法も解説【弁護士監修】
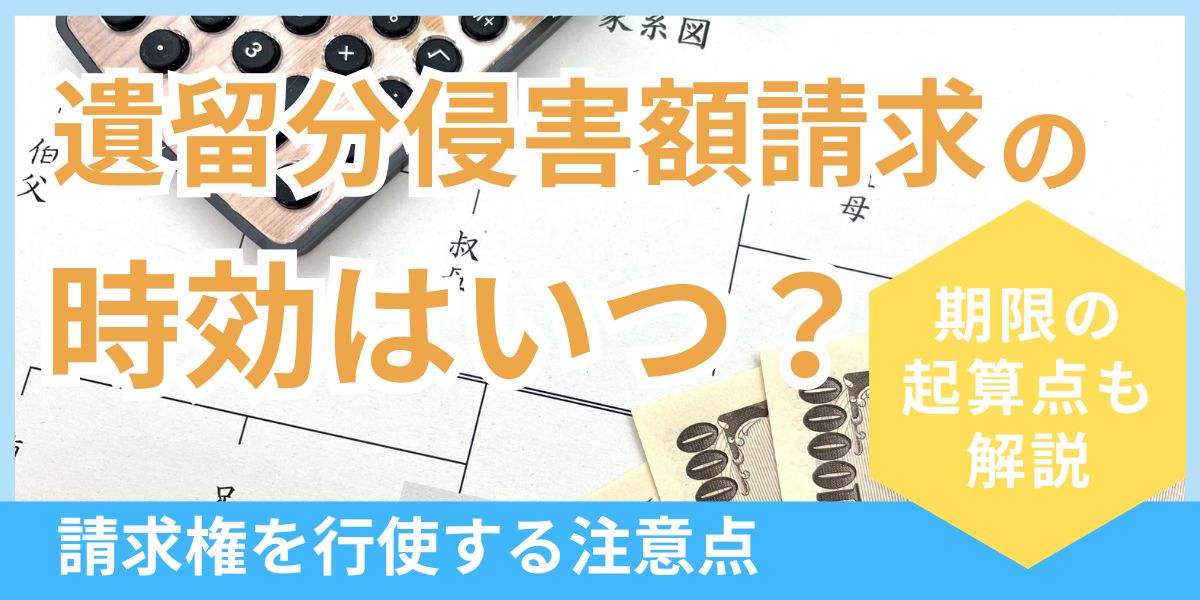
「遺留分侵害請求をしたいけれど、時効が過ぎていたらどうしよう…」と不安に感じていませんか?
遺留分侵害額請求は、時効によって権利が失われるリスクがあります。しかし、時効の期限や進行が始まる起算点などを正しく理解すれば、侵害された遺留分を消滅時効にかかることなく取り返せるのです。

本記事では、遺留分侵害額請求に関する時効の仕組みをわかりやすく解説し、具体的な対応策をお伝えします。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分侵害額請求の基礎知識
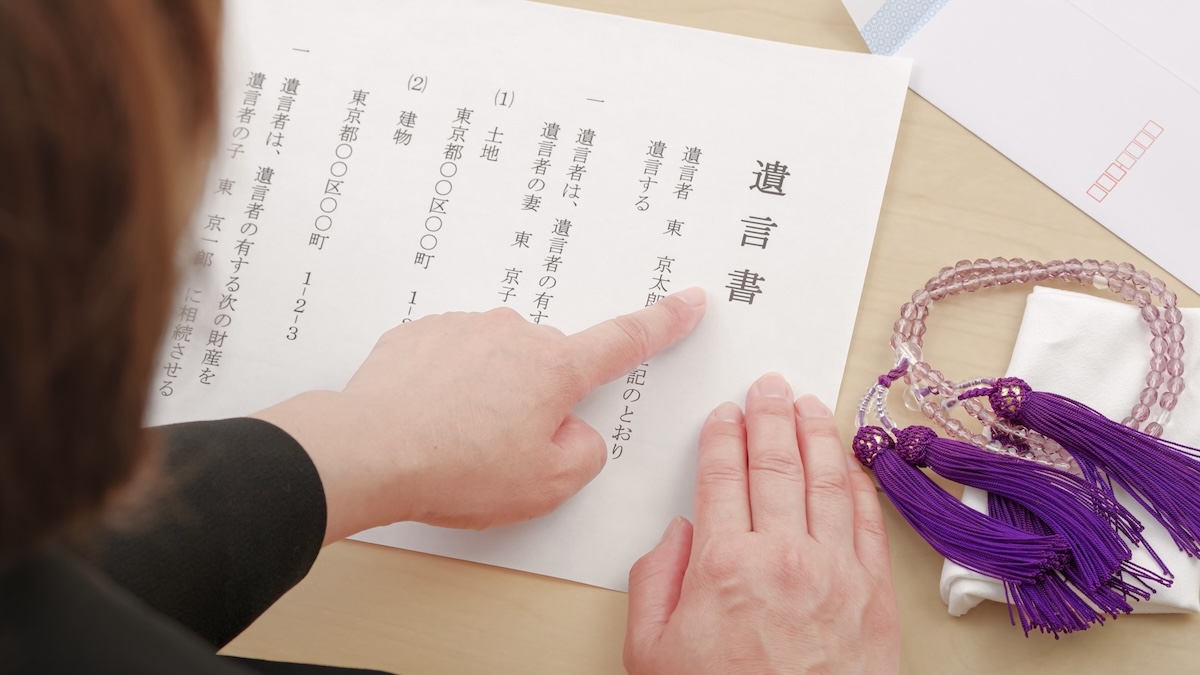
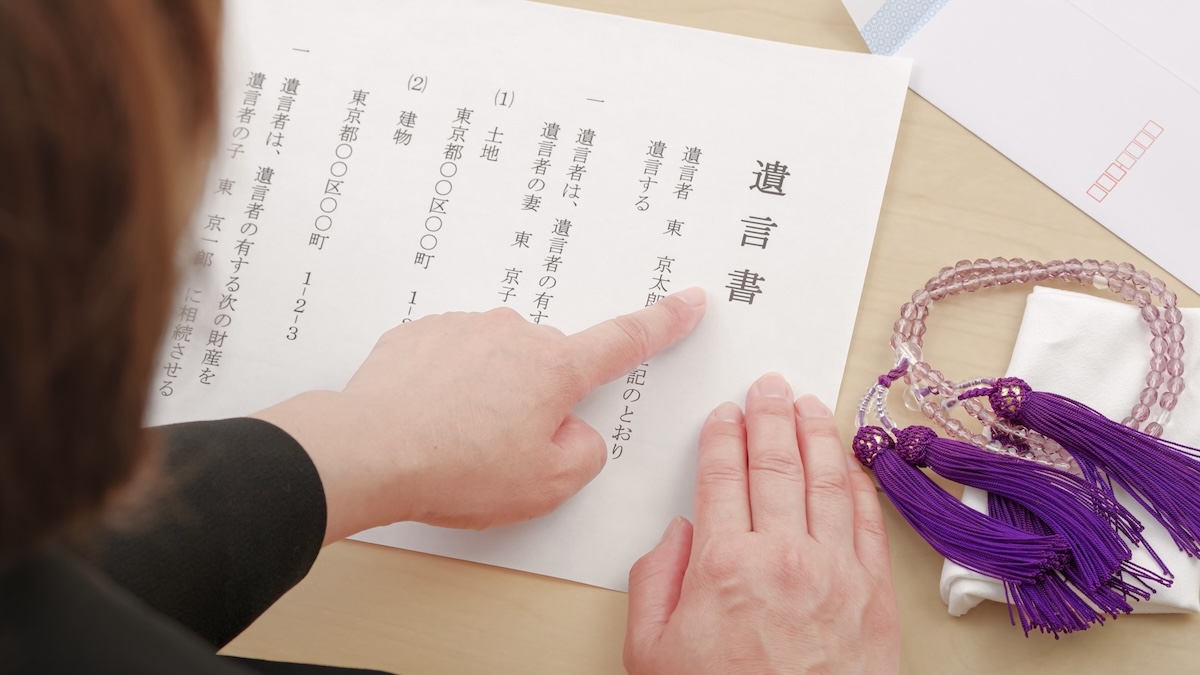
遺留分侵害額請求とは、民法で定められた遺留分を下回る割合しか相続を受けられないときに、不足分の金銭を請求できる権利です。
法定相続人となる配偶者や子ども(代襲相続人を含む)、直系尊属には、相続財産の一定割合が遺留分として保障されています。
そのため、被相続人の遺言や生前贈与によってこの権利が侵害された場合、救済措置として「遺留分侵害額請求」を行使できます。
遺留分とは
遺留分は遺産相続で、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属に対して法律で保障された最低限の取り分です。
被相続人は遺言や生前贈与で財産を自由に処分できますが、この遺留分により一定の制限が設けられています。
相続財産に対する遺留分の割合は、以下の通りです。
| 法定相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 子のみ | 子:1/2 | 複数いる場合は人数で等分 |
| 配偶者と子 | 配偶者:1/4、子:1/4 | 子が複数いる場合は人数で等分 |
| 直系尊属のみ | 直系尊属:1/3 | 父母がいる場合には祖父母には遺留分の権利はない |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:1/3、直系尊属:1/6 | 直系尊属は同順位で等分 |
| 配偶者のみ | 配偶者:1/2 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/8、兄弟姉妹:なし | – |
| 兄弟姉妹のみ | なし | – |
遺留分は、遺留分権利者の有無や組み合わせによって、保障される割合が定められています。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は民法第1046条に定められた制度で、遺留分権利者が遺言や生前贈与により遺留分が侵害された場合、受遺者や受贈者に不足分の金銭支払いを請求できる権利です。
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
出典:e-Govポータル|民法
たとえば、被相続人が遺言で財産の大部分を長男に相続させ、配偶者の遺留分が侵害されたケースでは、配偶者は受遺者である長男に遺留分侵害額の支払いを請求できます。
また、被相続人の生前贈与により遺留分が侵害された場合、受贈者に対しても請求が可能です。
遺留分侵害額請求については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【遺留分侵害額請求をわかりやすく解説】計算方法・請求のやり方・注意点
遺留分侵害額請求には時効がある


遺留分侵害額請求には、3つの期間制限があります。
【時効】遺留分の侵害を知った時から1年
遺留分を請求できる権利は民法第1048条の規定により、次の2つの事実を知った時から1年で時効にかかります。
- 相続が開始したこと
- 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
出典:e-Govポータル|民法
たとえば、被相続人の死亡時には遺言の存在を知らず、3カ月後に遺留分を侵害する内容の遺言が見つかった場合、その発見時点から1年以内に請求する必要があります。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
【除斥期間】相続が開始されてから10年
遺留分侵害額の請求には、相続開始(被相続人の死亡時)から10年という除斥期間が設けられています。
この期間が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
10年の除斥期間は、以下の場合でも例外はありません。
- 遺留分権利者が相続開始を知らなかった場合
- 遺留分侵害の事実を知らなかった場合
相続開始から10年が経過すると、遺留分権利者にやむをえない事情があったとしても、権利は行使できなくなります。
【債権消滅時効】遺留分侵害額請求権を行使してから5年
遺留分侵害額請求権は2020年4月の法改正で、遺産そのものを取り戻す権利ではなく、金銭を請求する権利に変わりました。
この金銭債権には、民法第166条第1項に基づく債権時効の適用を受けます。
遺留分侵害額請求権の時効期間は、権利の行使が改正民法施行日の前後で異なります。
具体的な時効期間は、以下の通りです。
- 2020年4月1日以降に請求権を行使した場合:5年の時効期間
- 2020年3月31日以前に請求権を行使していた場合:10年の時効期間
遺留分侵害額請求権を行使した後は、上記の期間内に請求額の支払いを受けるか、時効の更新手続を取る必要があります。
債権の消滅時効は請求権の行使により、金銭債権が確定した時点から進行し、裁判上の請求や侵害した側の債務の承認により更新されます。
遺留分侵害額請求については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:【遺留分侵害額請求の基礎知識】対象となる財産・手続きの方法・注意点
遺留分侵害請求の時効の起算点


遺留分侵害額請求の消滅時効の起算点は、次の通りです。
消滅時効前に遺留分侵害額請求を行使するには、時効までの起算点を明確に把握しましょう。
相続の開始時
相続は被相続人の死亡と同時に開始されます。相続の開始とは、被相続人の死亡により、その財産や権利義務が相続人に継承されることです。
相続開始日の具体的な基準は、以下の通りです。
| 自然死亡の場合 | 死亡診断書に記載された日付が基準 |
|---|---|
| 認定死亡の場合 | 戸籍に記載された死亡日が相続開始日 ※事故や災害で死亡したことは確実であるが、遺体が見つからない場合などが該当 |
| 普通失踪の場合 | 生死不明となってから7年が経過した日(民法第30条1項) |
| 特別失踪の場合 | 危難(戦争・船舶遭難など)が去った日(民法第31条) |
相続開始日は、遺留分侵害額請求権の行使期限の起算点となるため、正確に把握する必要があります。
遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時
遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときとは、遺留分権利者が自身の遺留分が侵害されている事実を具体的に認識した時点を指します。
たとえば、以下のような場合が該当します。
- 遺言書の開示により、他の相続人への遺贈が自身の遺留分を侵害していることを知った時点
- 被相続人が他の相続人に対して行った生前贈与や死因贈与により、自身の遺留分が侵害されていることを把握した時点
なお、時効は単に贈与や遺贈の存在を知っただけではスタートせず、その贈与や遺贈により自身の遺留分が侵害されていることを具体的に認識した時点から時効が進行します。
ただし、遺留分侵害を知った日の証明が難しいため、被相続人の死亡から1年以内に権利を行使するのが安全です。
お早めに専門家にご相談ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分侵害額請求の時効を中断する方法


遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分侵害を知った日から進行を始めます。
時効を止めるには、以下の方法があります。
内容証明郵便で遺留分侵害額請求を意思表示する
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されている相続人が、侵害者に対して請求の意思を明確に伝えることで行使できます。
意思表示の方法に法律上の制限はありませんが、後のトラブルを防ぐためにも、内容証明郵便の利用が推奨されます。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容を相手に通知したかを証明できる公的な手段です。
具体的には、以下の事項を記載した内容証明郵便を送付します。
- 遺留分侵害額請求を行う意思
- 遺留分を侵害されている事実
- 請求者の氏名・住所
- 遺留分を侵害した側の氏名・住所
遺留分を侵害した相手に対する意思表示は、遺留分侵害額請求権の行使を意味し、時効による遺留分侵害額請求の権利が消滅するのを防ぎます。
その後、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、裁判手続に移行します。
除斥期間は止められない
除斥期間は、時効とは異なり中断や停止ができません。
除斥期間とは権利を行使しないまま、定められた期間が過ぎてしまうと、権利が消滅する制度です。
時効と似ていますが、性質が異なる点があります。時効は裁判や債務の承認などによって中断が可能な場合があるのに対し、除斥期間は権利を行使しない限り進行を止められません。
遺留分権利者が相続の開始を知らなかったり、遺留分の侵害を認識していなかったりしたとしても、除斥期間が終わると遺留分侵害額請求権の行使ができなくなります。
そのため、遺留分権利者は、被相続人の死亡を知った時点で速やかに権利行使の要否を検討し、必要な場合は期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をしてください。
金銭債権の消滅時効を中断するには裁判を起こす
遺留分侵害額請求の意思表示をした後、その金銭債権は5年の消滅時効が適用されます。
この期間内に裁判などで請求を行わないと、侵害された遺留分を取り戻せなくなる可能性があります。
ただし、金銭債権の消滅時効は更新が可能です。
時効の更新には、以下のいずれかの方法を取る必要があります。
| 訴訟提起 | 金銭支払いを求める裁判を提起する |
|---|---|
| 債務の承認 | 遺留分を侵害した側(債務者)から債務の存在を認めてもらう |
これらの手段により、時効期間はリセットされ、新たに5年の期間が始まります。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺留分侵害額請求権を行使する際の注意点
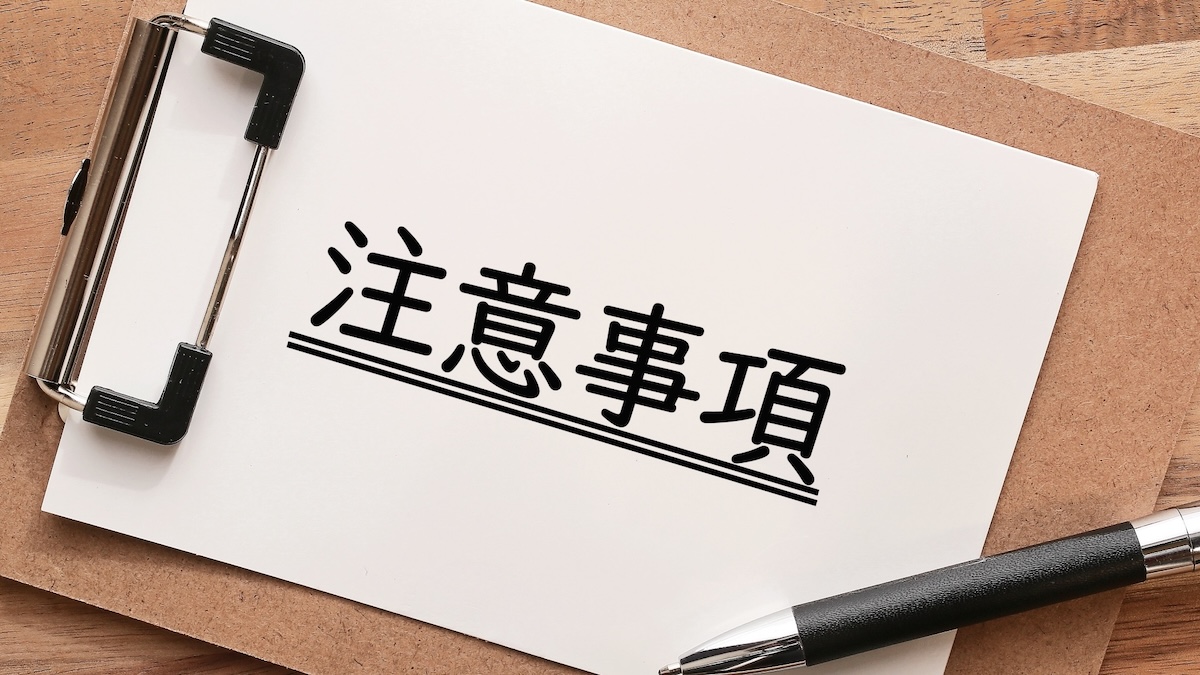
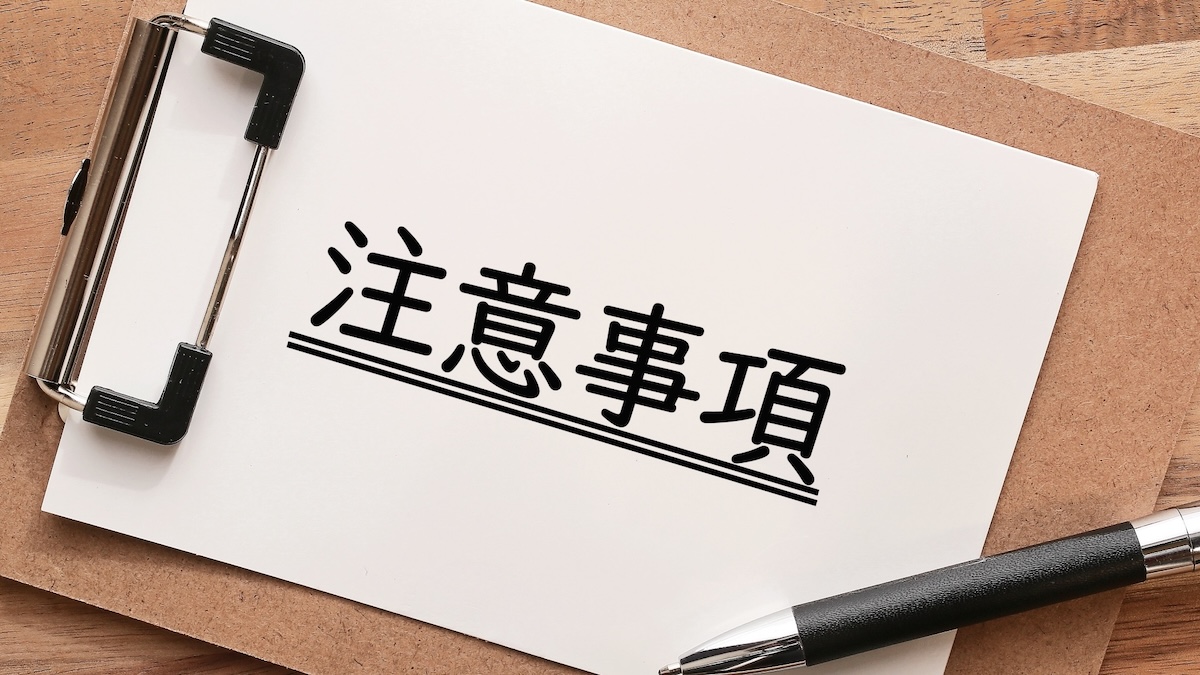
遺留分を侵害された相続人の中には、日頃、親族と疎遠で被相続人が亡くなったことを後から知ったり、遺言が正しく作成されたものか疑問に感じたりする方もいるでしょう。
ただし、遺留分権利者にさまざまな事情があっても、遺留分侵害額請求を時効前に行わないと、権利が行使できなくなってしまうケースがあります。
そのため、遺留分侵害請求権を行使する際は、以下の点に注意が必要です。
可能な限り相続開始から1年以内に行使する
遺留分侵害額請求の意思表示は、相続開始の1年以内に行うのが望ましいです。
なぜなら、遺留分侵害請求が、相続開始から1年が経過してしまうと意思表示のタイミングが争われてしまうケースがあるからです。
遺留分権利者が遺留分の侵害を知った時期が争点となると、それを立証する必要があり、証明が困難な場合もあります。
そのため、できるだけ被相続人が亡くなって相続が開始されてから1年以内に、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を意思表示するのがよいでしょう。
関連記事:遺留分侵害額請求は自分でできる?手続きの流れややり方をわかりやすく紹介
遺産分割協議や遺言の無効を争っている間にも時効は進行する
遺産分割協議や遺言の無効を争っている間であっても、遺留分侵害請求の時効が進行し続けます。そのため、遺言の有効性に疑問があり、無効を主張する場合でも、同時進行で遺留分侵害額請求の意思表示をしておきます。
これは、遺言が有効であると判断されたときに備えるための保全措置です。
遺留分侵害額請求の時効は、相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年と期間が短く、スピーディーな対応が求められます。
遺留分が侵害されていると認識したときは、できるだけ早く相続問題に強みのある弁護士に相談してください。
関連記事:【遺留分の請求】弁護士費用が安い事務所の選び方とは!費用の内訳や安く抑える方法も
民法改正前に発生した金銭債権の消滅時効は10年
2020年の民法債権法改正前(2020年3月31日以前)に遺留分侵害額請求を行っている場合は、権利を行使できる時から10年の消滅時効が適用されます。
債権の消滅時効における起算点の考え方が民法改正により以下の通り変わったため、遺留分侵害額請求権の行使時期によって時効期間が変わります。
民法債権法改正前の内容は、以下の通りです。
- 原則:権利を行使できる時から10年(改正前民法166条1項)
- 例外:商行為による債権5年(改正前商法522条)、職業別の時効期間(改正前民法169条~174条)
2020年4月施行の債権法改正後は、次の通りです。
- 原則:権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)
- 例外:権利を行使できる時から10年(客観的起算点)
以上により、2020年3月31日以前に請求権を行使していれば10年、同年4月1日以降に請求権を行使したときは5年が時効です。
もし、2020年3月31日よりも前に遺留分侵害額請求の意思表示を行ってから10年以内であれば、時効は完成していない可能性があります。
時効になる前に!遺留分侵害額請求の方法


遺留分侵害額請求の方法は下記のとおりです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額請求の流れについては、下記の記事も併せてご確認ください。
参考記事;遺留分の請求の仕方!流れや条件についてくわしく解説
当事者同士による話し合い
遺留分を侵害されたことを知り、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示を示した後、まずは当事者間で話し合いを行うことが重要です。
相手が遺留分の支払いに応じれば、調停や訴訟といった法的手続きを行わずに済みます。
支払いを受ける際には「遺留分侵害額に関する合意書」を作成する必要があります。
合意書には遺留分の計算方法、支払い方法、支払い期限を明記し、双方の署名捺印を行います。
遺留分損害額請求調停
当事者間での話し合いが難航する場合や合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。
ただし、調停を申し立てるだけでは意思表示とはならず、調停前に内容証明郵便などで意思表示を行う必要があります。
調停では調停委員や調停官が双方の主張や証拠を確認し、解決策を提示したりアドバイスを行ったりして、協議を進めます。
関連記事:遺留分侵害額請求の調停に関する記事を見る
遺留分損害額請求訴訟
調停で合意ができなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起できます。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴えます。
訴訟では遺留分侵害の事実や額を証明し、法律的に正しい主張を行う書面を提出する必要があります。裁判中に和解案が提示されることもありますが、和解に応じない場合は判決に基づき今後の対応が決まります。
ただし、判決に納得できなければ控訴も可能です。
支払い確保のためにあらかじめ遺産を差押える
上記の各手続きを取る前に、あらかじめ遺産の一部または全部を仮に差押えておくこともあります。
たとえば、主な遺産は不動産しかなく、その不動産を売却されてしまえばどこに財産があるのかわからなくなってしまうような事例では、裁判で勝っても実際に支払わせるための財産が見つからず回収ができないなどの事態を回避する必要があります。
そのために、あらかじめ遺産を仮差押えしておき、最終的に裁判で勝訴したときに確実に回収できるようにしておくのです。
ただ、差押えのためには法務局に担保金を積んでおく必要がありますし、専門家以外が安易にできる手続きではありませんので、必ず弁護士に相談して行うことをお勧めします。
関連記事:遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説
【よくあるケース別】遺留分侵害請求の時効適用判断の例を解説
遺留分侵害額請求には時効がありますが、「自分の状況は時効にあてはまるのか?」と迷う人も多いはずです。特に、遺言や贈与の事実を後から知った場合や、請求しても相手が無視した場合などは判断が難しくなります。
ここからは、よくあるケースを4つ取り上げて、時効が適用されるかどうかをわかりやすく解説します。
自分のケースがどれに近いかを意識しながら、読み進めてください。
相続から5年経っても遺言を知らなかった場合はどうなる?
相続から5年経っていても、遺言の存在を最近知ったなら、まだ遺留分侵害額請求が間に合う可能性があります。
時効のカウントが「侵害を知った日」から始まるためです。民法では、相続人が「遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内」に請求すれば時効にかからないとされています(民法第1048条)。
例えば、父親が亡くなったのは2019年でも、2024年に遺言の存在を知った場合、その知った日から1年間は請求が可能です。
ただし注意点として、相続が開始してから10年が経過していると、除斥期間により一切の請求ができなくなります。
相続から5年程度であれば、遺言を知った日から1年以内の請求で対応できる余地があります。確実に主張を通すためにも、知った事実を証明できる書類を早めにそろえましょう。
調停不成立後に再請求はできる?
調停が不成立になったあとでも、再度遺留分侵害額請求を行うことは可能です。調停不成立の段階では、請求自体が終了したとは見なされないためです。
調停はあくまで話し合いの場であり、強制力はありません。そのため、調停がまとまらなかった場合は、訴訟に進むことで再び請求を主張できます。
例えば、兄との調停が決裂して終わった後でも、家庭裁判所に訴訟を起こせば、時効中断の効果も得られたうえで請求が再開できます。
ただし、時間が空きすぎると新たに時効が進行してしまうリスクがあります。特に、調停終了後に5年間何もしていない場合は、債権消滅時効が成立する可能性が高まります。
調停が不成立でも道は閉ざされていません。早めに次の手続きを取り、時効を再び進行させないことが大切です。
関連記事:遺留分侵害額請求の調停に関する記事を見る
内容証明を送ったが調停や裁判をしていない場合は?
内容証明郵便を送っただけでは、時効を完全に止めることはできません。
内容証明には「催告」としての効果はありますが、その効力は6か月しか続きません(民法150条1項)。6か月以内に調停や訴訟などの正式な手続きを取らなければ、時効のカウントが再開されてしまいます。
例えば、2023年4月に兄に対して内容証明で遺留分を請求し、何も反応がなかったとします。そのまま裁判も調停も起こさず、2024年5月になっても行動していない場合は、1年の消滅時効が成立してしまう可能性があります。
内容証明を送っただけで安心してはいけません。6か月以内に調停や裁判へ進むことで、はじめて時効の進行を止められます。
相手に請求書を送って無視された場合は?
請求書を送ったのに相手が無視している場合でも、法的な手続きを取らなければ、時効は進行したままになります。請求書の送付自体には法的拘束力がないためです。
相手が対応しない限り、「話し合いの開始」とも見なされず、裁判所も時効中断とは認めません。
例えば、「2025年8月に遺留分を請求する手紙を出したが、兄からは何の返信もない」という場合、裁判や調停を起こしていないなら、2026年8月には1年の時効が成立してしまう可能性があります。
このようなケースでは、内容証明郵便を使い、6か月以内に法的手続きを行うことが有効です。
無視されても諦めず、正式な手段に移行する必要があります。相手の反応にかかわらず、行動を起こすことで自分の権利を守りましょう。
遺留分侵害額請求の時効まで期間は短い!早めに弁護士に相談しよう


遺留分侵害額請求は侵害した側がすんなり請求に応じてくれないケースが多く、調停の申立てや訴訟の提起が必要なケースもあるため、弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士は法的知識に基づいた遺留分の複雑な計算や、遺留分侵害額請求をするための書類作成を代行します。
また、遺言の有効性に疑問があり、無効を主張する場合でも、権利保全のため同時に遺留分侵害額請求権の行使も可能です。
遺贈や贈与などで遺留分の侵害があった場合は、迷わず弁護士に相談してください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼することで得られるメリット
遺留分侵害額請求は、法律知識が必要なうえに、時効や証拠の扱いが複雑です。
対応を誤ると、正当な取り分を失ってしまう可能性があります。そこで頼りになるのが弁護士のサポートです。
以下のようなメリットがあるため、早い段階で弁護士に相談する価値は十分にあるといえるでしょう。
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
時効の成立について判断してもらえる
時効の成立について正確に判断してもらえるのは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
時効には「知ったときから1年」「相続開始から10年」「金銭債権としての5年」の3種類があり、それぞれ起算点もルールも異なります。素人では判断がつきにくく、誤解していると泣き寝入りにつながるおそれがあるため注意が必要です。
「遺言を知らなかったからまだ請求できる」と思っていても、実際には相続開始から10年を超えており、完全に時効となっているケースもあります。逆に「もう無理だ」と思っていたケースでも、時効が成立しておらず、請求可能なことも珍しくありません。
こうした判断を的確にしてもらうには、相続に詳しい弁護士に資料を見てもらうのが確実です。時効リスクに不安があるなら、まずは弁護士の見解を得るところから始めましょう。
正確な遺留分侵害額を算出してもらえる
正確な遺留分侵害額を算出してもらえる点も、弁護士に依頼する大きな利点です。
遺留分は単純に相続分の半分とは限らず、計算には以下のような要素が影響します。
- 法定相続人の数
- 相続財産の評価額
- 生前贈与や遺贈の金額
- 対象となる財産の種類と範囲
また、不動産の評価についても、固定資産税評価額と時価では結果が異なります。さらに、借金や負債がある場合は、相続財産から差し引く必要もあります。
こうした複雑な条件をふまえて遺留分侵害額を正しく算出するには、法律と実務に精通した弁護士の力が不可欠です。
納得のいく金額を請求したいなら、弁護士に計算を依頼するとよいでしょう。
遺留分侵害額請求に必要な手続きを一任できる
遺留分侵害額請求に必要な手続きをすべて一任できるのは、大きな安心につながります。
遺留分の請求には、次のような膨大な手続が必要です。
- 内容証明郵便の作成と発送
- 家庭裁判所への調停申立書の提出
- 裁判所での主張と反論の準備
- 証拠資料の収集と整理
- 相手方との交渉や和解案の検討
自力で裁判に進むのは相当な労力と精神的な負担がかかります。また、手続きの流れや提出書類の不備で、こちらが不利になる可能性もゼロではありません。
弁護士に依頼すれば、すべてのやり取りや手続きを任せられます。本人が直接相手と対立しなくても済むため、心理的なストレスも大きく軽減できるでしょう。
時間と労力を節約し、確実に権利を守るには、弁護士に手続きを任せるのが最も効率的です。
遺留分侵害額請求にかかる可能性のある費用
遺留分侵害額請求を進めるには、手続きごとに費用が発生します。初期費用をできるだけ抑えたい人も、あらかじめ目安を知っておくと安心です。以下に代表的な費用項目を紹介します。
それぞれの費用がどのような内容なのか、具体的に見ていきましょう。
内容証明郵便の費用
内容証明郵便の費用は、郵便局で送付する場合は数千円程度が目安です。
内容証明郵便とは、誰が・いつ・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる仕組みです。遺留分侵害額請求においては、「請求の意思を相手に正式に伝えた証拠」として用いる場面が多くあります。
郵便局での内容証明にかかる費用は以下の通りです。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 基本料金(定型25g以内) | 約84円 |
| 内容証明料(1枚) | 約450円 |
| 書留料 | 435円 |
| 配達証明 | 320円 |
| 合計(目安) | 約1,300〜1,800円程度 |
文章が2枚以上になった場合や、同じ文書を複数の相手に送る場合は費用が上がります。弁護士に文書作成を依頼する場合は、別途1万円〜3万円ほどの報酬がかかるイメージです。
内容証明は比較的低コストで送れる手段ですが、証拠性を高めたい場合は専門家の関与も検討しましょう。
調停を申し立てる費用
調停を申し立てる費用は、収入印紙と郵便切手で合わせて数千円程度です。
遺留分侵害額請求の調停を家庭裁判所に申し立てる際には、裁判所に納める費用が発生します。具体的には以下のような内訳です。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙 | 1,200円(請求額により変動) |
| 郵券(切手) | 500〜1,000円程度 |
| 証明書等の取得費用 | 数百円(必要に応じて) |
ただし、これは手続きだけの費用です。自力で申し立てが難しい場合や、文書作成を弁護士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
調停自体の申し立て費用は比較的安く済みますが、準備や対応には手間がかかるため、サポートが必要な場合は弁護士費用もあわせて想定しておきましょう。
弁護士に依頼する費用
弁護士に依頼する費用は数万円〜数十万円と幅がありますが、項目ごとに内訳を確認すれば全体像が見えてきます。
以下は、遺留分侵害額請求で発生する代表的な費用です。
| 項目 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回30分〜1時間 | 0〜1万円程度 |
| 着手金 | 請求開始時に支払う | 10万〜30万円程度 |
| 成功報酬金 | 回収額に対する報酬 | 回収額の10〜20%前後 |
| 実費・雑費 | コピー代、交通費など | 数千〜数万円 |
| 調停・裁判対応 | 追加報酬や日当 | 内容により加算されることも |
遺留分侵害請求に関する弁護士費用については、以下の記事で詳しく解説しています。自分がどれくらいになるか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺留分侵害額請求の弁護士費用を解説
なお、法律相談は初回無料の事務所もあるため、費用が不安な場合は複数の事務所で見積もりを取りましょう。
費用は確かに発生しますが、「確実な請求」「精神的負担の軽減」「不利な結果の回避」というリターンを考えれば、検討する価値は十分にあります。
相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例
他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。
“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”
この事例では、
- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと
- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと
これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


遺留分侵害額請求の時効についてよくある質問
遺留分侵害額請求の時効が過ぎたらもう請求できないのですか?
相続開始から10年を経過すると、民法1048条が定める除斥期間により、遺留分侵害額請求権は自動的に消滅し復活も中断もできません。
第千四十八条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
ただし、10年を過ぎた遺留分請求であっても、協議や示談で解決できる可能性があります。
自分のケースで請求できるか悩んでいる方は、相続に強い弁護士への相談がおすすめです。
遺留分を払わないとどうなりますか?
遺留分を払わないで放置すると、調停や裁判に発展する可能性があるため、注意が必要です。
遺留分は法律で確保されている法定相続人の取り分であり、正当な請求を受けた場合は支払う義務があります。
無視をし続けた場合は、強制執行により財産差し押さえに至るリスクもあります。遺留分侵害額請求を受けたら早めに対応しましょう。
強制執行については下記の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ
本記事では、遺留分侵害額請求の時効について解説しました。
- 遺留分とは一定の相続人に法的に保障される権利で、遺留分侵害額請求とは遺留分が侵害されたときに行使する請求権である
- 遺留分侵害額請求権を行使しないと侵害を知った時から1年で時効を迎える
- 遺留分侵害額請求の除斥期間は10年で、侵害を知らなくても時効になる
- 遺留分侵害額請求権を行使して得た金銭債権の時効は5年
- 遺留分侵害を知った日の証明が難しいため、被相続人の死亡から1年以内に権利を行使するのが望ましい
遺留分を侵害した側からスムーズに支払いに応じてもらうためにも、交渉は弁護士に任せるのがよいでしょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応