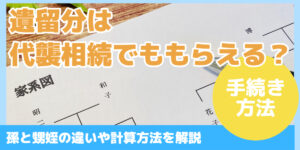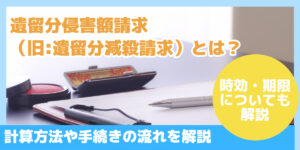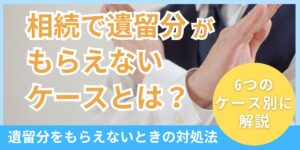【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分侵害額請求の期限はいつまで?2つの時効や注意点を弁護士が解説
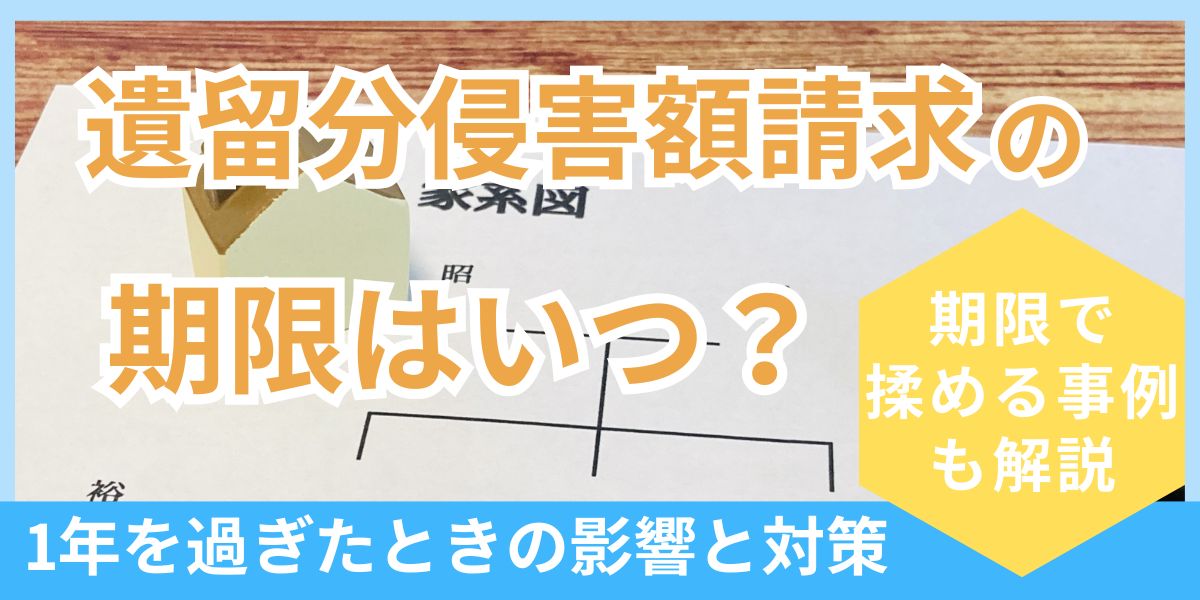
「遺留分の請求期限はいつまでなのだろうか?」
「時効が過ぎたらもう取り戻せないのだろうか?」
遺留分を侵害された方(相続人)は遺留分侵害額を請求できますが、請求の期限の有無や請求の仕方がわからないと悩む方もいるでしょう。
遺留分侵害額請求は、民法で2つの期限が定められています。正しく理解しておかなければ、気づいたときには時効となり、請求権を失うリスクがあるため注意しましょう。
本記事では、遺留分の期限や遺留分侵害額請求の流れ、注意点を分かりやすく解説しています。
- 遺留分、遺留分侵害額請求の基礎知識
- 遺留分請求の期限
- 遺留分侵害額請求の流れ・期限に関する注意点
- 遺留分の請求に関するトラブル事例

本来受け取れるはずの遺留分を取り戻せるのか悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分侵害額請求とは


遺留分侵害額請求とは、遺留分が遺言などにより侵害されている(自分が相続できる財産が遺留分より少ない)場合に、遺留分侵害額相当額の金銭の支払いを求めることです。
遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続分のことです(民法1042条1項)。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をして、自分の遺留分を侵害して相続財産を得た人から、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを受けられます。
この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求は2019年7月1日以降に生じた相続に適用されます。



それ以前に起こった相続の場合は、改正前民法の「遺留分減殺請求権」に基づき、金銭ではなく、物件返還請求をすることになるので注意が必要です。
裁判所|遺留分侵害額の請求調停
裁判所|遺留分減殺による物件返還請求調停
遺留分侵害額請求については、次の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事:遺留分侵害額請求の記事を見る
遺留分侵害額請求には2つの期限(時効)がある


遺留分侵害額請求には、次の2つの期限があります。
相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年
遺留分侵害額請求については、民法で「相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年」の期限の定めがあります(民法1048条前段)。
民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)前段
引用:民法|第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年行使しないときは、時効によって消滅する。
期限の起算点は次の2つを満たす時点になります。
- 「相続の開始を知った」:被相続人が死去し、かつ自分が相続人となったことを知ったとき
- 「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った」:自分の遺留分が侵害される贈与・遺贈があったことを知ったとき
たとえば、遺言書の存在を知るだけでなく、全遺産を他の相続人である兄弟などに遺贈するとの内容であることを知った知った時点が、期限の起算時点となるのです。
遺留分侵害額請求をする場合は、「知った」ときがいつかをめぐり争いになる可能性もあるため、できる限り1年以内の早期にしましょう。
相続開始から10年
民法は遺留分侵害額請求について「相続開始から10年」の期限も定めています(民法1048条後段)。
民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)後段
引用:民法|第1048条
(遺留分侵害額の請求権は、中略、時効によって消滅する。)相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
したがって、「相続開始の時から10年」経てば、遺留分侵害額請求権は消滅します。
「10年」の期限は、請求権者の個別の事情に関係なく進行するため、期間の進行は止められません。



いわゆる「除斥期間」のため、被相続人と疎遠で、死去の事実や自分が相続人になったこと、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すれば、侵害額請求はできなくなるのです。
時効を中断する方法については、下記の記事を参考にしてください。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
遺留分侵害額請求後の期限「5年」にも注意
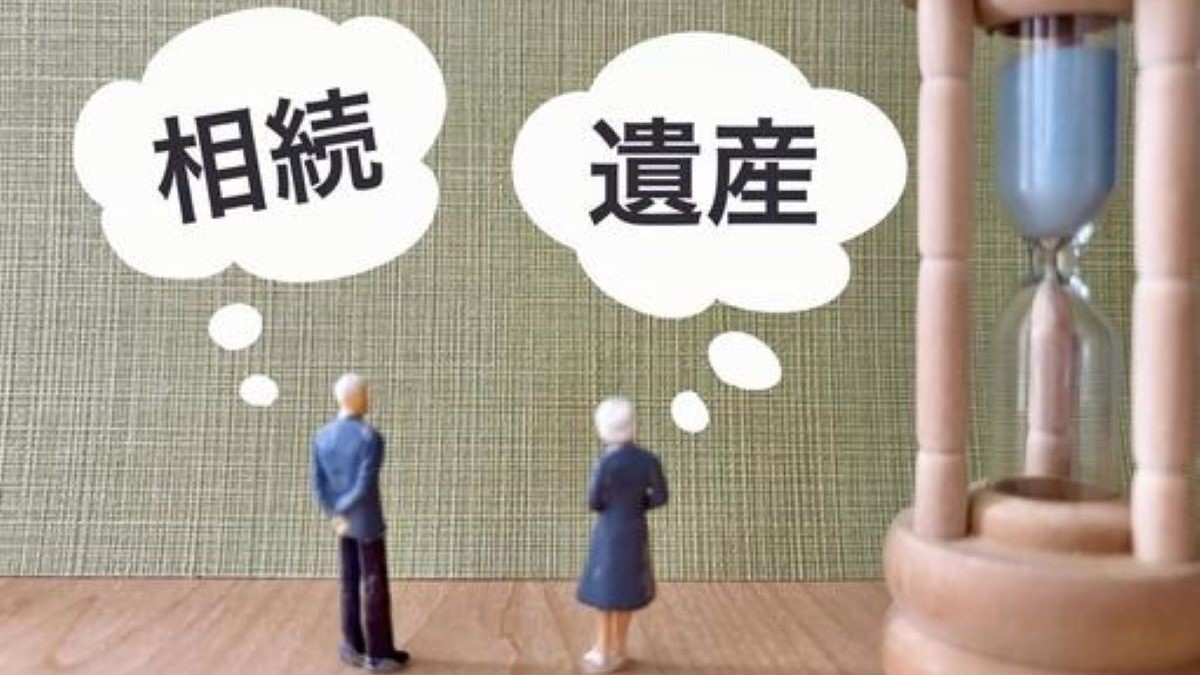
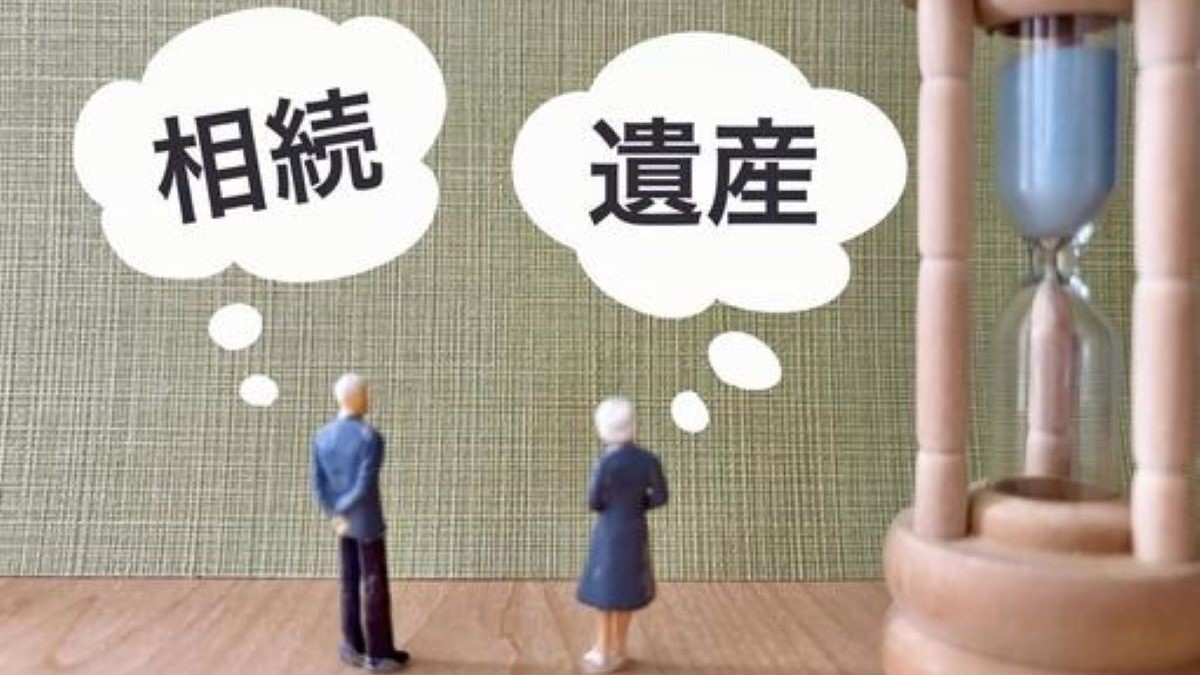
遺留分侵害額請求権の期限を回避する方法はあります。
民法の定めに従い「相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする」ことです。
遺留分侵害額請求の意思表示を行っておけば、民法1048条の期間の制限の適用はなくなります。
意思表示の方法にルールはありませんが、「言った・言わない」と揉めないように書面にして配達証明付き内容証明郵便で通知することをおすすめします。
遺留分を侵害している相手方との協議が難航する場合は、裁判所での調停や訴訟によって解決を目指すことが可能です。
ただし、複数人に贈与が行われている場合などは、請求すべき相手が明確でないこともあります。



請求相手や請求方法などに迷うときは弁護士に相談しましょう。
遺留分侵害額請求後の金銭支払い請求の期限5年にも要注意


遺留分侵害額請求をした後にも、5年の期限があることに注意しましょう。
遺留分侵害額請求の意思表示を行えば、協議が成立しなくても遺留分侵害額請求権がなくなるわけではありません。
しかし、遺留分侵害額請求により生じた「金銭支払い請求権(債権)」には、次の通り行使期間の期限(債権等の消滅時効、民法166条)があります。
- 「権利を行使できることを知った時から5年間」
- 「権利を行使できる時から10年間」
民法166条(債権等の消滅時効)
引用:民法|第166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
遺留分侵害額請求を行っても、侵害額相当の金銭支払いを期限内に求めなければ、払ってもらえなくなることがあるのです。
侵害額請求が認められた場合は、速やかに支払い請求手続きを進める必要があります。
また、遺留分侵害額請求権を行使したときは、金銭支払い請求権の消滅を防止するために、金銭支払いを求める裁判も5年以内に提起しておきましょう。
裁判の判決確定後から新たに5年の期限が進行します。
なお、2020年4月1日施行の民法改正法で請求期限のルールが変わっています。



改正法施行前に遺留分侵害額請求を行った場合の期限は、改正前民法が適用され「一律10年」です。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺留分侵害額請求の方法と流れ


遺留分侵害額請求の方法と流れを解説します。
原則として次の流れで進みます。
遺留分を侵害している相続人と協議する(配達証明付内容証明郵便の送付)
まず遺留分を侵害している相続人と協議しましょう。
相手が請求を容認すれば、当事者だけの合意で解決できます。
話し合いで穏便に解決できれば、それに越したことはありません。多少譲り合っても妥当な金額で早期に合意するメリットは大きいでしょう。
ただし、遺留分の正確な理解は難しく、話し合いは揉めることもよくあります。
スムーズな話し合いが困難な場合は、当事者だけで話し合うよりも、早めに弁護士へ相談して対応策を検討した方がよいでしょう。
また、遺留分侵害額請求は期限があるため、任意の協議中であっても請求を行った証拠を残す必要があります。
そのため、下記事項を明記した遺留分侵害額請求通知を配達証明付き内容証明郵便で送りましょう。(郵便局で手続きする方法とインターネット上で手続きするe内容証明もある)
- 請求者と相手方
- 請求の対象となる遺贈・贈与・遺言とその内容
- 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨
- 請求日時
遺留分侵害額請求調停を申し立てる
当事者の協議がまとまらない場合は、裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。
当事者が調停案に合意すれば調停成立となります。
調停申立は相手方への遺留分侵害額請求の意思表示にならないため、請求通知をしていない場合は、別に内容証明郵便により意思表示を行う必要があります。
| 申立人 | 遺留分を侵害された者 |
|---|---|
| 申立先 | 相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 申立費用 | 収入印紙1,200円分、連絡用の郵便切手 |
| 申立に必要な書類 | 申立書及びその写し(相手方の数の通数) 申立添付書類 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 遺言書又は遺言書の検認調書謄本の写し 遺産の証明書(登記事項証明書・固定資産評価証明書・預金残高証明書等) |
遺留分侵害額請求の調停の申立て(調停前置)については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
遺留分侵害額請求訴訟を提起する
遺留分侵害額の請求調停が不成立となった場合は、裁判所に訴訟を提起しましょう。
遺留分侵害額請求は、訴訟前に原則として家庭裁判所へ調停を申し立てなければなりません(調停前置主義、家事事件手続法257条)が、遺産分割協議のように調停から審判へ移行することはありません。
調停が不成立となった場合、最短6か月で遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成するおそれがあります(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新、民法147条1項)。
速やかに訴訟を提起する必要がありますが、訴訟の準備は専門的な知識が必要です。



訴訟の場でも、遺留分侵害の事実を証拠により立証する必要があるため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
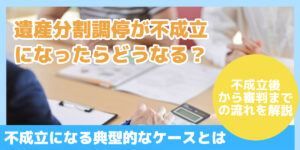
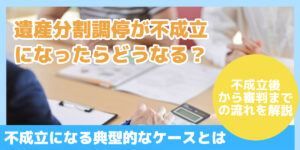
関連記事:遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説
遺留分侵害額請求の期限でトラブルになった3つの事例


遺留分侵害額請求の期限で揉める事例を3つ紹介します。
1.贈与無効確認訴訟と遺留分請求権の時効
遺言無効確認訴訟を提起したが、遺留分侵害額請求をしなかった事例です。
| 関係者 | 被相続人:父親 相続人:子2名(A・B) |
|---|---|
| 争いの経緯 | 父親が亡くなったが「全遺産を長男であるAに相続させる」という遺言書があった。 Bは「Aが全遺産を引き継ぐのは納得できない」として遺言無効確認訴訟を提起したが、遺言が無効だから遺留分請求は必要はないと考え請求しなかった。 Aは、遺言書は自筆の正当な遺言書であること、また遺留分侵害額請求はすでに1年の時効になっている旨を主張した。 |
| 対応策の検討 | Bは次の2点の理由から、遺言無効の訴えだけでなく、遺留分侵害額請求権を行使すべきであった。 1.遺言無効訴訟が勝訴するとは限らない。 2.遺言無効確認訴訟の提起だけでは、遺留分侵害額請求権の時効が止まるとは言えない。 対応は複雑で難しいため、早期に弁護士に相談すべき事案であった。 参考:裁判所|昭和57年11月12日最高裁第二小法廷判決 「遺留分権利者が同無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情が認められない限り、同遺贈が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当」 |
2.養子縁組が偽装との主張と遺留分請求
養子縁組は相続分を増やすための偽装(便法)との主張と遺留分請求に関する事例です。
| 関係者 | 被相続人:父親 相続人:子3名(実子A・Bと養子C(Aの子)) |
|---|---|
| 争いの経緯 | 亡父が生前、Cと養子縁組をした。 Bは、養子縁組はAが自分の遺産相続分を増やすための偽装(便法)だとして、養子縁組の無効と、兄弟2名による法定相続分通りの相続を求めた。 話し合いは平行線のままである。 |
| 対応策の検討 | Bは、養子縁組の無効を主張するとともに、予備的にAとCに対して遺留分侵害額請求権を行使しておくべきであった。 理由は、事例1と同様。 1.養子縁組無効訴訟が勝訴するとは限らない。 2.養子縁組無効訴訟の提起だけでは、遺留分侵害額請求権の時効が止まるとは言えない。対応は難しいため、早期に弁護士に相談する方がよい。 参考:裁判所|養子縁組無効確認請求( 昭和23年12月23日最高裁第一小法廷判決) 「単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、養子縁組は、効力を生じない」 |
3.遺留分請求をした者への特別寄与料の主張
遺留分侵害額請求権を行使した相続人に遺留分に応じた特別寄与料負担を求めた事例です。
| 関係者 | 被相続人:父親 相続人:子(A・B) 特別寄与を主張する者:C(Aの妻) |
|---|---|
| 経緯 | 亡父は生前、財産全部をAに相続させる旨の遺言をしていた。 Bは、Aに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。 Cは、相続分がないものとされた相続人Bも、遺留分侵害額請求権を行使した場合は遺留分に応じた特別寄与料を負担すると主張した。 |
| 対応策の検討 | 遺留分は最低限の持ち分なので、遺留分を取得したことをもって、遺留分に応じた特別寄与料を請求しても認められない。 寄与分の主張も同じく認められないので注意が必要です。 参考:裁判所|令和5年10月26日最高裁第一小法廷決定(特別の寄与に関する抗告事件) 「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である」 |
遺留分侵害額請求の期限についての3つの注意点


遺留分侵害額請求の期限についての注意点を3点紹介します。
1.遺言の無効や贈与の存在を争っていても請求期限は迫ってくる
遺留分侵害額ではなく、遺言無効や生前贈与の存在を争っている間も、遺留分侵害額請求権の期限はどんどん近づいてきます。
たとえば、「長男に全遺産を相続させる」という遺言書があったが、父親は認知症で遺言能力がなかったと考えた次男が遺言無効確認訴訟を起こしたとしましょう。
次男は「遺言が無効だから遺留分侵害以前の問題だ」と主張するかもしれませんが、遺留分侵害額請求の期限に影響はなく、期限はどんどん近づいてきます。
遺言無効確認訴訟が敗訴した場合、遺留分侵害額請求権を行使しようとしても、請求権はすでに消滅している可能性もあるのです。
遺言無効確認訴訟など他の訴訟を提起する場合、並行的に遺留分侵害額請求もしておきましょう。
2.複数の人に遺贈や生前贈与が行われている場合は請求相手に注意する
遺贈や生前贈与が複数人に対して行われていたときは、遺留分侵害額請求をすべき相手に注意が必要です。
民法は遺留分侵害額の負担者を次のように定めています(民法1047条1項)。
- 受遺者(遺贈を受けた者)と受贈者(生前贈与を受けた者)がいるときは、受遺者が先に負担
- 複数の遺贈や贈与が同時にされたときは、目的の価額の割合に応じて負担(遺言に別段の意思表示があるときを除く)
- 受贈者が複数いるときは、後の受贈者から負担
受贈者より受遺者への請求が先になるのは、遺贈が相続財産からの贈与であるのに対し、生前贈与は相続財産になる前の贈与のためです。
遺留分侵害額の請求先はわかりにくいこともあるため、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
3.相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しておく
遺留分侵害額請求権の行使を検討しているのであれば、相続開始から1年以内にまず権利を行使しておくべきです。
具体的な金額は、精査してから明確にすることもできます。
遺留分侵害額の算定は複雑な場合も多く、遺留分と侵害額請求額を正確に算定していると請求期限に間に合わないかもしれません。
そのため、まず1年以内の早期に具体的な金額は記載せず、侵害された遺留分を請求する旨の文書を送付しておいた方がよいのです。



請求権を行使しておけば、起算点をめぐる争いを避けられます。
遺留分侵害額請求の期限が不安なら弁護士に相談
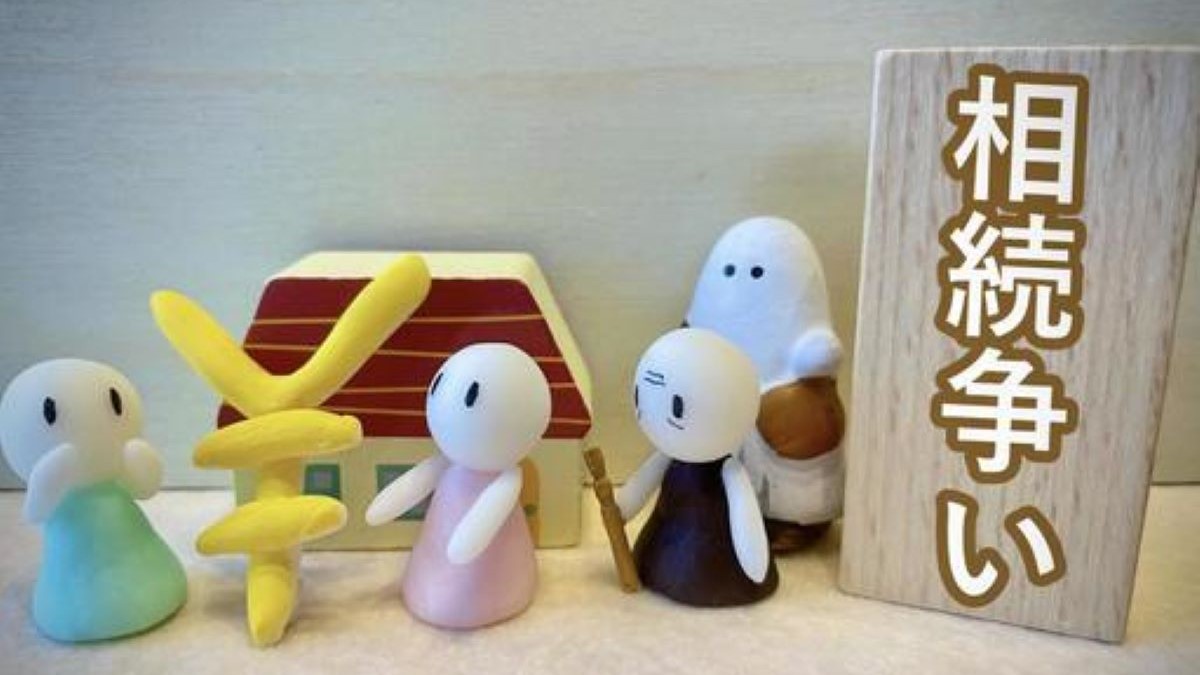
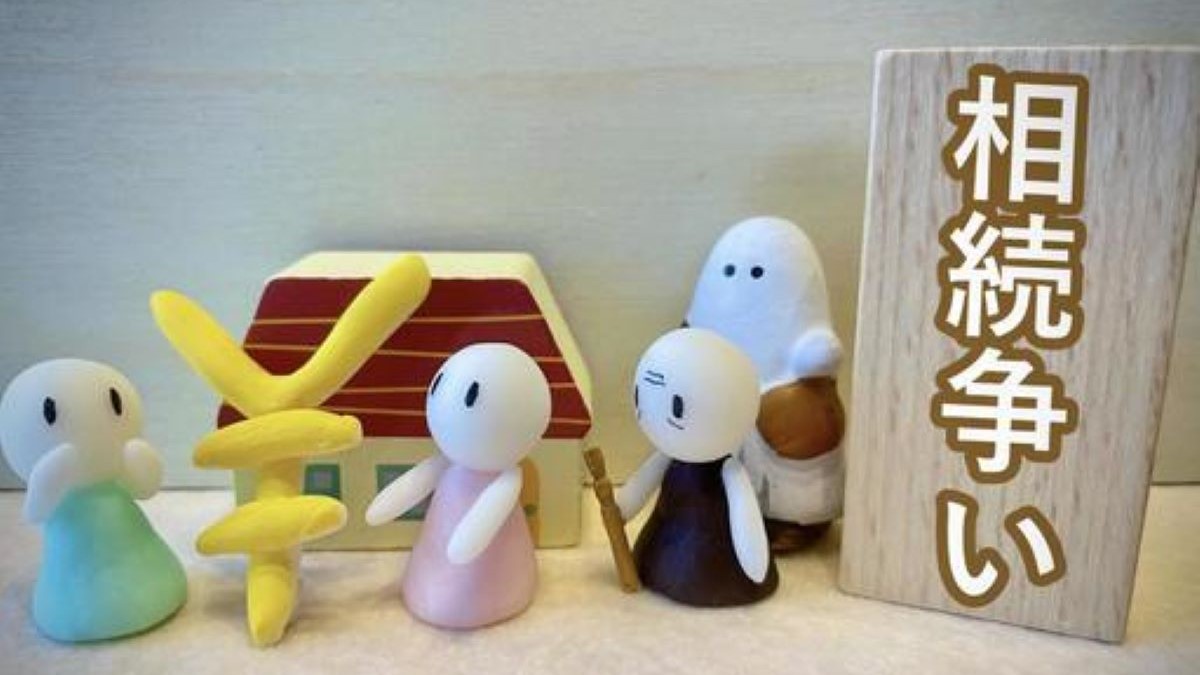
遺留分侵害額請求は複雑な場合が多く、次のような面倒な問題もあるため、弁護士に依頼しましょう。
- 遺留分侵害額請求は期限内にする必要があるが、期限の起算点の判断が難しい
- 請求相手の数や希望する請求内容によっては、手続きがさらに複雑になる
- 任意の交渉を続けても、相手方が請求に応じないケースも多い
弁護士に依頼すれば次のようなメリットがあります。
- 相手方と直接話をしなくてよい:交渉はすべて弁護士が行うため、相手と直接交渉するストレスから解放されます。
- 権利行使のタイミングを逃さない:請求権はタイミングを逃すと消滅しますが、弁護士に任せれば心配はいりません。
- 適切な遺留分を請求できる:遺留分の額はケースによって異なりますが、請求者のために最適な遺留分を請求できます。
- 十分な調査と適切な権利行使が可能:請求対象となる遺贈等の有無などの調査、請求先・請求内容を適切に判断できます。
- 法的対応をスムーズにできる:交渉段階から弁護士に依頼しておけば、法的手続きも視野に入れた交渉ができ、出廷等も弁護士が対応可能です。
弁護士は遺留分侵害額請求の必要書類の作成はもちろん、遺留分の複雑な計算・請求額の算定や、請求後の交渉を行えます。
遺言の無効を主張する場合でも、同時に遺留分侵害額請求権の行使も進めるなど、迅速に有効な対応をとります。



相手方との協議から、調停や訴訟になる場合も多いため、早めに弁護士に相談し依頼することをおすすめします。
相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例
他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。
“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”
この事例では、
- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと
- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと
これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


遺留分の期限についてよくある質問
公正証書遺言を無効にできるケースはありますか?
公正証書遺言は公証人が関与するため信用性が高い一方で、次のような事情があれば無効(または取消しの対象)と判断されることがあります。
- 遺言能力や意思能力に疑いがある(重い認知症等で内容を理解・判断できなかったと評価される場合)
- 詐欺・強迫・重大な錯誤がある(真意に基づかない作成)
- 方式・手続の重大な瑕疵(証人の欠格、立会いの欠如、読み聞かせ・趣旨の解釈確認不足など)
もっとも、いずれも立証負担は重く、診療録・介護記録、当日の公証役場の手続記録、同席者の供述など客観資料の収集が重要です。
無効主張とあわせて、期限が厳格な遺留分侵害額請求(民法1046条、民法1048条)を並行させるのが実務対応として安全です。
関連記事: 遺言書の効力はどこまで?いつから効力が発生する?書き方や無効なケースも解説
遺留分の請求に相手が応じないときはどうしたらいいですか?
放置は不利になりがちです。次の順で期限管理をしながら前に進めましょう。
- 内容証明で再通知:侵害の趣旨・概算額・根拠・回答期限を明示。起算点が争いになる前に意思表示を記録化します(民法1048条)。
- 条件提案で合意を探る:分割払い・期限の許与・担保提供など、履行可能なプランを提示(民法1047条)。
- 家庭裁判所に調停申立て:第三者関与で評価方法や支払条件の溝を整理。
- 訴訟と保全:和解困難なら提訴し、仮差押え等で回収確実性を高めます。
- 二重の時限を管理:①「知ってから1年/開始から10年」(民法1048条)に加え、②遺留分侵害額請求の意思表示後に生じる金銭債権は原則5年で時効(民法166条)。必要に応じて裁判上の請求等で完成猶予・更新を図ります(民法147条)。
不動産しかない事案では、換価分割・融資活用・売却猶予つき分割など実現可能な選択肢を並行検討すると合意に至りやすくなります。迷う前に早期に証拠とスケジュールを整えましょう。
被相続人の兄弟でも遺留分を請求できますか?
できません。 遺留分が認められるのは配偶者・子(代襲を含む)・直系尊属に限られ、兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれません(民法1042条)。
もっとも、兄弟姉妹の立場でも、遺言の有効性を検討したり、被相続人の生前の介護・看護等が著しい場合に遺留分とは別の法的手当を検討できることがあります。
事案により取り得る手段が異なるため、早めに相談されることをおすすめします。
まとめ|遺留分の期限は1年または10年!請求手続きは弁護士に依頼しよう
遺留分侵害額請求の期限についてまとめます。
- 遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害されている(相続できる財産が遺留分より少ない)場合に、侵害額相当の金銭支払いを求めること
- 遺留分侵害額請求には2つの期限(相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年、相続開始から10年)がある、侵害額確定後の金銭支払い請求期限5年にも要注意
- 遺留分侵害額請求の期限を回避する方法は、まず口頭で侵害額請求の意思表示をする、次に証拠を残すため書面を配達証明付き内容証明郵便で送付する。
遺留分侵害額請求は、請求相手・請求金額の算定など複雑な問題や面倒な手続きも多く、トラブルになりやすいものです。
期限内に間違いなく迅速に請求手続きを進めるためには、法律に関する専門的な知識が必要です。



わからないことや揉めごとがあるときは、遺留分侵害など相続問題に詳しい弁護士に早めに相談しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応